私たちの世界のとらえ方に、「写真」はどのように関係しているのだろう。インターネットやスマホの登場以降、ますます身のまわりに溢れかえる写真に、我々はどのように接するべきだろうか――。そんなことをあらためて考えさせる、現代写真シーンを代表するドイツ人写真家、トーマス・ルフの日本初の大回顧展が、東京国立近代美術館に引き続き、金沢21世紀美術館で開催されている。これまでの代表シリーズを東京会場より多い点数で網羅した、トーマス・ルフを知るための決定版ともいうべき内容だ。
先に「現代写真シーンを代表する」と書いたが、ルフの活動は従来の写真家のイメージを大きく逸脱している。自らの手で撮影することにこだわらず、天体写真から報道写真、ポルノ写真まで、インターネットやNASAから入手した既存の画像を加工して自らの作品とするなど、その表現はつねに異彩を放ってきた。そんな彼が約30年にわたる活動の中で、探求してきたこととは一体何なのか。今回の展覧会開催にあわせて来日した本人に話を聞いた。
多くの人々は日頃、写真に囲まれて生活をしているにも関わらず、その状況を自覚していない。
―展示を拝見して、あなたの写真表現の多様さをあらためて感じました。大学時代の仲間を撮影した初期の作品から、インターネットにおける画像の流通の問題を扱った作品、レンズを使わずにコンピュータ上で制作された作品まで、非常に幅広いです。これらの活動を通じてあなたが持ち続けてきた問題意識とは何なのでしょう?
ルフ:私が一貫して興味を持っているのは、我々のまわりに溢れる「写真」と呼ばれるものが、一体どのようなものなのか、どのように流通され発信されているのか、ということを考えることです。なぜそんなことに取り組むかといえば、多くの人々は日頃、写真に囲まれて生活をしているにも関わらず、その状況を自覚していないからです。
でも実は、人の世界のとらえ方の中には、写真が深く関わっています。だから、人々の足を少し止めさせて、彼らに「自分が何を見ているか」を考えさせる作品を作ってきたんです。
―つまり「写真を見ていること」そのものに、人の意識を向かわせようとしているんですね。
ルフ:そのとおり。そうやって人を啓発していきたいという思いが、制作の大きな動機になっています。私たちは、写真に写ったものを、つい現実そのものだと思い込んでしまいがちです。しかし多くの場合、写真は現実を素直に切り取ったものではなくて、カメラの背後にいる撮影者の意図や作為を反映したものです。そのことに気づいてほしいんです。実際に私が活動を始めた1980年代に比べて、現代はインターネットやスマホの普及によって、写真がとても深く社会の中に入り込んでいます。
―写真がどのようなものかを考える必要性は、近年ますます高まっている。
ルフ:そうですね。今は昔と比較して、写真がありとあらゆる場所に存在しています。写真がより巧妙に私たちの意識に働きかけてきているんです。そんな状況の中で、写真というメディアに向き合う態度を問いかけることは、ますます重要になってきていると思います。
でも、私が制作をする動機はそれだけではありません。私のこれまでの人生も作品に色濃く反映されています。日々の生活の中で湧き起こった関心を作品に生かしてきました。
―ルフさんが写真に興味を持ったきっかけは何だったのでしょう?
ルフ: 16歳のころに友達が35ミリのカメラを持っていて、撮影に一緒についていった際、自分もほしいと思ったのがきっかけでした(笑)。当時はごく普通に、アマチュアの写真雑誌を読んだり、巨匠の傑作に触れたりする程度でした。
あと、『ナショナルジオグラフィック』(地理学、人類学、自然・環境学などを取扱う、世界各地で発行されている学術誌)に掲載された写真が好きでしたね。まだ行ったことがない遠い外国の写真を見ては惚れ惚れとしていました。
―そんなルフさんはデュッセルドルフの大学で、ドイツの有名な写真家、ベルント&ヒラ・ベッヒャー夫妻に学びました。ベッヒャー夫妻は工業建築物を匿名的に撮影して羅列する「タイポロジー」という手法で知られて、その弟子は「ベッヒャー派」として現代写真の一大潮流になっています。彼らとの出会いは、どんなものだったのでしょうか?
ルフ:ベッヒャーとの出会いは、一言で言えば衝撃でした。大学の試験で、私はこれまで撮った中で選りすぐりの16枚のスライドを提出したのですが、入学後、はじめてベッヒャーに会ったとき、「トーマス、これはとても美しい写真だけど、君がいままで見た写真の模倣だ。だから、自分独自のものを見つけないといけない」と言われたんです。実際、その後ベッヒャー夫妻が撮った写真を見て、自分の写真は低俗なものに過ぎないと感じて、それから半年はまったく写真が撮れなかった。それほど衝撃的だったんです。
著名な写真家の中には「自分のこの特別なライカでなければダメ」などと言う人もいますが、自分の持つ手段に執拗にこだわる人は、虚栄心の満足を求めているだけだと思います。
―その恩師ベッヒャーから与えられた試練を、どのように乗り越えたのでしょうか?
ルフ:当時、写真の世界ではとにかく大きな写真が良いという流れがあったので、まずは大型のカメラを買って、身の回りの椅子を撮り続けました。それが、最初の『Interieurs(室内)』シリーズにつながります。
当時はまだカラー写真は亜流と思われていて、私もいろいろ批判を受けました。でも人間は色がある世界を見ているという素朴な思いから、カラー写真を選択したんです。そして写真を撮り続ける中で「ベッヒャーの作品はたしかに素晴らしいが、それはひとつの視点に過ぎず、他の視点も存在する」ということに、あるとき気がついたんです。
―さきほど言われていた写真というメディアに向き合う態度も、彼らから学んだものですか?
ルフ:そうです。たしかにすぐに「この作家の作品だ」とわかるような、一貫したブランディングをする作家もいますが、それに対してベッヒャーの教えは、「でも、撮っているのは機械であるカメラでしょう」ということだった。彼らはよく、写真など特定のメディアと関わるなら、その特徴を反映したものを作ろう、メディアの特性に誠意を持とうと言っていました。作家性というものには、最初からこだわりがなかったんです。
―その意味で、ルフさんを有名にした『Porträts(ポートレート)』のサイズの話は象徴的ですね。
ルフ:そもそも『Porträts(ポートレート)』は、コンセプチュアルアートなどが流行する時代に、現代アートから肖像写真が失われたのではないか、との思いから始めたシリーズでした。自分の友人を撮った作品で、最初は小さいサイズで展示したんです。そしたら会場に来た被写体でもあった友人たちが、その小さい写真を見ながら「これはヨハンだね」などと話していた。その光景を見て、私は「いや、本物のヨハンはそこにいるじゃないか」と思ったんです。
―写真と現実を混同していたと。
ルフ:そうです。そこで私は、彼らの写真をできるだけ引き伸ばして、再度展示した。すると「これはヨハンのずいぶん大きな『写真だ』」と反応が変わりました。つまり現実と写真の混乱がなくなって、写真を見ていることに自覚的になったんですね。写真の巨大化は、当時は二次的な芸術と思われていた写真が、第一級の芸術に仲間入りすることにもつながりました。人は写真の前を素通りできず、立ち止まって考えざるを得なくなったんです。
―その後、『Sterne(星)』や『Zeitungsfotos(ニュース・ペーパー・フォト)』のシリーズでは、「撮影」というプロセス自体が手放されることになります。前者は、ヨーロッパ南天天文台が撮影した天体写真のネガを元にした作品で、後者は、新聞から切り取られた報道写真を自分の作品としたものです。カメラを手放すことについて、躊躇はなかったんでしょうか?
ルフ:もちろん、最初は大変でした。自分で構図を決めることができないのは、やはり辛いことです。でも、私がこだわるのは、最終的にどのようなイメージを作り出すかという、結果なんです。
著名な写真家の中には「自分のこの特別なライカでなければダメ」などと言う人もいますが、私にとっては、そんなことはどうでもいい。自分の手持ちの技術で求める結果が達成できないなら、ほかの手段を探るだけです。自分の持つ手段に執拗にこだわる人は、虚栄心の満足を求めているだけだと思います。
―ルフさんは、少年時代から天体望遠鏡を持っていて、大学もアートの道に行くか、天文学を学ぶかで迷ったそうですね。ご自身の宇宙への関心が『Sterne(星)』の基となったと想像できるのですが、『Zeitungsfotos(ニュース・ペーパー・フォト)』では、なぜ報道写真というものに着目されたのでしょうか?
ルフ:もともと、面白いと思った新聞の写真を切り取って集めていたんです。それが10年ほど経つうちに、国際関係から経済、政治、スポーツ、文化などいろいろな写真が入り混じったものになっていきました。あるとき久々にそのコレクションを見返すと、写真が記事と切り離されたことで素性がわからないものになっていたんです。そこから、文章との関係が崩れたとき報道写真の「意味」はどうなるのか、ということに興味を持ちました。

『Zeitungsfoto 017』1990年 ©Thomas Ruff / VG Bild-Kunst, Bonn 2016
―最新作『press++』でも、読売新聞の過去の報道写真も含め、写真と裏に記された編集デスクの指示書きを同じ画面に印刷し、その関係にあらためて着目しています。
ルフ:そもそも、報道写真はひどい扱いを受けていると思っています。写真家が素晴らしい写真を撮っても、デスクの判断で勝手にクロッピング(不要な部分などを切り取る行為)され、ズタズタに編集されます。まったく尊重されない、単に情報のためにあるかわいそうな写真です。それらを、アート写真のように額縁に入れ、展示空間に大事に飾って救いたかったんです。
インターネットの登場以後の一番の問題は、人々がしっかり見ることをしなくなったことです。
―『Sterne(星)』も報道写真を扱った2つのシリーズは、一種のアーカイブを利用した作品だと思います。1990年代にはインターネットが現れ、誰もが画像のアーカイブにアクセスできるようになりますが、インターネットの登場はルフさんにとってどんな意味があったのでしょうか?
ルフ:インターネットは、私の人生の大事な一部になっています。多くの場合、私が求めているイメージは、インターネット上で見つけることができます。これは人類にとって明らかな進歩であり、実際、私はここ20年近く、図書館には足を運んでいません。でもインターネットを使う人の半数以上は、「一番安いスマホはどれか」とか(笑)、バカげたことを探しているだけなのではないかと思います。メディアは疑うのに、インターネットで見たものはすぐ信じる人が多いことも問題ですね。
―デジタル画像の流通の問題を扱った『jpeg』や『Substrate(基層)』シリーズは、そうしたイメージの正体を暴き、見る人に揺さぶりをかける意図も感じさせるものです。
ルフ:私たちが普段見ているものが、どういうものかを示したかったんです。インターネットの登場以後、一番の問題は、人々がしっかり見ることをしなくなったことです。表面ばかりを見て、それを読み解くことができなくなっていると思います。つまり、「見る」という行為の質が失われてきているということです。もちろん、目に見えるすべてのものを疑うわけにはいきませんが、違和感を敏感に嗅ぎとる力については、考えられなければいけないと思います。
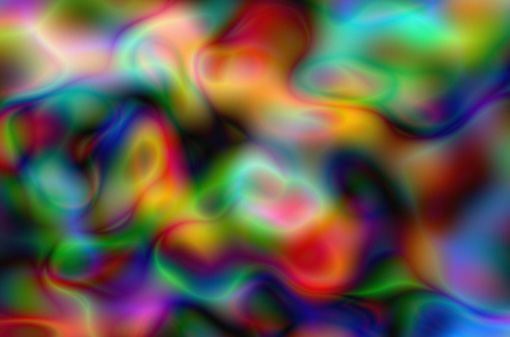
『Substrat 31III』2007年 ©Thomas Ruff / VG Bild-Kunst, Bonn 2016
―写真をどう読み取るかは、たしかにますます重要になっていますね。
ルフ:まもなく我々が周囲を記録する手法というのは、ボタンのような大きさの装置を使うことになるはずです。とにかく万物のすべてをとりあえず記録して、あとから、その焦点はどこにあるのかを解釈し、意味付けるような世界が現れるでしょう。そのとき、見ることの質が問題になるんです。
情報環境がどんなに整ったとしても、物事を単純化して考えるのではなく、生きていく上で感じるリアルで複雑なものに向き合うべきです。
―一方でルフさんの作品では、写真史も重要な要素だと思います。『Porträts(ポートレート)』もそうですが、ネット上のポルノ画像に独自のアプローチをした『nudes(ヌード)』、1920年代に流行った技法を再解釈した『Photogram(フォトグラム)』、約1世紀前に撮られた写真を元にした『negatives(ネガティブ)』など、写真史への言及が散りばめられていますね。
ルフ:写真史は、テクノロジーの歴史と不可分です。私は、20世紀の写真家たちが新しいライカを手にしたことと同じような意味で、いま使える技術を使っているわけです。『Photogram(フォトグラム)』は、印画紙の上に物を置いて露光させるという原始的な技術を、バーチャルな仕方で更新することを目指しました。
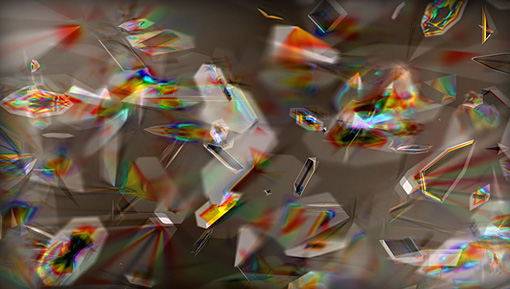
『Phg.12』2015年 ©Thomas Ruff / VG Bild-Kunst, Bonn 2016
ルフ:『nudes(ヌード)』では、自分なりにヌードという古典的な主題に挑戦しようとしたとき、ヌード写真の巨匠であるヘルムート・ニュートンなど男性的な視点でとられた写真が多い中で、そうではない新たな方法を模索しました。そして『negatives(ネガティブ)』シリーズは、私の娘のような、ネガというものに馴染みがない世代が現れ始めたいま、改めてその古い技術にもう一度、しっかり向き合うことで生まれました。

『nudes ez14』1999年 ©Thomas Ruff / VG Bild-Kunst, Bonn 2016

『negatives india01』2014年 ©Thomas Ruff / VG Bild-Kunst, Bonn 2016
―今の3シリーズはすべて「自身で撮る」ということから大きく逸脱したものです。多くの写真家が、自分の手でシャッターを押すこと、あるいはカメラという機械を使うことにこだわり続けることで、結果的に「写真」の可能性は狭まると思われますか?
ルフ:そう思います。NASAが公開する土星の画像を加工した『cassini(カッシーニ)』や、火星探査船が捉えた画像を加工した『ma.r.s』シリーズでは、カメラの背後には誰もおらず、まさに機械が撮った写真を使っています。高解像度のリアルな画像でありながら、究極のフィクションとも言える写真です。
科学者は好奇心の塊で、裸眼では捉えられないものを見るための装置を生み出し続けています。私の作品では、自分の作家性以上に、そうしたテクノロジーの進化によって、人の認識がどう変化したかを掘り下げているんです。
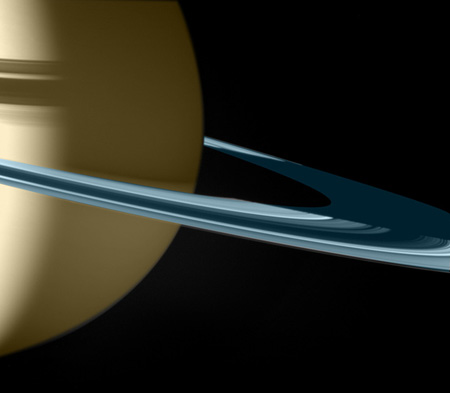
『cassini 10』2009年 ©Thomas Ruff / VG Bild-Kunst, Bonn 2016

『ma.r.s. 19』2011年 ©Thomas Ruff / VG Bild-Kunst, Bonn 2016
―最後にお聞きしたいのですが、あなたが活動を始めたころにはなかったインターネットの環境が、制作や生活の中で当たり前に存在している世代が登場しています。そうした状況の中で、若いアーティストが制作をする際に重要な意識とは何だと考えますか?
ルフ:どんな世代であっても、その時代ごとに独自の表現を模索するべきだと思います。なので若いアーティストには、きちんと時代に向き合った作品を作ってもらいたいですね。先ほど言ったとおり、私はテクノロジーの進化と過去のドイツ写真の歴史の中で仕事をしてきたと思っています。
ドイツ写真の歴史をどう扱うかは、いつも大きな課題のひとつであり、そうした課題は、日本も含めどの国や地域にもあるはずです。私は、いわゆる「インターナショナルスタイル」というものは、存在しないと思っているんです。情報環境がどんなに整ったとしても、物事を単純化して考えるのではなく、生きていく上で感じるリアルで複雑なものに向き合うべきです。
―ルフさんの今までの幅広い試みは、そのような複雑なものに向き合う中で生まれてきたんですね。
ルフ:自分でも、駆け出しのころには、まさか日本で個展をやるとは思いませんでした。ただ、あらためて自分がやってきた数々のシリーズを振り返ると、巨大なジグソーパズルのピースを少しずつ見つけてきたように思うんです。そのパズルが完成したとき、タイトルが「写真の文法」になるのか、「写真の歴史」になるのか、まだわかりません。でもその完成を目指して、今後も写真を通した世界の探求をしていきたいと思っています。
- イベント情報
-
- 『トーマス・ルフ展』
-
2016年12月10日(土)~2017年3月12日(日)
会場:石川県 金沢21世紀美術館
時間:10:00~18:00(金、土曜は20:00まで)
休場日:月曜日(祝日の場合は翌平日)
- プロフィール
-
- トーマス・ルフ
-
1958年、ドイツ、ツェル・アム・ハルマースバッハ生まれ。1977年から85年までデュッセルドルフ芸術アカデミーでベルント&ベラ・ベッヒャー夫妻のもとで写真を学び、ドイツ人家庭の典型的な室内風景を撮り続けた『Interieurs(室内)』シリーズを皮切りに、友人たちの肖像を巨大なサイズに引き伸ばした『Porträts(ポートレート)』で大きな注目を集めました。以来、建築、都市風景、ヌード、天体などさまざまなテーマで作品を制作し、明確なコンセプトに基づいたシリーズとして展開しています。今日に至るまで世界各国での展覧会が開催され、現代ドイツを代表する写真家として活躍しています。
- フィードバック 26
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-




















