尾崎世界観の歌詞とは仕事なのか、私語なのか?
クリープハイプ・尾崎世界観の歌詞集『私語と』が4月18日に発売された。本書には、尾崎自身が選定した75曲の歌詞が掲載され、また「帯」、「はじめに」、「おわりに」という本書のために書き下ろされた歌詞も加えて掲載されている。
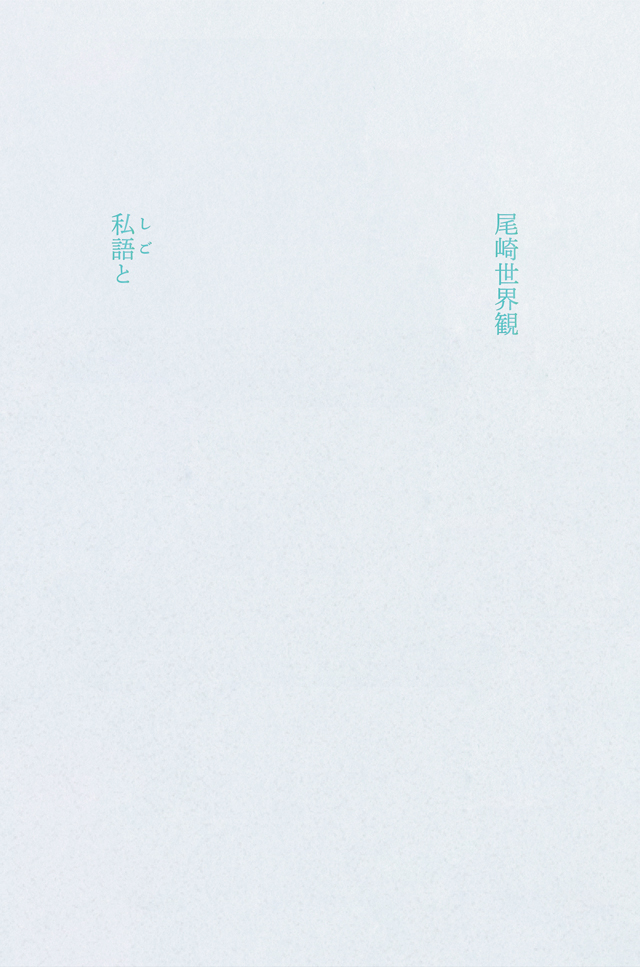
まず、『私語と』というタイトルがいい。クリープハイプは商業的にも成功しているバンドだが、では、彼らの歌詞とは仕事なのか、私語なのか。個人的なものなのか、社会的なものなのか。あるいは、そこに本当に区別などあるのか。同じ音に重ねられた多重の意味に、受け手の視点は滲み、思考は堂々巡りを始める。尾崎らしい言葉遊びだが、単なる遊びでは終わらない、核心めいたものがこのタイトルには既にある。
逆にもうブスとしか言えないくらい愛しい- (“愛す”)
それも言えなかった
急ぎなほら遅れるよ やがてドアが閉まるバス
上に引用したのは、近年でもっともセンセーショナルに受け止められたと言えるクリープハイプの楽曲“愛す”の歌い出しである。ちなみに、この曲のタイトルは“愛す”と書いて、読み方は「ブス」である。「そんな読み方アリなの?」と問われるかもしれないが、作品の神である作者がアリだと言っているのだから、アリなのである。
「え、それ言っていいの?」と、いまの時代どうしたってセンシティブに捉えてしまう「ブス」という言葉を意図的に使うこと、しかもそれを「愛す」と表記すること、そして、<ブスとしか言えないくらい愛おしい>という捻じれた感情を歌うこと。そんな堂々巡りの個人の心の世界とは裏腹に、進む時間とシステマチックに回る社会を暗示する「バス」の存在は、絶望か、救いか? 見事な歌詞である。
「この曲のメッセージはなに?」「この曲はなにが言いたい曲なの?」――そんな愚かな問いを一笑にふすように、この曲は人間という生きものの悲しく、愚かで、愛おしく複雑怪奇で答えのない時空、それ自体を描いている。
尾崎世界観は小説執筆などでも評価を得ていることから「言葉の人」と目されがちだが、それは言葉に対しての全面的な信頼があるということではない。「愛す」を「ブス」と読ませるトリッキーな手法に顕著なように、彼はむしろ「言葉」というものをとことん疑っている人と言っていいだろう。それは、彼が「世界観がいいね」という雰囲気だけの賛辞に嫌気がさして「尾崎世界観」を名乗り始めたというエピソードにも然り。言葉を疑うからこそ言葉に敏感にならざるを得なかった。尾崎世界観とはそういう人である。
言葉を疑うこと。それはすなわち、我々が生きるこの社会を、コミュニケーションを、疑うこととも言えるだろう。しかし、彼は反社会的な人間であるというわけでも、非社会的な人間であるというわけでもない。むしろ、社会とはなにか、個人とはなにか――そういった原始的な問いに対して、まるで人体実験でもするかのようにぶつかっていきながら、尾崎は彼自身なりの哲学を歌のなかで構築していったのだと、あるいはいまもその過程なのだと、この歌詞集『私語と』を読みながら尾崎のアーティストとしての歴史を振り返ってみて思うのだ。

尾崎世界観(おざき せかいかん)
1984年11月9日、東京都生まれ。2001年結成のロックバンド「クリープハイプ」のボーカル・ギター。2012年、アルバム『死ぬまで一生愛されてると思ってたよ』でメジャーデビュー。2016年、初小説『祐介』(文藝春秋)を書き下ろしで刊行。2021年『母影』(新潮社)が第164回芥川賞の候補になる。その他の著書に『苦汁100%』、『苦汁200%』(ともに文藝春秋)、『泣きたくなるほど嬉しい日々に』(KADOKAWA)。千早茜との共著に『犬も食わない』(新潮社)、対談集に『身のある話と、歯に詰まるワタシ』(朝日新聞出版)がある。
尾崎の詞作の特徴のひとつは、時折、他者と同化してきたことである。女性の目線で歌うとき、彼の男性としての身体は軋むだろう。ロックバンドのファンという目線で歌うとき、彼のロックバンドのボーカリストとしての身体は軋むだろう。そうやって軋みを上げる身体の当事者として、尾崎は「自分とはなんなのか」「社会とはなんなのか」を問い続けなら、自分自身と社会とのバランスを探り続けてきたのではないか。「こう生きるのが正しい」「こう考えるのが普通である」――そんな言説に納得できずに、自分なりの答えを探し求める。その不器用で誠実な態度が、この10年あまり、尾崎世界観という人を特別たらしめてきたといえる。
そんな彼の姿から、CINRAの記事の見出しになるような教義めいたものを得ることは難しいが、彼の「疑え」という鋭い眼光は痛いほど感じ取ることができる。
尾崎にとって「歌詞」は、音楽と言葉が密接に結びついて生まれたもの
歌詞集『私語と』は、まず冒頭に掲載される新作歌詞「はじめに」が興味深い。
この「はじめに」は、歌があり、その言葉が「歌詞」として抜き出され、本にまとめられるに至る――そんな、この歌詞集が成立する過程を綴ったものだ。それはこの歌詞が最後、<枯れた言葉を紙の上に並べて綴じれば / 立派な歌詞集の出来上がり>と締められているところからも明らかなのだが、ここで尾崎は、この歌詞集に掲載された言葉たちを「枯れた言葉」と表現している。
メロディーから引き離された時点で、ここに掲載される言葉たちは本来の姿とは「別物」なのだと彼は主張しておきたかったのだろう。この「はじめに」で、言葉がメロディーから切り離される瞬間の描写は、生きものを生きた状態で解剖するかのような、グロテスクさすら感じさせるものである。
歌として一つになった言葉とメロディーを- (“はじめに”)
テーブルの上に置く
言葉の中心を左手で摑み 右手でメロディーの根本を押さえつける
左手の指先に込めた力で メロディーから言葉を勢いよく引き剝がす
しかし、いくら「枯らす」という行為を通したとしても、この歌詞集に編纂された歌詞たちは決して腐敗してはいないのだから、ここにあるのは尾崎世界観という作詞家の凄みである、と、読者としては思う。だが、それでも尾崎が「はじめに」において、この歌詞集生成の過程をまるで肉体を喪失するかのような描き方で綴ったのは、それだけ尾崎にとって「歌詞」は音楽と言葉が密接に結びついて生まれたものであり、ここに集められた言葉たちはあくまでも音楽とともにあるからこそ表現し得たものたち、という意識が強いからだといえる。
尾崎は「歌」という身体表現だからこそできることをしてきた
自身で作詞をする音楽家に取材をしていると時折、話に聞くのは、作詞は不自由だからこそ難しい、ということである。メロディーの抑揚や楽曲の構成、あるいは楽曲の時間……等々、そうした「不自由」のなかでなにを語り、なにを描くのか? というところが、作詞家にはつねに問われる。そういった意味で、この「はじめに」の歌詞は、この歌詞集に掲載された言葉たちが本来的にいかに「不自由」とともにあったのかを主張しているとも言える。
「不自由」と書くとネガティブなように捉えられるかもしれないが、「歌の不自由さ」とは同時に「歌の秩序」とも言い換えられるだろう。「歌」という秩序のなかでこそ命を与えることができた言葉たちなのだと、尾崎はこの歌詞集の冒頭で強く発している。
最後に、個人的に興味深かった話をひとつ。去年、新潮社のYouTubeチャンネルで公開された尾崎と小説家・柳美里の対談動画のなかで、かつて柳が、尾崎が「イ」の音を歌っているときの表情がいいと伝えた、という話になる。そこで尾崎は、「イの発音がじつは苦手で、歌うことの苦しさの象徴のような音でもある」と語っている。そして、その苦手な発音を褒められることで救われる、と尾崎は柳に告げる。この場面に、私は尾崎の、言葉と身体の接続への自覚を感じた。尾崎世界観という人は本当に、「歌」という身体表現だからこそできることをしてきたのだと思った。
だからこそ、尾崎の歌詞を本当に堪能するのなら、やはりクリープハイプの音楽を聴くべきなのだ。尾崎世界観はドキュメンタリー作家でもなければ、嘘つきの教師でもない。彼は優れた音楽家である。だからこそ、この10年余りの期間に彼が成し得たことを考えようとしたときに、私はこの歌詞集から顔を上げて、もう1度、音楽プレイヤーの再生ボタンを押すべきなのだ。そうやって言葉から引き離されてしまった律動を、もう1度、聴き手としての力で、この言葉たちに与えよう。
- 書籍情報
-
 『私語と』
『私語と』
2022年4月18日(月)発売
著者:尾崎世界観
価格:1,870円(税込)
発行:河出書房新社
- リリース情報
-
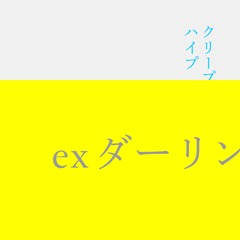 クリープハイプ
クリープハイプ
『ex ダーリン』
2022年4月18日(月)配信
- リリース情報
-
 クリープハイプ
クリープハイプ
『ex ダーリン 弾き語り』
2022年4月18日(月)配信
- プロフィール
-

- 尾崎世界観 (おざき せかいかん)
-
1984年11月9日、東京都生まれ。2001年結成のロックバンド「クリープハイプ」のヴォーカル・ギター。2012年、アルバム『死ぬまで一生愛されてると思ってたよ』でメジャーデビュー。2016年、初小説『祐介』(文藝春秋)を書き下ろしで刊行。2021年『母影』(新潮社)が第164回芥川賞の候補になる。その他の著書に『苦汁100%』、『苦汁200%』(ともに文藝春秋)、『泣きたくなるほど嬉しい日々に』(KADOKAWA)。千早茜との共著に『犬も食わない』(新潮社)、対談集に『身のある話と、歯に詰まるワタシ』(朝日新聞出版)がある。
- フィードバック 30
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-




