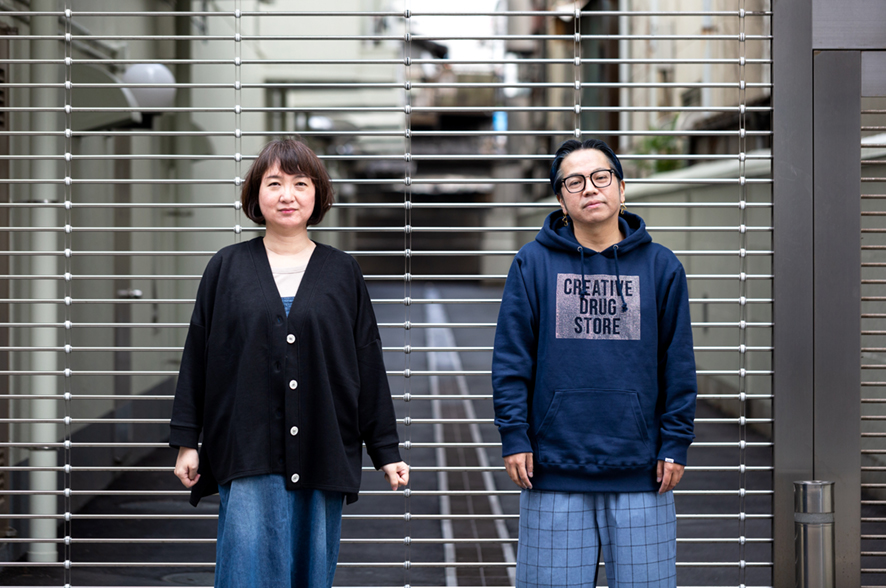企業に所属する会社員からは、なかなか想像が難しい「フリーランスで働く」立場。「どう仕事を増やすのか」「収入に関して心配はないのか」「依頼主とはどんな関係を築いているのか」。今回は、フリーランスで長年活躍を続ける2人のライターに話を聞いた。
1人はテレビや映画の分野で主に活躍し、2021年には共著『韓国映画・ドラマ――わたしたちのおしゃべりの記録2014~2020』を上梓した西森路代。もう1人は音楽ジャンルを中心に活動し、ライターだけでなくミュージシャンのマネジメント会社や音楽レーベルの代表も務める三宅正一。
自らがフリーランスとして働くことはなくても、フリーランスのクリエイターと協力して仕事をしている企業、フリーランスの協力なしに業務を進められない企業は多いはずだ。本記事が、フリーランスが置かれる立場を少しでも理解する一助になるとうれしい。
願望か、なりゆきか。2人のあいだで異なる、ライターまでの道のり
─本日はそれぞれに、「フリーランスとして働くこと」「フリーランスの置かれた立場」について、話せる範囲でお伺いできればと思っています。
三宅:この話題について話すのがぼくでいいのかなと思っていますが(笑)、よろしくお願いします。
西森:私もです……。ライターって決まったルートがないですもんね。

左から:西森路代、三宅正一
─いえいえ。むしろリアルな声だと思いますので、ありのままにお話しいただければと思います。最初に、おふたりがライターとしてフリーランスで働くようになった経緯を教えてもらえますか?
三宅:ぼくは大学卒業後、スイッチ・パブリッシングにアルバイトとして入社して、『SWITCH』というカルチャー誌で編集と広告営業をやっていました。でもいわゆるモラトリアムな感じで(笑)、2年くらいでほかのこともやりたくなって会社を辞めて。肉体労働の仕事をしながら次にやりたいことを探していたんですが、結局似たような仕事に辿り着き『EYESCREAM』という、これまたカルチャー誌の編集を1年くらい手伝って、そのあとフリーランスになりました。
恥ずかしながら、目的を定めてこの仕事に就いたというよりも、流れのままに生きていたらライターになっていたという感じで。じつは自分では「音楽ライター」とも名乗ってないんですよ。たまたま音楽中心のライターになってしまっただけで。
─実際、「気がついたらライターをやっていた」みたいな方は業界に多いですよね。
三宅:そうですね。もともとカルチャー誌出身なので、いろいろなジャンルをやりたいと思っていたし、いまもそう思っています。だから音楽以外の仕事でも依頼してもらえればお受けしています。
─フリーランスになった当初はどのように仕事を受注していましたか?
三宅:いろんな編集部に営業にも行きましたけど、最初は自分が所属していた雑誌からお仕事をもらうかたちが多かったですね。そこから派生していったという感じです。

三宅正一(みやけ しょういち)
フリーランスライター。音楽を軸としたカルチャー全般に関するインタビュー及び執筆を担当。レーベル・Q2 Records主宰。
─西森さんがライターになったのはどのような経緯だったでしょうか?
西森:私は地元、愛媛の大学を卒業後、地元のテレビ局で6年くらい働いて。そのあと誘われて別の仕事をやっていたのですが、それも終わってしまって……というのを繰り返して、どうしようも行き場がなくなったときに、「何も決まってないけど上京しよう」と思って東京に来ました。そのときは映画かメディア関連の仕事がしたいなと思っていたのですが、自分の経歴では難しそうなので、派遣でテレビ系の会社で働きました。
とはいえ、地元テレビ局のときも、派遣のときも、何か自分が作るということとは距離のある部署だったので、もうちょっと自分が企画などから関われる仕事がしたいなと思って、いろいろ探していたら、とある編集プロダクションが求人をしていて。当時の私は編集のイロハもまったくわからなかったのですが、その編プロさんは手芸の制作過程などがわかっている人が欲しかったようで、手芸が好きだった、製図を書ける私は無事働けることになったんです。そこから派遣と編プロを並行して、2年で派遣をやめました。
当時から私は映画……なかでもアジア系、特に香港映画や台湾映画が好きだったので、編プロ内で企画を立ち上げて雑誌をつくるようになって。それがエンタメ系の企画や記事に携わるようになったきっかけです。さらにその頃、ラジオの仕事に誘われたんです。
三宅:ほう。おもしろい展開ですね。
西森:アジア系のエンタメの現場で知り合った方に、「ラジオのディレクターをしないか」と誘われたんです。その番組のディレクターとして、構成原稿を書いたり、取材をしたり、キューも出したし、収録、編集、完パケまでやりました。ラジオディレクターとライターを3年くらいかけもちをして、その番組が終わると同時にライター1本になりました。
K-POPや韓国ドラマ、映画の取材にとにかく奔走していたので、そのときの経験がかなり役に経っています。いまはインタビューの仕事のほかに、批評やコラムを書いたり、対談をしたりもしています。

西森路代(にしもり みちよ)
フリーランスライター。主な仕事分野は、韓国映画、日本のテレビ・映画やお笑いについてのインタビュー、コラムや批評など。著書に『K-POPがアジアを制覇する』(原書房)、ハン・トンヒョン氏との共著に『韓国映画・ドラマ――わたしたちのおしゃべりの記録2014~2020』(駒草出版)。
─おふたりとも経歴が全然違って興味深いですね。
三宅:確かに。でもライターって皆さん、どうやってこの職種になっているんでしょうね。結構みんな違いますよね。
─私は昔から音楽ライターになりたいと思っていたので、三宅さんのように「いつのまにかライターになっていた」という話を聞くとうらやましいなと思います。
西森:わかります。私も派遣で働いていたときは特に「メディアの仕事がしたいけど、どうやったらなれるんだろう。何をしたらいいんだろう」と思っていました。
─資格があるわけでもないですし、「ライターのなり方」ってないですよね。
三宅:よく言われることですが、名刺を持っちゃえばその時点でライターと名乗れますしね。
西森:かといって、何も経験がないときに「ライターになりたいんです」と言ったところで、私がライターを目指していた時代だと、どの媒体からも仕事を頼んではもらえなかったですね。今はそんなことはないと思うんですけど。
三宅:昔はどこか出版社に何年か勤めて、ゆくゆくは独立みたいなイメージでしたけど、いまはSNSやブログもあるし、何かしらのプラットフォームで発信できる。そういう意味では、ライター志望の人にとってはいい時代なのかもしれない。
─実際にSNSで人気になって、ライターになっている方もいらっしゃいますしね。
三宅:ね、夢がありますよね。
起業と書籍の執筆。2人のライターとしてのターニングポイント
─おふたりはインタビューや批評などさまざまなお仕事をされていらっしゃいますが、これまでのお仕事のなかで一番うれしかったことはなんですか?
三宅:ぼくは松本人志さんにインタビューできたこと。あれはうれしかったですね。ダウンタウン世代なので。
─それはどういった経緯だったんですか?
三宅:松本人志さんが監督された映画『R100』(2013年)のプロモーションですね。『Rolling Stone Japan」『EYESCREAM』の2誌でインタビューさせてもらいました。付き合いのある編集部の方によく「ダウンタウンフリークで……」という話をしていたことから声をかけてもらえたんです。そういうのって大きいですよね。
西森:大きいですね。
三宅:光GENJIのかーくん(諸星和己)にインタビューしたいなとTwitterに書いたときも、その1か月後くらいにインタビューの機会をもらいました(笑)。かーくんの取材も最高だったなあ。本当に「言うもんだなあ」と思いましたね。
西森:私はインタビューでうれしいことも、もちろんたくさんあったのですが、一番というとやはり書籍を出したことですね。というのも、『K-POPがアジアを制覇する』という書籍を出す1年前くらいに「インタビューだけじゃなくて、批評やコラムを書くような仕事もしていきたいな」と思って、Twitterのアカウント名を本名にして。その頃K-POPの仕事が多かったこともあって、K-POPで思うことをTwitterで書くようにしたんです。そうしたら書籍のお話をいただけて。

西森路代『K-POPがアジアを制覇する』(原書房)書影
西森:その頃は2,000字のコラムすら書いたことなかったのに。しかもその出版社の批評の書籍は好きで読んでいたので、すごくうれしいかたちで叶いました。けどそのあとお話はいただいていたのに、自分の力量が足りなくて10年くらい本が出せなくて。ようやく2021年に、ハン・トンヒョンさんと2人で出せたので(『韓国映画・ドラマ わたしたちのおしゃべりの記録2014~2020』)、それもうれしかったですね。

西森路代+ハン・トンヒョン著『韓国映画・ドラマ わたしたちのおしゃべりの記録2014~2020』(駒草出版)書影
三宅:書籍を出されている人はシンプルに尊敬します。話をしていて、ぼくはインタビューが好きなんだなとあらためて思ったので、自分が書籍を出したいかというとそれはまた別の問題ではありますけど、「書籍を出していないコンプレックス」みたいなものも、なくはないんです。書籍を出しているとライターとして「格が違う」みたいな(笑)。
西森:そんなことないですよ。でも逆に、書籍を出すとインタビューの仕事があんまり来なくなったりするんですよ。
三宅:あー、「インタビューはしないんだろうな」って思われるんですか?
西森:そうそう。だから私はそう思われないように、「インタビューもやりますよ」「批評以外も書きますよ」「気軽に頼んでくださいね」というのを一生懸命、表に出していました。本を出すだけで食べていけるってことは、よほどベストセラーを毎回書けるとかではない限り、ほぼないと思うので。
─西森さんは「批評やコラムの仕事もしていきたい」と思ってSNSの使い方を変えたとのことでしたが、三宅さんもそういった模索をした時期はありますか?
三宅:模索……は常にしていますが、大きかったのは、会社を立ち上げたことかなあ。会社ではアーティストのマネジメントやレーベルもやっているんですが、「このままライターだけでやっていくのがイメージできないな」と思っていた30代後半くらいのときに、いまマネジメントをしているODD Foot Works(当時は「踊Foot Works」)と出会って。
会社をつくる気もなかったし、他人のマネジメントなんてできないと思っていたのに……つくっちゃいました。でもそこでライターをやめようとは思わなくて。むしろ両方ともやることに意義があると思って、ライターも続けています。ゆくゆくは新しい事業も展開したいと考えてます。
西森:インプットとアウトプットの両方ができるという意味でも、いいですよね。
─西森さんは、変革期を挙げるとしたらやはり書籍を出したときですか?
西森:そうなんですけど、経済的には本を出したあともわりと苦しくて。本を出したことが原因じゃないですけど、仕事量のわりにお金が稼げないとか、「なんでもやります」と言って受けても金額と見合わなくて、忙しいだけで、全然稼げてなかったとか……比較的最近までずっときつかったですね。
ライターって、雑誌などのレギュラー仕事が定期的にあると安定するじゃないですか。でも私はわりと変則的な感じなので、依頼が来る月もあれば来ない月もある。それにいまは上がってきてはいるけれど、ウェブメディアだと原稿料が低い場合も多かったりして。
三宅:それはありますよね。
自分で新しい仕事をつくり、次につなげる。業界がシュリンクする時代のライターの働き方
─三宅さんも「このままライターだけでやっていくのがイメージできないと思った」とおっしゃっていましたが、原稿料の低さも引っかかっていた要因の1つですか?
三宅:まあ、それもありますね。でもそこは難しい問題で。全部が全部、自分でどうにかできることでもないので。たとえば音楽業界だったら、業界全体のお金がシュリンクされつつあるわけで。そこから捻出されるお金に頼るよりも、自分で発信して何かを生んでいくほうがいいんじゃないかなと思ったというのもあります。受け仕事だけではなく、自分で仕事をつくっていくことをもっとやっていきたいなと。
「ライターだけじゃ食えない」じゃなくて、新しくお金をつくっていくという考え方にシフトしていったほうがいいんじゃないかなって。会社員をやりながらライター活動をされている方もいるじゃないですか。いま、自分がこういう働き方をしていて、あらためて「そういう二足の草鞋を履くやり方もあるよな」と感じています。

西森:私は、どこかで書いた記事がたくさん読まれて、それで知ってもらえて、ほかからも頼まれるみたいなことが時々あって。そういう仕事に広がりをもたらしてくれる記事を時々は書けたらいいなとは思います。
三宅:ああ、代表作みたいなものですよね。それは次の仕事につなげるために大切だと思います。
西森:あと、私はとにかくいつもツイートしていて(笑)。何を見たとか、こう思ったとか、いまこれにハマっているとか、だらだら書いているだけなんですけど、それで依頼がくることがすごく多いんですよ。昔は「業界人との飲み会に参加したほうがいい」みたいに言われていましたけど、絶対にTwitterをしていたほうが仕事は増えるんじゃないかって思っています。もちろん、無意識に不用意なことを言ってしまうかもしれないので、けっこうバランスは重要になってるかもしれないけど。
三宅:ウェブ媒体だったら、PV数に応じてプラスでインセンティブが発生するみたいなこともあるといいのにと思うんですよね。
西森:そういうシステムを導入している媒体もあったりしました。「何万PV以上でプラスいくら」みたいな。でもそこまでバズってたくさんの人の目につくと、いろんな意見が自分のところに来て大変な目に遭うこともあるんですよね。賛否の反響が多い記事だからこそよく読まれるところがあって。

─確かに、よく読まれる記事をつくった対価としてのインセンティブがあるといいなと思う一方で、私はウェブメディアでの編集も経験があるので、PV数を判断基準にするのは難しいなとも思っています。PV数って、もちろん記事の良し悪しも左右しますが、取り扱うアーティストやコンテンツの知名度や人気が直結することでもあるので、PV数のために人気のあるコンテンツばかりを追うようになってしまうのはメディアとしてどうなんだろうという気持ちもあって。
三宅:確かにそれはありますね。数字ばっかり追っていくと、記事のモラルが欠如しちゃう可能性もありますしね。暴走してしまう怖さとか。
西森:煽るようなタイトルをつけたりとかですね。
- ウェブサイト情報
-
 CINRAが提供する求人情報サービスはこちら
CINRAが提供する求人情報サービスはこちら
「CINRA JOB」はクリエイティブ業界の転職や新たなキャリアをサポートするプラットフォームです。デザイナーや編集者、プランナーなど魅力的な企業のクリエイティブ求人のほか、働き方をアップデートするヒントなど、さまざまなお役立ち情報をお届けします。
教育から発注の仕方まで。ライターとメディアのよりよい働き方
三宅:そういう意味では、タイトルや見出しをつける編集さんがしっかり品位のある仕事をしてくれると、一緒に仕事をするライターもすごく勉強になると思うんです。それは結果的にライターが育っていくことにもなると思っていて。特にウェブメディアはどうしても、書いて公開して、という歯車のサイクルで刹那的にやっているところが少なくない印象があるので。
実際、文章が破綻している記事をよく見かけますが、それだけ文字がどんどん消費されているということだと思うんです。そりゃ原稿料の単価も下がる一方だろうなって。昔は編集者が書き手を育てるみたいな意識があったけど、いまはその意識が希薄ですよね。もうちょっと媒体側もそういうことを意識してもらえたら、ライターも編集者も育っていくんじゃないかなと、常々思っています。
西森:取材しないでインターネットやテレビの情報を集めただけでインスタントにつくる「こたつ記事」なんかも話題になりました。予算がないなかで簡単にバズる記事をつくる方法を考えた結果、こたつ記事を量産するしかないという発想なんでしょうね。
私も経済的に苦しい時期があったので、そういう仕事をやるようになってしまうライターさんの気持ちもわかります。でも、やっぱり安易に記事をひっぱってきて、拡散させることで責任を問われかねないですよね。たぶん、働き方としても、短い時間で量産しないといけなくてキツいだろうし、結局はなかなかそこから次にはつながりにくいんじゃないかなと。
三宅:斜めな見方かもしれないですけど、ライターのギャラの単価が低いのって、そもそも「書こうと思ったら自分で書けるけど、まあ仕事あげますよ」みたいな感じで頼まれているからなんじゃないかなと思うこともあって(笑)。そういう意味でも、ライターが批評眼を持つということはすごく大事だと感じます。
西森:「インタビューにも批評性が出る」と音楽評論家の柳樂光隆さんが言っていたんですが、インタビューにもそういうものが自然と出ているでしょうしね。
三宅:その人ならではの視点のようなものですよね。
西森:だから、「インタビューは誰がやっても同じ」と思わないで頼んでほしいですね。

─メディアとの関係性の話が出ましたが、クライアントとの発注書や請求書のやりとりについても聞かせてください。私個人の体感としては、クライアントとの間で発注書を受け取ることが少ないという印象があるのですが、おふたりは毎回発注書を受け取っていますか?
三宅:発注書を受け取ることはありますね。送ってくれる企業は少ないですけど。
西森:そうですね。終わったあとにもらうことが多いかも。
三宅:あー、たしかに送ってくれる企業も、納品したあとにもらいますね。
─発注書って、本来は仕事を依頼する際に発行するものなんですよね。
三宅:たしかに。発注書どころか、なんならギャラの金額が提示されないまま進む仕事とかもまだありますよ(笑)。
西森:ありますね。フリーランスという立場上、仕事をする前に面倒なライターと思われたくないから、こちらからは聞きにくかったですけど。最近は少なくなりました。
三宅:あとで金額の交渉をする、みたいなこともありますよね。たまに、入金されるまで自分のギャラがいくらか知らないときありますもん。なるべくそうならないように努めてますが、あの前時代的な慣習は本当によくない(笑)。
─CINRAも導入しているシステム「pasture」では、納期やギャラ、仕事内容など、ログをきちんと残せるんですよね。
西森:CINRAのお仕事を同時期にいくつかやらせてもらっているときがあるんですけど、「依頼中」や「提出済み」といったステータスが、pasture上で見えるのがありがたいなと思っていました。
─請求書の発行タイミングにもメールが届きますしね。
西森:そうなんです。メールで通知が届くので、メールがきたらそのときにすぐ作業するようにして。そのおかげで忘れないから「なんて便利なんだ!」と思います。
三宅:確かに「忘れない」って大事ですよね。いままで請求書を出し忘れて取りこぼしている売上ってじつは結構あると思う。
─しかもpastureでは受注側の作業って内容を確認してクリックするだけなので。
三宅:自分で会社を始めてからは請求書をいただく側にもなったので、いまはあんまり忘れたり、作業を後回しにしたりしなくなりましたけど、会社を立ち上げる前にこのシステムがあったら、本当に楽だったと思います。
西森:私、本当に請求書をつくるのがめちゃめちゃ苦手で。朝、「あー、請求書つくらなきゃ」って考えていたら夕方になっていたりすることがあるんです。
三宅:めちゃくちゃわかります(笑)。
西森:昔は郵送だったから、プリントしたあと、用紙を折って封筒に入れて、切手を貼って郵送するという作業に1日かけてみたいな。でも結局ポストに出し忘れたまま家に帰ってきたり……って本当に大変で。1回、その様子をTwitterで中継してたこともありました(笑)。

─請求書をつくる上で、何が一番のネックですか?
西森:さきほども挙げたとおり、つい忘れてしまいがちになってしまう点ですかね。
あと、私は部屋が乱雑になりがちなので、そもそもプリンターまで行くのが大変(笑)。しかも、いざ請求書を印刷しようとしたらプリンターの調子が悪かったりすることが多くて。
三宅:わかります。必要なときに限って、プリンターのインクが切れていたりしてね。
─そういう意味でも、メールが来たらリンク先に飛んでチェックするだけのpastureは楽ですよね。
三宅:紙やPDFで管理するよりも媒体の編集さんの負担も少ないだろうし、なんなら全ての部署の人にとってありがたいシステムなんじゃないかな。
西森:pastureを使ってるCINRAの記事だから言っているんじゃなくて、本当にずっと思っていました、「やりとりのある会社がこのシステムを導入してくれないかな」って。
―メディアに限らず、クライアントがフリーランスの事情も汲んで、よりよい関係を築けるような発注や請求の方法を模索していってくれるといいですよね。

- サービス情報
-

- プロフィール
-
- 西森路代 (にしもり みちよ)
-
愛媛県生まれ。地元テレビ局、派遣社員、編集プロダクション勤務、ラジオディレクターを経てフリーライターに。主な仕事分野は、韓国映画、日本のテレビ・映画やお笑いについてのインタビュー、コラムや批評など。著書に『K-POPがアジアを制覇する』(原書房)、ハン・トンヒョン氏との共著に『韓国映画・ドラマ――わたしたちのおしゃべりの記録2014~2020』(駒草出版)がある。
- 三宅正一 (みやけ しょういち)
-
株式会社スイッチ・パブリッシング入社。カルチャー誌「SWITCH」の広告営業と編集を兼任。その後、カルチャー誌「EYESCREAM」の編集を経て、2004年に独立。フリーライターとしての活動を開始し、現在に至る。現在は音楽を軸としたカルチャー全般に関するインタビュー及び執筆を担当。レーベル・Q2 Recordsの主宰でもある。
- フィードバック 25
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-