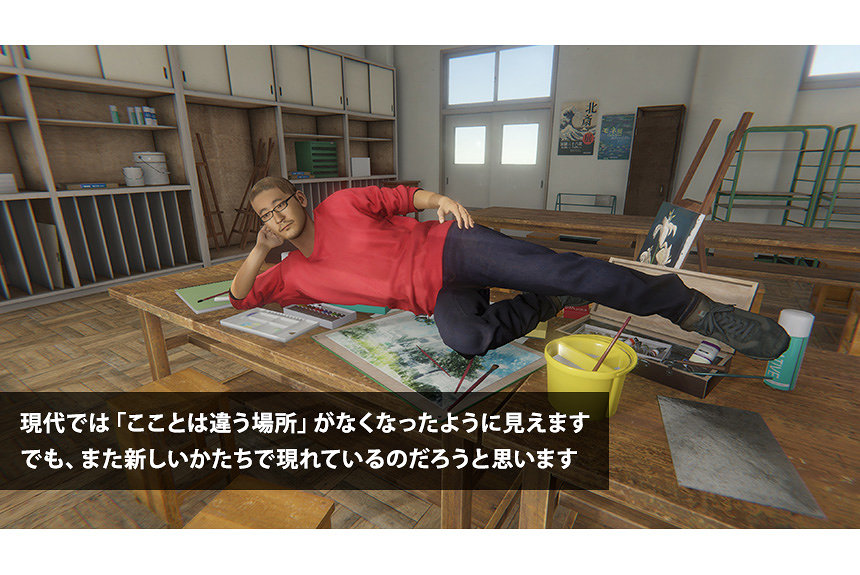2020年秋の開催をもってその役目を終えた『フェスティバル/トーキョー(F/T)』。1998年の『東京国際演劇祭’98池袋』を原点とする同フェスティバルは、東京オリンピック誘致のための文化事業という実利的な一面を持ちつつも、挑戦的な国内外のアーティストを多く紹介し、そのときそのときの東京の「いま」を、舞台芸術・身体表現というレンズを通してさまざまに描き出してきた。高山明 / Port B、飴屋法水、木ノ下歌舞伎など、作品制作・発表を通して評価を高め、またアーティストとしての新たな旅を歩み始めた者は少なくない。また、後期の『F/T』で、ZINE制作によって人と都市の関わりを実践的にプログラミングした「ひらけ!ガリ版印刷発信基地」も記憶に残るプロジェクトだ。
これらを概観し、「『F/T』とはなんだったか?」をごくシンプルに言葉にするならば、それは「芸術や劇場を社会にむけてひらき、発信する」ことであったかもしれない。今日あらゆる場所で語られる持続性やダイバーシティやセクシュアリティは『F/T』の約11年のあいだ、さまざまな作品のなかで語られてきた。あるいは暴力、差別、格差といった、人間社会に否応なくつきまとう暗い側面も、同様にさまざまに提示されてきた。2022年の今日においては、そのどれもがより切迫した現実として日本に住む人々に突きつけられていることを感じる。『F/T』が残したもの、示したものをアーティストやジャーナリストの寄稿から考えてみたい。
「ぼくは何をもって劇場を劇場だと認識していたのか、そもそも劇場とは何なのか」(文:演出家 / 舞台美術家・杉原邦生)

杉原邦生(すぎはら くにお)
演出家、舞台美術家。1982年東京生まれ、神奈川県茅ヶ崎市育ち。京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)映像・舞台芸術学科 同大学院 芸術研究科 修士課程修了。学科在籍中の2004年にプロデュース公演カンパニー・KUNIOを立ち上げ。(撮影:細野晋司)
ぼくが初めて『F/T』に参加したのは、2011年公募プログラムとして自身のカンパニー「KUNIO」で上演したKUNIO09『エンジェルス・イン・アメリカ』(以下、『エンジェルス〜』)でした。劇作家トニー・クシュナーが1980年代のアメリカを舞台に描いたこの傑作は、第1部「至福千年紀が近づく」と第2部「ペレストロイカ」にわかれており、上演時間は合わせて7時間半を超える大作でした。この上演が以降、木ノ下歌舞伎『東海道四谷怪談―通し上演―』(2013、2017年)『三人吉三』(2014、2015年)やKUNIO15『グリークス』(2019年)など、上演時間の長い作品へ定期的に取り組んでいくきっかけとなりました。

2011年『エンジェルス・イン・アメリカ』(撮影:清水俊洋)
また、吉田美枝氏による既存の翻訳をベースに、全編原本から翻訳を見直し自ら上演台本を作成した経験が、後に定着する「海外戯曲を上演する際には新訳台本をつくる」という創作スタイルのはじまりとなりました。さらに、『F/T』での上演で得た経験が、その後の創作活動に大きな影響を及ぼしています。
当時の活動拠点であった京都で初演された『エンジェルス〜』は、長方形の舞台を二側面から客席で挟むという形状の舞台美術でした。そのため、固定客席を持たない、いわゆるフリースペース型の劇場が必要条件だったのですが、公募プログラムに用意された会場にはそういった形式の劇場がなく、ぼくたちに割り当てられた上演会場は自由学園明日館の講堂という場所でした。この講堂は昭和2(1927)年、遠藤新による設計で建設されたもので、平成9(1997)年には国の重要文化財に指定された木造建築の建物です。
教会の礼拝堂のような雰囲気が『エンジェルス〜』の作品世界を体現しているように思え、空間そのものはとても気に入ったのですが、そもそも劇場ではないので、当たり前に劇場にある設備がまったく存在しません。まずは電源不足の問題、そして遮光と遮音ができず、照明機材やスピーカーを吊るためのバトンも皆無。劇場ではない空間を劇場に変えていくところからプランニングをしなければなりませんでした。
電源の問題は『F/T』側から工事を依頼し、希望するスペックには及ばなかったものの大幅な電力アップを実現してくれました。遮光と遮音については、窓ガラスに遮光板を貼り付けた上で、設置されているロールカーテンを閉めて対応しましたが、はっきり言って遮音についてはほとんど効果がなかったと思います。周りは閑静な住宅街、僕の演出作品ではかなりの大音量を出すので絶対に苦情が来ると思っていましたが、ひとつの苦情も出なかったことがいまだに信じられません。
さらに大変だったのはバトンの設置です。男性5〜6人で持ち上げるのが精一杯の立体トラス(照明や音響機材を設置するための骨組み)を組み立てていく作業の時には、大袈裟ではなくトラスの下で潰れ死ぬと思いました。この決死の作業により講堂が劇場へと変貌し、この作品のためだけの、えもいわれぬ劇空間が生まれたのです。
それまで、劇場(元は劇場ではない建物を改築した劇場を含む)での上演経験しかなかったぼくにとって、この「劇場化作業」は衝撃的な体験となりました。ぼくがそれまで何をもって劇場を劇場だと認識していたのか、そもそも劇場とは何なのか、劇場が持つべきものとは何か、そして、ぼくが求める劇場とはどんなものなのか。そんな思考が上演中、ぐるぐると頭を巡っていたような気がします。
観客が並ぶ客席最後列の2メートル後ろには細い路地があって、その路地の向かいには民家が立ち並んでいるという絶対的現実が在る。けれど、目の前では80年代アメリカを生きる人々の「ふり」をした日本人たちが演技をし、そこに立ち現れる虚構を観客たちが追い続けている。そんな空間をどこか冷静に見つめる自分がいました。

2011年『エンジェルス・イン・アメリカ』(撮影:清水俊洋)
『F/T』は「社会の中で舞台芸術を思考すること」を、観客、アーティストに強く問い続けてきた
この体験が、その後の作品創作における空間意識を決定づけました。劇が起こる「劇空間=舞台美術」の前提として劇場空間がある。そして、劇場の周りには他の建物や道路などその土地土地の環境が存在していて、その環境の集合体として社会があり、さらにそれらすべてを包み込む宇宙という空間があるーーその自明の事実にあらためて気づかされました。それまでも自身で舞台美術のプランニングをする際、まずはその前提となる劇場空間から思考するというプロセスに重きが置かれていましたが、そのプロセスがより深く、広くなっていったと感じています。
『F/T』はつねに「社会の中で舞台芸術を思考すること」を、観客にはもちろん、ぼくたちアーティストにも強く問い続けてきたように感じています。ですから、劇空間を思考することはその前提となる何層もの空間を、つまるところ、社会を思考することである。そう教えられたような気がするのです。『F/T』がぼくに与えてくれたこの試練のような経験は、忘れ難いものとなっています。
「ぼんやりしていた私の空白は、『F/T』によって埋められた」(文:劇作家 / 演出家・西尾佳織)

西尾佳織(にしお かおり)
劇作家、演出家。1985年東京生まれ。幼少期をマレーシアで過ごす。東京大学にて寺山修司を、東京藝術大学大学院にて太田省吾を研究。2007年に演劇ユニット「鳥公園」を結成し、2019年まで脚本・演出を担当。2020年より3人の演出家をアソシエイトアーティストに迎え、自身は劇作と主宰業に専念する新体制に移行。『カンロ』、『ヨブ呼んでるよ』、『終わりにする、一人と一人が丘』にて、「岸田國士戯曲賞」最終候補作品にノミネート。近年の活動に、マレーシアの振付家・ダンサーのLee RenXinとのからゆきさん共同リサーチなどがある。(撮影:引地信彦)
2009年から2020年の『F/T』で、私は観客として54本の舞台作品を観て、自分の作品を2本上演し、研究開発プログラムの1企画でファシリテーターを務めた。特に、2010年から2013年は毎年10本前後観ていた。大学院を出てなんの身分もなくなって、さて一体どうやって生きていこう? 自分のカンパニーをつくって創作活動を始めたものの、未来もあんまり見えないし……とぼんやりしていた私の空白は、『F/T』によって埋められた。
「埋める」という言葉はあまりいい言葉ではないかもしれない。でも当時の私は空っぽの皮袋みたいなもので、作品と、その底に流れる思想や歴史と、それらを実現させる制度と、批評や言説と、観客と……という生態系の全体を、『F/T』で丸呑みしたのだ。漠然と、自分もこういう方向にだったら進んでいけるかもしれないと思った。ただ一人の人間の勝手な気概や趣味としてではなく、パブリックなものとして、作品と創作活動の存在できる場所があり得るのかも……? という気配は救いだった。
『F/T10』の『巨大なるブッツバッハ村――ある永遠のコロニー』を、私は観られなかった。にも関わらずこの作品の名前が心に残っているのは、作品の紹介動画か何か(探したけれど見つけられなかった)で演出のクリストフ・マルターラーが、「私は大して何もしない。みんなで集まって過ごす。歌を歌う。それぞれがいろいろやって、いつの間にか作品ができる」というようなことを言っていて、ものすごく「そうだよねー!!!」と思ったからだ。(マルターラーの発言のこの要約は私の記憶のみに基づいているので、かなりいい加減かもしれない。しかし創作における態度に関して、神託か啓示のようなレベルでピーーーン!!! と来るインスピレーションがあった)
「そうだよねー!!!」の中身は、「やっぱりそうだよね! それでいいんだよね!!!(でも私の周りにある現状は全然そうではないっていうか、真逆だわ)」だ。作・演出家として、自分が一人でギコギコ頑張ってお膳立てして、みんなに「やってもらっている」ような感覚があった。俳優たちが何を考えているのかもっと知りたかったし、ものを言って欲しかった。


2010年『巨大なるブッツバッハ村――ある永遠のコロニー』(撮影:石川純)
それから『F/T12』の『女司祭―危機三部作・第三部』の当日パンフレットにあった「ポリフォニックなパフォーマンスのために」という言葉も、いまに至るまで自分のなかで響き続けている。
「リハーサル過程での私たちの主な目標は、異なる信条を拒絶することなく互いが影響し合うように、全体をまとめていくことだった。この舞台は、私たち一人ひとりの個人的な世界観を表現するための開放的な場でありながら、同時に、問題を共有するための上演のシステムを模索する場ともなる。つまり、私たちは、異なる世界観を持ったパラレルな声が生み出すハーモニーによる、ポリフォニックなパフォーマンスを目指していたのだ」
(『女司祭』パンフレットより)


2012年『女司祭』(撮影:片岡陽太 / Yohta Kataoka)
すごく大事なことを言っている気がする、とドキドキしながら何度も読んだ。稽古場で俳優たちとも一緒に読んだ。(ちなみに、『女司祭』の作品自体はあまりピンと来なかった。当事者演劇っていうのはなんか違うんじゃないか、とそのときから思っていた)
私たちは作品をつくりた過ぎるんじゃないだろうか? もちろん作品をつくるのは楽しいし、それがアーティストの仕事なんだけど、でも作品つくって、それで何なんだろう? つくった端から通り過ぎていく感じがして、空しい。どうしたら、「問題を共有するための上演のシステム」からつくり始められるんだろう?
「公募プログラムが終了したとき、多くの若手にとって、目指す方向の一つが失われた感覚があった」
公募プログラムに参加した2011年、他の参加団体10組の作品を公演日程が重なっていたもの以外はすべて観て、特に捩子ぴじん『モチベーション代行』と村川拓也『ツァイトゲーバー』にショックを受けた。もちろんふたつはまったく異なる作品なのだが、演技に関して、架空の第三者を演じに行かない(それなのにフィクションがものすごくクッキリした輪郭で立ち上がる!)ということに私はびっくりしてしまった。これがこんなに面白いなら、私が演技だと思っていたことはなんだったんだろう?
それまで私は、「おはなし」を見せることが演劇だと思っていて、そのためには出来るだけ細かくつくり込む演技が必要だと思っていた。それは、予め稽古のなかでつくっておいた完成品を観客に見せるようなことだったのだと思う。でもふたつの作品は、問いとコンセプトだけクリアに持っておいて、フィクションの立ち上げ作業は観客とその場でやっていくような感覚で、舞台上と自分のあいだにフィクションが生まれた。自分のなかにリアルタイムで新しい回路がつくられていって、ライブパフォーマンスのライブ性を感じた。


捩子ぴじん『モチベーション代行』 ©︎Ujin Matsuo


村川拓也『ツァイトゲーバー』(撮影:富田了平)
2011年のアワードを捩子さんがとって、その受賞スピーチの冒頭で「きっとここにいる他の公募プログラム参加アーティストのみなさんも、それぞれにスピーチの原稿を用意してきていることでしょう」と言った。私は、えー! 用意してないー!!! と思いながら、平然としたフリで聞いた。そうか、そういうもんか。そういう風に臨むのが、アーティストの態度ってものか、と思いながら初めて、この公募プログラムという場が、誰かの手によって、未来への希望とか意志を持って生み出されたんだなあということを考えた。
自分の方法もまだわからず、視野狭窄でただ必死だったあの時期に、公募プログラムの同じ土俵で同時代の表現と並び合って出会えたことは、幸運だったと思う。2013年で公募プログラムが終了したとき、多くの若手にとって、目指す方向の一つが失われた感覚があったのではないだろうか。
日本の私たちはこれから何をどうしよう?
そんな風にして、私のアーティストとしての土台や進む方向性は、『F/T』によって形づくられた部分がかなり大きい。他のなにとも関係できずにポツンと存在している星を目指して活動していたところから、その星が描いている星座が見えてきて、星座群の浮かぶ天球が見えてきて、その天球をまなざしている隣の人たちが見えてくるような感覚だった。
『F/T』の最終年度に当たる2020年に、研究開発プログラムの「アーティスト・ピット」でファシリテーターを務めた。作品をつくるためではなく、創作と創作のあいだでアーティストたちが集まって、ただ話す。そこで私は、「おおむね10年くらいのキャリアのあるアーティストたちで集まって、次の10年を考える」という場を設定した。自分自身が、初めの10年はがむしゃらに新作をつくり続けてきて、でも次の10年を同じように過ごすのはキツイし先が見えないな……と動けなくなっていたからだ。ディレクターの長島確さんの言葉が非常に印象に残っている。
「日本には『つくる』プロセスの部分を育てる機関が足りない。劇場や大学がそこを担ってはいるけれど、とくに一度世に出たあとのアーティストは自力任せで出来上がった花や果実を摘まれるばかりになりがちで、基礎研究や研究開発のチャンスがない。『F/T』もそこを担おうとしてきたけれど、でも本来フェスティバルっていうのは年に一度の打ち上げ花火みたいなものだから、『つくる』役割を一番に担えるわけじゃない」
ヨーロッパの舞台芸術の文脈と日本の文脈を接続し、双方に紹介したことは『F/T』の大きな功績のひとつだと思うけれど、そして日本の私たちはこれから何をどうしよう? というのは、残された課題だ。作品をつくりながら、同時に「つくる」部分を担い合うための仲間を探して仕組みをつくることを、アーティストの側からもしていくことが必要だと思う。
今日のアートに期待される社会的役割は、鬱屈の不安や分断の空気を一時忘れさせてくれる巨大なスペクタクルだけなのか?(文:美術ライター・島貫泰介)

島貫泰介(しまぬき たいすけ)
美術ライター / 編集者。1980年神奈川生まれ。京都・別府在住。
思い出に残る『F/T』の作品は数多い。ダニエル・コック・ディスコダニーの『ゲイ・ロメオ』(2012年)。捩子ぴじんの『モチベーション代行』(2011年)。高山明 / Port Bの『東京ヘテロトピア』(2013年)。これらの作品をいまあらためて並べてみると、個人的な体験・告白を、劇場という公的な空間に密輸入する(『ゲイ・ロメオ』、『モチベーション代行』)、あるいは逆に劇場や博物館といった公的空間で本来語られるべき歴史を、路上における個別の体験へと逆流させる(『東京ヘテロトピア』)企みを持った作品ばかりであったと気づく。
これらの作品と出合うことで現在進行形のパフォーマンスアートの世界に深く導かれていった私は、その後に住み慣れた東京を離れ、京都に移住し、そして現在はさらに西方の温泉の町・別府にも生活の拠点を持つようになり、東京を絶対的中心とするアートやカルチャーのメインストリームからは物理的に遠ざかりつつある(寺と温泉のある暮らしは楽しいですよ)。しかし、個人的にはそれは若隠居や後退の身振りではなくて、これら作品が示唆していた「観客」や「劇場」の問題を、自分なりの実践として探るための移動であったのだと思い返している。

ダニエル・コック・ディスコダニー『ゲイ・ロメオ』 ©︎ Sven Hagolan

高山明 / Port B『東京ヘテロトピア』 ©︎Masahiro Hasunuma
東日本大震災の余波が色濃く漂っていた10年前と比べて、今日アートに期待される社会的役割は大きく変質している。東京オリンピックがあり、SNSのさらなる台頭があり、コロナ禍があった。先日亡くなった安倍晋三元首相による長期政権も2012年から2020年に重なる。そういった時代に求められたのは、鬱屈の不安や分断の空気を一時忘れさせてくれる巨大なスペクタクル、あるいは存在しないスペクタクルを擬似的に感じさせてくれる作品であって、映画館での応援上映や、無数のアバターとしてメタバースに集い、人気ミュージシャンのライブに参加するゲームなどはその一例だろう。
観客が光に包まれたり霧に包まれたり大量のオブジェに取り囲まれたりするインスタレーション作品の隆盛もこれに当然重なる。そうやってつくり出された無数の「劇場」では、浴びるような物量と情報の嵐によって「観客」一人ひとりの想いや感情は「エモさ」や「クソデカ感情」といった擬似宗教的な喜悦に上書きされるのだ。
しかし自分が『F/T』で出会った劇場とはそのようなものばかりではなかった。冒頭で挙げた『ゲイ・ロメオ』は、同名のデートマッチングサイト(現在はromeo.com)を題材にした作品で、観客はダニエル・コック自身が実践した男性とのデートのエピソードの数々を配布された冊子を読むことで知る。モニターに表示された数字はエピソードの掲載ページを指示するもので、鑑賞時間の大半はそれを観客が個別に黙読することに費やされる。やがて作品が先に進むと、客席内にダニエルとデートした複数の人物が招かれているらしいことが示唆され、ダニエルは彼らに向けて非常に親密でセクシュアルな告白のスピーチを贈る(しかし、それが劇場内の誰に向けられたものであるかはわからず、観客は好奇の感情や居心地の悪さなどを抱える)。
作品はダニエルによるとても美しいポールダンスで終わるが、ストロボの激しい明滅のなかで中空に浮かんでは消える彼の姿は、刹那的な性行為やインスタントな愛情の喪失を想起させ、ストロボが明転した次の瞬間に彼自身が消えてなくなってしまっているのではないか……という畏れのような気持ちなどを私に抱かせる。
「感動や満足感に安易に一元化されない事物に出合える経験は、今日のスペクタクル偏重の社会において稀なものだ」
か細い記憶の糸を手繰り寄せて、約10年越しにこの文章を書いてみたわけだが、やはりどうしてももう一度見てみたい作品が『ゲイ・ロメオ』だ。その後のダニエルは、アンダーグラウンドカルチャーにさらに踏み込んだ変態性の強い作品を手掛けるようになり、この繊細で物悲しくもある愛の物語が再演されるのは難しいと思ってはいるが。
仮に役者がいなくなったとしても、劇場は観客不在では成り立たない。それなりの数の人々が1箇所に集い、共通の経験を共有することで、劇場と作品ははじめて実体を持つ。しかし、その経験がつねに個人的なものとして帰着できるのも劇場の面白さである。
『F/T』に限らないが、先鋭的なパフォーマンスアートのシーンでは、観客はもやもやとした感情を抱えて劇場を立ち去ることが多いだろう。その感情を即座に共有できる友人やパートナーに恵まれた人はかなり幸運で、人によっては寝ても覚めてもそのもやもやを引きずることになる。けれども、感動や満足感に安易に一元化されない事物に出合える経験は、今日のスペクタクル偏重の社会において稀なものだ。私が出合った『F/T』は、そのような場所だったと思う。
さて、最後に軽めの宣伝を許していただきたい。さきほど私は、別府での生活を「『観客』や『劇場』の問題を、自分なりの実践として探るための移動」と書いたが、今年10月の8、9日に同市内で自主企画するパフォーマンスイベントが、その「自分なりの実践」になる。高齢化と空き家問題に悩む地方都市だからこそ、自分の手が届く観客に向けて、その町ならではの劇場をつくることもできるだろう。これもまた、自分が『F/T』から受け取った10年越しの成果の一つかもしれない。
- イベント情報
-

- プロフィール
-

- 杉原邦生 (すぎはら くにお)
-
演出家、舞台美術家。1982年東京生まれ、神奈川県茅ヶ崎市育ち。京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)映像・舞台芸術学科 同大学院 芸術研究科 修士課程修了。学科在籍中の2004年にプロデュース公演カンパニー・KUNIOを立ち上げ。これまでに『エンジェルス・イン・アメリカ』『ハムレット』、太田省吾『更地』『水の駅』などを上演。木ノ下歌舞伎には2006年から2017年まで参加し、『勧進帳』『東海道四谷怪談―通し上演―』『三人吉三』など11演目を演出した。代表作は、スーパー歌舞伎Ⅱ『新版 オグリ』(市川猿之助との共同演出)、KUNIO15『グリークス』、シアターコクーン ライブ配信『プレイタイム』(梅田哲也との共同演出)、KAAT神奈川芸術劇場プロデュース『オレステスとピュラデス』、PARCO劇場オープニング・シリーズ『藪原検校』、ゴールド・シアター最終公演『水の駅』、COCOON PRODUCTION 2022 NINAGAWA MEMORIAL『パンドラの鐘』、歌舞伎座 八月納涼歌舞伎『東海道中膝栗毛 弥次喜多流離譚』(構成のみ)など。2018年(平成29年度)第36回京都府文化賞奨励賞受賞。
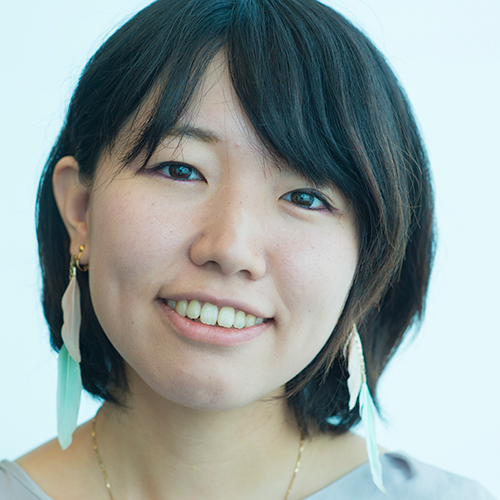
- 西尾佳織 (にしお かおり)
-
劇作家、演出家。1985年東京生まれ。幼少期をマレーシアで過ごす。東京大学にて寺山修司を、東京藝術大学大学院にて太田省吾を研究。2007年に演劇ユニット『鳥公園』を結成し、2019年まで脚本・演出を担当。2020年より3人の演出家をアソシエイトアーティストとして迎え、自身は劇作と主宰業に専念する新体制に移行。『カンロ』、『ヨブ呼んでるよ』、『終わりにする、一人と一人が丘』にて、「岸田國士戯曲賞」最終候補作品にノミネート。近年の活動に、マレーシアの振付家・ダンサーのLee RenXinとのからゆきさん共同リサーチなどがある。

- 島貫泰介 (しまぬき たいすけ)
-
美術ライター / 編集者。1980年神奈川生まれ。京都・別府在住。
- フィードバック 1
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-