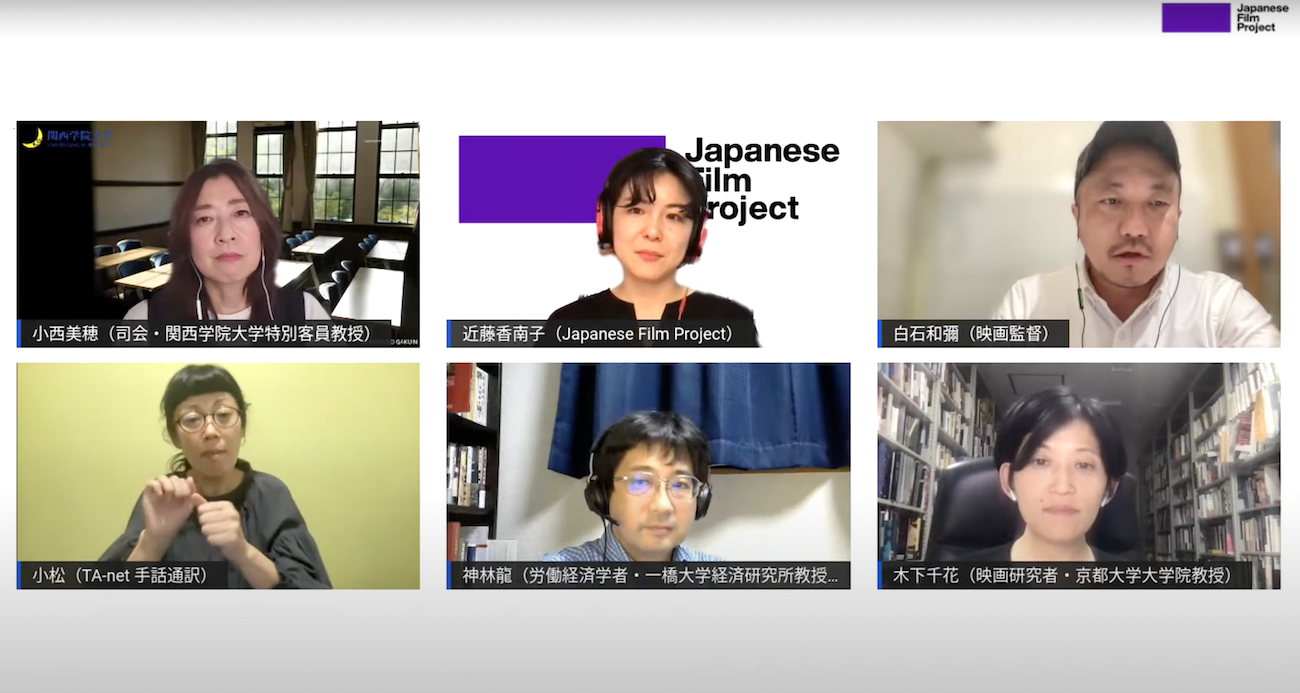『ジョゼと虎と魚たち』(2003年)や『メゾン・ド・ヒミコ』(2005年)などの作品を生み出し、長きに渡り映画監督として活躍している犬童一心。映画&ドラマ『グーグーだって猫である』シリーズをはじめ、映画『猫は抱くもの』(2018年)や『いぬのえいが』(2005年)内の中編「ポチは待っていた」を監督するなど、動物がテーマの作品を多く手がけているのもひとつの特徴といえる。
そんな犬童監督の最新作は、「ワン」と鳴けない保護犬が主人公の映画『ハウ』(2022年8月19日公開)。保護犬のハウは、民夫(田中圭)と家族になることで幸せな生活を過ごすが、ある出来事をキッカケに離ればなれになってしまう。犬と人との絆を描いた本作は、どのような想いでつくられたのだろうか。
今回は、犬童監督に単独インタビューを実施。動物映画のつくり方から、作品の題材における「犬」と「猫」の違いなどをうかがう。そして、私生活でも猫と暮らしている犬童監督とともに、動物と人間がより健全に暮らせる社会への実現にとって、必要なことも考えていく。
「犬」or「猫」によって、物語の性質が変わる? 動物映画で意識する設定とは
―犬童監督は、動物が題材の作品を多く手がけられている印象があります。動物がメインの映画を撮る際に意識していることはありますか?
犬童:まず行なうのは、その動物を「どういう設定にするか」ですね。たとえば、映画の『グーグーだって猫である』(2008年)のときに、「どういう猫なのか」などの設定の言語化をはっきりせずに制作したのですが、わりと苦労したんです。
その反省を生かして、2014年にドラマ版の制作を行なったときには、猫を「自然の世界やスピリチュアルな世界と、リアルの世界の境界線上にいる動物」と明確に設定しました。
それこそが物語の核となったので、「猫が出てくることで、自然界やスピリチュアルの世界と、リアルの世界が交わる」という物語の展開やビジュアル面の組み立ても明確になり、すごくやりやすかったんです。以降、動物をテーマにする際には、まず設定をしっかりするところから始めています。

犬童一心(いぬどう いっしん)
1960年生まれ。1999年に『金髪の草原』で商業映画監督デビュー。以降、『ジョゼと虎と魚たち』(2003年)、『メゾン・ド・ヒミコ』(2005年)、『眉山 びざん』(2007年)、『ゼロの焦点』(2009年)、『のぼうの城』(2013年)、『引っ越し大名!』(2019年)など多くの作品を手掛け、数々の映画賞を受賞。2022年8月19日に映画『ハウ』を公開予定。
―では、今回の映画『ハウ』の場合はどういう犬に設定しようと考えたのでしょうか?
犬童:脚本家の斉藤ひろしさんが書かれたシナリオを最初に読んだ際、「ある理由により『ハウ』としか鳴けない犬」という設定自体はありました。ただ、そのうえでハウが人間にとってどんな存在か、どんな影響力を持った犬なのか設定しないと、どう撮ったら良いかイメージが沸かなくて。
そこで、「物語が進むにつれて『聖犬』になる」という設定にできないかと、提案したんです。ハウは離ればなれになった飼い主を探す旅のなかで、新たに出会う人たちのそばに寄り添い、人々を癒やしていく。「救いを必要とする人々のもとへ行く聖犬」という設定にすることで、全体を考えていきました。
ですから、ハウが経験する青森から横浜へと帰ってくる旅は、聖犬へと近づいていく通過儀礼でもあるんです。映画の本編には、大元のシナリオにはなかった展開が散りばめられていて、そのどれもが「ハウが聖犬になる」という設定なくして生まれなかったものです。
2022年8月19日に公開する映画『ハウ』の予告編
―最初の設定を決めたあとは、そこからいろんな展開をつくっていくのですね。ちなみに、テーマが「犬」の場合と、「猫」の場合では、また設定の考え方も変わってくるのでしょうか。
犬童:そうですね。先ほど「猫はリアルと、スピリチュアルや自然の世界の境界線上にいる」とお話ししましたが、こうしたニュアンスの発想はぼくの作品に限らないようにも思います。
たとえば、30年間一歩も家の外へ出ることなく、庭の生命を見つめて描き続けた伝説の画家・熊谷守一を題材にした、沖田修一監督の『モリのいる場所』(2018年)。この映画では、縁側に猫がいますよね。
あの縁側は、リアルの世界と自然界、スピリチュアルな世界の境界線になっていると個人的に感じます。監督の沖田くんにそれを伝えたら、「そうですか?」と言われたけど(笑)。ぼくにはそうとしか見えない。きっと彼は、無意識に猫をそこで撮ったんでしょうね。
映画『モリのいる場所』の予告編
犬童:対して犬は、なぜかあまりスピリチュアルなところに置けない感じがあるんですよね。猫以上にもっともっと人間の世界に近い感じがするんです。猫は一緒にいても向こう側に近いところにいる感じがあるけど、犬はそう思えない。
これはあくまでぼくの感覚ですが、動物のなかでも「人間のそばにいるけど、人間ではない存在」として犬を見ていますね。そういう意識があるからこそ、人に寄り添う「聖犬」という『ハウ』の設定にもつながったのかなと思います。
言葉がないから築ける信頼関係もある。動物に気づかされる、他者に対する想像力
―このタイミングで制作された『ハウ』に関していうと、「聖犬が必要とされる世界」が描かれているのは、逆説的に「いまの時代は隣人愛が足りていない」というメッセージのようにも感じました。
犬童:そうですね。ただ、そういった意識はこの『ハウ』から、というわけでもないんです。『メゾン・ド・ヒミコ』(2005年)のときにも、「自分以外の世界や国、他人に対する想像力が追いつかないことの話」と考えてつくっていました。
外交や宗教の違いもそうなんだけど、たとえば、ひとつの宗教に入っているとほかの宗派の人間への想像が追いつかないケースは多いはず。そうした理解し合うことの難しさはいまに始まったことではないですし、映画をつくるうえで意識することも結構あります。


映画『メゾン・ド・ヒミコ』DVD発売中 / DVD:3,080円(税込) / 発売元:アスミック・エース / 販売元:TCエンタテインメント / ©2005「メゾン・ド・ヒミコ」製作委員会
―たしかに、他者に対する想像力を持ち、人間同士がわかり合うことの難しさは普遍的ですね。
犬童:でも意外と、動物はその壁を乗り越えるイメージがあるんですよね。言語がないせいもあるかもしれないけど、動物はあらゆる人を喜ばせたり、人間ができないことを当たり前にできたりする印象があって。
人間にとっては当たり前じゃない行動をするから、犬に対する想像力が強まって過大評価してしまい、ぼくが「聖犬」とか言い出すんだけど(笑)。あくまで犬は、自分が思うとおりに行動しているだけなんですよね。
―そう言われると、物語をとおしてもハウ自身は一定ですね。犬童監督としては、あくまで人間にとって聖犬になっていくというイメージだったのでしょうか。
犬童:そうそう。映画を撮るときに「別に主人公が成長しなくていい」という考えがずっとあるのですが、その最たるものだと思います。今回でいうと、物語を通して成長したり変化したりするのは、ハウの周りの人間なんですよね。

映画『ハウ』より
―その感覚は、犬や猫を家族として迎え入れている人々の日常生活にもあるように感じます。たとえば、日々で気持ちのアップダウンがあっても、家に帰ってきて変わらず一定でいてくれる犬や猫の存在に救われるというか。
犬童:きっと言葉が通じないからこそ、そう感じるんですよね。はっきりと「言語でコミュニケーションが取れない」とわかっているから、こちらも想像するというか。
ぼくの家にも猫がいますが、やっぱり相手の気持ちを能動的に想像せざるを得ない。おそらく猫のほうも、ぼくが何を伝えたいのか考える瞬間はあるはず。言葉は非常に大事なものだけど、言葉がないことで築ける信頼関係もあるのかなと思います。
愛猫との生活で得たものは? 命について考えるからこそ、生まれる情緒
―コロナ禍に入って人と動物の絆、人が動物を求める気持ちがより強まったような感覚もありますが、犬童監督はこの状況をどうご覧になっていますか?
犬童:コロナ禍で人とのコミュニケーションが少なくなり、そばにいてくれる動物への思いが強まった、という感覚はわかります。
ぼく自身はコロナ禍によって、ウチの猫と関係性が特別強まったという感覚はありませんけどね。ただ、一緒に過ごす時間が増えたことで、ぼくと猫では年を取るスピードが全然違うんだなと、あらためて感じやすくなりました。
犬童一心と愛猫のチャッピー(Instagramで見る)
―犬や猫は、人間の6、7倍の速さで年を取るといわれていますね。
犬童:生きているスピードが違う動物の存在は、そばにいるとかなり影響を受けますね。ウチの猫は16歳だけど、人間だったらまだ高校生。でも猫の年齢としては、人間換算で80歳くらいなわけです。
自分と比べものにならないスピードで死に向かっていく存在をそばで見ていると、「何かしなきゃ」という気持ちになります。たとえば、季節の移り変わりに対する感じ方なんかも、まったく違ってきますよね。命について考えさせられる機会があるからこそ、独特の情緒が生まれるのかなと。
―命が限られていると感じるからこそ、いまを大切にしようという考えにもなってきますね。
犬童:猫が年を取ってくるとさらにそれが進んで、「来年はもういないかもしれない」という考えが普通になってくる。人間にも共通しますが、そうなってくると日常の些細な物事が際立って見えてきますね。
愛猫のチャッピーとグーグーとの動画(Instagramで見る)
「かわいい、飼いたい!」だけで決断してはダメ。虐待や飼育放棄を防ぐために必要な制度
―動物と人間がよりよい関係で暮らしていくために、「こういった社会になったらいい」といったようなお考えはありますか?
犬童:「動物と暮らすには相当な覚悟が必要」ということを、より一般的に認識してもらえる社会になったらいいですね。日頃から熱心にそのことを考えているわけではないけど、動物を飼っている人間からすると、やはり飼い始めの意識が重要だと思うんです。
ルーズなペットショップなどで「抱っこしますか?」と聞かれた結果、「かわいい、飼いたい!」となって、安易にアクションを起こしてしまう。そうすると、「吠えるのがうるさい」「しつけや散歩が面倒くさい」となって捨てられたりする犬や猫が出てきてしまうんですよね。

―ぼくも保護猫と暮らしているので信じられないですが、本当によくある話と聞きます。
犬童:そういうことがなるべく起きないように、すべてのペットショップが「動物と暮らすと、こういうことがありますよ」と説明することは必須で、さらに「動物とちゃんと暮らせる人なのか」をいまよりしっかり選定する必要があると思います。
商売としては買う人が減ってしまうかもしれないけど、命を扱う仕事ならばいちばん大事なこと。いまお話しした「抱っこします?」って、昔からペットショップでは定番の接客だけど、いまは絶対にやらないペットショップも増えてきていますよね。世界では、ペットショップを廃止したほうがいいのでは、という動きも出ていますし。
―フランスでは2024年から、犬や猫の店舗での販売が廃止されると決定しましたね(*1)。
犬童:はい。日本だと、生後8週に満たない子犬や子猫の販売を禁じる「8週齢規制」も2021年6月に施行されましたよね(*2)。
それまでは実質7週だったので、小さいとかわいいから買う人も増えていたんですが、そのぶん猫や犬が大きくなると捨てる人も出てくる。しかも、子犬は最低でも8週目くらいまでは親と一緒にいないと、よくない行動や病気になってしまう可能性が高いんですよね。
それでペット問題や動物のことを大切に考えている人たちが業界の反対に遭っても何年も闘った結果、ようやく世界基準の8週に改善された。かわいいという理由だけで安易に飼ってしまう人の抑制になるから、制度が改善されたのはよかったなと思います。

―ペットショップ関連でそういった改善に向かうニュースは最近よく目にしますね。
犬童:そうですね。業者に対して、犬や猫を入れておくゲージの大きさは「犬の大きさに対してこれぐらい」という基準が明確に定まった(*3)のも、いいことですよね。あらゆる面でまだまだいろんな改善の余地はありそうですが、いい流れになってきているなとは思います。
動物はつらくても言葉にできない。映画界が今後も徹底すべき体制づくり
―保護犬や保護猫に関しても、各団体で制度や環境を整える動きが昔に比べて活性化しているように感じます。
犬童:今回の『ハウ』はフィクションですが保護犬の設定ということもあり、いろいろな関係者の方に協力いただきながら、取材や調査をして作品のところどころに盛り込んでいきました。
やはり昔よりは動物ファーストで考える時代になってきていると感じますし、そういう時流のなかで『ハウ』という映画を公開することに関しても特別な意識を持って臨みました。
だからこそ撮影時も、ハウ役の俳優犬・ベックに負担をかけるようなことがあってはならないと思い、細心の注意を払いながら行ないましたね。信頼できるトレーナーの宮忠臣さんがついてくださって、宮さんが「無理です」と言ったら絶対に撮らないようにしていました。
映画『ハウ』の公式アカウントより(Instagramで見る)
―宮忠臣さんといえば、『南極物語』(1983年)、『ハチ公物語』(1987年)、『クイール』(2003年)、『犬と私の10の約束』(2008年)などでドッグトレーナーを務めた方ですね。
犬童:やっぱり動物映画を撮る際には、そういう存在がいてくれることが重要ですね。時間に追われている撮影だと「まだいけるんじゃないか」と思ってしまうけど、動物にとってはつらいことかもしれない。でも、動物はその気持ちを言葉にできないじゃないですか。
ですから、動物に精通するトレーナーさんが毅然と「無理です」と言ってくれることで、ぼくたちも動物を守ることができると思うんです。昔の動物映画を観ていると「これ、いまの時代だったら絶対にNGだろうな」と感じるシーンもなかにはありますけど、いまはとくに厳しいし、その流れはもっと強まっていくと思います。
映画やドラマはもちろんですが、あらゆるコンテンツにおいて動物を撮る際の現場では、基本的にトレーナーさんのような動物に詳しい方に同席いただくと、人間も動物も安心なはず。そういった動物の気持ちを配慮した体制づくりに関しても、もっと常識として幅広く認知されるといいですね。

- 作品情報
-
 『ハウ』
『ハウ』
2022年8月19日(木・祝)から全国公開
原作:『ハウ』斉藤ひろし(朝日文庫)
監督:犬童一心
脚本:斉藤ひろし / 犬童一心
出演:
田中圭
池田エライザ
野間口徹
渡辺真起子
モトーラ世理奈
深川麻衣
長澤樹
田中要次
利重剛
伊勢志摩
市川実和子
田畑智子
石田ゆり子(ナレーション)
石橋蓮司
宮本信子
配給:東映
- プロフィール
-
- 犬童一心 (いぬどう いっしん)
-
1960年生まれ。高校時代より映画製作を行ない、『気分を変えて?』(1978年)がぴあフィルムフエスティバルに入選。大学卒業後にはCM演出家としてテレビCMの企画・演出を手がけ、数々の広告賞を受賞。その後、インディーズ作品『二人が喋ってる。』(1995年)が、映画監督協会新人賞、サンダンスフィルムフェスティバルin東京グランプリを受賞。1998年に市川準監督の『大阪物語』の脚本執筆を手がけ、本格的に映画界へ進出。1999年に『金髪の草原』で商業映画監督デビューし、夕張ファンタスティック映画祭グランプリを受賞。以降、『ジョゼと虎と魚たち』(2003年)、『メゾン・ド・ヒミコ』(2005年)、『眉山 びざん』(2007年)、『ゼロの焦点』(2009年)、『ゼロの焦点』(2009年)、『のぼうの城』(2013年)など多くの作品を手がけ、日本アカデミー賞をはじめとする数々の賞を受賞。テレビドラマ『グーグーだって猫である』(2016年)が放送文化基金賞。2016年、初の小説『我が名は、カモン』(河出書房新社)を出版。2022年8月19日に映画『ハウ』を公開予定。
- フィードバック 9
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-