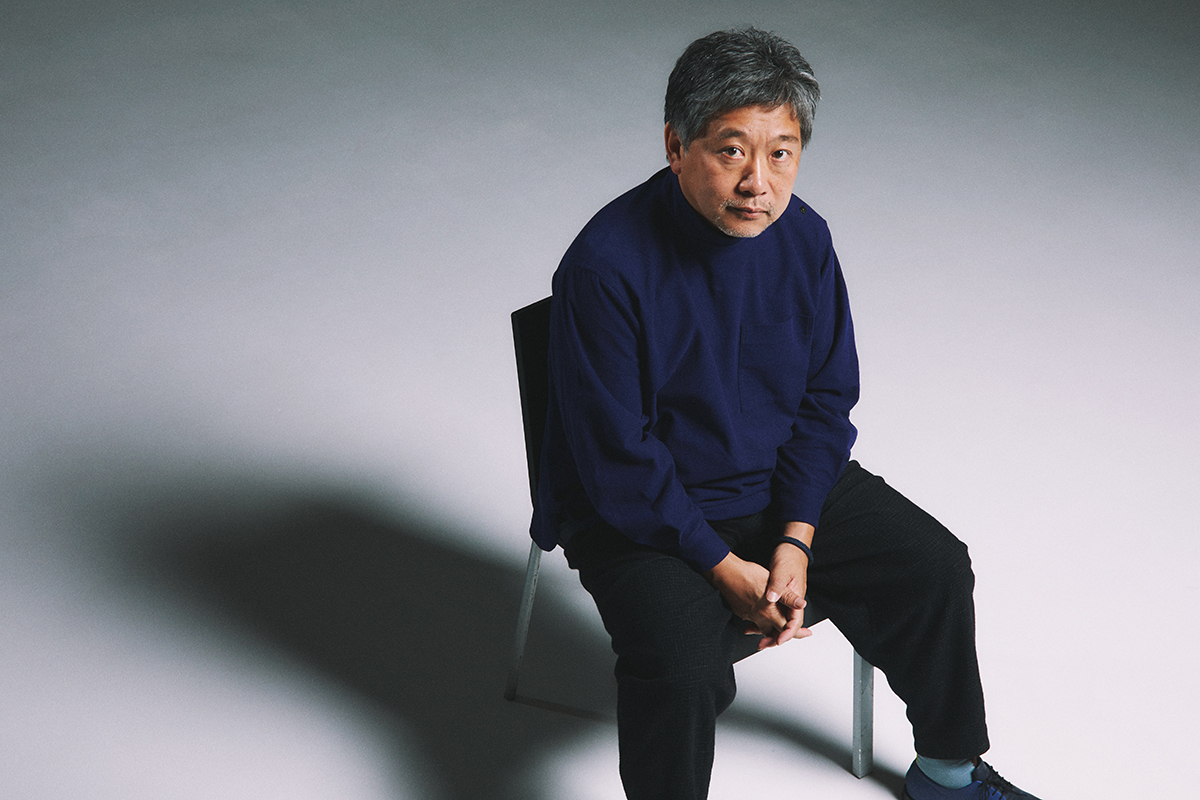レズビアンカップルのもとでナニーとして働きはじめる34歳の女性ブリジットを描く『セイント・フランシス』。8月19日公開のこの映画は、性や身体にまつわるさまざまな対話を私たちに提示してくれる。それは映画においてだけではなく、私たちが実際に生きている生活においても、なかなか詳らかにできずにいた対話だ。この映画を観た多くの人たちが、きっと劇場を出たあとにすぐ誰かと話をしたくてたまらなくなるだろう。
『セイント・フランシス』が決して絵空事ではなく、わたしたちの生そのもののリアリティをとらえられているのは、主演・脚本を務めたケリー・オサリヴァンが自身の人生を色濃く反映させているからかもしれない。今回行なったインタビューで、オサリヴァンは中絶など女性の身体のタブーを巡る問題、同性愛と異性愛、そして自分の物語を語ることの重要性について共有してくれた。
(メイン画像:© 2019 SAINT FRANCES LLC ALL RIGHTS RESERVED)

脚本を執筆し、自ら主人公ブリジット役を務めたケリー・オサリヴァン
監督を務めたのは男性パートナー。女性の身体をテーマにするということ
―本作は女性の身体の問題をひとつのテーマにしていながらも、オサリヴァンさんが脚本を書き、男性パートナーのアレックス・トンプソンさんが監督するという方法で撮られました。作品をつくるうえで、トンプソンさんとはどのようなコミュニケーションをとりましたか? それは、この映画が男性をわかりやすい「悪者」として描かず、女性と男性の対立構造をつくらない在り方ともつながっているようにも思うのですが。
ケリー:私とパートナーはとても信頼関係がありますし、私が監督するのでなければ、もう彼しかいませんでした。私とパートナーは、脚本家が脚本をすべて書き、監督に渡したらもう関わらないというような、いわゆる古典的な脚本家と監督の関係ではありません。
脚本自体は私が執筆していましたが、彼は随時それを読んで助言をくれていましたし、ずっと共同作業でした。女性のイシューを中心にした映画を男性が監督することに対して、彼はかなり気を配っていましたし、熱心に勉強してくれました。

6歳のフランシス(左)のナニーをすることになったブリジット(右)。フランシスやその両親との交流を通じて、ブリジットの生活に変化が訪れる © 2019 SAINT FRANCES LLC ALL RIGHTS RESERVED
―生理や中絶など、包み隠さずに女性に関するさまざまなことを描いているので、もしかしたら男性が知らないようなこともあったのではないかと思います。具体的にトンプソンさんはどんなことを勉強していましたか?
ケリー:たとえば生理用のナプキンひとつをとっても、重い日と軽い日でつけなければいけない種類が違うことを、必要のない男性は知らなかったりしますよね。序盤には月経の血の描写がありますが、「こんな感じでいいかな?」と彼と一緒に確認しながら撮りましたし、丁寧にコミュニケーションを取っていました。
彼はすべてに対して好奇心を持って学ぼうとし、オープンに接してくれて、わからないことはそのたびに確認を取りながら取り組んでいました。
中絶や産後うつ――女性が「恥」だと感じさせられてしまいがちなことをノーマル化したい
―ブリジットが男性とベッドをともにした後、月経の血があちこちについてしまっていたシーンが私はとても好きでした。作中、最初から最後まで「血」が出てきますよね。女性にとって血はすごく身近なものであるにもかかわらず、映画では――もちろんそれは現実においてもですが――、しばしば隠蔽されたり忌避されたりするものとして描かれてきたように思いますが、この映画に関しては血に対して親密さのようなものを感じました。
ケリー:本当にそのとおりで、女性と血は深くつながっているものですよね。多くの女性にとって、生理は身体の構造上起こりえることですし、描かれて当然だと思っています。
この作品の出血の描写に関して、ショックを与えるために誇張しているということは一切ありません。セックスの途中で生理になってしまうのも、中絶のあとに一か月以上出血が続くのも、すべて私が実際に経験したことなんです。私は中絶のあとに出血が起こる可能性を事前に知っていたおかげで動じずに済んだので、それはきちんと伝えなければいけないと思いました。
血ももちろんそうですが、中絶や産後うつなど、女性が「恥」だと感じさせられてしまいがちなことをノーマル化したい想いがありました。それらを取り繕ったり美化したりせず、ただそのまま提示することが、何よりスティグマを脱することにつながると考えたのです。

© 2019 SAINT FRANCES LLC ALL RIGHTS RESERVED
同性同士のカップルの子育てを「普通にあること」としてとらえたい
―「ノーマル化」というお話が出ましたが、それは主人公・ブリジットのナニー先であるアニーとマヤのレズビアンカップルの描き方に関しても言えると思います。先日、ある雑誌の座談会で『セイント・フランシス』を取り上げたのですが、男性パートナーと子どものいる女性が「レズビアンカップルのふたりが、育児や結婚について悩むことが私たちとまったく変わらないのだと思った」と言っていました。
ケリー:まさにその女性がおっしゃったとおりなんです。アニーとマヤも悩みを抱えていますが、それはセクシュアリティ云々ではなく、親として抱えるものです。
私はずっと演劇畑にいたのですが、周りにはLGBTQのカップルで、かつ子育てをしている人たちがたくさんいました。この映画のひとつの狙いとしては、まさに同性同士のカップルの子育てをノーマル化、普通にあることとしてとらえたいということがありました。
実際に彼女たちのようなカップルはわたしたちの社会ですでに生活をしていますし、異性同士のカップルが日々直面している悩みと同じ悩みを抱えているんだと描くことで、少しでもノーマル化できればと思いました。

ブリジットのナニー先は、6歳の娘フランシスを子育て中のレズビアンカップルの家庭。アニー(リリー・モジェク)は家族を支えるために仕事中心の生活を送っており、マヤ(チャリン・アルヴァレス)は産後うつに苦しんでいる © 2019 SAINT FRANCES LLC ALL RIGHTS RESERVED
―同性カップルのキャラクターを書くにあたって、どのようなリサーチを行なったのでしょうか?
ケリー:実際に演じた二人の俳優たちにも話を聞きました。セクシュアリティの問題も前提としてはあるのですが、彼女たちが住んでいるシカゴの北の方は非常に白人が多い地域なんです。人種の異なるカップルが直面することについてはより詳しく聞きました。あとはやはり同性カップルということで、人工授精などについてもしっかりリサーチしました。
―『セイント・フランシス』を観たレズビアンカップル当事者からの、何か記憶に残っているコメントや感想があれば教えてください。
ケリー:この映画を観た当事者の方々から肯定的なコメントを多くいただいて、本当に嬉しかったです。そのなかでも、まさにフランシスのような、バイレイシャルの子どもがいる女性と結婚した女性の方からのコメントがとくに印象に残っています。「映画のなかに私たちがいた」と言ってくれたんです。

© 2019 SAINT FRANCES LLC ALL RIGHTS RESERVED
中絶を「メインの出来事」にしない。自らの経験をベースに中絶を描く
―同性同士のパートナーシップに加えて、『セイント・フランシス』は中絶も重要なテーマになっています。アメリカ映画では、たとえばジリアン・ロベスピエール監督の『Obvious Child(原題)』(2014年)や、ポール・ワイツ監督の『愛しのグランマ』 (2015年) などがポジティブな中絶表象を描いた作品として挙げられると思います。『Obvious Child』は、主人公が中絶をしに行ったクリニックで同じく施術を待つ女性たちと微笑み合う描写があって、身体の自己決定権と女性たちの連帯的なつながりが交差して描かれています。
『愛しのグランマ』 は、レズビアンの女性と望まぬ妊娠をした孫が中絶費用を集める旅に出るんですが、二人が辿り着いた中絶クリニックの前でプラカードを持った反対派の親子と喧嘩するといったようなコミカルな瞬間が多くちりばめられているんですね。オサリヴァンさんが中絶をひとつのテーマに描くにあたって、なにか影響を受けたり、参考にしたりした映画はありますか?
ケリー:いま挙げてくださった二つの作品はとても良い作品だと聞いていますが、観ていません。というのも、自分の経験に基づいてこの作品を書こうとしたからです。参考にした映画といいますか、むしろ中絶の悪い例を描く映画は意識的に避けようとしました。
たとえば妊娠した女性がクリニックに行き、最終的に気が変わって中絶をやめる決断をする映画、あるいは最初から最後まで産むか産まないかという葛藤だけを描く映画もそうです。
最も心がけたのは、中絶を映画のメインの出来事にするのではなく、いくつかあるプロットのうちのひとつとして描くことです。

© 2019 SAINT FRANCES LLC ALL RIGHTS RESERVED
―フェミニスト映画としても有名なロシアの『ベッドとソファ』(1927年)には、まさに女性が中絶クリニックの待ち時間に偶然見かけた赤子を見て、中絶を思い直すという展開がありました。これは古典的な作品ですが、そうした描写は現在に至るまで多くの中絶を扱う作品に見出せます。でも、あなたの映画にはそうした典型的な描写はありません。
ケリー:私自身、妊娠がわかってすぐにクリニックで中絶の予約を取って行なったので、『セイント・フランシス』の中絶の描写は現実に起きた経験そのものになっています。
アメリカで中絶の権利が覆る判決。「非常に恐ろしいこと」
―6月に、アメリカで手にしたはずの中絶の権利が覆されてしまう出来事がありましたよね。(参考記事:オリヴィア・ロドリゴ、ハリー・スタイルズらが非難。「中絶の権利」求めて声を上げるアーティストたち)この映画がつくられた2019年当時ともまた状況が変わってしまったかと思いますが、作品が持つ力や意義などがどのように変容したと考えていますか? 私自身もこの流れには、強い憤りを感じています。
ケリー:たしかに私が脚本を書いていたときに比べて、残念ながら非常にタイムリーな作品になってしまいました。まさか「ロー対ウェイド」裁判の判決が覆されるなんて、書いている当時は思ってもいなかったですから。
この映画で描かれているように、中絶は実際500ドルもあればできたんです。いまでも私が住んでいるところでは合法ですが、出身地であるアーカンソー州では中絶禁止法が施行されて中絶ができなくなってしまいました。それは非常に恐ろしいことです。中絶の権利がより推し進められるどころか、逆行する流れになってしまっていることで、この映画がより意味を持ってしまったということはいえると思います。

最高裁の判決に、アメリカ各地では抗議デモが相次いだ
物語があればあるほど「恥」の意識はなくなっていく。中絶の話を語り合うこと、共有することの意味
―映画でブリジットは中絶を経口中絶薬で行なっていましたが、日本ではいまだに身体に負担の大きい掻爬(そうは)法が主流であったり、「配偶者」の同意が必要であったりなど、安全と健康が第一に重んじられていない、身体の自己決定権が当事者自身のもとにあるとはいえない状況だと思います。私の母は若い頃に中絶の経験があるんですが、手術のあとに胎児が体内に残ってしまい、高熱を出したそうなんです。ところが病院に行くと医者からは、「自分が悪いんだから痛い目に遭わないとダメだ」と麻酔すら使ってもらえずに乱暴な処置をされたと。ずっとその経験を人に話せなかったそうで、ようやく最近になって私に話してくれました。
ケリー:じつは私自身もあまり中絶の経験を周りに話していなかったんですが、ほかの人たちが話すのを聞くにつれ、解き放たれていくものがありました。私も話していいのだと次第に気づけたんですね。多くの物語があればあるほど「恥」の意識はなくなっていきますし、自分を受容できるようになっていくので、共有することが大事です。
沈黙はそれ自体が恥であることを証明してしまうんです。安全な場所で語り合い、共有することができれば、自分は一人ではないと思えるのではないでしょうか。

© 2019 SAINT FRANCES LLC ALL RIGHTS RESERVED
―パーソナルな身体の話である中絶経験について他人とシェアするのは、そもそも日本でもアメリカでもハードルがあるように感じます。オサリヴァンさんはそういった自らの経験を安全に語れる場所を、どう得たんでしょうか?
ケリー:まずは身近な友達ですね。若いときに中絶を経験した友達が、「恥も後悔も罪の意識もなかった」と私に話してくれて、気持ちが軽くなったということがありました。
あとはSNSです。Instagramで、中絶についてオープンに話そうと発信している「Shout Your Abortion」というアカウントがあって、そこにはさまざまなストーリーが投稿されています。それもまた救いになりました。
ケリー:また、ドラマシリーズにもなった、フェミニストのコラムニストであるリンディ・ウェストのエッセイ本『わたしの体に呪いをかけるな』も、中絶のことをオープンに扱っていたことに感銘を受けました。
―『わたしの体に呪いをかけるな』は日本でも今年、翻訳が出たんですよ。ウェストは自身の中絶経験を絡めながら「想像してほしい。わたしたちが本当に妊娠中絶について率直かつオープンに話せるようになった社会のことを」と、力強い筆致で綴っています。また、「月経が汚名を着せられる実際の要因はミソジニーなのだ」というフレーズにもハッとさせられるのですが、同時に月経のタブーについても喝破しているところなども『セイント・フランシス』との結びつきを感じさせます。『セイント・フランシス』について書いたのは、当初からこの映画自体がそういった「オープンに話せる場」になってほしいという期待があったからでしょうか?
ケリー:この脚本を書いていたときは、まさか劇場公開されるなんて想定していなかったので、自由に書いた部分が多かったんです。映画が公開される段階になって初めて、自分の経験を人に話さなければいけないということに気づきました。だからこの映画に際して行なわれた初めてのインタビューでは、自分のパーソナルなことを知られてしまう怖さもありましたし、震えていました。
ただ、話せば話すほどハードルが低くなっていくんですよね。この映画を観て、自分の中絶の経験を人に初めて話しましたという方も実際にいらっしゃいましたし、語ることや自分自身を受容すること、そういった想いは人に伝染していくものだと思うんです。
誰しもがそうではない。私自身は「開かれた本」のようなスタンスでいよう――。オサリヴァンの想い

―「オープンに話す」というスタンスは、この映画で重要な点ですよね。月経カップ、タンポン、卵子凍結など、女性の身体に関わる具体的な単語を、曖昧にしたりぼやかしたりしていない。日常会話でフランクに出てきます。自分自身を思い返しても、日常生活のなかでそこまでオープンに話せているだろうか? と聞かれると自信がありません。この辺りもオサリヴァンさん自身の生活にそのまま根ざしているのか、それとも創作した部分もあるのでしょうか?
ケリー:私は日頃から友達とさまざまなことをオープンに話します。じつは最近卵子凍結をしたので、それについても友達とたくさん話しました。ただ、親は私が中絶したことをこの映画の紹介記事を読んで初めて知ったんです。この映画のおかげで親ともそれ以降はオープンに話せるようになり、中絶については話せなかったのに、最近の卵子凍結のことは話せたんです。
私の日常では居心地のいい関係のうえでオープンな対話が成り立っていますが、もちろん誰しもがそうではないのだろうと思います。私自身は、どこからでも読んでいい本のような、誰でも読める開かれた本のようなスタンスでいようと心がけています。
―素敵なお話をありがとうございました。『セイント・フランシス』は、女性たちにとってそれまで言葉にできなかったことを紡ぎ出す勇気を与えてくれるような、そんなきっかけになりえる優しい映画だと思います。
ケリー:ありがとうございます。そうであることを、心から願っています。
- 作品情報
-
 『セイント・フランシス』
『セイント・フランシス』
2022年8月19日(金)からヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館、シネクイントほか全国ロードショー
監督:アレックス・トンプソン
脚本:ケリー・オサリヴァン
出演:
ケリー・オサリヴァン
ラモーナ・エディス・ウィリアムズ
チャーリン・アルヴァレス
マックス・リプシッツ
リリー・モジェク
字幕翻訳:山田龍
配給:ハーク
配給協力:FLICKK
- プロフィール
-

- ケリー・オサリヴァン
-
俳優、脚本家。アーカンソー州ノースリトルロック出身。『セイント・フランシス』が初の長編映画脚本となる。俳優としてはステッぺンウルフ・シアター、グッドマン・シアター、ライターズ・シアター、パシフィック・プレイライト・フェスティバル、Ojai Playwrights Conferenceで舞台に立つ。テレビ出演には「Sirens」の2シーズン、映画出演にはインディペンデント映画の「Henry Gamble’s Birthday Party」「Olympia」「Sleep with Me」などがある。ノースウェスタン大学、ステッぺンウルフ・シアターカンパニー付属の演劇学校を卒業、プリンセスグレース財団の劇場向けの奨学金を受け、3Arts Make a Wave(シカゴを中心にしたアーティスト間の寄付プログラム)の受賞者でもある。
- フィードバック 25
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-