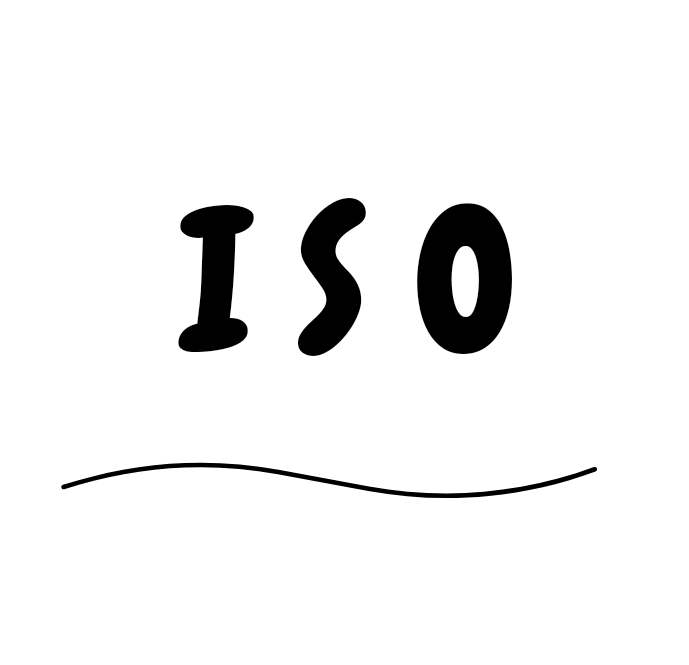メイン画像:Films Boutique
イランで2022年、「頭髪をスカーフで適切に覆っていなかった」としてある女性が道徳警察に逮捕され、その後死亡した事件が発生。その死を契機に、女性の人権を求める抗議デモが国中に広がっていった。
映画『聖なるイチジクの種』のモハマド・ラスロフ監督は、刑務所のなかでその一連の動きを知り、本作の構想を膨らませたという。イランにて国家安全保障に反する罪によって懲役8年、鞭打ち、財産没収の実刑判決を受けている監督は2024年、本作が『カンヌ国際映画祭』で発表され、諜報機関に発覚したことをきっかけに、母国イランを脱出した。
監督はじめスタッフのすさまじい覚悟によって世に出された本作。体制批判を含む社会派の作品であるのはもちろんだが、家父長制への抵抗、登場人物の葛藤、スリラーのようなシーンなど、物語としての面白さもふんだんに詰まっている。監督にインタビューし、その真意や背景を紐解いていきたい。
あらすじ:市民による政府への反抗議デモで揺れるイラン。国家公務に従事する一家の主・イマンは護身用に国から一丁の銃が支給される。しかしある日、家庭内から銃が消えた。最初はイマンの不始末による紛失だと思われたが、次第に疑いの目は、妻、姉、妹の3人に向けられる。捜索が進むにつれ互いの疑心暗鬼が家庭を支配する。
服役中に構想。圧政的な組織に仕えたら、ほかすべてを犠牲にするのか?
—劇中でも言及されますが、本作は2022年9月に起きた「マフサ・アミニの死」(※1)と、その後に続く「女性・命・自由」運動(※2)がベースになっていますね。監督は服役中に本作を思いついたということでしたが、当時の出来事にどのように触発され、権力の象徴である「銃」をめぐる物語として展開していったのでしょうか?
モハマド・ラスロフ(以下、ラスロフ):絶対的な体制のなかでおのれのすべてを差し出して仕事をする男の話を描きたい、と昔から考えていました。
私が刑務所に収監された2022年、刑務官の男が「仕事が苦しい」という話をしていたんです。彼いわく、こういう仕事をしていると家族内にもプレッシャーがあり「早く辞めなさい」と言われることもあるし、とても落ち込んで自死を考えるときもあると。その姿は、私が考えていた体制や組織のなかで自らを犠牲にしていく男のイメージと合致しました。
そして「体制で仕事をするうえでどれほどの責任を感じるか。それが圧政的な組織であった場合でもすべてを犠牲にするのか」という問いを軸にアイデアを練っていたときに、塀の外でマフサ・アミニの死と「女性・命・自由」運動が起こりました。私やほかの政治犯も、外で起こる社会の大きな変革に驚いたことを覚えています。この運動を支援したいという思いもあり、現実の要素も織り交ぜながらこの物語を練っていきました。
※1 2022年9月13日、クルド系イラン人のマフサ・アミニさん(22)が適切にヒジャブを着用していないとして道徳警察に逮捕され、その後死亡した事件。この事件に端を発して民衆蜂起が起こった。
※2 マフサ・アミニの死を契機に、イラン中に広がった「女性、命、自由」をスローガンとする反政府デモ。治安部隊による激しい弾圧を受け、500人以上の抗議者が殺害されたという。

モハマド・ラスロフ
1972年、イラン生まれ。大学で社会学を学ぶ傍ら、ドキュメンタリーや短編映画で映画制作のキャリアをスタートさせる。2002年に『Gagooman』で長編監督デビューを果たし、その後『ぶれない男』(2017年)で『カンヌ国際映画祭』「ある視点」部門最優秀作品賞を、『悪は存在せず』(2020年)で『ベルリン国際映画祭』最高賞の金熊賞をそれぞれ受賞。一方、イランでは国家安全保障に反する罪によって懲役8年、鞭打ち、財産没収の実刑判決を受け、2024年に国外へ脱出。28日間かけて『カンヌ国際映画祭』に足を踏み入れ『聖なるイチジクの種』のプレミアに参加。本作は審査員特別賞を受賞した。
—妻と2人の娘は、従う者、疑問を持つ者、抗う者と、イランにおける世代の異なる女性を象徴する存在として描かれているように感じました。このキャラクター像をどのように探求していったのでしょうか?
ラスロフ:私が刑務所を出所したときにはすでに、「女性・命・自由」運動は下火になっていました。しかしそのときに何が起きていたのかを知りたいと考え、当時撮られたデモの映像を見ると、多くの若い女性や男性がその運動に参加していたんです。
そこから彼女、彼らに話を聞いて、世代によってどのように考えているのかなどを取材していきました。その内容と実際の映像、そして自分のビジョンも合わせて、女性たちのキャラクターをつくりあげていきました。

Films Boutique
—実際のデモ映像は劇中でも使われていましたね。そのような映像はソーシャルメディアで拡散され、娘たちはそこから情報を得るという情報の伝播が本作でも描かれていました。検閲の厳しいイラン社会において、スマートフォンとソーシャルメディアの普及は人々の考え方にどのような影響を及ぼしたと思いますか?
ラスロフ:ご存知かもしれませんが、イランではほかの国々のように記者が自由にリサーチや取材をすることはできません。とりわけ反政府デモが起きているときは、そのなかに入ってその様子を記録することは不可能なんです。
その状況下で、多くの人々はスマートフォンを使って何が起きているかを記録し、ソーシャルメディアを使ってニュースとして流しています。現在、検閲はますます強まっているので、人々は国営放送のテレビより自分たちを信じているし、皆が取材班のように動くようになりました。
国営放送は完全に体制派なので、その報道番組ではプロパガンダやフェイクニュースばかりが流されるんです。ほかの国ではテレビのほうが信用があるのかもしれませんが、そのような理由から、イランでは一般的にソーシャルメディアで流れる情報のほうが信頼されています。
—国営放送に対する世代間での信用度の違いが劇中でも描かれていましたね。

Films Boutique
父親が支配する家庭と、体制が支配する社会を重ねて
—作中でイマンが女性を「座らせる」行為を何度も行いますね。非常に抑圧的で、イマン一家に根付く家父長制を強く感じさせられました。世界各国でいまだ家父長制は根強く残っていますが、イラン社会においてもそれは同様なのでしょうか?
ラスロフ:そうですね。伝統的なイラン社会のなかでは、家父長制の家庭がいまだ多く見られます。
この映画のなかでもそうですが、家庭において、すべてを自分が望むようにコントロールしようとする男性は多いでしょう。「もっとも小さな社会」と呼ばれる家でそうであるように、視野を広げると国という社会全体でも同じような考えが根付いているんです。
でもそれに対して、女性や子どもたちは抵抗を示している。劇中でその様子が外から映し出されることがありますが、それは家のなかを男性が支配する状況と、外=社会を体制が支配する状況は似ているということを示しているんです。

Films Boutique
—「女性・命・自由」運動の映像を見ると大勢の男性の姿が見受けられます。さきほど監督も「デモには多くの若い男性も参加していた」と述べていましたが、いまだ家父長制が根強いなかでもイランの男性の考え方は変化しつつあるのでしょうか?
ラスロフ:「女性・命・自由」運動は、単なる女性運動というわけではありませんでした。フェミニズムの文脈というより「人権の危機である」と感じ、性別問わず皆で抗議をしていたんです。
そして、人権という部分を大前提としつつ、多くの男性たちは女性の権利を向上させて、尊厳や自由を守る必要があると主張していました。そういう意味では多くの男性の考え方は変わりつつあるのだと思います。

Films Boutique
※以下、物語終盤に関するネタバレを含みます。
イランの何千年もの歴史や文化や価値観を継ぐ場所で
—ジャンルが転調する終盤の展開には驚きました。イマンは父から継いだ故郷の家に家族を閉じ込め、さらに遺跡での追走の果てに文字通り転落していく示唆に富んだシークエンスがありましたが、どのようにこのクライマックスをつくりあげていったのですか?
ラスロフ:イランの出来事をどうナラティブに語るか、どのようなメタファーで語るかということはつねに考えていました。そして最終的に妻と娘にフォーカスしながら、イマンの感情や精神面が変わっていく過程を(視聴者が)目撃するという構成にしようと決めたのです。
たとえば、イマンやその家を水の上に浮かぶ小さな船だと想像してください。最初は静かに漂っているだけでも、嵐が起きて波が激しくなったら、小さな船もすごく揺れますよね。それと同じように、デモで社会がぐらついたことで、イマンの精神状態や家族の在り方は小さな船のように大きく揺さぶられる。そのイメージをベースに、終盤の激化していく展開を想像していきました。

Films Boutique
—ラストの舞台となる遺跡がとても印象的でしたね。
ラスロフ:聞いた話では、あの遺跡は何千年か前のものなんだそうです。つまりはイランの何千年もの歴史や文化や価値観を受け継いできた場所であり、だからこそ私はこの物語をその場所で終わらせようと考えました。
イマンは遺跡の暗闇に入ったり、登ったり、降りたりしながら、女性たちを従わせようとするんです。これが象徴するのはイランの男たちがたどってきた歴史です。だけど最終的には女性が勝つ。そのメッセージを伝えるためにあの遺跡を選びました。
体制批判の作品をつくるリスク。原動力は「自由への渇望、人権への希求」
—体制を真っ向から批判した本作をつくった監督はもちろん、参加したキャストやスタッフも危険に晒されているかと思いますが、そのリスク共有をどのように行ったか気になります。また監督は実刑を受ける前にイランを脱出しましたが、キャストやスタッフは現在どのような状況にあるのでしょうか?
ラスロフ:イラン政府の許可なしで映画をつくる際にはアンダーグラウンドで隠密に撮影するのですが、やはりそれに参加するキャストやクルーにも危険がつきまといます。そのリスクに関しては、本作に参加する時点で皆が理解していました。撮影も可能な限り少人数で行い、情報が漏れないように終始徹底していましたね。
本作の存在は、『カンヌ国際映画祭』で発表されたことで諜報機関に発覚しました。その前に国外へ脱出した俳優も2、3人いますが、イラン国内にいたクルーや俳優たちは諜報機関に呼び出され、尋問を受け、出国することも禁じられました。現在は、裁判所から何かしらの命令があって……というところまでは掴めているのですが、その後の状況は我々も返事待ちです。

Films Boutique
—監督は本作撮影後、禁錮8年を含む実刑判決を受けたことから、命懸けでイランを脱出したとうかがいました。祖国を離れるということにはかなりの葛藤があったかと思いますが、現在監督が抱くイランへの思いを教えてもらえますか?
ラスロフ:国外にいるとイランや故郷が恋しくて仕方ないときはもちろんあります。ただ近年はインターネットもSNSもあって、イラン国内ともやりとりができるので、遠く離れていても祖国や故郷の文化や人々ともつながりを持てる。物理的にイランにいるのとはまったく違いますが、それでも昔に比べると寂しさはましなのかなと。
ただやはり私の希望として、46年前のイスラム革命で今の体制になってから、イランから何かしらの事情で出国せざるを得なかった人々といつか祖国に戻りたいな、と。そしてまた故郷で皆が一緒に生活できる日がくればいいと願っています。

Films Boutique
—あなただけでなくジャファール・パナヒ監督(1960年生まれ。『白い風船』『チャドルと生きる』『オフサイド・ガールズ』『人生タクシー』などで国際的な評価を得ている)やマリヤム・モガッダム監督(1970年生まれ。自ら出演し、共同監督・共同脚本も手掛けた『白い牛のバラッド』で脚光を浴びた)など、イランには検閲や体制の抑圧に抗いながら映画製作に挑む方々が幾人もいますね。
ラスロフ:映画監督だけがそのような抗議の意味を込めた作品をつくっているわけではなく、ミュージシャンや作家、リポーターなどあらゆるジャンルの人々が、いまの抑圧されている社会のなかで抗議し、闘っています。皆、いまの社会を変えないといけないという意識を持ち、いろんな人がそれぞれのかたちで抗議活動を繰り広げているなかで、たまたま映画監督が目立っているだけなのだと思います。
—過去に懲役刑や鞭打ちなども受けた監督が、それでも作品を通じ体制批判を続けることには畏敬の念を抱くばかりですが、何があなたの原動力となっているのでしょうか?
ラスロフ:おそらく自由への渇望、そして人間としての権利を求める気持ちが原動力になっているのだと思います。

Films Boutique
- 作品情報
-
 『聖なるイチジクの種』
『聖なるイチジクの種』
2025年2月14(金)TOHOシネマズ シャンテほか全国公開
監督・脚本:モハマド・ラスロフ
- プロフィール
-
- モハマド・ラスロフ
-
1972年、イラン生まれ。大学で社会学を学ぶ傍ら、ドキュメンタリーや短編映画で映画制作のキャリアをスタートさせる。2002年に『Gagooman』で長編監督デビューを果たし、その後『ぶれない男』(2017年)でカンヌ国際映画祭「ある視点」部門最優秀作品賞を、『悪は存在せず』(2020年)でベルリン国際映画祭最高賞の金熊賞をそれぞれ受賞。一方、イランでは国家安全保障に反する罪によって懲役8年、鞭打ち、財産没収の実刑判決を受け、2024年に国外へ脱出。28日間かけてカンヌ国際映画祭に足を踏み入れ『聖なるイチジクの種』のプレミアに参加。本作は審査員特別賞を受賞した。
【2025/2/17 記事の中の一部表記を修正しました。】
- フィードバック 24
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-