2024年、『「ビックリハウス」と政治関心の戦後史――サブカルチャー雑誌がつくった若者共同体』を出版した社会学者の富永京子。「ほんとうに若者たちは政治に無関心なのか?」という問いのもと、読者投稿を中心とする1970〜80年代の伝説的なサブカルチャー雑誌『ビックリハウス』の膨大なテキスト研究から、当時の若者と政治、社会運動との距離感を探っている。
今回はその著書を中心に、当時といまの共通点をはじめ、政治を「おもしろネタ」として昇華する功罪や、ジェンダーの課題についての姿勢から見えてきたことなど、縦横無尽にたっぷり語ってもらった。
インタビューの内容は、『聞くCINRA』エピソード93、94で配信しています。
若者は政治に無関心か?という問いから『ビックリハウス』に向かった理由
昨夏に出版された『「ビックリハウス」と政治関心の戦後史――サブカルチャー雑誌がつくった若者共同体』。「聞くCINRA」の収録ではまず、「まだ読まれていない人もいると思うので」と、MCの南麻理江がまとめた「この本のここがすごい! 3つのポイント」の紹介から始まった。
まず一つ目は、研究対象である雑誌『ビックリハウス』そのものが「めちゃくちゃユニークである」こと。1974〜1985年に発行されていた、日本の伝説的なサブカルチャー雑誌『ビックリハウス』は、例えば糸井重里やYMO、タモリら錚々たる文化人が編集者、寄稿者として関わり、それらと横並びに読者投稿が並んでいる。読者の投稿が中心コンテンツになっているのが特徴だ。
二つ目は、『ビックリハウス』全130冊の、膨大な量のテキストをすべて文字起こしし、分析したこと。三つ目は、富永が着眼したテーマ。著書は、当時の若者と政治や社会運動との距離感とは実際どうだったかを検証するために書かれているが、特に着目した3つのテーマが「戦争」「ジェンダー」「ロック」。「この3つが注目テーマであることもとても現代につながる予感がして面白い」とした。
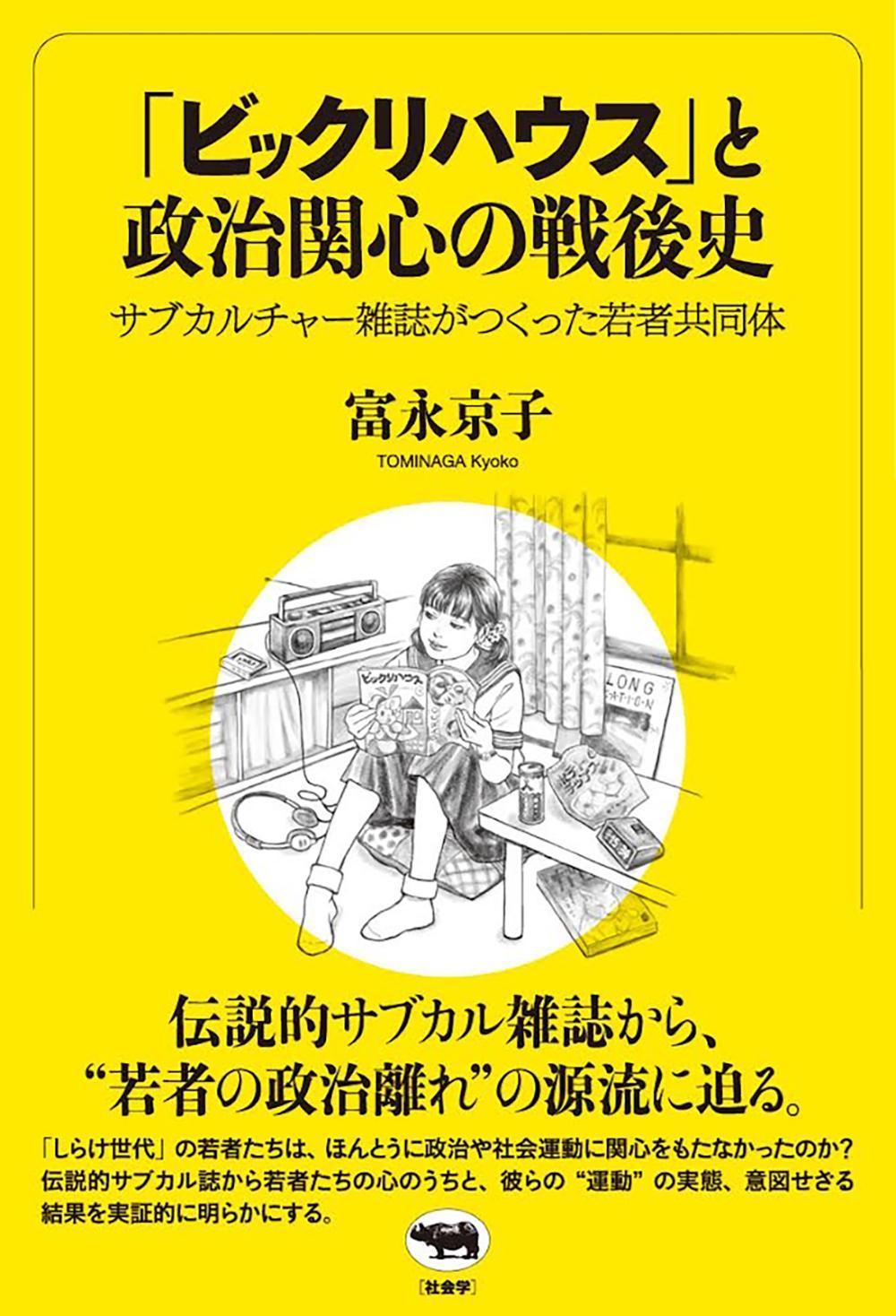
『「ビックリハウス」と政治関心の戦後史――サブカルチャー雑誌がつくった若者共同体』(晶文社)
—まず、この本をつくるきっかけとして、どんな課題感があったのでしょうか。
富永京子(以下、富永):メディアに出たときに、社会運動について聞かれることってすごく多いんですが、特に、2015年に安保法制抗議行動の際に「SEALDs(シールズ)」(※)という学生のネットワークが話題になったとき、「なぜ日本の若い人は社会運動をやらないのか」という質問をよくされたんです。
そのなかで記者らマスコミの方が話題にするのが、「1960年代の学生運動が過激だったから、その反省やトラウマがあるんですかね」、あるいは上の世代からは「いまの社会が物質的に豊かだから、若い人はそれで満足してるのかな」というようなことだったりするんですが、果たしてそれは本当にそうなんだろうか、と。
例えば、高度経済成長期やバブル経済のときでも、チェルノブイリ原子力発電所事故からの脱原発運動や、労働組合の運動はあったわけで、まったくなかったわけではない。さらに、そうした運動には当然若い労働者や、映画や小説などのカルチャーを通じて触れた若い人もいたわけで、先ほど触れた言説は「ちょっと乱暴なんじゃないの」とは思っていたところではありました。
※2015〜2016年に活動していた日本の政治団体、学生団体。

富永京子(とみなが きょうこ)
1986年生まれ。立命館大学産業社会学部准教授。専攻は社会学・社会運動論。東京大学大学院人文社会系研究科修士課程・博士課程修了後、2015年より現職。著書に『社会運動のサブカルチャー化ーーG8サミット抗議行動の経験分析』『みんなの「わがまま」入門』。朝日新聞での連載「あちらこちらに社会運動」ほか、さまざまなメディアへの寄稿などをしている。
—『ビックリハウス』に着目した理由は、どういうところにあったんですか。
富永:2016年ごろ、運動としては安保法制の抗議行動の大きい波が一段落したので、いままでマスコミの人から聞かれてきた、いわゆる「70〜80年代に社会運動なかった説」をちゃんと検証したいなというふうに思いました。でも、仮に「なかったもの」を検証するのは難しいと思っていたら、東京ステーションギャラリーで『パロディ、二重の声 日本の一九七〇年代前後左右』(※1)という展示があって、そこで『ビックリハウス』が展示されていて、それをたまたま見たんですよね。面白いなと思ったのが、すんごい、熱いんですよ。
熱いんだけど、非政治的。全然政治の話には触れてないけど、すごい情熱があった。かつ創刊されたの1975年で、まだ学生運動や連合赤軍事件(※2)から5年も経っていないようななか、非政治的で情熱的、その反発する2つの要素があるというのは、研究対象として最適なんじゃないかと。つまり、なかったことを検証できるし、なかったなかにあるものも検証できるんじゃないかと思って、メルカリやヤフーオークションを使って買い集めて、研究を始めたというところですね。
※1 2017年開催。かつて芸術の要件であった個性やオリジナルを権威とみなし、それをあえて取り込むことで翻弄、介入し、崩壊をも企みながらパロディを試みた1970年代の日本の現代アートを振り返った。
※2 あさま山荘事件。1972年2月19日に連合赤軍のメンバーが軽井沢の保養所「あさま山荘」に立てこもり、人質をとって発生した事件。警察の機動隊員2人が殉職した。

—著書を読むとその軌跡を体験できますが、研究を進めるなかで、どんな発見がありましたか。
富永:最初の2年間は、本当につらくて。何もないんですよ。
2019年ぐらいになってようやく政治的に引っかかる部分……「学生運動いじりネタ」みたいなものが少しずつ見つかるんですが……といっても、ネタの大半は「お父さんのおならがドレミの音がした」とか「担任の先生の髪の毛が最近薄い」みたいな、そういうネタなんですね。このままじゃ何も見つからないかも…という焦りが長い時間続きました。砂漠でベージュのアイシャドウを見つけるような、そんな感じでした。
時間はずいぶんかかりましたが、専任スタッフの方と文字起こしをしていくなかで、ジェンダーに関する言及はやっぱり多いな、ウーマンリブ(※)の時代だったこともあったかもしれないな、やっぱりロックの話は多いな、当時は日本語ロックがちょっとずつ出てきた頃かな……とちょっとずつ引っ掛かりが出てきました。
※1960年代後半から1970年代前半にかけてアメリカで始まった女性解放運動。
政治が「おもしろネタ」に昇華されてしまう功罪。民主的、自発的決定の難しさ
—先ほど「お父さんのおならがドレミの歌」というネタにも言及されましたが、著書でも、面白いことが正義といった雰囲気で、それがどんどん加速して競争のようになり、アウトなことまで笑いにしてしまうような状況になっていったと分析されていました。70〜80年代のことを拙速にいまと結びつけられないかもしれませんが、現代のXを中心としたSNSにも共通点を感じますが、富永さんはどう思われていますか?
富永:じつは自分自身、ハガキ職人というか……深夜ラジオや雑誌に投稿していたのですが、そういうものっていいものだ、と思っていたんですよね。当時、何の力もない、田舎の中学生だった自分が何十万部も刷られる雑誌や、多くの人が聞いているラジオを通して、いろいろなところに声を届けられるわけで。それってすごく民主的に見える。ただ、民主的であることを尊ぶと参加のハードルはどんどん落ちていくんですよね。
『ビックリハウス』の政治ネタは、どういうかたちで政治家が登場するかというと、例えば課税批判ではなくて「NHKの中継で田中角栄の鼻毛が出てた」とか、そういう話になるわけです。最近でも、岸田元首相が「増税メガネ」って言われていましたが、おそらくそれは最初は、政治や政策に批判的な人がある種の道具として使った言葉だと思うんですよ。でもその後、その面白さみたいなものに、どんどん人が集まってきて「おもしろネタ」として昇華しちゃう……みたいな状況はありますよね。だから、民主的、自発的っていうのは、私はハガキ職人としても社会運動の研究者としてもいいことだと思っていたんだけれども、実はそればっかりでもなかったのかなというふうに思うようになりました。

—企業や組織のなかで、どのように意見を集約していくか、ということにおいても相似点を感じます。例えば入社したてでまだ知識もない状況のメンバーからも、意見は募りたい。一方で、その意見の一つひとつを精査していると、決定までのスピード感が問題になる、といった具合に。
富永:博士論文を書いたときに、私は社会運動未体験者だったので、まず社会運動組織の一種であるNGOの人に話を聞きに行ったんです。そうしたら、意外と民主的じゃないなって感じて、それが面白くて。
つまり、社会運動をやっているから民主的な意思決定が好きなのかなと思ったらそうでもなくて「いや、いろんな人から意見を聞くって言うけど、大変だよ。まず時間がかかるでしょう。あと、誰も責任取れないもん」って言うわけですね。それももちろんうまく組織機構をつくればできるとは思うのですが、トップダウンのいいところは責任の主体が明確になることだ、とおっしゃって。だから「みんなで決めた」っていいことに聞こえるんだけれども、工夫しないと難しいなっていうところですよね。
—難しいけど、壮大な問いですね。もう一つ注目したいのは、読者投稿、つまり民主的に誰もが意見を発信できることの裏の部分には、それを選んでいる編集者がいるわけですよね。著書でも指摘されていますが、結局は編集者の意向が色濃く出ているのかなって思ったんですが、どうなんでしょうか。
富永:もちろんありますよね。歴史社会学者の福間良明先生が、同時代の教養雑誌の研究をされていて、そのときに、編集者が査読、掲載という権力を握っていたという話をされています。それは私の研究した『ビックリハウス』にはより強くあったのではないかと思います。
つまり、主な投稿者は10代ですけれども、編集者は20代から30代前半なわけで、そうなるとやっぱり身近だからこその権力——学校の先生より塾のお兄さん、お姉さん先生のほうが偉く見えるというか、説得力のあることを言ってるように聞こえるといったことはあったと思います。そういう意味での仮想的な民主的な空間に生まれた、「民主的な顔をしているお兄さん、お姉さん」っていうのは、それは権力になるだろうなっていう感じはしますよね。
当時のフェミニズムへの冷笑と、いまにつながる姿勢と。時代の変化を感じる瞬間も

—私(南)は特に、ジェンダー分析の章は本当に身につまされるものがあって。20代後半から30代の若い世代の女性の方が編集長をやられていたり、編集者も大半が女性という、この年代からすると先進的な場所でもあるし、実際女性の社会的な自立にとても肯定的な側面もある一方で、フェミニズムやウーマンリブに対してはすごく冷ややかなんですよね。「私の偉いところはプラカードを持ったりしないところだ」っていうことを言っていたりして。
富永:身に詰まされますよね。実は、この章を書けたとき、この本はまとまるなって思いました。先行していくつか論文を出してからまとめるというのが、学術書のよくあるつくりかたで、これもそうしているのですが、ジェンダーの章のもとになる論文を書けたとき、これは現代とつながると思いましたよね。
自分だって、あまたのブス自虐をやり、あまたの「フェミニズムってわがまま過ぎるんじゃないの?」みたいなことを言っていた時代もあり、かといって、「お嫁さん願望」にも乗りきれず、昔でいうキャリアウーマンみたいな「かっこいい女のモデル」にも乗れず(というのを経験してきました)。結果として、いまでいう「おもしれー女」みたいなものを……この女性編集者さんたちもたどっていくわけですが、それって、本当「いま」ですもんね。
—私も過去、同じようなことを言ってきたはずなんですよね。だからそれを再生産したくはないと思ったとき、どんな発信とか声掛けを、自分よりも若い女性にできるんだろうみたいなことを、あらためてこの本を読んで考えてしまいました。
富永:1975年が専業主婦率のピークで、男女雇用機会均等法の成立が1985年ですから、『ビックリハウス』の編集者らは、そのはざまの女性たちなわけですよね。だからサバイブするので精一杯というか、そういう感じがすごく伝わってきますよね。
同時に、時代が変わってるなって思うこともあるんです。それは、この研究は一部を学生と作業したのですが、学生が『ビックリハウス』を見て——『ビックリハウス』や編集者に責任があるわけじゃなくて、その時代に責任があったということですけど——「あまりにも描写がきつすぎる」ということをぽろっと言ってくれた。例えば同性愛差別や女性の自虐ネタがたくさんあるなかで、それを見てシンプルに「ひどい」って思う感性がある。時代が変わったんだなって思いましたよね。
社会は1人で変えるのではなく、みんなで変えるもの
—たしかに若い世代の感性や認識がアップデートされていると思いますが、社会運動への参画意識みたいなところについてはどう考えられていますか?
富永:最近、社会運動のイメージに関する調査も色々見られるんですが、(社会運動への)忌避感そのものについては、実は10代20代ではちょっとずつ減ってるんです。忌避感が強いのは、だいたい30〜40代なんですよね、つまりわれわれ世代ということになっちゃうのですが。そういう意味では、それこそSEALDsやそれ以前のいろんな社会運動が、その障壁をちょっとずつ取り払ってくれた部分もあるのかもしれません。
もう一つ、現在の若い人のアクティビズムは生活型になっていて——例えば、トイレに生理用ナプキンを置くことであったり。そういう意味で忌避感というものは少し変わってきているんじゃないかなと。肯定的なバイアスが強いかもしれないですけど、社会運動の研究者としてはそう思っていますね。

—ちょうどいま放映中のドラマ『御上先生』では、「Personal is political(個人的なことは政治的なこと)」という言葉がよく使われています。若い世代が、そういう認識を持ち始めてきているということでしょうか。
富永:そういう感覚はあるなと思いますね。毎年、期末には学生のレポートやプレゼンを見るのですが、社会運動というときにイメージするものが10年前とは変わったなって、観測の範囲ですが思うんですよね。
例えば、いままで見たことのある社会運動を聞くと、友達が校則を変えるように頑張っていたことだったり、バイト先で自分と友達が店長に交渉したことだったりを挙げる。そういった「Personal is political」のような雰囲気は、近年のMeToo運動、KuToo運動や、外国ルーツの若い人の運動などを通して変わってきているのかなと思いますよね。
—ただ、一方で、「社会運動に参加するならば、完璧でなければならない」というプレッシャーに苛まれている人もいますよね。社会運動に関与していく難しさって、どう考えていますか。
富永:それは、極めて重要だなと思います。社会運動をやっている人って真面目な人が多いから、実直にどんどん生活を政治化しようとして、どこかで燃え尽きちゃうというか……。全部はできないですからね。
そういうときに考えてほしいのは、ちょっと引いて見ること。もちろん、個人個人の行動の集積が社会を変えているのは事実。ただ、それを個人化しすぎると疲れちゃうので、一方で「ここで1人が車で移動したところで、気候変動はそう大きくは変わらないだろうな」などと客観的にというか、楽観的にというか、引いて考えることも大事だと思うんです。1人で社会を変えているんじゃなくて、みんなで変えているので、そういう意味でその「みんな」を、自分の心を楽にするために一瞬使ってもいいんじゃないかって私は思うんですよね。
完璧を求めすぎると、社会運動に自己責任を持ち込んでしまうことになると思うんです。社会はみんなで変えるものだから、自分がちょっとここで手を抜いても、誰かが頑張ってくれると思えるシステムでもあるわけですから。

左から杉浦太一、富永京子、南麻理江
- 書籍情報
-
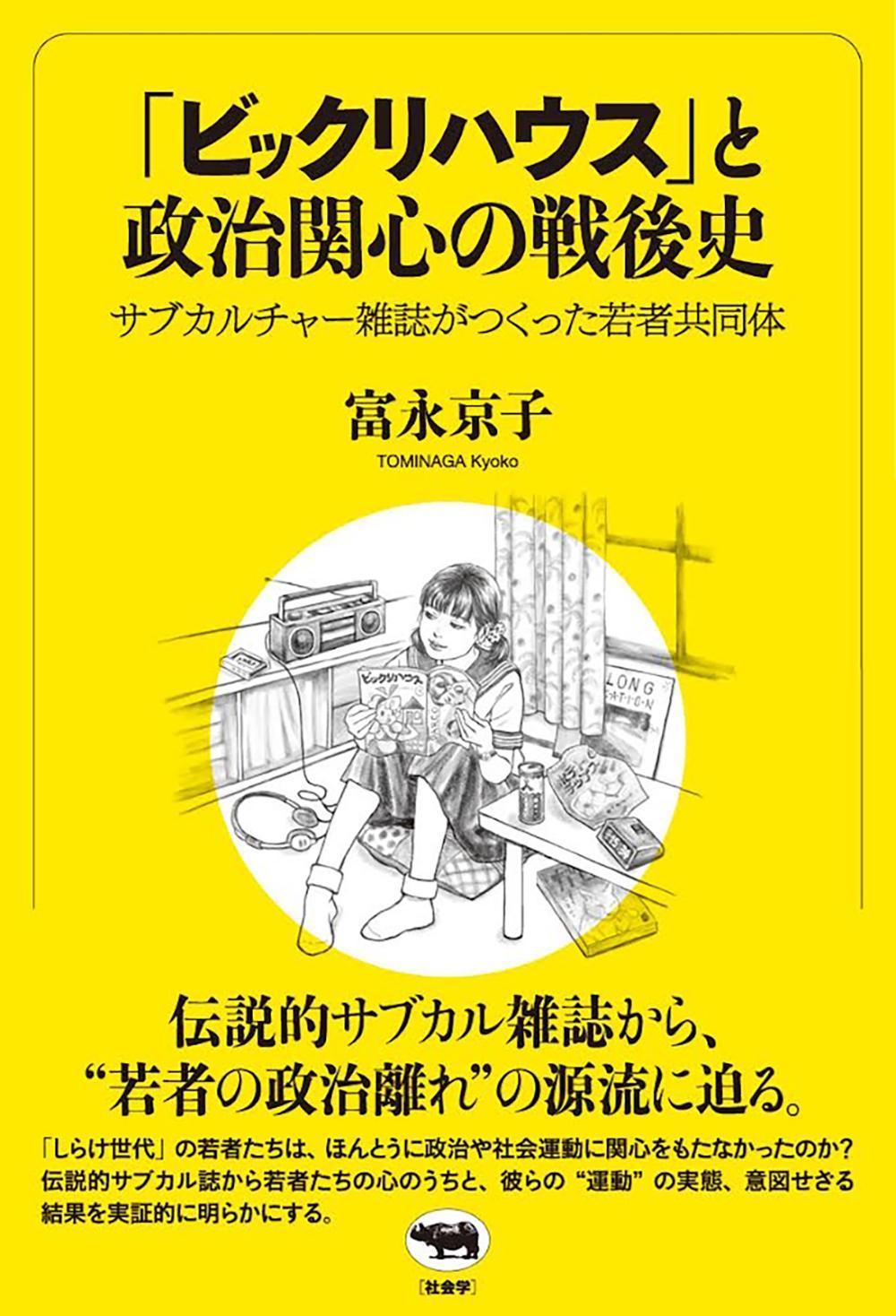 『「ビックリハウス」と政治関心の戦後史――サブカルチャー雑誌がつくった若者共同体』 著:富永京子 価格:2,750円(税込) 発行:晶文社
『「ビックリハウス」と政治関心の戦後史――サブカルチャー雑誌がつくった若者共同体』 著:富永京子 価格:2,750円(税込) 発行:晶文社
- プロフィール
-
- 富永京子 (とみなが きょうこ)
-
1986年生まれ。立命館大学産業社会学部准教授。専攻は社会学・社会運動論。東京大学大学院人文社会系研究科修士課程・博士課程修了後、2015年より現職。著書に『社会運動のサブカルチャー化ーーG8サミット抗議行動の経験分析』『みんなの「わがまま」入門』。朝日新聞での連載「あちらこちらに社会運動」ほか、さまざまなメディアへの寄稿などをしている。
- フィードバック 6
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-











