『マンガ大賞』に2年連続ランクインし、『手塚治虫文化賞』など数々の漫画賞を受賞した大ヒット漫画『チ。 ―地球の運動について―』を手がけた漫画家の魚豊さんがCINRAのPodcast番組『聞くCINRA』に登場。
100メートル走を題材としたデビュー作『ひゃくえむ。』をつくったきっかけや、漫画を描くうえで大切にしていること、陰謀論と恋愛をテーマにした『ようこそ!FACT(東京S区第二支部)へ』と現代社会についてなど、さまざまな角度からお話しを聞いた。
「リアル」と「リアリティ」は違う。魚豊がアリストテレスから学んだこと
─デビュー作の『ひゃくえむ。』ではどのような着想から「100メートル走」というピンポイントな競技を掘り下げたのでしょうか?
魚豊:2016年にリオオリンピックの100メートル走の予選を偶然テレビで見ていたら、フライングで失格になった選手がいたんですね。この人の次のチャンスは4年後かもしれないし、最後のオリンピックだったかもしれない。そう考えたら、とんでもない緊張の世界だなと思って。「走れもせずに終わるんだ」みたいな。戦えずに負けてしまうっていうことが、一瞬のできごとで決まってしまう。なんか不思議だなと思ったんです。
それで100メートル走を題材にした漫画はないか調べたら少なかったので、描きたいと思ったのが始まりでした。
─スポーツはやっていらしたんですか?
魚豊:スポーツはめっちゃ苦手で、何もやっていません。ただ、スポーツ漫画は世界観の説明をしなくていいので、本題や人間ドラマに入りやすいんです。なので、デビューから初期の段階では、その楽さもあって選んでいました。特に読み切りの場合、50ページ以内で勝負しないといけないので。
─経験がないなかで作品として突き詰める大変さもあったのではないでしょうか?
魚豊:究極、漫画ってやったことないことを描くものだと思います。人を殺したことはないけど殺人は出てきますし。
僕が作品を描くなかで重要だったのは、自分がやっていることや、自分がどう生きていきたいかみたいなことを、キャラたちに言わせることでした。だから、ストーリーでぶち当たる壁も、どの生き方をしていてもぶつかるような問題が多くなっています。そのテーマに関わりがない人でも読めるような作品にしたいと思っていたので、テーマ自体をガッツリ描くやり方はしてなかったですね。
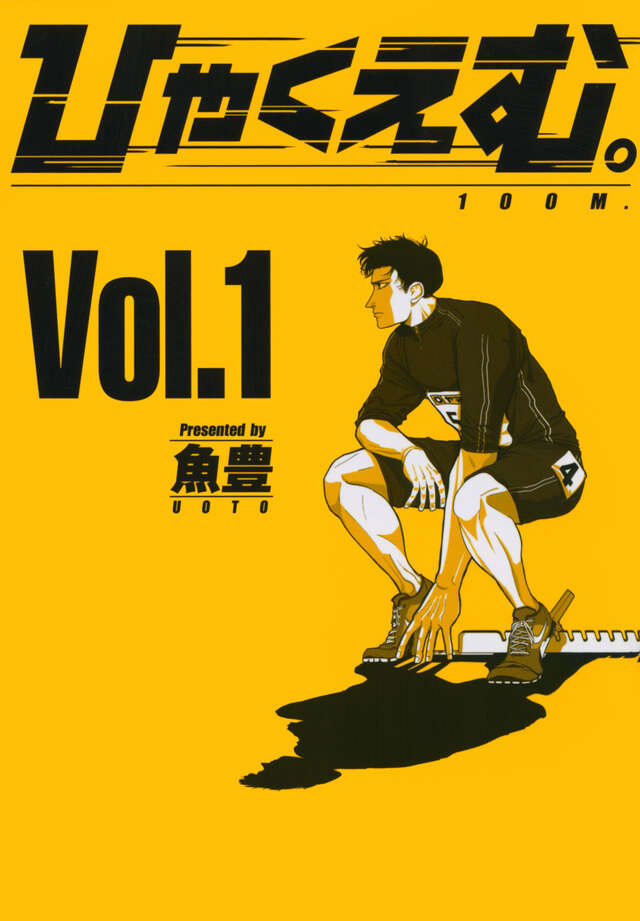
─主人公のトガシくんにとっての100メートル走が、読者にとっては別の何かであるということですね。魚豊さんにとっての「何か」は、漫画でしょうか?
魚豊:そうです。あるとき、僕は漫画しか描いてきてないので、自分には描けるテーマがないなと思ったんですよね。でも、そういう考え方自体をアナロジーで表現すれば応用が効くんじゃないかなと気づいてからは、あんまり悩まなくなりましたね。
─具体と抽象で言えば、抽象的な部分があれば、どんな具体にも対応できるというようなことでしょうか。
魚豊:そうだと思います。で、作家っていうのは、おそらくそこを掴む職業なんだろうなと。テーマそのものにこだわってその精度を上げていくことも重要だと思いますが、それは本質ではない。そういう認識を絶対にぶれさせないようにするのが重要だと感じています。
「伝える」ことと「描く」ことは別で、リアルとリアリティには違いがあると思うので、抽象的なままでいるという点は大事にしていますね。
─リアルとリアリティの違いはどんな部分なのでしょうか?
魚豊:「それっぽさ」と「それそのもの」は違うというか。僕が1番大事にしていて何回も立ち返る本がアリストテレスの『詩学』なんですが、そこでは歴史と詩学=創作をしっかり分けているんです。歴史は起こったことで詩学は起こりうることだからこそ、詩学のほうが哲学的だと。そして歴史は個別で、詩学は普遍と書かれていて、その部分はすごく大事にしています。
本当の歴史や詳細な情報の束ではなく、「こういうキャラだったらこういうこと起こりそうだよね」という、あるあるのような感覚を描くんです。それを読んだ人間が「なんかわかるわ」と思えちゃうところが創作の面白さだと思うので。
─リアルではなくリアリティの世界で語るからこそ、いろんな人が自分の人生に置き換えやすくなって、広がっていくというのもありそうですね。
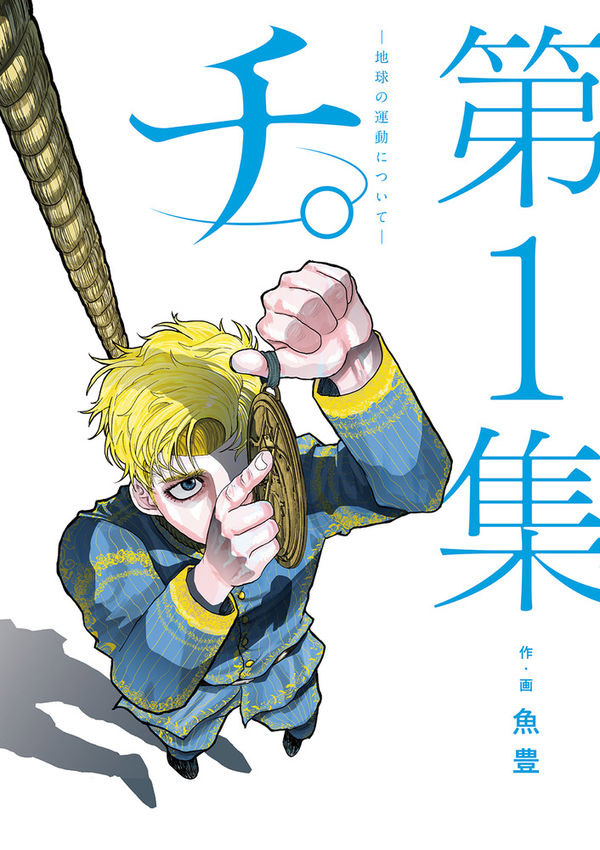
「嫌さを嫌さのままで終わらせたい」。モヤモヤできない現代の危うさ
─魚豊さんは過去に「何かに出会うことで人生が変わる経験は、豊かな人生を歩むために100パーセント必要」とおっしゃっていましたが、ご自身はそのような人生が変わった体験はあったのでしょうか?
魚豊:それがなかったんです。漫画をやめるくらいの何かに出会ってないっていうやばさがありますね。何を見てても何をやってても、漫画に使えるか使えないかで考えちゃってて、ある意味ですごく貧しいなと思っています。全部が意味に紐付けられていて、「意味ないこと」がないんです。
去年、何かやったことないことをやってみようというノリで自動車免許の合宿に行ったんですが、本当につらくていろんな人に脱走したいと相談していました。
でもみんな、「つらいのもいつかネタになるじゃん」って言ってくれたんです。それは優しさだし、自分もそう思ったんですが、それが嫌だと思ったんですよ。
そのときに感じた嫌さを嫌さのまま終わらせたいというか……いい思い出になったり、金になったりしたら、このつらさがなかったことになっちゃうじゃんみたいな。
悲劇を悲劇として受け止めずポジティブに考えることは人間の良さだと思うんですが、その速度が早すぎると思っちゃったんです。みんな賢くなりすぎて、いろんな人にいろんな気持ちがあることや、こういうことがあったときにはどういう言葉遣いをすればいい、みたいなことを学びすぎて、秒で切り離しちゃってるというか。
みんな、傷つきやむかつきをすぐにエネルギーにできるようになっていますが、モヤモヤの期間って、実はあったほうが新たな何かにつながったりもするんじゃないかなと思っています。
─社会が作ってくれた文脈や意味に、自分の経験、気持ちをすぐ明け渡してしまう現代の危うさは感じます。
魚豊:悩んでいる人にアドバイスを求められても「こうしたほうがいいんじゃない? でもそうじゃない可能性もあるよ」みたいな。自分の言ったことが暴力的になってしまうことを恐れるあまり、何も言っていないChatGPTのようなコミュニケーションがうまくなってるっていうか。そういう「悩めなさ」みたいなものがあると思います。
あまりに深い言葉が早く出てきすぎてるみたいな。この人がたどり着く速度じゃない、僕たちが本来この会話のなかでたどり着けないスピードで結論や言葉にたどり着いてしまうことには、不気味さを感じますね。

─魚豊さんの作品は現在の世界で、ある種の社会問題化されている事象をエンタメとして描かれるバランス感覚が凄いと感じています。社会を描くことと面白く書くことの舵取りで悩むことや、工夫されていることがあったら教えてください。
魚豊:たぶん、社会を描けていたらそれは面白い作品なんだと思うんですよね。人と人とのネットワークみたいなものが描けていたら僕は面白いと感じるので、その状態に近づきたいですね。
「物語を成立させる」ことは、それこそAIなんかでも簡単にできる事です。ただ、それがユニークか、自分が面白い、美しいと思えるかが課題で、漫画家や物語をつくる人にとって重要だと思っています
そのうえで自分が好きなもの、好きなキャラクター、好きなストーリーにどれくらいお客さんがつくかはギャンブルで、運次第なんだと思います。
僕は好きな映画も本も漫画も売れている作品なので、本当に自分が好きなものを描けたら一定数見てくれる人がいるだろうと思うんですが、知り合いには「本当に人が理解できないものが人生で1番好き」と言っている漫画家の方もいて、そういう人がもし売れたいと思ったら、折り合いをつけなきゃいけないんだろうなと思いますね。
魚豊が感じた陰謀論の「面白さ」
─『ようこそ!FACT(東京S区第二支部)へ』に登場する飯山さんは一見意識高い系の嫌なキャラにもできそうですが、魅力のある人物として描かれていました。主人公も含めて、紋切り型のキャラクターではない深みが、読者として愛せるポイントだと思いますが、人物造形のときに考えていることはありますか?
魚豊:「悪役だけの悪役」はあまり書かないようにしています。いじめっ子になるために生まれてきたいじめっ子みたいなキャラは描かないようにはしてるんですが、それって結構みんなできることなんですよね。むしろ、本当に「悪役のために生まれた悪」みたいなキャラを描くほうが難しいし、面白いというか。
ただ、『ようこそ!FACT(東京S区第二支部)へ』に関しては、飯山さんが笑われてしまったり、寒いと思われたりする状況になると漫画はもう崩壊すると思って。自分のなかでは100パーセント肯定的に描いたつもりなので、そういうふうに言ってもらえるのは嬉しいです。
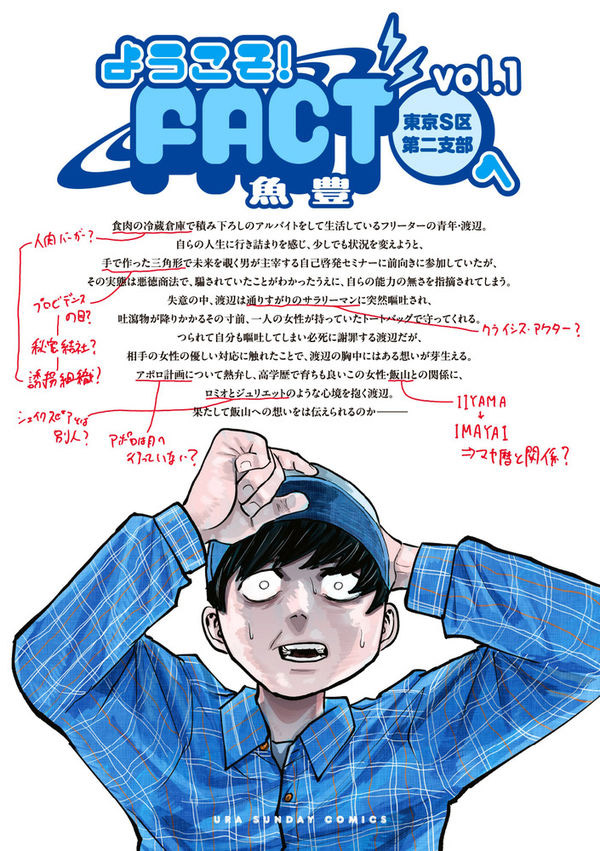
─テーマとして陰謀論を取り上げられていますが、陰謀論が力を持つ社会に対して一石を投じたいという熱のようなものはあったのでしょうか?
魚豊:それはあまりなくて、自分が面白いと思うかどうかが大きいですね。これまでに見たことがあるものはもう見なくていいかなと思っていて、漫画の構造は王道のものを使っていますが、テーマとしてはなるべく自分が知らないものを書きたいです。
─陰謀論のどんな部分に面白さを感じたのでしょうか?
魚豊:もともと興味はずっとありました。哲学を学ぶなかで、思想ってもうかなり更新されていなくて、なにも生まれてないなって思っていたんです。でも2020年代に入って陰謀論が活発になって、思想っていう思想ではないのですが、かなり新しい思想の動きだと思いました。新しい社会問題と、人間の考えと、自意識と、自尊心みたいなものがつながってるのが、すごく面白いと感じたんです。
もちろん、陰謀論自体はすごく昔からあるんですけど、こういうかたちで表面化してきてバズワードになっているのは最近だった気がするので、この時代に自分の世代の作家が描いたら面白いんじゃないかなと気になっていました。
─魚豊さんとしては、いまの社会状況をどう思われているのでしょうか。距離をとって冷静に知的好奇心の対象としてみられているのか、「これはまずいぞ」というような良し悪しの感覚があるのでしょうか?
魚豊:ずるい答え方かもしれないですが、どっちもあって、それが人間なんだろうと思います。
自分が本当に憎んでいる事件や憎んでいる相手を描いたとしても、描くと自分のなかでその人が生まれて、その人と一緒になっていくんです。だから、何かを馬鹿にしきるとか、何かを憎しみきるまま表現するのはたぶん不可能だと思いますね。
─漫画を描くことで世界の混沌や憎悪を少し愛せる部分はあるんでしょうか。
魚豊:それはあるような気がします。何より恐れるべきは、自分のなかでつまらないものを描いてしまったと感じるときだと思うんです。そのときにはすごく後悔してしまうと思います。僕はいまのところ、自分で描いたものはぜんぶ好きなので、そこまでマイナスな気持ちになったことはないです。
─最後に、今後の展望ややりたいことについて教えてください。
魚豊:当分は漫画をやっていくので、売れたらすげえ嬉しいです。今年は自分が原案の元のアイデアと1話のネームを少し協力した『ドクターマッスル』という作品が1月後半から始まり、『ひゃくえむ。』の劇場アニメも公開されるので、それをぜひ見ていただきたいのと、別の発表もたぶん年内にあると思うので、それもよければぜひ見てください!
- フィードバック 24
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-





