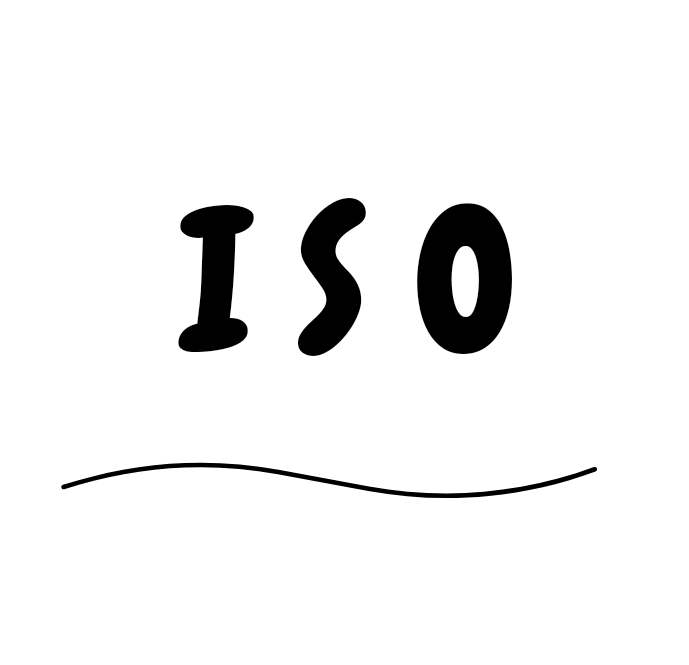『第75回カンヌ国際映画祭』で「ある視点」審査員賞とクィア・パルム賞を受賞したパキスタンの映画『ジョイランド わたしの願い』が、10月18日より公開された。
パキスタンの大都市で、保守的な中流家庭で生まれ育った主人公・ハイダルは、就職先となるダンスシアターでトランスジェンダー女性のビバと出会い、妻を持ちながらも、強く惹かれていく。一方、ハイダルの妻ムムターズは仕事にやりがいを感じていたが、義父から仕事を辞めて家庭に入り、子供を産むことを強く望まれてしまう。
家父長制に縛られる人々を繊細な映像と豊かな登場人物で描き、パキスタンでいったんは上映禁止になるなどの話題を呼んだ作品だ。CINRAでは本作を手がけた33歳の新鋭サーイム・サーディク監督にオンラインインタビューを実施。トランスジェンダー当事者の起用をはじめ、さまざまな立場の女性たちを描いた理由などについて聞いた。
※記事の終盤で、物語の結末について触れています。お読みいただく際はご注意ください。
「異性愛者の男性が、トランスジェンダー女性と恋に落ちる」物語の構想
『ジョイランド わたしの願い』予告編 / あらすじ:大都市ラホール、保守的な中流家庭ラナ家は3世代で暮らす9人家族。次男で失業中のハイダルは、厳格な父から「早く仕事を見つけて男児を」というプレッシャーをかけられていた。妻のムムターズはメイクアップの仕事にやりがいを感じ、家計を支えている。ある日ハイダルは、就職先として紹介されたダンスシアターでトランスジェンダー女性ビバと出会い、パワフルな生き方に惹かれていく。その「恋心」が、穏やかに見えた夫婦とラナ家の日常に波紋を広げてゆく——
—本作は監督が24歳のときに生まれた構想だそうですね。抑圧的な社会を複層的に描く本作の出発点は何だったのでしょうか?
サーイム・サーディク(以下、サーディク):正直なことを言うと、本作の起点となるアイデアがどこからきたのか自分でもよくわかっていないんです。あるときパッと思い浮かんだアイデア、それが「異性愛者の女性と結婚している異性愛者の男性が、トランスジェンダー女性と恋に落ちる」という三角関係でした。
そこにはドラマチックで観客を物語に引き込む要素がありますし、恋愛のみならず、主人公と妻、そして家族全体の関係性や家父長制による抑制、人々の欲望についても探求できる可能性があると感じたんです。それはまさに私が興味のあるテーマについて語れるアイデアでした。

サーイム・サーディク
—その過程で出来たのが短編映画の『Darling』(2019)(※)なのですか?
サーディク:そうとも言えますね。大学院在籍中から『ジョイランド』の草案となる脚本を2つほど書いていたんですが、同時に卒論にあたる映画をつくらなければなりませんでした。
そこで、『ジョイランド』の世界を探求するにあたってのリサーチも兼ねて、成人劇場に焦点を当てた映画を撮ることにしたんです。ある意味で研究プロジェクトのようなものですね。当時パキスタンにはトランスジェンダー女性の俳優がおらず、自分の手で発掘する必要がありました。それで私は演技に興味があるトランスジェンダー女性を募集し、オーディションをして見つけ出したのが『ジョイランド』でもビバを演じるアリーナ・ハーンなんです。彼女を中心に成人劇場の世界に没入するような映画を目指し製作したのが『Darling』でした。

主人公ハイダルが惹かれるトランスジェンダー女性、ビバを演じたアリーナ・ハーン
サーディク:『ジョイランド』とはストーリーは大きく異なりますが、テーマ的に共通する部分もあり、制作過程からは多くのことを学びました。そして『Darling』制作後はアリーナと仕事したことで得た知識を活かし、それまで書いていた脚本のほぼ全部を書き直したんです。成人劇場で働く本物の演者たちと撮影するという経験をした私は、『ジョイランド』でも同じ劇場で撮影をすることを決めました。
※『Darling』……ダンサーとして踊るため成人劇場のオーディションを受けるトランスジェンダー女性と、彼女に思いを寄せる青年の姿を描くサーイム・サーディク監督の短編映画。『ジョイランド わたしの願い』でビバ役を演じたアリーナ・ハーンが主演を務める。
トランスジェンダーの役を当事者が演じる重要性。「映画が良くなることにつながる」
—日本でも最近になり、トランスジェンダー役を当事者が演じる機会がわずかながら増えてきました。『Darling』『ジョイランド』でアリーナ・ハーンさんを起用してきた監督は、当事者に演じてもらう重要性をどのように考えていますか?
サーディク:とても重要だと思います。ただそのトピックについて「適切なキャスティング」という意味ではなく、さも慈善事業かのように「トランスジェンダーの人々に役を与えてあげるべき」という会話が交わされることもあるように感じています。でもそれはちょっと上からな考え方の気がするんです。
私が当事者をキャスティングするのは、映画をより良くしたいという非常に利己的な理由からでした。トランスジェンダーの俳優がトランスジェンダーの役を演じることは、キャラクターがより精細で信憑性のあるものになるので映画が良くなることにつながるのです。
キャスティングの方法として、それぞれの役柄に最適な人を選ぶことを人々は考えるべきだと思います。トランスジェンダーのキャラクターを演じるのに最適なのは、つねにトランスジェンダーの人です。キャスティングのプロセスは義務的なものではなく、創造性を重視した決定であるべきだと私は思います。
また、現代の社会ではほとんどの人が、「トランスジェンダーであるとはどういうことか」や「トランスジェンダーが生きるうえでの経験」を理解しようとしていません。私がトランスジェンダーのキャラクターを登場させ、当事者に演じてもらう理由のひとつは、人々がその状況を理解すべきだと思うからなのです。

—パキスタン映画におけるクィア当事者の起用状況について教えてください。
サーディク:残念ながらまったくありません。これまでもトランスジェンダーのキャラクターが映画に登場することはありましたが、それをトランスジェンダー当事者が演じるのは短編なら『Darling』、長編なら本作がはじめてだと思います。じつはヌチ役(ハイダルの義姉)の俳優を何名かにオファーしたところ、皆ビバ役を演じたいと言ったんです。その役は当事者の俳優に演じてもらうのでそれはできませんとお断りしましたが。
—世界的に映画のなかでも現実でもレズビアンは透明化されやすい状況にありますが、パキスタンではいかがでしょうか?
サーディク:パキスタンでも同様で、レズビアンやそれに近しい描写を描いた映画やテレビ作品を私は知りません。仮にあるとしても、それがメインストリームの作品であるならばまったくうまく描かれていないでしょうね。
女性の性欲、子供を求めず働く女性。さまざまな女性を描いた理由

—ハイダル、ムムターズ、ビバの関係や葛藤をどのように探求していったのでしょうか?
サーディク:彼らの関係は、これまでの人生で経験したり周囲から見聞きしてきた人間関係をベースにしつつ、想像力を膨らませながら構築していきました。ハイダルとムムターズの夫婦の関係というのは深い友情であり、プラトニックな深い愛情でもあります。
しかしその関係のなかで、ハイダルは仕事へと出かけ、ムムターズには家に取り残されることによる嫉妬心が生まれ、またビバとの恋愛という裏切り、罪悪感といった負の感情も芽生えていきます。「このプロットならこういう関係だろう」と特定のかたちに無理矢理押し込めることをせず、彼らの人物像や関係を現実にあるものとして息づかせることを意識してつくりあげていきました。
—(煙草を吸う監督を見て)伝統に従いながら生きるヌチが密かに煙草を吸っている姿が印象的でしたね。
サーディク:伝統に従って家事や育児をこなし、それでいて幸せそうなヌチが煙草を吸うのは面白いですよね。喫煙は彼女の秘密のひとつですが、秘密にすることで彼女はワクワクする楽しいことをしている気分を味わっています。
単なるニコチンの摂取ではなく、喜びを見出す意味ある行為なんです。パキスタンでは多くの女性が煙草を吸っていて、それをオープンにしている人もいれば秘密にしている人もいます。本作では男性が喫煙していない一方、女性が喫煙している姿を入れるのが面白いと思いました。

ムムターズの義理姉であるヌチ(サルワット・ギラーニ)。3人の女児の母で、男児を産むことを望んでいたが……。
—この作品ではトランスジェンダーのみならず、女性の性欲や、子供を求めず働く女性像、年配女性の恋心と孤独など、従来あまり描かれてこなかった女性の姿が描かれていたように思います。そこには女性の姿を覆い隠すことなく率直に描こうという意図があったのでしょうか?
サーディク:これまで映画やTVでは、男性に焦点を当てた作品が男性によってつくられてきましたが、そこでは女性やトランスジェンダー、そのほかのあらゆるマイノリティの描写がいつも一面的でした。
だから女性やトランスジェンダーはみんな同じだというような偏見に満ちた見方をする人が多いのだと思います。もしかするとこの映画を観た人も、ビバがトランスコミュニティ全体を代表する人物としてとらえ、皆が彼女のように野心家で気の利いたことを言うと考えるかもしれません。
この映画でビバは威張るような態度を見せますが、私はその部分が気に入っています。というのも、これまでトランスジェンダーのキャラクターはとても弱々しく、愛らしく、親切なイメージばかりで描かれてきました。でも、当たり前ですがそんな人ばかりではありません。それはどんな属性においても当てはまります。これまで男性がそう描かれてきたように、この映画ではビバもさまざまな面を持つ人物として描きたかったのです。

サーディク:それは女性においても同様です。私は女性たちが家父長制に対し、それぞれ異なる反応を示す様子を描きたいと考えました。ある女性は周囲からの期待にうまく適応し折り合いをつけることができますが、当然すべての女性にそれがあてはまるわけではありません。
特定の状況を受け入れる人もいれば、納得できず逆らう人もいて、対処できない人もいます。たとえば子供を望まない人もいれば、貧しくとも子供がほしいという人もいたりと、人それぞれです。この作品では、その違いを表現することが非常に重要だと思いました。

—パキスタンではトランスジェンダー法が法制化されているにもかかわらずヘイトクライムが起きている状況だとうかがいました。それはなぜなのでしょうか?
サーディク:パキスタンではトランスジェンダーの権利を求める運動がまだ初期段階にあるためだと思います。もちろん以前からトランスジェンダーの人々は存在していましたが、これまで彼らは自分たちの権利を強く要求していませんでした。しかし彼らは仕事やメディア、教育や日常生活などさまざまな面で平等な機会と社会参加を望んでいます。そして昨今、各方面から上がる要望がある種のグループとしてまとまり、政治的な代表者も生まれ、声を上げられる状況へと変化していきました。
右翼はそれを「自分たちが闘うべきもの」だと意識しはじめます。そして虐げられてきた人々がいまこそ行動を起こすべきだという機運が高まったときに、激しいバックラッシュが起こるのです。
残念なことですが、歴史や世界の動きを鑑みるとそれは避けては通れない道だと思います。重要なのは対立や衝突を乗り越えていくこと。そうして物事を前進させていくしかないのです。
「家父長制とは誰の得にもならないシステムです」
—パキスタンのみならず、世界中でトランスジェンダー差別が激化する中、トランスジェンダーへの暴力や偏見、差別を内包した本作を描いたことにはどのような思いが込められているのでしょうか。
サーディク:この映画をつくったのは、世界の状況が一向に変わらないから。トランスジェンダーの人々だけでなく、家父長制のなかで生きるあらゆる人々がこの映画を観ることで、ポジティブな影響が生まれることを願っています。
特に男性たちがどれほど自分が家父長制に苦しめられているかに気付いてくれると嬉しいですね。なぜなら、男性が自分の苦しみに気付けば、周囲の女性やトランスジェンダーの人々に対し共感を示すことができるからです。

一家の家長であるアマン(右)は、失業中の次男ハイダルに子供を持つことを強く求め、ムムターズには仕事を辞めるように要求する。
サーディク:多くが理解しているように、家父長制とは誰の得にもならないシステムです。男性に権力を与え、多くの利益をもたらすように見えても、必ずしも彼らを幸福にするわけではありません。そう認識することは社会全体にとって重要であり、健全であると思います。そしてさまざまな女性やトランスジェンダーの人々がスクリーンに登場することで、彼女たちも自分たちと同じ普通の人々であると観客の皆さんが認識してくれることを願っています。
パキスタンの色合いを表現した映像や色彩設計
—夫婦がベッドで語り合うクローズアップ、女性二人がアトラクションに乗るシーン、ハイダルとビバのキスが深く心に残りましたが、映像面で意識したことはありますか?
サーディク:多くの登場人物がいるこの作品において、何をどう撮るかは非常に重要でした。この映画の本質は「人々が多くの感情を秘めながら、それを率直に語らないこと」にあります。
登場人物たちは本当に最後の最後まで、本心についてほとんど口にしません。彼らが「大丈夫」と語っていても本当は大丈夫ではないこと、日常生活を続けながら心の奥底で何かが起きていることを観客にどうやって伝えるかが大きな課題でした。
なぜなら、登場人物の多くが、自分は抑圧されているということをまったく自覚していないからです。だから彼らが台詞で「私は抑圧を感じている」と言うのではなく、視覚的にその抑圧を感じさせることが重要だったと思います。
たとえば家族が揃うシーンでは緊張感が漂い、たびたび重い出来事が発生します。映像においても、その状況と同様に緊張感があるものを目指しました。その一方で、あなたが挙げた遊園地やキスシーンなどでは、憂鬱から解放されるような心の動きやロマンスが表現されています。それらの場面ではワクワクするような、流動的なトーンを意識しました。

—色彩設計も素晴らしく美しかったです。特に赤が鮮やかで、終盤にいくにつれて色味がなくなっていく演出をされていたのかと思うのですが、色彩面でのこだわりを教えていただけますか?
サーディク:一般的に映画の色彩をイメージするとき、つねにその題材や内容が考慮されると思います。例えばこの映画は家父長制や抑圧などを題材としているため、色の少ない憂鬱な映像を想像するでしょう。
しかし、私はその反対をいこうと思ったんです。なぜならパキスタンがとてもカラフルな国だから。我々の文化には色とりどりの織物があり、壁や家も色彩やパターンであふれています。その点ではミニマルなイメージのある日本と正反対なのかもしれませんね。

サーディク:なので、私はパキスタンにある空間をできるかぎり忠実に再現したいと思いました。とても抑圧された家なのに、色彩やパターンで溢れているというのは興味深く映ると思います。
終盤では色味が変わりますが、季節が変わったことも理由のひとつです。霧が多いラホールの冬の景色は、それまでの季節とはまったく異なります。そのため葬儀のシーンでは突然、家が色褪せた空間になります。その色合いの変化は、不思議と皆が同じような色を着ているように見え、誰もが同じように見えるという効果ももたらしました。
そのなかで、トランスジェンダーであるビバが、家父長制の家庭にただ歩いて入って来ることが重要でした。葬儀という儀式においては、人はひとつにまとまります。故人の冥福を祈りにきた彼女は、その日だけ受け入れられるのです。
もちろんその出来事が突然ビバと社会を結びつけることはありません。きっと電車などの日常生活では、いまだに彼女は女性たちと一緒に座ることは許されないでしょう。でもその瞬間は女性たちと一緒に座ることに対し、誰も文句を言いません。そこでビバが周囲に溶け合って目立たなくなる様子を、色彩の変化で表現したのです。

※以降、作品の結末について触れています。ご了承ください。
ハイダルのセクシュアリティについて 「彼自身が理解しておらず混乱している」
—ハイダルのセクシュアリティについて、この映画のなかでは明示されませんね。
サーディク:彼は自分自身を理解しようとしている最中にあります。自分がビバに惹かれているかはわかるけど、なぜそう思うのかよくわかっていません。それは自身のセクシュアリティを把握する非常に初期の段階です。
セクシュアリティに関する会話は「ラベル付け」が中心となっていますよね。もちろんあらゆる人を受け入れる人はいますが、そのなかにはゲイやレズビアン、トランスジェンダーといった自分が認識しているラベルに属する人だけを受け入れ、どのラベルに該当するかわからない人相手だとと混乱してしまう人もいます。
本作では、自分自身をまだ理解していない人物を中心に物語を展開することがとても興味深いと思ったんです。ビバは、自分が男性に惹かれるトランスジェンダーの女性であり、人生で何を望んでいるかを理解しています。ほかの人々も同様で、自分が何者でありどうなりたいのかをわかっています。
そんななか、ハイダルだけは自分が何が好きか、それはどうしてか、彼自身どうなりたいかを理解しておらず混乱しています。そんな状態であるために、彼はほかの人から受け入れられないのです。
ムムターズの自死 「彼女には最後の権利が残されていた」

—ハイダルがセクシュアリティを隠して家庭を築いた結果、家父長制に押しつぶされたムムターズが自死につながる悲劇的な連鎖反応が描かれていました。男児を妊娠した身体としてしか重宝されないムムターズの一種の復讐だったのでしょうか?
サーディク:このシーンについてはいろんなことを考えましたが、復讐ということは意図していません。その決断はある意味で反抗とも言えますが、彼女が持っていた権利を行使しただけなのです。
彼女は働く権利だけでなく、健全な結婚生活を送る権利、子供を産まないという権利さえも奪われていました。でも、彼女にはまだ生きるか死ぬかを決める最後の権利が残されていました。彼女は今後の人生に、生きる理由となる素晴らしい出来事が残されているとは思えなかった。彼女が自分の人生に生きがいを見いだせないと判断したのなら、そこから脱出するという決断を下すことが間違っているとは思えません。
もちろん彼女にとってはつらいことです。妊娠中ですし、自死は簡単な選択ではありません。でも彼女は最終的に、他者や神のためではなく自分自身への優しさからその決断をしたのです。
—おそらくこの物語で語られているような、セクシュアリティを隠し、心理的な負担を感じながら家庭を築いている人は世界中に大勢いると思います。そんな人々からも反応が寄せられたのでは。
サーディク:それはありませんでした。そういった人々はセクシュアリティを隠して生きていますから、たとえ共感したとしてもまわりの環境によってそれを認めることは難しいのでしょう。一方で私にはゲイやバイセクシャルの友人がいますが、彼らからは多くの反応を得ました。彼らの多くは女性と結婚していましたが、時間とともに自分のセクシュアリティに気付き、カミングアウトして結婚生活を終わらせました。
その後、ありのままの自分を受け入れ、アイデンティティを取り戻したんです。彼らはこの映画にとても感動し、自分の気持ちを代弁してくれたように感じてくれました。しかし、彼らが自分らしく生きるという決断は、場合によっては相手の女性を深く傷つけるかもしれないということを突きつけられ、罪悪感に駆られたとも言われました。社会の状況や環境が影響している側面もあると思いますが、この気付きもまた重要なことであると感じます。
- 作品情報
-
 『ジョイランド わたしの願い』
『ジョイランド わたしの願い』
10/18(金)より新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国順次公開
監督・脚本:サーイム・サーディク/出演:アリ・ジュネージョー、ラスティ・ファルーク、アリーナ・ハーンほか
製作総指揮:マララ・ユスフザイ、リズ・アーメッド『サウンド・オブ・メタル 〜聞こえるということ〜』 ほか
英題:JOYLAND/2022年/パキスタン/パンジャーブ語、ウルドゥー語/1.33:1/ 5.1ch/127分
日本語字幕:藤井美佳
© 2022 Joyland LLC
- プロフィール
-
- サーイム・サーディク
-
ラホール経営科学大学で人類学の学士号を、そしてコロンビア大学で映画監督の修士号を取得。短編映画「NICE TALKING TO YOU」(2018)が、2019年に開催されたサウス・バイ・サウスウエスト、パーム・スプリングス・インターナショナル・ショートフェストに正式出品され、BAFTAショートリストの最優秀学生映画賞を受賞。またコロンビア大学映画祭2018で最優秀監督賞を受賞した。またKodak Student Scholarship Gold Awardも受賞。続いて製作された短編映画「DARLING」(2019)はパキスタン映画として初めて第76回ヴェネチア国際映画祭でプレミア上映され、最優秀短編映画賞のオリゾンティ賞を受賞。トロント国際映画祭2019にも正式出品され、サウス・バイ・サウスウェスト2020では審査員特別賞を受賞した。現在は、『行き止まりの世界に生まれて』(2018)のビン・リューが監督を務める、ベストセラー小説「Hotel on the Corner of Bitter and Sweet」の映画化作品の脚本を執筆中。
- フィードバック 14
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-