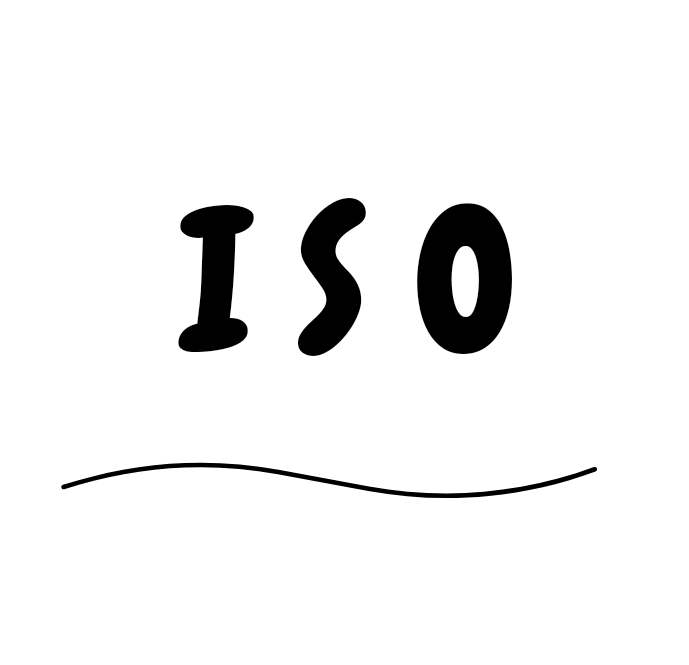11月20日はヘイトクライムなどの迫害によって亡くなってしまったトランスジェンダーの人々を悼み、トランスジェンダーの尊厳と権利について考える「国際トランスジェンダー追悼の日(Transgender Day of Remembrance)」だ。2024年の同日、映画監督有志らがトランスジェンダーを含むLGBTQ+への差別に反対する声明を発表した。発起人となった8人を含め、映画監督97人が賛同人として名を連ねている。
近年、ネット空間など、社会にはトランスジェンダーや性的マイノリティを標的にした差別的な言説が広がっている。声明では、「私たち映画監督は時として作品内で社会的マイノリティの表象を用い、現実社会に影響を与える立場にあります」と綴られており、偏見や差別に晒される少数派の人々を描く際には「細心の注意が必要」だとしている。
この声明を発表した背景には何があったのか。発起人となった映画監督の加藤綾佳、バイセクシュアル当事者である映画監督の東海林毅に聞いた。
小説家有志たちも声明を発表。「攻撃的な言説がものすごく溢れている」

—まずは「トランスジェンダーを含むLGBTQ+差別に反対する映画監督有志の声明」を掲示するに至った経緯を教えてください。
東海林毅(以下、東海林):小説家の李琴峰さんから、「LGBTQ+差別に反対する小説家の声明」の掲示に合わせて隣接業界で同じような動きをやれば、この訴えを大きなうねりにできるんじゃないかとご提案いただいたのがスタートでした。
東海林:昨今日本において、国が同性婚を認めないことに対する違憲判決や、戸籍の性別変更における手術要件の撤廃の判決(※)など、性的マイノリティの権利回復に関わる司法判決が続いていると感じています。
(※)同性婚訴訟の違憲判決……法律上の性別が同じ人同士が結婚できないのは憲法に違反しているとして、同性カップルらが国に賠償を求めている日本初の裁判。札幌、東京、名古屋、大阪、福岡で裁判が続いている。これまで地方裁判所で6つの判決が言い渡され、2024年3月には札幌高裁が違憲判決を下した。 / 性別変更における手術要件撤廃の判決……現在、トランスジェンダーの人は戸籍上の性別を変えるうえで、性同一性障害特例法によって生殖能力をなくす手術を受けることが義務付けられている。その要件が憲法に違反するかが問われた家事審判で、最高裁は2023年10月、要件は「違憲」とする決定を下した。
東海林:それは良い流れだと思う一方で、激しいバックラッシュ(反発)も起きており、SNSやネットを中心に性的マイノリティに対する攻撃的な言説や排斥的な動きがものすごく溢れている。自分にとってもつらい現状だったので、李さんのお誘いにぜひと快諾させていただきました。
とはいえ映画業界全体となると広すぎるので映画監督という枠に絞りまして。まず発起人として加藤さんをはじめ差別に対して一緒に声をあげてくれそうな方や、普段から社会問題について発信されている方、デモでお会いした方などにお声がけして、本プロジェクトを立ち上げていきました。

東海林毅
—東海林監督と加藤監督はもともとどのようなつながりだったんですか?
加藤綾佳(以下、加藤):もともとは飲み友達でしたよね(笑)。
東海林:ですね(笑)。加藤さんは日本映画監督協会で唯一の女性理事なんですよ。今回は映画監督有志の会という括りなので、ぜひ協会側にも協力してほしいとお声がけさせていただきました。
加藤:常日頃から差別が起こっていることを感じていたこともあり、ご連絡をもらって即答で参加させていただきました。私は決して有識者ではありませんが、差別はいけないというのはごく当たり前のことだから、それを声に出していきたいなと。
バックラッシュが起きている状況について、我々のような名前を表に出している人間が問題意識を持つことが大切だと感じているので。それで今回の声明も映画監督協会の会報に掲載して共有していきました。
—20人以上いる理事会のなかで唯一の女性理事とのことで、男性中心の日本映画監督協会で意見を言うのはなかなか大変なのでは……?
加藤:もうすぐ90周年を迎える映画監督協会は会員の年齢層も高く、最初は緊張していましたが(笑)。今後に向けアップデートしていかないと若い世代も入ってこないので、理事会でも変化の必要性は日頃から積極的に訴えるようにしています。特にここ数年、映画監督の言動が問題視されることも多いので、業界全体としてそれらも変えていきたいなと。

加藤綾佳
目指すべきは「公言する・しないに関わらず、すべての人が働きやすい職場」
—声明にあわせて、「映像や・映画・演劇、・芸能業界で働く性的マイノリティ当事者が受けたハラスメントや、偏見、差別などの事例集も発表しています。その経緯は?
東海林:賛同を募る過程で、「映画業界にLGBTQ+差別ってあるんですか?」や「映画とLGBTQ+差別は関係あるんですか?」という声が上がることがあったんです。当事者からすると、なぜこれが見えていないのだろうと思いつつ、これまで意識したことがない人にとっては寝耳に水だということを理解しました。
それでそういった人のために、「実際にこういう事例がある」と被害を可視化するのが良いのかなと考えたんです。性的マイノリティ当事者の映画関係者にコンタクトを取り、シェアできる経験があれば教えてほしいと聞き取りを行ないました。
性的マイノリティの業界人同士で「この状況では俳優もカミングアウトできないね」と話すこともあるんですが、それが慢性化しているために、被害者のなかには被害を受けたという自覚がない人もいる。事例集で、この業界にどのような問題があるかみんながきちんと認識してくれたら良いですよね。
—今回いろいろな人に聞き取りをされたかと思いますが、やはり映画製作の現場でも性的マイノリティであることを公表している人は少ないのでしょうか?
加藤:マイノリティ当事者であることを公言しているスタッフもいますが、少ないと思います。とはいえ公言は本人の自由で強制するものではないので、目指すべきは公言する・しないにかかわらず、すべての人が働きやすい職場ですよね。「セクハラやパワハラをやめよう」と同じで、誰かが傷つきかねない言動をやめようという意識をみんなが持てることが大切だと思います。
東海林:たとえば「職場の女性に対するセクハラ発言をやめよう」と言われたら対象が明確ですが、性的マイノリティの人はオープンにしていないことが多い。そこが見えないから、そもそも気をつけようと意識する人が少ないんじゃないかなと。だから「特定の誰か」ではなく「つねに」言ってはいけない、という根本的な意識を変えていく必要があると考えています。
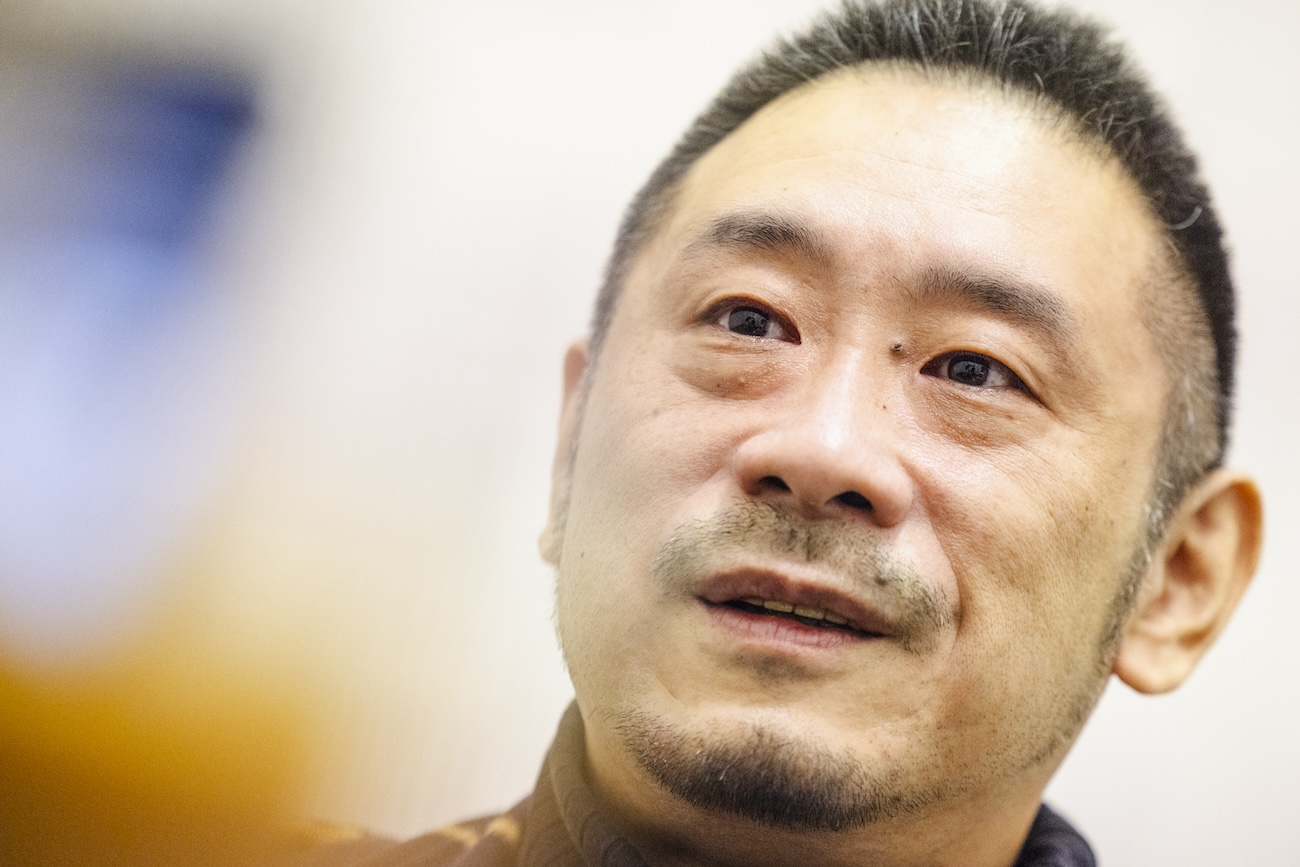
—性的マイノリティが映像業界で働きやすい環境をつくるために大切なことは何だと考えますか?
加藤:「映像業界で差別があるのか」という声が上がるということは、それだけ透明化されてきたということ。それが今回の声明や事例集であらためて明確化されたので、まずは自分の身の回りにも性的マイノリティの人がいると理解すること。そのうえで明確な事例をもとに、こんなことを言うと当事者の尊厳を傷つけてしまうと学んでいくことが大切だと思います。
表現を狭めるのではなく、声明文で主張しているのは『差別はいけない』ということ
—映画やドラマなどの作中では、少しずつ透明化されていた人々が可視化されてきたと感じています。ただそれに対するバックラッシュとして「過剰なポリコレ」といった言論が視聴者や映像関係者のなかでも目立ちますが、この状況を制作者側はどのように見ているのでしょうか。
東海林:僕自身は「トランスジェンダーをはじめとする性的マイノリティの役は当事者の俳優が演じたほうがいい」という考えを強く持っているので、おそらく僕は「ポリコレ」が暴走している代表格のように思われているかもしれませんね(笑)。
東海林:ただ、そもそも勘違いしている人が多いと思うのですが、ポリティカルコレクトネスは決して表現の幅を狭めるためにあるものではないんです。むしろこれまで透明化されてきた人や、社会的に不利な立場にある人を包摂するような表現を目指そう、という裾野を広げるためにあるもの。それを我々が実践して伝えていく必要があると考えています。
加藤:当事者に演じてもらうことが、性的マイノリティを理解する入り口になればいいですよね。ただ性的マイノリティ役は絶対に当事者でなければいけないというわけではないと思うんです。でも、演じるうえでは理解することは必要。その入り口としてまずは当事者が演じるのは良いことだと思うし、それが「ポリコレ」だとは思いません。

東海林:包摂的な表現を主張すると業界内で「我々の表現を狭める気か」と反発されることがあるんですが、こちらにはそんな権力はないですからね。今回の声明に関しても、反差別には賛同するが、そうするとしたい表現ができないのではと心配する人もいて。でもそういうことは声明文で言ってないし、強制力もない。LGBTQ+を題材とする時に、何をどう表現するかは各々が決めていくべきこと。だから「表現を狭めてしまう」という反論は完全に論点がずれていると思います。
加藤:今回の声明に対し「何をもって差別というのか」と問われることもありました。でもたとえばセクハラに関して、これはセクハラか否かとつねに考えながら行動しているわけではありませんよね。あくまで大切なのはセクハラをしてはいけないという意識を当たり前に持ち、行わないことのはず。我々が言いたいのはこれまでの事例や状況を鑑みて、これからみんなで差別のない業界や社会を目指していこうということ。
東海林:声明文で主張しているのは「差別はいけない」と「包摂できる表現を目指そう」という単純なことなんです。その具体的な方法は、みんながそれぞれ考えていくことだと思うので。

当事者のキャスティング、監修。映像業界で起きている変化とは?
—日本で初めてトランスジェンダー女性の俳優オーディションを開催した『片袖の魚』(2021年)を東海林監督が手がけた理由のひとつに、業界の悪循環を変えることを挙げていたかと思います。今年に入りトランスジェンダー男性の主人公を当事者が演じる『息子と呼ぶ日まで』(2024年)という作品もつくられましたが、キャスティングに関する状況に変化は感じますか?
東海林:以前よりは感じます。今年だとNHKが『虎に翼』で当事者のキャスティングをしてくれたのは嬉しかったですね。もっと早くできたのではと思いつつも、当事者が演じる重要性に目を向けて実践してくれたことは評価すべきこと。映画業界でも少しずつ当事者に演じてもらうのが良いよねという認識が広まりつつあります。
長編映画『老ナルキソス』(2023年)を世界中のクィア映画祭で上映したんですが、そこでは「ゲイの主人公は当事者ですか?」と聞かれることも多かったです。それくらい世界的にも当事者のキャスティングは当然のこと。当事者をキャスティングしていないというと、社会的な壁や問題があるのではないかと受けとめられてしまうんです。
—今年日本公開のパキスタン映画『ジョイランド わたしの願い』(2022年)でもトランスジェンダー女性の役を当事者が演じていて。それについて監督に質問をしたら、当事者が一番うまく演じられるし作品のクオリティを上げることにつながるという話をされていました。当事者のキャスティングに加え、性的マイノリティを表象する際に監修が入ることも増えてきていますね。
東海林:とても良いことですよね。ただ、一部の作品ではプロデューサーがいわゆる「炎上」を恐れて監修を入れるということもあると感じています。それもインティマシーコーディネーターやLGBTQ+監修が広まる一助となっているとは思いますが、監修を人権や尊厳を守るために入れているのか、炎上が怖くて入れているのかどちらなんだろうと疑ってしまうこともありますよね。
加藤:監修は本来、誤った表象を防ぎ、キャラクターへの理解を深め、作品をより良くするためのもの。炎上を防ぐための防波堤の役割を押し付けるために監修を入れるのは本末転倒だし、そうであってはいけないと思います。

東海林:プロデューサーの仕事として作品を守るために手を尽くすことは理解しますが、それは現状きりがないことだと思うんです。性的マイノリティとマジョリティのあいだに社会的格差や不均衡がある状況において、どれだけ施策をめぐらせても絶対に炎上の可能性はありますから。それを防ぐためには平等な社会をつくること以外にないと思います。
加藤:あと監修を入れるのであれば作品本編だけでなく、宣伝にも入れたほうがいいですよね。
東海林:すでに宣伝にも採用している作品もありますが、それは本当に重要だと思います。作品本編自体が真摯につくられているのに、例えば俳優や監督のインタビューなどで性的マイノリティが置かれた社会的な状況に理解のないような発言が出てしまい、がっかりしてしまう観客もいるかもしれない。それはとてももったいないことだと思います。

女性表象のクィア映画を増やすには女性差別の解消も必要
—両監督ともに作品で性的マイノリティの姿を描いてきましたが、表象する際に意識していることはありますか?
加藤:BLドラマを監督する際は原作に準拠しつつ、主体性と意思を持った個人と個人、一対一の恋物語であるということに重きを置いて制作していきました。BL作品は少女漫画等と同じくジャンルものという側面も大きい。ゲイ・バイセクシュアル当事者のなかでも好き嫌いが分かれるものをどう描くかというのは難しいところもありますが。
東海林:僕個人としてはBLにはあまり食指が動かず、あくまで男性同性愛を描きたいのですが、BLというジャンルで性的マイノリティを表現することはまったく問題ないことだと思います。
—現在LGBTQ+の表象といえば男性同性愛者(ゲイ、バイセクシュアル)の割合が大半で、レズビアンやアセクシュアル、ノンバイナリー(※)などの表象はまだまだ足りていない状況かと思います。その状況をどのように考えていますでしょうか?
東海林:僕は2018年くらいから世界各国のクィア映画祭に行くようになりましたが、どの国のラインナップを見ても半分くらいが男性同性愛の物語なんです。
くわえて現在世界的にトランスジェンダー差別の問題に直面していることから、エンパワメントや理解推進のためにトランスジェンダーを扱う作品が3割。女性同性愛者(レズビアン、バイセクシュアル)が1割で、残りのすべてで1割という印象でした。
その理由のひとつは、女性映画監督の総数自体がまず少なく、クィア映画祭に参加しているのもゲイの男性監督が多いということ。映画業界において女性とレズビアンというダブルマイノリティである以上、映画を撮ることが難しい不利な立場にあることは容易に想像がつきますよね。だから女性表象のクィア映画を増やすためには、当然女性差別の解消も同時に進めていかなければいけません。
(※)アセクシュアル……他者に性的に惹かれない人 / ノンバイナリー……性のあり方が男性か女性という性別二元論にとらわれない人。英語圏では主に「ノンバイナリー」や「ジェンダークィア」といった言葉が使われ、日本語圏では主に「Xジェンダー」が用いられている。

加藤:私はレズビアンとバイセクシュアルの女性の関係を描いた『さよならシンデレラ』(2018年)という短編を手がけたことがありますが、次に撮ってみたいと思うのが、アセクシュアルの人々の物語。これまでの映画は「恋愛とは良いことだ」という主張が強すぎると感じているので、恋愛しなくても良いのだという価値観をもっと肯定したいんです。恋愛に気持ちが向かないという人はアセクシュアルに限らずすごく多いとも思いますし。
東海林:じつは、数年ほど前に自分がアロマンティック(※)だと気付いたんです。子どもの頃から映画やドラマ、漫画の恋愛描写を見ると、恋愛という謎の状態によって冷静な判断ができなくなったおかしな人たちだと感じていて(笑)。
でも、恋愛することが当然だというプレッシャーも感じていたので、20代の頃は無理してお付き合いをしていたこともありました。自分は恋愛に縁のない人間なんだと納得するようにしていましたが、つい数年前にアロマンティックという言葉を知って、ようやく「僕はこれだったんだ」と自分のなかでこれまでのことの説明がついたんです。だから僕は自分の映画の恋愛描写はすべて第三者にチェックしてもらうようにしているんですよ。わからないので(笑)。
(※)アロマンティック……他者に恋愛的に惹かれない人。
—映像作品で多様な表象があれば、数年前の東海林さんのように、当事者が自分を理解することにもつながりますよね。そういう意味でも包摂的な表現の重要さを感じます。
東海林:僕が子どもの頃は基本的にクィア映画というものはなかったですし、ゲイやレズビアンが登場しても特殊な役割ばかりで、普通に社会生活を送る人間としては表象されてきませんでした。それが最近になって増えてきたのはすごく良いことですよね。
僕が中学生のときにNetflixの『HEARTSTOPPER ハートストッパー』が放送されていたら人生が変わっていたかもと思いますよね。
エンタメ・文化芸術業界のポジティブな動きや変化
—日本のエンタメ・文化芸術業界のなかで、LGBTQ+の権利に関してポジティブな動きや変化を感じたことはありますか?
加藤:性的マイノリティに対する認知が高まっていることは良いことだと感じています。東海林監督が言うように、昔は特殊な人物としてばかり描かれ、そのとおりに認識されていたと思いますが、いまは性的マイノリティの人物が登場しても、あくまで多様な性自認やセクシュアリティのひとつであるということが説明なしでも認識されている作品も増えてきていますよね。それはとてもポジティブな変化だと思います。
東海林:少し前ですが、『カランコエの花』(2018年)がつくられたのは大きいと思いました。非当事者のマジョリティである監督が性的マイノリティを題材とすること自体はめずしくありませんが、マジョリティであることを公言している監督が「マジョリティである主人公の目線から性的マイノリティを描く」という点で、エポックメイキングな作品でした。
東海林:マジョリティの監督が性的マイノリティを主人公にすることがよくありますが、みんなどうしてよく知らないものを撮りたがるのかと、ずっと思っていて。この映画はいわゆる「同性愛狩り」を描いていて、当事者からするとつらい作品ではあるのですが、マジョリティの監督が「マジョリティとしてどう向き合えばいいのかわからない」という状況を描いた素直な作品なんです。こういう作品が生まれたことは意味あることだと思います。
—最後に、性的マイノリティについての理解を促し、表象を考えるうえでのおすすめの資料や映像作品があれば教えてください。
東海林:声明文の賛同を募るにあたって、監督のみなさんがどういう認識かわからないじゃないですか。もしかするとネットのスティグマを鵜呑みにして間違った受けとめかたをしているかもしれない。そういった情報のせいで不安に感じている人がいれば、と紹介したサイトと書籍があるのでぜひそれを参考にしてもらえれば。まずは遠藤まめたさんが立ち上げた「trans101.jp」というサイト。そして周司あきらさんと高井ゆと里さんの共著『トランスジェンダーQ&A 素朴な疑問が浮かんだら』です。
加藤:私が個人的に性的マイノリティについて考えるきっかけにもなった作品としておすすめしたいのが『チョコレートドーナツ』(2012年)ですね。LGBTQ+に焦点を当てたうえで社会とのつながりが描かれていて、解決するべき問題も明確化されている。そういう作品が世界中の観客賞を席巻していたこともとても印象に残っています。
東海林:『チョコレードーナツ』は主役である性的マイノリティ2人の関係ではなく、子どもも含めた3人が社会のなかでどう生きるのかという点に焦点が当てられているのが良いですよね。それはクィア映画としてとても大事なこと。性的マイノリティ同士の恋愛や関係性を描くだけの作品は、僕個人としては、クィアではないと考えているんです。その人たちがこの社会制度のなかでどう逸脱していて、どう生きているのかという「対社会」を描いてこそのクィア映画なのではないかなと。

【2024/12/7 14:00 記事の中の一部表現を修正しました。】
- フィードバック 22
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-