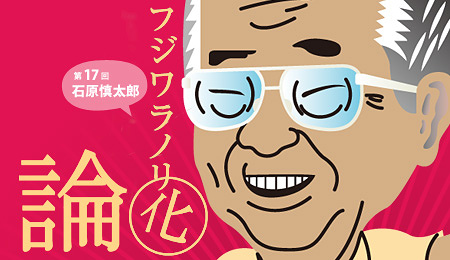其の一 「こころづかい」も「思いやり」も見えない男
休日、月島でもんじゃ焼きを食べ、高校の同級生の車で東から西へ、東京の中枢を駆け抜けながら都下へ戻っていた。移転先に基準値の43000倍の有害物質ベンゼンが検出されたにもかかわらず「彼」が強引に移転を進める築地市場の文字が散らつき、反対論が浮上したにも関わらず「彼」が聞く耳持たず強引に命名した大江戸線に吸い込まれるいくらかの人々を見やり、官公庁をすり抜け皇居を横目に靖国神社を左折、靖国通りの行く先に新宿の高層ビル群が見えるようになったころ、同乗していた二人に、おもむろに聞いた。「ところで、石原慎太郎って、どう思う?」。二人が即座に返事をくれる。「え、いいじゃん」。「どうして?」「だって、ズバリ物申す人ってあの人くらいじゃん」「例えば?」「………」。この反応は、何も彼等が無知だからではない。むしろ、この「………」こそ石原慎太郎がここまで都の長でいられた理由だと言える。その理由は、これからいくらでも述べるつもりでいるが、しかしまあ、これほど、噛めば噛むほど味が薄くなる人物を他に知らない。駄菓子屋の10円ガムでももうちょっと味が保つ。この連載も17回目となるが、断言する。これほど薄い人はいない。
東北大震災の後に彼が発した言葉を、忘れる人はいないだろう。「日本人のアイデンティティーは我欲。この津波をうまく利用して我欲を1回洗い落とす必要がある。積年たまった日本人の心の垢をね。やっぱり天罰だと思う。」あらゆる批判をぶつけても追いつかない愚かな発言だ。政治家の失言を引っこ抜いて辞職に追い込んでは毎月恒例の世論調査に反映させて政治を転換させる作法には飽き飽きしている。政治家の失言をあげつらうのは健康的ではないと強く思っている。しかし、石原慎太郎の場合は、口がすべる、というレベルではない。「いやでもやっぱ石原さんでしょ」と本稿を放り投げられる前に、いくつかの発言と所作を並べておこう。2007年の能登半島地震の際、彼は「ああいう田舎ならいいんです」と言った。つまり、東京に地震が来なければ、それでいいと思っている男なのだ。重度身体障害者施設へ出向いた後には「ああいう人ってのは人格あるのかね。つまりは意思持ってないんだからね」と言い、代議士時代には面会を求めてきた水俣病患者から逃げ麻布のテニスクラブでテニスに興じた。血税で出張という名の海外旅行に出かけ、(妻を同行させた上で)計11人・10日間で2135万円の費用を浪費している。その他、いくらでも具体例を挙げることが出来るが、それは本稿の目的ではない。石原慎太郎の人生を丁寧に解く評伝・佐野眞一『誰も書けなかった石原慎太郎』や、綿密な調査で彼の軽薄さを象っていく斎藤貴男『東京を弄んだ男』を拾い読みするだけで、薄情と強情があちこちから漂ってくるだろう。地震で総崩れになった本棚から石原慎太郎の本を探し抜いて、デスクの横に積んでいるが、私には、これこそが、洗い落とせない我欲そのものに見える。
カルチャーサイトで政治家を取り上げるのはいささか気が引ける。思想信条にかかわる原稿を書く場ではないからだ。連載のサブタイトルをおさらいすると、「必要以上に見かける気がする、あの人の決定的論考」とある。政治家を、とりわけ都知事選の真っ最中の人物について書けば、賛否のどちらかに区分けされてしまう。ほう、おまえはそっちかと。そういう弁別に加担する気は毛頭ない。むしろ、このサブタイトル的に彼を見つめていく、ただそれだけのことをしたい。つまり、サブタイトルを膨らませるならば、「多くの人は具体的に問われた場合『………』になってしまうのにもかかわらず、何故か最終的に選ばれてしまう、あの人の決定的論考」という立ち位置だ。これまでの連載、要するに荒川静香や加藤浩次や土田晃之を見つめるやり方を踏襲する。
「だって、ズバリ物申す人ってあの人くらいじゃん」と、もんじゃ臭の充満する車内で友人はズバリ返答した。しかし、そのズバリの成分は、重みの無い無色透明の空気のくせして人畜有害である。それでも何故、我々は消去法でその刃物を選んでしまうのだろう。江藤淳は、石原慎太郎を「無意識過剰」と称した。或いは彼の息子たちは父を、「心配障害者」とネーミングした。血の遺伝を感じる酷いネーミングだが、勇ましく雄々しく大声で陣頭指揮に立っている風の彼の裏側にある線の細さ、肝っ玉の小ささを探るのは容易いということだろう。彼の本や様々な石原論を浴びていて思い出したのは、前から見ればスーツ姿だが後ろから見れば裸状態のびんぼっちゃまだ。その分、自分が東京を引っ張るのだというイメージを編み出す戦略に長けていることは確かだろう。1999年、知事選に立候補し告示後、初めての街頭演説を行なったのは、他の候補がターミナル駅前だったのに対して、都庁前だった。街宣車の下からカメラで彼を映せば、あたかも都庁を背負う男、のイメージが出来上がるというわけだ。
彼は失言を逃れる度に「文学者としての表現だ」を乱発する。芥川賞受賞作にして彼のデビュー作、障子に陰茎を突き立てる『太陽の季節』については別の章で特殊な方法で取り上げるが、文学をあやふやに高尚に持ち上げて逃げ道にする作法、その作法以前に文筆力が文学の世界の中で通じなくなっていることは、彼が1995年から選考委員を務める芥川賞選評の筆致を覗けば明らかだ。「何かがおかしい、何かが衰弱している。何かが見当違いだ」(第142回)だそうだ。これで評の骨子を締めくくる態度が文学だとするならば、こちらがそちらに申し上げられるのは、「おかしい、衰弱している、見当違いだ」となろう。いつの時代も、悪しき権威主義の輪郭は、過去の礼讃が、新参者に向かう頭ごなしの否定にベタベタに塗り付けられることで成り立ち、行く先の視界を汚す。彼の言質に追っていると、必ずゴニョゴニョ弁舌をふるった後に、「男」「戦争」「日本」「文学」といった、大文字の言語で締めくくりにかかろうとする。その出口にふと立ち会った人が、「おお、この人はズバリ言ってくれる」と誤解するのかもしれない。幼少期を過ごした小樽文学館に訪れて、自分の本が無いと係員を怒鳴りつける肝の小ささが吐き出す言葉に、「ズバリ」など期待してはいけない。
文化をカタカナにして「カルチャー」、その言葉に石原慎太郎を掛け算することはできるのだろうか。彼は、都知事就任後すぐに十代の頃に書いた絵画を展示する会を開いている。また、都知事室には自らが書いた裕次郎の画が飾られているという。文学のみならず芸術への感度が高いという自負があるのだろう。石原慎太郎が取り組んだ制度に、ヘブンアーティスト制度がある。「東京都が実施する審査会に合格したアーティストに公共施設や民間施設などを活動場所として開放し、都民が気軽に芸術文化に触れる機会を提供していく」、大きな公園等で観られる大道芸の公認化である。では、彼が芸術家を理解しているかと言えば、NOだ。NOというか、彼の頭の中の、強固な選別によって虐げられている。「青少年健全育成条例」については後述するが、制度に反対する漫画家についてどう思うかと問われた彼は「その連中、芸術家かどうか知らないけれど、そんなことぐらいで、書きたいものが書けなくなった、そんなものは作家じゃない、本当に、言わせれば。ある意味で卑しい仕事をしているのだから、彼らは。」と答えている。人の仕事を詳しく味わいもせずに「卑しい」と断じる態度が、カルチャーにとって最も卑しい行動であることは、その当事者であるならば、絶対にわかってくれると思う。こういう排他をこの人は平然と繰り返してきた。なお、ヘブンアーティストについては、第1回では220組が応募し140組が合格、正直、その称号を欲する面々がどれほどいるのかは不明だ。ただし、その称号があれば自由だが、無ければ制約が生まれる。事実、アーティストは、その称号によって、昨日まで敵だった警察や警備員が今日から味方になったと漏らしたそうだ。それがアートの条件であっていいのだろうか。
改めて書くまでもないが、漫画を読みもせずに卑しいという人に、カルチャーの行く末を委ねていくことは出来ない。しかし、都知事という役職は強権を持っている。東京はあらゆるエンターテイメントが集積する。ここで強権が発動すれば、表現は萎縮を迫られ、知らず知らずの間に消えていく。ヘブンかヘルか分からないが、あの世へ消える。週に2、3度しか都庁に登庁しないことを問われ、「都庁にいてできない仕事はたくさんあるよ。あまりばかなこと言わない方がいいよ」と答える薄っぺらな恫喝老人に、何も期待をしていけない。「ズバリ言ってくれる」という印象論だけを頭に残し、彼を消去法で愛でるのはもう止めないか。次回以降、この暴発する老兵に向けて懇切丁寧に惜別を申し上げていくことにする。
- フィードバック 1
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-