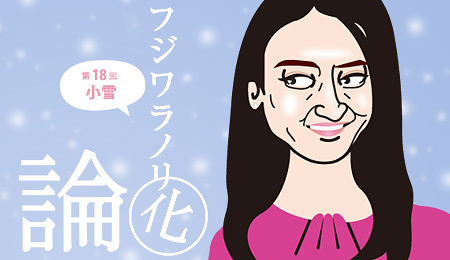其の二 小雪×美人史
美人は3日で飽きる、ブスは3日で慣れる、という悲惨な言い方がある。賛同しないが、ひとまずその風説に付き合ってみる。では、4日目からは何が生じるのか。3日で慣れたブスも、その後の3日で飽きるのではないか。3日で飽きた美人は、4日目から馴染んでくるはずだ。ブスも、3日で慣れてその後の3日で飽きれば、7日目から馴染んでくるはずだ。結果、長年寄り添った夫婦にしてみれば、その3日など些細な差になる。となれば、美人だブスだを、付き合うだとか結婚するだとかの真面目な議論に持ち込んじゃいけないんんじゃないのか。
大抵の女優は、キレイですねーと言われれば、そんなことはないですよーと返し、学生の頃からモテたんじゃないですかーと言われれば、まったくモテませんでしたよーと答える。トーク番組などで繰り返されるお決まりのやり取りだが、これほど生産性の薄い会話も珍しい。特別視の果て、という意識が無ければ女優が女優でいられるわけはないんだから、その視線を取っ払おうとする言質の薄っぺらさはむしろ下品にうつる。キレイだモテモテだの浅い議論の他に、ちょっとした挫折体験や貧困体験を肴に這い上がろうとするケースもある。この2つの点について、小雪は潔い。エッセイでこう書く。「これまでの人生であまり『挫折』を感じたことがない」。そんなことないですよー私はみなさんと一緒ですよーという譲歩をした上で、これまで大変だったんだからもう、という共感を投げてみるのが大抵の女優エッセイの基礎構造であったのだが、小雪はそのやり方を真っ向から否定していく。
エッセイの巻末には、「小雪の『より美しくなるためのQ&A』」というコーナーが設けられており、「美を意識し始めたのはいつ頃?」「美しい人でありたいなと改めて思う瞬間は?」といった、自分の美を前提とした質問に平然と答えていく。謙遜は無い。「みんなと一緒だよ」をアピールする媒体になりつつあるこの手の本で、みなさんとは違うけれど、という無言の前提を敷きっぱなしにするのは斬新ですらある。バレーボールに明け暮れた高校時代、引退後、友だちに誘われて『non-no』のモデル募集に応募したら見事に合格、看護師学校を中退してモデル業に専念していく、という、乱れの無い順調な経緯を故意的にグラつかせて見せることをしない。目の前に広がった舗装された歩道を、まっすぐ一直線に歩いてきたのだ。
小雪の突っ込みどころが、「顔」に集中するのは、現在のポジショニングへ至る経緯と現在が極めて無難だからに違いない。オッサンメディアは、誰それは芸能界デビュー前にキャバクラで働いていた、といった過去を嬉々として持ち出す。小雪にはその手の突っ込みが出来ない。余白すら探せない。だって、順調に歩んできただけなのだ。そんなこんなで突っ込みどころを探し疲れると、いつのまにか「顔」に辿り着くわけである。「Yahoo!知恵袋」を覗くとこんな質問にぶつかる。「松山氏と結婚した小雪さんは、一重でしゃくれていて、般若の面にそっくりだと思うのは私だけですか? みなさんはどう思いますか?」。みなさんの答えはこうだ。「一重でしゃくれていて、鼻と顔の輪郭が変で、はっきり言って小雪さんの顔は気持ち悪いです…すみません…」「私は小雪さんの顔、けっこう好きですよ。純和風な感じで、無駄に派手な顔よりも、飽きがこない気がします。」「あーおばあちゃんちにあるあのお面…誰かに似てたけど小雪さんだ!」。
小雪は「どのような容姿の女性が美しいと思う?」との設問に、「私はベビーフェイスじゃないから、ベビーフェイスの人を見ると、はっとしたり、かわいいなと思うこともあるし、でも、その一方で絶対的にきれいな人もきれいだなと思うし……」と答える。何だか的を射ない返答だ。雰囲気という四次元ポケットに吸収させようとする小雪の悪いクセが出てしまっている。知恵袋にあった、般若と純和風、つまりは、小雪の顔をどう捉えるか。自身からの回答が望めないとなれば、日本の美人史を少しばかり振り返りながら導き出してみよう。村澤博人『顔の文化誌』(講談社学術文庫)、井上章一『美人論』(リブロポート)などに頼りながら、日本の美人の変遷を小雪に寄せ付けてみる。
今では信じ難いが、明治期には終身の教科書に美人罪悪論が記されていたという。「美人は、往往、気驕り心緩みて、却って、人間高尚の徳を失ふに至るものなきにあらず」、現代語訳にすれば、「美人は、多くの場合、おごりたかぶって心が緩んでおり、人間としての知性や品格を持ち得ない場合が多い」とまあこんな感じのことが書かれていた。超訳をすれば「美人は性格が悪い」という、現世でもしばしば囁かれる通説に繋がってくる。どの時代も、美人への妬みを、内面に転嫁して罵るというやり方があったのかもしれない。
古代の美人像とはどうであったか。ふくよかな顔がよしとされていたことは有名だ。いわゆる「平安顔」というやつ。切れ長の目に一重まぶた、口は小さく、白い肌が優れているとされた。女性の口の大きさは、女性の社会的地位とリンクしてきた。封建的社会では、口が小さい=モノを言わない女性がよしとされた。口紅は古くからある化粧法だが、口を小さく見せることを求められた時代には、唇の外側を白く塗ってまで唇を小さく見せたという。白い肌が重宝されたのも、封建的社会=女性は外に出ない=〈外で労働をしない→日を浴びない〉性差の象徴として、であった。美人を象徴する白に対応する、或いは補填・増長させる意味で、黒髪の美しさも同時に求められてきた。その前提から考えると、内(家)に閉じこもってきた女性が外へ解放され、外でアイデンティティを発揮させるべき現代に近付く過程の中で、大きな口にテカったグロスを塗り、白い肌に対抗するようにガングロが生まれ、黒髪を染色し、一重まぶたにコンプレックスを持った女性が、アイプチで偽物であろうと二重まぶたにこだわる姿が見られるようになったのは、至極真っ当な「解放」であったと言えるだろう。
さて、その中で小雪はどうなのか。純和風なのか。白い肌と長い黒髪、これはもう、クラシックな日本美人の象徴と言える。目は二重だが、いわゆる浜崎あゆみ的なくっきり真ん丸お目めではなく、どこかに冷たさが流れている。口も平均的な大きさだ。おちょぼ口でも吉田美和のようなバカでかい口でもない。すっと横に平行線を引くようなベーシックな口だ。特徴的なのは鼻の高さだ。鋭く高い鼻立ちは、顔の焦点を牛耳っている。これが般若と呼ばれる所以だろう。芥川龍之介『鼻』という作品は、鼻が大きすぎるのを苦にした主人公が何とか鼻を小さくしようとする話。鼻がデカい、というコンプレックスもあったのだ。一方で、鼻の大きさが地位の大きさに比例して語られる時代もあった。江戸時代の資料には、平民は鼻が低く、役職あるものは鼻が高く書かれている絵画などが存在するという。
小雪は純和風の美人、この言い方をそこかしこで聞くことだろう。しかし、小雪の顔のどこに、「和」が残っているのだろうか? 二重まぶたと大きな鼻は、和のテイストからもっとも離れている。黒髪にしても、清純派の女優にはそんなに珍しいことではない。1976年生まれの小雪、同い年に、女性誌の表紙をローテーションで飾るような女性たちが名を連ねていることに気がついた。SHIHO、内田恭子、井川遥、中谷美紀、この4人は小雪と同い年である。ファッションモデルという職業をライフスタイルまるごと憧れの対象にさせた筆頭であるSHIHO、天然系でオジ様の心を転がしておきながら、フリー転向後はキチンと女性から目線を浴びる体制を整えた内田恭子、癒し系の先鋒であったグラビア時代からいつのまにか働くキレイな女性のモデルケースとなった井川遥、線の細さと精神の細さを相互補填で女優魂に繋げていく中谷美紀、この4人には、「今、どういう女性が女性らしいとされるか」という情報を常に取り入れて更新していく積極性があるし、取り入れた後で、少しだけ更にその先に自分がいてやろうとする先天性と執念がある。
小雪にはおそらくそれがない。先天的な感性で少し先の美人でいようとする能動性。小雪はエッセイの中で「まっすぐ生きてきた」と繰り返す。まっすぐ生きるために余計なものを排除してきた。添加物・付着物をふるいおとして、自分の直球を信じ込んできた。顔の作りであろうとも、いわゆるメイク法であろうとも、同じである。我が直球だけを信奉する。今、様々な媒介において「和」が語られる時、余計なものを加えない引き算の美学を「和」とする傾向がある。しかし、その「○○は○○を必要としません」という引き算のメッセージ自体が強制化し、発想として無理強いを含む足し算となっている場合が多いんじゃないか。小雪と同い年の4人を見ていると、そういうベクトルを、自身の変化球として取り組んでいる場面が少なくない。その点、小雪はクソマジメにストレートだ。自分の直球以外は、自分には必要ない。メイクだファッションだと値踏みされても、小雪は動じない。その動じなさが、美を日に日に前向きに改訂していく顔に慣れた人から、「和」だと片付けてしまうのだろう。
小雪は般若だ、とは、顔ではなくむしろ、般若という言葉が持つ仏教的意味、「修行の結果として得られる悟り」として語られるべきだろう。つまり、小雪は、私はもうこの顔なのです、と決め込み悟っている。美人かどうかという議論は、小雪には愚論なのだ。もうとっくに、答えが出ている問題なのである。
- フィードバック 1
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-