其の一 ギョーカイとお茶の間を行き交う達人
前回この連載で堂本剛を取り上げたが、予想通りかなりの閲覧数だったようである。大好きな「堂本剛」で検索クリックし続けるアフタヌーンをお過ごしの方々には、「いつものルールが守られていない」堂本剛論はいささか刺激的だったようだ。こちらは文章に劇物を混ぜ込んだ思いは全くないのだが、自分の意に反することは全て劇物として処理する対応を心せずして身につけてしまっている熱心なファンは、そこに書かれている記載のどこそこに腹が立った、間違っている、と指摘してくるのではなく、その存在をまるごと否定しにかかった。改めて冷静に、或いは、これを機に読んでいただければ分かると思うのだが、攻撃的な物言いなど盛り込まれていない。あくまでも冷静な(それが冷淡だというなら反論はしない)分析に過ぎない。本人の所作を全て受け入れるのはそのファン個人の勝手だが、だからといって、受け入れないとする少しばかりの意見表明に対して、その具体を叩かずに、存在から根こそぎとろうとするセンスには、首をかしげてしまう。
ファンというのは、盲目である。自覚もある。多くの誰それがKinKi Kidsに盲目的なように、例えばそうだなあ、自分もカテドラル(イギリスのドゥームメタルバンド)に関してならば、もう彼らが何をしようともその音楽を認めてしまう。でもそれは、対象にとって、つまり、KinKi Kidsやカテドラルにとって、結構なことではない。走っても歩いても逆立ちしても体育座りしてもワーキャーと騒いでしまっては、もはやその対象に成長は問われないのである。堂本剛がKinKi Kidsだけではなく自分のソロプロジェクトを次々と始動させたのは、自分が何をやっても肯定される環境ヘの疑いと、そこからの脱却という側面が少なからずあったはずである。今いるファンをそのままスライドさせるために新たなことを始めるわけはない。評価が固形化し、もはや誰も溶かそうとしないから動くのだ。少しでも外部から熱を加えようとすると、ちょっと待ってください何をするんですかと熱を上げて物申すファンがいる。それが、本人にどう作用するのか、それは分からない。そう、皮肉を一つ。評価を溶かすのは、守っている側の、貴方たちが急に声を上げ出すその熱によってかもしれない。バリケードを張って守っているつもりかもしれないが、ガードの中を振り返って欲しい。その熱によって、守るべき対象が溶け始めてはいやしないか。堂本剛が、ソロ活動に力を入れ始めたのは、その熱に頼る在り方に危機感があったからではないのか。
ハードなファンと思しき方々から直接メールで意見をいくつかもらった。意見というかなんというかではあるのだが。人に意見する時は、自分はこう思うが先立たなければならない。田中さんが怒ってましたよ、佐藤さんが微妙な反応してましたよ、と、人の感触を伝達するだけでは、それは意見ではなく、郵便屋さんである。いただいた意見と言うのは熱心な郵便業に専念しているに過ぎず、こちらも、返す言葉を持てなかった。熱心すぎる郵便屋の難点は、発送元の依頼も無いくせに、勝手に意見を伝達してしまう所にある。剛くんは悩みながら自分の人生を見つけようと頑張っているんです、と言われても、それにどう答えよう。剛くんのことを思うとムカついて涙が出ました、と言われても、どうすればいいのだろう。拭えばいいのか。欠落している。とにかく、何に対して自分が何を感じ、だからこう思うという、自分という主語が欠落している。欠落した自分を補う為に、勝手に大きな名前を借りて報告をする。そんな郵便屋さんの行為に、何を感じれば良いのだろう。封を開けたら空っぽだった手紙の読みどころが分からずにいる。
今回取り上げるのはとんねるずの石橋貴明である。この人たちがテレビに出てきたのは、80年代初頭のことだから、ちょうど自分が生まれた頃だ。80年代後半に差し掛かる中で「オールナイトニッポン」や「ねるとん」がとんねるずの存在を急速に押し上げていき、92年に「ガラガラヘビがやってくる」をリリースする頃になると、お笑い芸人の枠を超える人気者となる。そのころ自分は10歳かそこらである。親に内緒で、或いは親に許可をもらった限られた時間指定でつけたテレビに映るとんねるずというのは、完成された大物としての彼らであった。おそらく、現在の35歳辺りと25歳辺りにとってのとんねるずの評価軸は、彼らを見かけたのが仕上がり前だったか後だったかによって大きく異なってくるであろう。今回は、ここ何年にも渡って言われ続けている、石橋貴明の賞味期限について考察を薦めていきたく考えている。うなぎ上りの頃の「上りかた」を見ていない弱みは確かにある。しかし、だからこそ、現在の石橋貴明には素直に向き合えるのではないかと考えを変えてみる。80年代のあの頃と比べて、と、前においてしまうと、とんねるずのみならず、吉永小百合だって中曽根康弘だってボン・ジョヴィだって、衰えたことになってしまう。そういった郷愁の名を変えた現状否定は、いつものように避けて通っていく。
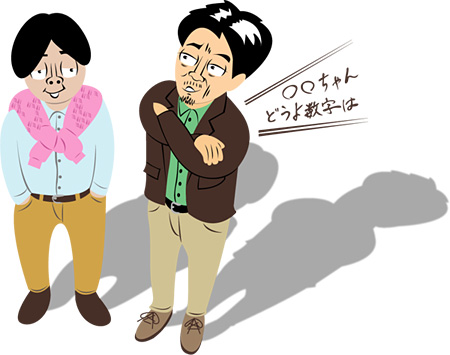
茶の間がギョーカイ化し、ギョーカイが茶の間化しているという指摘を何度かしてきた。改めて持ち出して考え直してみると、茶の間に、ギョーカイを浸透させた先鋒は石橋貴明なのではないか。カメラの手前にいるスタッフを野次り、特定のカメラを見つけて変顔を残し、オンエア時にCG合成させる。石橋貴明という存在は、テレビと世間を接着した。接着剤にしたのは、ギョーカイネタである。ある時は、ここの照明会社はよぉと周りに引きつった笑いを呼び起こさせ、ある時は、ギロッポンでシースーと、実は誰も使いはしないギョーカイ用語をわざとらしく過剰に振りまいてみせた。制作スタッフ連中で作った音楽グループ「野猿」など、彼のやり口の分かりやすい例だろう。それらは確かに面白かった。黒子であるべき人たちを引っ張り出してイジるという「身内ネタ」は、気づかずに膨らんでいく。面白い所は、身内ネタが殻を破ってデカくなっていくのではなく、身内ネタとしてそのまま大きくなり、その身内ネタに答える体を、視聴者に作らせたのである。すなわち、視聴者を「身内化」させていったのである。素人イジリだけではない。これも後で語ることになるだろうが、「うたばん」におけるモーニング娘。の飯田香織・保田圭やELTの伊藤に注視し盛り上げるやり口など、素人でも芸能人でも、あまり光の当たらない所にライトを当てて、不慣れな灯りに汗をタラタラ流す誰それを笑うというスタイルを持ち続けている。そういった石橋貴明のやり方に対して、弱いものイジメをして笑いをとっているという短絡的な評定を見かけるが、そうは思わない。常に意外性を狙うというやり方がさすがに老朽化し始めているのではという不安を除けば、石橋貴明の笑いの取り方、対象との付き合い方は実に温かいものがある。保田や伊藤がそうだったように、つぼみを強引に開いて花を咲かせてしまうのだ。ここ最近のヒット企画「細かすぎて伝わらないモノマネ選手権」は、ネタをやり終えて階下に落ちた芸人の後に石橋や木梨の反応が映し出されるというのがワンセットとなっている。「『いい旅夢気分』で、旅館の部屋からの眺めがすごく良いのに全然違う所に感動する岡本信人」を真似る芸人に腹をかかえて笑ってみせる石橋貴明の姿は、茶の間とギョーカイを巧みに行き交ってきたこの20年の歩みがようやく余裕として備わったかのように見える。
芸人ブームの中にあって、とんねるずの需要が薄まってきたと言われる。お笑い芸人がアイドル化した現在において、ファンとお笑い芸人の距離は、ファンの勝手な歩み寄りで、近くなってきている。書店にはファンブックのような芸人本が並ぶ。KinKi Kidsファン自身が知らぬ間に堂本剛を主語に使ってしまうように、お笑い芸人に対する信奉にも同質の強制が帯びかねない段階にある。石橋貴明がやってきた茶の間とギョーカイの横断は、視聴者側が勝手な密着させてしまうことで、画期的なやり口として受け取られなくなった現状にある。しかし彼はまだテレビの中で、細かなネタを灯しては笑い転げている。この術をしっかりと解析していかなくてはならない。次回は、「時代と寄り添いすぎた石橋の不遇」と題して、今現在、何故彼が追いやられている(と思われている)のかを、石橋貴明の道程を簡単に振り返りつつ考えていきたい。
- フィードバック 1
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-


