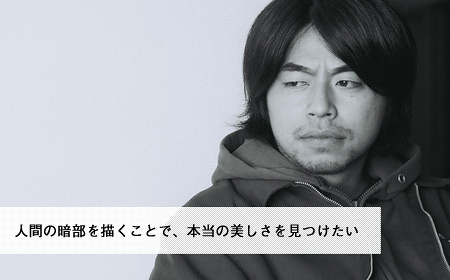僕の映画は、女性に対する白旗宣言なんです
―石井監督の作品には、普段怒らなさそうな女性が、激怒したり暴れたりするシーンがよく登場しますね。
石井:そうですね。僕の映画は、女性に対する白旗宣言なんです。「あなた達には、すいませんが勝てません」と。僕自身もそう思っていて、無意識のうちに女性が超然としたキャラクターになっているかもしれません。演出している時、よく女性の役者さんに「子宮で考えて演技してください」と言うんですが、ちょっとしたきっかけを与えるだけで女性はすごく堂々とした演技をするんです。女性達の持つたくましさとか強さには、やはり尋常ではないものを感じます。男性は、やっぱり理屈で動いていますから、「あなたの面白いところはここだからこうやって見せよう」と、理屈で説明します。もちろん例外はありますけど。
―そういった、「女性って強いな」という意識は、生活している中での実感から得たものですか?

石井:そうですね。強いと言うか、絶対的に必要な存在じゃないですか。逆に男なんてそんなに必要じゃないですよ。長い人生の中でやるべきことと言ったら一回か二回、精子を引っかけるだけじゃないですか。あとは基本的に暇なんです。暇だから宇宙船を作って月に行ってみようとか、核兵器を作って戦争をしてみようとか考えるわけです。映画だって、たぶん暇だから作るんですよ。
―そういった女性観には、作品を創りつづけていくうちに変化はあったのですか?
石井:あったかもしれないですね。今までの話と矛盾するかもしれないですが、基本的に僕は女の人を信用できないんです。男は割と信用できるんですが。最初の2作ではそれが顕著で、『剥き出しにっぽん』とか『反逆次郎の恋』では、女の人が途中からいなくなったり、殺されてしまったりして、出てこなくなるんです。「女の人って、いつか絶対裏切るんでしょ?」、「そのうち黙って去っていくんでしょ?」っていう感覚がすごく強くあるんですよね。
―長編3作目の『ガール・スパークス』は、ヒロインの瑞々しい魅力があふれた作品で、結末も女性への信頼を感じさせるものでしたが。
石井:そうですね。僕もだんだん大人になっていってるのかもしれないですね。裏切られてもいいから信用してみようっていう意識にはなってるかもしれないです。まあ、どうせ裏切られるんでしょうけど(笑)。
―4つの長編の中では、『反逆次郎の恋』が、一番身も蓋もない、というか、強烈な映画でした。そして監督の実感がこもっているというか、すごく愛せる映画だな、と。

石井:僕は『反逆次郎の恋』をほめてもらえるのが一番うれしいんです。僕もすごくいい映画だと思ってるんですよ。あの作品には、一番打算がないんです。何と言うか、「気高い」んです。甘くない映画なので、商品価値はダントツに低いんですけれども。『剥き出しにっぽん』が完成した2ヶ月後に撮影したんですが、前作で自分の能力をフル稼働させて全部出し切ってしまったんで、終わったあとに身ぐるみをはがされた感じがしていたんです。すると、僕の中にはもはやコアな部分しか残っていないので、それを見せるしかないということで、ああいう映画になりました。
僕にとって『反逆次郎の恋』は、段階を踏むという意味ですごく意義のある映画でした。作ったのは22歳の時ですが、作品を今振り返ると「俺、ちゃんと真面目に生きてたわ」と自分の過去に自信を持てますね。これがあったからこそ、長編3作目の『ガール・スパークス』では割り切ってもっと見やすい映画を目指せました。その甲斐あって一般的な評判はすこぶるいいですね。でも、棺桶には入れないでください、みたいな(笑)、いや、好きなんですけどね。
人間の美しさというのは、うんこの中にある
―『ガール・スパークス』は、最近の日本アニメ作品に多く見られる「セカイ系」と呼ばれる作品群に近い世界観だと感じたのですが。

石井:いとうせいこうさんが『ガール・スパークス』についてのコメントで、「これはセカイ系映画の教科書だ」っておっしゃっていたんですが、僕はその言葉の意味が分かりませんでした(笑)。セカイ系ってなんですか?
―さまざまな解釈が存在するようですが、男の子(ぼく)と女の子(きみ)の恋愛関係といったごく小さな問題が、たとえば世界の危機といった大きな問題に、第三者の目線などの中間的な要素を挟まず直結してしまうような世界観を言うようですね。
石井:なるほど、そうなんですね。PFF(ぴあフィルムフェスティバル)の審査員をやっていた鈴木則文さんが、「今の若い人は自分の周囲の狭い範囲のことしか描けないが、『剥き出しにっぽん』はそうじゃなかった」というようなことをおっしゃっていました。僕はここでも実感がわかなかったんですが(笑)。セカイ系的な世界観を作り上げよう、というのは、あんまり自覚的にやっていないですね。
―監督が意識されていなくとも、セカイ系の作品と世界観がシンクロしている点が面白いですね。
石井:ただ、社会学とか、客観的にものを見ることが好きで、中学生の時は政治にものすごく興味がありました。最近はなくなりましたが。『剥き出しにっぽん』は、最初の脚本ではもっと政治的な内容だったんです。でも今では、移り変わりの激し過ぎる政治にはほとんど興味を失いました。もっと普遍的なもの、変わらないものしか信用できないんです。
―長編4作目の『ばけもの模様』が特に顕著ですが、作品にうんこがよく出てきますね。なにか理由があるのですか?

石井:単純に僕がうんこが好きっていうのもありますが、うんこという下品な題材を出すことによって「人間は醜くて下品だが、それでも魅力的なんだぜ」というのを声高に主張したいんですよ。格言チックに言うと、「人間の美しさというのは、うんこの中にある」と(笑)。
誰かが言っていたんですけど、笑いというものを追求していたら、気づかないうちに人間の悲しみが目の前にあった、と。今度は逆に、人間の悲しみを追求していたら、気づかないうちに笑いが目の前にあった、と。それと同じような感覚なんですが、僕は人間の汚い部分、暗部みたいなものを追求していったその先にある、一抹の希望の光というか、美しさっていうものを描きたいと常日頃思っています。それこそが本物だ、っていうのがあるんですよ。
―チャップリンなんかもそうですね。
石井:そうですよね。『ばけもの模様』は、人間の暗部の描写の連続の中に、どっかのタイミングでホッコリするというか、希望みたいなものが見えてくるという作り方を意識的にしました。その一番わかりやすい例として、うんこがあるという。
―『ばけもの模様』で、それこそやりきった、という感じは受けましたけども。
石井:そうですね。出し切った、みたいな(笑)。
メディアとしての映画というものに呆れ返っているんです
―そもそも、映画を志したきっかけというのはなんだったんですか?
石井:映画が大好きだからこそ映画の学校に入るというケースが多いと思いますが、僕はそうでもなくて、大学入学以前はそんなに映画も見てなかったです。ただ、小学生くらいの頃から「お前、将来何になりたいんだ?」とか聞かれるじゃないですか。その時々で適当に答えていましたが、それではダメだと思いまして、18歳の時に「じゃあ映画をやっていくことに決めます」と。退路を断って、とりあえず何でもいいから決めちゃった方がいいと思ったんですね。だから、たまたまです。
―『剥き出しにっぽん』というタイトルや、作品中でのセリフにも、日本をどこか相対化したいというか、外から見たいという気持ちを感じるのですが、そういったことを意識されたのですか?

石井:はい。それもありますが、と同時に、僕は「日本」を主張しているんです。『剥き出しにっぽん』はまさにそうだし、『ガール・スパークス』では女子高生、そして『ばけもの模様』では、「ばけもの」っていう英語に翻訳できないもの。なぜそう主張するかというと、まさに日本的だと感じられる映画は海外でウケがいいと思ったからです。
これは打算ですが、20歳ぐらいから僕は外国で評価されることしか考えていませんでした。デビュー作の『剥き出しにっぽん』で16ミリフィルムを使ったのも、あのちょっとノスタルジックでチープな画質で、日本の原風景みたいな田舎の農村を撮り、『剥き出しにっぽん』というタイトルで海外に出したらこれはウケるんじゃないかという。もちろん取ってつけたテーマではないんですが。
―20歳ということは、もうはじめての長編を撮り始める時に意識していたと。なぜ日本向けではなく海外向けだったんですか?
石井:誰でもそうだと思うんですけど、これからの将来って不安だと思うんですよ。映画をやってた先輩もたくさんいたんですけど、結局よくわかんないうちにやめちゃったりして。僕もそうなるのがすごく怖かったんで、どうにかして映画を撮り続けられる方法はないか、と模索してたんですよね。その上で、卒業制作をしっかり作って、まず海外で正当な評価を受ければよいのではないかと考えたんですね。
- 次のページへ
松本人志や北野武の映画はどう思う?
男の切ないロマンを描きたい
―役者さんを集めるときにも、海外を狙うという話をされたんですか?

石井:はい。この映画に出演することのメリットはそれだ、と。要はペテンに近いですよね(笑)。ギャラなんか払えない状態だったのに大口を叩きました。でもそれがこうして現実になっているので、恐らく大口でもペテンでもなかったんでしょうね。
―どの方も個性的で素晴らしい才能だと思いますが、大学時代に出会われたんですか?
石井:そうですね。『反逆次郎の恋』の主役の内堀くん(最近「とんとろとん」に改名)は美術担当でもあります。なまじ俳優をやりたいです、と言ってチャラチャラしている人より、スタッフの方が面白かったりするので、僕の場合そういう人に出演してもらうケースが非常に多いです。
―登場人物が、自分の思いを言葉にして説明する場面が多いですが、なぜなんですか?
石井:言葉にしないで映像で語るというのが映画表現においてのセオリーなので、技法としては失格なんでしょうね。逆に、だからこそついついやってしまうんです。僕は最近、メディアとしての映画というものに呆れ返っているんです。暴言なんですけど(笑)。映画の存在意義や可能性を作家が信奉し切ってしまうことは危険だと思っています。映画に関わっているからこそ、映画というものに疑念を持ち続けたいと言うか、常にある程度の距離を置いておきたいんです。
―「映画を壊す」と言っていた松本人志の『大日本人』や、北野武の映画についてはどう思いますか?

石井:面白かったですよ。意識的に映画を壊そうとするのはすごく好きですね。どうやったら映画が壊れるか、ということですけど、あれぐらい知名度があって、お金も人も自由に使えてっていう立場の人が、映画という枠組みのギリギリの中で破壊しにかかるという行為がやっぱり偉大というか、いいなあと。ポップであることからそれちゃいけないというか、絶対その中で壊さなきゃいけないんですよ。
―他に好きな監督はいらっしゃるんですか? またそういった方を意識したりしますか?
石井:好きな監督はもちろんいます。岡本喜八とか、神代辰巳とか、キアロスタミとか。でも好きなだけで意識はしていません。強いて言うなら、意識しているのはビートルズですね。撮影前に必ず見るのは『ビートルズ・アンソロジー』のDVDです。あの4人の「世界をとってやろう」みたいな野心を見ていると、こっちの心もギラギラしてきます。俺もなんかやってやろうというモチベーションがすごく上がるんです。
―たとえば、他の方が書かれた脚本でも、やってみたいと思いますか?
石井:そうですね。脚本を書くよりも、監督をする方が好きなので。パソコンから出てるウィーンていう音を聞きながら脚本を書くよりは、外でみんなとワイワイと肉体労働するほうが好きですね。
―監督に専念したいということは、全然毛色の違った映画も撮りたいということですか?

石井:そうですね。たとえば何も考えずにふらっとキルギスに行ってみて、役者さんも現地の人を使って、そこに着いてから全部決めて撮る。で、撮り終わったら次の土地に行く、というような撮影にも憧れます。文化や歴史が異なる場所でも、共通する普遍的なものがあって、それを外に出ていくことでさらに深く理解できるのではないかという淡い期待があるんです。あとは全然違いますけどテレビもやりたいですし、アイドルのイメージビデオとかもやりたいですね。文芸大作もやりたいし。
―今後の予定などは決まってるんですか?
石井:今年の夏と来年の春と、二つの映画の撮影があります。映画以外ではチャベス・シネマという団体を作りました。いま10人くらい所属してるんですけど、俳優が多いですね。内堀くんとかを筆頭に、みんな本当にすごい才能なので彼らを売り込みたいと思っています。プロダクション化したいんです。
―次回作はどういった作品になるんですか?
石井:何て言うんでしょうか…、21世紀になって男がダメなことはもう立証されちゃったじゃないですか。でも、ダメだけど、いまだに男の道っていうのがあると思うんですよ。新時代の男の道というか、新しい時代の男とは何ぞや、というのがテーマになった作品です。男の「新しいロマン」っていうのを探ってみたいんです。
―今後、石井監督がどのような作品を創っていかれるのか、とても楽しみです。
石井:ありがとうございます。頑張ります。
- イベント情報
-
-
『剥き出しにっぽん』
2008年5月31日(土)~6月6日(金)『ばけもの模様』
2008年6月7日(土)~6月20日(金)料金:特別鑑賞券1,200円 当日1,500円
※初日、公開中の監督、出演者、ゲストによる舞台挨拶あり。
-
- プロフィール
-
- 石井裕也 (いしい ゆうや)
-
1983年生まれ。大阪芸術大学の卒業制作として『剥き出しにっぽん』(91分/16ミリ/2005)を監督。この作品で、第29回ぴあフィルムフェスティバル「PFFアワード2007」グランプリ&音楽賞(TOKYO FM賞)受賞。以降も長編映画『反逆次郎の恋』(89分/DV/2006)、『ガール・スパークス』(94分/DV/2007)、『ばけもの模様』(93分/HD/2007)などを制作。第37回ロッテルダム国際映画祭および第32回香港国際映画祭にて、上記の長編映画全4作品が特集上映された。さらに同年、香港で開催されたアジア・フィルム・アワードにて、アジアで最も期待される若手映画監督に送られる第1回エドワード・ヤン記念アジア新人監督大賞を受賞。現在、最も活躍が期待される若手映画作家である。
- フィードバック 0
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-