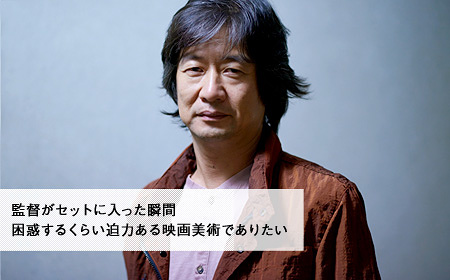世界各国の映画監督から熱いオファーを受けて、縦横無尽に活躍する映画美術監督・種田陽平。日本を代表する映画人の1人でありつつ、2011年の展覧会『借りぐらしのアリエッティ×種田陽平展』ではスタジオジブリアニメとのコラボレーションで実物のセットを製作し、展示するなど、映画美術界において独自の「作家性」が際立つ異色の存在でもある。
そんな彼が三谷幸喜監督と組んだ最新作『清須会議』の公開に先駆け、東京・上野の森美術館にて開催されているのが『種田陽平による三谷幸喜映画の世界観展』だ。今回のインタビューでは、展示内容だけでなく、映画美術やそこにかける想いについて、幅広くお話を伺った。
『キル・ビル Vol.1』で、ハードな作品をやるモードに入っていたので、三谷さんの映画美術をやることになるとは思ってなかったんです(笑)。
―まず今回の展覧会の大まかな内容について教えてください。
種田:三谷さんとは、『THE 有頂天ホテル』(2006年)、『ザ・マジックアワー』(2008年)、『ステキな金縛り』(2011年)、そして間もなく公開の『清須会議』と、4本の映画を一緒に作ってきたので、その映画美術の総括をするって感じですね。
―巨大なセットはどのように展示されるんですか?
種田:僕は、どの映画でも必ずセットのために模型を作るんですよ。「映画美術は建築だ」っていうコンセプトで、『THE 有頂天ホテル』ならホテル、『ザ・マジックアワー』なら港町、『ステキな金縛り』では法廷、『清須会議』ではお城の巨大セットを建てたんですけど、その製作のために作った実際の模型を展示します。こういうのって撮影が終わると大抵壊しちゃうんですけど、結構残していた。あとはイメージ画や、撮影に使われた小道具・装飾などです。

『ステキな金縛り』 ©2011フジテレビ 東宝
―『THE 有頂天ホテル』から種田さんが美術として入られたことによって、三谷さんの映画は以前とまったく表現の形が変わりましたよね。それまでの『ラヂオの時間』(1997年)、『みんなのいえ』(2001年)は「脚本の映画」だったと思います。でも『THE 有頂天ホテル』からは「空間性」が凄く重要になっています。
種田:三谷さんの映画って、たくさんの役者さんが出演しますよね。そしていろんな場所で、いろんなことが起きる。それを演出するうえで、空間の広がりはそもそも大事なんですね。僕が美術として入って、その要素を強調したことは確かだと思います。
―最近はセット作りのために、模型ではなくてCGを作る監督もいらっしゃるそうですね。
種田:なぜ今回セット模型を展示しているかっていうと、三谷さんがその模型を使って演出のシミュレーションをされているからなんです。CGシミュレーションだと、映像を重視する監督にはいいんだけども、役者をどう動かすかということに重点を置くタイプの監督にはあまり向かないと思う。模型だと演出と役者のアンサンブルを考えるには、凄くいいみたいです。
―そもそも『THE 有頂天ホテル』では、三谷さんの映画に種田さんが入られること自体が意外だったんですが、どういうきっかけがあったんですか?
種田:僕も自分が三谷さんの映画美術をやるようになるとは思わなかったです(笑)。特に『キル・ビル Vol.1』(2002年 / 監督:クエンティン・タランティーノ)をやったあとだったし、アクションとかハードな作品をやるモードに自分も入っていたから。
―ええ。
種田:実は三谷さんの作品って、前作までは興行的に意外と伸びてなかったらしいんですね。だから『THE 有頂天ホテル』では、プロデューサーたちがもっとメジャーなエンターテイメントとして、お客さんがたくさん駆けつけるような映画にしたいという気持ちが強かったみたいで。美術だけじゃなく、撮影、照明などスタッフも替えて取り組みたいと言われました。三谷さんとプロデューサーから依頼を受けたとき、僕は「ロビーやラウンジ、エントランスなどはホテルの顔なので、もしどこかのホテルを借りて、看板をつけ替えてやるだけのようなものだったら、申し訳ないけど僕は乗れないです。ただ、それらを全部セットで作れるのなら是非やらせてください」って言ったんです。

『THE有頂天ホテル』 ©2006フジテレビ 東宝
―その結果、『THE 有頂天ホテル』は大作的な凄みもありましたし、興収は60億円を超えたんですよね。
種田:僕の提案でお金を使わせてしまったので、大ヒットしてホッとしました(笑)。
『ザ・マジックアワー』の舞台美術は、セットをトライアングルに配置することで、奥行き感を作り出せました。
―三谷さんの映画では『ザ・マジックアワー』が大好きなんですよ。『THE 有頂天ホテル』の次に公開された、ほとんど実験作に近い変な映画。舞台の港町がめちゃくちゃデフォルメされていて、凄くシュールな無国籍空間じゃないですか。
種田:あれは本当に難しかったんです。もともと三谷さんは『ワン・フロム・ザ・ハート』(1982年 / 監督:フランシス・フォード・コッポラ)の世界観をイメージされていた。セットだけで作られた街を舞台に、映画制作の舞台裏の話をやりたいと。でもプロデューサーいわく、『ワン・フロム・ザ・ハート』はアメリカでも大コケしたと(笑)。そのままやるとマニア向けの映画になっちゃうから、どうすればより多くの人に受ける娯楽映画として成立させられるか? と相談を受けたんです。

『ザ・マジックアワー』 ©2008フジテレビ 東宝
―コッポラはあの作品で巨額の借金を抱え、自分のゾーイトロープ・ロス・スタジオを売却しちゃいましたからね(笑)。
種田:『ワン・フロム・ザ・ハート』の場合は、本当に書き割りのような作り物の世界ですよね。だから『ザ・マジックアワー』では、ちゃんとお客さんが映画の世界観の中に入りこめないとダメだなと。例えば『ツイン・ピークス』(1990年〜1992年 / 監督:デイヴィッド・リンチほか)みたいに、観客が不思議な世界へ入っていくための回路を設置する。そこが難しかった。
―具体的にはどんな工夫をされたんですか?
種田:パラダイス通りのセットですが、主人公の村田が宿泊する「港ホテル」をY字に開いた道の要に配し、そのホテルに向かって立って右に町を牛耳るボス・天塩幸之助の事務所「天塩商会」を、左に天塩の部下・備後が支配人を務めるクラブ「赤い靴」のエントランスと屋上テラスを置きました。港ホテル、天塩商会、そしてクラブ赤い靴をトライアングルに配置したわけです。そうすることでセット同士が正対しないので、パース感が出て、広がりと奥行き感を出せた。作られた奥行き感、それがこの映画のセットの特徴です。
寺山修司映画の現場の雰囲気が凄く面白くて、泊まり込みながら背景の絵を描き続けていました。
―面白いやり方ですね。ところで、「映画美術」というものをもう少し詳しくお伺いしたいのですが、種田さんってもともとは武蔵野美術大学油絵専攻ご出身だったんですよね。画家志望だったんですか?
種田:ええ。でも大学で誘われて、映画研究会に入っちゃったんですよね。僕は中学・高校時代から、都内の名画座に通いまくっていた。それで大学に入ったときに、僕のことを「池袋の文芸坐で見た」とか。「三鷹オスカーで見た」とか、いろんな目撃情報が映研内で飛び交っていたみたいで(笑)。
―有望な新入生がいると(笑)。
種田:またその頃は、日本映画も変革の気運があった時代だったんですね。1970年代末期ですけど、例えば石井聰亙(現・岳龍)監督のような異端の才能が学生映画界から出てきていたり。それで映研にいたときに、「寺山修司の映画の背景の絵を描く人、誰かいない?」って、画家の合田佐和子さんが捜していて、『上海異人娼館 チャイナ・ドール』(1981年)の現場に僕を含め数人で描きに行ったんです。日本に作った上海のセットの中で数か国語が飛び交う現場で、その雰囲気や体験が凄く面白かったんですね。続けて寺山さんの遺作になった『さらば箱舟』(1982年 / 公開は1984年)にも参加して、また泊まり込んで絵を描きました。
―じゃあ、そのまま映画美術の世界に入って行かれた?
種田:美大を卒業してからは、しばらく悶々としてた。油絵科だったので美術教師になるっていう道もあって、教員免許も持ってたんです。中学・高校の教員試験にも合格して、親はてっきり先生になるもんだと思ってたみたい(笑)。でも寺山さんの現場で知り合った人たちから、また映画の話が来たんですよ。「ちょっと美術の仕事を手伝ってくれよ」って。その1本は、崔洋一監督のデビュー作『十階のモスキート』(1983年)。あと1本、村上龍さんがピーター・フォンダ主演で撮った『だいじょうぶマイ・フレンド』(1983年)。それでもう教師の道は忘れちゃった(笑)。そうやって映画業界の中にいたら、若い監督たちとも当然知り合うんですね。
―じゃあ出会いの中で仕事が自然に連鎖していった感じですか。
種田:そう、ただ流されて(笑)。それで周防正行さんから「ピンク映画で小津安二郎をやろうよ」って誘われて、『変態家族 兄貴の嫁さん』(1984年)の美術を人件費込みの25万円で任されることになったんです。これは頑張りました。その頃、同時にいろんな映画の美術助手をやってたんですね。今だから言えるけど、並行して参加していた『湯殿山麓呪い村』(1984年 / 監督:池田敏春)のセットの椅子やテーブルを周防さんのピンク映画の現場に運んで使っていたんです。ピンク映画だから撮影は1週間で終わるじゃないですか。それでまた『湯殿山麓』の現場にセットを返して(笑)。もちろん許可はもらってましたけど。
―あの2本は美術でつながってたんだ!(笑) でも絵画から映画美術へって飛躍が凄くないですか?
種田:他にそういう人間はあまりいないでしょうね。この業界はだいたいデザイン系か建築系から来るんで。だから僕は仕事をやりながら、自分なりの方法論をつかんでいきました。でも、面白かった時代ですよ。石井聰亙(岳龍)監督とやった『半分人間/アインシュテュルツェンデ・ノイバウテン』(1986年)は、相米慎二さんの『雪の断章』(1986年)の美術助手の仕事と並行してやりました。普段は商業映画で美術助手の仕事をやって、その合間に、若手同士の作品で美術監督をするっていうノリだったんです。
『スワロウテイル』は、ほとんど命がけでやりきりました。あれ以前と以後で僕の仕事もハッキリ変わりましたね。
―僕が種田さんのお名前を意識したのは、やはり『スワロウテイル』(1996年 / 監督:岩井俊二)なんですよ。あの作品は今につながる「美術が主張する」ってことをハッキリやられていますよね。
種田:美術助手をやっていた頃から10年経っていますからね。僕は28歳のときに一般映画の美術でデビューしたんですけど、商業映画をやることに行き詰まり感を覚えてしまったんです。要は周防さんや石井さんと一緒にやってきたことが、商業映画ではあまり活かせなかった。だから一度映画の美術の仕事を辞めたんですよ。「映画は当分やんないから」って公言して。
―その間、何してたんですか?
種田:生け花と海外旅行(笑)。その期間が終わってからは、自分で美術の会社を作ったんですね。でも「映画はやらない」と。その代わり、いまミュージックビデオが面白いから、MVとCMの仕事をやりますって。『スワロウテイル』をやるまでの5年間は寝る間もなくMVとCMの仕事をしていた。
―その仕事の流れで岩井俊二さんとも知り合われたんですか?
種田:ええ。ある日、「プロモーションビデオの監督の岩井さん」と出会った。最初に組んだのは“想い出の九十九里浜”(1991年)でブレイクしたMi-KeのMVでした。そのとき、岩井さんが「いつか映画を撮りたいんですよ」って言ってたんですね。「じゃあ映画を撮るときになったら呼んでくださいよ」って答えて。だから、それが実現した『スワロウテイル』は、もう確信犯的にやりきりました。時間をかけて集中して、ほとんど命がけ。あれ以前と以後で僕の仕事もハッキリ変わりましたね。
―あの作品で徹底的にやろうと思ったことを言葉にすると何ですか?
種田:「日本発アジア映画」かな。
―同時代的に見ていても、ウォン・カーウァイらの作品とリンクする作風でしたよね。それは確かに岩井さんと種田さんのコラボレーションによって「アジア性」が濃厚に出たからだと思います。
種田:あの作品は大変だったんです(笑)。岩井さん自身は「和」の部分が結構ある人なので、実はアジアの混沌感が生理的に苦手な方だと思うんですよ。最初はアジアで撮ろうということになり、僕がロケハンに行って、マレーシアから帰国したら41.5度の高熱で入院して死にかけたり。そうやって何か月も苦労したあげく、岩井さんが「やっぱり日本で撮りたい」って言い出して(笑)。それで結局日本に帰って、2か月後にクランクインっていう怒涛のスケジュールでした。
―でも結果的に、種田さんがロケハンされて得たアジアの風景のイメージを日本で再現するという作業で、凄くオリジナルな美術になりましたよね。
種田:その通りです、逆に良かった。むしろ香港や中国、台湾の人たちが、この映画にびっくりしたんですね。「あんな場所、昔は確かにあったけど、今はどこにもないよ」って。
―そこから種田さんは、『不夜城』(1998年 / 監督:リー・チーガイ)や『キル・ビル Vol.1』、そして『セディック・バレ』(2010年 / 監督:ウェイ・ダーション)など、どんどんアジア性を延長されていきましたよね。
種田:ただ僕はアジアを含む海外の映画だけでなく、同時に日本映画もいっぱいやっていますから。その中で三谷さんとの出会いもあったし。だから「どこでやってるか」は関係ないんですよね。あくまで作品ありき、なので。

『セデック・バレ』第一部 太陽旗/第二部 虹の橋 © Copyright 2011 Central Motion Picture Corporation& ARS Film Production ALL RIGHTS RESERVED
―むしろ「異邦人」ですか。
種田:いつも旅の途中で、あっち行ったりこっち行ったりしているのが好きなんです。「場所を探しつつ、世界観を作りつつ」っていう両輪でやるのが好きなんですよ。本来、映画美術は結構ドメスティックな仕事なんですけどね。だから僕みたいなのは少ない。旅をする感覚だと、美術の世界観を作るときに毎回違うものができるんです。同じ場所で、同じスタッフで作り続けることは、自分にとって退屈なんだと思います。
美術は「出演者」だと思う。つまり被写体だから「撮る側」と迎合してちゃダメなんです。映される側として挑戦しなくちゃいけない。
―なるほど。ところで今展覧会のコピーに「役者と共演する映画美術」とありますけど、同じ意味のことを、種田さんはかなり以前からインタビューなどでおっしゃってますよね。
種田:スタッフとして美術をやっていると、つい監督や撮影、照明という「撮る側」の話に付き合っちゃうわけですよ。でも美術は「撮る側」じゃなくて「出演者」だと思うんですね、被写体だから。つまり「撮る側」と迎合してちゃダメなんです。俳優が凄くいい芝居をしたとき、監督もカメラも「どう撮ったらいいかわかんない!」くらいの迫力が出るでしょう。それと同じで、美術も映される側として挑戦しなくちゃいけない。それを怠っていると、どんどんブルーバックばっかりになっていったりとかね。
―現状はハリウッドを中心にどんどんCG、VFXが伸びてますよね。それに対抗する意識もある?
種田:対抗しようとは思っていない。CGやVFXで描ける世界も広がっていることは確かだから。けれど、そこについても、この先、もう一歩意識を進めていかなくちゃいけないと思っているんです。つまりCG隆盛の中で、いかに人の手のかかった美術が生きていくのかというテーマ。もう1つのテーマは、20世紀の映画空間に対する、21世紀的な解釈ってことですね。そこを開拓しないと新しいルックは出てこないと考えている。ロケでもない、CGでもない、映画的空間の21世紀バージョンっていうものが、まだなかなか実現できていないと思いますね。
―なにか良いアイデアはありそうですか?
種田:常にそこを模索しながら作っているし、安易にまとめようとは思っていません。その中でCGチームが震え上がるようなリアルセットや、ドキュメンタリーの人たちが凄いと思えるような美術で映画のための世界を作りたい。それがいろんな国を越えて映画が伝わっていく力になると思っています。世界的に見ると、決してハリウッドと日本だけが映画を作ってるわけではないんですよね。中国でも、インドでも、エジプトでもどこでも、たくさん映画が作られている。あとヨーロッパには映画と演劇の歴史がしっかりありますからね。

『清須会議』 ©2013フジテレビ 東宝
―種田さんって、映画以外にもたくさん仕事されているじゃないですか。舞台美術、空間デザイン、アートブックなど……。これはなぜなんですか?
種田:「映画一筋」みたいな職人性は、いまひとつ自分の中にないんですよ。簡単に言うと、挑戦が好きなんです。新しい分野に挑戦すると、何か自分のやることが客観的に見えて、終わったときに満足感が凄くあるんですよね。だからジャンルを越え、国を越え、「越境」するたびに、とりあえずやる気が湧くんですね。
―「越境」はまさに種田さんのキーワードですね。最初も油絵から越境してますし(笑)。
種田:それでずっと来たから、このスタイルはもう変えられないんでしょうね。きっと生涯、「越境人生」です(笑)。思えば三谷さんの映画って意外に欧米に意識されていない。アジアでの人気は凄く高いんけど。でも『清須会議』はそこが広まる気がする。時代劇ってこともあって、欧米にも「越境」する可能性があると思いますよ。まずは日本で大勢のお客さんに観てもらって、それからでしょうけど。期待しているんです。
- イベント情報
-
- 『種田陽平による三谷幸喜映画の世界観展〜「清須会議」までの映画美術の軌跡、そして…〜』
-
2013年10月12日(土)〜11月17日(日)
会場:東京都 上野の森美術館
時間:10:00〜17:00(土曜、11月3日(日・祝)、11月15日(金)は20:00まで、入場は閉館の30分前まで)
料金:一般1,300円 大学・高校生1,000円 中・小学生500円
※未就学児入場無料
- プロフィール
-
- 種田陽平(たねだ ようへい)
-
三谷幸喜監督の映画『THE有頂天ホテル』『ザ・マジックアワー』『ステキな金縛り』『清須会議』、舞台『ベッジ・パードン』の美術監督をつとめる。『フラガール』『悪人』『空気人形』『ヴィヨンの妻』などの日本映画の他、クエンティン・タランティーノ、チャン・イーモウ、キアヌ・リーブスら海外の監督作品も手がけ、2010年芸術選奨文部大臣賞、2011年に紫綬褒章を受けている。
- フィードバック 4
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-