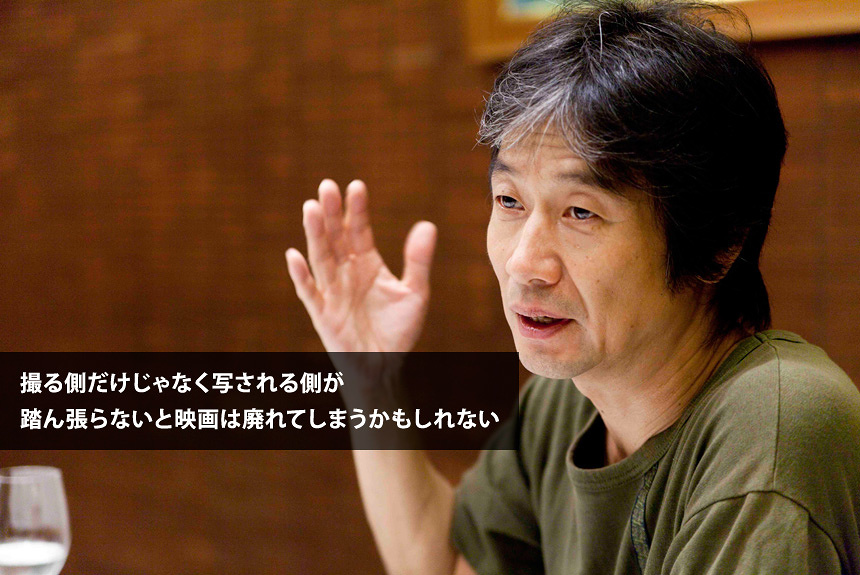サイレントからトーキー、モノクロからカラー、西部劇から文芸作品まで、半世紀以上にわたってさまざまなジャンルの作品を撮り続け、ハリウッドの黄金期を体現した、アメリカを代表する映画監督ジョン・フォード。彼の生誕120年を記念して、あらゆる西部劇の中の頂点ともいわれる『駅馬車』(1939年)と、自身のルーツであるアイルランドを舞台にした傑作ヒューマンラブストーリー『静かなる男』(1952年)の2本が、デジタルリマスターでスクリーンに甦る。黒澤明やジャン=リュック・ゴダールなど世界中の映画監督に影響を与え、すでに古典とされるジョン・フォードの映画を、2014年の現在、どのように見ることができるのか? 幼少の頃からその作品群に親しみ、日本を代表する美術監督として世界中で活躍する種田陽平に、ジョン・フォード映画の魅力を聞いた。
『駅馬車』って、子どもが見てもワクワクできるし、クライマックスのアクションシーンは、今見ても素晴らしいですよ。
―ジョン・フォード監督生誕120年を記念して、この度、代表作の中から『駅馬車』と『静かなる男』の2作がデジタルリマスターで公開されることになりました。ジョン・フォードは1973年没なので、すでに40年以上前に亡くなっているわけですが、まずは種田さんが最初にジョン・フォードの映画を見たときの話を聞かせていただけますか?
種田:僕の父親がジョン・フォードが好きだったんです。父親は昭和初期の生まれなんですけど、その世代はだいたい西部劇が好きなんですよね。だから、小学校の低学年の頃には、『駅馬車』はもちろん『荒野の決闘』(1946年)や『リバティ・バランスを射った男』(1962年)など、ジョン・フォードの西部劇の作品は何本もテレビのオンエアで家族で見てました。それで、73年には『駅馬車』がニュープリント(劇場でかけるフィルムを新しく作り直すこと)でリバイバル公開されるというちょっとした事件があって、父に連れられて映画館に見に行ったのを覚えています。

『駅馬車』 ©MCMXXXIX BY WALTER WANGER PRODUCTIONS, INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.
―種田さんが何歳ぐらいのときですか?
種田:中学1年生ぐらいだったと思います。まだ家庭で視聴できるビデオソフトもない時代だから、ニュープリントでリバイバル上映というのは貴重だったんですよ。それまでにテレビでは何度も『駅馬車』を見てたんだけど、そのとき初めて劇場で見て、とにかく大迫力! って映画の世界に引き込まれてしまいました。『駅馬車』って基本はアクション映画だから、子どもが見てもワクワクできるし、クライマックスのアクションシーンというのは、今見ても素晴らしいですよ。
―ジョン・フォードは様々な映画を撮っていますが、主に西部劇を見ていたんですか?
種田:子どもの頃は西部劇全体が好きだったので、『シェーン』(ジョージ・スティーヴンス監督 / 1953年)やハワード・ホークスの西部劇もよく見てました。ただ、周りの友達が『荒野の七人』(ジョン・スタージェス監督 / 1960年)やスティーヴ・マックイーンの西部劇にはまっているときに、僕はジョン・ウェイン(ジョン・フォード作品の看板俳優)がカッコイイと思ってたから、世代的に20~30年ズレてましたね(笑)。そういう子どもだったので、ジョン・フォードはやはり特別な監督だったと思います。
―では、今回リバイバルされるもう1本の『静かなる男』を見たのはもっと後になってからでしょうか?
種田:大学に入ってからですね。ちょうどその頃、映画評論家による「ジョン・フォード再発見」の動きがあって。当時は、アート系の映画監督のほうが娯楽映画の監督より偉いと考えられていた傾向があった。そこでその方たちが、ジョン・フォードやハワード・ホークス、ヒッチコックといったいわゆるハリウッドの娯楽映画の監督が、実はすごいシネアスト(映画作家)であり、真のアーティストだというふうに持ち上げて、彼らのポジションを上げたんです。
―そうやって、ジョン・フォードが再び脚光を浴びたんですね。
種田:ただ、僕はそれがある意味不幸なことだったんじゃないかと思っています。僕の中ではジョン・フォードって子どもでも楽しめるエンターテイメントの人だったのに、それをきっかけに映画を研究している人が必ず見なきゃいけない映画作家みたいな雰囲気になっちゃった。地位が上がったことは良かったんだけど、結果的には一般の若い世代を遠ざけてしまって、ジョン・フォードが普通に見られなくなってしまったんじゃないかな、とも思うんです。
かつての絵画のような質感の映像を安易に手放してしまっていいのか、これからの映画の作り手は真剣に考える必要があると思います。
―本来は、子どもでもワクワクするような、単純に楽しめる映画のはずなのに。
種田:だから今回のリバイバルも、若い人たちにはお勉強みたいな感じで見てほしくはないんですね。チラシには溝口(健二)や小津(安二郎)といったそうそうたる監督のコメント(1939年『駅馬車』公開当時の宣伝文の引用)が載っていますけど、彼らだって娯楽映画としてすごく良い作品だと言ってるんだと思う。それこそ黒澤明の傑作娯楽映画『七人の侍』と『椿三十郎』をニュープリントで楽しもうみたいな感覚で見るとすごくいいんじゃないかな。
―では、ジョン・フォードの映画を美術監督の目で見ると、どんな魅力がありますか?
種田:『駅馬車』にはあまり美術は出てこなくて、むしろモニュメント・バレーのロケーションが素晴らしいですよね。当時の西部劇の中でも、実際の西部で大ロケーションを敢行したのはこの作品が最初じゃないですか? それまではセットの中に背景画を描いてそれで良しとしたり、ハリウッドの近くで撮って済ませていたのが、この映画でクルーを引き連れて、砂漠の中に宿泊施設やオフィスを全部作って撮影を始めたのは、当時のハリウッドでもセンセーショナルなことだったようです。そうやって作った『駅馬車』が大ヒットしたことで、本格的なロケの西部劇が次々と作られていったんです。

『駅馬車』 ©MCMXXXIX BY WALTER WANGER PRODUCTIONS, INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.
―ロケ撮影のパイオニアだったんですね。ジョン・フォード監督は映像へのこだわりも強かったようですが、映像美についてはいかがでしょう?
種田:当時の人は、ジョン・フォードのモノクロを見て、夜のシーンなのに空が明るかったり、昼のシーンなのに空が暗いことに驚いたんです。それはどのシーンも昼間に撮影しているせいなんですけど、モノクロの中にグレートーンの階調があって、写真の美学が生きているんですよね。
―インタビューでも「白黒こそがフォトグラフ」という発言を残してますよね。
種田:映像のトーンには相当うるさかったみたいですね。それはカラーになっても同じで、『静かなる男』はカラーですが、発色が今の映画とは全然違いますよね。初期のフィルムは発色のコントロールが難しかったので、光を強く当てて撮影したり、補正したりいろんな工夫をすることで、映画の世界が本物らしく見えるように映像にも演出を加えていた。つまりそれは絵画的な美しさだったわけです。一方で最近のカラー映画というのは、解像度が良すぎるせいか、ほぼ実物の見た目通りに写るので、こういう油絵みたいな映画がなくなってきました。かつての絵画のような質感の映像を安易に手放してしまっていいのか、これからの映画の作り手は真剣に考える必要があると思います。

『静かなる男』 ©1952 MELANGE PICTURES LLC. ©2012 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHT RESERVED
当時の役者の輝きというのは、演出、美術、撮影など映画作りにおける仕事のすべてが機能し合って生まれた輝きであって、映画の黄金時代の総力の結果だったと思います。
―かつての映画の伝統を受け継ぐ必要があると。
種田:もちろん今でも残っている部分もあるんですけどね。例えばモノクロの表現は光と影で作るわけですけど、人の輪郭を光でふちどったりするんです。それは今のアメリカ映画にも継承されていて、カラーフィルムで撮られた『アメイジング・スパイダーマン2』(2014年)も同じような演出をしてます。
―種田さんがかつての絵画のような映画を今求めるのには、どういう理由があるのでしょうか?
種田:かつてのカラー表現における工夫の話にもつながりますけど、今の映画は、リアルな空間を解像度の高い映像でそのまま映すことが多くて、映画ならではのフォトジェニックな感じが出ないんです。『静かなる男』でジョン・ウェインがヒロインのモーリン・オハラの手を引いて村中を歩いていくシーンがありますけど、ああいうのは今の映画でやっても画としてはまらないし、力強く面白いシーンとして成立しないことのほうが多い。
―リアルな背景の中では、演技もリアルなものが求められると。
種田:僕がこんなことを言うのはちょっと恥ずかしいんですけど……ジョン・フォードの映画に特徴的なのは、ポエジーがあることだと思う。どの映画の中にも、胸がキュッと締め付けられるような詩的な瞬間があって、それがアクションの合間や後にポンと顔を出す。だからちょっとおとぎ話風で、現実離れしてるわけですよ。そこが、他の映画にはないすごさなんです。しかも、役者たちががその演出に見合うすごい肉体を持っていて。

『静かなる男』 ©1952 MELANGE PICTURES LLC. ©2012 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHT RESERVED
―と言うと?
種田:なんていうか、男優はもちろん女優も体が分厚く立体的です。つまり映画の中で存在感を放っている。さっき、ジョン・ウェインが好きだと言いましたが、彼の魅力というのは、黒澤明作品における三船敏郎と同じだと思うんです。三船さんは大根役者と言われた時期もあった。でも、演技の上手い下手ではなくて、三船さんにしかできないすごい演技と存在感があった。ジョン・ウェインも賞とは無縁でずっと演技が下手だと言われていたけど、やっぱり他に彼の代わりになる役者はいないんですよね。また、今の女優さんがどんなに頑張っても、モーリン・オハラやマリリン・モンローのように映画の中で存在できない。それは、今の役者さんのせいじゃなく、当時の役者の輝きというのは、演出、美術、撮影、など映画作りにおける仕事のすべてが機能し合って生まれた輝きであって、映画の黄金時代の総力の成果だったからだと思います。
素人でも、良いデジタル機材を使えばそれなりに面白く撮れるし、後処理でなんとかなる時代だから、やっぱり映画が勝負するところは「味」だと思うんですよね。
―種田さんは三谷幸喜監督とタッグを組んで多くの作品を手がけられていますが、三谷作品と同様に、ジョン・フォードの作品には集団劇の面白さがありますよね。
種田:脇役たちの描き方が魅力的ですよね。『駅馬車』の酔っ払いの医者なんかが、意外と物語の重要な歯車になって映画が展開していくのも面白いし、『静かなる男』も、脇役のおじさんやおばさん、エキストラの存在感がすごい(笑)。
―最後は村人全員出てきますからね。
種田:舞台とも違う、映画ならではの虚構の中にいる登場人物たちが生き生きしてる。僕が(クエンティン・)タランティーノを好きな理由のひとつは、アクの強い脇役が出てくるからなんですけど、今ああいう脇役は、アメリカ映画でもなかなか出てこないですよね。
―当時の日本の観客にとっては、ジョン・フォードの映画を通して「アメリカ的精神」みたいなものを見るところもあったと思うのですが、その辺りはいかがですか?
種田:黒澤明も小津安二郎もみんなアメリカ映画のファンで、脇役の描き方なんて特にアメリカ映画のようです。特にシリアスな状況におけるユーモラスなキャラクターの際立たせ方は、アメリカ映画に由来していていると思います。今の日本映画に一番欠けているのは、リアルすぎてしまって、ユーモアがないところかもしれません。監督を目指している人がジョン・フォードの映画を見ると、そこが一番勉強になるかもしれませんね。
―冒頭に、アート映画として再定義されてしまったことが、ジョン・フォードにとって不幸だったというお話がありましたが、種田さんのお仕事は、アート性の強い仕事を手がけつつ、大勢の人が見る映画であることが両立されているように感じます。娯楽であることと芸術であることのバランスをどのように考えられてるのでしょうか?
種田:僕の仕事は美術なので、監督やキャメラマンみたいにアート性の高い映像を作ろうというふうに映画を支配できるわけじゃないんですね。だから、その発想ではやってないんですよ。もちろん関わった映画が賞を獲ったり評価されるのは嬉しいけれども、やっぱり今の時代の美術の役割というのは、一般のお客さんにお金を払って映画館で映画を見に来てもらうに足る世界を見せられるかどうかが大事だと思っています。
―最近の著書『ジブリの世界を創る』の中では「『撮る』から『描く』へ」ということをおっしゃっていますが、デジタルの技術や機材の進化の一方で、美術に求められる役割も変わってきていますか?
種田:美術は写される側なので、機材が高品質になればなるほど味わいがなくなってしまうリスクがある。仮にすごく味わいのある美術を作ったとしても、高解像度のデジタルでバシッと写されると雰囲気が出ないから、そこがこれからの映画作りの課題だと思います。素人でも、良いデジタル機材を使えばそれなりに面白く撮れるし、後処理でなんとかなるから、やっぱり映画が勝負するところは「味」だと思うんですよね。どこまで役者の味を出せるか、あるいは美術や衣装の味を出せるのかっていうのは、日本の映画制作者はもうちょっとこだわったほうがいいと思いますよ。

『静かなる男』 ©1952 MELANGE PICTURES LLC. ©2012 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHT RESERVED
―それはジョン・フォードが活躍した時代の映画には確かにあったものですね。
種田:そうですね。やっぱりヒッチコックの映画でも、たとえハードな内容であっても、映像に味があって、女優が輝いていて、びっくりするくらい美しいシーンがあるわけじゃないですか。あれは、ただ撮ってるわけじゃなくて、生み出してるわけですから。そういうのを知ってる僕らの世代が、しっかり映画作りをしないといけないと思っています。昔は、映画の売りというのは、他の映像とは違うっていうことだったんです。
―今だとリアルな映像がいいと思いがちですけど、映画とは本来、そういうものじゃないと。
種田:僕らの世代にとって、映画館で映画を見るというのは贅沢な体験だったし、テレビとは違う非日常の体験だという概念があったんですよ。でも今は、映像技術としてリアルな表現を求めることと、その技術によって映画をリアルに撮ることが一緒になってしまってる。映画はもっと、映像と美術と役者で作りこんでいくという基本的なことをやらないといけないし、ただ映像を切り取るのは、もういい加減にしなければと思いますね。そういう映画は王道に対するアンチテーゼとして機能している分にはいいですが、今は手持ちカメラでドキュメンタリー風に撮るのも、ひとつのテクニックとして確立してしまったわけで、新しいことではないですよね。
―種田さんは、その点で葛藤されていらっしゃるわけですね。
種田:映画作りには、監督やプロデューサー、撮影、照明、録音……いろいろな方が関わるわけですけど、僕は、役者と美術だけは違う役割があると思っています。それは、カメラに写される側だということ。写されるからには、そこでひと芝居しなきゃいけないわけです。役者なら何か意図的にそこで演技をして観客の心をつかむ必要があるだろうし、同じように、美術も写される側である以上は、役者と一緒になって魅力的な演技をしなきゃいけない。

『駅馬車』 ©MCMXXXIX BY WALTER WANGER PRODUCTIONS, INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.
―美術が「演技」するとは、目から鱗の発想でした。
種田:これからの映画は技術も機材もどんどん進化していく。でも、たとえ3Dや4Dになっていったとしても、結局画面の中には、役者と美術が作った世界が写っています。だからこそ僕らは写る側として頑張らなきゃいけないと思うんですね。今、撮る技術、ポストプロダクションの技術ばかりがどんどん進化していってるけれど、役者と美術はそれに見合うぐらい頑張れているのか!? ということです。映画はそこが根本なんですよ。ジョン・フォードの映画でも、映画作りの総合力がすごいということは、役者も美術も僕らが真似できないくらい高いレベルにあったわけですから。
―CGで何でもできる時代だからこそ根本の部分を見直す必要があると。
種田:撮られる側が踏ん張らないと、映画は廃れてしまうと思うんですね。「あっ、そこは後処理でやっておきます」という感じになっちゃうと、どんどん衰えてしまう。そのうち役者の演技だって後から修正できるようになっちゃうかもしれない(笑)。やっぱり役者と美術はライブで頑張らないといけない。それを再認識するためにも、映画の作り手にとって今回のジョン・フォードのリバイバル上映は必見かと。もちろん、一般のお客さまに、アクション娯楽映画として楽しんでもらいたいですけど。
- イベント情報
-
- 『ジョン・フォード監督生誕120年!「駅馬車」「静かなる男」デジタルリマスター版上映』
-
2014年9月27日(土)から10月17日(金)までシネマート新宿、シネマート心斎橋にてロードショー、ほか全国順次公開
※シネマート心斎橋は10月10日(金)まで。『駅馬車』デジタルリマスター版
1939年 / モノクロ / 99分
監督:ジョン・フォード
出演:
ジョン・ウェイン
トーマス・ミッチェル
配給:マーメイドフィルム『静かなる男』デジタルリマスター版
1952年 / カラー / 129分
監督:ジョン・フォード、モーリン・オハラ
出演:ジョン・ウェイン
配給:マーメイドフィルム
- プロフィール
-
- 種田陽平(たねだ ようへい)
-
美術監督。武蔵野美術大学造形学部油絵学科卒業。岩井俊二、三谷幸喜など日本を代表する映画監督のみならず、クェンティン・タランティーノ、チャン・イーモウなど海外の監督からも絶大な信頼を得、数々のヒット作品を手がけている。日本映画の代表作として、『スワロウテイル』(岩井俊二監督、1996年)、『不夜城』(リー・チーガイ監督、1998年)、李相日監督の『フラガール』(2006年)、『悪人』(2009年)、『空気人形』(是枝裕和監督、2008年)など。最新作としてスタジオジブリのアニメーション『思い出のマーニー』(米林宏昌監督、2014年)が公開中。映画固有の世界観の創造に定評があり、CF、PV等の映像表現、インスタレーション、舞台・コンサート・イベントなど空間表現などジャンルや国境を越境し活動を続け、これらの成果により、2010年に芸術選奨文部科学大臣賞を、2011年には紫綬褒章を受賞。著書に、角川oneテーマ21『ジブリの世界を創る』がある。また、10月24日には映画美術監督たちとの対談をまとめたインタビュー集『伝説の映画美術監督たち×種田陽平』の刊行が予定されている。
- フィードバック 1
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-