「街おこし」のためのアートプロジェクトが各地に立ち上がり、社会問題にアーティストが進んで言及することが珍しくなくなった昨今。「アートと社会のつながり」というと聞こえはいいが、税金を投入したアートプロジェクトの乱立に比して、その内実が検証される機会は少ない。アートプロデューサー、相馬千秋が2014年に設立したNPO法人「芸術公社」は、この関係性のあり方をあらためて問うとともに、『東京オリンピック』に向けて、アートプロジェクトのオルタナティブなモデルをいくつも模索、展開してきた。
その「芸術公社」の新企画『レクチャーパフォーマンス・シリーズ』が2月より開催される。この機会に今回は、相馬に加え、アートの「社会」の扱い方に疑問を抱き、学者やアーティストが意見交換をする「社会の芸術フォーラム」を立ち上げた社会学者の北田暁大に、お互いのアートへの認識を語ってもらった。より多様な視点を社会に与えるために、アーティストやアート関係者に求められる態度とは何なのか。二人の話に耳を傾けてほしい。
「芸術と社会をつなぐ」という、フワッと語られがちな事柄を、もう一度、解像度を上げて見る必要がある。(相馬)
―国際舞台芸術祭『フェスティバル/トーキョー』(以下『F/T』)でディレクターをつとめられた相馬さんが、『F/T』を離れ、2014年に立ち上げたのが「芸術公社」です。その設立にはどんな背景があったのでしょうか?
相馬:『F/T』もそうですが、いま多くのアートイベントには、公的なお金が投入されています。その予算や開催数は、2020年の『東京オリンピック』まで、確実に増え続けるでしょう。では、本来的には個人に立脚するアートという営みを、公的資金を使って提示することにはどんな意味があるのか? そこでは当然、社会との軋轢が生まれる場合もあります。たとえば、ある現実に対して、単一的ではない複数の見方を複雑なまま提示できるのがアートなのに、社会の一番ヒリヒリした部分に触れた途端、規制が入ることは少なくない。その状況を変えるには、「芸術と社会をつなぐ」というフワッと語られがちな事柄を、もう一度解像度を上げて見る必要があると思ったんです。
―検証なきアートの過剰状態があるということですか?
相馬:ええ。いま各地で「地域おこし」に芸術文化が使われることが常態化しています。そのおかげでアーティストの発表機会が増え、アートの雇用が拡大すること自体は悪いことではありません。しかし実際には、同じようなアーティストやスタッフが、同じようなプロジェクトを各地で展開している面もあるのではないでしょうか。またその評価基準も「祝祭性」に偏っていて、動員数やメディア掲載数が中心になっている。別の指標や作品そのものの価値についての議論はあまりにもなされていない。こうした状況に対して、別のパラダイムを仕掛けていきたいというのが、芸術公社の根底にあります。
アートが社会の外側にある「特別なもの」のような発想自体をやめないと。(北田)
―一方、北田さんが共同代表をつとめる「社会の芸術フォーラム」は、同じ「アートと社会のつながり」という漠然とした問題を、社会学の立場から言葉にするための活動と言えますね。1つの問いに対して、2つのプロジェクトが別々の立場から動き出したのが興味深いです。
北田:千葉大学教授の神野真吾さん(芸術学)や、アート団体「CAMP」の井上文雄さんらと「社会の芸術フォーラム」の準備をしているときに「芸術公社」を知り、心強く感じました。われわれの動機としては、アートで語られる「社会」や「公共性」なる言葉が、社会学とはだいぶ違う文脈で使われていることへの違和感があったんです。たとえば、地域系アートイベントに参加するアーティストの「社会」への眼差しが単純だと、作品がその地域において提示される理由がわからくなるし、ときとして「問題」を生み出すこともある。そこで、アート側と社会科学側が互いの考え方を交差できる場として、フォーラムを立ち上げたんです。どっちが「上」という立場ではなく。
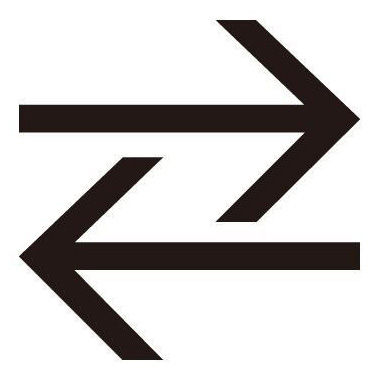
社会の芸術フォーラム メインロゴ
―「社会と芸術」ではなく「社会の芸術」フォーラムとしたのは?
北田:アートという実践、制度もひとつの社会だからです。アートが社会の外側にある「特別なもの」のような発想自体をやめないと。作品の意味を経済や法や科学に還元しないことは重要ですが、無縁ではないんですよね。その観点からすると、アートは他の社会領域との関わりに無防備な感じがする。
―社会からはみ出している「自由で特別なもの」がアートなんだ、という考えは、アート関係者にも少なからずあるような気がします。
北田:社会学者が地域研究をする際は、「地域は複雑で、容易な理解を許さない」という前提から入るんですが、一方、アートではある地域を単層的に捉え、そこにある経済や権力の構造に無頓着な場合が多いと感じます。これでは善意で介入しても、逆に、その地域の既存の権力構造に加担してしまうことにもなりかねない。
相馬:昨今の地域アートプロジェクトに感じるのは、地域のニーズに合わせるだけなら、コンサルタントや広告代理店が手がける「街おこしイベント」となにが違うのか? ということです。政治や経済、ジャーナリズムは、事前のアジェンダに沿って物事を進めるものだと思いますが、アートは着地点が見えない状態で進むもの、むしろその過程に価値を与えられる唯一と言っていい領域だと思います。実際、優れたアーティストほどリサーチや対話といった制作プロセスのなかで自分を疑い、自身や作品を変化させることができる存在だと感じます。その結果、たとえ地域のニーズを一時的には裏切ったとしても、もっと長いスパンで、未来に向けた問いを投げかけられるのがアートではないでしょうか。アーティストがインサイダーになってしまったら、批評性は生まれません。作り手がいかに対象と距離をとれるかが重要だと思います。
福島で作られた作品で未来に残るのは、ほんのわずかだと思っています。多くの作品は「行ったもん勝ち」「やったもん勝ち」で、根本的に社会をナメている。(北田)
―「アート」と「社会」というと、東日本大震災以降、福島の問題に限らず社会問題を扱う作品が増えた実感があります。
北田:ぼくは、2011年以降に福島で作られた作品で未来に残るのは、ほんのわずかだと思っています。端的に言えば、多くの作品は「行ったもん勝ち」「やったもん勝ち」で、根本的に社会をナメていると感じる。これは、上から目線で社会学がアートの良し悪しを判断しているのではなく、地域に入る際のまなざしの精度の問題です。たとえば沖縄の基地移設問題がある。あれを描くとき、反対派の人だけをフォローすればいいのか。実際には、移設に賛成している県民も多いし、その人々は別に「騙されている」のではなく、彼らなりの合理的な判断をしているわけです。
―問題の結論を先取りしてしまうと、その複雑性は見えてこないでしょうね。
北田:その当事者の合理性を、勝手に上から目線で裁断することはできません。言葉にできない立場に置かれている人たちも多い。アートがそうした社会の複雑さをさまざまな角度から見た上で作品を描いているのか、疑問があるんです。逆にきちんと細かにリサーチをして、そのなかで残っていく作品は、優れた社会学的研究にも通じるところがあると思う。たとえば藤井光さん(美術家、映像監督)の作品などはきわめて「社会学的」であると私は思いますし、友人の社会学者、岸政彦の社会の描き方は「アーティスティック」であると思います。複雑さをそのものとして描く意味での「ART=技術」ですね。
相馬:実際にいま、アートの世界ではリサーチに基づいた作品やプロジェクトがとても増えているんですね。ただ、アーティストは学者ではないので、確立されたリサーチのメソッドもないし、なにをどういう切り口でリサーチするか、人それぞれという状況です。そのことはどうご覧になっているのでしょうか? このリサーチは面白いと感じたものはありますか?
北田:ぼくもすべてを見ているわけではないですが、職業柄、対象に関する過去の言説の蓄積を踏まえたものか、問題を偽悪的に扱うだけの暴露型ジャーナリズムのようなものかは、すごく気になります。たとえば、各地の「ドヤ街」を舞台にしたアートプロジェクトがありますよね。そのなかでも、大阪の釜ヶ崎を舞台にした「特定非営利活動法人 こえとことばとこころの部屋(ココルーム)」の活動には、現地の人権センターの研究者とも協働した濃密なアプローチを感じましたが、横浜の黄金町で「NPO法人黄金町エリアマネジメントセンター」が行なっているものの一部には、全体として歴史をしっかり調べた形跡が希薄で、違和感がありました。
―というと?
北田:もちろん後者でも、相馬さんが演出家の高山明さんと実施されたツアーパフォーマンス『赤い靴クロニクル』などもあるわけで、全否定するのではありません。しかし黄金町という都市の固有の歴史性が全体的に消去されてしまっている、というか、消去の道具としてアートが使われているようにも思えました。
相馬:私が横浜の「急な坂スタジオ」のディレクターとして、黄金町の再生のための委員会に出席させていただいたのは、2007~2008年のことです。当時は現地の風俗街が一斉摘発されて間もない頃で、「ちょんの間」と呼ばれる3畳ほどの部屋にはまだ売春用の布団が残っていて、体臭も感じられる状態だった。街のイメージを改善したい住民の切実さを理解する一方、強制退去させられた人たちはどこへ行ってしまったんだろう、と。
―そこでやられた『赤い靴クロニクル』は、地域住民に街を案内してもらいながら、黄金町の複数の場所をツアーして回る作品でしたね。
相馬:さらに「ちょんの間」の部屋に架空の語学学校を設け、アジア各国から来たさまざまな背景を持つ女性と観客が直接対話をする、という演出が仕掛けられていました。性、言語、被植民など地域に凝縮していた問題を、複雑なまま受け手に問いかけるものだったと思います。その後、さまざまなアーティストが制作するなかで、壁紙や看板をアート風に替えたりして、場所の歴史を上書き、漂白するようなプロジェクトもあったかもしれません。ただ、黄金町の負の歴史を忘れたい地域住民には、こういうわかりやすさのほうが求められているという面もある。ここが本当に難しいところですね。
北田:昔の黄金町はとても治安が悪かったし、ジェントリフィケーション(再開発による街の高級化)を受け入れざるを得ない状況があったのはたしかです。ただそのとき、住民でもなく、性的搾取の被害者でも利害関係者でもないアーティストが、行政からお金をもらったからといって、どこまでできるのか、と。事実上強制的に連れて来られた女性も多い「ちょんの間」文化を、安易に肯定する昭和仕草に乗るわけにはいかないけれど、行政の上書きにも乗れない。社会学の研究はそこで「こんな状況、記憶がある」「住民の利害関係や資源の配分はこうなっている」と終わらざるをえないわけです。その複雑さをどうかたちにするのか。そこをアートに期待したい気持ちがあるんです。
相馬:アーティストは、都市や社会の課題を直接的に解決するため制作を行っているわけではないですが、政治やジャーナリズムなどでは語られない部分こそ語ることができる存在でもあるはず。「芸術公社」でも社会学との接触面を増やしつつ、アーティストと制作のなかで探っていきたいところですね。
違和感も軋轢も含めて、わかり合えない他者がいることをわかる。それがアートの得意とすることだと思っています。(相馬)
―まさにいま進行している最中ですが、2020年の『東京オリンピック』に向けてはさまざまな試みが立ち上がり、東京の街も大きく変わるでしょうね。
相馬:ハード面はともかく、ソフト面での展開が20世紀的な祝祭のモデルを単純になぞるものだと残念ですよね。利権の配分によって、オフィシャルな東京のイメージが上塗りされてしまっては本末転倒です。一方、文化的に異なる背景を持った在日外国人の数も、テロの脅威も増しているいま、アートが向き合うべき課題も変化しているはずです。しかし、いかに新たな方法や視点を獲得するかという議論は現時点では未成熟ですし、普通に従来のフェスティバルを拡大して盛り上げよう、という機運のほうが強い。
北田:日本では幸い、「キリスト教VSイスラム教」のような対立は薄い。「文明の対立」なんて本気で考えている研究者などいないし、そういう枠組みで日常世界を理解している人はそうは多くありません。しかし、近年イスラム教への偏見は強まっているし、他のアジア諸国に対する偏見は強い。そもそも入国管理局の受け入れ態勢のひどさもあって、移民賛成、反対以前に、他の国の人々を受け入れる器、制度が現在あるかというと、ないと思う。
―その実態の認識がないまま、不安だけが増している感はありますね。
北田:ドイツやフランスの状況を引き合いに出して、「移民が押し寄せてくるぞ」とマスコミが移民脅威論をあおっていますが、現状の受け入れ態勢や賃金制度では頭下げても来てもらえないと思いますよ。彼らはまず、中国を目指すでしょう。日本では中国人が大量にものを買っているだけで「爆買い」と騒いでいるレベルですから、このままでオリンピックに耐えられるはずがない。そんななか「啓蒙」活動ではない方法で、多文化共生社会へのコンセンサスをとっていく際に、行政や社会科学だけではなく、アートだからこそできることが少なからずあるわけです。言葉や背景が違う人々を、共同作業、共在の事実性を通じて出会わせることができるわけですから。
相馬:「芸術公社」では、「アートはあらたな公共の社会モデルを提示し得る」とうたっていますが、ある社会学者の先生に「理念は正しいが、実際にアートが社会を変えた例はあるのか?」と問われたことがあります。たとえば、植樹を行なったヨーゼフ・ボイス(1921-1986年、ドイツの現代美術家)の『7000本の樫の木』プロジェクトでさえ、社会を具体的に変えるものとは言えないでしょう。しかし私たちが提示したいのは、新しい関係性であり、新しいコミュニケーション方法なんです。普段は出会わない他者や、価値観を共有できない他者の存在を知る回路を、アートを通じて仕掛けたい。違和感や軋轢も含めて、少なくとも「わかり合えない他者がいる」ということがわかる。それがアートの得意とすることだと思っています。
「フェスティバル=祝祭」という20世紀型のモデルのままで観客数を増やすことは、マーケティングの課題ではあっても、アートの根本的な革命にはなり得ない。(相馬)
―芸術公社は、拠点となるスペースを持たないで活動されているそうですね。
相馬:ええ。「芸術公社」はNPOで、インディペンデントな存在ですが、日本語で「公社」というと少しドキッとしますよね(笑)。ただ、「公社」は中国語だと「コミューン(共同体)」の意味で、真逆のイメージです。さらに英語訳では「コモンズ」という言葉を当てている。つまり、独立した個々がゆるやかにつながっているイメージで、実際、複数のディレクターがプロジェクトごとにユニットを組むわれわれのあり方を指しています。「アーツ・コモンズ」として、複数のモデル事業を次々と展開したい。繰り返しますが、現在は「フェスティバル=祝祭」という20世紀型のモデルが、各地で縮小再生産されている状態です。そのモデルのままで観客数を増やすことは、マーケティングの課題ではあっても、アートの根本的な革命にはなり得ない。それに変わる別のモデルを考えるのが、私の次のチャレンジです。
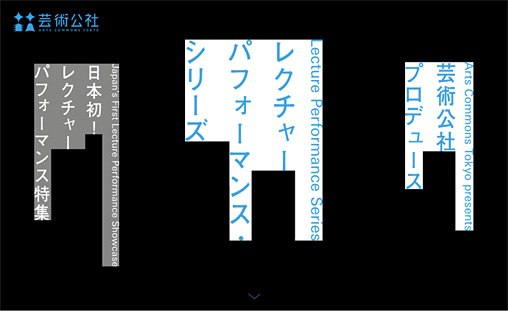
芸術公社プロデュース『レクチャーパフォーマンス・シリーズ』ビジュアル
―立ち上げから1年以上経ちましたが、いかがですか?
相馬:たとえば、東アジア4か国のアーティスト、キュレーターが対話する「r:ead(レジデンス・東アジア・ダイアローグ)」や、東北地方を周遊しながら開催する若手アーティスト育成ワークショップ「みちのくアート巡礼キャンプ」などもそうですが、小回りのきくプロジェクトは、他者の手によって勝手に発展していくんです。「r:ead」も最初は東京での開催でしたが、台湾や韓国の参加者が自国で行いたいと言ってくれて、それぞれの都市や文脈に合わせてローカライズしながら、私を招いてくれるようになった。今年は香港での開催準備が進んでいます。「みちのくアート巡礼キャンプ」も、参加者がワークショップの成果を発展させ、東北各地で実現しようと動きはじめている。私はこの展開がすごく面白いと思っているんです。場所を持たないと、「蓄積ができない」「求心性を持てない」と思われがちですが、むしろ「どこでも芸術公社」という広がりが生まれているんです。
「アート」と「学問」の大きな違いは、学問ではいい意味で、あまりオリジナリティーが必要とされないことです。(北田)
北田:「どこでも芸術公社」になっているというのは、重要なお話ですね。近代以降の「アート」と「学問」の大きな違いは、学問ではいい意味で、あまりオリジナリティーが必要とされないことです。日本ではなぜか『ノーベル賞』がオリンピックの金メダルのように語られますが、実際には、先行研究の蓄積の上に一石を積み重ねる能力が問われているわけです。文理を問わず、「スター」が引っ張るのではなく、「コモンズ=共同研究」を行って、蓄積の上の一石を、という状況になっている。

芸術公社プロデュース『レクチャーパフォーマンス・シリーズ』ビジュアル
―ただ一般的には、天才神話や、天才待望論は常にありますね。
北田:結果的に、そのなかに否定しようのない「天才」がいることもある、というだけのことです。まあ、どの分野にも「これは私のモデルだ!」と声高に言う人がいますが、そんな人は早くどっかに行ってほしい(笑)。アートもそうした方向性に変わったほうが、個々は小さなプロジェクトでも、総体的に大きなプロジェクトとしての広がりを持てるのではないか。『東京オリンピック』後の文化予算の縮小は目に見えているわけで、いまが「スター」になるための競争ではなく、持続可能な広がり、アートワールドの連帯を作るチャンスでしょう。ラストチャンスかもしれない。
相馬:そうですね。『東京オリンピック』に向けてもうひとつ考えているのは、東京とあらためて向き合いたいということです。普段とは違う目線で都市を見るフレームを設定し、見えない都市のレイヤーを浮かび上がらせることで、都市の祝祭を演劇的に読み替えたい。たとえば先述の高山明さんはいま、アジア各地の高校生が修学旅行で東京のどういう場所を訪れるのか、リサーチをはじめている。どうやらわれわれには想像もできない場所を回るらしく、韓国とシンガポールでも違うらしい。そうした独自のリサーチの成果を活用することで、東京の見方をズラせるのではないか。デベロッパー的な大規模な更新には対抗できないけれど、裏をかくような視点は提供できるはずです。

芸術公社プロデュース『レクチャーパフォーマンス・シリーズ』ビジュアル
北田:それは面白い。昨年末、山手線の各駅のイメージを調べたというニュースがあったのですが、ぼくがわりと近くに住む「鶯谷駅」が最下位だったんです。でも、たとえば根岸は文化的な街としてよく肯定的に紹介されますが、根岸と鶯谷は同じ街だろ、と(笑)。なんでわざわざ境界を作るのかと感じますが、路線図やメディア、行政区割によって与えられた都市のイメージを、ぼくらはなかなか崩せないんですね。だから「この街を盛り上げよう」ではなく、そうした既存の区分を解体する視点が作れると面白いですよね。
アートも学問も、いかに社会に資源として使ってもらうか、いい加減に本気で考えないと、つぶされても文句が言えない状況だと思っています。(北田)
―個人のなかに新しい社会の見方をインストールしていくモデルをたくさん展開されていることがわかりました。芸術公社が2月に開催する『レクチャーパフォーマンス・シリーズ』も、作品を見せるだけでなく、アーティストが語りも含めたパフォーマンスを行うということですが?
相馬:アーティストを神格化する必要はありませんが、私のなかではやはり特殊な能力を持った人たちです。付き合ったらこんなに面倒な人たちはいないのですが(笑)、だからこそ誰も考えられない発想や、驚くべき解像度で現実を見ることができる。他方、いま多くの地域系アートプロジェクトやグループ展では、個々のアーティストに十分光が当たっていないように感じます。彼らがどんな社会に生き、独自の方法論を生み出してきたかという理解なしに、作品が地域や展覧会の文脈だけに回収されていくのはつまらない。こうした認識から、アーティスト自身の問題意識や方法論がクリアに通じる形式として「レクチャーパフォーマンス」を特集しようと思いました。
―いわゆるベタなアーティストトークではない?
相馬:まったく違います。むしろ、「レクチャー的な要素を含む、映像と語りを織り交ぜたパフォーマンス」と思っていただければ。第1回のパフォーマーは、コロンビアの「マパ・テアトロ」という劇団を主宰する、ロルフ・アブデルハルデンです。多くの人がパッと地図で指差せないようなコロンビアという国で、インディペンデントな劇場を作り、麻薬や暴力が横行する社会と向き合う活動を長年実践しているアーティストです。世界の演劇界ではとても知られた存在ですが、日本は初登場になります。
―さらに第2回のパフォーマーは、台湾のチェン・ジエレンですね。
相馬:彼はアート好きなら知らない人はいない映像作家ですけど、台湾が厳戒態勢にあった時代には、ゲリラパフォーマンスをやっていたそうです。かつて日本統治時代に設立されたハンセン病患者収容施設を巡る映像作品『残響世界』を発展させ、レクチャーパフォーマスとして上演してくれます。
北田:現代アートは理論によって担保されている部分が大きいので、論文や単なる説明ではない、おっしゃったような新しいインターフェイスが出てこないと厳しいと思う。昨年12月に民主党への政策提言を行うシンクタンクを立ち上げたんですが、社会科学の蓄積も、議員さんには「だからなに?」と言われる世界です。その意味で、アートと立たされている立場は似ている。わかってもらうには技術が必要で、統計をいじって学者同士で批判し合うのもいいけど、自分の持ち物をいかに社会に資源として使ってもらうか、いい加減に本気で考えないと、つぶされても文句が言えない状況だと思っています。
相馬:コンテンツのレベルを下げるような本末転倒な方法ではなく、いかにそうした裾野の拡大を行えるかが重要ですよね。相手に合わせるのではなく、つねにドアをオープンにしておくような試みをしないといけない。今日は小さなモデル事業の話をしましたが、本来はいろいろな試みがあるのがいいと思うんです。私自身、アジアの街でどんどん勝手にローカライズされ増殖していくようなモデルも進めたい一方で、やはりオリンピックに向けては、都市を舞台にした大胆な演劇的祝祭の読み替えをやりたいと思っています。
- イベント情報
-
- 芸術公社プロデュース『レクチャーパフォーマンス・シリーズ』
-
Vol.1 ロルフ・アブデルハルデン / マパ・テアトロ(コロンビア)
『廃墟の証言』
2016年2月4日(木)~2月6日(土)19:00開演(6日のみ17:00開演)
会場:東京都 芝浦 SHIBAURA HOUSE
料金:一般前売2,500円 当日3,000円 2演目セット券4,000円(枚数限定)Vol.2 チェン・ジエレン(台湾)
レクチャーパフォーマンス版『残響世界』
2016年2月16日(火)~2月18日(木)19:00開演
会場:東京都 芝浦 SHIBAURA HOUSE
料金:一般前売2,500円 当日3,000円 2演目セット券4,000円(枚数限定)※2公演とも、毎公演終演後にアーティストと観客の対話の場「コモンズトーク」を開催
- 関連企画
映像上映『残響世界』 -
2016年2月12日(金)~2月26日(金)
時間:11:00~、13:00~、15:00~、17:00~
会場:東京都 虎ノ門 台北駐日経済文化代表処台湾文化センター
料金:無料
- 社会の芸術フォーラム
『シンポジウム02|都市と祝祭』(仮) -
2016年3月13日(日)14:30~18:30(予定)
会場:東京都 本郷 東京大学本郷キャンパス 安田講堂
企画・コーディネート:相馬千秋
- プロフィール
-
- 北田暁大 (きただ あきひろ)
-
1971年生まれ。東京大学大学院情報学環教授。社会学、メディア論。博士(社会情報学)。広告や映画館などのメディア史分析、社会学的な行為理論、責任論などを軸として研究を進めてきたが、近年は、再度「社会(学)にとって社会調査とはなにか」という社会学の基礎的問題に、理論的・実証的両側面から取り組んでいる。『意味への抗い』『責任と正義』『増補・広告都市東京』『嗤う日本の「ナショナリズム」』など。
- 相馬千秋 (そうま ちあき)
-
アートプロデューサー。これまで、国際舞台芸術祭『フェスティバル/トーキョー』初代プログラム・ディレクター(『F/T09春』~『F/T13』)、横浜の舞台芸術創造拠点「急な坂スタジオ」初代ディレクター(2006-10年)、文化庁文化審議会文化政策部会委員(2012-15年)等を歴任。2014年仲間とともにNPO法人芸術公社を立ち上げ代表理事に就任。国内外で多数のプロジェクトのプロデュースやキュレーションを行うほか、アジア各地で審査員、理事、講師等を多数務める。早稲田大学、リヨン第二大学大学院卒。
- フィードバック 1
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-











