批評家の佐々木敦が主宰する音楽レーベルHEADZが、昨年発足20周年を迎えた。それを記念して、5月に開催されたイベント『HEADZ 20th Anniversary Party“HEADZ 2015-1995=20!!!”』の会場は、HEADZとは1年違いで今年20周年を迎えたTSUTAYA O-nest。HEADZとO-nestの関係性は深く、2000年代半ばまではHEADZが日本での普及に大きく貢献したポストロック / エレクトロニカ系の来日公演の会場として、00年代後半からは日本人アーティストのレコ発、さらには雑誌『エクス・ポ』の発行にあわせて開催されていたライブとトークのイベント『エクス・ポナイト』の会場として、これまで歩みを共にしてきている。その長い歴史はライブハウスという「場」の意味合いがいかに変化してきたかを表しているとも言えよう。
そこで今回は、佐々木にHEADZとO-nestの20年の歴史を振り返ってもらうと共に、インターネットの登場に伴う「現場性」の変容についての考察を語ってもらった。また後半では、かつて徳間ジャパンに在籍し、HEADZと共にシカゴ系のアーティストを盛り上げ、その後にHEADZの一員となった荻原孝文も参加。今のライブハウスシーンのリアルな現状から、今後のイベントに対する展望まで、話はさらに広がっていった。
90年代って「なんとかなるんじゃない?」って錯覚を起こさせた時代で、その大きな理由のひとつがインターネットだった。
―今回取材をするにあたって、HEADZのイベントページを見返してたんですけど、1990年代から頻繁にO-nestを使ってたのかと思いきや、2000年代に入ってからなんですよね。
佐々木:それはホントに鋭い指摘で、僕もHEADZの初期からネストを使ってたと思ってたら、違ったみたい(笑)。まあそうやって記憶違いをするくらい、ネストとは昔から深い関係だって気持ちがありますね。
―そもそもHEADZは、どういうキッカケでスタートしたんですか?
佐々木:HEADZは1995年の5月に作ったんですけど、雑誌の編集をしていた原雅明と、「家で仕事をしてると煮詰まるよね」っていうよくある話で事務所を探して、偶然渋谷でいい物件を見つけたところから始まっていて。つまり最初はただの仕事場のつもりだったんだけど、せっかく場所があるし、HEADZって名前も付けちゃったから、「なんかやった方がいいんじゃない?」ってなって(笑)。
―(笑)。それで洋楽のリリースなんかを始めたんですか?
佐々木:当時は荻原さんが徳間にいて、Tortoiseとかシカゴ系のリリースを徳間で始めるというときに、それに協力して日本盤のライナーを全部HEADZで書いたり、プロモーションにも協力したりと、だんだんHEADZとしての事業を増やしていったんです。
―その延長で、招聘もやろうと。
佐々木:90年代の半ばって、まだ洋楽が盛り上がってて、ポストロック含め、新しいものがどんどん出て来た時代だったから、自分たちでプロモーターみたいなこともできるんじゃないかと思ったんです。そのころはまだシカゴ系が日本に紹介され始めたばかりで、人気が出るかもわかんなかったから、大手プロモーターは呼ばないわけ。だったら、うちらがレコード会社と組んでそういうアーティストを招聘しようってことで、96年とか97年くらいから始めました。
―でも、最初のころはネストは使ってなくて、青山のCAYとかが多かったんですよね。
佐々木:最初は勢いがあってお客さんも入ったから、CAYの他にも(渋谷)クアトロとか、まだ歌舞伎町にあったころのリキッドルームとかでやってたんだけど、世紀の跨ぎ目くらいで早くも失速して(笑)、あんまりでかいところだとできなくなってきて。だから、正直最初は「ネストだと小さ過ぎる」ってイメージだったんだけど、後に『LIVE IN JAPAN』っていうCDになるFENNESZの公演(2003年2月)が、HEADZとしてネストを借りた最初でした。
―さきほどおっしゃられた通り、当時はまだ洋楽の勢いがあって、それこそ今では国内盤にならないような作品もたくさん出てましたよね。とはいえ、HEADZとしていきなり招聘をやるというのは、かなり苦労もあったのではないですか?
佐々木:僕はそれまで物書きしかやったことがなかったから、もちろんノウハウも何も持ってないし、普通はそこで「やれないよね」ってなると思う。だけど90年代って「なんとかなるんじゃない?」って錯覚を起こさせた時代で、その大きな理由のひとつがインターネットだったわけです。95年以降インターネットが急激に広がり始めて、原くんは当時そっち専門のライターもやってたから、僕も彼にいろいろ教えてもらって、海外の人と直接メールのやり取りができて、それで「招聘できるんじゃない?」って思って。
―それで、思い切ってやってみたと。
佐々木:僕は「やれるんじゃない?」って思うと、「ホントにやれるか試してみよう」って気持ちが強くなる。極端に言うと、失敗してもそんなにへこまないんです。成功とか失敗よりも、やりがいがあったかどうかの方が重要で、人が入ってもがっかりするときはがっかりしたし、その逆もあったり、当時はそういう気分でやってましたね。
ネストがなかったら、もっと早く招聘をやめてたと思う。
―FENNESZの公演で初めてネストを使ったのはどういった経緯だったんですか?
佐々木:ちょうどそのころ『Endless Summer』が出たばっかりで、僕はそれにすごくハマってたんです。そうしたら、北九州にある現代美術センターのCCAっていうところがFENNESZを呼ぶって知って、じゃあ、そのタイミングで東京でもライブをやってもらおうと思って。スケジュール的にも結構ギリギリで決まった話だったから、他に場所が見つからなくて、ネストになったっていう偶然もあったかもしれない。実際、そのライブは満員だったしね。
―それまで使ってた大きめの箱がそのときは使えなかったと。
佐々木:そうですね。あと、そもそもなんでCAYとかをよく使ってたのかって、従来のライブハウスとはイメージが違うじゃないですか? 僕はどこかでHEADZとしてのブランドイメージを気にしてたから、普通のライブハウスではやりたくないって気持ちがあったのかもしれない。
―他にも吉祥寺のSTAR PINE'S CAFEだったり、六本木のSUPER DELUXEだったり、たしかに「いわゆるライブハウス」とはちょっと違ったところでよくやられてましたね。
佐々木:そうそう。そういう意味で、ネストは選択肢のファーストオプションに入ってなかったんだと思う。でも、実際使ってみると、すごい使い心地がよかったんだよね。何でかって言うと、僕らはあえてライブハウスじゃない場所を選ぶことが多かったから、その分余計な苦労があったの。つまり、機材とかを毎回発注しなきゃいけなかったりね。でも、ネストでやると「もともとドラムあるじゃん」って、そんな普通のことに気付いたのが、21世紀に入ってからだったっていう(笑)。
―入口がおかしかったわけですね(笑)。先日CINRAでネストの店長の岸本さんにも取材させていただいたんですけど、当時から担当は岸本さんでしたか?
佐々木:そうですね。彼の飄々とした面白がり感が、僕らにとってはすごくやりやすかった。僕はあんまりグイグイ来る人が苦手で、かといって、全然何もない人とは仕事しにくいじゃないですか? 彼ぐらいのカジュアルな距離感の人って、ライブハウスの人としては結構珍しかったんですよね。
―岸本さんももともと洋楽が大好きな人で、ご自身で招聘もやられていたので、リンクする部分もあったんでしょうね。THE RED KRAYOLAの来日公演打ち上げで、ジョン・マッケンタイアとジム・オルークがネストのバーフロアで話し込んでるのを見て感動したって、先日の取材でおっしゃってました。
佐々木:そういう時代だったってことだよね。最初のTHE RED KRAYOLAの来日は90年代の前半で、それが僕にとってもジムとの出会いでした。そうやって、たまたまネストとHEADZの誕生が、1990年代のポストロック勢の盛り上がりと時代的にシンクロして、成熟してきた状態のなかで21世紀を迎えたんじゃないですかね。
―そのころはホントに数多くの来日公演を手掛けられてましたよね。TortoiseやMouse on Mars、Oval、ジム・オルーク、JOAN OF ARC、FENNESZ、カールステン・ニコライなどそうそうたるアーティストを呼びつつ、日本のアーティストと共演させていく。その流れで、洋楽ファンが国内の音楽に耳を傾ける機会にもなったと思います。
佐々木:ある時期までは、Thrill JockeyとかDrag City(どちらもシカゴのインディーレーベル)のバンドがコンスタントにアルバムを出してて、それに合わせて日本に呼ぶっていうのが常態化してたから、もう「やらないわけにはいかない」みたいな感じもあったかな。でも、ある時期からは新しい人を呼ぶというよりも、今まで呼んだ人たちをまた呼ぶって感じになっていって、そうするとだんだん集客も減ってきたり、CAYがしばらくライブをやらなくなったりして、ネスト一本になっていきましたね。逆に、ネストがなかったら、もっと早く招聘をやめてたと思う。

2004年8月にネストで行われたDavid Grubbs来日公演の模様(撮影:相田晴美)
―その一方でHEADZは、荻原さんも加わって、国内アーティストをリリースする音楽レーベルとしての色も強めていきましたね。
荻原:そうですね。海外アーティストの招聘が減っていくのとシームレスに、日本人アーティストの発売記念ライブの主催も増えて来て、□□□、豊田道倫、蓮沼執太、空間現代、Moe and ghostsなどのレコ発会場としても、ネストを使わせて頂きました。
ライブハウスとクラブを混ぜる実験の場としても、ネストはすごくいい場所だったんです。
―その後の『エクス・ポナイト』にもつながる話だと思うんですけど、ネストはバーフロアがラウンジ的に機能していて、あの場所の存在はとても大きいですよね。
佐々木:大きいよね。ひとつの場所で、同時多発的にいろんなことができるのってすごく重要。僕は単にライブを見せるだけじゃなく、他のものとミックスしたいと考えていて、メインのライブを見てる人もいれば、外でDJ聴いてる人もいるみたいにしたかったの。そういう意味でも、ネストのような二層構造はすごくよくて、その規模に見合ったフェスみたいな感覚のものができるんだよね。
―そういう意味では、フェス文化の浸透ともリンクする部分があるかもしれないですね。ライブを見るだけじゃなくて、そこで交流も生まれたり。
佐々木:フェスの前に、1990年代にはクラブが登場したじゃないですか? 家じゃないところで音楽を聴く選択肢として、それまではライブハウスかディスコだったのが、ディスコの代わりにクラブが急激に広がって、「クラブVSライブハウス」って対立項が出てきた。で、僕はある種のロックもある種のクラブミュージックも好きだから、「何でここって変な壁があるのかな?」っていうのがずっとあって、それを混ぜるような実験の場としても、ネストはすごくいい場所だったんです。バーフロアでDJがやって、ライブフロアでバンドがライブするっていう分け方ができたから。
―あの規模感で、ちゃんとフロアが分かれてる場所って他にはあんまりないですもんね。『エクス・ポナイト』に関しても、そういったイベントの延長線上にあったわけですか?
佐々木:僕はHEADZを作る前から『UNKNOWNMIX』っていうイベントをやっていて、それは音楽かけながらその解説をするっていう内容だったんです。だからライブとDJのミックスの次の可能性として、トークもあるんじゃないかなっていうのは考えていて、それが『エクス・ポナイト』につながっているんです。そもそも『エクス・ポ』は音楽専門誌ではなくて、音楽を一要素とするカルチャー誌というか、自分が面白いと思うものを全部入れた雑誌として2007年に作ったんだけど、そのイベント版を作ることは最初から考えてました。
―たしかに『エクス・ポナイト』は、舞台表現の人たちのライブもあれば、批評家、編集者、作家、学者などのトークもあったり、かなりクロスカルチャーなイベントでしたよね(過去に菊地成孔、宇川直宏、大友良英、ジム・オルーク、飴屋法水、岡田利規、本谷有希子、東浩紀、鈴木謙介、松江哲明、冨永昌敬などが出演)。実際にやってみての発見はありましたか?
佐々木:思ったよりも人が来たかな。正直そのころ僕がやってたイベントは「3勝5敗」くらいだったんだけど(笑)、『エクス・ポナイト』の2回目とか3回目はすごく人が入って、そこでまた意識が変わったかもしれない。「人の話を聞きたい人がいるんだ」っていうね。でも、『エクス・ポナイト』はいろいろ無理をしてたイベントで、1回目はありえない時間の押し方だったから、ホントにネストさんのホスピタリティー、寛容さに助けてもらいました。いろいろ迷惑をかけた(笑)。
―大変だったんですね(笑)。
佐々木:でも岸本くんって全然テンパった感じを出さないから、すごくありがたかったですね。ホントに岸本くんとネストっていう組み合わせがあったからこそ可能な、僕のわがままだったと思います(笑)。
「その場に居合わせる」っていうこと自体に価値があって、その感覚は00年代の終わりくらいに急激に生まれてきたと思う。
―00年代も後半になってブロードバンドが普及してくると、「現場の意義とは?」という議論も盛んに行われるようになりましたよね。
佐々木:インターネットは距離を無化するというかさ、そういうテクノロジーなわけだけど、それによって立ち上がってきたのは、むしろ「現場の意義」だった。トークとかもそうだけど、情報化されたら大して喜ばれないことでも、「その場に居合わせる」っていうこと自体に価値があって、その感覚は00年代の終わりくらいに急激に生まれてきたと思う。
―『エクス・ポナイト』も、その流れにハマっていたと言えそうですね。
佐々木:だから00年代終わりぐらいに、トークとかレクチャー的なものってすごく増えたんですよ。それで僕は渋谷の事務所の一室で「BRAINZ」っていう20人しか入れない授業をやってみたんだけど、要はそれも同じことで、そこに来る、しかも20人しか入れない、それを逆に売りにしたわけ。
―なるほど。「BRAINZ」もある意味特殊な体験の場でしたもんね。
佐々木:そういうことと、ライブハウスみたいな空間の意味合いの変化がパラレルに起きてて、それこそ今のネストの屋台骨を支えているであろうアイドルイベントも、一続きの考え方だよね。今のアイドルは映像とか音源だけじゃ成立しない、握手とかチェキとか、そのときその場での体験が重要で、やっぱりそれも「現場性」ってことだと思う。ネストは20年前はホントに普通のライブハウスだったわけじゃないですか? でも、だんだん単なるライブ以外もやるようになって、『エクス・ポナイト』みたいなのの入れ物にもなってくれて、今のアイドルのイベントは午前中でも人が来るわけだよね。
―すごい変化ですよね。
佐々木:ネストでイベントをやって成立するって、キャパ的に地下アイドルの最初のステップとして適してて、次の大きな箱への経由点になってる。それって実は、以前の普通のバンドがやってたことと同じだよね。そういう経由点になるようなキャパシティーの箱ってすごく重要で、でもそれが最近減ってきてるから、そういう意味でもやっぱりネストは貴重だと思いますね。
今HEADZがアイドルやるってなったら、一瞬バズるんじゃないかな。たぶん、すぐ消えるけど(笑)。
―荻原さんはHEADZのレーベル業務やライブイベント制作に携わり続けてきたわけですが、最近のライブハウスを巡る動きについて、どんなことを感じられていますか?
荻原:さっきのアイドルの話にも通じますけど、まずネストでやって、次に(渋谷)WWW、クアトロ、リキッドみたいに、着実にステップを踏んでいく傾向はあるかなと思います。しかも、それをわりと短期間でやっていく。そうじゃないと目立ちにくいという状況があるんだと思うんですけど。
佐々木:サバイブするって意味で言うと、そういうグイグイ来てる感を出さないと、すぐ横並びの中の一個に沈められちゃうんで、実際のステップアップよりも、見た感じそう見えるようにするっていうのが結構あると思う。僕はそういう考えがほとんどない人で、「ずっと同じとこでいいんじゃない?」って思うから、下手に動いて失敗するよりは、ずっと同じところでやり続ける方がいいと思うんだけど、でもそれは実際よくないんだろうね。
―どこを目指しているかにもよると思いますが、難しいところですね。
佐々木:あと最近荻原さんと話すのが、今小中規模のイベントを成功させる要因は、出演者および主催者の交遊関係だけ。つまり、友達が多いやつは友達が来るから、それで成立しちゃう。その場に来る理由の第一義が音楽じゃない方が、むしろ集客って意味では磐石なんですよね。それに対する危機感は強い。「なんか違うんじゃない?」って思っちゃう。
荻原:今って友達の定義も難しいんですよ、SNSでつながったファン同士の友達っていうのもありますからね。豊田(道倫)くんがよく言うのは「自分のお客さんはみんなサッと帰る、自分もそうだった」ということで、昔はいいライブを見ても、それを友達と共有したり、ミュージシャンに「ファンなんです」って言わずに、内に秘めて帰ってた。でも今は「ファンなんです」って知らせたがるんですよね。
佐々木:そうだよね。何にでもあてはまることだと思うけど、今の集客とか動員の大きなポイントは、「コミュニケーション」と「コミットメント」だと思う。ある種の錯覚も含めて、そういう気持ちを与えられるかが圧倒的に大きくて、純粋に音楽として受容するっていうのは嫌みたい。自分に何か意味があると思いたいっていうのかな。今の時代それを抜きに物事は語れないと思うけど、でも僕はもともとそういう感覚がないから、「困ったな」って(笑)。
―コミュニケーションツールの変化が、ライブハウスという現場に変化をもたらしているわけですね。この10年は特に、ツールの変化が大きい時代でした。
荻原:何でも事前に確認できてしまうツールも増えましたよね。
佐々木:前回実績データが蓄積されちゃってるから、すごくでかい賭けじゃなければ容易に予想が出来てしまうよね。そういうわけで、小っちゃく勝ってくことはできると思うんだけど、コツコツ小っちゃく勝っていくことと、未来のビジョンがだんだん乖離していく現象が起こってて、そうなると、何のためにやってるのかわからなくなっちゃう。僕はホントは今も大きな賭けがしたいんだけど、歳も取ってきたから、「そんなことしてもしょうがない」って気持ちも出てきてて。まあ、『エクス・ポナイト』はもう1回ぐらいやりたいけどなあ。
荻原:今はネストもアイドルが昼間から使ってるので、『エクス・ポナイト』みたいに早い時間からやれる日程を押さえるのがなかなか難しいんですよね。
佐々木:ネストがすごく貴重な場所だと思ってる人は僕らだけじゃないから、みんな早めに日にちを押さえにきてるし、最近はそこにアイドルまで参入してきて……だからたぶん、うちが次にやれることはアイドルですね。俺はアイドルに全然興味がないから、今の状況を不可解に感じちゃうので、逆にやってみたい。今HEADZがアイドルやるってなったら、一瞬バズるんじゃないかな。たぶん、すぐ消えるけど(笑)。
―それこそかつて招聘を始めたときのように、また「やれるんじゃない?」ってなれば、気持ちに火が点くんじゃないでしょうか(笑)。
佐々木:蓮沼(執太)っちとかみんなにプロデュースしてもらうとして、あとは誰をアイドルにするかだなあ。「オーディションやろうか」とかって言うと、荻原さんたち「絶対嫌だ」って言うんですよ。アイドルやってみたいなあ。これぜひ書いといてください。この記事の反応見て、どうするか決めるんで(笑)。
- 書籍情報
-
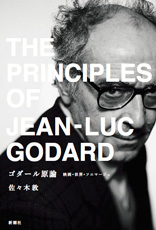
- 『ゴダール原論: 映画・世界・ソニマージュ』
-
2016年1月29日(金)発売
著者:佐々木敦
価格:2,700円(税込)
発行:新潮社
-

- 『例外小説論「事件」としての小説』
-
2016年2月10日(水)発売
著者:佐々木敦
価格:1,728円(税込)
発行:朝日新聞出版
-

- 『ニッポンの文学』
-
2016年2月16日(火)発売
著者:佐々木敦
価格:929円(税込)
発行:講談社 現代新書
- イベント情報
-

- 『nest20周年記念公演』
-
2016年3月24日(木)
会場:東京都 渋谷 TSUTAYA O-nest
出演:
在日ファンク
思い出野郎Aチーム2016年3月25日(金)
会場:東京都 渋谷 TSUTAYA O-nest
出演:あふりらんぽ
DJ:37A2016年3月26日(土)
会場:東京都 渋谷 TSUTAYA O-nest
出演:
The Dylan Group
テニスコーツ2016年3月29日(火)
会場:東京都 渋谷 TSUTAYA O-nest
出演:
DE DE MOUSE
アカシック
POP2016年3月30日(水)
会場:東京都 渋谷 TSUTAYA O-nest
出演:
group_inou
People In The Box
- プロフィール
-
- 佐々木敦 (ささき あつし)
-
1964年生まれ。批評家。HEADZ主宰。雑誌『エクス・ポ』編集発行人。『批評時空間』『未知との遭遇』『即興の解体/懐胎』『「批評」とは何か?』『ニッポンの思想』『絶対安全文芸批評』『テクノイズ・マテリアリズム』など著書多数。新著『ゴダール原論―映画・世界・ソニマージュ―』が2016年1月に、『例外小説論』、『ニッポンの文学』が2016年2月に刊行。
- HEADZ (へっず)
-
映画、音楽ライターとして活動していた佐々木敦とシティ・ロードの編集者であった原雅明の二人によって1995年5月にスタート。以来、カッティング・エッジな音楽雑誌『FADER』、ジャンルレスな濃縮雑誌『エクス・ポ』他の編集・発行、トータス、ジム・オルーク、オヴァル、カールステン・ニコライ他の海外ミュージシャンの招聘(来日公演の企画・主催)、UNKNOWNMIXやWEATHERといった音楽レーベル業務、飴屋法水の演劇公演の企画・制作等(ままごと『わが星』のDVD他、演劇やダンス・パフォーマンスの作品を発表するplayレーベルもスタート)、多岐な活動を続けている。音楽レーベルとしての最新作は昨年のO-nestでの20周年記念イベントでの共演がきっかけで、制作された4月6日発売のMoe and ghosts × 空間現代『RAP PHENOMENON』(UNKNOWNMIX 42 / HEADZ 212)。
- フィードバック 2
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-





