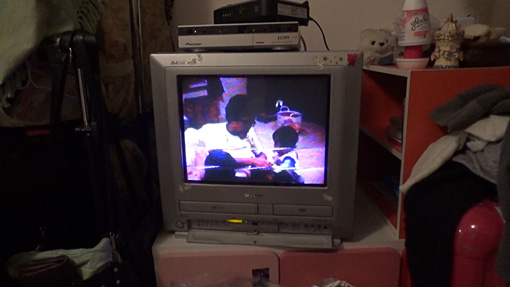映像編集はおろか、カメラを手にすることさえも、すべてが初めてだった一人の女性監督が完成させたドキュメンタリー映画『ディスタンス』が、数多くの秀作を発掘し続けている『山形国際ドキュメンタリー映画祭』で昨年高い評価を得た。極私的なホームビデオを眺めているうちに、確かに映画的な強さを持った得体の知れない魅力が、見る者をラストシーンまで牽引する。かつて一緒に暮らしていたが、今は別々に生活している特別ではない家族の風景とありふれた愛が映し出される。
ポストポップスの代表格ceroの高城晶平が営むカフェバー「roji」で、アルバイトをしていた岡本監督。店の片付けをしながらランタンパレードの“名言を言おうとしない”を初めて聴いた瞬間に、この曲を使って家族を撮りたいと強く思ったという。取材当日にrojiで開かれた今作の公開記念イベントには、今作を応援する親しい仲間が集い、高城やランタンパレードによるミニライブが行なわれた。イベント終了後、岡本まな監督、高城晶平、本作のプロデューサーでceroのPVなども手掛ける映像作家の浅井一仁の三人で、映画『ディスタンス』に描かれる「家族」と「日常」を語ってもらった。
家族の殺伐とした空気が嫌で、家族と離れて今までのしがらみから抜け出したかったんです。(岡本)
―映画『ディスタンス』では、一緒に生活していた頃のホームビデオを交錯させながら、ばらばらに暮らす家族の現在が描かれていますが、何がきっかけで、今、家族を撮ろうと思ったんですか?
岡本:10年くらい会っていなかった父と兄が再会したんですよね。それにかなり影響を受けて、そこから撮りたいなと思いました。
―本作は、お父さんとお兄さんが再会を果たし、和解した後から映し出されていますね。
岡本:そうですね。お兄ちゃんはずっと、お父さんのことになると感情むき出しで完全に拒絶していて。もう一生この二人が会うことはないんじゃないかと思っていたんですけど、和解したんです。二人の再会は、自分とは関係ないと思っていたけど、やっぱりものすごく嬉しくて。
高城:両親は離婚してるんだよね?
岡本:私が3歳の時に離婚してます。だから私にとってお父さんはよくわからない存在だし、実際に何かされたわけでもないので憎む理由はないんですけど、お父さんという存在にあまり感情を抱かないようにしていました。
―岡本さんが上京したのはおいくつの時ですか?
岡本:18歳の時です。家族の殺伐とした空気が嫌で、地元を離れたかったし、とにかく東京に行きたくて。家族とも離れて今までのしがらみから抜け出したかったんです。
―親元を離れたことで家族に対する考え方に変化はありましたか?
岡本:東京にいる時にお父さんと電話ですごい喧嘩をしたんです。「お兄ちゃんにこんなことして」って。私はお兄ちゃん子だったので、お兄ちゃんを苦しめたお父さんが許せなかったんです。でも、私は家族の中でお父さんと一番近い距離感だったし、なんだかんだ愛情もあって。ただ、お母さんとお兄ちゃんへの愛情があったから、自分自身でお父さんに対する感情に蓋をしていたんだって、その時に気づいたんです。
―でも、そういう距離感にいた岡本さんが、唯一家族のパイプ役になれたことで、この映画では、一人ひとりの感情が整理されて、作品になりえたんだと思いました。
岡本:そうかもしれないですね。特に父はかなり変化したように思います。映画を見て、実の息子が自分を「殺したい」って思っていたことにすごくショックを受けていて。でも、お父さんは、撮影し始めた頃に比べて、映画が出来上がるまでにかなり人間味が増していったように思えて、私たちの前で泣いたりするようにもなりました。それは今までわたしたちが知らないだけだった父の姿でもあるのかもしれませんが、今までは考えられなかったことで。この映画をきっかけにお父さんとお兄ちゃんの関係もさらに良い方向に変わった気がします。
浅井:映画を撮ることで、家族を繋いだんですよね。カメラが介入していくことで変わっていったのかもしれない。
岡本:お父さんとお兄ちゃんは、和解はしたけど、お父さんが直接謝ったり、実際に何かしたってことはなかったんです。だから、お兄ちゃんの中に、まだしこりがあったんでしょうね。それが解かれるのを期待していたのかも。
―冒頭に「この映画をなかしーに捧ぐ」とありましたが、この方はどういう方なのでしょうか?
岡本:なかしーは私を初めてrojiに連れて行ってくれた友人です。上京して最初にすごく仲良くなった子で、いつも叱咤激励してくれるような存在で。この映画も「すごく感動したよ」って気に入ってくれたんですけど、その1か月後くらいに急に亡くなっちゃって。
高城:なかしーはいつもまなちゃんを見守ってる感じだったよね。そこからまなちゃんは僕らとも、rojiのお客さんともすぐ仲良くなったんですよ。
岡本:それで、高城くんがceroで忙しくなってきた頃に、「月に1、2回働いてくれない?」ってルミさんに誘ってもらったんです。
高城:ルミさんっていうのは僕の母親でrojiを作った人なんですけど、かなり目利きなんです。この子はお店に向いているなとか、この人とこの人の化学変化は面白いかもって感覚的にわかるし、人を繋ぐのも得意で。
浅井:ルミさんの勘はすごくて。僕とまなちゃんを繋いでくれたのもルミさんなんですけど、本当に突然「浅ちゃん、まなちゃん手伝ってあげな」って言われたんですよね。だから本当にrojiから広がった感じですね。
父親だから、母親だから、娘だから、息子だからっていう役割はくだらないと思います。(高城)
―高城さんは東京が地元でずっと家族と過ごしていますよね。離れてみようという意識はなかった?
高城:そうですね。家族の距離感がうまく取れていれば割と一緒にいられると思いますよ。うちは、「お父さん」「お母さん」じゃなくて名前で呼ぶんです。だから、仲は良いんですけど他人っぽい距離感もありました。だらだら一緒にいる友達みたいな。だからこそ、お店も一緒にやれたのかなって思います。
―その呼び方のきっかけはなんだったんですか?
高城:気がついた時にはもう呼んでいました。子供が生まれたら自然と夫婦が「お父さん」「お母さん」って呼び合うようになると思うんです。それを聞いて子供も呼び方を覚えると思うんですけど、うちの場合はずっと恋人同士の時の名前で呼び合っていたんでしょうね。
―「お父さん」「お母さん」になった瞬間に「良い父」「良い母」でなければならないということになって、子供もそれを期待すると思うんです。
高城:そういう感覚が残っている家庭ってまだまだ多いと思うんですけど、家族の幸せっていう意味でも「個人」であることはすごく大事なんじゃないですかね。「父親だから」「母親だから」「娘だから」「息子だから」っていうのはくだらないと思います。
―そういう役割は担わないけど、家族として「良いチーム」でありたいっていうことは思いますか?
高城:そうですね。だから『クレヨンしんちゃん』の野原家とか、いいなって思います。野原家も「ひろし」「みさえ」って呼ぶよね。
―岡本さんのお兄さんも両親を名前で呼ばれていますね。
岡本:そうですね。お兄ちゃんが6歳くらいの時に、お父さんと住んでいた家を出たんですけど、お母さんが「ケイゴ、私はあんたのお母さんだけど、私は一人の人間だから、ちゃんと守ってね」って言ったんですって。お兄ちゃんは未だにそれを覚えていて。結構プレッシャーというか、「あ、守らなきゃ」って思ったって。
高城:それすごくいいね。個人として接してくれってことだよね。僕の実家のトイレに貼紙があるんだけど、「あなたの子供はあなたを通して来るが、あなたの所有物ではない」「あなたが訪ねてみることもできない明日の家に住んでいるのだから」(ハリール・ジブラーンの詩『子どもについて』)って書いてあって。それはすごく高城家を表しているなって思う。
―高城さんは、お子さんが生まれて、その言葉の解釈って変わりました?
高城:昔から自分に子供が生まれたらそういう風に育てようと思っていたので、それを実践しています。ただ、自立する分、スキンシップがかなり大事になってくると思っていて。今は子供が小さいからほっぺにキスしたりハグしたりできるけど、大きくなったらできなくなるじゃないですか。でも外国じゃ大人になっても親子でハグやキスをするわけで。
―確かに。
高城:自分の子供の世代くらいからは、日本でもスキンシップが普通にできるようになったらいいなと思っているんですけど、『ディスタンス』を見ていたら、まなちゃんのお兄ちゃんが、お母さんやおばあちゃんにハグやキスで愛情を示していて、すごくいいなって思いました。
岡本:うちはもともとかなりスキンシップが多い家族なんです。小さい時からのお母さんの教育というか。夜寝る前は必ずキスしてから寝たり。
高城:お兄ちゃんはそれをある時期から嫌にならなかったのかな?
岡本:一時期はなかったと思うけど、大人になって復活したかな。お父さんも結構ハグとかするんですよね。お兄ちゃんと再会した時も嬉しかったみたいで、スキップして私のほっぺにチューしてきたんですよ(笑)。
高城:僕は、結構この話は根が深いし暗いものだと思っていて。日本人って本質的にスケベだから、特に男だと思うけど、触れ合ったことで身体反応が出てしまうんじゃないかとか極度に恐れていると思う。他の国の人はもっとカラッとしていて、恐れずにスキンシップしてストレートに愛情を表すんじゃないですかね。まなちゃんの家族はそういうのを恐れてないのかなって。
岡本:うちの家族は確かにあんまり考えずに本能のまま動く感じではありますね(笑)。
お母さんが踊るシーンを見た時は「これはいい映画になるね」って二人で確信しました。(浅井)
―今回『ディスタンス』を撮影するにあたって、岡本監督は、カメラの使い方もPCのドラッグ&ドロップもわからないほどだったそうですね。
岡本:もう全然わからなかったですね(笑)。
―今までやったことのないことを20代後半で一から始めることってハードルが高いと思うんですが、岡本さんは何をもってモチベーションを保っていたのでしょう。
岡本:感情ですね。家族以外のことでも苦しい時期が続いて、それを脱したかったし、表現に変えたいと思ったんです。rojiで働いていた頃に聴いたランタンパレードさんの“名言を言おうとしない”が流れるシーンまで映画を持っていこうっていうのは最初から思っていました。
―この映画が、ただのホームビデオではなく作品として成立している要因に音楽や踊りがありますよね。高城さんは「日常」を音楽に落とし込んでいますが。
高城:僕も本当は映画や漫画をずっとやりたくて。まなちゃんみたいにできたら良かったなって今でも思うんです。でもやれなかったんですよね。漫画もずっと描いていたけど最後まで描き終えられたことがなかったし、手に負えなかったんです。唯一手に収められるのが、1曲や、詞の1編っていう単位の表現だった。そう気づいてからは、音楽で表現するようになりました。
―でも高城さんの作られたその音楽が映画の中でかなり効いていますよね。
岡本: ceroの“Orphans”が発表されたばかりの時に、私が家族に聴かせたくてかけたら、みんな踊り始めて(笑)。音楽をかけると踊るんですよね。
高城:僕が作った音楽を、まなちゃんが実家に持って帰ったら、みんなが踊るっていうのは愉快ですね。いい話だなって思うし、嬉しいです。
浅井:監督は家族が暮らす地元の北海道で映像を撮影して、それを東京に戻って来て編集するっていう作業を繰り返していたんですけど、初めの頃は、お父さんとおばあちゃんがひたすらふざけているシーンばっかり撮ってきて……。でも、お母さんが踊るシーンを見た時は「これはいい映画になるね」って二人で確信しました。

cero“Orphans”で踊る岡本監督のお母さん。映画『ディスタンス』より

cero“Orphans”で踊る岡本監督のお兄さん。映画『ディスタンス』より
―ナレーションで説明する方法もあるのに、映像の言語力が強くて見事に物語っていますよね。
岡本:説明しすぎるよりも、音楽とか踊りのある映画が好きなんです。ゴダールの作品とか、『Buffalo '66』(1998年のアメリカ映画。ヴィンセント・ギャロが監督・脚本・主演・音楽を手掛け、恋人役としてクリスティーナ・リッチが出演した)のクリスティーナ・リッチが踊るシーンとか、すごく好きで。最初から踊りや音楽を入れたいっていうのはあったんですけど、自然と入っていきましたね。
―浅井さんは映像制作について岡本さんに何かアドバイスされたんですか?
浅井:僕は映画の学校を出ていて、仕事でもPVなどを作っているので、基本的なテクニックみたいなものは編集と一緒に教えました。でも、ホームビデオを超えた映画的な映像が撮れるのは監督自身の力ですね。
―「映画的な映像」というのは、浅井さんから見てどういう部分だと思いますか?
浅井:例えば、夜にお母さんが佇んでいる庭の電気が消えるシーンがあるんですが、あれは、超天才監督がフィクションで撮った絵のように、現実を超えている表現だと思います。
高城:昔のホームビデオがブラウン管に映っているのを、さらにカメラで撮影している感じとかね。
岡本:小さい頃にお父さんと過ごした思い出は少ないけど、写真やビデオが大量にあったので、それに浸る時が結構あったんですよね。
高城:小さい頃の映像って、親が子供にカメラを向けるわけじゃん。でも、子供がある程度大人になるとカメラを向けることもなくなっていって。まなちゃんが画面に映るホームビデオを撮ったことは、今度は親が被写体になって、撮る者が撮られる者に変換される瞬間が見えて面白いよね。この映画は最初から人に見せたいと思って撮り始めたの?
岡本:どっちかというと自分の記録かな。映画にしたいなっていうのはあったけど、たくさんの人に見てもらいたいっていう感じではなかったです。
浅井:でも、まなちゃんの好きな映画館という空間で流したいっていう思いはあったんだよね。スクリーンで流れるイメージを持っていたよね。
岡本:そうですね。自分の好きな空間に、それこそなかしーみたいな、自分の好きな人たちが集まって見てほしいとは思っていました。
今、家族や愛にプレッシャーを感じている人も、時を超えていつか愛だとわかるものもある。(浅井)
―でも、本当によく一から撮り切りましたね。
岡本:家族から逃れたくて東京に出て、外の世界に目を向けていた時期もありますけど、結局、幼少期の記憶にとらわれて生きていたことに気づいたんです。保育の学校にいて子供のことを勉強していた時に、普段思い出さないような幼い時の辛いことを自然と思い出して。同じ時期に色んな映画も見たんですけど、カサヴェテスの『こわれゆく女』(1974年。アメリカの映画)も、その記憶をさらに呼び起こす感じだったんです。そういう体験に突き動かされたかもしれないです。
高城:子供ってほんとタイムマシーンだよね。僕は、小3以前の記憶がほぼなくて。でも自分の子供を見ていると、自分の幼少期がフラッシュバックすることがあるんです。まなちゃんのお兄ちゃんも、子供ができて自分で消していた思い出とか、お父さんに対する憎しみじゃない部分を思い出す気がする。
―岡本さんも現在妊娠されていて、東京から地元の北海道に帰ったり、めまぐるしく変化されている中で、改めて『ディスタンス』を通して気づいたことってありますか?
岡本:まだ生まれてないですけど、子供がお腹にやってきて、お母さん目線に立てるようになった気がしますね。今までは「母と娘」の娘側でしか家族を見てなかったんですけど、お母さんが若い時はどういう心境だったんだろうって想像したり。そう思うと私のお母さんは辛かったんだろうなって。
高城:僕は子供を持ったばかりの親としてこの映画を見たけど、自分の幼い頃を思い出したり、子供がこういう風になっていくのかなって思うところがあった。これから夫婦になったり、子供を持ったり、家族が増えるタイミングにいる人が見たら、今までと違った視点が得られるんじゃないかなと思います。
浅井:僕はまだ家族を持っていないけど、自分が家族を持つことに不安があったり、幸せについて考えることもあって。この作品は、確かな愛の手触りがある映画だと思うんです。今、うまくいかなくて不安でも、時を超えていつか愛だとわかるものもあるのだなと映画を通して知りました。家族や愛にプレッシャーを感じている人も、心が楽になる作品になったと思います。
岡本:みんな、家族のことで葛藤していたとしても人になかなか言えないじゃないですか。特に幼少の記憶なんかは。そうやって普通に生活している人に、一つの家族の中で生まれたちょっとした奇跡みたいな瞬間を、重ねてみてもらえたらいいなって思います。
- 作品情報
-
- 『ディスタンス』
-
2016年7月23日(土)からポレポレ東中野ほか全国公開
撮影・編集・監督:岡本まな
プロデューサー:浅井一仁
音楽:ランタンパレード
- プロフィール
-
- 岡本まな (おかもと まな)
-
1988年北海道函館市出身、高校卒業後18歳で上京。女優を志し、いくつかの自主映画やミュージックビデオに出演する。その後、保育士やバーの店員、家事代行、競馬場でのチケットもぎり等をしながら東京で生活をしていたが、映画への情熱は忘れられず、何も分からないまま映画を作ることを決意。2014年より東京と函館を行き来する日々がはじまる。翌年、映画完成後に地元へ戻り、現在は函館で暮らしている。
- 高城晶平 (たかぎ しょうへい)
-
様々な感情、情景を広く『エキゾチカ』と捉え、ポップミュージックへと昇華させる音楽集団ceroのメンバー。2015年5月27日に、3rd Album『Obscure Ride』をリリース。オリコンアルバムチャート8位を記録し、現在もロングセールスを記録中。2016年5月21日には日比谷野外音楽堂にて、7月10日には大阪城野外音楽堂にて、ワンマンライブ『Outdoors』を開催。阿佐ヶ谷のカフェバーrojiを営む。
- 浅井一仁 (あさい かずひと)
-
1984年神奈川県横浜市出身。日本大学芸術学部映画学科卒業後フリーのディレクターとして活動。cero、どついたるねん、BiS、BiSH、Rev.flom DVLなど様々なアーティストのミュージックビデオやCMなどを演出する。映画『ディスタンス』が初のプロデュース作品。現在自身が監督する新作映画を準備中。
- フィードバック 2
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-