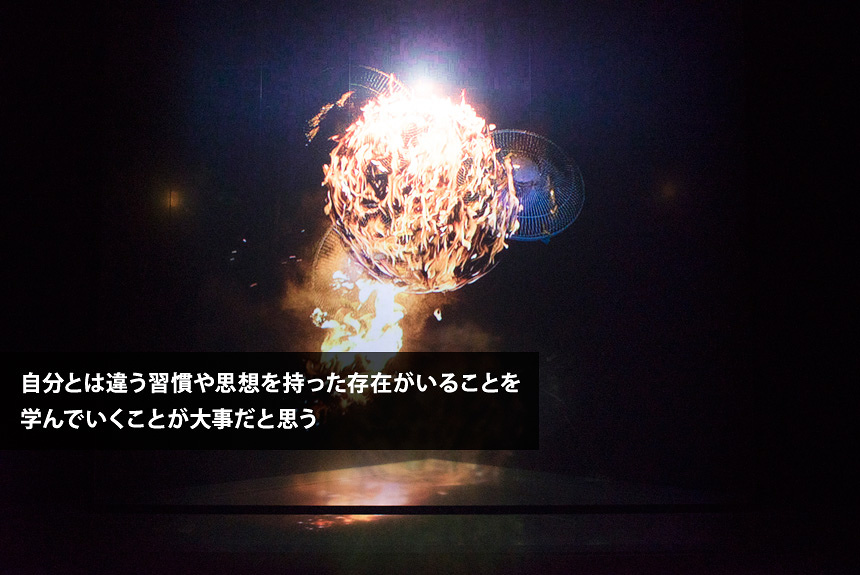あらためて言うまでもないが、私たちの身体はそれぞれ、個別の歴史を生きてきた。しかし私たちはときとして、あまりに無自覚に「典型的な日本人」「ふつうの身体」などという表現を使って、その個別性を無視してしまう。そこで言う「典型的」「ふつう」の範囲とは何なのか? じつはその取捨選択こそ、ある時代、ある社会の産物なのではないか?
10月1日から横浜美術館で開催されている『BODY/PLAY/POLITICS』は、そんな個人の思考や身体性と、それを取り巻く環境との関係性を、あらためて考えさせる展覧会だ。ヨーロッパとアフリカ、東南アジア、そして日本から集まった6名の作家は、彼らが生きてきた地域の人々の考える「当たり前」にメスを入れ、それをある歴史が構築したものとして分析してみせる。横並び思考がいまだ強く、同質性が高いと言われる日本社会で、本展を開催する狙いとは何か? 担当キュレーターの木村絵理子に訊いた。
私たちは何気なく「典型的な日本人」などと言ってしまいがちですが、その「典型的」って何だろう? と。
―美術にとって身体(BODY)をどう表現するかは古典的なテーマですが、なぜいま身体という問題を取りあげようと考えたのでしょうか?
木村:今回の展示の源流は、2007年に企画した『GOTH -ゴス-』展という展覧会にあります。その展覧会は、私がずっと抱いていた当時のパーソナルな身体への関心から生まれたもの。もともと、中世ヨーロッパの建築や美術のスタイルを指す言葉であった「ゴシック」は、18世紀以降にゴシック・リバイバルとして再燃し、リバイバルとしてのゴシックが、現代文化におけるゴス的なるものの源流になっています。展覧会は直接的にファッションや音楽、小説などのゴス文化を扱うものではなく、より広く病や死、あるいはタトゥー、ピアッシングといった身体改造、自分の皮膚やジェンダーといったものを通して、死生観や病などに言及するような作品を国内外の6作家に出品してもらいました。

ピュ~ぴる《純白》2007年、ミクストメディア(布、毛髪、針金など)、約200×500×500cm、横浜美術館寄託 photo: masatoshi sakamoto
木村:この展覧会は、ネガティブに捉えられがちな身体の側面に、よりリアルな生を感じる傾向を「ゴス」と位置づけて、現代社会における生きるためのスタイルとして提示しようとしたものでした。今回の展示は、自分の中ではこの『GOTH -ゴス-』展の第2弾と考えています。
―第2弾をやろうと思ったのは、どうしてでしょうか?
木村:『GOTH -ゴス-』展で取り上げたようなパーソナルな身体の問題にはずっと関心がありますが、一方この10年間で、「国」のような大きな枠組みから個人を捉える傾向が強くなったと感じています。「BODY」という単語には、個人の身体という意味のほかにも、「集団」や「かたまり」といった意味があります。今回はそれらの意味も含めた「BODY」が、「社会的な役割を演じる(PLAY)」場合の政治性「POLITICS」について考えたいと思っていて。たとえばいまは、10年前に比べて「人種」や「国民性」という話題が公の場で話されることが増えましたよね。
―そんな印象はありますね。
木村:なぜか大勢の人が、驚くほどにそうした話題に興味を持ち始めて、表立って話すようになってきた。そしてそのとき、私たちは何気なく「典型的な日本人」などと言ってしまいがちですが、その「典型的」って何だろう? と。自分の社会的な言動は、いったい何に基づいているのか? という疑問を持ち、今回の展示では自分を取り巻く「集団的な身体」に注目した作品を発表している作家たちを選びました。
―日本社会は、同質性が高いと言われますよね。つまり、何となく「みんな同じ」という感覚が強い。一方、木村さんは小さい頃、アメリカに住んでいたとお聞きしたのですが、アメリカは「みんな違う」ことを前提にした社会というイメージがあります。
木村:小学校時代にカリフォルニアに住んでいたのですが、仲が良かった友人はルーマニア、トルコ、メキシコ、イスラエル、中国、韓国系と、非常に多様でした。象徴的なのは給食の時間で、お弁当を持ってきても、カフェで食べてもいいんです。というのも、宗教的に食事に制限がある子も多いし、身体の大きさも違うから食べられる量も違う。それが日本に帰ったら、みんな同じものを同じ量で食べないといけないのがつらくて、疑問でした。
―日本の子どもも、一人ずつ違うはずですよね。
木村:日本人でも身体の大きさは違うし、アレルギーのある子もいる。いまは給食のシステムもだいぶ変わりましたが、まだ選択の幅は狭いですよね。
日本全国で多様なバックグラウンドを持つ人たちが共存することが増えていく中で、これまで以上に重要なのは、「自分が何者か」を歴史的な文脈で知っておくことだと思います。そうしないと、「私はムスリムだから豚肉は食べられない」というような選択の理由を説明することもできません。
―今回の展示は、そんな時代に向けた一種のレッスンにもなりそうですね。
木村:そう思います。とは言っても、出品作品はどれもそんなに堅苦しいものではありません。タイトルにある「PLAY」という言葉どおり、表現の仕方としては「遊び」の要素があったり、パッと見ただけでも美しいと感じられるものが多いですよ。
私たちの周囲にも、ルーツを探ったらじつは思っていた出自と違ったというものが多いですよね。
―展覧会の最初に登場するのは、ナイジェリア系イギリス人アーティストのインカ・ショニバレMBEです。彼は1990年代に頭角を現し、黒人として初めて世界的な現代アートのアワードである『ターナー賞』にノミネートされた作家ですね。

インカ・ショニバレMBE ©James Mollison 2014
木村:彼はロンドン生まれですが、幼少期に両親のルーツである元イギリス領のナイジェリアに移りました。ただ、当時のナイジェリアにはイギリス流の教育が残っていて、彼曰く「違うようで同じ国」だったそうです。10代でロンドンに戻った彼は、この出自に着目し、アフリカとヨーロッパの植民地関係に自覚的な作品を作るのですが、そこで扱ったのがろうけつ染のアフリカ更紗です。

インカ・ショニバレMBE 左:《さようなら、過ぎ去った日々よ》2011年、右:《蝶を駆るイベジ(双子の神)》2015年 会場風景 Courtesy the artist and James Cohan Gallery, New York photo:Yuri Manabe
―ろうけつ染は、溶かしたろう(蝋)を使った染色の技法ですね。
木村:一見して「アフリカっぽい」印象を与えますが、じつはこの布はもともと北インドなどで作られていて、早い時期からインドネシアなどの東南アジアやアフリカでも生産されるようになり、大航海時代にヨーロッパへ渡ったものなんです。綿が育たないヨーロッパで、この生地は人気となり、その後、オランダを中心に生産・販売されて、ヨーロッパのファッションに多大な影響を与えたようです。その後、オランダやイギリスは、植民地から原綿だけを輸入し、ヨーロッパ内で加工したものを、再び素材の原産地である植民地に売りつけるという関係になっていきます。
―つまりパッと見はアフリカ風だけど、一大生産地はヨーロッパだと。
木村:ショニバレは、ナイジェリアなどの旧植民地がイギリスから独立する時に、自分たちのアイデンティティーを象徴するものになった布が、じつはヨーロッパで量産された逆輸入品だったという皮肉な歴史を背負っていることに着目して、ロンドンで買ったヨーロッパ産のアフリカ更紗を作品に使っているのです。でもよく考えると、私たちの周囲にも、ある国の象徴と言われるけど、ルーツを探ったらじつはそうではなかったというものが多いですよね。
―たしかに。
木村:今回、彼が出品する映像では、オペラ作品の『椿姫』を、アフリカ更紗の服を来た黒人の女性オペラ歌手が歌っている。一般的に『椿姫』は白人が歌うものと認識されていますが、まさにアフリカ「風」更紗がそうであるように、ある時代やジャンルにおいて「それっぽい」と思われた感覚は、正しいと言えるのか? じつはそれは別の歴史を背負っているのでは? と問いかけてくる、本展の始まりにふさわしい作品です。
たわいもない会話の中に、直接的ではないけどその国の身体が垣間見られる。
―次はマレーシア出身で、今回、唯一の女性作家であるイー・イランです。作品を見ると、髪を垂らした7人の女性が、たわいもない話をしているようですが……。
木村:彼女たちが体現しているのは、マレーシアでは「ポンティアナック」と呼ばれる、超自然的な存在。これはマレーシアでは妊娠中や出産時に死んでしまった女性の、一種の幽霊なんですね。夜中に歩いていると、このポンティアナックが襲ってきて、男性の内臓や性器を食べると言われているそうです。

イー・イラン《ポンティアナックを思いながら:曇り空でも私の心は晴れ模様》2016年 会場風景 ©Yee I-Lann photo:Yuri Manabe
―男性によって抑圧された、女性の象徴のような存在?
木村:我々が見るとそうとしか思えませんが、イー・イランによると、現地ではとくにそう解釈されているわけではなく、B級ホラー映画やミュージックビデオなどにもしばしば登場するごく普通に知られた存在だそうです。でも、東南アジアの多くの国では、いまも宗教的な理由などによって、男性に比べて女性の発言は制限されている。それで彼女は今回、ポンティアナックにフェミニズム的な意図を込めて、現代の女性を象徴する存在として表現しています。
―背景は深刻ですが、女性たちの話している内容が、自分の男性観や結婚観、あるいは「猫が好き」など、いわばガールズトーク的な軽いノリなのが面白いですね。
木村:そうなんです。みんな言いたいことを自由奔放に話す、元気な女性が登場していますよね。「出演したいと言ってくれる人が予定よりたくさん集まって、14人を7人ずつの2組に分けて撮影したの」と作家は言っていました(笑)。でも、そのたわいもない会話の中に、直接的ではないけどマレーシア社会の姿、いわばその国の身体が垣間見られるところが面白いんです。
アピチャッポンは詩的で抽象的な映像の話法を駆使して、固着したタイ社会をチクチク批判する。
―ちなみにイー・イランも含め、東南アジアの作家が多いのはなぜですか?
木村:東南アジアには、地域の歴史を引き受けて、それを作品化する手法に意識的な作家が多いというのがひとつ。それと、あまりに遠い国よりは、日本との接点を見つけやすいということもありますね。続くアピチャッポン・ウィーラセタクンも、タイを代表する映画監督でアーティスト。日本でも人気が高いですが、抽象的なシーンのつながりから、タイ社会の現在を浮かび上がらせる、とても詩的な映画を撮る監督ですよね。

アピチャッポン・ウィーラセタクン photograph by Chai Siris
―(日本では今年公開された)2015年の新作『光りの墓』も話題になりました。彼は日本のギャラリーでもたびたび展示をしていますが、その映画と美術作品の関係とはどんなものなのでしょう?
木村:両者にはパラレルな関係があって、映画がナラティブに物事を表現するとすれば、そこからいろんな要素を抜き取った抽象度の高いものが、美術作品だと思います。今回の映像作品も、出品作品で唯一、具体的な身体が登場せず、一番抽象的なのですが、展示コンセプトを聞いた彼が、「ぜひこれを」と提案してくれたものなんです。

アピチャッポン・ウィーラセタクン《炎(扇風機)》2016 年 会場風景 Courtesy of Apichatpong Weerasethakul photo:Yuri Manabe
―巨大な火の玉が、ゴーッとすごい勢いで燃えています。
木村:燃えているのは、じつは扇風機です。この太陽のような炎は燃え尽きそうで燃え尽きないのですが、これにはどんな意味があるのか。この作品は『光りの墓』の完成後に撮られたのですが、同作はかつての王族同士の争いが題材でした。
現在のタイの国土はその昔、タイとラオス、カンボジアなどの王朝が入れ替わり支配していて、作家の故郷の東北部は、ラオスの一部でした。それをいまのタイ王朝が支配するようになるのですが、東北部には言葉の上でも経済的にも、中央との地域間格差が残っています。あとは日本でもよく報じられる通り、現在のタイは軍事的にコントロールされ、国民を縛りつけるようになっていますよね。
―王朝批判をすると「不敬罪」で投獄されるなど、厳しい状況だそうですね。
木村:彼は抽象的な映像の話法を駆使して、それをチクチク批判しているようにも見えます。『光りの墓』に映画館のシーンがあって、タイでは映画の開始前に全員で国歌を聴くはずが、ここでは流れない。そしてその後、天井の扇風機が回って、空気が攪拌されるシーンが続くんですね。
―タイでは、映画を観る前に国歌を聴くということも知りませんでした。
木村:そうですよね。そこから今回の作品をあらためて見ると、扇風機というモチーフは、いまの厳しいタイ社会の空気を攪拌するものにも思える。『光りの墓』はタイでは上映しなかったそうですが、今回の作品が、タイの現状を知るきっかけにもなるといいですね。
「生きる戦後史」のようなベトナムの作家・グエンは、人間の発展への欲望と、それに対する対価の関係に関心を持っています。
―続いて登場するウダム・チャン・グエンは、ベトナム戦争の真っ最中の1971年に生まれたアーティストです。
木村:彼はある意味で、ベトナムの生きる戦後史のような存在です。芸術家の父親は徴兵されて戦地に行くのですが、退役後、精神的にたいへんなショックを受けて、家族で渡米することになった。つまりグエンは、ベトナムで社会主義教育を、アメリカで西側の教育を受けたわけです。冷戦の構図を、10~20代に一気に経験するんですね。
―現在はベトナムに戻っているのですか?
木村:はい。ベトナムにも複雑な歴史があり、フランスの植民地時代に社会主義国家となってからは旧ソ連の影響下にあり、また経済発展したいまでは、アメリカの影響も受けています。彼の映像作品に登場するのはベトナム人の主要な足であるバイクで、その群れがまるで街という体内を流れる血液のように走り回るのですが、その中でフランス植民地風や社会主義風の建物など、街がいろんな表情を見せます。

ウダム・チャン・グエン《ヘビの尻尾》2015/2016 年 会場風景 © UuDam Tran Nguyen. Courtesy of the artist. photo:Yuri Manabe
―バイクにチューブのようなものが付いていますが、これは?
木村:ビニール製のチューブで、排気ガスで膨らんだものです。言ってみれば活発な街の呼吸のようでもあるし、一方では人体に悪影響を及ぼすものでもある。同国の経済発展に対するグエンの視点は複合的で、人間の発展への欲望と、その代償との関係に関心を持っています。たとえば彼の作品にはいろんな人類の創造物のイメージが入っていて、そのひとつであるバベルの塔は、人間が天まで届く建物を作ろうとして失敗し、その結果、みんながバラバラの言葉をしゃべるようになったという神話です。
―一見すると非常にポップですが、警告的な作品でもあるわけですね。
木村:直接的に説教臭くはないんですけど、いろんなかたちで人間の発展に向けた欲望に対する批判的な視点が含まれていると思います。今回は、実際のバイク12台も展示されていますよ。
石川竜一の写真に写る人は、一般名詞として「日本の人」と言ったときに、なかなかイメージしないような人たちなんです。
―残りの2名は、日本の作家ですね。沖縄県出身の写真家である石川竜一さんと、富山県出身で横浜とも縁が深い、アーティストの田村友一郎さんです。
木村:石川さんは沖縄を拠点に、ストリートで出会った人々のポートレートを撮り続けている写真家です。
―昨年、『木村伊兵衛写真賞』も受賞しましたね。
木村:はい。それで作品を見た方も多いでしょうが、ヤンキーからLGBTまで、多種多様な人が登場します。しかも、そこに写る人は、一般名詞として「日本の人」と言ったときに、なかなかイメージしないような人たちなんですね。
石川さんにとっては日常ですが、国内における「当たり前」とのズレが衝撃を与えます。今回は、彼が沖縄県内と県外の日本各地で撮った人々の写真を初めて混ぜて展示しますが、それはもはや「沖縄の写真」ではなく、日本に住む多国籍な人々も含めて「現在の日本のありのままを写した写真」として我々に迫ってきます。
―いわば、多くの人が抱くような「日本人像」を揺るがす仕組みになっていると。
木村:もうひとつ、彼には何年も撮り続けている被写体が何人かいて、そのシリーズも初めて公表されています。一人は「グッピー」と自称する女性で、すごくカラフルなファッションをまとっていて、お菓子しか食べないそうです。長い時間をかけた撮影は、その場限りの関係からは見えない、被写体と石川さんとの関係性を見ることでもある。彼の写真からは、そんな日本社会の主流からはこぼれてしまう人々の姿が感じられるはずです。

石川竜一《グッピー》2011-2016 年 会場での制作風景 photo:Yuri Manabe
GHQが来るまで、日本人は西洋人に比べて胴長短足で、グラマラスではない自分の身体を、恥ずかしいとは思っていなかった。
―一方で田村さんは、展示場所の歴史を取材して、制作するタイプの作家ですが、今回は「ボディビルディング」がテーマだとか。なぜ、ボディビルなんですか?
木村:ボディビルは彼が長年取り組んでいるモチーフで、今回はそれをメディアの歴史と絡めて見せます。というのも、横浜とボディビルには深い関係があるんですね。
近代のボディビルは、プロイセンで19世紀末に生まれるのですが、そこで怪力ショーなどの興業として身体を見せていたのがユージン・サンドウという人だそうです。彼はアメリカに渡り、万博などで大人気になりますが、そのとき一役買ったのが「写真」です。そして広まったボディビルが、GHQを通して戦後の横浜に入ってくる。横浜にボディビルの器具が持ち込まれ、アメリカ兵が身体を鍛えているのを見て、日本人が初めて近代のボディビルディングと出会ったのだそうです。

田村友一郎《裏切りの海》2016年 会場風景 撮影:田村友一郎
木村:そのアメリカ兵の身体に魅せられてボディビルディングを始めたのが、現在、日本のボディビルディングの第一人者となった方です。彼は三島由紀夫の肉体訓練の師匠でもありました。三島はいわば日本戦後史の中で、日本人の身体と古代ギリシア的身体との関係を我々につきつけた人物ではないかと思うのですが、展示では三島がアメリカやギリシアなどへ向けて旅立った頃の物語を織り交ぜながら、横浜に現存する、アメリカ兵や船乗りの集まるバーの空間を模したインスタレーションを行ないます。
―日本へのボディビルディングの輸入って、意外に大きな意味があるんですね。
木村:GHQが来るまで、日本の庶民は西洋人に比べて胴長短足で、グラマラスではない自分の身体を、恥ずかしいと思うことはなかったのではないかと思います。戦後に、日本人の身体観自体が変わったのではないでしょうか。そこで大きな役割を果たしたのが、街を闊歩するアメリカ兵の身体であったというのが田村さんの作品にも語られていて、それに憧れを持つようになる人が日本に現れた。そのとき軍人の身体は、広告塔のような存在だったんじゃないか。ボディビルは象徴的な例ですが、このように身体がメディアともなることに、田村さんの関心はあるんです。
何か定められた標準の枠内にないと批判されるのが、いまの日本の現状ですが、違いを知らないと他者への思いやりも生まれない。
―いま僕たちは、当たり前のように西洋人の身体を「カッコイイ」ものとして見てしまいがちですが、その認識も歴史の上にあることが、感じられるわけですね。
木村:これは展示全体についてですが、観客の方に、現在の日本がどのように成立したのか、自分が身を置く状況を再確認するきっかけになるところまでいけたらといいと思っています。今日、お話しした作家の順番は、展示順でもあるのですが、遠い国から始めて日本の作家たちで終わるのも、問題の糸が徐々に身近な場所まで引っ張られてくるようにしたかったから。自分の認識や習慣をそうたらしめている歴史について、目を向けていただけたらいいなと思います。
―その上で、お互いの違いが当たり前に表に出せるようになるといいですね。
木村:日本だと、自分語りをするのはどちらかというと嫌われる行為じゃないですか。でも、例えば多国籍のアメリカの小学校では、自分を主張するのは当たり前のことだった。先日、横浜の入国管理局で収容していたイスラム教徒の人に、食事として間違えて豚肉を提供してしまったというニュースを知って、非常にショックだったんです。この国では、入国管理局のような海外との窓口のような場所で、そんなことが起こるのかと。
2020年の東京オリンピックなどに向けて、こうしたほころびがこれからもいっぱい出てくるのではないかと思うのですが、むしろどんどん表面化すればいいと思います。そうやって自分の当たり前が、他の人には当たり前じゃないということ、違う習慣や思想を持った存在がいることを、身をもって知ることが大事だと思う。
―「みんな違う」ということに、日本人も馴れようと。
木村:そうです。何か定められた標準の枠内にないと批判されるのが、日本の現状ですが、違いを知らないと他者への思いやりも生まれない。そしてそこでは、自分の「当たり前」を支える歴史を知ることが重要で、今回の展示をそのきっかけにしてもらえたら嬉しいですね。
- イベント情報
-
- 『BODY/PLAY/POLITICS』
-
2016年10月1日(土)~12月14日(水)
会場:神奈川県 横浜美術館
時間:10:00~18:00(10月29日、10月28日は20:30まで、入館は閉館の30分前まで)
出展出品作家:
インカ・ショニバレMBE
イー・イラン
アピチャッポン・ウィーラセタクン
ウダム・チャン・グエン
石川竜一
田村友一郎
休館日:木曜(11月3日は無料開館)、11月4日
料金:一般1,500円 大・高校生1,000円 中学生600円
※小学生以下無料
- プロフィール
-
- 木村絵理子 (きむら えりこ)
-
横浜美術館主任学芸員。主な展覧会に『GOTH -ゴス-』展(2007-08 / 横浜美術館)『森村泰昌:美の教室、静聴せよ』展(2007 / 熊本市現代美術館・横浜美術館)『金氏徹平:溶け出す都市、空白の森』展(2009 / 横浜美術館)『束芋:断面の世代』展(2009-2010 / 横浜美術館・国立国際美術館)『高嶺格:とおくてよくみえない』(2011 / 横浜美術館・広島市現代美術館・鹿児島県霧島アートの森)『奈良美智:君や 僕に ちょっと似ている』(2012 / 横浜美術館・青森県立美術館・熊本市現代美術館)『Welcome to the Jungle 熱々!東南アジアの現代美術』展(2013 / シンガポール美術館との共催企画/ 横浜美術館・熊本市現代美術館)『BODY/PLAY/POLITICS』展(2016 / 横浜美術館)など。
- フィードバック 1
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-