『世紀の光』『光りの墓』といった長編映画の相次ぐ劇場公開や、『さいたまトリエンナーレ』や横浜美術館でのグループ展『BODY/PLAY/POLITICS』への参加など、2016年における日本での活躍が目覚ましかったタイの映画監督・映像作家、アピチャッポン・ウィーラセタクン。現在、大規模な個展『亡霊たち』が東京都写真美術館で開催中だ。
本展では、アピチャッポン作品の重要な要素でもある、目に見えない亡霊=Ghostをキーワードに、これまで直接的に言及されることが少なかった社会的、政治的側面にフォーカスが当てられ、彼の作品世界とその背景を読み解く絶好の機会となっている。伝説や民話、個人的な記憶などを題材に、自己と世界の再発見の方法を探求する彼の作品が孕む政治性とは如何なるものか。さらに、近年のプロセスを重要視する制作スタイルや、常にアイデアの源泉となってきた「夢」についてなど、アピチャッポンの最新の関心事を聞いた。
「政治的」と言っても国家間の政治だけではなく、個人的な生活と政治の関係性を見せたい。
―今回は東京都写真美術館での大規模な展覧会となりますが、かなり準備にも時間をかけたとうかがっています。展覧会にあたって特に重視した点はどんなところでしょうか?
アピチャッポン:日本の公立美術館で初めての個展をここで開催することはすごく重要な意味を持ちますし、満足しています。ただ空間的なことを言うと、正直もうちょっとスペースが欲しかったですね(笑)。私の作品では、空間における音と映像の関係が大切なのですが、限られた空間で作品をどう見せるかということについて、博子さん(本展キュレーターである田坂博子)たちとディスカッションしながらいい関係が作れていると思います。

アピチャッポン・ウィーラセタクン。『ゴースト・ティーン』が『炎』にうっすら映っている。各作品が関係し合うような展示レイアウトが特徴的 /『炎』2009年 インクジェット・プリント 東京都写真美術館蔵
―展覧会のタイトルになっている「亡霊たち」というテーマは、どこからきているのですか?
アピチャッポン:私が2009年に執筆した「Ghosts in the darkness」という論文をもとに、美術館のほうから提案がありました。「亡霊」にはふたつの意味があって、ひとつは写真や映像などのメディア自体が持つ特性。もうひとつは、政治や歴史の中に潜む、見えざる力です。
今回の展覧会で一番重要なことは、私の作品に内在している政治的な要素にフォーカスを当てたことです。「政治的」と言っても国家間の政治だけではなく、日常の中の個人的なものや、生活における政治との関係性を、個展を通して見せたいというのが背景にありました。

アピチャッポン・ウィーラセタクン『悲しげな蒸気』2014年 ライトボックス、昇華型熱転写方式
―実際、作品に表象されているものは、「夢」や「記憶」など極めて個人的なものですね。
アピチャッポン:はい。私の作品にはすべて個人的な体験が反映されています。国や育った場所に何か変化が起きると、日常の感じ方にも変化が起きる。すると、ゴーストとフィクションの境目にあるものが現れてきて、さらにそれらを大きく広げていくと、今度は「物語」と「政治」がどう変化し、関係性を築いていくのかということが浮かび上がってくると私は考えます。政治的な背景を読み込むことで、タイに住んでいることのアイデンティティーを問いかけるきっかけにもなっているのではないかと思いますね。
自分自身を発見したり、今生きている世界を再発見するためにアートを利用している。
―日本ではタイの歴史や社会状況を詳しく知らない人も多いですが、あなたの作品をきっかけに関心を抱いたという人もいると思います。アートのフィールドだからこそできることや、アートの表現の自由度みたいなものは感じていますか?
アピチャッポン:アートは表現の自由という意味において、精神的な部分で可能性を持っていると思いますが、私個人としては、自分自身を発見したり、今生きている世界を再発見するためにアートを利用していると言えます。
あまり誰かのためにとか、何かを変えるために利用しているわけではないんですね。たしかに作品の背景に政治的なメッセージは入れていますが、私は活動家ではなく、あくまでアーティストです。
―2000年代後半から、生まれ故郷であるタイ東北部のイサーン地方を作品で主に扱うようになりましたが、何か特別なきっかけはあったのでしょうか。
アピチャッポン:まずは第一に自分が生まれ育った場所だからです。タイの映画製作は首都であるバンコクが中心だったのですが、そこから抜け出して、自分のアイデンティティーや文化としてのタイをいかに見せるかということに興味がシフトしていきました。
もうひとつの理由としては、その頃から映画監督としてだけではなく現代美術家としての活動も広がったこと、それからテクノロジーが進化して移動や撮影もいろんな場所でできるようになったという要因がありますね。
この展覧会自体がひとつの大きなゴーストという装置と見なすことができるかもしれません。
―あなたの作品で重要なモチーフのひとつに光と影があります。今回展示されている最初期の作品『Windows』(1999年)も、薄暗い空間の中で明滅する光を映し出した映像作品です。
アピチャッポン:それまでは16ミリフィルムなどで実験映画を撮っていたのですが、『Windows』は初めてHi8(ハイエイト)のビデオで撮った作品です。窓から差し込む光がテレビ画面に反射していて、それをビデオで撮ることによってフリッカー現象(蛍光灯やブラウン管を用いたディスプレイに生じる細かい明滅、ちらつき)を起こし点滅しているんですね。そのエレクトリックな質感と光の見え方がフィルムにはない刺激的なもので、新しい発見となりましたし、とても重要な作品になりました。
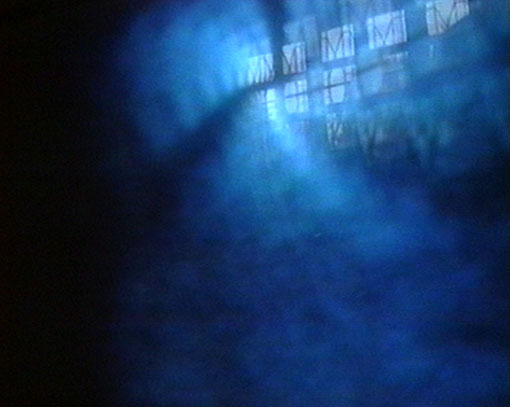
『窓』1999年 シングルチャンネル・ヴィデオ SDデジタル、カラー、サイレント 11分56秒 東京都写真美術館蔵
―フリッカー現象は、メディアを媒介にして現れる像としてのゴーストという意味合いもあり、展覧会テーマとも繋がってきますね。
アピチャッポン:はい。これは両親が経営する病院の中で撮影したのですが、自分にとってゴーストというのは、ポリティカルなメタファーとして使っている部分もありますが、他にも自分の子供時代に暮らした環境や記憶、過去という得体の知れないものに対してなど、いくつかのメタファーを意識しています。
そういう意味では、この展覧会自体がひとつの大きなゴーストという装置と見なすことができるかもしれません。ここで観客が体験するものは、実際に触ることができない視覚的なもので、すべてを持ち帰ることができません。
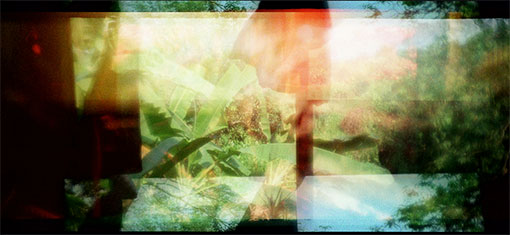
アピチャッポン・ウィーラセタクン『灰』2012年 シングルチャンネル・ヴィデオ 東京都写真美術館蔵

アピチャッポン・ウィーラセタクン『灰』2012年 シングルチャンネル・ヴィデオ 東京都写真美術館蔵
―その得体の知れないものというのは、恐怖でもあるし、一方で惹かれてしまうという相反する対象でしょうか?
アピチャッポン:そうですね。たしかに怖い部分と好奇心と両方あるのですが、もしかしたら自分にとって作品というのは、子供のときにおもちゃで遊んだり、新しい道具を使ってみたり、光を発見したりといった、純粋な喜びや楽しみから作っているところがあるのかもしれません。
―幼少期の体験ということでいえば、あなたの実家が診療所であったということは、やはり影響を与えていると思いますか?
アピチャッポン:もちろん生まれ育った場所という意味で影響はあります。ただ、それは病気や疾患といったことの哲学的な意味での影響ではなくて、病院という居場所で子供時代を過ごしたときの生活のリズムや、その空間の光や音や匂い、そういうものの影響だと思います。
「完璧な映画」というのは何だろう? と思ったんです。
―『カンヌ国際映画祭』でパルムドールを受賞した『ブンミおじさんの森』(2010年)にも発展した「プリミティブ」というプロジェクトなど、近年は、地元の若者や映画出演者たちとの協働作業を積極的に行なっていますが、それは通常の映画制作と比較すると珍しい作り方ですよね。
アピチャッポン:アートとして映像を作るときと、映画を作るときは少しアプローチが異なるのですが、映画の場合はある程度物語を自分の中で考えていて、その物語にある程度マッチする人を探します。そして、見つけたら、今度はその人たちからいろんなものをいただきながら内容を膨らませていきます。
例えば、私が長く一緒に仕事をしているジェンジラー(・ポンパット・ワイドナー)。彼女の体験や記憶、連れて行ってもらった場所などから物語が変容していくことが多々ありました。
―プロの俳優ではない一般の人と作ることが重要なことなんですね。
アピチャッポン:もちろんそうです。
―それはなぜでしょう?
アピチャッポン:プロの俳優はある意味で入れ物(容器)であり、そこに台本なりキャラクターをつめ込んで演じます。でも、私の場合はまったく違うアプローチなので、リアルに生きている人たちの中にすでに入っている本当の物語を一緒に共有して使わせてもらうというのが、とても重要な意味を持ちます。
―その協働によって、監督も彼女たちの人生に何か影響を与えているわけですよね。
アピチャッポン:まさにその通りです。出演者たちも刺激やインスピレーションを受け、制作プロセスを通して記憶や体験の探求ができるし、そこで出てきたものが、また私の映画にとって違う意味を生み出していくわけです。

アピチャッポン・ウィーラセタクン『ゴースト・ティーン』2013年 インクジェット・プリント
―その制作スタイルは徐々にでき上がっていったものなのでしょうか?
アピチャッポン:映画を作り始めた最初の頃は、自分ですべてをコントロールしようとして、スクリプトからキャスティングから、完璧に撮ろうとしていました。でもある時期から、そこの「プロセス」に含まれる重要性に気づいて、当初のプランを遂行することよりも、そこまでの過程における体験がとても重要に思えるようになったんです。もちろん映画というのは、できあがったらひとつのプロダクトになってしまうわけですけど。
―予定通りに作ると何かこぼれ落ちてしまうものがあったということですか?
アピチャッポン:というよりも、例えば人間は病気になって初めて「病気になりました」と認識しますけど、まったく病気にならないのは異常なことで、人間は本来病気になるものだと思うんです。そういう視点から映画を見たときに、「完璧な映画」というのは何だろう? と思ったんですね。
実際、問題が起きたときにこそ、想像してなかったミラクルやエネルギーが現場に生まれます。だから今は、映画を作るときは問題を楽しむというか、その問題からどんな展開が生まれるのかをすごく重要視しています。
私にとって夢というのは、究極の映画です。
―ところで、今朝は何か夢をご覧になりましたか?
アピチャッポン:うーん、今日は見てないですね(笑)。最近見た面白いものだと、どこかで洪水が起きた後だったみたいで、自分の下半身が水に沈んでいる状態で街をさまよっているという夢を見ました。
―夢日記をつけているそうですが、夢は書くともっと見るようになると聞いたことがあります。
アピチャッポン:ああ、そうなるといいですね。私は目覚めてすぐに書きとめるようにしているんですけど、朝起きてシャワーを浴びたりしているうちに、どんどん抜け落ちていって忘れてしまいます。夢を記述するというのは、何か逃げてくものを掴んでいくような、不思議な感覚ですよね。
―それこそゴーストみたいな。
アピチャッポン:そうそう(笑)。
―あなたにとって夢というのはどんな存在ですか? 日本では、「他人の夢の話はつまらない」などと重要視されない場面も多いので、おうかがいできたらと。
アピチャッポン:私にとって夢というのは、究極の映画ですね。生理学的には人間の脳は何か情報を整理しなくてはいけなくて、そのプロセスの中で夢を見ているんですけど、常に夢は受動的なものです。そういう意味では、映画館の椅子に座って見ながら受けとめる映画も夢と似ていると思うんです。

アピチャッポン・ウィーラセタクン『ナブア森の犬と宇宙船、2008年』 2013年 発色現像方式印画 東京都写真美術館蔵
―夢の本質はストーリーにあるのではなくて、さっきおっしゃったような、モヤモヤした中で掴み損ねる感じにあると思うんです。アピチャッポンさんの作品には、その夢の質感が上手く表現されていると思います。
アピチャッポン:ただ、夢と映画の大きな違いは、映画はどうしても切り取られたフレームの中でしか見られないということです。実際の夢は360度開かれていますよね。だから、もしかしたら今後VRのような技術がもたらすものというのは、今まで夢に追いつけなかった映画が、だんだん夢に近づいていくことにあるのかもしれない。
時間や場所を超えて、自分自身の意識が別のところにトラベルしたとき、それは自己なのか魂なのか。
―というと、将来的にはVR的な作品も作ってみたいですか?
アピチャッポン:自分の作品でも使いたいと思っているんですけど、まだ今の段階では技術的には未発展なので、しばらくは様子を見ています。もしかしたら、私の究極的なアート作品は、視覚ではなく脳に直接刺激を与えてイメージを投影させるものかもしれません。『メコンホテル』(2012年)という映像作品では実際そういうシーンが出てくるんですけど、おそらく実現するのも時間の問題だと思いますね。
―そういった脳科学の分野にも興味があるんですね(展示室入口に展示されたアーカイブコーナーには参考書籍として神経学者であるオリヴァー・サックスの『色のない島へ 脳神経科医のミクロネシア探訪記』がある)。
アピチャッポン:はい。それから、ネイティヴアメリカンたちが儀式のときに使うサボテンのペヨーテ(幻覚剤)が、時間や空間を行き来する道具としてとらえられていたというのも興味があります。そういった外から摂取した化学物質が脳にもたらす作用についても関心を持っています。
―では、1960~70年代のカウンターカルチャーやサイケデリックのムーブメントにも興味ありますか?
アピチャッポン:そうですね。ただ、その時代は調べる取っ掛かりにはなるかもしれませんけど、私自身がアプローチするものは、もっと時代を遡った別のところにあると思います。おそらく私が興味を持っているのは、スピリット(魂)と呼ばれているものかもしれません。時間や場所を超えて、自分自身の意識が別のところにトラベルしたとき、それは自己なのか魂なのか? ということに関心がある。
―輪廻転生はあなたの映画でもたびたび描かれていますね。日本の観客が、既存のコードにとらわれないあなたの映画に驚きを覚えつつも、どこか懐かしく感じられるのは、深いところで民話や伝説が息づく世界に類似性を見出すからかもしれません。
アピチャッポン:私が日本の漫画を読んでも共通性を感じますよ。『蟲師』とか素晴らしいですね。それから、日本の言い伝えにある、夢を食べる動物・獏の話もとても好きです。
―SNSなどに象徴されるように「今」というリアルタイムが重視される時代には、あなたの作品のようにどこかに時間が移動したり、過去や記憶を思い返したりということが逆に見直されてきたと言えるのかもしれません。
アピチャッポン:面白いコメントですね。ただ、相反するかもしれないですけど、私自身は「今」ということが重視される瞑想をすごく大切にしているんです。でも、結果的に完成したものを通して、常に過去の時間や記憶、あるいは未来にアプローチすることを大切にしている。自分自身がその矛盾を抱えながら、過去や未来を行ったり来たりしているのかもしれませんね。
- イベント情報
-
- 『アピチャッポン・ウィーラセタクン 亡霊たち』
-
2016年12月13日(火)~2017年1月29日(日)
会場:東京都 恵比寿 東京都写真美術館 地下1階展示室
時間:19:00~
※ただし、2017年1月2日、1月3日は13:00からの上映となります。
※木・金曜は夜間開館日のため展覧会は20:00までご覧いただけます。
休館日:月曜(祝日の場合は翌日、1月3日は開館)、12月29日~1月1日
料金:600円 学生500円 中高生・65歳以上400円
※小学生以下、障害者手帳をお持ちの方とその介護者は無料
※第3水曜は65歳以上無料
-
- 『アピチャッポン本人が選ぶ短編集』
-
2016年12月13日(火)~2017年1月5日(木)
会場:東京都 恵比寿 東京都写真美術館 1階ホール
時間:各日19:00~(2017年1月2日、1月3日は13:00からの上映)
※木・金曜は展覧会が20:00まで開催されているため、展覧会を鑑賞後、スムーズに上映イベントを鑑賞可能
休館日:月曜(祝日の場合は翌日、1月3日は開館)、12月29日~1月1日
料金:当日(1プログラムにつき)一般1,500円 学生1,200円 中高生1,000円 65歳以上1,000円 障害者手帳をお持ちの方とその介護者1,000円
リピーター割1,000円(本プログラム当日券または『アピチャッポン・ウィーラセタクン 亡霊たち』展のチケット提示)
- プロフィール
-
- アピチャッポン・ウィーラセタクン
-
映画作家・美術作家。1970年、バンコク生まれ。タイ東北部のコーンケンで育つ。1999年の山形国際ドキュメンタリー映画祭で短編映画『第三世界』が上映され、国際的な注目を集める。2000年に完成させた初長編『真昼の不思議な物体』以来、すべての映画が高く評価されている。2015年には新作『光りの墓』がカンヌ国際映画祭ある視点部門で上映され、大きな称賛を得た。美術作家としても世界的に活躍しており、2016年は『さいたまトリエンナーレ2016』に参加、横浜美術館『BODY/PLAY/POLITICS』展に出品、2016年12月から東京都写真美術館にて個展『アピチャッポン・ウィーラセタクン 亡霊たち』を開催。
- フィードバック 7
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-







