普段、接する機会のない文化や社会との出会いは、歴史上、つねにアーティストたちの創造性を刺激してきた。それは、その接触が、表現者に自らの属する世界のシステムや、ジャンルの本質を問い直す喜びを与えるものだったからだろう。
2015年に始まった「TURN」は、異なる背景を持った個人や社会コミュニティーの積極的な交流によって、アートの定義に揺さぶりを掛けようとしているプロジェクトだ。中核をなすのは、福祉施設やフリースクールなどにアーティストが通い、利用者や職員とのコミュニケーションを通して相互作用を生み出す「交流プログラム」。
今回は、このプログラムに参加しているファッションレーベル「writtenafterwards」のデザイナーであり、ファッション学校「ここのがっこう」を運営する山縣良和と、TURNのコーディネーターであり、障害者支援を行う社会福祉法人が運営する美術館「みずのき美術館」のキュレーターとして、福祉におけるアートとの関係を問い続けてきた奥山理子に話を訊いた。二人にとって、さまざまな背景を持った人々が交わす関係性の可能性とは何か? そこからは、人との違いをポジティブに捉え直す彼らの姿勢も見えてきた。
僕みたいに、既存のシステムにハマりたくてもハマれない子がたくさんいると思った。(山縣)
―はじめに、奥山さんが「TURN」に関わり始めた経緯を聞かせてください。
奥山:私が京都で拠点としている「みずのき」は、重度の知的障害のある方たちが暮らしている入所施設です。母の職場でもあったので、昔からよく遊びに行っていたのですが、この施設では1964年から絵画教室の取り組みが行われていて、1990年代には日本で最初のアウトサイダーアートの発信地のひとつとして注目を集めました。
―「みずのき」が草分けだったのですね。
奥山:はい。ただ、みずのきの取り組みは、選抜された入所者に、絵の先生が丁寧に描き方を教える、一般の美術教育に似たものだったんです。
―場所は異なるけれど、内容は美術大学などに近いものだったと。
奥山:そうです。でも、2000年代になると、制作者本人が独自に編み出したスタイルによって生み出された作品やそれを支える現場が全国に出てきて、同時に福祉も指導から支援へという転換期でもあったので、教育を行っているみずのきは方向性を見失いました。
2万点近い所蔵作品をどう扱うべきかも、職員だけでは見当がつかなくなってしまったんです。そんな中、2012年に「みずのき美術館」が開館したのですが、難しい領域を前に迷っていたところ、アーティストの日比野克彦さんに出会いました。

奥山がキュレーターを務める「みずのき美術館」(写真:阿野太一)
―日比野さんは、TURNプロジェクトの監修者ですね。
奥山:当時はまだTURNの枠組みはなく、日比野さんとは、アウトサイダーアートや障害のある人の表現について議論を重ねて。その中でアートと人生そのものとの関係まで視野を広げようとなり、「陸から海へ」というキーワードが生まれました。
人は海から陸に進化したけど、もう一度、海に戻ってみよう、息ができない不自由さの中でも、海に心地よさを感じる潜在的な可能性に気づけるんじゃないかと。そのイメージを言い換えたのが「TURN」です。
―なるほど。
奥山:TURNには「向きを変える」のほか、「生まれつき持っている」という意味もある。その考えを軸にした展覧会を、日比野さんを監修に迎えて行ったのですが、日比野さんから自分もTURNする現場に入りたいとの声があり、みずのきでショートステイに来ていただいて。そこで感じた手応えが東京での「交流プログラム」につながっていきました。
山縣:僕は今回日比野さんからお声がけいただいたのですが、アウトサイダーアートには、鑑賞者として心揺さぶられることが多く、もともと関心がありました。僕の運営している「writtenafterwards」も「ここのがっこう」も、ファッション業界や教育の中では完全にアウトサイダーとよく言われていたので(笑)、キーワードとしては身近だったんです。
―山縣さんはなぜここのがっこうを始められたんですか?
山縣:僕は日本とイギリスの学校でファッション教育を受けたのですが、雰囲気が全く違うんです。日本の学校では僕は挫折組だった。答えがあるものを作るのがすごく苦手で、馴染めませんでした。それがイギリスに行くと、みんなが予想していない変なものを「いいじゃん」と言う空気があって、すごく助けられたんですね。そんな場所を日本でも作ってみたかった。
―それがいまや9年も続き、注目されるデザイナーも輩出している。いわゆる「できる人」で周りを固めることもできるのに、そうされなかったのはなぜですか?
山縣:僕みたいに、既存のシステムにハマりたくてもハマれない子がたくさんいると思ったからです。そもそも僕自身、既存のイメージでのファッションデザイナーをやろうというより、この職業をもう少し広く考えているところがあります。生きづらかった自分が、ファッションを通して社会とどう関わるかということが活動のテーマとしてありました。そんな僕にとっては、彼らとの関わりから気づかされることが、とても多いんです。
僕らは普段、集中できていないし、できなくなっていると思った。(山縣)
―実際に関わられてみて、奥山さんから見た山縣さんの印象はいかがですか?
奥山:最初、ここのがっこうの授業風景を見させていただいたとき、山縣さんの姿勢がとても誠実だなと感じました。山縣さんはゴールを設定して逆算的に物事を見るのではなくて、そこにすでにあるものの膨らませ方を、つねに探していますよね。人生への不安を抱えた学生さんと向き合いながらも、話している内容は創造的なファッション論なのが面白いです。
―現在、山縣さんは、交流プログラムのひとつとして、鹿児島県の障害者支援施設「しょうぶ学園」との交流を行なっています。これは、どのように始まったのですか?
山縣:しょうぶ学園と出会ったのはTURNと関わる前で、ここのがっこうの学生から、そこで行われている「nui project」を教えてもらったことでした。これは「針一本で縫い続ける」行為を通して、人の個性を発見するものなのですが、ぜひ現場に行ってみたいと思って。
というのも、そのころ僕は神戸ファッション美術館で行われていた『BORO(ぼろ)の美学 ―野良着と現代ファッション』という展覧会に参加していたんです。これは、青森の民俗学者である田中忠三郎が収集した東北の伝統的な衣服をテーマにした展覧会だったのですが、そこで「刺し子」が扱われていたんです。現代において、そんな刺し子のような存在を精神的に継承しているのはnui projectじゃないかと思って。
―刺し子とは?
山縣:布に糸で幾何学的な模様を描いていく手芸の分野です。田中さんによると、刺し子というのはお母さんが家族の寝静まった真っ暗な中でずっと刺していたもので、その行為はある種、日々の辛さを忘れさせる精神的な営みだったようです。それを知りたいと思っていたときに、ちょうどTURNから声をかけていただきました。
―しょうぶ学園では、どんな交流を行われているんでしょうか?
山縣:最初は学生と施設に行き、その空気を感じることから始めました。その後、ワークショップをやりたいと思ったのですが、なかなか何をすべきかわからなかったんです。
でも、施設にいる方たちの没頭する力を見ると、僕らは普段、こんな風に集中できていないし、できなくなっていると思った。それで、決められた時間、事前に何を作るかを決めずに、「ひたすら行為に集中する」というワークショップにしました。
―すごくシンプルですね。
山縣:この活動に限らないですが、僕はファッションの本質に触れたいんです。TURNに共感したのも、ビジュアルや作られているものが、「何かを纏うこと」や「身体との接触」のような、ファッションの本質に近い要素が多くあることでした。いまファッションは、業界全体がシュリンクしていて、悲壮感がすごいんです。
でも、それも仕方なくて、大量生産・大量消費に走り過ぎた結果、過剰供給すぎるんですよね。その土壌で話していても、ラチはあかない。もっと本質的な部分に戻るべきだし、そうじゃないと、ファッションの魅力が伝わらない。TURNやnui projectの取り組みは、業界にとってもヒントが多いはずです。
奥山:かつて、しょうぶ学園の施設長の福森伸さんが、「針と糸を持ったら、みんな何かやり始めるんだよ」とおっしゃったんです。それを聞いた後、ある日みずのきでも、ビーズに糸を通す遊びをしたとき、手の自由がきかない入所者の方が、ものすごく器用に針で通していったことがありました。
山縣:すごいですね。
奥山:すごいですよね。何でこんなことできるんだろうと、私もとても驚いて。でも、山縣さんがおっしゃるように、縫うことには人の本質的なものがあるのかもしれない。
しょうぶ学園さんとしても、その活動に秘められた可能性は、もっとあると感じておられると思うんです。それを山縣さんと一緒に考えられることで、施設にとっても発見があれば良いなと思います。
ファッションを、人間の生命のリズムとは違う場所で、無理やり変化させていることに違和感がある。(山縣)
山縣:福森さんは、「入所者は瞬間の連続を生きている」ともおっしゃっていました。過去や未来より、その瞬間の連続を生きていると。それはある意味、ファッションの究極だと思うんです。ファッションを突き詰めて考えると、「変化の連続性」ということがある。
もともと「流行」、つまり「流れる行方」という意味もあるし、変化を受け入れ瞬間を生きること。しょうぶ学園さんはそんなファッションクリエイションの究極をやっている。
―逆に言えば、そうした有機的な変化に、ファッション業界では出会えない?
山縣:これは僕も含めての問題ですが、変化してはいるんです。でも、大きく言えば、資本主義的に行き過ぎたものになっていて、自然的に変化しているというより、人間の生命のリズムとは違う場所で、市場原理によって無理やり変化させているんです。そこに違和感がある。
―動物的ではないというか。
山縣:数十年前までは、変化がもっとゆっくりでした。たとえば年2回のパリコレでデザイナーが発表して、半年後に一般にも影響が現れるという流れだった。でも、ファストファッションができたことで、パリコレの2週間後には、コピーブランドが類似した商品を出してしまう。
つまりコピーとオリジナルが逆転して、頑張ってクリエイションした人が損するシステムになっているんです。そこではデザイナーもサイクルを早めざるを得ず、結果、デザイナーは疲れてしまった。クリスチャン・ディオールのデザイナー、ラフ・シモンズが最近ブランドを辞めた理由もそれです。
奥山:福祉にも似た状況があります。システム化されて、人の有機的な部分が削ぎ落とされてしまう。たとえば、診断名や数値に個人の特徴を置き替えたり、「発達障害」という便利な分類をつけることで、サービスを当てはめやすくする。
たしかにその方が運営はしやすくなると思うのですが、福祉なのに、どうして人をすぐに数値や障害特性に当てはめるんだろうと、すごく思います。だから、TURNがやるのは施設や福祉の新しいモデルを作ることじゃなくて、あらゆる社会システムをもう一度、有機的な方にほぐし直していくこと。アートだからできるんじゃないかと思うんです。
社会は自分の外にあって隔絶されているものだという意識になって、絶望感を抱いていた。(奥山)
―ここのがっこうでの山縣さんの教育は、生徒自身のルーツを問い直し、それを制作に活かすものです。そのようなプロセスを大事にされているのは、なぜでしょうか?
山縣:自分がなぜか自然にやってしまう行為ってありますよね。僕はクリエイションを、それに近づけていきたいんです。でも、大人でそれが自然にできる人はなかなかいない。だから、自分はどこから来たのか、何を見て来たのかとあらためて問うことで、純度の高いクリエイションを目指しています。
僕自身、自分でも意識していないことに、影響を受けていることはよくあって。たとえば、母とあまり仲が良くなく20年以上会っていなかった伯父さんと再会したのですが、実は僕が驚くくらいエキセントリックな女装癖を持った人だったんです。おばあちゃんからよく「お前に似ている」と聞いていたのですが、なるほどと(笑)。しかも、警備員をしながら詩を書いていて。
奥山:かなり面白そうな方ですね。
山縣:なぜ詩を書いているかというと、僕の親戚に詩人の尾崎放哉(1885年生まれ。自由律俳句で著名)がいて、それに影響を受けているんです。尾崎の生誕の地は、僕の実家のすぐ裏手で、小さいころから不思議な雰囲気を感じていた場所だったのですが、尾崎の存在をずっと知りませんでしたし、20代後半になって初めて女装癖のおじさんにそのことを聞いて、びっくりしました。
尾崎は世捨て人として知られていて、当時、地元ではあまりいい評判ではなかったみたいです。そういうこともあってか、いろいろ苦労したのか、母親はそのルーツを全然語る人ではなかったです。僕はそういった自分の知らなかったルーツに向き合ったもの作りを大切にしたいと思い、2015年の春夏シーズンでは、尾崎の生涯をテーマとしたコレクションを発表しました。
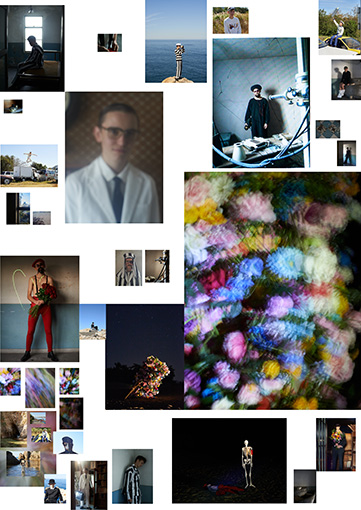
written by 2015SSコレクション。尾崎放哉の人生をテーマに、「漂白の詩人」をイメージして作り上げた
奥山:自分のルーツや現実に向き合いきれず、心身を壊したりしてしまう方は多いはずです。実際、すごく難しいし、どうしても深刻になってしまう。でも、山縣さんの教える姿を見ると、こんな風に深刻にならず、自分を痛めつけるような方法ではない向き合い方があるんだと感じます。向き合い方こそ、想像力が発揮できる部分なんだと。
山縣:僕は悲観的ではあるのですが、物悲しいエピソードもどこか面白おかしく感じちゃうところがあるんですよね。クリエイションってそういうルーツは積極的に掘り返した方が面白かったりしますし、説得力にもなる。
ブランド名の「writtenafterwards」も「あとがき」という意味ですが、僕のクリエイションでは、悲観的でありながらも楽観的で詩的な要素や物語、書き手の意味を込めた過去分詞の「written」の感覚を大事にしていて、そういうのもいま考えると、自分のルーツからの影響が少しはありそうだなと思いました。
―ルーツで言うと、奥山さんがこれだけアートに関わるようになったきっかけは?
奥山:じつは私、不登校だったんです(笑)。原因はひとつではなくて、もともと同年代に馴染めなかったんですけど、思春期に目指したいことや、日常生活の複雑なことのバランスが崩れて、食事が取れなくなったり、学校に行けなくなったりしてしまいました。そのとき、社会は自分の外にあって隔絶されているものだという意識になって、すごい絶望感を抱いていたんです。
奥山:それで、母のいたみずのきに通い始めました。さらに、当時ちょうど、みずのきでも絵画や彫刻ではない、いわゆるリレーショナルな表現をする若いアーティストと関わりが生まれていて、日常生活の何気ない行為や関係性がアートになり得ることに衝撃を受けたんです。そこから、アートの現場に関わるようになったのですが、関わりながら自分が再構築されていく感じだった。社会の一員になれたという思いがしたんですよね。
人生のつまづきや生きづらさという、一見ネガディブな「はずれ」が、表現の世界では好転する。(山縣)
―ご自身の経験を通して、奥山さんは、美術館で展示されたり、市場で売買されたりする作品と、みずのきなどで触れている作品の間に違いはあると思いますか?
奥山:世の中で志向される主流とは異なる方法を探している私たちがやるべきなのは、市場主義ではない、新しいアートの受け止められ方を築いていくこと。それは、アートの論理だけではできなくて、やはり福祉の問題でもあるので、いろんなジャンルの人と関わりながら、考えていきたいです。
山縣:外に開いていく努力は大切ですよね。ファッションで言うと、僕もyohji yamamotoやCOMME des GARÇONSには影響を受けましたが、彼らの時代の目的意識は、ファッションの領域の内部で、いかに世界の中心地に入っていくかだったと思うんです。
そして、当時はその中心に求心力があったので、ほかのジャンルの人々がどんどん関わってきてくれた。でも、いまはそれだけだとダメで、自分たちからファッションの外に出て行って、積極的にファッションというジャンルの意味や価値、社会に貢献できることを示さないといけないと思います。
奥山:現状に満足しているアーティストって、いないと思うんです。自分自身で開拓したい人は多いはずで、そうしたエネルギーをいろんな場所から集めてつなげるのが、TURNや私の役割だと思います。
その意味で言うと、TURNの意義や使命は、プロジェクトが始まった当初とは、まるで違うものにまで広がっている。「私って何だろう」とか、「社会と関係するって何だろう」とか、そうした根本的な問題をいろんな角度から掘り下げて、深め、広げたい。まだ試行錯誤の日々ですけど、最後はそれこそ、自分のクリエイションそのものだと呼べるものにしていきたいです。
―山縣さんとのある対談の中で、哲学者の鷲田清一さんが、「ファッションって人生の『はずれ』を『はずし』に裏返すもの」とおっしゃっていたんです。今日は、お二人の人生と活動にも、TURNにも、似たところがあると感じました。
山縣:鷲田先生、良いことを言いますよねえ。ファッションの「はずし」ってポジティブな意味なんです。人生のつまずきや生きづらさという、一見ネガディブな「はずれ」が、表現の世界では好転する。ファッションやアートには、その「はずれ」を「はずし」にする機能があるということですよね。
それは、まさに僕がやりたいことだし、やるべきことだとも思います。TURNでのプロジェクトも含めて、人とは異なった部分をポジティブに裏返せる場所というものをどんどん作っていきたいです。
- イベント情報
-
- 『TURNフェス2』
-
2017年3月3日(金)~3月5日(日)
開室時間:9:30~17:30(入室は閉室の30分前まで)
会場:東京都 東京都美術館1階 第1・第2公募展示室
- プロフィール
-
- 山縣良和 (やまがた よしかず)
-
1980年、鳥取県生まれ。大阪の服飾専門学校を中退、2005年にイギリスの名門セントラル・セント・マーチンズ美術大学ウィメンズウェア学科を首席卒業。2015年『LVMH Prize』に日本人初ノミネート。ジョン・ガリアーノのデザインアシスタントを務める。帰国後、2007年に自身のブランド「writtenafterwards」をスタート。自由で、本質的なファッションの教育の場として「ここのがっこう」を開催している。
- 奥山理子 (おくやま りこ)
-
アーツカウンシル東京「TURN」コーディネーター、みずのき美術館キュレーター。1986年京都府生まれ。母の障害者支援施設みずのき施設長就任に伴い、12歳よりしばしば休日をみずのきで過ごす。2007年以降の法人主催のアートプロジェクトや、みずのきの農園活動にボランティアで従事した後、2012年みずのき美術館の立ち上げに携わり、現在企画運営を担う。企画、制作した主な展覧会に『ayubune 舟を作る』(2014年)、『TURN / 陸から海へ(ひとがはじめからもっている力)』(2014-2015年)、『共生の芸術展「DOOR」』(京都府委託事業、2014年、2015年)、『みんなのアート -それぞれのらしさ-』(岐阜市委託事業、2015年)など。
- フィードバック 2
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-











