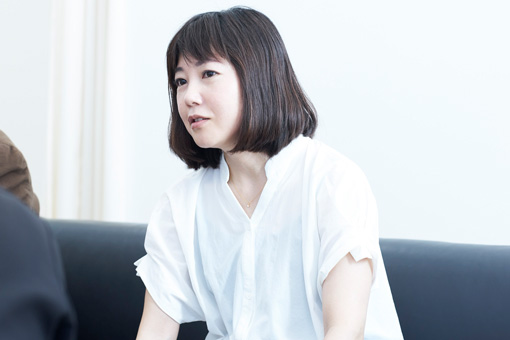同じく2016年秋に公開され、大きな話題を呼ぶと同時に、年度末には数々の映画賞に輝くなど、高い評価を獲得した2つの日本映画――『永い言い訳』の西川美和監督と、『この世界の片隅に』の片渕須直監督の対談が実現した。
今年2月、ともに出席した『毎日映画コンクール』の授賞式で、初めて言葉を交わしたという二人。実写とアニメという手法の違いはもちろん、性別も年代も異なる両者は、お互いの映画をどんなふうに見たのか。さらには、この2作をはじめ、作品的にも興行的にも、大きな盛り上がりをみせた、昨年の日本映画の状況に対し、二人はそれぞれどんな思いを抱いているのか。
奇しくも『この世界の片隅に』の舞台である広島県の出身である西川と、彼女の作品をすべて見ながら、その核心に「嘘」があることを見抜いた片渕。まったく違うようでいて、随所で思わぬ意気投合ぶりをみせる対談の行方は? 日本映画の未来が、ここにある。
人の心という迷路に分け入っていくのが、西川さんはお好きなんじゃないかなって思いました。(片渕)
―片渕監督は、西川監督の映画『永い言い訳』を、どんなふうにご覧になられましたか?
片渕:以前から西川監督のことは存じ上げていたんですけど、今回の『永い言い訳』を見て……「この主人公は、なんでこういう人柄なんだろう?」っていうことを思ったんですね。それで、1作目の『蛇イチゴ』(2002年)から、西川さんの作品を改めて遡るように全部見させていただいたんです。
西川:ありがとうございます。
片渕:そうしたら、『永い言い訳』で本木雅弘さんが演じている主人公は、「嘘をついている人」なんだなっていうことが、だんだんわかってきたんです。彼は不倫をしている役でしたけど、西川さんは嘘をついている人物のなかにある真実みたいなものを、撮り続けているんじゃないかなって思って。
―なるほど。
片渕:最初、主人公はあそこまで女性に対してゆるくなくてもいいだろうって思ったんです(笑)。でも、ああいった振る舞い自体に、彼が自分の「正体」に対して嘘をついていることを感じさせて。ある種、自分を装って生きている人ですよね。
片渕:で、そうやって見ると、『蛇イチゴ』の宮迫(博之)さんとか、『ディア・ドクター』(2009年)の(笑福亭)鶴瓶さんとか、みんないろんな類の嘘つきなんですよね。嘘をついている人だからこそ、最後の瞬間にポロッと真実が出てきたときに、「ああ、やっぱり人の心って、こうありたいよね」っていう思いが、作品としてちゃんと込められているように感じて。それがすごく印象的でした。人の心というのは迷路のようになっていて、そこに分け入っていくのが、西川さんはお好きなんじゃないかなって思いました。
嘘で覆い隠したもののなかに、自分自身の本当の姿があるような気がしているんです。(西川)
―西川さん、いかがですか?
西川:そうなのかなあと思います。自分もやっぱり、いろんな嘘をついて生きているし、嘘をつかなくてもいいところで、なんとなく嘘をついてしまったり、見栄を張ってしまったりすることがあるので。
その裏に潜んでいるものというか、嘘で覆い隠したもののなかに、自分自身の本当の姿があるような気がしているんですよね。それは私だけではなく、人間みんなそうだとは思うんですけど。でもやっぱり、自分自身の嘘つき体質が反映されているのかな、とは思います(笑)。
―本木さんが演じている主人公のモデルは、西川さんだという説もありますが。
西川:そうですね(笑)。自分に程近いところはありますし、今回の作品は、自分がこれまで生きてきたなかにおける、生活とか人生の実感を投影したところがあります。ただ、それを映画監督という設定にすると、あまりにもストレートにすぎるので、小説家という形をとって……あと、女性を主人公として描くよりも、男性で描くほうが思いきれるところもあったので、こういう形になったんです。

本木雅弘演じる主人公・衣笠幸夫 / ©2016「永い言い訳」製作委員会
片渕:僕、実はいちばん映画監督を感じたのは、『ディア・ドクター』で鶴瓶さんが演じているお医者さんだったんですよ。
西川:ああ……はい。
片渕:西川さんはいざ知らず、自分の立場で言うと、映画監督って、名乗ろうと思えば誰でも名乗れちゃうんですよね。資格を取る必要もないし、正規の教育を受けている必要もないので。
西川:ええ、そうですね。
片渕:で、鶴瓶さんが演じていたニセ医者は、なんとなく見聞きしたことのなかで、「このときはこうだな」「このときはわからないから、ちょっと調べよう」っていうことをやっているじゃないですか。いざとなったら、看護師さんとか、製薬会社さんの営業の人とか、その場においてはプロフェッショナルな人たちが、彼のことを支えてくれるんですよね。で、よく考えたら、映画も、それと同じように作られているなって思って。スタッフの存在ですよね。だから僕は、あのニセ医者さんが、全然嫌いになれないんですよ(笑)。
西川:ふふふ。
肉親たちが話していた、かつてあった美しい広島の風景というのを、初めて見た感じがしたんです。(西川)
―片渕さんが、あのニセ医者の役が嫌いになれないというのは?
片渕:こういうやつがいてもいいだろうって思ってしまったんです(笑)。もちろん、お医者さんの場合は、生命に関わることだから問題ですけど……でも、「生きている人を楽しませる」っていうことで言うならば、あのニセ医者さんの在り方って、すごく映画監督に近いなって感じたんです。そう思うと、あの映画は、ものすごい心当たりがあって、とてもグサグサくる。
西川:あの映画は、まさにそういうところもあったんです。私が2本目に撮った『ゆれる』(2006年)という映画があるんですけど、それが思っていた以上に評価されてしまったんですね。自分としては、デビューから2本目だったので、何の手応えも確信もなかったんですけど、世の中的に持ち上げられてしまったところがあって。
その違和感から、次はニセモノの話を作りたいなって思って書いたところがあるので、まさに今、片渕さんがおっしゃられたとおりというか……でも、片渕さんがおっしゃってくださったように、あのニセ医者をなにか目に見えない形で、「人間の心に作用する仕事」っていうふうに解釈すれば、すごくこう、自分自身も救われます。
―一方、西川さんは、片渕監督の『この世界の片隅に』を、どんなふうにご覧になられましたか?
西川:私は広島の出身で……市街の中心地ではないですけれど、私の家族も原爆を体験しておりますので、子どもの頃から、そういう話は嫌というほど聞かされて育ってきたんです。だから女性の主人公で、戦時下の広島を描いた作品を見るということに対して、ある種のしんどさが、自分のなかにはあって。そういう意味で、ちょっと腰が重い部分があったんですけれど、後輩のディレクターが、「とてもいいですよ」と言っていたので、早い時期に観させていただいて……。
―広島で生まれ育っただけに、当初は戸惑いもあったと。
西川:やっぱり、いろんな思いがありました。すごく難しいテーマだし、繰り返し描かれてきたテーマだからこそ、それを今の時代に作る難しさもあるでしょうし。いろいろと複雑な思いを抱えつつ観に行ったのですが、始まってすぐにですね……のんさんの第一声から、その広島弁のイントネーションの確かさと、あのちょっと抜けた感じのしゃべり方に、これまでの戦争もののヒロインとは少しトーンの違う現代性みたいなものを感じたんですね。
―ほう。
西川:始まってすぐのシーンで、すずさん(のんが声を担当した『この世界の片隅に』の主人公)が砂利船に乗って、市内に行かれるじゃないですか。あれは、本川という川でそこから空撮のようなアングルでパンアップして、相生橋が出てきて、そのあと元安川と合流して、原爆ドーム、もとの産業奨励館の緑の屋根が見えたときに……自分がもう聞くのも嫌だなと思っていた、肉親たちが話していた、かつてあった美しい広島の風景というのを、初めて見た感じがしたんです。
自分の家族のふるさとを、初めてオールカラーのきれいな形で見たような気がして。そこで、自分でも驚くほど自然なノスタルジーというか、自然な感動があったので、とても物語に入り込みやすかったんですね。それからサンタクロースが出てきて……あれは昭和何年でしたか?
片渕:昭和8年の12月ですね。
西川:そのサンタクロースを見たときに、これは、いわゆる戦争ものとして、「戦争はいけませんよ」「原爆は悲惨ですよ」っていう固定的な観点からではなく、まずはその時代の生活図鑑を見るように、人々の生活の移ろいを見ていけばいいのではないかという、気楽さのようなものを感じたんです。そこから腰が重かったことも忘れて、「ああ、こんな暮らしがあったんだな」とか、一つひとつに発見と楽しさを感じながら見させていただいたように思います。
絵で描くんだったら嘘がつけるって思って、アニメーションに興味を持つようになったんです。(片渕)
西川:ひとつお訊きしたかったんですけど、ひょっとして片渕さんは、もともとアニメーションではなく、実写的なものに対してカメラを回すところから、映像を始めているのですか?
片渕:そうです。母方の祖父が、映画館をやっていたもので……僕の母親も、35ミリの映写機を回せるとか言っていて、もう80歳をすぎているんだけど、映画館に連れて行くと、「光源は何を使っているの?」とか知りたがるんですよ(笑)。そういう環境だったので、高校の頃は、8ミリ映画のカメラで、身の回りのものを撮っていました。
西川:そうだったのですね。
片渕:その頃は、真剣にアニメーションをやろうなんて思ってもなく、映像系のなにかをやりたいという気持ちはあったんですけど……さっきの西川さんの話じゃないですけど、僕は嘘をつくのが不得意だなって思ったんですよね。

『この世界の片隅に』 ©こうの史代・双葉社 / 「この世界の片隅に」製作委員会
西川:(笑)。
片渕:嘘をつくのが不得意なら……昔、NHKで『自然のアルバム』(1960年~1985年にかけて放送された教養番組)という番組があったんですけど、北海道にある1本の木に棲むフクロウが、卵を産んで、雛が孵って巣立ちをするまでを、ずーっと映像でとらえていたりしている番組で。漠然とそういう仕事をしたいと思っていたというか、そういう距離感で、自分は実写というものをとらえていて。実在の人物が出てきて、そこで嘘をつくっていうところまで、うまく自分の発想が辿り着かなかったんですよね。
―片渕さんと実写の距離感は、フィクションを撮るというものではなかったと。
片渕:だけど、絵で描くんだったら嘘がつけるって思ったのが、高校3年生ぐらいの頃で。そこから急に、アニメーションに興味を持つようになったんです。
―なるほど。そのあたりは、他のアニメーション作家と、少し違うところなのかもしれないですね。
西川:他のアニメーション作家の方については、正直私にはわからないんですけど、『この世界の片隅に』を観て、やっぱりこれは実写じゃないほうがいいと思いました。私が映画とか小説を見たり読んだりして、「あ、いいな」って思う瞬間って、「これは映画でしかできないだろう」「この表現は小説でしか無理だよな」「詩でしか無理ですよね」っていうものが垣間見られたときなんですよね。だから、そういうものをなんでもかんでも実写映画にするのは、すごくもったいないっていう……まあ、成功するケースもあるんだけど。
―わかります。
西川:『この世界の片隅に』を観たときに、これはどんなにCGの技術が発達していて、達者な俳優たちがいたとしても、生身の人間でやるよりは、アニメーションという表現でやられたことが、とてもよかったんじゃないかと随所で思ったんです。もともと漫画という原作があったにしても。そう、漫画と映画でいちばん違うのって、時間の流れがあることだと思うんですよ。
アニメーションだと、なにを描いても同じ「絵」なんですよ。(片渕)
―漫画と映画のいちばんの違いは時間の流れがあることだと。詳しくお話いただけますか?
西川:この映画を観たときに、本当にスピード感があるなあと思ったんです。まるで日記を読むように、どんどん日々が過ぎていく。だから、実はものすごい情報量なんですけれど、それがアニメーションならではの人物の動きであるとか、そういうものの重なりによって、すべてがスーッと入ってくる感覚があるんですよね。
―確かに。
西川:それでいながら、実写では表現できない視覚的な美しさや柔らかさも詰まっているような感じがして。私にはアニメーションはできないし、演出の仕方もわからないですけど、この世界観を表現するために、アニメという表現媒体があって、本当によかったんだろうなと思いました。
片渕:アニメーションだと、なにを描いても同じ「絵」なんですよ。実写の場合だと、撮影できないところは、CGになって、はめ込みのようになってしまうじゃないですか。ところが、アニメーションの場合は、戦艦大和を描くのも、すずさんを描くのも同じなんですよね。それだけでも、この作品は、アニメーションがいちばん向いていると自分たちで思うには十分でした。
でありつつ、さっきお話したドキュメンタリー趣味みたいなものも持ち込めたかなとは思っていて(笑)。西川さんが、「日記を読んでいるみたい」とおっしゃられましたけど、実はすずさんの日記っていうのを書いていまして……。
西川:えっ、どういうことですか?
片渕:映画では描かれていない、原作にも描かれていない平坦な日々でも、その日なにがあったかっていうのを書き綴っているんです。そうすると、「今日は晴れ」で終わる日とかも、結構あるわけですけど、人生っていうのは、そういうものだなって思って。「今日は晴れ」とだけ書いて終わらせてしまっていたときに本当は目に映っていたものを覚えていられたら、どんなに幸せだろうって思うんですよね。

『この世界の片隅に』 ©こうの史代・双葉社 / 「この世界の片隅に」製作委員会
西川:ああ……わかります。
片渕:そういうことが本当は描きたくて、ドキュメンタリー的な体裁を取り入れたんだろうなって感じていて。戦艦大和が入港してきたのを描くシーンで、その日の夕景が、どれだけきれいだったかを描けたらいいなあっていう気持ちはありました。そういう表現ができたのが、自分としては今回よかったところですね。
やっぱり、存在感ですよね。それを出すためには、事前調査と細かなディテールが必要で。(片渕)
―お二方の共通点として、事前の綿密なリサーチと細やかなディテールがあるように思いますが、それについてはいかがでしょう?
片渕:やっぱり、存在感ですよね。それを出すためには、事前調査と細かなディテールが必要で。
西川:そうですね。それをどこかで忘れなきゃいけない瞬間もあるんですけど、フィクションを作っていくうえでの基本姿勢として、なくてはならないものだと私は思っています。逆に言うと、取材したり調べていくことで発想が生まれてくることも多々あって。
さっき挙げていただいた『ディア・ドクター』の場合、なんらかのニセモノの話をやるにあたって、「どの職業だったら一般の人が身近に感じてくれるだろう?」と考えて、お医者さんになったんです。だから撮るまでは、僻地医療の問題を考えていたわけではなくて。取材をしていくなかで、どういったコミュニケーションがその現場にあるのかっていうことがわかっていったことが大きかったんです。
―なるほど。
西川:今回の『永い言い訳』も、「血の繋がっていない子どもと暮らす」という設定をとったのは、私自身は子どもがいないので、赤の他人の子どもと何日か暮らしてみたら、どんな感覚があるんだろうとか、保育園に行く子どもは、どういう生活をしているのかっていうことを、自分で実際に体験してみたのが大きかったんです。
西川:そこから、「血の繋がらない子どもに対して、大人はどういう感情を抱くのか?」「自分のなかからどんな感情が出てくるのか?」ということがわかってきて。そうやって、それを自分の物語作りの筋肉にしているんです。だから、そういう意味では、『この世界の片隅に』とは、まったく違うのかなって思っていて……。
小説を先に書いたのは、事前に細かく設計したかっただけなんです。(西川)
―『この世界の片隅に』が、西川さんの制作手法とはまったく違う作られ方をしているというのは?
西川:『この世界の片隅に』は、非常に綿密に調べられているんだろうなという信頼感があるんです。江波のほうでは、こんな暮らし方をしてたんだなとか、福屋のまわりは……福屋っていうのは、広島にあるデパートなんですけど、そのあたりは、こんな感じだったんだろうなというふうに見せてくれる。その裏にある綿密なリサーチに、全面的に頼りながら見ていく頼もしさのようなものがあって。それが本当に楽しかったんですよね。
片渕:それはやっぱり、リサーチしたうえで、それを自分たちの体感まで落とし込んだことが大きかったように思います。「広島とか呉に、何度もロケハンに行ったんですよね?」って訊かれるんですけど、調べもののためではなくて、広島の街の地理や歴史を頭に入れたうえで、現地に行っているんです。つまり、「ここからここまで歩くと、こんなにくたびれるんだ」とか、「ここは上り坂で結構息が切れるんだ」とか、そういうものを味わいに行ったように感じているんですよね。
―現地に行ったのは、実感値を高めるためだったと。
片渕:あと、あの原作漫画って、ちょっと変わっていて。広島のどこなのか、ほとんど明示してないんですよ。「中島本町」って書いてあるけど、そこがのちに平和記念公園になったとは、ひと言も書いてなくて。それは江波の町に関してもそうですけど、それがどこにあるのか、まったく読者に教えてくれないんです。
西川:ああ、なるほど。私は広島出身なのでわかりましたけど。
片渕:そう、広島出身者には、かなりわかるようなんですけど、僕らは最初まったくわからなかったんです。だから、漫画の読解だけで、ものすごく時間が必要だったんですよね。
―そういう意味では、西川さんの場合、今回は映画の制作に入る前に、原作小説を自らお書きになられているわけで。のちに小説化することはこれまでありましたけど、映画よりも先に小説を書くというのは今回が初めてですよね?
西川:そうですね。でもまあ、要は事前に細かく設計したかっただけなんです。最初にシナリオから入ると、どうしても氷山の一角を書くことになってしまうところがあって。シナリオを書くときは、いろいろ用意して取り揃えたものをあえて全部書かずに、限定されたものを書くことを目指すんですよ。映画なので、2時間前後の話にしなくちゃいけないし、いろいろ書きたいエピソードがあっても、尺にはまるように物語作りをするんです。
―なるほど。
西川:そういうことを今までずっとやってきたんですけど、今回が5作目の長編映画になるので、ちょっとこれまでとは違うアプローチをしてみたいなと思って。
脚本を書いているときは、夢がいっぱいなんですよ。(西川)
―小説を先に書くことで、「『豊かな無駄』をゆっくりと熟成し、登場人物や物語を練り込む時間が取れたと思っています」と、西川さんは制作発表時にはコメントされていました。
西川:そうです。だから、本当に取るに足らないエピソードもあって、それこそ小説のなかには、主人公が書いた日記の章なんかも出てくるんですけど、それは本来、映画にはならないんですよ。
ただ、そうやって書きたいものを書きたいだけ書くなかで、本来映画になるはずがないと思っていたものが、実は映画になるかもしれないし……そういう実験も含めて、誰からも文句を言われない形で、1円もかけずにやるためには、やはり小説しかないなと思って(笑)。小説という形で、まずは一度、風呂敷を広げてみた感じなんですよね。
片渕:今の話は、すごくよくわかります。脚本は脚本としての読み下し方というか、テンポがあるから、そこに細かいディテールみたいなものはいらないんですよね。だから、すずさんの日記のような、実際に作ったシーンとシーンのあいだのイメージというか、すずさんはこうやって生きていたんだろうなって思えるようなものを、いっぱい用意したんです。
そうすることで、ある瞬間だけを切り取っても大丈夫なような強度を保てたというか。実際に使ってはいないけど自分のなかに存在するイメージが支えになったんです。それはある意味、究極の嘘のつき方かもしれないですよね。人に信じてもらいたい以上に、自分が信じてしまうっていう(笑)。
西川:まさにそうだと思います(笑)。
片渕:やっぱりね、脚本を書くっていうのは、夢を広げる作業なんですよ。実際に映画を撮るというのは現実との闘いになっていくので。現実との闘いに終始してしまったら、映画監督なんて、まったくつまらない仕事になってしまう(笑)。
西川:はははは。
片渕:だから、その前に、どれぐらい夢を抱けるのかっていうのは、すごく大事なんですよね。
西川:そうなんですよ。脚本を書いているときは、夢がいっぱいなんですよ(笑)。実際の現場になると、あれもダメこれもダメっていう現実的な制約が出てきて……それこそ実写の場合は、お天気のいい、きれいな陽の光のなかで撮りたいと思って3年前から準備しているのに、撮影当日が雨だったりするんです。
だけど、その合間を縫って撮るっていうのが、私の抱えている現実なんですよ。そういうことを考えると、アニメーションはいいなっていう(笑)。もちろん、アニメはアニメで、また違う現実との闘いがあるとは思いますけど。
片渕:(笑)。そういう意味で言ったら……先ほど、西川さんがのんちゃんの話をしてくださいましたけど、自分たちで絵を描く分には、自分たちの夢を自分たちの裁量で叶えていくことができるんです。でも、音に関しては、かなり難しいところがあって。
―CINRA.NETでは、劇場公開時に音楽を担当されたコトリンゴさんに取材したのですが(のん主演『この世界の片隅に』の立役者 コトリンゴインタビュー)、何度も「難しかった」とおっしゃっていたのが印象的でした。
片渕:そこに関しては、自分たちでアプローチできないところが、どうしても残ってしまうんです。だけど、『この世界の片隅に』に関しては、音楽もそうですけど、特に声を担当してくれた役者さんたちが、あまりにも自分たちの思ったとおりの声で演じてくれたんですよね。
自分たちの夢の世界というか、自分たちの想像力のなかから直接出てきたような声で演じてくれて。それは僕だけではなく、実際に絵を描いているスタッフたちも、同じことを言っていましたね。だから、それは本当に得難い感じというか、まさしく奇跡のようでした。
競いあってもしょうがなくて、こんなにたくさんいいものがあるんだから、それで幸せじゃないかと。(片渕)
―『君の名は。』をはじめ、『シン・ゴジラ』が大ヒットを記録するなど、去年は非常に邦画に勢いがありました。そうやって映画館に多くのお客さんが足を運んでくれる状況のなか、今後お二人はどんな映画を作っていきたいですか?
片渕:そうですね……これまで、アニメーションというのは、ある種イロモノとして存在していて。実写で真面目な映画を作ってらっしゃっている方々のなわばりのなかに入っていって、そのお客さんやスクリーンを奪うというか……そういうふうに、ちょっと苦手に思われていたところが確実にあったと思うんですよ。
実写の監督さんで、アニメはちょっと距離があるっていう意識で見られている方も、実際いたりして。ただ、そうではなく、相乗効果が成り立つようなところまで、去年はいったんじゃないのかなって思うんです。
―実写とアニメの間で相乗効果があったと。
片渕:映画館にお客さんがやってきて、「こういうものもあるなら観よう」というふうに、実写を観にきた方がアニメーションを観る、アニメーションを観にきた方が実写を観るという具合に。そうやってそれぞれの作品を観たときに、その質から言っても距離感がなくなってきているんじゃないのかなっていう実感があったんです。アニメは「オタク向けである」という見方から、シネフィルの人たちも含めて、より多くの人たちに観て、感じてもらえるようになったというか。
―確かに、それはあるような気がします。実写映画の監督として、西川さんは、どんなふうに感じていますか? 興行面から言うと、なかなかアニメは強力ですが。
西川:でも、今は本当に、実写とアニメ、特撮とかの境がなくなって、同じ「映画」という土俵の上に立っているんだなって感じますし、そのバリエーションこそがいいなあっていうふうに思うんですよね。
片渕:そうなんですよ。競いあってもしょうがなくて、こんなにたくさんいいものがあるんだから、それで幸せじゃないかと。だから、先日の『毎日映画コンクール』の授賞式のように、実写とアニメーションをひとつの場で評価していただいたのは、すごくよかったような気がします。
西川:そう、だから逆に言うと、これまでの日本の映画界は、非常に貧しかったんだと思います。ストーリーテリングの能力や才能は、漫画とアニメの世界に全部持っていかれているのかなっていうコンプレックスが、実写映画を撮っている側には逆にあったんです。
今はそういう境界がなくなりつつある状況で、お互いがお互いのものを近い距離感のなかで意識しながら制作することで、またなにか違ってくるのかもしれないなあと思います。そういう意味では、私も『毎日映画コンクール』の授賞式は嬉しくて。いろんなものがごちゃまぜになっていて、すごく面白いなあって。
―『君の名は。』の新海誠監督や、『シン・ゴジラ』の樋口真嗣監督も、いらっしゃったんですよね。
片渕:いつもだったら、僕らは、それこそ「アニメーション映画賞」っていうような部門賞だけで出番が終わっていたけど、今回はみなさんと一緒に最後まで残ることができて、本当によかったなと。で、それは、僕らが賞をいただけたからよかったっていうわけではなく、全体としてバリエーション豊かになっていることがよかった。少なくとも去年の日本映画界は、そういう感じになっていましたよ。
―今後、日本映画はますます面白くなっていきそうですね。
西川:そうですね。だから、いろんなバリエーションのものが存在していけるように、私もきちんと作品を作っていきたいなって思います。
片渕:また、西川さんの描かれる素晴らしい嘘つきに出会えることを、僕も楽しみに待っています。
西川:(笑)。
- リリース情報
-

- 『永い言い訳』(DVD)
-
2017年4月21日(金)発売
価格:4,104円(税込)
BCBJ-4726原作・脚本・監督:西川美和
原作:西川美和『永い言い訳』(文春文庫)
-
- 『永い言い訳』(Blu-ray)
-
2017年4月21日(金)発売
価格:5,616円(税込)
BCXJ-1054原作・脚本・監督:西川美和
原作:西川美和『永い言い訳』(文春文庫)
- 作品情報
-

- 『この世界の片隅に』
-
2016年11月12日(土)からロングラン上映中
監督・脚本:片渕須直
原作:こうの史代『この世界の片隅に』(双葉社)
- プロフィール
-
- 西川美和 (にしかわ みわ)
-
1974年、広島県出身。2002年『蛇イチゴ』でオリジナル脚本・監督デビュー。2006年、長編第二作『ゆれる』を発表し、第59回カンヌ国際映画祭監督週間に出品。国内で9か月のロングラン上映を果たす。また撮影後に初の小説『ゆれる』を上梓した。2009年、僻地の無医村に紛れ込んでいた偽医者が村人からの期待と職責に追い込まれてゆく『ディア・ドクター』を発表。本作のための僻地医療の取材をもとに小説『きのうの神さま』を上梓。2011年、伯父の終戦体験の手記をもとにした小説『その日東京駅五時二十五分発』を上梓。2012年『夢売るふたり』を発表。2015年、小説『永い言い訳』を上梓、初めて原作小説を映画製作に先行させた。2016年、映画『永い言い訳』を発表。
- 片渕須直 (かたぶち すなお)
-
アニメーション映画監督。1960年生まれ。日大芸術学部映画学科在学中から宮崎駿監督作品『名探偵ホームズ』に脚本家として参加。『魔女の宅急便』(1989年 / 宮崎駿監督)では演出補を務めた。TVシリーズ『名犬ラッシー』(1996年)で監督デビュー。その後、長編『アリーテ姫』(2001年)を監督。TVシリーズ『BLACK LAGOON』(2006年)の監督・シリーズ構成・脚本。2009年には昭和30年代の山口県防府市に暮らす少女・新子の物語を描いた『マイマイ新子と千年の魔法』を監督。口コミで評判が広がり、異例のロングラン上映とアンコール上映を達成した。またNHKの復興支援ソング『花は咲く』のアニメ版(2013年 / キャラクターデザイン:こうの史代)の監督も務めている。
- フィードバック 0
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-