11月11日、12日に多摩ニュータウンの小学校跡地で行われるCINRA主催のカルチャーフェス『NEWTOWN』。様々なカルチャーが一堂に会するこの「大人の文化祭」では、現代美術のアーティストたちによる自主企画展『ニュー・フラット・フィールド』も開催される。
企画者となるのは、多摩ニュータウン生まれで郊外的な人工空間と人間の関わりテーマに制作を続ける石井友人。横浜市都筑ニュータウンに育ち、田園都市線沿線の路上でプロレスを繰り広げる代表作を持つ中島晴矢。広島の郊外育ちで生活における美術(インテリアアート)をモチーフにする原田裕規。
日本の高度経済成長を象徴するように建設されたニュータウンの現在の姿を、アーティストたちが捉え直しリアルに描き出すという『ニュー・フラット・フィールド』とは一体どのような展覧会なのか? 開催を目前に控え、企画者三人に話を聞いた。
ニュータウンは善かれ悪しかれ戦後日本の都市開発の象徴的な場所。自分たちの社会の土台がどのようにできてきたかを眺めるいい機会になると思います。(石井)
―まず、なぜいまニュータウンという場所で美術展をやるのでしょうか?
石井:ニュータウンはかつて社会的な重要トピックでした。例えば高度経済成長による都市や国家の発展として、またそれに伴う社会の負の部分と関連して語られてきたり。それがある時期から、ニュータウン的な背景を持つ社会構造は変わらないのに、それについて語ることは飽きられていったんです。
原田:特に震災以降、一般に郊外論は語られなくなっていますよね。それ以前と比べて、郊外をトピックとして語りづらくなったり、被災地の状況に先行して、いま語ることの必然性が失われつつある状況が生まれたりしました。
かといって自分は被災地に住んでいないし、「被災地」と呼ばれる場所の内側にも様々な分断がある。そんななかで、自分がいま当事者として語り直すことができるトピックってなんだろうと考えていました。
中島:いまオリンピックに向けて東京が注目されてますよね。一方で、二人が言ったように東北や沖縄などの周縁部がいまトピックになっている。「中央」と「周縁」が注目されている状態で、その中間地帯が見られなくなっているんじゃないか。
でも、ニュータウンというのは中央でも周縁でもない「両義的な場所」です。そういったあいまいな場所を取り上げることが、色々なニュースや話題に隠れている本当のリアリティーを考えるきっかけになるのではないかと考えています。

左から:中島晴矢、原田裕規、石井友人 / 取材は『NEWTOWN』開催会場の小学校で行われた

『NEWTOWN』イベント会場となるデジタルハリウッド大学 八王子制作スタジオ(旧三本松小学校)
―ニュータウンというと、土地の固有性や歴史性があまり無いイメージがあります。
石井:かつて都市が拡張し、周縁を侵食していく境界線が「郊外」と言われていた時期があります。その境界線の拡がりは「年輪」みたいなものになっているんです。開発前の土地の固有の歴史や差異は忘却されたとはいえ、都市計画がはじまってからの歴史は見えてくる。
東京オリンピックが1964年と2020年を繋ぐように、ニュータウンも戦後日本の年輪として読み解くことができるんじゃないかな。いまでもニュータウンは善かれ悪しかれ戦後日本の都市開発の象徴的な場所だから、僕たちの歴史を振り返るときに、かつての都市の形成のされ方や、自分たちの社会の土台がどのようにできてきたかを眺めるいい機会になると思います。
匂いが生まれる瞬間が、土着のものが生まれる瞬間。そしてニュータウンにも匂いは立ち上る。(原田)
―ニュータウンによって日本全体が均質になって、つまらなくなったとか、のっぺりした顔のみえない空間になっているという批判もあります。
原田:僕は「のっぺり」していないと思います。ニュータウンにはコンビニやショッピングモール的な「無味無臭な」空間ってたくさんありますが、どこも数年経ってくると「匂い」が立ってくるんですよ。その匂いが立ちのぼる瞬間が、ニュータウンに土着のものが生まれる瞬間だと思うんです。
最近の写真論では「バナキュラー(土着のもの)」という言葉が流行していましたが、身近な感覚でそれは「匂い」を指すのではないか。人の家の匂いとか、コンビニの匂いとかです。その匂いの無い感覚が「のっぺり」と形容されるんだと思うけど、しばらく暮らしているとニュータウンでも匂いは立ちのぼりますよね。
原田:もうひとつ、先日アメリカのニュージャージーに滞在していたときに郊外でショッピングモールが廃墟のようになっているのを見た光景が印象的でした。日本では、トイザらスの日本進出をきっかけに大店法の規制緩和があって、アメリカ型の消費生活が遅れて入ってきた。そんなショッピングモールが、今年9月のトイザらスの破産申請に象徴されるように、ネットショッピングや消費生活の変化によって廃墟化してきている。匂いの生成と廃墟化が、同時に進行してるんです。
―廃墟化といえば、日本のニュータウンでも少子高齢化の影響で人口が少なくなって、治安の悪化や団地が廃れてきたとも言われていますが、会場となる多摩ニュータウンの実際はどうなんでしょうか?
石井:地域の集会場で友達のお母さんや住民の方とお話する機会があったんですが、やはり子供は減っているし、老齢化も進んできていて、正直厳しい状況だとおっしゃっていました。会場のある「松が谷」という地区は、ニュータウンのなかで特別人気がある地区ではないと聞きました。
他方で、勢いがある地域は新規住民が来て人口が増えているようです。一般的にニュータウンはかつての都市計画が破綻した場所と言われがちなんですが、地域によってケースバイケースなので、一括して語ることは難しいのが現状です。
記憶と結びついた匂いがある。でも一見すると空虚で無機質。その両面をきちんと見据えた上で、アートとして可視化したい。(中島)
―ニュータウンについて、ゴーストタウンなどと批判的に語られがちでしたが、そうじゃない捉え方もあるということですね。
石井:そうですね。おぞましさや空虚さを表象するニュータウン、それ以前はアートによる社会批評として「人間と空間の均一化を打ち破れ」という態度の表現も多かった。そういうふうに批判的に対象化されていた場所が、「いや待てそうじゃない、そこには生きているいろんな顔があるぞ」と最近捉え直されている傾向があると思います。
中島:僕もニュータウンで生まれ育ってきたので、そこに記憶と結びついた匂いがあることは当たり前のように知っています。でも批判する立場も理解できるんです。ニュータウンは一見すると空虚で無機質なので、批判しやすいんですよ。その両面をきちんと見据えた上で、アートとして可視化したいですね。
―皆さんの手掛ける作品はニュータウンとどのように関連しているのでしょう?
石井:自分のアイデンティティーについて考察する時に、常にニュータウンは根無し草のような、土着性の無い場所として設定されています。にもかかわらず、そこに自分の根のようなものを感じていたんです。
僕は10年ほど前から作品のモチーフとして鉢植えの観葉植物や温室の植物園を油彩画で描いています。自然の森林にある樹木は地面に根を張り、風や動物が種子を運ぶ、というルールのもとで移動していきますよね。でも人の住む環境の中で、鉢植えは根を規定したうえで、生活に合わせてどこにでも持ち運ぶことができる。人工的な環境における植物と人間の関係は、社会を描き出す隠喩になりうると考えています。
石井:また、観葉植物を集めた温室の植物園は、団地的な集合住宅やニュータウン的な人工都市であったり、はたまた、温室育ちの自画像のようにも思えて、ある種の見立てとしてそれらを捉え描いてきました。
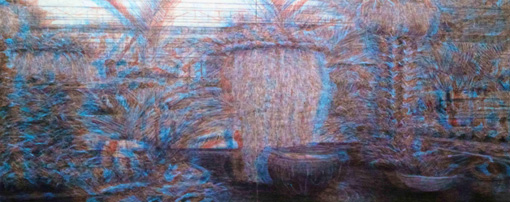
石井友人『Sub image (green house botanical garden)』(2017年)
「この場所になにかの匂いが残っている気がする」という感覚が次のイメージの生成に繋がるんです。(原田)
中島:僕にとってもニュータウンはアイデンティティーの問題なんです。歴史性の無いところに自分が生まれ育ってきた、まさに根無し草であるということに対するコンプレックスがありました。
ニュータウンって、幼少期は楽しいけど思春期になると物足りない町なんですよね。子供を公園で遊ばせたり、フードコートで食事をしたり、小さい子を持つファミリーに最も特化した作りになっている。だから、整然としている代わりに、変な路地や猥雑なエリアが排除されているんです。
中島:ニュータウンで路上プロレスをし続ける僕の映像作品では、そういった日常性を壊そうとしました。面白いのは、徹底的に都市に介入して非日常化しようとしても、日常の層がとても分厚くて、壊そうとするとかえってこちらが滑稽になるんです。今回の展覧会は、そういう日常的なリアリティーを考えるきっかけにしたいですね。

中島晴矢『バーリ・トゥード in ニュータウン』(2014年)
―原田さんは、ニュータウンとの自作の関わりはどんなところにあるのでしょう?
原田:僕は最近、普通の人が撮った写真を集めているんです。たとえば人が亡くなったときに、ご遺族の方が遺品一式を廃棄することがあります。そうやって家財道具と一緒に捨てられるはずだった写真を、ご遺族の許可を頂いて集めているんです。そうした写真には、コミュニティーがしっかりと機能している農村部で生まれ育った子ども時代から、戦争を経て、結婚して郊外に家を建てて家族が増えて亡くなるまでの人の一生が刻印されています。
原田:でも、そういった写真も全てゴミとして捨てられようとしている。それこそ根無し草が再び引き抜かれて、また空き地になるような現場です。だけど、それで本当に全部消えてしまうかというとそうではない。現に手元には写真が残されてるし、地下茎のようなイメージが残ってるということについて考えています。
―ものとして実際に存在している、と。
原田:消えていくイメージではなくて、残っていくイメージに興味があります。どこかに必ず跡が残る、それは匂いが残ることに似ていて、「この場所になにかの匂いが残っている気がする」という感覚が次のイメージの生成に繋がるんです。しかしこれは客観的に語りづらい話なので、従来の郊外論ではあまり語られてこなかった側面だと思います。
当時あった、なにかができあがる予感。それをいま改めて見ることで、違う景色が見えてくるのではないか。(石井)
―『ニュー・フラット・フィールド』は皆さん三人が企画者となって、作家を選定するという構成だと伺いました。それぞれの企画について教えてください。
石井:昔、多摩ニュータウンに住んでいたときに見ていたサンリオピューロランドのファサードはすごく艶やかにできていて、虹みたいなアーチがかかっている。でもあるとき、その脇にある道を下って裏側を見たら、従業員の出入口やゴミの搬出口のような機能的なものがむき出しになっていて、そのすぐ脇には普通の一戸建てがガーッと並んでる風景にびっくりした記憶があります。僕が選定させて頂いた方々は、そういう日常に潜んでいるファサードの裏側を見せてハッとさせるようなアーティストが多いです。
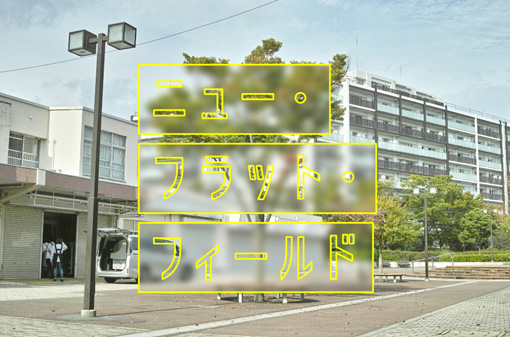
『ニュー・フラット・フィールド』メインビジュアル(サイトを見る)
石井:タイトルは『虹の彼方』としました。虹というのは未来や夢の象徴ですが、ファサードを突き抜けた向こう側には必ず舞台裏がある。その表裏の境界と共に舞台裏を見せたいと思っています。例えば出展作家のひとり、小林のりおさんは、多摩ニュータウンと繋がりが深い写真家です。写真集『LANDSCAPES』(1986年)や『FIRST LIGHT』(1992年)で、当時まだ開発中だったニュータウンの状況を撮影されています。まだ造成中の空間にはなにが建つかはわからなかったけど、なにかができあがる予感はあった。その予感を捉えた写真をいまのニュータウンの真っ只中から改めて見ることで、違う景色が見えてくるのではないかと思います。

小林のりお『LANDSCAPES』より(1984年、八王子市別所)
人が関わることでニュータウンと呼ばれる空間が立ち上がってきていることに注目したい。(原田)
中島:僕は都市の風景を写し、そこに身体的に介入する作品を作ってきました。風景とは物理的に広がっているものではなく、内面を通して映し出されるものです。そこから浮かび上がる建築物や町並みに対して、さっき言ったような「愛憎」があるんです。
そういったことを前提に今回、ニュータウンの風景を描いている作家を選定させて頂きました。その風景には、作家それぞれの捉え方があるはずです。愛着を持って描いてる作家もいれば、絶望的に捉えてる作家もいる。それらを全体として提示したい。そいういう意味で『愛憎の風景』と名付けました。
原田:『愛憎の風景』というと人との関わりを必然的に感じますが、かつての郊外論やニュータウン論を読むと、人の気配がしない話が多いんです。でもニュータウンにかつて暮らしていた人たちの写真を集めていると、基本的に中心にいるのは人間なんですよね。周りに見える景色は背景であって、そこに人が関わることで「ニュータウン」と呼ばれる空間が立ち上がっていることに注目したいと思います。
中島:それと同時に、主役と脇役が逆転する瞬間もある。人間がいるのに風景が侵蝕してきて主役になる、そういう入れ替わりもあり得ます。だから「愛憎」とは、人間と風景の関わり方として考えられるんです。
会期中にはトークイベントも予定しています。例えば『生きられたニュータウン』(2015年)を著した哲学者の篠原雅武さんを招いて、「ニュータウン発の文化の可能性」というテーマで、いまニュータウンからどういう文化が生まれうるのかということを実践的に議論したり。
石井:他にも、『floating view』(2011年)という3.11以前に、郊外論の刷新をテーマにした企画展を開催されたことのある、映像作家佐々木友輔さんによる展覧会内展覧会『仮留めの地』があります。大きな転換点を経験した佐々木さんが、いまどのように郊外空間を捉えるのか、非常に興味深いものになりそうです。
―最後に本展の魅力をみなさんにお伝えできればと思います。
原田:日本人って生活を大事にしますよね。政治や経済や芸術よりも「生活」が上位にあります。ぼくがかつて取り組んでいたラッセンも「インテリア・アート」として生活に関わりますし、ニュータウンにおけるアートもその点で同様なので、この展覧会を通して日本におけるドメスティックなアートのあり方を考えていきたいですね。
中島:それこそ日本各地で芸術祭が開かれ、サイトスペシフィックなアートも一般的になってきているいま、生活空間、居住空間であるニュータウンの元小学校でアートプロジェクトを展開するのは、意義深いことだと思います。
石井:ニュータウンについて、ニュータウンから発信する美術展はいままでほとんどありませんでした。その先駆的な事例を、ぜひ『ニュー・フラット・フィールド』で体感してほしいですね。
- イベント情報
-

- 『ニュー・フラット・フィールド』
-
2017年11月11日(土)、11月12日(日)
会場:東京都 多摩センター デジタルハリウッド大学 八王子制作スタジオ(旧 八王子市立三本松小学校)
展覧会ディレクション:石井友人、中島晴矢、原田裕規
『虹の彼方』企画構成:石井友人
『仮留めの地』企画構成:佐々木友輔
『愛憎の風景』企画構成:中島晴矢・原田裕規
会場構成協力:佐藤研吾、帆苅祥太郎
展覧会グラフィック:仲村健太郎
参加作家・登壇者:
石井友人
地理人(今和泉隆行)
かつしかけいた
Candy Factory Projects
小林健太
小林のりお
佐々木友輔
佐藤研吾
篠原雅武
関優花
筒井宏樹
中島晴矢
原田裕規
門眞妙
山根秀信
-
- トーク
『ニュータウン発の文化の可能性』 -
2017年11月11日(土)
登壇:
篠原雅武
中島晴矢
原田裕規
石井友人
- トーク
『風景のメディウム──キャラクターから何が見えるか』 -
2017年11月12日(日)
登壇:
筒井宏樹
門眞妙
佐々木友輔
- トーク
『ニュー・フラット・フィールドとその作品について』 -
2017年11月12日(日)
登壇:
石井友人
小林のりお
佐々木友輔
佐藤研吾
中島晴矢
原田裕規
ほか
- トーク
- プロフィール
-
- 石井友人 (いしい ともひと)
-
1981年、東京都生まれ。多摩ニュータウン育ち。美術家。2006年、武蔵野美術大学大学院造形研究科美術専攻油絵コース修了。2012-13年、Cité internationale des arts滞在。絵画を主な表現手段としながら複合的な形式で作品を発表している。2017年「未来の家」(Maki Fine Arts)でニュータウンや郊外空間をテーマにした個展を開催。主な展覧会に「グレーター台北ビエンナーレ」(NTUA、2016年)、引込線2015(旧所沢市第二学校給食センター、2015年)、「わたしの穴 美術の穴」(Space23℃、2015年)、「新朦朧主義 2」(Red Tory Museum of ContemporaryArt, Guangzhou、2015年)、「大和コレクション Ⅶ」(沖縄県立博物館・美術館、2015年)、「パープルーム大学Ⅱ」(熊本市現代美術館、2014年)
- 中島晴矢 (なかじま はるや)
-
1989年、神奈川県生まれ。都筑ニュータウン、田園都市線沿線にて育つ。現代美術家・ラッパー。法政大学文学部日本文学科卒業・美学校修了。美術、音楽からパフォーマンス、批評まで、インディペンデントとして多様な場やヒトと関わりながら領域横断的な活動を展開。重層的なコンテクストをベースに、映像や写真を中心としたミクストメディアで作品を発表している。近年は特に「散歩」を軸に据え、都市と身体を捉え直す試みを実践中。主な個展に「SURGE」(gallery TURNAROUND /仙台 2017)、「麻布逍遥」(SNOW Contemporary/東京 2017)、「ペネローペの境界」(TAV GALLERY/東京 2015)、「上下・左右・いまここ」(原爆の図 丸木美術館/埼玉 2014)、「ガチンコーニュータウン・プロレス・ヒップホップー」(ナオ ナカムラ/東京 2014)、主なグループ展に「ground under」(SEZON ART GALLERY/東京 2017)、「INSECT CAGE」 (ANAGRA/東京 2017)、カオス*ラウンジ 市街劇「小名浜竜宮」(萬宝屋/福島 2016)など。
- 原田裕規 (はらだ ゆうき)
-
1989年、山口県生まれ。広島市東区・成城台育ち。最寄りのショッピングモールはダイヤモンドシティ・ソレイユ。美術家。絵画、写真、インスタレーション、テクスト、印刷物などを用して、出来事(event)から印刷物(printed-matter)へと至る閉じられた円環を「どうでもよくするため」、美術=展覧会という制度の内外(インサイド/アウトサイド)で活動している。主な著作に『ラッセンとは何だったのか?』(フィルムアート社、2013年)、共著に『ラムからマトン』(アートダイバー、2015年)、印刷物に『Fwd: print n.1』(2017年)、展覧会に『作者不詳#1』(CAGE GALLERY、2017年)、『エンドロール』(パープルームギャラリー、2015年)、『心霊写真展』(22:00画廊、2012年)、『ラッセン展』(CASHI、2012年)など。武蔵野美術大学を卒業後、東京藝術大学大学院美術研究科修士課程先端芸術表現専攻修了。2017年、文化庁新進芸術家海外研修制度研究員としてニュージャージーに滞在。2018年春にKanzan Galleryで作者の分からない写真をテーマにした個展を開催予定。
- フィードバック 1
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-















