緑豊かな里山で暮らす高木正勝が自宅スタジオの窓を開け放ち、鳥や虫たち、風や雨とセッションした記録が、2017年から「音の日記」のようにネット上で公開されてきた。それが、『Marginalia(マージナリア)』プロジェクト。2017年の『山咲み』が自然と共生する隣人たちとの交流で生まれた福音だとすれば、『Marginalia』は彼自身がいまいちばん近く感じる存在=自然との、言葉を超えた対話だろうか。
自宅を訪ねてのインタビューで語られた言葉は、自然の恵みと脅威への向き合い方から、「関係性がきちんと入っている音楽」への想い、また商業性とは離れた『Marginalia』の試みを始める上での覚悟まで、多岐にわたった。
自分の暮らす場所を「いつか自然に還っていくもの」ととらえると、自然の恩恵も脅威も一緒くたで、はっきりした区別はないとも言えます。
—今日(取材は2018年9月6日に実施)は、未明に北海道で大きな地震がありました。この夏は大きな豪雨・台風の被害もあり、自然との関係を改めて考えさせられます。高木さんはこの里山で、「自然の恵みと脅威」とをどう感じていますか?
高木:自然を、「恵み」と「脅威」という両極端に捉えがちなのですが、ここに引っ越してからは変わったかもしれません。たとえば、さっきこの家の上にある山を案内しましたね。あそこも数十年前はきれいな田んぼだったそうですよ。


高木:自分の暮らす場所を「いつか自然に還っていくもの」ととらえると、自然の恩恵も脅威も一緒くたで、はっきりした区別はないなと感じます。特に里山は、放っておいたらすべてが自然へと戻っていくのがよくわかる環境です。それに森では、今日は恵み、翌日は脅威というより、もっといろんな変化が、細やかなものから大きいものまでありますから。
—逆に、もともと自然の少ない都市の暮らしでは、普段それを実感しにくい。
高木:だから災害が起こると、自然が「脅威」としてのみ、ドッと現れる印象が強いのでしょうね。でもここでは、いろんなことが起こり得ると思えます。たしかに、野菜やくだものが実ればありがたい恵みだと感じるし、逆に嵐や川の氾濫などは本当に恐ろしいのですが、自然の中にいるのは僕 たちですから。自然も自分も一緒だという感覚を大事にしたいです。

—今年の台風は大丈夫でしたか?
高木:ひとつ前の台風(2018年8月18日に発生した台風20号)がほぼ直撃で、古民家の我が家は吹き飛ぶかと思いました(苦笑)。ほかにも、ドライアイスの塊のような雹(ひょう)が降ってきて、畑がバキバキになってしまったこともあります。天候以外でも、飼っていた烏骨鶏(うこっけい)たちが、野生のテン(イタチ科に属する動物)に襲われて持っていかれたことも。そうしてなにか起きるたびに、「じゃあこうしておこう」という対策を考えています。

高木:ただ、たとえば野生動物を防ぐ柵も、竹で作ると3年耐えればいいほうで。もっと保たせようと思うとプラスチックや金属になるけれど、自分はどうしようかと思ったときに、なるべく土に還りやすい方法を探したり、なにをするにも色々と考えてしまいますね。

—日々の変化と同時に、より長いスパンでの付き合い方もあるということですね。
高木:はい。ここは1年を通じてすごく変化があります。春には、ここから見える景色が桃や桜でピンク一色になる。それが冬になると真っ白になるし、より長い時間を通じた見え方もあります。いまこうしてパッと見える山の景色も、村のおじいさんたちに聞くと「濃い緑のところは植林で、わしが中学生のときに植えた。30~40年前ははげ山だった」とか話してくれて。
そういう話を聞いていくと、景色の見え方も変わってきます。「なぜこんな場所に家が?」といった不思議も、理由がわかってきます。ここに生まれてずっと住んでこられた方たちはそうして、歴史のレイヤーが積み重なった状態でこの風景を見ています。僕はまだ暮らし始めて5年ですが、それでもこれまで旅先の風景をただ「綺麗やな」と見てきたのとは違う見方をしていると感じます。

僕は、絵や写真がうまいとか、メロディーがきれいとかではなく、関係性がきちんと入っている表現に感動します。
—高木さんの2017年の作品『山咲み』は、この集落の人々と過ごすそうした暮らしを豊かに音楽にしたものだったと言えるでしょうか。
高木:以前の僕は隣に住む人のこともよく知らないまま、部屋の中で音楽を作っていました。なので、いまと比べるともうちょっと自分勝手に作っていたと思います。直に触れ合わないというか、自分の音がどこに届いているのか、どういう風に届いた先で混じり合っているのかイメージできていませんでした。
対して、こちらに越してきて村の集会などに出ると、まったく違う音楽のあり方にふれることになりました。まず、特定の主役がいない。みんなで酔っ払って古い歌を歌ったりするのですが、誰かが途中で間違えたり忘れたりして(笑)。すると次の人がパッと引き継ぐ。それでばーっと盛り上がるんです。

—先ほどの言葉を受けて言うなら、みんなが直に響き合っている?
高木:そうです。そうして「誰々がうまかった」ではなく、歌によって「いい場ができたこと」を喜んで終わるんですね。「よい歌ができた」って言うんです。以前にエチオピアの小さな集落や、北海道の阿寒湖(あかんこ)でアイヌの村を訪ねたときも似た感覚がありました。
外からやって来た大勢のお客さんのために舞台に上がって歌ったりすることもあるけれど、歌や踊りって、本来は会話の延長のようなものなのだと思う。そして、それを人と人でやるときもあれば、鳥や風と一緒にやるときもある。いまでも残っていますが、かつては世界中にそうしたことがもっと普通にあったと思うんですね。

—録音技術の誕生や音楽の産業化で、そのあり方も変わってきたのでしょうね。
高木:これは写真でたとえるとわかりやすいかもしれません。たとえば誰かを写真に撮るとき、同じ距離、同じ角度で撮ればだいたい同じ写り方をする。それでも、お母さんが子どもを撮るとき、その関係性は確実に写真に残ってしまうでしょう。やっぱり僕は、絵や写真がうまいとか、メロディーがきれいとかではなく、関係性がきちんと入っている表現に感動するんです。
ソロモン諸島での経験を経て、周囲の環境の側に立って想像してみることに気づかされたんです。
—そうした「関係性がきちんと入っている音楽」を多彩なミュージシャンと結実させたのが『山咲み』だとしたら、2017年に始めた『Marginalia(マージナリア)』は、いまのお話をご自分と自然環境との対話にまで広げたものという気がします。自宅スタジオの窓を開放し、虫や鳥の鳴き声、また風や雨、雷と一緒に演奏し、日記のように公開していますね。
高木:窓を開けた向こう側に、自分の演奏を聴いてくれているというか、 こちらの音が届いてしまっている存在がいることに、きちんと気付いたんですね。鳥や虫たちが僕のピアノを聴いて、そして歌い返してくる、僕も彼らの歌を聴いて、ピアノを奏で返す。そう思いながら弾いてみると演奏の仕方も変わるし、録音するとその関係性をそのまま残せるので、とても面白いんです。
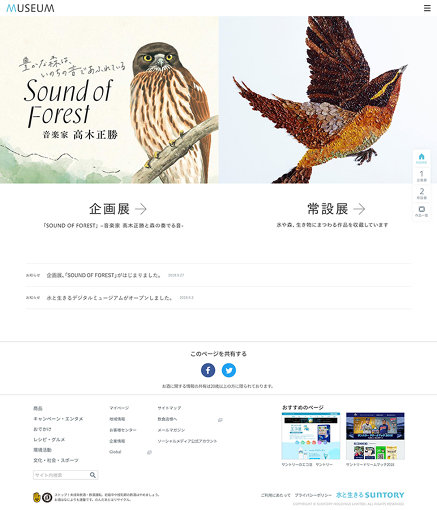
—言葉の通じない生きものたち、さらに雨や風とも向き合うことになったのは、具体的なきっかけもあったのでしょうか?
高木:南太平洋に浮かぶソロモン諸島を旅したときの経験が直接のきっか けだったかもしれません。海にぽつぽつと小さな島がたくさん浮かんでいるところで、島にあるのはたった1軒の家だけというのも多くて。お隣さんを訪ねるのに泳ぐか、カヌーを漕ぐか。自然に溢れた楽園のようなところでした。
その島のひとつで1週間ほど過ごしました。もちろんインターネットはないし、電気や水道も通っていません。とても穏やかで、波の音と生きものの音しかしない。そこで過ごしていると、耳やほかの感覚が開いていく感じがありました。
そんな静かな夜にぐっすり寝ていたら、「ドン、ドン、ドン、ドン」と低音のリズムが耳鳴りみたいに聴こえてきたんです。「あれ?」と思って外に出たら、妻もやってきて「なにか鳴ってるよね」って。でも音の源は見つからない。海の向こうをじっと見つめると、はるか遠くに光が小さく見えて、低音のベースラインまで聴こえてきました(笑)。これは人間の作った曲だな、向こうの島でパーティーかなにかをやってるんだなと。

—どれくらい離れていたんですか?
高木:20kmはあったので、音が届くはずもないとも思ったのですが、実際に聴こえてくる。それに気づいたとき、もうこちらは島の魚や鳥と感覚が同じつもりになっていたので、「いや、いまこの夜にはそんな低音と早いリズムは嫌でしょ!」って憤りが湧いてきて(笑)。そこで初めて、人間 以外の生きものたちの側に立ってものごとを受け取ってみなければと気づかされたんです。
—それが『Marginalia』につながったんですね。
高木:それまでも、外から入ってくる音が録音されてしまってもいいやという気持ちはあったのですが、演奏するときはスタジオの窓を閉めていたんです。でも、いま話したようなこともあって、むしろ自分はそれ(外界の音)と響き合いたいんだと思った。それで、窓を開けて演奏し、録音マイクは外の音も一緒に録れるセッティングにしようと思って。そうして『Marginalia』は始まりました。


人は過去にすごくこだわるけど、虫や鳥たちはいまこのとき、またはほんの少し先だけを見て生きている。
—現在、48作公開されている楽曲群では、実際に虫や鳥たちの鳴き声と交わる演奏を聴くことができます。
高木:たとえばセミは、外に出て成虫になってからは1か月ほどしか生きないと言われますよね。もし窓を開けてピアノを弾いたら、演奏を通じて、その貴重な生のひとときに関わってしまうということになる。だからこそ「いい時間にしたいね」という思いになります。それもあって、漫然と弾くとか、逆に練習とか入念な準備もありません。向こうが鳴き始めたらこちらも集中して始めるんです。
たとえばこの取材中も、外ではミンミンゼミが鳴いています。「ミーンミンミン」ときて、次にまた繰り返してくれるかどうかはわからない。でも、僕がここらでちょっと盛り上げようかという音を出すと、「ん? よしよし、いいぞ!」みたいに応じてくれることもあるし、それに引き寄せられるように、別の生きものたちが集まることもあります。すごくいいときは本当に盛り上がって、「なんていいタイミングで鳴くんだ!」と思わせられる場面もあります。

—反対に、うまくいかないときも?
高木:あります、あります。でもそういうときの原因ははっきりしていて、僕の側に自我があるというか。要はノスタルジーですね。過去にこだわっているときは、うまくいかない。前にうまくいったことを得意気に繰り返していると、録音を聴き返したときに「ああ、生きものたちは思い切り『今日のこと』をやっているのに、僕だけ過去のことをやっているな」とわかって嫌になるんです。
人は過去にすごくこだわりますよね。虫や鳥たちも過去を気にしているかもしれませんが、いまこのとき、またはほんの少し先だけをしっかり感じて生きているように思えます。それに近い感覚で演奏すると、意外に練習なしでも指が動いたり、新しい音楽が出てきたりするものです。

—『Marginalia』では、生物側のコンディションで、難しいときもありますか?
高木:虫や鳥たちの力がすごく強いときですね。そういう日は生きものの量が違います。空間がびっしり音で満たされて。彼らの鳴き声を録るだけなら最高の日。でもそこに演奏で入ろうと思うと、向こうはそれどころじゃないという感じの鳴き方だから、僕のほうが「うーん、わからん」となってしまいます。
勇気を出して音を奏でてみても、今度はあちらがシューっと引いて終わってしまう。「あ、違ったんですね。邪魔しちゃったな」という感じで演奏をやめると、向こうがまた始めるっていう(苦笑)。いずれにしても、やはりこちらの音は聴いているんだなと感じます。

目の前で起こっていることをそのまま音楽として収めればいいだけなのに、ずいぶん遠回りをしたなと思う。
—今回『Marginalia』から6曲が、サントリーが9月に新設したウェブ上の『水と生きる デジタルミュージアム』に出展されます。きっかけは、水源涵養活動の「天然水の森」活動や愛鳥活動、次世代に水の大切さを伝える環境教育などを続ける同社のコンセプト「水と生きる」が、『Marginalia』とも通じるというミュージアム側の思いと言います。
高木:サントリーさんの件は、意外でもありました。というのも、当初は「こんなことを始めたら仕事の依頼は減っていくな」と思っていたからです。『Marginalia』に収められた自然の音は、多くの仕事では「ノイズ」とみなされ、「取り除いてほしい」と言われるものですから。妻(絵本作家のたかぎみかを。『Marginalia』では曲ごとの写真も担当している)にも「たぶん今後2年くらいは、仕事が減るかも」と伝えたのですが、「思ったようにやればいいんじゃない」と言われました(笑)。
サントリーさんの『愛鳥活動』のウェブサイトに鳥の歌がわかりやすく分類されていますよね。さっき歌っていた鳥はなんていう鳥だろうって気になったときに何度もお世話になっていたので、今回、デジタルミュージアムに『Marginalia』の音たちが並んでいて、とても嬉しいんです。


—高木さん自身も、サントリーのウェブサイト『日本の鳥百科』をご覧になって鳥の鳴き声を調べたりするそうで、互いに共感したから楽曲を出展されたんですね。ある種の抽象化や純粋化を目指すと、ノイズとして排除されるものがあるけれど、それこそ大切なものだという見方もあります。
高木:世界の民族音楽の音源を聴いていると、多くはスタジオ録音ではなくて、普段の生活の中でおじいちゃんや子どもたちが演奏したりして、「茶化し声」も入るし、失敗したらみんなで笑う。周囲の暮らしの音もそのまま入っていて、でもそれがいいんですよね。
少し視点が変わりますが、この集落で採れた野菜ってやっぱり美味しいんです。採れたてを食べるせいもありますが、なにより、その土地で採れたものを食べるからかなと思って。
僕ら現代人は、世界中のいろんな産地からやってきたものを食べ、体に取り入れています。でもこの辺りにいる虫や鳥や植物は、みんなここにある同じ水や土を糧に生きている。自分たちもそういう風になると、だんだん周囲の生きものたちと近づいていくのかなって。これは、いま『Marginalia』でしていることにも通じるように感じます。
—まずは目の前にあるものと向き合うことから始める?
高木:これまで僕が作ってきた音楽の中には、時代も場所もバラバラなと ころから色々なものを取り入れて、それを調理していたものもあったと思うんです。もっと「目の前で起こっていること」をそのまま、きちんと受け止めて、やわらかく結びつけていけばよかったんですね。自分がもともとしたかったのは、もっとシンプルなことだと、ちゃんと気づいてきたんです。人も自然も、どこかで「あなたも私も一緒やな」と感じられたらいいなって。

とにかく「全取り」しようとせず、望みを少し緩めるだけで可能性が広がることも、多いのではないでしょうか。
—ノイズも含めて「目の前にあるもの」を受け入れられるか。それは、「調和」をどう考えるかという話でもありますね。
高木:そうですね。なにを軸にするか次第で、調和のバランスも大きく変わる。畑をやっていても思うのですが、すべての野菜を虫喰いなしに収穫するのを目指してしまうと、虫が1匹でも湧いたら大変。でも、「100の野菜のうち50が収穫できればええやん」と思った時点で、全体は虫1匹くらいで揺らがない心や環境が生まれてくるんですね。
むしろ、「なぜ虫が来るんだろう」「隣の雑草と野菜はなにが違うんだろう」と観察し始めて、またいい発見がいっぱいある。とにかく「全取り」しようとせず、望みを少し緩めるだけで可能性が広がることも多いのではないでしょうか。

—たしかにそうかもしれません。
高木:もちろん世の中には、より難しい問題もいっぱいあります。ひとつの山を考えたときも、なにがそこでの調和なのかは複数の見方があって、一方の考えが他方に反することもまたありえる。そして、両者がたまたま近くでぶつかってしまうと大変になる。自分の近くにある環境が変化を迫られたり、脅かされたりしたとき、それにとにかく抗うべきか、または反対するだけではなにも変わらないのか。こういう場所で暮らすようになってから、特にそうしたことは色々と考えさせられます。
—「調和」は、ひとつの山でもなかなか難しいものなんですね。
高木:そもそも、僕がこうして山の中でピアノを弾いて暮らすことも、この土地のあり方を少なからず変えてしまったかもしれない。配達トラックは、僕が来る前はこんな頻繁に来ていなかったかも、とか(苦笑)。こういうことって、むしろほかの誰かの行いが気になったときに、「自分もそうかも」とハッとすることが多くて、そういう点でも難しさがあると思います。

—でも、複数の立場や視点を想像できることは、調和の大事な出発点ですよね。そこから自分の立ち位置が確認できるという点でも。
高木:たしかに、きっかけはなんでもいいと思うんです。ある映像作品 で、南米のインディアンの人が「川の音の聞き方」を語る場面が面白かったんです。人が川の音としてイメージするものって「ザーッ」「さらさら」とか単純になってしまう。でも実際に耳を澄ましてみると、こっちで「どっぽん」、あっちで「ぴょろろろ」とか、すごく多彩な音が数えきれないくらい鳴っている。鳴っている音すべてを聴こうとして、最終的にその全体をひとつのものとして聞けたら、それが「その川の音」なんだよと、その人は話していました。
「心地良さ」って見た目も大切だと思いますが、音で判断すると見えてくるものがあるんです。
—このお家の裏にも小川が流れていますね。
高木:越してきた当初は、この川って「不安な音」がずっとしているなと思ったんです。「なんでだろう」と川べりを降りて行ったら、水が落ちる場所があって、そこから低ーい音が出ていた。そこに大きな石を持っていって水が当たるようにしてみたら、スッキリした音になりました。
以来、「音の盆栽」みたいな感覚で石を置いたり、土を足したり、色々やっています。1度は嵐で見事に全部流されてしまいましたが(苦笑)、そのあとも少しずつ続けて、今年の夏は蛍が100匹くらいやってくる場所になりました。自分が何日も掛けて手を出した場所に、そうやって生きものがわいわいやってきてくれるのって、ほんとうに嬉しいんですよ。

高木:スタジオも最初は音がこもっていたので、1階の天井を一部抜いたり、壁だったところを一面窓に変えたりして。「心地良さ」って見た目も大切だと思いますが、音で判断すると見えてくるものがあるんです。

—高木さんは日々の暮らしと創作が直結しているようですね。それもまた、目の前にあるものと響き合うことから始める感覚なのでしょうか。
高木:うちは猫も飼っているんですが、猫が嫌がることと、ゴロゴロと気持ち良さそうになることって、それぞれありますよね。こちらの勝手な愛情でかまっても、嫌がられたり(笑)。そういう、自分だけがやりたいことじゃなくて、向こうからも答えをくれることだと思うと、そのほうがうまくいくし、心が楽ちんです。
だから、正解をふわっとしたところに求めず、まずは目の前にある相手が「オッケー」と言ってくれるかどうか。こちらがまず相手を受け止めて、それで自分を受け止めてくれる相手がいて、お互いがより心地よくいられるあり方があって。そうやれている限り、心安く生きられると思います。目の前にいるものたちと一緒に作り上げたのですから。家族だったり、村だったり、山や海だったり、音楽も。いろんな形はあっても、自分たちなりの関係性ですから。鳥も虫も好きだなあ、人も好きだなあという気持ちが、たくさん行き交っていて、楽ですし、面白いですよ。

- リリース情報
- プロフィール
-
- 高木正勝 (たかぎ まさかつ)
-
1979年生まれ 京都府出身12歳よりピアノに親しむ。19歳より世界を旅し撮影した映像で作品を作りはじめる。2001年、アルバム「pia」をアメリカのCarpark Records、「eating」をドイツのKaraoke Kalkより発表。以降、 国内外でのコンサートや展覧会をはじめ、映画音楽(「おおかみこどもの雨と雪」「バケモノの子」「未来のミライ」「夢と狂気の王国」)、CM音楽、執筆など幅広く活動している。
- フィードバック 9
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-


