カルチャーの拠点は、都会から郊外へ?
「いま、カルチャーは郊外が面白い」。そんな意見にすぐ同意してくださる方は多くないと思うけど、渋谷や原宿、新宿、下北沢などの「都会」の求心力が弱くなったという話については、そこまで意見がズレることはないように思う。
いまや家にいれば、Amazonが何でも届けてくれるし、Uber Eatsがご飯を買って来てくれる。NetflixやSpotifyというデジタルライブラリーは、僕たちが死ぬまで新鮮な音楽や映画やドラマを提供してくれるだろう。とにかく便利でインスタントな時代になった。昔みたいに、雑誌で話題の場所をチェックして、ちょっと緊張しながら都会に出かけていく、みたいなことはもう不要。怖い人がたむろってる雑居ビルにレコードを探して踏み込んだり、ブート盤を探して西新宿を歩き回り、チンピラに絡まれたりする必要は、もうない。
こうやって振り返ってみると、自分が思う以上のスピードで、街のあり方が変わってきていることに改めて驚く。渋谷系から20年、再開発まっただ中の渋谷なんて、大きな商業ビルの建設ラッシュだ。若者の街と言われていた渋谷も、いつの間にかビジネスマンの街になっているかもしれない。
下北沢も、駅の改札がどこにあるのかわからないくらい、大規模に街が変わっている。下北沢の再開発に反対した「Save the 下北沢」を取材したのはもう10年以上前のことになるけど、下北に個性的な個人店が集まったのは、大きな道路がなく、小さな道が入り組んでいるからだと聞いた。数年後に完成する予定の大きな道路ができたら、下北沢はどうなるんだろうか。「ファスト風土化」という言葉が生まれたのも「Save the 下北沢」を取材した頃だったけど、日本の風景は確かに均質化して、いまや都会の街々も、その波に飲み込まれようとしているように見える。
街の役割の変化。そして、「郊外」について語るべきいくつもの文脈が表面化し始めている
街が均質化していく一方、ネットやスマホの普及で人々のコミュニケーション手法は多様化した。ドコモがi-modeを始めたのが1999年だから、渋谷系の時代は、携帯電話すらなかったわけだ。平成生まれの人は知らないと思うけど、当時は良くて「ポケベル」で、それまでは家の固定電話でやりとりしていた(!)。
渋谷系レコード文化を牽引した橋本徹は「自分が好きなものに対する共感者を増やせるチャンスが広がった時代」とインタビューで当時を振り返っていたけれど、雑誌くらいしか情報入手手段がない時代、人は街に集まるしかなかった。都会のレコ屋やクラブやライブハウス、洋服屋、本屋やミニシアターなんかに行って、情報や物をゲットする。趣味を同じくする共感者たちと出会い、遊び、情報交換をしに、街へ出かけて行ったのだ。
しかしいま、そういった街の役割はネットへ吸収されていき、共感者と繋がることも、情報を得るのも、比較的容易になった。同時に、共感者たちが集うリアルな場所も多様化して、いたるところに点在する。そのひとつこそが自分が暮らす「地元」であり、「郊外」からカルチャーの発信が増えてきている理由と考えることはできるだろう。実際、今回取材を行った府中の芸術祭『フェット FUCHU TOKYO』をはじめ、東京郊外発の面白いイベント、プロジェクトが増えてきている。

例えばCINRA.NETで取材をしている中だけでも、足立区千住地域で行われている『アートアクセスあだち 音まち千住の縁』や、中央線沿線(杉並、武蔵野・多摩地域)に点在しているアートスポットをつなぐ『TERATOTERA』、千葉・松戸のプロジェクト「PARADISE AIR」、横浜市中区黄金町で10年続いている『黄金町バザール』、そしてつい先日開催された『鉄工島FES』(大田区の京浜島)などがあり、いずれも郊外を舞台に様々なカルチャープログラムを展開している。
また一方で、表現者たちが「郊外」に着目する動きも目立ってきた。そもそも「郊外」とは、大都市の外縁部にあり、人が生活を営み、子供を育てるベッドタウンのことだ。言ってしまえば日本のごく一般的な風景。そんな場所で、日本人(アーティストも含む)の多くが生まれ、育っているのだから、表現のテーマとして取り上げるのはごく自然なことなのかもしれない。
一例として自分たちの話をするのは恐縮だが、昨年CINRA.NETが多摩ニュータウンの廃校で開催し、今年も開催間近に迫った文化祭『NEWTOWN』も、そうしたプロジェクトのひとつ。この場所でイベントを始めたのは、会場となった廃校が自分の母校だったという理由も大きかったが、「郊外」「ニュータウン」という言葉に、アーティストたちが強く呼応してくれたのは嬉しい驚きでもあったし(参考記事:Chim↑Pom卯城竜太×中島晴矢 日本郊外でいかにサバイブするか)、我々の動きとは全く関係なく、tofubeatsが「(自分の故郷である)ニュータウンが冷徹な街だとするなら、そこをよくしていくのは、自分なんじゃないか?」と語ってくれたインタビューも、記憶に新しい(参考記事:tofubeatsが「他人任せ」から「自分でやる」に変わったこの3年)。

また、均質化しているように思われていた「郊外」も、アーティストたちが「自分のルーツ」としてそれぞれの町のリアルを発信し始めたことで、各町のオルタナティブな場所性が立ち上がってきてもいる。それをもっとも強く打ち出しているのがラッパーたちであり、近年ではテレビ番組『フリースタイルダンジョン』が大いに盛り上がったり、KOHH(王子)やBAD HOP(川崎)など地元のリアルを言葉にするニュースターたちに、若者の支持が集まっている。
いま、「郊外」を語る文脈が、同時多発的に表面化し始めているのだ。
「いま住んでる場所を、もっと自分たちが面白いと思うような町にしたい」
では、実際に郊外から発信している人の声を届けよう。今回取材を行ったのは、東京の西、府中市内で始まった芸術祭『フェット FUCHU TOKYO』だ。2016年に初開催され、府中市内に点在するギャラリーやアトリエを中心に、府中市美術館などとも連携する「暮らしと表現の芸術祭」。
正直「府中」というと、競馬場や刑務所といったイメージが先行するし、他の郊外と同様、「カルチャー」とは縁遠いようにも思える。この芸術祭を主導している府中生まれの芝辻ペラン詩子さんも、初めはそんな府中から一刻も早く抜け出したいと思っていたという。それがなぜ府中で芸術祭を興すことになったのだろうか?
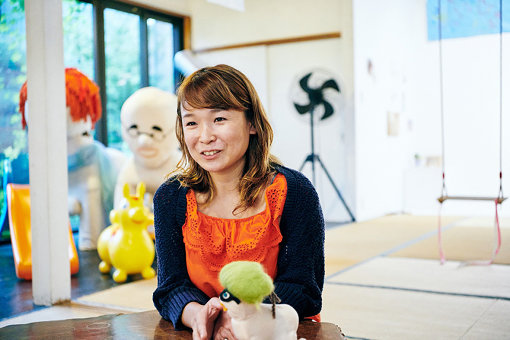
芝辻:そう、府中に良いイメージを持てなかった時期もあるし、いまも「自分の故郷のために!」みたいな想いが強いわけではないんです。実際、ネットがあれば同じような興味を持つ人と繋がれるから、遠くからでも興味のある人に来てもえばいいし、近所の人にきてもらう必要もないかなと思ってました。
でも、東日本大震災が起きて、考え方が大きく変わったんです。今年も自然災害がすごく多かったですけど、ああいう困った時に、近くに住んでいる人たちと、直接助け合えるようなコミュニティー作りをしておかなければって思ったんですよね。
もうひとつ大きかったのは、子育てをするようになったこと。この場所で子供を育てようって考えたら、少なくともこの先十数年は府中にいることになるし、その間に都心はいいなあとか、お隣の国立市はいいなあとか思い続けるのは嫌だったんです。いま住んでる場所を、もっと自分たちが面白いと思うような町にしたいし、それを自らイニシアティブをとってやろうと思ったのが、プロジェクトの始まりでした。

府中を、自分たちが面白いと思うような町にしたい。そんな芝辻さんの想いが現実味を帯びてきたのは、1人の人物との出会いだったという。
芝辻:「BEPPU PROJECT」っていう大分県別府市の活動で出会った人が、府中市美術館で学芸員をやっている神山亮子さんを紹介してくれたんです。彼女を通じて、府中にもアーティスト活動をしている人がたくさんいるってわかったし、私と同じように、府中でアトリエやギャラリーを構える仲間も増えてきて。
それでまず、Artist Collective Fuchu(以下、ACF)という団体を作りました。府中や近隣地域で活動するアーティストや芸術愛好家の集まりなんですけど、ACFを起点に、地域のアートスポットを結ぶボトムアップ型の芸術祭や、町作りをしていったら、府中にもアートが好きな人が集まってくるかもしれない。そんな計画が、『フェット FUCHU TOKYO 2016』に繋がっていきました。

地域から日本のカルチャーを「ボトムアップ」する
この「ボトムアップ型」というのは、郊外型イベントに数多く見られる面白い特徴だ。『フェット FUCHU TOKYO』がイベントのコンセプトを「暮らしと表現の芸術祭」と打ち出しているように、趣味と暮らしが同居した熱量の高いコミュニティーが、その地域から外側へ向けた発信を行いつつ、自分の町の中にカルチャーをインストールしていく。
もちろんそれは、著名なアーティストたちがしのぎを削る、カルチャーの表舞台を代表するようなイベントではないのかもしれない。しかし、本当の意味で一番最初にカルチャーや表現が生まれる場所――みんなが住まう「郊外」の中にこうしたプロジェクトが生まれることで、子供たちの想像力を育んだり、近隣に住まう、これまでカルチャーに興味を持たなかった人々にその魅力を伝える機会になる。こうした試みが全国に広がれば、それこそ日本の文化全体が更新される可能性すらあるのだから、CINRA.NETとしても応援したくなる試みだ。
芝辻:ボトムアップ型の良いところは、やりたいと思った人が、自分で企画して自発的に行動できるところです。地方の大きな芸術祭だと、有名なアーティストやディレクターが上に立って主導するケースがほとんどだと思いますけど、それだとその地域の力は育ちづらい。下から湧いてくるものがないと、なかなか底上げされないと思うんです。

芝辻:それと、ACFのメンバーが共通して言うのは、この活動をしていると、面白い人たちに出会えて楽しいっていうことなんです。ご近所なのに、現代美術の作家とか、ジュエリーデザイナーとか、面白いことをやってる人たちがいっぱいいることを知らなかったから。
ACFができるまでは、府中にはアートの受け皿になるような組織や場所がなかったし、府中で何かを発表するっていう文脈すらなかった。府中は寝に帰ったり制作する場所で、発表や仕事は都心でやるものだっていう固定観念が染み付いていたんです。だけどいま、そういう考えはどんどん変わってきている。
ローカルなアーティストが地元から発信したり、これまで作家活動をしていない人が初めて挑戦する機会になったり、そういう方が『フェット FUCHU TOKYO』をきっかけに、他の展示にも誘われたりするようになってきて、少しずつですけど、府中にアートのコミュニティーができてきました。自分の子供たちのためにも、そうやって地域を新しくしていけたらいいなと考えています。
町はどう変われるのか? 郊外イベントの難しさ
この日、芝辻さんの案内で府中を巡っていると、大きな施設の多いことに気がつく。まず駅前には1900年の歴史を持つ大國魂神社。サントリーや東芝、NEC、キューピーマヨネーズの工場、大東京綜合卸売センター、そして中央競馬場。大きな競馬が行われる日、府中はフェスのように人でごった返すらしい。
「府中」とはそもそも、奈良~平安時代にかけて、国府が置かれていた地域に付けられた名前だ。だからなんと(僕もこの取材をするまで知らなかったのだが)、東京都府中市は「大化の改新」(645年)から武蔵国(東京都、埼玉県、神奈川県にまたがる日本でも最大級の国)の国府として栄え、東京の中でも特に古い歴史を持つ地域なのだ。
そういうわけで、府中は昔から東西南北への交通の要所。大企業の工場などが集まり、戦後からもいまだに人口が増え続けている人気のベッドタウンになっている。東京郊外の中でも、かなり多様な歴史と住人を内包している町と言えるだろう。
そんな町で、イベントをやるのは間違いなく大変だ。人が集まる都会ならまだしも、人が住まう地域。周りは住宅街なのだ。そういうところでイベントをする場合、主催者側が最も頭を悩ませるのは、そこに住まう地域住民への説明、そして応援をしてもらうことだろう。
芝辻:府中は歴史のある地域なので、やっぱりすごく保守的なところがあると思います。私みたいに……土着民って呼んでるんですけど、何世代も住んでいる人たちの方が、町の権力を持っている。でも府中って、住み良い町としても有名なので、マンションもどんどん建って、新しい住民がかなり増えているんです。だから次世代のことを考えると、変わっていかなきゃいけないこともたくさんある。
私たちがやってるようなアート系のことも、新住民の人の方が興味を持ってもらいやすくて、逆に土着民の知り合いにはまだ来てもらえていない現状もあります。ACFがそういうところの架け橋にもなっていきたいんですよね。

こうした地域の課題は、場所によって様々なのだと思う。『NEWTOWN』を開催している多摩ニュータウンの松が谷地区は、高齢化と過疎化という課題があって、静かに暮らしていたい方もいれば、町おこしのために若者の手助けを求める声もあった。こうした一つひとつの声や課題に向き合い、応えながら、地域にカルチャーを浸透させていく。
今回の取材で案内してもらった大東京綜合卸売センターは、50年の歴史を持つ、昭和の匂いを残した市場。芝辻さんは子供の頃からこの場所で遊んでいたそうで、『フェット FUCHU TOKYO 2016』の際には、この場所でイベントを開催したそうだ。

この日はもう市場が閉まっていて静かなものだったが、市場に残っていた肉屋の親方は、熱い口調で『フェット FUCHU TOKYO』のことを語ってくれた。
親方:この辺りでも高齢化と後継ぎ問題はあって、市場も店の数が減ってるんだよね。商売がすごく難しい時代になってる。周りに大型のお店もたくさんできてるしね。だから『フェット』をここでやってくれて、すごく良かった。イベントをきっかけに、初めてここに来てくれた地元の人がたくさんいたし、僕たちが普段見ないようなものをやってくれて面白かったし。市場もいま、空いた店舗を学生に貸してサークル活動なんかに使ってもらうようになってきて、変わってきているんだよね。

いま日本中で開催されている地方の芸術祭も、カルチャーの力で地域の課題解決をしようとしているものは多いが、時代とともに町が変わっていく中で、その綻びをつくろう役割を、カルチャーが担うこともできるのかもしれない。
こうした郊外からの発信が、今後どのような形で萌芽するのかはわからない。しかし、人が暮らす町の中に、アートや音楽や演劇が普通に存在する社会の方が、ハッピーだろうという確信はある。
町は当たり前のように変わっていく。良い方にも、悪い方にも。その中で、自分の「好き」を町作りに活かそうとする芝辻さんのような人がいることは、町にとってとても幸せなことだろう。その事実は同時に、自分自身の姿勢を問いかけもする。自分は、自分が住んでいる町にどう関われるんだろう?
- イベント情報
-

- 『暮らしと表現の芸術祭 フェット FUCHU TOKYO 2018』
-
2018年11月22日(木)~12月9日(日)
会場:東京都 府中市内
- プロフィール
-
- 芝辻ペラン詩子 (しばつじ ぺらん うたこ)
-
武蔵野美術大学映像学科卒業後、渡英。The Surry Institute of Art and Design University College( 現 University for the Creative Arts), BA(Hons)Animation卒業。マンチェスターの人形アニメーションスタジオでの研修を終えて帰国。大人の女性の着せ替え人形としてリバイバルした「ブライス」のプロモーション映像ディレクターとなる。2007年頃から、アニメーションのみならず、動くぬいぐるみやオブジェの制作、発表を開始。基本的に社会派、ポップでシュールな世界観が特徴。2009年、結婚を期に独立し、府中の実家を改装したギャラリーカフェ「メルドル」をオープン。2016年に任意団体「Artist Collective Fuchu」を設立して『フェット FUCHU TOKYO 2016』を運営。2018年には、NPO法人「アーティスト・コレクティヴ・フチュウ」創設し、現在は『フェット FUCHU TOKYO 2018』の準備に奔走中。
- フィードバック 1
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-


