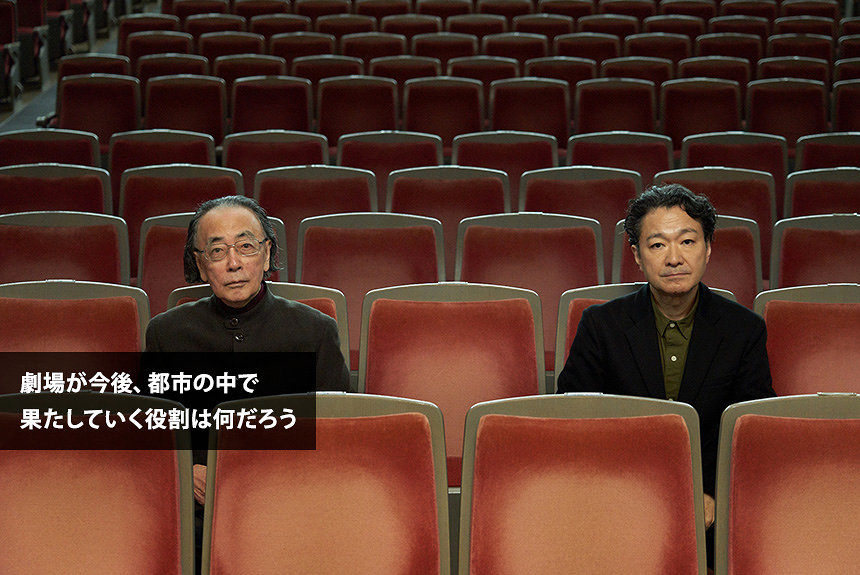先輩の話は聞くものだ、と私たち若い世代は知っている。歴史を学ぶべきだ、ということも。でもどうしたって、あくせくする日常の中で目の前のことに囚われて、貸す耳を持たなくなってしまいがちだ。そうこうするうちに、時代は思わぬ方向へ流れていってしまう。
でもここに、どこまでも優しく、そして情熱的なアジテーションで、自らの歩みを伝えてくれる先達2人がいる。ダンサーとの大々的なコラボレーションを行う舞台『Memory of Zero メモリー・オブ・ゼロ』を手がける、現代音楽界のレジェンドにして作曲家・ピアニストの一柳慧、そして同じく演劇界の第一人者である演出家・俳優の白井晃だ。
神奈川芸術文化財団の芸術総監督である一柳、KAAT 神奈川芸術劇場の芸術監督である白井による本作は、「身体と記憶」をキーワードに、ダンスの歴史を振り返り、そして人気作家ポール・オースターの作品を用いていくという。2人が半世紀を超える半生から今回の公演の真意を語る時、それは私たちに向けた、とてつもなく熱い鼓舞になっていた。
いまだに僕は、20歳前後に観た舞台表現に触発されて得た感覚を追い求めているだけかもしれない。(白井)
—今日はまず、お2人がそれぞれ20~30代の時期に、何を考えていたのかを伺ってみたいと思っています。1957年生まれの白井さんは、1983年に劇団「遊◎機械/全自動シアター」を立ち上げましたよね。
白井:京都に住む学生だった20歳前後にアンダーグラウンドな舞台表現にのめりこんだんです。鴨川のほとりでは唐十郎さんがテントを張って芝居をやっていて、「何だこれは!」と。寺山修司さんや麿赤兒さんの大駱駝艦をはじめ、ものすごいエネルギーに満ち溢れていて、ハッキリ言えばドロドロの芝居がいっぱい来ていたんです(笑)。
それまで思っていた演劇という既成概念を完全に崩されて、いまだに僕は、その時に触発されて得た感覚をずっと追い求めているだけかもしれない。あの感動をお客さんにも味わってもらいたくて、演劇を壊し続けているのかもしれないとさえ思います。

—いずれも舞台表現の革命児の方々ですね。既存のフレームが壊れていく面白さは、1933年に生まれ、1954年に渡米された一柳さんが味わっていたものに近いのではないでしょうか。
一柳:敗戦後、焼け野原の日本で、電気やガスはもちろん、食べるものさえない中で生きていました。楽器もなければ楽譜もないので、音楽をやりたいと思ってもそうした環境は望めず、ニューヨークのジュリアード音楽院に行ったんです。ただ、私はあまり学校でのアカデミックな教育が好きではなくて(笑)。
日本との違いで一番ビックリしたのは、ニューヨークの街並みです。メインのアベニューには、まるでブティックが点在するように、数軒おきにギャラリーやミュージアムがあり、現代アートが展示されていた。本当に面白くて、学校はなるべくサボって(笑)、そうした場所や劇場に足を運びました。そこから学んだもののほうが、今につながっているものとしては大きいんです。

ジョン・ケージと一緒に行動しているうちに、芸術活動とはこういうことなのか、と飲み込めてきたんです。(一柳)
—お2人ともそうした日々の中、既存の枠組みの「外」で、ダンスにも出会われたわけですよね。
白井:そうですね。演劇の先輩たちから得た衝撃と同様に、それまでの概念から逸脱して表現されていたダンスに、猛烈に揺さぶられたんです。ダンスを貪るように観るようになったのは1980年代でしたが、それ以前からモーリス・ベジャールやローラン・プティといった世界的なバレエの振付家が来日した際などは好きで観ていました。彼らも既に、既存のバレエという概念からは逸脱し始めていましたね。僕にとって一番コンテンポラリーだったのは、ピナ・バウシュ、ウィリアム・フォーサイス、マギー・マラン、ヤン・ファーブル……。

—コンテンポラリーダンスの歴史を形作ってきた方々ですね。
白井:一柳さんが出会ったマース・カニングハム、あるいはマーサ・グラハムといった人々は、後から知っていきました。そして1980年代当時、僕らの同世代の振付家の人たちも出て来て、僕も同様に、先輩たちから得た衝撃を演劇の可能性としてどのように引き継いでいけるだろう、と考えていた。ダンスから受け取ったものは、すごく大きいんです。
—一柳さんも、1959年にジョン・ケージに出会った後、ダンスとの本格的な出会いを経験されますね。
一柳:元からダンスそのものには非常に関心はあったんです。順を追ってお話しすると、私が出会ったジョン・ケージは、アカデミックな学校からは縁遠い人でした(笑)。結局、フリーランサーという形で、実験の場を自分で作って広げていった人だったんです。私も、弟子としてジョン・ケージという先生から何かを習おうということではなく、一緒に行動するという経験をしているうちに、芸術活動とはこういうことなのか、ということがだんだん飲み込めてきたんです。
ニューヨークにいた私は、学校の先生方のレッスンでバイオリンやチェロの伴奏などをしていたんですが、演奏するのはクラシックがほとんどでした。それがジョン・ケージと出会ってから変わったんです。マース・カニングハム舞踊団の音楽監督だった彼から、カンパニーでピアノを弾いてくれないかと頼まれた。それが本当に、私のためになったんです。
—どういうことでしょうか?
一柳:具体的には、楽譜が突如なくなったんです(笑)。私は、ずっと即興でピアノを弾きっぱなしです。踊っているダンサーに対して、音楽も完全にひとつの独立した分野としてぶつけ合う、という感じでした。

汗をかき、血も出し、つばも吐くような肉体が目の前にある、という点で、ダンスに惹かれるんです。(白井)
—そうした折、一柳さんは、カニングハムのもと、ダンサーとの経験に触発された。
一柳:そうですね。カニングハムのスタジオはグリニッジ・ヴィレッジに近いところにあって、若い人たちが集まっていました。ダンスや、あるいはジャズも盛んで、その区域全体が盛り上がっていた。非常に見ごたえがあって、驚きをもって観られる演目がたくさんありましたよ。
その後、私は1961年に帰国したんですが、1960年代の日本でビックリしたのは、先ほど白井さんからお話が出たような、寺山修司さんや唐十郎さんのような人たちが活躍をされ、外国でも公演をしているような状況だったことです。ニューヨークで体験したようなことが日本で起こっているその渦中に戻ってきたことは、幸せなことだったと思っています。

白井:1960年代に唐十郎さんは「特権的肉体論」ということをおっしゃっていました。今は情報の価値が優先されて、肉体の感覚がどんどんなくなっている時代だと思いますが、そうした肉体――汗をかき、血も出し、つばも吐くような肉体が目の前にあって、それを共有する、という点で、ダンスに惹かれるんです。それは、寺山さんや唐さんの芝居で圧倒的なエネルギーをもつ肉体を見た時に引きつけられるものと、同じなのかもしれません。
一柳:今回行う『Memory of Zero』のように、いくつものジャンルの境界を突破した表現が生まれていた。違うジャンル同士、横の同時代的なつながりのなかでコミュニケーションをとって、一緒に共同作業していたのが刺激的だったんです。それまでは縦のつながりだったものを、横につなげていったのです。
白井さんも、脚本も書けば演出もされるし、演劇外の音楽やダンスの領域にも、どんどん関心を持って入っていかれますよね。あらゆる可能性に向けて押し出された形で活動していくあり方です。音楽の世界でも、昔はバッハ、ベートーヴェン、モーツァルト、ハイドン、ブラームス……みんな作曲もして、ピアノも弾き、演奏会のプロデュースまでしていた。しかし、このトータリティー(全体性)というものが、今は失われている、と私は危惧しているんです。


『Memory of Zero』フライヤー(サイトを見る)
熱狂的なファンの人たちは盛り上がっているけれど、分からない人にはまったく無縁、という状況がすごく多くなっている。(白井)
—トータリティーが失われた現代とは、どういうことでしょうか。
一柳:情報化社会がもたらしたものは、非常にメリットもあるとは思います。しかし……この表現が当たっているかどうかはわかりませんが、社会が非常に「企業化」した、と私は感じています。それはつまり、すべてのことが細分化されて、大きなものをトータルに見る目や力を失ってしまった、という懸念を抱くんですね。
白井:自分も、社会が細分化してしまったというのは、強く感じています。それは空気としかいいようがないのですが、人と会っていても、街でお店や広告を見かけても、一つひとつは特化しているのですが、本当は全体があるからこその特化であるはずなんです。舞台表現でも同様に細分化が始まっていて、熱狂的なファンの人たちは特化して盛り上がっているのだけれども、分からない人にはまったく無縁、という状況がすごく多くなっていると感じます。
—そうした時代の中で、「身体と記憶」をテーマにした今回の演目は、どのような意味を持つのでしょうか。
白井:今回は一柳さんから、ダンスに焦点を当ててみたい、というお話があったんです。最初は驚きましたが、僕も興味がある分野でしたので、それは面白そうだ、と。
一柳:言葉を持たないダンスの身体感覚というものを今、提示してみたかったんですね。今回の第一部では、クラシックバレエからモダンバレエ、モダンダンス、そしてコンテンポラリーダンスへという歴史が踊られるのですが、ダンサーの皆さんを見ていると、その歴史を辿って現代、あるいはもっと先の未来のことも意識しているように見えます。この公演をきっかけに、自然とそういった意識が生まれていくとよいですね。

複数分野の結びつきの表現を、もう一回考え直す時期に来ているんじゃないか。(一柳)
—今回の演目では、“タイム・シークエンス”“リカレンス”といった、1970年代に一柳さんが機械文明と対話し、抗っていらした頃の楽曲も演奏されるようですね。
一柳:それは私が抱いている音楽の現状への懸念と結びつきます。今、先端的とされる表現、出し物で、現代音楽を使うことが減ってきています。そこで音楽はメインの出し物と合体してはいるんだけれども、一般的に流れているようなエンターテイメント性がどうしても入ってくる。いえ、エンターテイメントが悪いとはいっていません。しかし、メインの出し物が非常に先端的なものを提示し、総合的な表現をプレゼンテーションしているのに、音楽の方は本当に理想的な表現を追究しているのか、と違和感を抱くのです。
半世紀前、自分たちが活動していた頃の発想、思想の中に、「妥協」はなかったと思います。本当にやりたいこと、理想を自由に追求していた。その意味で、私がニューヨークから帰ってきたころに行われていたような、複数分野の結びつきの表現を、もう一回考え直す時期に来ているんじゃないか、という気がしているんです。
—妥協なき音楽、トータルな表現を追求するときに、今回の対話の核として身体=ダンスがある、と。
白井:物を作る時、「融合させよう」と僕たちはよくいいます。でもポジティブに、積極性として融合を目指そうとするがゆえに、一柳さんがおっしゃるような気がつかない妥協をしてしまっているのではないか……その危機感は僕も最近持つことがあります。
僕もダンサーとコラボレーションしてきましたが、演劇も、そして音楽も、ダンスのバックアップになってしまってはいけない。皆が本当の熟練、鍛錬、突き抜ける努力をする必要がある。強化されたもの同士が共存した時、それは初めて融合と呼べるのでしょうから。

一柳:今回やるのは一種の総合芸術です。古典的な総合芸術は、みんなで100を目指すものでしたが、それではどこかが崩れたら破綻してしまう。それは場合によって音楽がそうであるように、他の表現に依存してしまっている、ということです。そうではなくて今回は、それぞれの表現が100を出して自由に羽ばたき、全体で400、500へと向かっていくようなものにしたいんですね。
—第二部では白井さんがたびたび取り上げてきた現代アメリカの作家、ポール・オースターの作品から、『最後の物たちの国で』が扱われますね。20世紀以降を彷彿とさせるような、崩壊した世界で兄を探す女性のお話です。
白井:これはすべてが崩壊する話です。すべてが崩壊する中で、さて、我々は最後にどこに行くのか。その中で、この劇場空間、ダンサーの肉体、振付、一柳さんの楽曲、その演奏が「これは何だ?」と観客の皆さんから問われる。一つひとつの要素が、厳然として存在できるのかどうかのせめぎあいです。第二部のプロットをお渡しした時、一柳さんから“交響曲第8番 リヴェレーション2011”の名前が挙がったんです。
一柳:ええ、ピッタリだと思いました。
—「予兆」「無常」「祈り(レクイエム)」「再生」の4セクションで構成される、一柳さんが東日本大震災を受けて書かれた楽曲ですね。その中で踊るダンサーを、観客は眼前で観る、と。
白井:劇場が今後、都市の中で果たしていく役割は何だろう、ということをすごく気にしています。だからこそ、この劇場そのものを見せようともしているんです。スマートフォンで得た手の中の情報は、あっという間に消えてしまう。でも自ら足を運んで、五感で得たものは、記憶に残り、自分を形作っていくはずなんです。
昔の僕は、寺山修司の「書を捨てよ町へ出よう」という言葉に衝撃を受けました。それは、自分とは違う「異物」に出会うということであり、異物を異物だと思うということは、自分を知ることでもあります。場所と時間を共有することの意味――それを今、僕たちは一番発信しなければいけないのではないか、と思っているんです。

- イベント情報
-

- 一柳慧×白井晃 神奈川芸術文化財団芸術監督プロジェクト
『Memory of Zero メモリー・オブ・ゼロ』 -
2019年3月9日(土)、3月10日(日)全2公演
会場:神奈川県 横浜 神奈川県民ホールピアノ:一柳慧
構成・演出:白井晃
振付:遠藤康行
指揮:板倉康明
演奏:東京シンフォニエッタ
出演:
小池ミモザ
鳥居かほり
高岸直樹
引間文佳
遠藤康行
梶田留以
木ノ内乃々
五島茉佑子
児玉アリス
佐藤明花
鈴木彩海
鈴木春香
平雛子
まりあ
米持愛梨
上田尚弘
大橋武司
掛場一慶
郡司瑞輝
ながやこうた
水島晃太郎
吉﨑裕哉
料金:一般6,500円 学生3,000円
※学生は24歳以下が対象・枚数限定
※未就学児は入場不可
- 一柳慧×白井晃 神奈川芸術文化財団芸術監督プロジェクト
- プロフィール
-

- 一柳慧 (いちやなぎ とし)
-
1933年神戸市生まれ。ピアノを原智恵子、B・ウェブスターの両氏に師事。高校時代に毎日音楽コンクール(現日本音楽コンクール)作曲部門第1位入賞。1954年からジュリアード音楽院に学び、クーリッジ賞、クーセヴィツキー賞等を受賞。留学中にジョン・ケージと知り合い、不確定性の音楽を展開、61年に帰国。これまでに尾高賞、フランス芸術文化勲章、サントリー音楽賞等多数受賞。また紫綬褒章、旭日小綬章、文化功労者に顕彰される。平成28年度には第65回尾高賞、日本芸術院賞、及び恩賜賞を受賞。平成30年秋、文化勲章を受章。現在、日本・フィンランド新音楽協会理事長、神奈川芸術文化財団芸術総監督。(プロフィール写真撮影:Koh Okabe)
- 白井晃 (しらい あきら)
-
演出家、俳優。京都府出身。早稲田大学卒業後、1983-2002年、遊◎機械/全自動シアター主宰。劇団活動中よりその演出力が認められ、多くの演出作品を手がける。演出家として独立後は、ストレートプレイからミュージカル、オペラまで幅広く発表し、緻密な舞台演出で高く評価される。中でもポール・オースター作『ムーン・パレス』『偶然の音楽』『幽霊たち』やフィリップ・リドリー作『ピッチフォーク・ディズニー』『宇宙でいちばん速い時計』『ガラスの葉』『メルセデス・アイス』『マーキュリー・ファー』『レディエント・バーミン』など海外の小説・戯曲を独自の美学で演出し、好評を博す。神奈川県民ホール開館30周年記念事業 一柳慧作曲 オペラ『愛の白夜』(06年、09年再演)では演出を手がけ高い評価を得た。読売演劇大賞優秀演出家賞、湯浅芳子賞、佐川吉男音楽賞、小田島雄志・翻訳戯曲賞などの受賞歴がある。2014年4月KAAT 神奈川芸術劇場アーティスティック・スーパーバイザー(芸術参与)。2016年4月、同劇場芸術監督に就任。(プロフィール写真撮影:二谷友希)
- フィードバック 1
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-