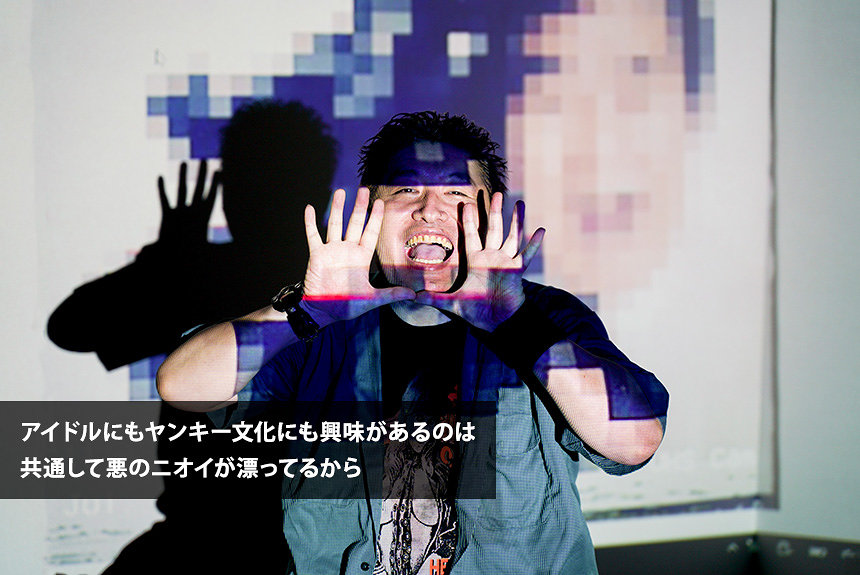もしかしたら今年一番の問題作になるかもしれない。そんな予感に溢れたNetflixオリジナルシリーズ『全裸監督』が、2019年8月8日より世界190ヶ国で配信開始された。本作では、アメリカ司法当局から370年の懲役を求刑されたり、50億円の借金を背負ったりといった数々の逸話を残す伝説のAV監督・村西とおると、その仲間たちの青春と熱狂が史実に基づくフィクションとして描き出されている。
地上波では間違いなく放送できない過激な描写も多く、Netflixだからこそ実現できた映像作品といえる。また、主人公・村西とおるを演じる山田孝之をはじめ、満島真之介、玉山鉄二、リリー・フランキーなど豪華俳優陣を揃えたキャスティングも話題だ。今回はこの『全裸監督』を、村西監督とも親交が深いプロインタビュアーの吉田豪に視聴してもらった。1980年代カルチャーにどっぷり浸かっていた彼の目には、この作品はどう映ったのだろうか。シーズン2の制作も決定し、『全裸監督』の波が広がる本作について、当時の思い出も交えて感想を伺った。
アイドルもヤンキーの嗜みだった。1980年代に惹かれた、いかがわしい文化
―村西監督は1984年にAV監督デビューしているので、『全裸監督』の舞台となっている時代に吉田さんは青春を過ごしていたことになるのですが、当時どのような目で村西監督を見ていたのでしょうか?
吉田:ボクが18歳になるのは1988年なので、表向きにはそれまで村西作品を見ていないってことになるんですけど(笑)。もちろん村西とおる直撃世代で、存在をはじめて知ったのはフジテレビで放送されていた深夜番組『オールナイトフジ』でした。女子大生がAVの内容を説明する「ビデオソフト情報」っていう、いまだったら確実にセクハラ&パワハラで問題になるコーナーがあって。そこで村西監督の作品も紹介されてたんですよ。なんだこれは! と視聴者側も出演者側も衝撃を受けましたね。
その後、番組のレギュラーだった片岡鶴太郎さんが番組中や『オレたちひょうきん族』(フジテレビ / 1981~89年放送)で村西監督のモノマネをするようになったこともあって、村西語録のひとつである「ナイスですね!」が学校内の流行語大賞を獲るんじゃないかってくらい流行ってました。あだ名が「ナイス」なクラスメートとかもいました。ボクの世代にとって、ああいう独特な英語の使い方をする人の原点は長嶋(茂雄)監督じゃなくて、村西監督だったんですよ。

1970年、東京都出身。プロ書評家、プロインタビュアー、ライター。徹底した事前調査をもとにしたインタビューに定評があり、『男気万字固め』、『人間コク宝』シリーズ、『サブカル・スーパースター鬱伝』『吉田豪の喋る!!道場破り プロレスラーガチンコインタビュー集』などインタビュー集を多数手がけている。

―そんなに盛り上がっていたんですね。
吉田:ちなみに1980年代は鶴太郎さんがいちばん面白かった時代だと思っていて。まあ、なかなか再評価されないんですけど(笑)。ボクシングやアートや俳優業に目覚める前は、とにかく下品かつ破壊的で、そこが村西監督ともシンクロしてたんでしょうね。
―それでいうとテレビからの影響が大きかったですか?
吉田:そうですね。1980年代は死ぬほど暇でなにもすることがなかったので、ずっとテレビを見ていました。それに当時はフジテレビの黄金時代でしたから。片岡鶴太郎さんだけじゃなくて、とんねるずやおニャン子クラブとか、いわゆる『夕やけニャンニャン』が青春だった世代で。学校のヤンキーたちと一緒におニャン子クラブ初の卒業公演に行ったこともあるんですよ。
おニャン子クラブ“セーター服を脱がさないで”(Apple Musicはこちら)
―ヤンキーとですか?
吉田:当時、「アイドル」はヤンキーの嗜みだったんです。人気のあるアイドルはヤンキーに牛耳られていて、「俺はこの子が好きだからお前らは応援するな!」って謎の圧をかけられるっていう。それでおニャン子の武道館公演に行ったら、いまと違ってインターネットもないからセットリストも簡単に入手できないんですよね。で、どうするのかっていうと公演が2部制だから、連れのヤンキーが1部公演終わりのオタクを暗がりに連れ込んで、胸ぐらを掴みながら「おい、1部のセットリスト教えろ!」って恫喝するんですよ(笑)。
その後、入場口の荷物検査でヤンキーたちの鞄から三段式警棒とか物騒なものが次々と出てきて没収されたりもして。「アイドルのコンサートは怖い!」と思いましたね。当時は親衛隊が腕っぷしの強さで会場を制圧していた時代でもありましたし。
―怖いと思いながらも一緒にコンサートに行ってたんですね。
吉田:悪のニオイに惹かれちゃうんですよね。あんまり平和なものとか無難なものが好きじゃなくて、もっと不穏なものが好き。世の中に受け入れられない、白い目で見られてるぐらいの状態が心地いいんだと思います。だからこそ、アニメ好きのオタクがやがてヤンキー文化に興味を持つようになったわけです。パンクを好きになったのもアイドルにハマったのも理由は共通していて。「危険なニオイがするぞ、ここ!」っていう。
―それでいうと、当時のとんねるずも不良のニオイがしますよね。
吉田:完全にそうだと思います。秋元康さんがとんねるずを高卒として打ち出したことで、ちょっと前のキャロル(矢沢永吉がリーダーを務めたロックバンド)とかクールス(舘ひろしが所属したロックバンド)と同じように当時の不良たちから支持を集めることになりましたから。秋元さんが命名した「学歴の途中下車」というフレーズ、いまでも忘れられないです。

Twitterでも伝わる、プロインタビュアーとしての客観的な視点を持つことへの思い
―豪さんが悪のニオイに惹かれるのはなぜなんですか? そのあたりに豪さんが興味を持つ人の共通点があるような気がして。
吉田:緊張感があるからですかね。冷や汗をかきたい。これは仕事の姿勢にもしていることなんですけど、とんでもない地雷を踏みそうで踏まない、そのギリギリのところを攻めたいんです。だから、世の中で怖がられているような人とか、嫌われているような人を取材するのがすごく好きで。
たとえば、ボクの『人間コク宝』シリーズ(コアマガジン)というインタビュー集に登場する人は、半分くらい前科者なんですけど、彼らにも言い分があるんです。でも、それがちゃんと世に出ることってほとんどないじゃないですか。あっても社会正義というフィルターを通されることが多い。小林旭さんをインタビューして、「オレがヤクザとゴルフしたからって、誰が困るってんだよ」ってタイトルの記事になったことがあるんですけど、井上公造さんが「あれは僕にはできないインタビューだからうらやましい」っていってました。
ボク自身は善悪のジャッジを下さず、相手のいい分をちゃんと引き出して、読者にジャッジしてもらう。そんな姿勢で仕事を続けていたら、次第にいろんなことに巻き込まれるようになって(笑)。
―なにがあったんですか?
吉田:「この人は客観的な視点で話を聞いてくれるから」ってことでスキャンダルの渦中にいる人から連絡が来たりするんですよ。つい最近もあるマンガ家さんから女性問題で報道される前に取材してほしいと連絡があって。そういうのって受けるか受けないかは別として、お金にはならないけど面白そうだから相談には乗るじゃないですか。

―自分から巻き込まれにいくんですね(笑)。
吉田:ASKAさんが捕まったときも、意識的にCHAGE and ASKAのスタッフジャンパーとかTシャツを着てテレビに出ていたんですよ。たまに「Tシャツが見えないように上着のチャックを閉めてください」とかスタッフに注意されて、「E and A」しか見えなくなったりしながら(笑)。ボクとしてはちょっとしたいたずら心でもあったし、そういうことでメディアからあっさり抹殺されちゃうことへの反発心でもあったんですけど、ファンの人が「吉田豪さんがASKAさんにエールを送ってくれた!」って深読みするようになって。最終的にはASKAさんがAbemaTVの特番に出演するときに、インタビュアー2名のうちの1人としてボクが選ばれるっていう。ちなみに、もう1人のインタビュアーは亀田興毅さん(笑)。
―そういう意味では、豪さんってあんまり自分を主語として語ることは少ないですよね。
吉田:そうですね。「俺はこう思う」じゃなくて、「この人はこういう人だから、どう思うのかはあなたが考えて下さい」っていうスタンスなので、意見を押し付けたくないし、一方的に「こいつはクズだ」みたいなことは絶対にいいたくないんですよ。「さあ、みんなで考えよう」という、『クイズ世界はSHOW by ショーバイ!!』(日本テレビ系列 / 1988〜1996年放送)の逸見政孝さんみたいな感じでやってます(笑)。

―そのスタンスはTwitterではけっこうわかりやすく出ていますよね。淡々と賛否のツイートをリツイートしていますし。
吉田:ボクの仕事は相手のいい分を聞くことで、それをどう思うかは読み手が決めればいいことだと思うんです。明らかに相手がどうかしたことをいっているときも、それを糾弾したりする気はないし、その間違いを掘り下げるのがボクの仕事で、それをそのまま提示したいんですよ。たまに「豪さんはどう思ってるんですか?」って聞かれることもあるんですけど、それを確認するのってすごく野暮じゃないですか? それくらい自分でジャッジしろよって。他人に判断を委ねちゃうのは絶対に危険なんですよ。
それに、すべてが善悪で判断できるとも思ってなくて。社会的には問題があるけど人間としては信用できる人とか、なにも罪を犯していないけど人間的に好きになれない人もいますから。村西監督も完全にどうかした人だし、その波乱万丈な人生は間違いなく面白い。その上で、それぞれがジャッジすればいいんじゃないですかね。
1980年代に青春時代を送った吉田の、村西とおるへの視線
―たしかに、『全裸監督』を見ても波乱万丈ぶりがよく伝わってきますよね。主人公のモデルとなった村西監督が、他の人たちと決定的に違ったものってなんだったんでしょう?
吉田:突き抜けていかがわしいかったですよね。やっぱり、次の世代のV&Rプランニングやソフト・オン・デマンドとかの名物監督なり名物社長なんかと比べると、完全に生き物として別種じゃないですか。やっぱり悪のニオイがするというか。1980年代から面白コンテンツとして村西監督を消費しようとする空気はありましたけど、それじゃ収まらないぐらいに危ない橋を渡ってきた人間ならではの凄みもあったし、言葉は丁寧だけど暴力のニオイもあった。
ボクも村西監督に取材したことがあるし、本が出るとサイン入りで送ってくれたりもしてくれるんですけど、、すごくフレンドリーな人ではあるし、いまも事務所は近所らしいんですが、一定の距離は保つようにしています(笑)。ある意味、アントニオ猪木に似ていると思ってるんですよね。事業欲が強いけど失敗していく感じや、キャラクターを演じきっているけれど実像は怖そうな感じとかが。
―それが村西監督の複雑さでもあるんでしょうね。
吉田:魅力はあるけど、下手に近づくと危険(笑)。ボクは村西監督のズレた感じが大好きなんですよね。たとえば、ある大手アイドル事務所の看板タレントのスキャンダルをネタにAVを作ったことがあるんですけど、ちょっと考えたら問題になるのはわかるじゃないですか。当然のごとく揉めて。でも、怒られると火がつくのも村西監督らしくて。
その後、過去にその事務所に所属していたアイドルを引っ張り出してきて復活させるんですけど、歌手として再起させるのかと思ったら手品を教え込むんですよ(笑)。それでパブとかをどさ回りさせる計画だったから、担ぎ上げられたほうはこんなはずじゃなかったと途中で決裂してしまう。端から見たらそうなることは予測できるんですけど、村西監督は冗談ではなく本気でやってるんです。そういうところがどうかしてますよね。

―村西監督への憧れも強いんでしょうか?
吉田:憧れというか、やっぱり思春期に衝撃を受けたリビング・レジェンドではありますからね。個人的に嬉しかったのは、2007年に幕張メッセで行われた『アダルト・トレジャー・エキスポ』というアダルトトイとかAVの展示会に呼ばれたことで。掟ポルシェと一緒にトークショーをすることになったんです。その前説を村西監督があの名調子でやってくれて。そのときに「自分もここまで昇り詰めたか」と感動しましたね。このイベント、クレイジーケンバンドとかZEEBRAとかマキシマム ザ ホルモンとかボーイズIIメンとか、めちゃくちゃ豪華な人たちのライブもあって。でも、ライブのブースだけ別料金だったから、ボーイズIIメンとか人が全然入ってなかったですけど(笑)。
1980年代の倫理観をアップデートする、『全裸監督』に見られた現代のリテラシー
―今回、豪さんには先行して『全裸監督』を見ていただきましたが、率直な感想を教えてください。
吉田:とにかく予算の違いがひと目でわかりますよね。こういうVシネぐらいでしか扱えないようなテーマでも、予算と時間をかけて作るとちゃんと面白くなるんだなって。そして、アクションシーンも激しいし、想像以上にスプラッターですよね。
―物語の展開上必要なシーンであれば、削除せず描くことができるNetflixならではですよね。
吉田:あと、フィクションの混ぜ方がうまくて、ファンタジーに昇華してますよね。ボクは原作(『全裸監督 村西とおる伝』本橋信宏著 / 太田出版 / 2016年)も読んでるんですけど、あれをそのまんまやっちゃうと現代ではアウトになる部分も多いと思うんですよ。そのあたりをうまくこの時代のリテラシーに合わせて作っているのが流石だなと。原作で引っかかった部分がほとんどクリアされてました。

―山田孝之さん演じる村西監督はいかがでしたか?
吉田:完璧ですよね。山田孝之さんが白ブリーフになった瞬間に「きた!」と思える。もともと憑依型の役者さんではありますけど、ここまで村西とおるをちゃんとやり切れるのかと驚きました。眼力スイッチが入っていないときの村西監督の得体のしれない凄みみたいな部分も、ちゃんと再現してるんですよね。あと森田望智さんが演じる黒木香も、顔は全然違うのに完全に黒木香なんですよ。

―他のキャストで印象に残っている方はいますか?
吉田:石橋凌さんも素晴らしかったですね。ボクの中で石橋さんはA.R.B.というロックバンドの人なんですけど、パンクスとしては乗り切れなかったんですよ。その後、松田優作さんの遺志を継ぐってことで役者に転身してからもモヤモヤしてきたんですけど、年齢を重ねて風格も出て、黒っぽいアダルト業者がハマりすぎでした。

―石橋凌さんは業界最大手の社長役として登場し、ことあるごとに村西監督を妨害しようとしますよね。そのあたりのAV業界黎明期の光と闇も本作では描かれています。
吉田:思った以上にアウトローの世界だったらしいですからね。そもそもエロ自体がアウトローというか、1980年代にビニ本を作っていた人に話を聞くと、ここではいえないようなことばかりですし(笑)。ヒッピー上がりの人が多かったせいか、薬物が当たり前みたいな。
―そういう時代だったんでしょうね。
吉田:AVにしても黎明期のスターである代々木忠監督が元闇社会の人ですからね(笑)。1990年代前半、『宝島』というサブカル雑誌がエロ本化していった流れがあって、そこにこの仕事を始めたばかりだったボクも少し加担していているんですよ。当時所属していた編プロで引き受けていたエロ特集の評判が良くて、次第にヘアヌード雑誌になっていったから。ボクは風俗特集とかAV特集とかを担当したんですけど、まあいかがわしいアウトローな人ばかりでしたからね。
風俗取材に行ったら、そこの店長さんが「『宝島』か、懐かしいなー」とかいってて、実は某ハードコアパンクバンドの人だったりとか、ヤクザの事務所みたいなところに通されたりとか、アポを取った時間にカメラマンが遅刻したら「こっちが頼んで取材してもらうわけじゃねえんだよ、コラ!」ってブチ切れられたりとか。某AV女優を取材したときも「私のバックには●●がついてるから」とか突然いわれたりで、これはスリリングな世界だと思ってましたね。そのときクリスタル映像にも行って、「ここが村西とおるの城だったのか!」とか感慨深い思いをしたのも、よく覚えてます。

―でも、どんな体験をしてもネタとして昇華できるのが豪さんらしいですよね。最後にお伺いしたいのですが、『全裸監督』の舞台にもなった1980年代のカルチャーは豪さんにどのような影響を与えていると思いますか?
吉田:時代としていちばん好きなのは1970年代なんですけど、10代を過ごしたのが1980年代だから、思い入れはそこにありますよ。ボクが18歳になって最初に借りたAVが、大好きだった岡田有希子さんにそっくりな女優さんが出ている企画ものだったんです。その後、編プロに就職してエロ本の仕事をするようになったときに、そのAV女優さんがVシネマの主演に選ばれてインタビューをすることになって。これは感慨深いなと思って取材に行ったら、その女優と映画プロデューサーの距離感がものすごく近くて、どうにも愛人関係のニオイがするんですよ(笑)。あからさまにいかがわしい状態で。
低予算だから写真撮影もボクが担当したんですけど、思い入れもあるから頭の中でフリッパーズ・ギターの“カメラ!カメラ!カメラ!”が流れるようなキラキラした感じもありながら、隣には愛人っぽいプロデューサーもいて、彼女は多いっきりパンチラしている(笑)。これはなんなんだろうと思ったんですけど、やっぱりボクの柱になる部分を作ったのが1980年代の文化なので、そうやって当時の人を取材できる機会があれば喜んで行っちゃうし、一生引きずり続けるんだと思いますよ。

- 作品情報
-
- Netflixオリジナルシリーズ『全裸監督』
-
Netflixにて全世界独占配信中
総監督:武正晴
監督:河合勇人、内田英治
原作:本橋信宏『全裸監督 村西とおる伝』(太田出版)
音楽:岩崎太整
出演:
山田孝之
満島真之介
森田望智
柄本時生
伊藤沙莉
冨手麻妙
後藤剛範
吉田鋼太郎
板尾創路
余貴美子
小雪
國村隼
玉山鉄二
リリー・フランキー
石橋凌
- プロフィール
-
- 吉田豪 (よしだ ごう)
-
1970年、東京都出身。プロ書評家、プロインタビュアー、ライター。徹底した事前調査をもとにしたインタビューに定評があり、『男気万字固め』、『人間コク宝』シリーズ、『サブカル・スーパースター鬱伝』『吉田豪の喋る!!道場破り プロレスラーガチンコインタビュー集』などインタビュー集を多数手がけている。
- フィードバック 6
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-