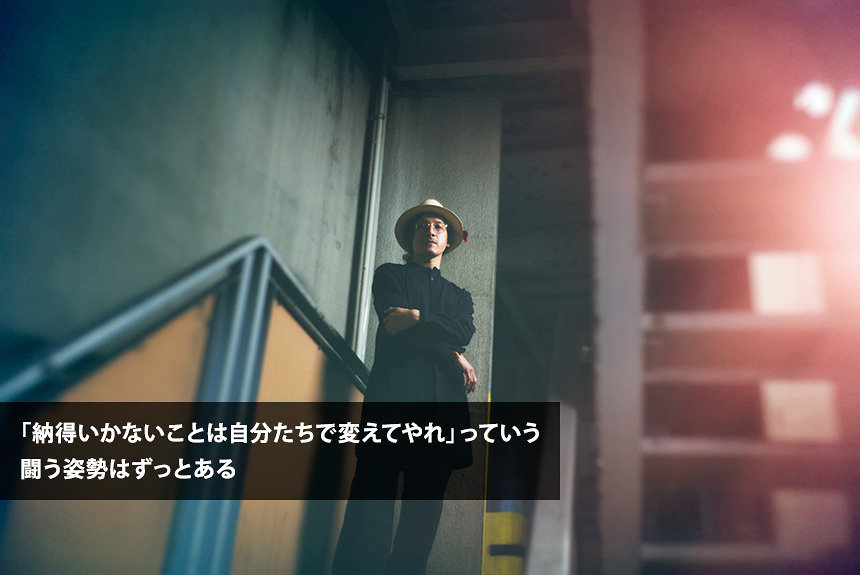日本のオルタナティブシーンを代表するバンド、downyが結成から20年の節目を迎えた。変拍子を駆使したハードコアサウンドとサイケデリックなVJを組み合わせた独自のスタイルで、NUMBER GIRLや54-71らとともに、異質な存在感を放っていた2000年代。活動休止期間(2004年12月~2013年10月)を挟んで、トラックメイクの色合いを強め、生のバンドサウンドとビートミュージックを組み合わせたような、現代的でありながら、やはり他の誰とも似ていない作品を生み落した2010年代。downyは常に革新的なバンドであり続けてきた。
2018年にオリジナルメンバーである青木裕が逝去し、サポートを務めていたトラックメーカーのSUNNOVAが正式メンバーとして加入するという、バンドにとって最大の変化を経て、通算7枚目となるアルバムが完成。タイトルはもちろん、「無題」である。
今回は、小林祐介(THE NOVEMBERS)、波多野裕文(People In The Box)、金子ノブアキ、アフロ(MOROHA)、薫(DIR EN GREY)、中尾憲太郎(NUMBER GIRL)、ミト(クラムボン)といった、downyと縁の深いミュージシャンからの手紙を青木ロビンに読んでもらいながら、20年の歴史を振り返るとともに、新作について語ってもらった。「アート」「オリジナリティー」「怒り」といったキーワードから、青木ロビンの表現の根本を紐解く。

2000年結成当時よりメンバーに映像担当が在籍するロックバンド、downyのフロントマン、ソングライター。zezecoとしての活動に加え、映画、アーティストへの楽曲提供、アレンジ、プロデュースも手がける。MONO、envyとともにフェス『After Hours』を立ち上げ、国内外での開催で成功を収めている。音楽以外にも、空間デザインや、アパレルデザイナー等、多岐にわたって活躍。
downyは、ロックバンドという総合芸術。THE NOVEMBERS・小林も感化された、創作におけるマインド
―今回はdownyの20年の歴史のなかで関わりの深いミュージシャンからの手紙を読んでいただきつつ、バンドのこれまでをお伺いしたいと思います。まずは、THE NOVEMBERSの小林さん。
「いまわからないものを、わからないままに」体験し、味わい、楽しむ。なるべく無心に。
例えば、目の前にある知らない花を見て美しいと感じた次の瞬間には、この花の名前はなんだとか、文化の中での根付き方だとか、市場価値は、とかいろんな言葉が頭を駆け巡ってしまうことがある。
いま目の前にあるものを、ただ味わうのは実はとても難しい。わかろうとしてしまうからだ。「わかること」は味わうことの一つのスタイルにすぎない。見慣れない図形に補助線が引かれることで、それが実は三角形と四角形から成る図形だったと「わかる」。その補助線は、知識や、訓練、修練、または一種の閃きによって引かれる。自分が、過去の体験をもとにすぐ「わかろうとする」重力圏内にいることを、downyは教えてくれた。音楽に限らず、目の前にあるあらゆるものを、まず見る、ただ見る、ありのままに味わうことの難しさを知ったことで、初めて「ものをわかる」ことの豊かさを学ぶことができた。そして、それが不可逆だということも。わからなかった頃、あの頃にはもう戻れない、だからこそいまの自分にしかできない「わからない」を思いきり楽しみたい。
『第七作品集「無題」』の完成、そしてdowny結成20周年、心よりおめでとうございます。
あなた達は僕の世界に補助線を引いてくれた偉大な芸術の一つです。
小林祐介

―downyの復活作である5作目と、ロビンさんがプロデュースをしたTHE NOVEMBERSの『zeitgeist』はどちらも2013年の11月にリリースされていますが、どういった経緯で近いタイミングでのリリースとなったのでしょうか?
青木:もともとはdownyが活動を再開する2年くらい前に、小林くんから「プロデューサーをやってもらえませんか?」っていう連絡をもらっていたんです。僕もいずれは音楽活動を再開させたかったから、いいきっかけになるかなと思ったんですけど、そこで震災(東日本大震災)が起きて。音楽だけにフォーカスすることができなくなったので、そのときは「また次回」って話をしたんです。だから、そのときはまだ会ってもいなくて、電話とかメールだけ。
downy『第五作品集「無題」』(2013年)を聴く(Apple Musicはこちら)THE NOVEMBERS『zeitgeist』(2013年)を聴く(Apple Musicはこちら)
―そのあとに仕切り直して、それがdownyの活動再開のタイミングと重なったと。
青木:そう。もう一度声をかけてもらったときは、downyの活動再開が決まっていて音楽モードだったから、「やれるかも」と思いました。最初に声をかけてもらって、シンプルに嬉しかったですね。自分自身、当時はもう「ミュージシャン」って感覚はなくて、ただの「音楽好きの人」でしたし、そんな自分に声をかけてもらえたのは過去にやったことが実った感覚もあって。蒔いてきた種が少しでも芽吹いてくれたのなら、ありがたいことだなって思いましたね。
―小林さんの文章のなかには「芸術」という言葉が出てきますが、ロビンさんがdownyとして音楽に向き合う感覚についてお聞きしたいです。
青木:自分にしか作れない総合芸術をやっているというか、シンプルに言えば、アートですよね。だからこそ、僕たちには映像があって、いつも一枚絵を描いているみたいなイメージで音楽を作ってます。自分の生活で得たインスピレーションを、どうやって立体的に表現するか。自分たちにしか作れないアートを作る気持ちでいつもやっています。

過去の作品は「壁」でしかない。downyの足跡は、自らの表現を磨き抜き、更新し続けてきた闘いの歴史である
―では続いて、People In The Boxの波多野さん。
僕がこれまでに最も影響を受けたバンドは、downyだと間違いなく断言できる。
「本当の意味でのオリジナルは存在しない」という言説があるが、downyを聴くたびに、その是非はともかく、あまり意味のない言葉であるように思える。downyの音楽は形こそロックバンドの体をとりながら、聴き手がこれまでに観たことのない景色をいつでも眼前に広げ、ショックを与えてきたからだ。一曲一曲がまさにオリジナルと呼ぶに相応しいと思う。
同時に、永久機関のように律動し続けるビート、暗くも鮮やかなグラデーションで縦横無尽に描かれる音像、謎めいた曲をさらに謎の情感で彩る歌は、まさにdownyという他ない。こんなの、かなうわけがない。
5thアルバム『無題』発表前のくらいの時期にTHE NOVEMBERSのケンゴマツモトが青木ロビン氏に引き合わせてくれて以来、個人的にも付き合いがあるのだけれど、時折ファンとしての自分が勝ってしまい、いつもインタビューのような質問をしてしまう。そして質問したところで、The Beatlesがルーツとか、ユニコーンが好きとか、なぜdownyのような音楽になるのか、全く要領を得ない。
けれど、こうしてリアルタイムで新譜が聴けて、しかもその度に自己を更新していく、そんな先輩の背中を身近でみられるということ、一音楽家として、それに勝る幸運はないように思います。
いつもありがとうございます。

―「いつもインタビューのような質問をしてしまう」とありますが、実際そうなんですか?
青木:初めて飲んだときは本当に質問攻めでした(笑)。彼は北九州の出身で、downyが福岡でライブをするときは観に来てくれていたみたいで。初めて飲んだ2週間後くらいに沖縄に泊りに来て、酔っ払って「セッションしましょう!」みたいな感じになって、本当に音楽が好きなんだなって思いました。
―小林さんや波多野さんといった下の世代の作り手との出会いは、自分たちがやってきたことを再認識する機会にもなったのではないかと思います。
青木:でも、自分はあんまり振り返らないんですよね。アルバムは「作り終わったもの」って感覚で。もちろんライブで演奏するときは、そのときのイメージを呼び起こすんですけど、基本的に作ったものはもう「壁」でしかなくて。

青木:彼(波多野)も言っているように、僕はとにかくオリジナリティーのある、僕らにしか作れないものを作りたくて、そうやって作り上げたものに感動してほしいんです。「すげえ!」でもいいし、極端に言えば「超嫌い!」でもいい。だから、僕ら放っておくと永久に作り続けちゃうんですよ。
―アルバムタイトルが毎回『無題』なのはその意識の表れですよね。あくまで、そのときにできたものでしかないというか。
青木:そう。毎回、そのときのベスト盤みたいな感覚なんですよね。
downy『第六作品集「無題」』(2016年)を聴く(Apple Musicはこちら)
2000年代前半の下北沢シーンで、downyは気骨あるバンドマンたちに愛されていた
―続いて、金子ノブアキさんです。
下北沢の路上でバッタリ会った裕さんに出来たてのレコードをもらった。
1音目を聴いたその瞬間から今まで、ずっと自分の体内で鳴り続けている。
音は、バンドは、不死である。
日本ロック界のしなやかな背骨、downy。
前進を続ける勇気に敬意を表して。

―金子さんとはどのような接点があるのでしょうか?
青木:最初の接点はRIZEじゃないですかね? ソロもすごくいいですよね。ダンサーと一緒にやってるの(パフォーミングアーツカンパニー「enra」とのコラボレーション)もかっこよかった。もともとdownyを好きでいてくれてて、よくライブを観に来てくれていたんです。活動休止前の最後の下北沢SHELTERでのライブも観に来てくれました。当時から、downyのライブにはミュージシャンがよく観に来てくれていたんですよ。
こっちからすると、向こうのほうが売れていたりするわけですけど、自分たちがかっこいいことをやっている自信はあったので、特に気にはならなくて……下手したらお客さんがバンドマンばっかりのときもあったんじゃないかな(笑)。周りにいたのが54-71とか、百々くん(MO'SOME TONEBENDERの百々和宏)とかだったから、とにかく男臭かったんです。
―2000年代前半は「対バンで仲よくする」という雰囲気はなく、シーン的にもわりとピリピリしていて、真剣勝負でしのぎを削っていたような印象があります。
青木:対バンの勝った / 負けたはありましたね。でも、それはリスペクトし合っているからで、打ち上げも普通にしてましたし。逆に、僕の目からすると、ゆるく音楽をやってるように見える人たちとは全く接点がなかったです。話しかけられても、興味がないから、「あ、どうも」くらい。でも、かっこいいバンドとは「また一緒にやろうね」となって、馴れ合いではない関係性があったと思います。

downyのオリジナリティーの原点にある、青木ロビンがひとり抱えてきた「怒り」。歳を重ね、家族ができても変わらないこと
―続いては、MOROHAのアフロさん。
downy、『第七作品集「無題」』を聴いた。
言葉にさせる気なんて一切ないくせにどういうつもりでコメントを求めているのだろう、という怒りが胸に溢れています。
自分の作品でしか太刀打ち出来ません。

青木:アフロくんらしい。声が聞こえてきますね。怒るくらい新譜がよかったと言ってもらえるのは素直に嬉しいです。アフロくんも若い頃からdownyが好きだったみたいで、沖縄にライブをしに来たときに呼んでくれて、観に行って、そのまま飲みに行ったのが最初ですね。それで僕らも『After Hours』に誘ったり。
青木:沖縄に住んでいていいことのひとつなんですけど、アーティストのみんながライブで沖縄に来るときに、「どこか連れて行って」とか声をかけてくれるんです。だから、東京にいるときよりミュージシャンに会う機会が多い気がします(笑)。
MOROHAは本当にオリジナリティーがありますよね、ギターの彼も超上手いし。対バンはなかなか実現していないですが、いつか戦うような対バンができたらいいなと思ってます。
―アフロさんが、downyの音楽を通じて自身の創作にも繋がるような「怒り」を感じられたというのはすごく象徴的で。downyの表現の根本には「怒り」という感情もあるように感じられるのですが、いかがでしょうか?
青木:僕はハーフで、香港にいるときは「日本人」と呼ばれて、東京に行ったら「外人」と呼ばれて、沖縄に行ったら「ないちゃー(本土出身者のこと)」と呼ばれてきて。いつもはみ出してるというか、ホームがない感覚は強く持っていました。
なかには「沖縄はまだドル使ってんでしょ?」みたいなことを言うやつもいて。多感な時期だったから、そういう言葉は抜けないトゲみたいに刺さって、心の奥底に「怒り」はありましたね。

青木:僕らが東京に行ったのはメジャーからのリリースがきっかけだったんですけど、なかなか好きなことをやらせてもらえなくて。それは僕らが中途半端なものを作っていたから、「ポップにもいける」なんて思われているということで。だからダメなんだと思ったんです。
外から誰かに触られてしまうような、「商材」にされてしまうようなものではなく、もっと尖って、もっとオリジナルなものを作って、そいつらを見返してやるっていう……そういう「怒り」というか「悔しさ」がパワーの源にはなっていましたね。
―現在はどうですか?
青木:年齢も重ねて、家族もできて、いちいち怒ることはなくなりましたけど、「闘う」っていう姿勢は変わっていないと思います。自分たちのやりたいことをやるために、今回で言えば自分たちでレーベルを作ったし、イベントをやったりもしているし。「納得いかないことは自分たちで変えてやれ」っていう闘う姿勢はずっとあると思います。
―近年で言えば、『After Hours』もそういう思想から生まれたものですよね。
青木:ロックは基本そういうものというか、反骨心から生まれるものですよね。今は「よくない」って言われても、いちいち怒らないけど、昔だったら「お前らよりマシだよ」って、ぶん殴ってたかもしれない(笑)。

2018年に逝去した青木裕とDIR EN GREY・薫。対談も実施した2人の物語には、まだ続きがあった
―続いて、DIR EN GREYの薫さんです。
DIR EN GREYで2013年に廻った北米ツアー。
その会場の楽屋でいつも流していたのが『第五作品集「無題」』。
現地のスタッフにも「これは一体誰?」とよく聞かれた。downyをちゃんと聴いたのはこのアルバムが初めてだった。
青木さんから届いたこのアルバムは、自分の中にある音の扉を解放させてくれた作品だった。無限の可能性を感じるのに、どこを切り取ってもdownyでしかない。
完全に理想のバンド像。
好きに決まっている。

―薫さんには以前、CINRA.NETで裕さんと対談をしていただいていて、裕さんとはとても近い距離にいた方ですよね。
青木:裕さんが持っていたメインのギターが3本あって、一本は僕の手元に、一本はworld's end girlfriendの前田くんに、もう一本は薫さんに渡したんです。「僕が受け取っていいんですか?」って言われたんですけど、本人が薫さんにすごく感謝していたし、好きだったし、「絶対に喜ぶと思います」って話をして。
青木裕『Lost in Forest』(2017年)を聴く(Apple Musicはこちら)
―裕さんはMORRIEさんやSUGIZOさんとも関係性が深いですし、秋山さんはBUCK-TICKの櫻井敦司さんのTHE MORTALでも叩いていたり、今回の企画もそうですが、downyのメンバーは交流が広いですよね。
青木:みなさんどこで知ったのかライブを観に来てくれていたみたいなんですよ。当時のことはうろ覚えですけど、普通にチケットを買って見に来てくれて、うちのマネージャーがびっくりした、みたいな話を聞いたことがあります。SUGIZOさんはもともとレーベル(EMBRYO)をやっていて、そこに所属していたhoneydipとdownyはよく対バンをしていたので、SUGIZOさんがレーベルオーナーとして見に来ることもよくありました。
―上の世代との交流からは、どんなことを得たと言えますか?
青木:『After Hours』の中心メンバーもみんな年上だし、当時一緒によくやっていた(中尾)憲太郎とか向井くん(NUMBER GIRL、ZAZEN BOYSの向井秀徳)、百々くんも年上かな? その頃、僕らはどこにいても「下の世代」って感じだったんですよね。
僕は一度休んじゃいましたけど、みんな何だかんだずっと続けていて、それにはシンプルに感動します。とはいえ生きてる以上、絶対に衰えはあるわけで。それでも若い子に負けないパワーでやり続けるのって、とんでもないパッションが要りますよね。そうやって続けている人に対しては、リスペクトの気持ちが強いです。

かつての同居人・中尾憲太郎との青春秘話。downy結成前夜を振り返る
―続いては、中尾憲太郎さんからです。
99年あたりに福岡から東京へ活動拠点を移すタイミングが一緒だったのでロビンと同居していました。
そのときはdowny前夜、2人で様々な音楽の情報交換をしていました。そのときに教えてもらって印象的だったのはThe Drumというバンドのアルバムで、元China Drumというメロディックパンクのバンドが改名して打ち込みを取り入れて大きく変化したバンドサウンドになったものでした。そのアルバムは酷評だったらしいのですが、私とロビンは大好きで良く聴いていました。そしてその時期はロビンにとってもそんなタイミングだったのかもなぁとThe Drumのアルバムを久々に聴きながら思い出すわけであります。

青木:実は一昨日も憲ちゃんと飲んだんですけど、憲ちゃんとは福岡時代、10代からの付き合いで、最初の出会いは共通の友人が僕の家に連れてきたときですかね。そのあとバンドをはじめて出たライブハウスの照明が憲ちゃんで。照明もやってもらったし、よく対バンもしてましたね。
downy『第一作品集「無題」』(2001年)を聴く(Apple Musicはこちら)NUMBER GIRL『SCHOOL GIRL DISTORTIONAL ADDICT』(1999年)を聴く(Apple Musicはこちら)
―ロビンさんと中尾さんは当時ルームシェアをしていたんですね。
青木:お互いミュージシャン仲間をよく家に連れて来たので刺激的な生活でしたよ、本当に(笑)。吉村さん(bloodthirsty butchersの吉村秀樹)と吉野さん(eastern youthの吉野寿)が夜中にいいちこを持って、「ガンガンガン!」ってドアを叩いたり、山ちゃん(toeの山嵜廣和)が作った棚が台所に置いてあったり。
遊びに来る人たちも含めて、音楽について情報交換してました。僕がdownyをイメージしてバンドのメンバーを集めているときに聴いたのがThe Drumで、特にそのアルバムの1曲目が好きで曲作りに影響を与えたと思います。そのあとThe DrumはあっさりChina Drumに戻っちゃいましたが(笑)。downyをはじめてからも「このバンドの立ち位置どう思う?」とか相談に乗ってもらっていました。

―復活したNUMBER GIRLは観に行かれましたか?
青木:沖縄来たときに観に行きました。うちの子どももNUMBER GIRL大好きなんですよ。振り返ってみると、憲ちゃんのおかげで広がった人脈もたくさんあって感謝してます。憲ちゃんは人と仲よくなる才能があって、いつもフラットなんですよね。本当に見習いたいです。
聴く者の感情を揺さぶり続けてきた20年。表現の原点に「怒り」はあれど、彼らは特定の感情を表現してきたわけではない
―では最後に、クラムボンのミトさんからです。
正直、この世にいない青木くんのギターの面影を絶対追いかけてしまうと思って、最初にロビンから新譜をもらった時に、ちょっと身構えてしまった。
でも、聴き終わった後の「downyはまだ生きている」という確信が凄くて、逆に嬉しさが先走った。
当たり前だけど、青木くんのギターの音は、downyの音だったんだ。
ロビンが僕に言った「かなり手応えある作品になりました」の言葉の意味がわかった。
青木くんの、いやdownyの音がこれからもずっと、僕らの感情を揺さぶり続けてくれる。
クラムボン ミト

―ミトさんも「同世代の盟友」みたいな感じでしょうか?
青木:ミトもdownyをやる前からの知り合いじゃないかな? クラムボンとdownyはよく一緒にライブをして、僕らの企画にも呼んだし、活動再開してすぐにクラムボンのトリビュートにも参加したり。まあ、ミトとはアホみたいに飲みましたね。去年末にクラムボンが沖縄にライブに来たときも2人で飲みに行きましたし、郁子ちゃん(原田郁子)も沖縄に来ると僕のカフェに遊びに来てたりしましたよ。
downy『第三作品集「無題」』(2003年)を聴く(Apple Musicはこちら)
―ミトさんは「僕らの感情を揺さぶり続けてくれる」と書かれていますが、downyの音楽から感じられるのは決して「怒り」の感情だけではなくて。特に今作を聴いていると様々な感情が揺さぶられて、そういうところもdownyの音楽を特別なものとしているんだろうなと思います。
青木:まあ、そもそもひとつの感情で生きてる人なんていないわけじゃないですか? 楽しい日もあれば、辛い日もあるわけですけど、そういう意味で言うと、downyはいい意味で無機質なのかもしれない。無機質だからこそ、逆に全部があるというか。「怒り」「優しさ」「愛」とかって、人間だからもちろん持ってるものですけど、自分たちが音楽を作るときに必要なものではなくて。

青木:今回で言うと、裕さんのことで「悲しい」とか、SUNNOVAくんが入って「嬉しい」とかはありますけど、それをいちいち「この曲はこういう感情」って作ることはないんです。
「自分たちにしか作れないものを作りたい」っていう思いだけがあって、感情的にはフラットで無機質なものを作ると、人間味だけが残るのかもしれないですね。

青木裕の喪失を乗り越えて。新メンバー・SUNNOVAを迎えて歩み出すまで
―ではここからは、新作と現在のdownyについてお伺いしたいと思います。まずはサポートを務めていたSUNNOVAさんが正式メンバーとして加入したわけですが、もともとの出会いは5枚目のリミックス盤(2014年)ですか?
青木:そうです。そのとき紹介してもらって、ライブにもよく観に来てくれて、飲みに行ったりしました。
downy“燦 SUNNOVA remix”を聴く(Apple Musicはこちら)
―もともとハードコアパンクバンドのギタリストだったそうですね。
青木:もともとそっちの界隈で、「自転車で学校行くときにいつもdowny聴いてました」みたいに言ってくれて。音楽のリズムをすごく理解している人だなって印象があって、僕も彼の作る音楽を追いかけていました。それでSUNNOVAくんには、裕さんがいつギターを持てなくなるかわからなくなってきたなかで、バックアップとして参加してもらうことにして。
―裕さんのギターの音を、SUNNOVAさんがサンプラーで出すことにしたわけですよね。
青木:そう。裕さんに、ライブでやってる10数曲分のギターの音を録音してもらっていて、裕さんの解説を聞きながらSUNNOVAくんとリハをして。3月19日のワンマンはもともと裕さんとやるつもりだったんですけど、数日前に体調を崩して、ちょっと難しくなってしまったんです。
すぐにどうこうってことではなかったので、SUNNOVAくんにお願いしてやることにして、当日の朝に裕さんに挨拶だけにしに行ったら、そのときにはもう亡くなっていて。到着する30分前くらいだったのかな……最初、ライブは中止のつもりだったんだよね?
マネージャー:僕は「やめてもいいです」って言いました。
青木:それで、ひとまず関係者とか友人たちにあちこち電話してたら、本当に未だに誰に言われたのか覚えていないのだけど、「もうステージ行っちゃったんだよ」って言われて。そうかと思って、「もう先に行ってるかもしれないから、僕らも行こう。やろう」ってなって。

青木:これはちょっとオカルトみたいな話になっちゃうんだけど、そのあと誰に聞いても、「そんなこと言ってない」って言うんですよ。
―……不思議な話ですね。
青木:とにかく、それがSUNNOVAくんのdownyでの初ライブ。そのときも頼もしかったし、友達としても最高だったから、すぐにメンバーになってもらうこともアリだったんだけど、そもそもトラックメーカーがギタリストの役割をやるわけですからね。既存の曲はまだ何とかなるにしても、一緒に曲を作るのはやってみないとわからないわけで。
でも、それにも食らいついてきてくれて、「これなら大丈夫だ」と思った矢先、昨年末にSUNNOVAくんがぶっ倒れちゃったんです。集中治療室に入るくらいの状態で、「これで何かあったらもうバンドが立ち上がれないかもしれないぞ」って僕らは思ってて。でも、そのあとにしっかり回復して、SUNNOVAくんも「やります」って言ってくれたので、正式加入を発表しました。
―“砂上、燃ユ。残像”には、裕さんのギターの音が使われていて、この曲タイトルは3月19日のライブのタイトルでもありましたよね。
青木:もともとあの日のライブでこの曲をやる予定だったんです。本人に確認できないから、ギターの音はEQまったくいじらずに入れています。
青木:裕さんとは“角砂糖”も途中まで一緒に作っていて、楽曲の頭に入ってるギターは「サイドチェインを生でやろう」って作った音。あとはノイズ的に散りばめたりもしているんですけど、「使っていいって言ってない。使うならもう一回やり直すのに」って声が聞こえてきそうなんで、オフィシャルには言ってないです。
downy“角砂糖”を聴く(Apple Musicはこちら)
―改めてですが、裕さんはdownyにとってどんな存在だったと言えますか?
青木:最初期からのメンバーは僕とマッチョ(仲俣和宏)と裕さんなので……家族以上のものではありますよね。音と音で繋がろうとするって、難しいことじゃないですか?

青木:僕がバンマスだから、僕のイメージに合わせてくれた部分もあるだろうけど、それでも「よし、出そう」ってなったら、ひとつの塊になって、お互いの魂に触っているというか、積み重ねてきたすべてを5人でギュッと形にするわけで。それをアルバムとしては6回、ライブでは何度もやって……だから、自分の一部だし、彼にとっても僕が一部だったと思います。
研究を重ね、現メンバーでdowny独自のサウンドを模索。原点回帰とも言えるような音が生まれるまで
―SUNNOVAさんとの制作によるこれまでの作品との変化については、どのように感じていますか?
青木:作り方は大きく変わってないんですけど、最後のサウンドデザインで、今までギターでやっていた部分をSUNNOVAくんとやるにあたって、どうすれば僕ららしいオリジナリティーが出せるかは、かなり研究しました。
立体的なサウンドにしたかったので、サブベースとかも使いつつ、でも出し過ぎると、バンドでできなくなるから、そこもいろいろアイデアを出してくれたり。あとSUNNOVAくんは結構歌を触ってくれて。僕は自分でやるとすげえリバーブかけたり、歌を遠くにしちゃうんですけど、「これくらいの音量がいいです」って、現行のサウンドにしてくれたというか。

―リズムの構築に関してはいかがですか?
青木:立体的なサウンドにするために今回ドラムはセパレートで録って、デザインされた音を目指しました。3枚目のときもそういう考えだったんですけど、当時は肉体的であることは求めてなくて、もうちょっとカチカチした感じだったんです。でも、今回は立体感がありつつ、訛りもちゃんと残しかったので、コンビネーションで叩きながら、キックはミュートして、ハットだけ録るとか、そういうことをしています。
downy“ゼラニウム”を聴く(Apple Musicはこちら)
―ラストに収録されている“stand alone”は初期のdownyっぽさを感じさせつつ、そこから展開してあくまで今のdownyの音になっていますよね。こういう曲で20年目のアルバムが締め括られているのは、とても意味があるなと感じました。
青木:今回レコーディングが一度止まってしまったので、何をきっかけにしてアルバムのモードに戻るのかが難しかったんです。いろいろ手探りでやっていくなかで、まずはシンプルにライブで新曲をやろうということになり、それこそ原点に戻るというか、ファーストの感じを新しいメンバーと作るイメージでした。
downy“stand alone”を聴く(Apple Musicはこちら)
青木:最初は「今さらこういうのは……」って思われるかなとも思ったけど、「いいね」ってなって、SUNNOVAくん含めてセッションをして。超難しい拍子なんですけど、SUNNOVAくんが入れてくれたピアノがめっちゃよくて、もう一度僕のPCに落とし込んだうえで、ライブでやりました。
―初期っぽさはありますけど、決してただの原点回帰ではないですよね。
青木:僕は最初もっとガシャガシャしたイメージで録ろうとしてたんですけど、秋山くんと話して。「ドラムの音はもっとモダンにしよう」という話でまとまって、それが功を奏しましたね。
マッチョもベースの音をすごい面白く作っていて、這うような感じなんだけど、ガツッとした印象も残しています。この曲を足がかりにして、バンドアンサンブルを重視しつつ分離のはっきりした、立体的な音を表現できたので他の曲にも取りかかるモードになれたんです。
生きることと作ることがイコールになった先で。音楽家として「自分の足で立つ」ということの持つ意味
―“stand alone”という曲名は、ある種の意思表示だと言えますか?
青木:意思表示というよりは、僕の内々にあることだと思いますね。つまるところ僕らはいつもひとりだし、今は味方も増えて、できることも増えたけど、結局自分の両足で立ってないと何もできない。そういう気持ちで作った曲です。

―今回手紙をくれた人たちは仲間だけど、でも彼らもやっぱり自分の足で立ち続けて、自分の表現を突き詰めてきた人たちで、だからこそ、仲間になれたとも言えますよね。downyの20年も、そうやって自分の足で立ち続けてきた20年だったというか。
青木:まあ、「20周年」みたいに言ってますけど、そもそもほぼ10年休んでいたバンドが言っていいのかって話ではあるんですよね(笑)。ただ、その約10年間のなかで、アルバムを7枚出せたのは大きなことだと思っています。
最初が4年で4枚だから、今思えば異常だったなって思うけど、それだけ精力的にやってこれたということで。途中の諸先輩方の話とも繋がりますけど、心と体のコントロールができなくなると、音が崩れるんですよね。
―活動休止期間もありつつ、心と体のコントロールの仕方を、バンドとしても、メンバーそれぞれも、これまでのキャリアのなかで身に着けることができたと。
青木:もっと言えば、創作自体が死生というか、僕らはそれを強く感じざるをえない環境になったんですよね。生きているから音楽を作るし、生きているから表現をするし、これからは逆算して、「あと何枚作れるだろう?」って考える必要もあるかもしれない。だから、昔みたいに「怒り」の勢いだけで作るわけじゃなく、その土台に肉づけされた僕らの生活、音楽のキャパシティーがあったうえで、これからも変わらずに作品を作り続けるつもりです。


- リリース情報
-

- downy
『第七作品集「無題」』(CD) -
2020年3月18日(水)発売
価格:3,080円(税込)
RHEN-00011. コントラポスト
2. 視界不良
3. 36.2°
4. good news
5. 角砂糖
6. ゼラニウム
7. 砂上、燃ユ。残像
8. pianoid
9. 鮮やぐ視点
10. adaptation
11. stand alone
- downy
- イベント情報
-
- downy
『雨曝しの月』 -
2020年6月6日(土)
会場:大阪府 梅田 Shangri-La2020年6月7日(日)
会場:愛知県 名古屋 CLUB UPSET2020年6月13日(土)
会場:東京都 渋谷 WWW X料金:各公演 前売4,000円(ドリンク別)
※高校生以下は写真付学生証とチケット半券の提示で1,500円キャッシュバック
- downy
- プロフィール
-

- downy (だうにー)
-
2000年4月結成。メンバーに映像担当が在籍する、特異な形態をとる5人編成のロック・バンド。音楽と映像をセッションにより同期、融合させたライブスタイルの先駆け的存在とされ、独創的、革新的な音響空間を創り上げ、視聴覚に訴えかけるライブを演出。2004年に活動休止し、2013年に再始動。2018年にギタリストの青木裕が逝去。2020年2月、SUNNOVA(Samlper,Synth)が正式メンバーとして加入。2020年3月18日、『第七作品集「無題」』をリリースした。
- フィードバック 10
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-