うごめくカルチャーと共に生きることは、どこかで社会とつながって生きることだ。ならば、「文化の社会的役割とは?」という問いは、しゃらくさいと切って捨てるのでも、行政や事業の運営者のみが考える問題でもなくて、私たちの日々と強く結びついたトピックであるはず。
2015年から「長崎市チトセピアホール」を運営し、その斬新な取り組みから全国的な注目を浴びるようになった出口亮太と、コンテンツレーベル「黒鳥社」主宰の編集者・若林恵。2人がじっくりと語り合ったのは、今「文化」は「公共」の夢を見ることができるのか、という可能性についてだった。
文化施設の社会的な機能とは何なのか、大きなテーマになってきている。(若林)
―昨年2019年7月に、チトセピアホールで若林さんを招いた講演会を開催されたそうですね。
出口:そもそも僕が若林さんのことを強烈に意識するようになったのは、編集長を務めていらした『WIRED』日本版の「NEW CITY」特集(Vol.24、2016年8月発売)に載っていた文章なんですよ。さしたるコンテンツもないのにハコモノを作ってどうするんだ、という内容でした。若林さんの単著『さよなら未来』にも収録されていますね。

1979年長崎市生まれ。2015年、若干35歳で長崎市チトセピアホールの館長に就任、これまでに50本あまりの企画を運営。近年では、ホール内での事業にとどまらず、教育機関や医療機関、地元のNPOとの協働事業を企画運営しながら、現場での実践をもとにした公共文化施設についての講義を県内の大学でも行う。また、近隣の公共施設と連携し長崎市チトセピアホールで企画した事業を巡回させるネットワーク作りも行っている。

―「Pitchforkとバワリー・ボールルーム」という文章ですね。
出口:身内や業界の内側でそんなことを言ってくれる人は意外といないし、行政もハコを建てることありきで話を始めてしまいがち。そこをスパッと鋭い切り口で書いていらして、ぜひ、チトセピアホールで行っている『あたらしいハコモノのカタチ』という文化講演会のシリーズでお呼びしたいな、と思ったんです。

若林:そもそも文化施設を作るということが何をもって正当化されてきたのか、という話を、僕としては珍しく真面目にプレゼンしたんですよ(笑)。そもそも、「文化」ないしそれにまつわる装置には、ある種のコンテクストが埋め込まれている、と。
一つは近代化のなかで、「国民をきちんとした近代人へと教化していく」という立てつけにおいて正当化されてきた、というコンテクスト。たとえば戦後日本でも、新しい民主国家として国民を育てていくための文化行政、という意味合いがあったわけです。しかし、このようなトップダウンの「教養」は、今では疎まれるようになった。
一方で、産業社会における市民が楽しむ余暇、というコンテクストがある。こちらは消費文化との接点において、たとえば六本木などに私営の美術館といった文化施設が建てられていったわけです。けれど、市場に委ねたために経済的な合理性に見合わない文化は扱いづらくなってきてしまった。

1971年生まれ。編集者。ロンドン、ニューヨークで幼少期を過ごす。早稲田大学第一文学部フランス文学科卒業後、平凡社入社、『月刊太陽』編集部所属。2000年にフリー編集者として独立。以後、雑誌、書籍、展覧会の図録などの編集を多数手がける。音楽ジャーナリストとしても活動。2012年に『WIRED』日本版編集長就任、2017年退任。2018年、黒鳥社(blkswn publishers)設立。
―旧来の2方向の「文化」が、共に手詰まりなんですね。
若林:既存のコンテクストと、それを享受する側の人間の感覚がもはや乖離しだしている中で、もう一度どのように結び合わせるのか。文化施設の社会的な機能とは何なのかということが、大きなテーマになってきているわけです。
ただ東京はそれでも、無理やりマーケットソリューションで……つまりかろうじて金回りがいいことで課題を解決してしまえるところがある。一方で地方は、予算も含めたスケールが小さい分、危機感が強いだろうし、状況に対して小さな穴をプスプス開けている人がいると思うんですね。それこそ出口さんのような、熱心というか、変な人もいるわけですし(笑)。
出口:僕は民間の管理会社の人間でして、2015年から指定管理者としてチトセピアホールを運営しています。いわゆるPPP(Public Private Partnership、公民連携)の枠組みですね。自主事業として、今年度であれば劇団のマームとジプシーや、古典芸能では浪曲師の玉川奈々福さん、春風亭一之輔師匠など、「今」の表現者の方々にお越しいただきました。先ほど触れた文化講演会も、この自主事業の一環ですね。


出口:自主事業にかんしては長崎市からの事業予算がゼロなので、チケットの売り上げ、あとは助成金や協賛金で賄っています。たしかに企業は、利益を追求するものなのかもしれません。でも文化施設はもっと面白く、同時代的であるべきだと考えて活動することで、一定の成果を出しながら、少しずつ認知も高めてこられたと考えています。
―出口さんは以前のインタビューで、「文化は大事だから大事」というトートロジーの論理では、外に開かれた公共性が生まれない、という話をしていましたね。
若林:本当にそうだと思う。僕は2018年、パスカル・ロフェという指揮者とのトークイベントに、作曲家の藤倉大さんと一緒に出たことがあるんですけど、そのときの話が面白くて。
―フランスを代表する指揮者で、コンテンポラリーの世界でも有名な方ですね。
若林:僕はトーク相手としてちょっかいを出してやろうと思って、「そもそも自分はオーケストラというものがすごく嫌いだ」と話したんですよ(笑)。オーケストラは、近代の軍隊のモデルに依るものだろう、と。そうしたらパスカル・ロフェは、顔を真っ赤にして怒り出したんです。

『あいちトリエンナーレ 2019』は、アートの役割をきちんと表明する千載一遇のチャンスでした。(若林)
―パスカル・ロフェは何と言って怒ったんですか?
若林:かつてオーケストラが近代的な軍隊モデルであったことは認める、でも今はそうではない、と言うんです。彼の話は、オーケストラに対する助成金をどのように正当化するのか、あるコミュニティーがオーケストラを持つことへの説明責任を果たしていました。
具体的には、「現在のオーケストラは、新しい市民社会のモデルを提示している」と語ったんですね。地下鉄に乗るとき、もしかしたら同じ車両にテロリストが乗っているかもしれないと恐怖を感じながら皆が生きていくような社会でいいのか。そこで民主主義的な理念、新しいモデルを、社会に先んじてオーケストラが提示していくのだ、と。

若林:熱いなあ、さすがだな、と思いました。実際に彼らはオーディションする時も、応募者のことが見えない状態で審査するそうなんです。年齢やジェンダー、肌の色がわからない状態で、ダイバーシティを実現する雇用の形態にもチャレンジしている。それがオーケストラのミッションだ、と。感動しましたね。フランスでも「文化は大事だから大事」なんてことは通用しなくて、きちんとしたロジックを考えている。
出口:若林さんの「2020年代の希望のありか:後戻りできない激動の10年を越えて」(参考記事:Rolling Stone Japan)という文章で、文化施設専門のアメリカのコンサルティング会社「La Placa Cohen」が3年ごとに行っている定量調査「Culture Track」に触れていましたね。
最新の2017年のレポートを僕も読んでみたんですけど、文化は何の役に立つのかという問いに対して、きちんと応答していました。文化は個人の内面に変容を与えるものであり、コミュニティーの構築や教育に役立つものである。他者への寛容さや多様性を文化によって育むのだというロジックを、きちんと周りに伝えるために知恵を絞っていました。

若林:彼らは9.11をきっかけに定量調査を行うようになったんです。あの後、アメリカの文化施設は何をやったらいいのか……愛国心を煽るのでもない、かといってみんなが安らぐものを作るのが文化施設なんだっけ、と本当にわからなくなった時期があったようなんですね。文化施設全体のフレームを考え直すためには、みんながそこで何を感じているのかちゃんと調査しよう、となった。
近年は文化が民主化され、たとえばミケランジェロやカラバッジョといった西洋絵画を鑑賞することと、コーチェラに行くことが完全に等価になっている中で、文化施設は何を期待されているのか、何を提供するのか。そのロジックを、調査をもとに考えている。
若林:昨年の『あいちトリエンナーレ 2019』の動向は興味があって追いかけていたんですが、アートの役割を――気持ちよくなるとか、教養として授かるのではなく、さまざまな意見が非言語的にぶつかり合うことで寛容性を育むものだ、ということをきちんと表明する千載一遇のチャンスだったように思ったんです。ところが、それが語られる前に政治的な空中戦がはじまって、個人的には非常にモヤモヤしてしまい……「誰かちゃんとアートの話をしてくれよ」って。

若林:唯一彫刻家の小田原のどかさんという方が『美術手帖』誌上で問題になった展示に出品されていた全作品の解説をしてくださって、「やっと出た!」と感動したんですが、本来であれば、それを真っ先にキュレーターなり企画サイドが提示すべきだったように思うんですよね。(参考記事:『美術手帖』私たちは何を学べるのか? 小田原のどか評「表現の不自由展・その後」)。
社会に受け入れられるかどうかは別にして、アートがいま社会においてどういう役割を担おうとしているのか、何が期待されているのか、あるいは企画者がなにを期待しているのかを、政治ではなく、アートの話として聞きたかったんですけど、具体的なアートをそっちのけで、「表現の自由」をめぐる抽象論に覆い尽くされてしまい……個人的にはとても残念でした。
―そうした社会的情勢の中でチトセピアホールは、尖ったプログラムを組むことで、地域におけるオルタナティブスペースとして機能させようとしてきました。
出口:去年の秋に、金沢の『地域における文化施設とはどうあるべきか』という研修会で事例発表をしてきました。その会の後に参加者から話しかけられた内容が面白かったんです。

出口:金沢21世紀美術館は国家の文化観光戦略のうえでドライブさせ、質の高いものを提供している。一方で、縮小していく地域社会という前提の中で活動するチトセピアホールは対照的だ、と。
おそらくチトセピアホールのような現実=環境はどの地方においても珍しくなくなるでしょうから、僕たちはまさに新しいモデルを提示していくべきだな、と思いました。
若林:それはどちらか片方だけじゃダメなんじゃないかと思います。複数のミッションを同時に走らせておかないと危ないんですよ。観光政策の中だけで文化施設をドライブさせようとしても、最近みたいに感染力の高いウイルスが出たら一発でアウトじゃないですか。金沢がそうであるということではなくて、一般的に観光経済って依存的でサステナビリティーがない、危ないビジネスなんですよ。
日本に来て金を落としてくれ、って言うだけなのもダサいでしょう。たとえばミュージシャンだったら、良いプレイヤーやスタジオがあるから、みんなアイスランドへレコーディングしに行く。それはカッコいいし、大味な観光政策とは異なるもの。そうしたローカルな市民との関係性やサステナビリティーという点で、文化施設のミッションは複数走らせておくべきでしょう。

ラストワンマイルの使い方と開発は、広く開かれているんですよね。(出口)
―出口さんは2020年度からチトセピアホールに加え、併設されている長崎市北公民館を含めての一括管理を行う予定だそうですね。
若林:関連したトピックで、イギリスで一昨年「孤独担当相」が新設されたように、「孤独」という社会問題への対策が注目されていることは気になります。医療や経済といった複数分野が連携・連動した対策になるわけで、文化もその中でうまく立ち上げ直すことはできる。
出口:他の分野とのつながりで言えば、学びも含まれるかも。SDGsでも謳われているように、多分野に連鎖した社会的課題の解決のためには、こちらもコレクティブインパクトを目指した連携を視野に入れないといけないわけで、そのための場として機能することは意識しています。そういう意味ではスポーツを軸に子育てや教育、街作りまで視野に入れたスタジアムシティみたいな考え方にはとても親和性を感じますね。
公民館の英訳は、文部科学省が海外向けに出している文書ですと「Community Learning Center」となっているんですよね。学びの場――義務教育の期間を過ぎた人にも学ぶ権利が保障されており、その学びが実現する場であることを打ち出している。
その上で僕たちの現状を考えると、「ホールについてくれる利用者」の方々が増えてきたんですよ。落語にもジャズにも、講演会にも来る、というような。すごく嬉しい話ですし、学びの場としての公民館へとつながるような手応えを得ているんですよね。

若林:先だって「90年代のヒップホップがすごく楽しくて、毎週のようにシスコに通っていて、面白かった」と言う人がいたんですが、彼が面白かったのはヒップホップ自体ではなくて、毎週、渋谷・宇田川町のシスコにレコードを買いに行っていたことかもしれない。つまり、文化と習慣化という話です。
今、音楽配信はグローバルでは金曜日に新譜が出るので、僕もバーッとチェックする。それを長く続けていると、流れがわかる。各メディアが年末に出すベストランキングに載るものはだいたい知っているようになり、「ピッチフォークはなんでこのアルバムがこんな下なんだ」とか言い出すようになる(笑)。習慣化に向けた行動変容という話は、アプリのUXのデザインなどでは基本として言われる話ですが、文化を考えるときに、もうちょっと意識していいかな、と。
―うごめく文化に継続的に触れることは、世界のダイナミズムを感じることにつながりますよね。
出口:若者は文化を通じて社会とつながり、成長する面がある。「文化を通じた社会」を地方でも感じられる、現代にコネクトする場として機能すべく、小さな試みを重ねています。公民館で行う講座も、LGBTQを含めた現代的なものにアップデートできるはずです。

若林:あとはね……ここまでの話で前提としている民主主義って、実は効率は悪い、ということは踏まえたほうがいい。
―若林さんの責任編集による『次世代ガバメント 小さくて大きい政府のつくり方』にも、デンマーク政府関係者が涙目になりながら努力しているエピソードがありました。
若林:中国のような管理体制をとるのでもなく、一方で西洋的なシチズンシップも根づいていない日本社会はどうするのか。先日読んだ、前田勉『江戸の読書会』という本は、江戸の儒学塾から始まった読書会が明治以降に近代化したときの公共性を準備した、という話なんだけど、ヒントにはなるよね。身分制の社会において、農民から武士の子まで集うダイバーシティ的な場がポコポコあった。

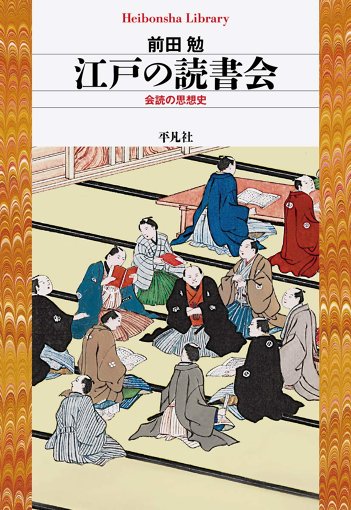
若林:いや、要はさ、新橋のサウナにいったら猛然とパソコンで仕事をしているオッサンがいるわけだし、カラオケボックスだって別に歌わなくてもいい場所として多様化・複合施設化しているし、キャバクラだって昼キャバみたいに営業時間が前倒しになって、お年寄りの方が集まっているわけじゃない?(笑)
それって既にコミュニティスペースじゃないか、まるでWeWorkじゃん、と定義するところから始められることはあるはず。これだけ世にはトークイベントが溢れている中、コミュニティスペースとしてのホールや公民館が選択肢に上がってもいいでしょう?
―運営側だけでなく利用者側にもさまざまな可能性があるわけですよね。チトセピアホールが建物の2階、公民館は3階でつながっていることも示唆的です。
出口:今でもホールは、たとえば平日の午前中に椅子を取っ払って、子供たちが遊べる全天候型の体育館として使えるようにしています。僕は既存の施設を使い倒していくという意味でタクティカルアーバニズム(公共空間の長期的変化を目指した短期間、小規模からはじめる社会実験)にはとても共感を覚えていて、ホールを使うという目で見ると音響やキャパが気になりますけど、屋根と電源があればオッケーじゃんという目で見れば、ライブハウスにもなる。そうした大きな政策を実現するローカルなラストワンマイルの場としての使い方と開発は、広く開かれているんですよね。公民館も同様です。
若林:僕はよくミュージシャンに、ライブだけでなくてトークイベントをやれ、と言うんですよ。バンドやりたい高校生を地元で集めて、曲の書き方を教えてあげるとか。美術の道に進みたい中学生が、アーティストのリアルな話を聞ける、というのもすごく価値がある。そうしたラーニングへの貢献、連動の仕方はあるわけです。
出口:消費者としてではなく、より能動的なポジションで皆さんに参加してもらえるようにしていきたいですね。『あいトレ』の話に戻りますが、ニッセイ総合研究所の吉本光宏さんのレポートで引用されていた経済学者ケインズの言葉がとても印象に残っています。「公的機関の仕事は、指導したり、検閲したりすることではなく、勇気と自信とチャンスを与えることなのです」と(参考記事:『ニッセイ基礎研究所』基礎研REPORT)。何かをセーブする施設管理ではなく、若者や市民の背中を押してあげるような場を目指したいですね。

- プロフィール
-
- 若林恵 (わかばやし けい)
-
1971年生まれ。編集者。ロンドン、ニューヨークで幼少期を過ごす。早稲田大学第一文学部フランス文学科卒業後、平凡社入社、『月刊太陽』編集部所属。2000年にフリー編集者として独立。以後、雑誌、書籍、展覧会の図録などの編集を多数手がける。音楽ジャーナリストとしても活動。2012年に『WIRED』日本版編集長就任、2017年退任。2018年、黒鳥社(blkswn publishers)設立。
- 出口亮太 (いでぐち りょうた)
-
1979年長崎市生まれ。東京学芸大学で博物館学を学んだ後に長崎歴史文化博物館の研究員を経て長崎市チトセピアホールの館長に若干35歳で就任。先鋭的な企画と助成金に頼らない運営スタイルが、地方における中小規模の公共ホールの新しいかたちとして注目を集める。その活動はホール内にとどまらず、近隣の公共施設や教育機関、医療機関、地元のNPOなどを巻き込んだネットワーク事業を展開する。また、現場での実践をもとにした運営論について全国公立文化施設協会研究大会をはじめ各地で講義を行う。活水女子大学非常勤講師(舞台芸術論)。2020年度からは市内で最大の利用者数を誇る長崎市北公民館の館長も兼任する。
- 長崎市チトセピアホール
-
長崎市千歳町に1991年に開館した500席を擁する多目的ホール。先鋭的な企画、オルタナティブスペース的な空間活用、助成金に頼らない運営を特徴とする自主事業活動で注目を集める。これまでの出演・登壇者は伊藤ゴロー、角銅真実、神田松之丞、岸野雄一、スガダイロー、高浪慶太郎、瀧川鯉八、立川吉笑、玉川太福、玉川奈々福、内藤廣、中島ノブユキ、中村達也、二階堂和美、柳亭小痴楽、若林恵、渡辺航など。事業内容は舞台芸術の分野だけでなく、まちづくり、建築、福祉、医療、食育分野とのコラボレーション企画も多く、公共ホールの可能性を拡張する活動を続けている。
- フィードバック 4
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-


