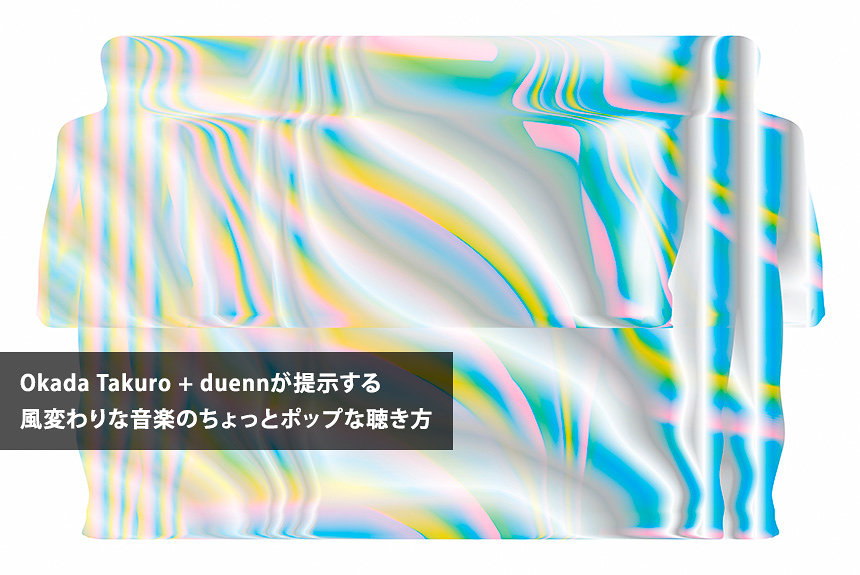毎日のように同じ時刻に鳴り響く防災行政無線の放送。店先で通行人に向けてマスクを売り込む声。不気味なほど静まり返った繁華街。あるいはこれまで気づきもしなかった虫の音との出会い。アパートの一画は以前に比して賑やかだ。新型コロナウイルスの災禍は都市部の音風景を少なからず変えてしまった。「新しい生活様式」という言葉を持ち出すまでもなく、多くの人々の生活様式それ自体が変わりつつある——むろん変わりようがない人々もいる。そのような時代に新しい録音作品はどんな意味を持つのだろう。
ギタリスト / 作曲家 / プロデューサーとして活躍する岡田拓郎と、福岡を拠点にイベント企画やレーベル運営も手がけるサウンドアーティストduennによる、2016年の『無常』以来4年ぶりとなるデュオアルバム『都市計画』が5月20日にリリースされた。レコードショップではアンビエントミュージックのコーナーに置かれるようなささやかで穏やかな作品である。だがよく耳を傾けて音を観察してみると、なにやら奇妙に動き回るメロディーとつかみどころのない質感に釘づけになってしまう。ポップスのようでいてヘンテコな形をしている。
再生環境は高級スピーカーでもiPhoneでも構わない。それぞれに特有のサウンドがリスナーをとりまいていく。『都市計画』はおそらく、環境音のように身近な響きでありながら、日常の音風景を一変させてしまうような面白さも秘めている。そもそも音楽とは生活に寄り添うとともに、思考の可能性を開いてくれるものではなかったのだろうか。岡田拓郎とduennが語る言葉は、コロナ禍でも変わることのないそうした音楽の意義を、改めて見つめ直すことへと導いてくれるはずだ。

1991年生まれ。東京都福生市育ち。2012年にバンド「森は生きている」を結成。P-VINE RECORDSより『森は生きている』、『グッド・ナイト』をリリース。2015年に解散。2017年10月、ソロ名義「Okada Takuro」としてデビューアルバム『ノスタルジア』を発表。2020年6月、約3年ぶりとなる待望の2ndアルバム『New Morning』をリリース。

福岡在住。エレクトロニクス / コンポーザー。必要最小限の機材でミニマル的な作品を制作。国内外のレーベルより多数の作品をリリース。ソロワークの他、Merzbow、Nyantoraと共にエクスペリメンタルユニット「3RENSA」、写真家吉田志穂とのアートユニット「交信」としても活動中。Nyantoraとアンビエントイベント「Haradcore Ambience」共催。
「ザ・ドリフターズで言ったら高木ブーみたいなもの」――実験的な音楽が持つ、この社会における意味
―コロナ禍のタイミングで新しい録音作品をリリースしたことについて、どう思いますか?
duenn:自分たちなりのささやかな社会実験という気持ちはあります。ポップスとも実験音楽ともつかない、アンビエントな、ある種曖昧なものを受け入れてくれる土壌がまだ社会のなかに残っているのかを知りたいと思っていて。
岡田:今の世の中って、中間の立場を取るような考え方が嫌がられることが多いと思います。でもこれだけ情報があふれていたら、どんな意見でも正解を見出すことが難しいと思うんです。もちろん作品が中立的な意味合いを持っているとは思いませんが、そうした環境下で音楽から響きだけを抽出したような、けれど音楽の立場としてはオブスキュアなものについて改めて考えてみようと思いました。
―通常のポップスとは異なるこうした実験的な音楽には、どのような意義があると考えていますか?
duenn:そもそもどんな音楽も歴史を遡るとアンダーグラウンドなものに行き当たるわけじゃないですか。そう考えると、ある種エンタメ化しているのが不自然な状況なのかなと思います。
岡田:音楽や芸術が社会の外側にある思考を引き立てるようなものだとしたら、アンダーグラウンドな音楽のプロセスって、音楽以外にも広く応用できるものだと思うんですよね。たとえば、硬直化した思考に対して社会の外側からテコ入れすることもできるかもしれない。
やっぱり資本主義下における大衆音楽はそれ自体が硬直化していると思うんですよ。日本の場合は特に。けれどもアンダーグラウンドな音楽というのは、常に既成の概念に囚われないことへと挑戦してきたものだと思うんです。今のような社会ではそうした音楽は商業的な場や、スピーディーな損益を考えれば真っ先に淘汰されてしまうかもしれませんが、そこをなくしてしまうのはものすごく危うい話だと強く思います。
duenn:たぶんですね、我々がやってるようなアンダーグラウンドな音楽というのは、ザ・ドリフターズで言ったら高木ブーみたいなものだと思うんですよ。
岡田:どういうことですか?(笑)
duenn:要か不要かで言ったら、高木ブーは不要だと思われていた時代が長かったじゃないですか。だけど高木ブーがいなくなったドリフを想像したときに、みなさん何を感じますかっていうことなんですよね。それがおそらく社会におけるアンダーグラウンドな音楽の意味だと思うんです。
岡田:めちゃくちゃポップでいい喩えですね(笑)。
おばあちゃんの会話や壊れた室外機に音楽的快楽を見出す二人にとっての、「アンビエントミュージック」
―新作のタイトルは『都市計画』ですが、お二人は都市のなかでどんな環境音を聴くのが好きですか?
duenn:僕はおばあちゃんの会話を耳にすると気分がアガりますね。同じことを何回も繰り返していて、もう最高なんですよ。
岡田:ミュージックコンクレート(人の声、動物の声、鉄道の音、自然界の音、都市の環境音のような日常聞こえる音を録音編集、エフェクト処理して制作された音楽)に似ているのかもしれないですね。
duenn:たしかにコンクレートっぽいかも(笑)。あとはファクシミリの音も好きですね。
岡田:僕は室外機の音が好きかなあ。異様なノイズを出していたり、安らかでサラッとしたリズムを刻んでいるのもいいと思います。
duenn:モーター系はいいよね。予期せぬリズムを刻んでくれる。換気扇も好きだなあ。
岡田:そういう音が音楽的に聴こえる瞬間ってありますよね。キース・ロウもそういう視点でモーターを使ってたのかな。
―音楽的に聴こえる環境音がある一方で、環境音楽やアンビエントミュージックという音楽ジャンルもありますよね。お二人はそれぞれアンビエントミュージックをどのように定義しているのでしょうか?
duenn:うーん、僕はアンビエントをやろうと思って音楽を制作しているわけではないんですよね。結果的にアンビエントミュージックとカテゴライズされることはありますけど、自分の音楽はアンビエント的とも言えるし、そうじゃないとも言える。
強いて言えばそういうぼんやりとした感じが僕にとってのアンビエントなのかもしれません。僕がやっている『HARDCORE AMBIENCE』というイベントは、実はDOMMUNEの宇川直宏さんが名づけ親で、そういうふうに第三者が決めたものに乗っかるのもアンビエント的だなと感じます。
岡田:アンビエントって、ある音楽の形式というよりは、音楽のムードを示す言葉だと僕は思っています。浮遊するような質感だとかフワッとしたのものだとか、そういうムードを示すこと。聴き手にとって意識的に聴取を向けられるようなものではないけれど、それは常に誰にでも開かれた状態で、第三者が入る余地がある音楽空間でもあるというか。
この音楽は、聴く人の周囲の環境、音と混ざり合うことで完成する。実験的アティテュードの奥にあるもの
―ブライアン・イーノはかつてアンビエントミュージックを「興味深くて、かつ無視することが可能なもの」と定義しましたよね。イーノの定義はどのように思いますか?
岡田:最近、イーノの考え方に改めて興味が湧いているんですよね。BGMのように空間を覆い尽くすのではなくて、レストランでスプーンとフォークが擦れる音や、会話のなかで起きた沈黙の気まずい時間を、そっと包み込むような音楽という考え方。
ただ、イーノの音楽が生まれた背景には、やっぱりTangerine Dreamをはじめとした1970年代当時のスピリチュアルな電子音楽という流れがあって。そうしたものに対抗するための新しい手段として、生活と密接に関わっていて穏やかな構造を持つ音楽を打ち出したところが、すごく興味深いなと思っています。
ブライアン・イーノ『Ambient 1: Music for Airports』(1978年)を聴く(Apple Musicはこちら)
―今回の『都市計画』の制作過程では、ブライアン・イーノの概念について議論することはなかったのでしょうか?
岡田:特にありませんでしたね。ただ、どこの場でも空間に溶け込むみたいな感覚はduennさんとの共通の認識、ムードとしてありました。特定の場所を想定して音を作っていったわけではないですけどね。
duenn:そうだね。もちろん、聴く人がイーノと結びつけることがあるとは思いますよ。音楽というのは、聴く人が音から何かをイメージすることで初めて作品として完成すると思っているので。
岡田:それはポップスをやるときも僕は気にしていますね。作り手の意図を感受して「ああ素晴らしい音楽だ」と思うのではなくて、作品が作者の手から離れた以上、あくまでその作品は作り手から切り離されたものというか。100%の割合でそうとは言い切れませんが、そうした考え方も人間が作る作品を感受するうえで、何%かは気にします。
―環境音や自然音にはない音楽としての魅力が『都市計画』にあるとしたら、それはどのようなものだと思いますか?
duenn:『都市計画』はいろんな音と混ざることで成立する音楽かなと思うんですよね。
岡田:たしかにそうですね。今ちょうど家の近くで工事をやっているんですけど、部屋の窓を開けながらアンビエントを聴くと、工事の音がなぜか緩やかなものとして聴こえてくる。他にもいろいろな環境の響きと作用して別の音楽の形に聴こえてくることもあるんです。何かと混ざることで別の音楽になるというのは、現実の環境音とはまた異なる魅力ですよね。
―アルバムを流すことで初めて気づく環境音もあるかもしれません。単なるBGMとは異なり、聴いている人に現実の環境への通路を確保するような音楽とでも言えばいいでしょうか。
岡田:そう考えるとブライアン・イーノが定義したアンビエントミュージックの概念にも通じるところがありますよね。ただ、イーノの「Obscure Records」みたいに、こういうことをポップに伝えられたらいいなと思っているんですよ。今の時代にSpotifyでアンビエントのプレイリストを聴いていても、イーノの話は知らないという人も多いんじゃないかと思いますし。
プレイリスト「Ambient Relaxation」を聴く(Spotifyを開く) / 2020年6月時点で同プレイリストは98万人以上がフォローしている
「風変わりな音楽のちょっとポップな聴き方を提示するというか」(岡田)
―新作のタイトルにもなっている「都市計画」というコンセプトについて教えてください。
岡田:もともとは音楽を形作る最小限の要素だけでメロディアスなポップスを作ろうと考えていて、そういった音の質感のイメージからなんとなく浮かんだ言葉なんです。
ザラッとしたコンクリートではなくてツルツルで、光沢はないけれどもマットでもないような、そういう都市的なイメージを持つ質感だけでポップミュージックを作ろうと。それで「都市計画」と仮タイトルを決めて、そこからイメージするものをduennさんと二人で作っていきました。
―なぜポップスという形式で音楽を作ろうと考えたのでしょうか?
岡田:前作(『無常』)がものすごくハードコアな作品だったから、反対のことをやろうというのが最初のアイデアでした。それと実験音楽を聴く若い人は今もいると思うんですけど、ポップスも実験音楽も分け隔てなく聴くという人は僕が10代の頃よりも少なくなったんじゃないかなと感じていて。雑誌が減って入り口が少なくなったということもあるでしょうし。
そうしたなかで音楽の間口を広げるために、たとえばアンビエントアイドルで商売をしようだとか、アニメキャラが演奏してわかりやすく伝えるとか、そうしたやり方ではなく、ある程度シリアスにポップな提示をすることに今は意味があるんじゃないかなと思って。
Okada Takuro + duenn“Waterfront (UP-01)”を聴く(Apple Musicはこちら)
岡田:ブライアン・イーノの「Obscure Records」でジョン・ケージやマイケル・ナイマンが紹介されたことって、その後の音楽にとってすごく意味があったと思うんですよね。そうしたことの可能性を今の時代にできたら面白いんじゃないかと思いましたね。
duenn:どうしてもこういうタイプの音楽って、コアな人にばかり目がいってしまうと思うんですよ。わかる人だけわかればいいというスタンス。なので、ポップスの方法論を取り入れることで、マスでもコアでも対応可能な作品になればよいなと。
岡田:たとえば「30分のドローンに何を感じますか」って言われても答えるのは難しいじゃないですか。けれども、都市計画というコンセプトやポップスの形態があると、聴き手がいろいろなものと紐づけしやすくなりますよね。風変わりな音楽のちょっとポップな聴き方を提示するというか。
「工芸品のように、自分の名前をつけてもつけなくてもいいと思いながら取り組んできました」(duenn)
―前作『無常』と比べると、かなりコンパクトかつ穏やかな作品になりましたよね。
duenn:短い曲を何十曲か作ろうという方向性は岡田くんのアイデアで、僕はプロデュースされるがままに乗っかっていきましたね。
岡田:ポップスの尺よりも短い、けれども30秒のインタールードというほど短くもない、1分程度のトラックがたくさんあるアルバムって面白いなと思って。1トラックにつき1要素みたいな縛りを設けて、どこを切り取っても反復的ではないけれどある程度キャッチーなメロディーが出てくる状態を意識していました。始まりも終わりもあるにはあるけど、どの部分から再生しても楽曲としての印象はあまり変わらないというような。
Okada Takuro + duenn“Aquapolis (UP-02)”を聴く(Apple Musicはこちら) / 今作は、全編にわたってduennが初めて作ったメロディーで構成されており、それに対して岡田は「楽器の手グセとは違う音の並びなのに不思議と有機的に聴こえるような瞬間もあって。人間が初めてメロディーを作るとこういう感じになるのかと思いました(笑)」と語った。
岡田:自分の音楽を部屋で繰り返し聴くことってあんまりないんですけど、『都市計画』に関しては何回もループして聴いているんですよね。それは今回のアルバムが自分の身体的な部分から切り離された音楽だからなのかもしれない。
―「身体的な部分から切り離された音楽」とは具体的にどのようなものなのでしょうか?
岡田:以前、duennさんに「ライブ中はずっと観察をしている」って言われてハッとしたことがあったんです。僕は楽器を前提とした演奏家で、器楽性から切り離せないところでずっと音楽をやってきたので。自分から離れたところで鳴っている音楽を観察しながら、そこに乗っても乗らなくてもいいみたいな、そうした感覚を録音作品のフォーマットに落としこめたら面白いんじゃないかなと。
duenn:補足すると、音を出しているのは僕なんだけど、「別に自分じゃなくてもいい」という意識でライブやアルバム制作をずっとやってるんですよね。今回の『都市計画』もひとつの工芸品のように、自分の名前をつけてもつけなくてもいいと思いながら取り組んできましたね。
岡田拓郎が語る、音楽が聴く人にもたらすものがあるとすれば?ーー「人間を人間たらしめる思考の選択が音楽によって広がった」
―工芸品には機能性や実用性がありますよね。お二人は音楽の役割についてどのように考えていますか?
duenn:音楽を演奏したり聴いたりすることは、僕にとってはセラピー的な部分もありますし、誰かの役に立つ可能性もゼロではないとは思います。ベタですけど、落ち込んでいるときに音楽を聴いて元気になるという人もいますよね。
岡田:もちろんそういう側面もあるとは思うんですけど、音楽や芸術が何をもたらすかを考えたときに、やっぱり僕にとって一番大きかったのは実験音楽やフリーインプロビゼーションなんですよね。
今でもちょっとした瞬間に、高校生の頃に読んだマイケル・ナイマン(ミニマル・ミュージックの作曲家であり、現代音楽評論に多大な影響を与えた音楽評論家)や高柳昌行(大友良英やジム・オルークらにも影響を及ぼしたフリージャズギタリスト)の本の記憶が出てくることがあるんです。それは必ずしも音楽に関係することだけではなくて、自分の思考そのものと密接につながっていることがあって。
高柳昌行アングリー・ウェーブス『850113』(2019年)を聴く(Apple Musicはこちら)
岡田:僕は音楽があったから、それまでよりいろいろな思考のチャンネルを持てるようになったと思ってます。音楽には工芸品みたいな実用性はないかもしれませんし、社会的に期待される機能もないかもしれません。音楽にどんな力があるのかといえば、正直、何の力もないように思えなくもない。けれども今、改めて自分の人生を振り返ると、人間を人間たらしめる思考の選択が音楽によって広がったなとは思います。
duenn:どうして音楽やってるのかなとは常に考えてますね。ただ、答えは出ない。答えが出ないからやってるのかなとも思います。
直接的に社会を変えられないとしても、二人が信じる音楽という文化・芸術の持つ可能性
―コロナ禍で世間一般に向けて音楽がいかに社会に必要かを主張せざるを得ないという状況もありますが、それについてはどう感じていますか?
duenn:僕は音楽以外で昼に福祉の仕事をやっているんですけど、それと通じる部分を感じています。介護で人を救うことって難しいんですよ。でも人に寄り添うことならできるんですよね。相手の痛みや苦しみに寄り添うことならできる。
音楽で社会のシステムや人の思想を直接的に変えることは難しいと思いますけど、人に寄り添って、ときには気持ちを開かせるようなことはあるんじゃないのかなと思いますね。
Okada Takuro + duenn“Third Sector (UP-03)”を聴く(Apple Musicはこちら)
岡田:音楽のように形のないものが世の中でどう機能していくかというのは、どうやっても計り得ないところがあるので難しいですよね。正直に言えば、今の状況で音楽に何ができるのかは全くわからない。けれどもやっぱり、物事に関する思考の可能性を与えてくれるのが音楽をはじめとした芸術だとは思う。
音楽がなかったら生まれなかった思想やアイデアは、たくさんあると思うんです。逆に音楽には大衆を牽引する力があるだとか、人々を励ますことができるとか、そういうことを提示してきたポップス的熱狂は素晴らしいと思う反面、膨大な情報が溢れ記事の見出しだけで物事を判断するような時代ではそれはとても危うい面を孕んでいると思えなくもない。そうではない音楽の可能性を僕は模索してみたいとは思ったりもします。
「(細野晴臣は)時代にも音楽にも常にアンテナを張り続けてきて、それは今でも変わらないことのようで、本当に頭が上がらない」(岡田)
duenn:そういえば岡田くん、この前、細野晴臣さんのラジオ(『Daisy Holiday!』、InterFMにて放送)に出てたよね。あれどうだったの?
岡田:ニューエイジミュージックのディスクガイド本のインタビューだったんですけど、やっぱり細野さんから話を聞くのはめちゃくちゃ面白かったです。時代にも音楽にも常にアンテナを張り続けてきて、それは今でも変わらないことのようで、本当に頭が上がらないと思いました。すごく興味深い話をたくさん聞けて、思考がとても刺激されましたよ! duennさんは細野さんの音楽はよく聴くんですか?
duenn:『MERCURIC DANCE』(1985年)がすごい好き。だからやっぱりアンビエント期の細野さんがグッとくるんだよね。あと『THE ENDLESS TALKING』(1985年)も大好きだなあ。
細野晴臣『MERCURIC DANCE』を聴く(Apple Musicはこちら)細野晴臣『THE ENDLESS TALKING』を聴く(Apple Musicはこちら)
岡田:めっちゃいいアルバムですよね。インタビューもちょうどそこら辺の話で。はっぴいえんどやYMO時代の再評価はよくありますけど、細野さんのアンビエント期はこれまであんまり取り上げられてこなかったので、貴重な話をお伺いすることができました。
―昨年、細野さんも参加しているコンピ『KANKYO ONGAKU』(正式名称は『Kankyō Ongaku: Japanese Ambient, Environmental & New Age Music 1980-1990』)がリリースされるなど、昨今は1980~90年代のニューエイジ / アンビエントがリバイバルしていますよね。お二人は1980年代のアンビエントミュージックもよく聴くのでしょうか?
V.A.『Kankyō Ongaku: Japanese Ambient, Environmental & New Age Music 1980-1990』(2019年)を聴く(Apple Musicはこちら)
duenn:僕はそこまで、1980年代のアンビエントを好んで聴くというわけではないですね。
岡田:僕もある時代のニューエイジミュージックが取り立てて好きというわけではなくて、とにかく良質な音楽が好きなだけですね。ただ、いろいろと掘った結果、めちゃくちゃ良質だと思ったのはやっぱり吉村弘と芦川聡だった。
吉村弘『Music For Nine Post Cards』(1982年)を聴く(Apple Musicはこちら)
duenn:その二人は別格だよね。ロックで言ったらThe Beatlesみたいなもので、すべてがそこに集約されているというか。あと僕は1980年代に子ども時代を過ごしたので、その頃の音楽を聴くとどうしてもノスタルジックな気分にもなってしまいますね。
岡田:1980年代に特有のゲートリバーブやFMシンセの音って、特定の時代を表してしまっている一方、それは僕たちの思い込みなだけの部分もあって。もっと素直に聴けば、いくらでも可能性が見出せるんじゃないかと思う。
ただ、装飾的なテクスチャーがあると、どうしても特定の時代を反映させてしまうところはあるんですよね。そういうテクスチャー的な部分をすべて排除した音楽を作ることが『都市計画』の出発点でもありました。
duenn:そうだね。いかにミニマルなものを目指していくかっていうことはありましたね。
岡田:今リバイバルしているニューエイジものに比べると、『都市計画』は極めて音数が少なくてミニマルな音楽なんじゃないでしょうか。
Okada Takuro + duenn“Hana To Midori To Hikari (UP-04)”を聴く(Apple Musicはこちら)
ポストパンデミック時代に、音楽とどのように付き合っていけばよいか?
―物理的な音としては同じでも捉え方によって聴こえ方が変わるということは確かにあると思います。ちなみにコロナ禍で音楽の聴き方が変化したりしましたか?
duenn:実は僕、もともと音楽を聴くことがあまりないんですよ。NHK-FMしか聴かないんで。ただ、コロナが来てから音楽を作ることは増えましたね。岡田くんはどう?
岡田:僕ははじめの数週間は気持ちが滅入ってポップスもあんまり聴く気になれませんでした。でも今はなんだかんだ聴いてます。今日もチェット・ベイカーとヴィンセント・ギャロとヤコブ・ブロを聴きましたし。
―ポストパンデミック時代に、音楽とどのように付き合っていけばよいと思いますか?
duenn:個人的には音に関係することであればなんでも大歓迎なので、Bandcampでもソノシートでもライブでも、見える形が違うだけで変わりないと思っています。なのでどんな状況になっても、音楽家は適応できるんじゃないのかなと思いますね。
岡田:そうですね。ただ商業ベースの音楽になると、大きな収入源となっていたライブができない以上、これからの見通しが立ちませんよね。配信というフォーマットも今はまだ成り立つ部分もあるかもしれないけど、生のライブを経験している人間は絶対にいつかこのmp4というフォーマットに飽きてしまうと思うし。異なるフォーマットを作るか、ライブの新しい鑑賞の方法を考えなければいけないんじゃないかなと。なので、音楽のあり方を変えるというか、ライブとは別の道を作っていかないとならないと思います。
Okada Takuro + duenn『都市計画(Urban Planning)』を聴く(Apple Musicはこちら)
- リリース情報
-

- Okada Takuro + duenn
『都市計画(Urban Planning)』 -
2020年5月20日(水)配信
1. Waterfront (UP-01)
2. Aquapolis (UP-02)
3. Third Sector (UP-03)
4. Hana To Midori To Hikari (UP-04)
5. Nijuuisseiki No Mori (UP-05)
6. Green Park (UP-06)
7. Social Welfare (UP-07)
8. Public Space (UP-08)
9. New Urban Center (UP-09)
10. Subcenter (UP-10)
11. Landscape (UP-11)
12. Zone (UP-12)
13. 116 (UP-13)
14. Public Open Space (UP-14)
15. Cosmodome (UP-15)
16. Infrastructure (UP-16)
- 岡田拓郎
『Morning Sun』(CD) -
2020年6月10日(水)
価格:2,400円(税込)
ODCP-0231. Morning Sun
2. Nights
3. Birds
4. Lost
5. Shades
6. No Way
7. Stay
8. New Morning
- Okada Takuro + duenn
- プロフィール
-
- 岡田拓郎 (おかだ たくろう)
-
1991年生まれ。東京都福生市育ち。ソングライター / ギタリスト / プロデューサー。2012年にバンド「森は生きている」を結成。P-VINE RECORDSより『森は生きている』、『グッド・ナイト』をリリース。2015年に解散。2017年10月、ソロ名義「Okada Takuro」としてデビューアルバム『ノスタルジア』をHostess Entertainmentからリリース。2018年には、1983年リリースされたスティーヴ・ハイエットの『渚にて』に収録されている“By The Pool”のカバー曲を含む4曲入り『The Beach EP』をリリース。2020年6月、約3年ぶりとなる待望の2ndアルバム『New Morning』をリリース。
- duenn (だえん)
-
福岡在住。エレクトロニクス / コンポーザー。必要最小限の機材でミニマル的な作品を制作。国内外のレーベルより多数の作品をリリース。ソロワークの他、Merzbow、Nyantoraと共にエクスペリメンタルユニット「3RENSA」、写真家吉田志穂とのアートユニット「交信」としても活動中。Nyantoraとアンビエントイベント「Haradcore Ambience」共催。
- フィードバック 0
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-