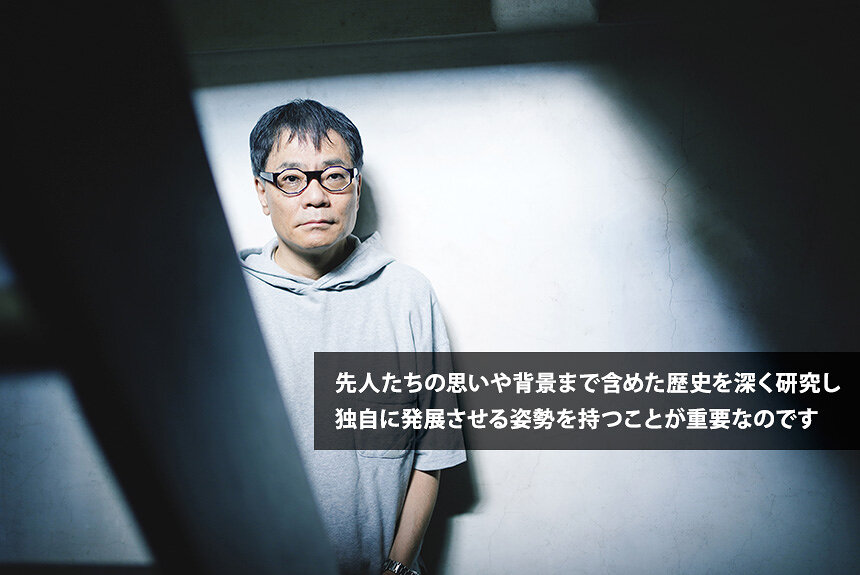俳優、小説家、タレント、ミュージシャンと多彩な顔を持つ、いとうせいこう。1980年代にはラッパーとして活動し、ヒップホップ黎明期において日本語ラップの文化を根づかせていった先駆者でもある。
1989年のアルバムリリースを最後に一度ヒップホップから離れた後は、歌舞伎や能といった古典芸能に傾倒。そこで学んだ新たな表現方法を携え、再び音楽シーンへと舞い戻る。「ヒップホップ」と「古典芸能」。まるで畑違いに思える両者には大きな共通点があり、それこそがいとうの表現の源になっているのだという。
空間を豊かにするLIXILの壁材商品「エコカラット」のプロジェクトLIXIL「PEOPLE & WALLS MAGAZINE」とCINRA.NETのコラボレーションにより、空間と人との関係にフォーカスし、インタビューを行っていくこの連載。第5回目となる今回は、いとうがのめり込んだヒップホップや古典芸能の魅力と共通点。さらに、それらを深く学ぶことでたどり着いた、全く新しい音楽表現についてお話を伺った。

俳優、小説家、ラッパー、タレントとさまざまな顔を持つクリエーター。雑誌『ホットドッグ・プレス』の編集者を経て、1980年代にはラッパーとして藤原ヒロシらとともに最初期の日本語ヒップホップのシーンを牽引する。その後は小説『ノーライフキング』で小説家としてデビュー。執筆活動の一方で宮沢章夫やシティボーイズらと数多くの舞台・ライブをこなすなど、マルチな活躍を見せている。
1980年代に惹かれたヒップホップ。既存のレコードを使った「反音楽」性
―いとうさんは1980年代にラッパーとして活動し、日本語ヒップホップのシーンを牽引したオリジネーターの1人でもあります。まずはそのルーツ、ヒップホップとの出会いから教えていただけますか?
いとう:出会いは大学生の頃ですね。FEN(現AFN)という在日米軍向けのラジオで流れてきたヒップホップを聴いたのが最初でした。これまで聴いたこともない、でも、どこか懐かしい「祭囃子」のような跳ねたビートに言葉を乗せているのが面白くて。そこからヒップホップというものの構造を勉強するようになり、のめりこんでいきました。
―ヒップホップのどんなところに、特に惹かれましたか?
いとう:既存のレコードからビートをサンプリングするところ。つまり、「人の音楽を使っていい」「演奏しなくていい」ってことですね。当時はバンドブームのはしりで、みんなが演奏をうまくなろうとしていた時代だったから、「演奏しない」という宣言が余計にかっこよく思えました。これは「反音楽」だなと。とても先鋭的だと感じたし、自分でもラッパーをやってみたくなったんです。
いとうせいこう & Tinnie Punx『建設的』(1986年)を聴く(Apple Musicはこちら)
―いとうさんはその後、藤原ヒロシさん、高木完さんたちとともに黎明期のヒップホップシーンを盛り上げていくことになります。
いとう:当時はそれをやろうとしていたのが本当に数人しかいなかったから、自分たちでアイデアを出し合い、触発しあって新しいものを作っていく面白さがありました。例えばライブのDJテーブル1つとっても、大道具さんに作ってもらった木製のやつは細かく振動しちゃって胴鳴りがやまなかったり。台を揺らさないために重りを置いたり、レコードの針が飛ばないよう50円玉を乗せて針圧を強くしたり。そういう細かいことも含めてチャレンジしながら解決していきましたね。
―試行錯誤しながら新しい「文化」を作っていく面白さがあったと。
いとう:はい。「こんなことできたらいいな」っていうビジョンが先にあって、実際にやってみたらいろんな問題が起きる。それを解決するソリューションを仲間全員で考えるのが楽しいんです。当時は日本だけでなく世界的にもヒップホップはまだ「よくわからないもの」だったから、ニューヨークやロサンゼルスでも同じことが起きていたと思いますよ。

―その後、世界中の音楽シーンでヒップホップの存在感が増していきますが、いとうさん自身は1989年のアルバム発表を最後にいったん音楽から距離を置いています。
いとう:理由はいくつかありますが、ひとつはメンバーの「音」が変わっていく中で、僕の「言葉」が追いつかなくなっていったこと。当時、一緒にライブをしていた彼らの音がどんどん進化していき、「僕らは僕らで好きな音を出すから、いとうくんは好きにラップしていいよ」と言われたんですけど、当時はフリースタイルなんてなかったし、そもそも僕はその場で言葉を発するよりも、コンセプチュアルに書いた歌詞を表現したいタイプだった。そこで、「僕がここでやれることはなくなった。あとはみんなに任せよう」と思ったんです。
インプロビゼーションで行う相手とのセッションと気付いて、のめり込んだ古典芸能の世界
―ヒップホップと一旦、距離を置いたあと、いとうさんは歌舞伎や能、人形浄瑠璃といった古典芸能の世界へのめり込んでいきます。きっかけはなんだったのでしょうか?
いとう:もともと学生時代から歌舞伎には縁がありました。早稲田大学の劇団が劇場を持っていたんですけど、そこで歌舞伎研究の大家である郡司正勝さんが「アングラ劇団をやる」と言い出して、劇団に出入りしていた僕も手伝うことになった。のちに俳優になる篠井英介さんや加納幸和さんらと一緒に黒子をしながら、歌舞伎が作られていく過程を間近で見ることができたんです。
―それは貴重な体験ですね。当時、特に印象深かったことはなんですか?
いとう:稽古中に役者さん同士が芝居を作っていく様子が面白かったですね。立ち廻りをする役者さん同士が「私はこう斬りかかります」「じゃあ、私はこう抜けます」といった具合に、アレコレ言い合いながら動きを組み立てていくんです。それまでは古典芸能って、最初から最後まで決まった型通りに演じるものだと思っていたんですけど、型はあくまでモジュールであって、それをフリーに組み合わせて作っていく可変的なものなんだとわかった。なんだか、ジャズみたいですよね。途端に歌舞伎や古典芸能への興味が湧いて、劇場へ通うようになりました。

―先人たちが編み出した型を組み合わせるという点は、ヒップホップにおけるサンプリングに通じるものがありますね。
いとう:そう思います。そこに気づいたのも、音楽を離れたあとで古典芸能に傾倒していった理由の1つですね。歌舞伎だけじゃなく、能や人形浄瑠璃などにも同じことが言えますから。今でも能の稽古を毎週しているんですけど、面白いですよ。例えば、違う流派の人同士が集まって公演するときでも、簡単な申し合わせをしただけでポンと舞台に上がってしまう。それでも、しっかり面白い芝居として成立する。違う流派が全然違う芸をしているようでいて1つにまとまるのは、各々が型を守りながらも相手の出方に合わせてインプロビゼーション(即興)で動いているからですよね。
―本当にジャズみたいですね。
いとう:だから、同じ演目でも配役が変わればまるで別の面白さがあります。前回は泣けなかった場面で泣けたりする。それは役者によってアプローチや奏でるセッションが異なるからではないでしょうか。
―ある意味、舞台上で演者同士が張り合うような感じでしょうか?
いとう:まさにそう。人形浄瑠璃なんか見てると、それが顕著に感じられますよ。人形浄瑠璃は太夫・三味線・人形が一体になって1つの舞台を作りますが、それぞれは「合わせ」にいっちゃダメなんです。太夫はあくまで自分のテンポで語るし、三味線はそれに合わせず「自分のほうがすごいでしょ!」という感じで弾く。人形もそう。強いほうが勝つ、という戦いなんですよ。彼らは江戸時代からずっと、そんなことをやってきたわけです。それに比べると、今の音楽の予定調和な演奏って、ミュージシャンとしてどうなの? と思ってしまうところはありますね。

ヒップホップ、古典芸能を経て辿り着いた、言葉と音の理想的なセッション
―そうした古典芸能の探究を経て、いとうさんは再び本格的な音楽活動を再開させます。特に2010年代からは「いとうせいこうis the poet」としてダブポエトリーという新しい音楽ジャンルに挑まれていますが、これはどういったものでしょうか?
いとう:思いついて、そこに行き着いたんですね。DJが流す音楽を聴きながら、さまざまな言葉を選んで読んでいく。詩や文学の一節、ときには過激な言葉や政治的なステートメントなどを、最高のダンスミュージックに乗せていくんです。DJは勝手にどんどん音楽を変えていくし、僕もそれを受けて好き勝手に読みたい言葉を選ぶ。そして、その言葉にまたエコーやディレイを勝手にかけてきたりする。DJと僕、どっちがねじ伏せるかの戦いをするわけです。
―先ほどおっしゃっていた人形浄瑠璃の「強いほうが勝つ」の精神ですね。
いとう:そうです。このやり方だったら、コンセプチュアルに練り上げられた言葉と音楽がまぐわえる。僕が音楽でやりたかったのはこういうことだったんだなと、すごく充実感がありましたね。

―かつてヒップホップを離れたときに諦めたことが、ダブポエトリーなら実現できると。
いとう:はい。特にそれを感じたのは、初めて生バンドでダブポエトリーをやったときです。一応リハはするけど、どんな演奏にするかは決めず、僕が用意してきた詩もメンバーに共有せずに本番を迎えました。そしたら、僕が読む言葉によって音楽が変わっていって、詩がクライマックスを迎えるタイミングで全員がドーンと「サビ」の音を出したんです。
―それはすごい。いとうさんがどんな詩を読むか知らないミュージシャンたちが、一斉に「一番の盛り上がりどころ」を察知したわけですね。
いとう:終演後、みんなに「どうしてあのタイミングでサビにいけたの?」と聞いたら、「いとうくんの詩を聴いていたら、自然とそうなった」って言うんです。言葉の意味を聞いていて、文脈上ここが一番盛り上がるところだと全員が思ったからピッタリと演奏が合った。これこそ音楽としても言葉としても、最高の状態ですよね。
―ただ、そのやり方だと毎回ビシッと決まるわけではないですよね? 演奏と言葉がうまく噛み合わず、頓珍漢になってしまうことはないですか?
いとう:セッションに正解はないし、逆に「間違い」もないと思っています。もちろん全員の演奏と言葉がビシッ! とハマれば気持ちいいけど、誰か1人が飛び出して全く違うリズムになっちゃうときもあります。でも、そうなったらまた全員で食らいついていく。全員が頭をフル回転させ、どうにかねじ伏せて最後まで持っていく。「おいおい、どこでサビに行くんだよ」って全員が冷や汗をかきながらも、演奏していくうちに誰かからアイデアのようなものが出て、不思議と折り合いがつくんですよね。そういうのもダブポエトリーの醍醐味だと思います。
―さまざまな経験を経て、本当にやりたいことにたどり着いた。そんな充実感が伺えます。
いとう:まさに(笑)。いろんなことに悩んできて、ようやくこの形になれた。毎回のライブやレコーディングが新鮮ですし、楽しくてしょうがないですね。

―ダブポエトリーにも人形浄瑠璃のアイデアが入っていますし、いとうさんのお話を伺っていると、全てに共通するのは「過去の音楽や文学など既存のものを用いて、新しいなにかを生み出す」という点かと思います。そして、それは音楽に限らず、全ての物事に生かせる考え方ではないかと。
いとう:そうですね。世の中がどんなに変わっても、「過去に学ぶ」という視点は持ち続けるべきだと思います。先人たちが何百年も試してきたことに、優れた知見が詰まっているのは当然ですから。ただ、それを全て鵜呑みにすればいいというわけでもない。「なに」の「どんな点」がよかったのかを見極める目が必要です。
―それこそ、サンプリングのスキルが問われますよね。
いとう:はい。ヒップホップは過去の名曲の面白い部分だけを引っ張り出してきて、それらをつないで新しいトラックを作るわけですからね。ただし、単に上澄みだけをすくってもいいものはできない。古典芸能を学んできたからこそ感じるのですが、先人たちの思いや背景まで含めた歴史を深く研究し、独自に発展させる姿勢を持つことが重要なのだと思います。
LIXIL「PEOPLE & WALLS MAGAZINE」では、いとうせいこうさんのインタビュー後半を掲載。「当時新しい文化だったラップをどう民謡っぽく聴こえないようにするか」「古来の日本の住まいをヒントにどう壁を意識するか」など、温故知新という切り口からいとうさんらしい壁の新しいアイデアを語っていただきました。
- プロジェクト情報
-
- LIXIL「PEOPLE & WALLS MAGAZINE」
-
壁は間取りを作るためのものだけではなく、空間を作り、空気感を彩る大切な存在。その中でインテリアや照明が溶け込み、人へのインスピレーションを与えてくれる。
LIXIL「PEOPLE & WALLS」は、LIXILとCINRA.NETがコラボし、7名のアーティストにインタビューを行う連載企画。その人の価値観を反映する空間とクリエイティビティについてお話を伺います。
- プロフィール
-
- いとうせいこう
-
俳優、小説家、ラッパー、タレントとさまざまな顔を持つクリエーター。雑誌『ホットドッグ・プレス』の編集者を経て、1980年代にはラッパーとして藤原ヒロシらとともに最初期の日本語ヒップホップのシーンを牽引する。その後は小説『ノーライフキング』で小説家としてデビュー。独特の文体で注目され、ルポタージュやエッセイなど多くの著書を発表。執筆活動の一方で宮沢章夫やシティボーイズらと数多くの舞台・ライブをこなすなど、マルチな活躍を見せている。近年では音楽活動も再開しており、□□□やレキシ、いとうせいこうis the poetなどにも参加している。
- フィードバック 11
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-