大阪のクリエイティブセンター大阪で、言葉に溢れた現代における「沈黙」をテーマとした企画展『沈黙のカテゴリー』が3月28日まで開催されている。
本展の大きな特徴は、特設サイトや広報物のデザイン、あるいは入場券として配布される冊子「ブループリント」に掲載された論考や詩、解説まで、通常は展覧会の「周縁」に位置付けられるあらゆる要素を、会場の展示作品と同じように扱っている点だ。背景には、昨今の美術業界における組織運営やハラスメントの問題に対する、布施琳太郎の危機意識がある。
そこで今回は、布施とともに、大妻女子大学の田中東子を訪問。メディア文化論やフェミニズムを専門とし、インターネットと女性たちの文化実践との関係にも詳しい田中に、布施が本展を機にめぐらせたさまざまな疑問や思考をぶつけた。二人の対話は、アートや文化にかぎらず、組織運営に関わるすべての人たちにいくつもの視座を与えてくれる。
SNSにおいて進む「言葉の単純化」への危惧や、「個」を確立することの難しさ
布施:いま、大阪で『沈黙のカテゴリー』という企画展を開催しています。この展覧会の準備期間に美術業界でさまざまなハラスメント問題が露わになったことを受け、作品の枠組みや組織運営に関わる実験を行うことになりました。それと並行してこの一年ほど、フェミニズムに関して少しずつですが勉強をしました。今日は同展についてというより、その準備のなかで考えたいろいろな疑問を、著書を通して知った田中さんにぶつけ、学びたいと思っています。
最初に、とても基本的なことなのですが、「男女」と「ジェンダー」という言葉にはどのような違いがあるのでしょうか? たとえば、『あいちトリエンナーレ2019』では、出品作家の「ジェンダー平等」の取り組みが話題になりました。ここでは「ジェンダー」という言葉が使われていましたが、実際のデータを見ると「男女」のバランスを取る試みに思えます。この試みの重要性はもちろん理解しているのですが、あらためて、両者の違いについて確認したいと思いました。
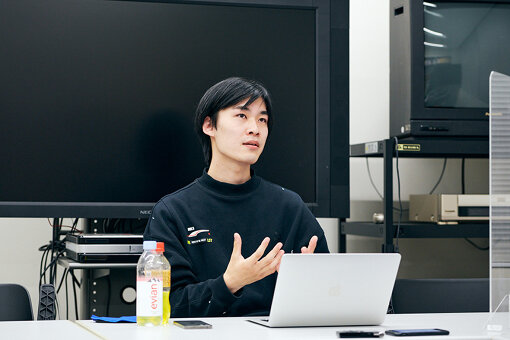
アーティスト。1994年生まれ。2017年東京藝術大学美術学部絵画科(油画専攻)卒業。現在は同大学大学院映像研究科後期博士課程(映像メディア学)に在籍。iPhoneの発売以降の都市において可能な「新しい孤独」を、情報技術や文学、そして洞窟壁画をはじめとした先史美術についての思索に基づいた作品制作、展覧会企画、テキストの執筆などを通じて模索、発表している。主な展覧会企画に『iphone mural(iPhoneの洞窟壁画)』(BLOCK HOUSE、2016)、『The Walking Eye』(横浜赤レンガ倉庫、2019)、『余白/Marginalia』(SNOW Contemporary、2020)、『隔離式濃厚接触室』(ウェブページ、2020)など。『美術手帖』や『現代詩手帖』、各種ウェブメディアに寄稿多数。
田中:「男女」というと、性別は二つに限られてしまいますが、「ジェンダー」というのはもともとそうした二種類の性別しかないという認識を壊し、批判的に考えるために導入された言葉です。なので、本来は「ジェンダー」というときは、「女」と「男」だけに限られないそのほかさまざまな性を含みます。さらに、「ジェンダー」は、社会的・文化的に構築された性や性的関係のことを示す言葉でもあります。ただ、言葉は使われるうちに単純化され、本来の意味を失ってしまうことがあるんですよね。
たとえば、いまジェンダーの問題というと、女性や性的マイノリティの問題であるかのように受け取られる傾向がありますが、実際は男性も含めてすべての性に関わる問題です。この言葉を使うときは、きちんと個別の文脈を深掘りし、性の二元論に陥らないようにすることが重要になると思います。

1972年横浜市生まれ。博士(政治学)。大妻女子大学文学部教授。専門分野はメディア文化論、ジェンダー研究、カルチュラル・スタディーズ。第三波フェミニズムやポピュラー・フェミニズムの観点から、メディア文化における女性たちの実践について調査と研究を進めている。著書に『メディア文化とジェンダーの政治学-第三波フェミニズムの視点から』(世界思想社、2012年)、編著や共著に『出来事から学ぶカルチュラル・スタディーズ』(共編著、ナカニシヤ出版、2017年)、『私たちの「戦う姫、働く少女」』(共著、堀之内出版、2019年)、翻訳に『ユニオンジャックに黒はない――人種と国民をめぐる文化政治』(ポール・ギルロイ著、共訳、月曜社、2017年)などがある。
布施:もちろん、これまで不当な扱いを受けてきた女性作家をピックアップする試みには価値があると思います。一方、言葉がもつコンテキストが消去されることで、また何かべつのものが抑圧されることもあるのかなと感じました。
「言葉の単純化」は、とくにSNSにおいて過剰に進むと思うんですね。しかし田中さんはご著書で、SNSについて、小さな声に力を与えてくれるメディアであるとも書かれてきました。最近の現状についてはどのようにご覧になっていますか?
田中:いわゆるSNSに限らず、コロナ禍で利用機会が増えたZoomなども含め、オンラインのメディアには良い部分もあると思っています。たとえば、フェミニズム関係の対面式イベントの場合、どうしても都心で、夜間での開催が多くなり、子育て中の女性は参加しづらくなる。でも、オンラインだと子育て中の母親や地方で孤立する学生、障がいのある方なども参加しやすくなります。
他方で、やはりメッセージの単純化や、「いいね!」の数だけを評価する傾向など、手放しでほめられない部分も多々ある。誰にでも制限なく開かれているオンライン空間では、女性を攻撃したいという目的のためだけに、そうした場を訪れる人も現れます。それに、そもそも人間には、実空間でガッと群れになることで凝縮されて生まれるパワーもある。オンライン化が進むことで、そうした力が削がれてしまうかもしれないという危惧は感じますね。

布施:少し抽象的になってしまうのですが、SNSは本質的に「私たち」を作るのにはすごく向いてると思うんです。共同体やパーティー、連帯感を作るのには長けてる。同時に、そこでは「私」を確立することがすごく難しい印象があって。「私」と「私たち」がうまく両立できないというのは、SNSだけではなく、フェミニズムにも関わる問題ですか?
田中:そうですね。おそらくフェミニズムにも一枚岩で連帯して戦うことがもっとも有効であると考えられた時代がありました。でも現在、女性を抑圧する条件や機構は、日常生活や労働の場で細分化していますし、女性の生き方やキャリアも分岐しています。また、ジェンダーの問題は、人種やセクシュアリティ、階級や格差、世代や住んでいる地域などとクロスさせて考えなくてはならないというときに、簡単に「私たち女性は」と言えない状況になるんだと思います。こうした一括りにすることの困難さから「第三波フェミニズム」のムーブメントが生まれました。
その担い手たちは、それこそ「個」として状況にどう切り込むかを考えていました。このとき重要な手段となったのが、アートや音楽や小説といった表現文化です。しかし、近年起きている問題は、カルチャーがどんどん商業化されてしまっていること。あらゆる文化が経済的価値に変換され、飲み込まれてしまうようになった現在、文化による抵抗がもはや力を持ちえなくなっているのではないか、文化にはもはやカウンター的な要素はないのでは? という厳しい意見も出てきています。
アート界でも起こるハラスメント。直接の当事者ではない人間は、問題にどう関わり、語ることができるのか?
布施:昨年、国内外で男性のアート関係者に対するハラスメントの告発がありました。それぞれが係争中ですので、ここでの言及は避けたいと思います。しかしその国内外のアート関係者のなかには、さきにお話ししたインターネットのなかの「個」や、作者とは何か? を問いながら、アートシーンに出てきた人たちも含まれていました。つまり芸術実践と私生活のあいだにギャップがあったとも言えます。
田中:カルチャーの世界のハラスメントで言えば、ほかにも雑誌『DAYS JAPAN』や映画配給会社「アップリンク」で起きたハラスメントの問題もありましたね。いずれも代表の人たちは、表向きは立派な活動や発言をしていたかもしれない。ただ、その仕事と、普段の生活や振る舞いが乖離してしまっていた。これは、アカデミズムの世界でも起こりうることです。私はこういう問題について、布施さんのような世代がどう感じているのかに関心があります。

布施:僕が率直に感じるのは、こうした問題に向き合ったときの自分の言葉の無さです。自分は男性で、大学院まで行き、家庭もある程度恵まれていて、一般的に搾取される側、というよりも搾取する側であるというときに、自分が言葉を持てていない、向き合い方がまだ見つけられていないこと自体への焦燥感のようなものを感じます。
田中:その「言葉の無さ」には、ハラスメントやジェンダー問題について自分は知識が足りていないかもしれない、って意識もあるのかな?
布施:それもあるかもしれません。あるいは当事者ではないけれど、無関係でないような人間がどのように個別の問題に対して語るべきかという葛藤もあります。当然、被害者や当事者の方々の声を遮ることがダメなのはわかるのですが……。これはハラスメントにかぎらず、移民難民の問題や自然災害など、あらゆる問題に対しても思います。

田中:学問の世界でも当事者性をどう捉えるかというのは大切なテーマですよね。難しいのは、当事者が語るべきという声がある一方で、「つねに当事者ばかりが話をさせられている」という批判も当事者のなかから生じることがあります。当事者ではない人たちがなぜ自分たちの代弁をしているのかという声と、マイノリティがつねに社会に異議申し立てすることを求められているという声がある。これはすごく複雑だし、繊細に捉えないといけない問題です。
ただ、代理で語るのは行き過ぎだとしても「寄り添いながら語る」という道は、当事者ではない人にも残されていてほしいと思います。そうしないと、あらゆる問題に当事者しか関われなくなるし、マイノリティが力を得ることが遠のいてしまうかもしれない。とはいえ、当事者に寄り添いながら語るというのは、じつは文化的な表現がこれまでずっとやってきたことだし、得意なことだと思います。
布施:視点は違いますが、展覧会などである作品が「炎上」した際、作者やキュレーターが「部分だけを切り抜かないで、全体を見て話してほしい」と言うことがあります。それは匿名の群れであるはずの「鑑賞者」を「当事者」に置き換えることであり、突き詰めていくと当事者という役割を負う人しか感想を言うことが許されない状況を意味するように感じます。何かを鑑賞した後は、誰もがその断片からしか語りはじめられないのは当たり前にも感じるので、こうしたロジックは感想や批評を発する機会自体を失わせる危険もあると思っています。

田中:おそらく、「みんなが何でも言えちゃう」と「みんなが何も言えない」という両端を抱えながら生きていかざるをえないのが今という時代なのかな、と。以前は、公の場で意見を言える人は、ジェンダーや経験の差などでかなり限られていた。でも、SNSって、その状況をある日、突破してしまうわけですよね。感想や意見を言う手段が、すべての人に与えられた。いまは過渡期なので、いずれどこかで折り合いをつけていくことが求められると思います。
もちろん、あらゆる人に声が与えられたことは意味がある。今後は、誰もが発言の席につける状況はキープしつつ、いかに「イエス」か「ノー」、白か黒かしか許さない状況に対抗していくのかが重要になる。要するに、グレーゾーンを可能にするような補完的な討論の場を作ることが重要になると思います。
展覧会づくりの過程にも根づいていたアンコンシャス・バイアス。女性の参入障壁となる組織運営や意識の問題
田中:布施さんは、今回の展示で組織論について考えられているんですよね?
布施:そうですね。展覧会を作るプロセスは、作家からデザイナー、スタッフまで、一時的に集められたメンバーによって行われるわけですが、その人選に自分のなかでも無意識にバイアスがかかることがあります。たとえば、壁を白く塗るとか、壁を立てるといった作業の場合には、どうしても男性を呼びがちなんです。
でも、以前ある女性から「別にできるよ」と言われて、目が覚めるような気持ちになりました。実際、そうした作業には美大生の男性などを呼ぶことが多いように思うのですが、その過程で仲良くなり、別の発表の可能性が生まれることを考えると、そこにすでに機会の差が出ている。展示作家だけでなく、そういう部分から考えないと意味がないんだということは、今回の展示を作りながら考えました。


田中:それは重要な視点ですね。最近翻訳が出版された『ひれふせ、女たち:ミソジニーの論理』(ケイト・マン著、小川芳範訳、慶應義塾大学出版会、2019年)という本に、こういう例が出てきました。アメリカで、キャリアも業績も学歴もほぼ同じような男性と女性の資料を管理職採用の面接に回した場合、どちらが管理職に選ばれるか。すると、無意識にみんな男性を選ぶそうなんですね。アンコンシャス・バイアスによって、男性の方が能力が高いのでは、みたいな。そういうことの積み重ねによる男女間の機会の不均衡って、組織運営において大きいと思うんです。

田中:そうした女性の参入に対する障壁は、日本でもあらゆる分野にある。いまの設営の例でも、本来は性別に関係なくできる作業であるはずなのに、女性はそこになかなかたどり着けない。じゃあ、そこで女性もメンバーに入れようとなると、「女にだけ下駄を履かせるのか!」というお決まりの批判が出てくるんですよね。でも、2018年に発覚した東京医科大学などにおける不正入試問題で明らかになったことは、むしろ男性の方に下駄が履かされていたということで。
布施:そうですね。
田中:しかも、そこには男性にだけ「下駄が履かされていた」ことの忘却もある。たまに話すと、高校生でも「女子大は男性を排除していておかしい」という生徒がいる。でも、それは逆でしょう、っていう。そもそも女子大は、かつて大学に女子がなかなか入れてもらえなかった時代に設立されたものですよね。下駄を履かせてもらえない状況を埋め合わせるためのシステムなのに、その背景が都合よく忘却されてしまうんですね。
ハラスメントや、やりがい搾取を防げる組織の形とは? 学術組織と展覧会づくり、それぞれの立場での実践
布施:女性の参入は間違いなく進めていくべきで、一方、それが進んだ結果、組織の内部でハラスメントのようなことが起きると、本末転倒になってしまいますよね。組織化するなかでハラスメントが起こらないようにする工夫では、何が大切だと思いますか?

田中:風通しのいいコミュニケーションのできる空間を保証することが重要だと思います。要は、「セクハラ的な発言をされました。嫌なので止めてください」「ごめんなさい。嫌だと感じているとは知りませんでした。以後、気をつけます」という対等なコミュニケーションの回路が保証されていれば、大概の人はそこでハラスメントを止めると思うんですよね。たまに、嫌がっている女性を見て、「喜んでいるにちがいない」と感じてしまう認知の歪んだ人もいるので、話はそれほど簡単ではないのですが……。
20年くらい前に既存の権威主義的な風潮の学会は嫌だ、と感じている有志で集まって民主的な学術組織を作ろうと、『カルチュラル・タイフーン』というイベントを立ち上げました。この組織はだいぶいい感じで今日まで来ているんですけど、それは参加者全員の確固たる「民主的にやるぞ」という意識の共有があってこそなんです。
イメージとしては、『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』に出てくる「公安9課」。全員が集団にもなるし、個として切り離されてもいて、並列化しつつ、すごく高い意識とレベルで任務を遂行していく。そういうイメージで学術組織を運営しているんです。
布施:カッコいいですね。
田中:でしょ?(笑) もちろん、絶対に起こらないようにしようと思っても、残念ながら問題が生じることもあるけれど。比較的、風通し良くうまくいっている組織だと思います。

布施:この一年間は、とくにオンラインで交流する機会が多かったですよね。そこで僕は今回の展覧会にあたっては、この状況を逆手に取り、オンラインでは性別に関わらず関係者と一対一でしか喋らないことにしたんです。それは、複数人のなかに僕がいると、企画者という立場からどうしても僕の意見を一度に複数人に浸透させる力が働いてしまうから。でも、一対一の場合、対話のなかで両者のアイデアの折衷と創発が生まれ、展覧会の主語が「僕」から広がるような感覚があるんです。とはいえ、展示会場などの実空間ではどうしても複数人で集まらざるを得ない場面もあるのですが、そうした安全な密室としてのインターネットとの行き来で展覧会を作れたらと思っていました。

田中:一対一で話すというのは、たしかにオンラインだからこそできる方法かもしれないですね。私の関わる組織で言うと、ほかにも年配の男性の先生を権威にしないということは意識しているかな。たとえば、うちの団体の代表は、受付をやらされたり、机や椅子を運んだりするんですよ。会議のときも、普通は偉い人が正面に座るけど、そういう座り方はしない。中心や上下関係をつくらない。そういうことを日々浸透させていくことを意識していますね。
布施:それは、ハラスメントややりがいの搾取を防ぐという予防的な意味だけでなく、従来の組織のあり方では考えられない問題について考えるための方法でもあるんでしょうか?
田中:そうです。いろんな人が発言できる組織の方がいいアイデアが浮かぶし、ハラスメントも起こりづらいはず。若い人たちも生き生きと参加できる。
布施:田中さんが本(『メディア文化とジェンダーの政治学 第三波フェミニズムの視点から』世界思想社、2012年)のなかで、ミシェル・ド・セルトー(フランスの歴史学者。著書『日常的実践のポイエティーク』の文庫版が3月にちくま学芸文庫より刊行)の「そっとしのびこんだメタファー」という言葉を引用されながら話しているのも、それに近いことですよね。組織やある場所の直接的な転覆ではなく、そのなかに遊びを忍ばせて変えていく、という。
田中:気づいたら変質させられているというイメージですね。もちろん、間違ったことやおかしなことを正面からダメだと批判したり怒ったりすることは大事。でも、それとは違うやり方、こっそり変質させてしまうやり方もあって、たぶん文化的な領域で変化を引き起こすときには、後者の方が向いていると思います。

不可視化されやすい立場の人や、「裏方」的な仕事に光を当てること
田中:布施さんは今回、普段の展覧会づくりでは目立ちにくい立場の人の仕事も、「展示作品」と同じように扱っていますよね。そのサジェスチョンも重要だと思うんです。
組織や集団には不可視化されやすい立場の人がいて、じつは大学もそうなんです。私はよく学生に、「大学には学生と先生しかいないと思っているでしょう? でも、よく見てごらん。ほかにもいろんな人たちがいるよ」と言うんです。そのあと一週間くらい学内を放浪してもらってからあらためて聞くと、「掃除している人がいた」とか、「食堂で外国籍の人がご飯を作っていた」とか、気づいて帰ってくる。そうやって、「透明にさせられてる人がいるよね」ってサジェスチョンするだけで、見えてくる風景というのは変わってくるんですよね。

布施:そうですね。たとえば今回、肥高茉実さんという『美術手帖』などのメディアで編集者やライターをしている方にステイトメントを書いてもらいました。肥高さんと話すなかで、もともと翻訳的な要素を持つアート作品を作っているけれど、いまは編集の仕事もしていると聞いたときに、今回の展覧会が普段の仕事とはべつの能力を発動する機会になったら面白いと思ったんです。ほかにも広報画像のデザインは、展覧会で最初に目にする創作物だけど、通常は裏方的な要素として見なされている。今回のデザインを担当してくれた八木幣二郎さんは、そうした問題意識を共有しながら仕事をしてくれたように感じていますし、そうした場所にも光が当てられたらと思いました。
田中:それを、男女比を意識して提示できると、さらに面白いですよね。竹田恵子さんの分析による統計データで見ると、アートの世界では美術館の館長や著名アーティストには男性が多い一方で、それを支えるスタッフには非常に女性が多いということがわかっています。非常にジェンダーバランスの悪い業界ですよね。
水平的なコミュニケーションと、カリスマ的リーダーの両立は可能か。展覧会というフォーマットに見る可能性
田中:ひとつ布施さんに質問したいことがあります。アート界の有名アーティストは、ある種のカリスマ性や神秘性を纏うことも、仕事のひとつなのかなと思うんです。そのとき、先ほど話したようなカリスマを置かない、平等で水平的なコミュニケーションの組織のあり方と、カリスマ的なアーティストのあり方というのは、両立可能なんだろうかって。
布施:それはたぶん可能で、むしろ、可能であるからこその難しさがある気がします。たとえば僕のようなキュレーションをする立場と他のアーティスト、もしくはアーティストとそれを支えるスタッフというような関係において、ある人が考えていることを要約してべつのコンテキストにつなげたりする作業を共同でするなかで、それが相手の話か自分の話か分からなくなってくるということはよくあります。だから今回の展示で、並列的な関係を複数持つこと自体の暴力性もあるとも思いました。自分の意見や研究が、誰かのカリスマ性に知らないうちに回収されてしまう暴力の可能性があると思うんです。

田中:なるほど。一方でもっと単純に、カリスマ的アーティストを見てその組織に入ってくる心酔者というか、フォロワーもいますよね。アカデミズムの世界でも同じことがあって、やっぱり有名な男性評論家に群がる人とかもいるわけですよ。
布施:そうですね。前提として、人を魅惑する力がなくなってしまえば、それはもはや文化としての意味がないとも思うんです。その上で、アーティストやクリエイターが成長するなかで、その人自身と創作物の過剰な一致を避ける、つまり作品が魅惑するのであって、作者が魅惑するのではないという距離の取り方は可能なはずだと思います。そこには、人生自体をプロジェクトとして提案するのではなくて、作品をひとつずつ完成したものとして提示する姿勢が必要になる。それは物書きもアーティストもキュレーターも一緒だと思います。
田中:アーティストや文化事業者にはある種の外部性も大事で、みんながみんな、いまの社会規範や社会常識に従っていたら、「いまここにないもの」を見せる契機がなくなってしまう。それを提示するのが、そうした人たちの役目ではあるんだけど、思うのは、カリスマであることの発露がセクハラでええんかい、っていうことなんですよね。
布施:そうですね。
田中:ハラスメントに帰結しないカリスマ性の発揮の仕方を、もっと真剣に模索しましょうよ、っていう。そのとき、すごく基本だと思うんだけど、他人は自分ではないっていうことをちゃんと心の底から自覚することは大切だと思うんです。理想に燃えるリーダーほど、「俺たちのユートピアのためにお前はなぜ身を粉にして働けないんだ」となってしまうことも多いんだけど、他者は他者であり、自分のコピーではない。

布施:自分の活動に引きつければ、キュレーションというのはひとつの空間をどうやって秩序づけるのかという試みで、それを小さな民主主義の実験場として捉える人もいます。一方、すごくトップダウンではあるけれど、リーダーの理想を出品作家やスタッフに浸透させることで何かが実現される場合もあった。
そうしたなかで僕自身が展覧会企画のときに大事にしてきたのは、締め切りを守らなさそうな人とか、言うことを聞かなそうな人を数名呼ぶことです。そういう人がいると、べつの作家から「他の人はどんなものを出すんですか?」と聞かれたとき、「あの人は最後までわかりません」と、企画のなかに予期せぬものが入り込む余地ができる。つまり依頼を逸脱する可能性が担保されている組織が創造的だと思うんです。直接何をやってもいいということではなくて、ある枠組みは与えたうえで、関係するみんなに「はみ出す可能性」を許すため、そもそも僕の理解や依頼を逸脱する人材にあえて入ってもらう。それでも作品は完成させなくてはならないですし、そのために一緒に走ることは自分自身の変化を感じられて楽しかったりします。

田中:枠組みがある上での逸脱というのは、ポリティカル・コレクトネス(PC)を踏まえた表現にも重なりますね。「PCで表現の自由が奪われる」と言う人もいるけど、PCというのは共有された枠組みであって、他者の尊厳を踏みにじらない、他者を抑圧しないかたちで逸脱していくということは、アートや文化の世界ではいくらでも可能だと思います。
布施:もうひとつ、展覧会というフォーマットやその運営組織の面白いところは、「期限付きである」ところだと思います。ある期間だけ集まって、終われば解散する。会社組織で言えば「プロジェクトチーム」ですよね。作品は「期限なし」だけど、それを社会が扱ううえで組織が必要になる。そのとき、人間関係からその統治の仕方まで、「こういう組織はどうだろう」と、学生でもいろいろ試せる可能性がある展覧会というのは、すごくよくできたプラットフォームだと思うんです。でも、とくに東京の場合、それをいわゆるアートの内部の人だけでやっていることもあって、なかなか多様な作り方を試せていないという面があると思う。本来は、その場所をもっと組織運営の実験に使ってもいいはずで。

田中:面白いですよね。上の世代の展覧会に参加する学生からしたら、そこでいろんな組織のモデルに触れることで、社会に出てべつの展示に関わったときも、「あれ? 布施さんのときにはこうだったのにな」と、何か気づきを得るきっかけにもできますね。
布施:展覧会の作り方は一個しかないわけではないんですよね。これまでにないものの作り方や集まり方を試すチャンスとして、それを使うこともできる。もともと自分は、インターネットのことをずっと考えてきた人間です。だからこそ今回の展示は、インターネットのかつての失われた夢を、展覧会のなかで試してみたいと思いながら準備を進めていて。展覧会自体がひとつのフィジカルなインターネットで、そのなかにいくつものウェブサイトがあるみたいな……。過去に夢見られていたはずの自由と平等の両立みたいなものを刹那的に作る機会として、この場所を実験的に使ってみたいと思っていました。
田中:展示会に至るまでのプロセスも含めて作品として提示する、ということの中に、新しいものの作り方や新しい人の集まり方を試していくという試みはとても興味深いですね。人が集まると、必ず問題は生じます。もちろん、誰かが犠牲になったまま突き進むのはよくないけれど、起こった問題から、立ち止まって考える人も現れる。その意味で私は、人が群れ、集団になることにそこまで絶望してはいないんです。先にも話したように、人には、集まることで生まれる力もある。いろんなあり方を試しながら群れ続けることが大事ですね。

- イベント情報
-
- 『沈黙のカテゴリー|Silent Category』
-
2021年3月14日(日)~3月28日(日)
会場:大阪府 クリエイティブセンター大阪
時間:13:00~20:00
休館日:月、火曜
ステートメント:肥高茉実
デザイン:八木幣二郎
特設ページ:山形一生
展示:小松千倫、鈴木雄大、高見澤峻介、都築拓磨、中村葵、布施琳太郎、三枝愛、宮坂直樹、山形一生
寄稿:井岡詩子、黒嵜想、水沢なお
論考:石原吉郎
映像記録:佐藤友理
写真撮影:竹久直樹
運送:奥祐司
キュレーション:布施琳太郎
料金:500円(ブループリント付属)
- プロフィール
-
- 布施琳太郎 (ふせ りんたろう)
-
アーティスト。1994年生まれ。2017年東京藝術大学美術学部絵画科(油画専攻)卒業。現在は同大学大学院映像研究科後期博士課程(映像メディア学)に在籍。iPhoneの発売以降の都市において可能な「新しい孤独」を、情報技術や文学、そして洞窟壁画をはじめとした先史美術についての思索に基づいた作品制作、展覧会企画、テキストの執筆などを通じて模索、発表している。主な展覧会企画に『iphone mural(iPhoneの洞窟壁画)』(BLOCK HOUSE、2016)、『The Walking Eye』(横浜赤レンガ倉庫、2019)、『余白/Marginalia』(SNOW Contemporary、2020)、『隔離式濃厚接触室』(ウェブページ、2020)など。「美術手帖」や「現代詩手帖」、各種ウェブメディアに寄稿多数。
- 田中東子 (たなか とうこ)
-
1972年横浜市生まれ。博士(政治学)。大妻女子大学文学部教授。専門分野はメディア文化論、ジェンダー研究、カルチュラル・スタディーズ。第三波フェミニズムやポピュラー・フェミニズムの観点から、メディア文化における女性たちの実践について調査と研究を進めている。著書に『メディア文化とジェンダーの政治学-第三波フェミニズムの視点から』(世界思想社、2012年)、編著や共著に『出来事から学ぶカルチュラル・スタディーズ』(共編著、ナカニシヤ出版、2017年)、『私たちの「戦う姫、働く少女」』(共著、堀之内出版、2019年)、翻訳に『ユニオンジャックに黒はない――人種と国民をめぐる文化政治』(ポール・ギルロイ著、共訳、月曜社、2017年)などがある。
- フィードバック 7
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-




