バリアフリー化が進んでいる近年では、音声ガイド付きの映画、手話付きの演劇など、身体的困難を持つ人に対して、鑑賞のアクセシビリティを高める様々な取り組みが行なわれている。見えるものを音で、聞こえるものを手話で表現することは、つくり手が意図したことを正確に伝えられるかなど、様々な難しさがあることは容易に想像できるが、本質的には洋画に日本語字幕をつける翻訳と変わらないということは、忘れてしまいがちなポイントだろう。
もっと言ってしまえば、たとえ身体的困難がなかったとしても、鑑賞者によって解釈が異なるのは当然のこと。誰かと一緒に映画を観に行ったが、感想が大きく違った。こんな経験をしたことがある人も多いのではないだろうか。
2月より番組レポートを掲載しているポッドキャスト番組『MOTION GALLERY CROSSING』では、4月7日より4週にわたって「見える音、聞こえる風景」と題した特集を配信。文化芸術へのアクセシビリティ向上に取り組むゲストを迎えて、どのような試みが行なわれているのか活発な議論が繰り広げられた。

編集者の武田俊と演劇モデルの長井短が「これからの文化と社会のはなし」をゲストとともに掘り下げていく、日本最大級のクラウドファンディングサイト「MOTION GALLERY」によるポッドキャスト番組。毎月テーマに沿ったゲストトークが行なわれるほか、「MOTION GALLERY」で進行中の注目プロジェクトも紹介。東京・九段下の登録有形文化財「九段ハウス」で収録され、毎週水曜に最新回が公開されている。
作り手として「伝わってほしいけど、何を受け取ってくれるかは、受け取り手の自由」(長井)
今回のテーマとなった「見える音、聞こえる風景」を語るにあたりゲストに迎えられたのは、美術雑誌『美術手帖』のウェブ版編集長を務める橋爪勇介と、『THEATRE for ALL LAB』編集長でボイスパフォーマーの篠田栞。『MOTION GALLERY CROSS-ING』では、はじめにテーマありきでゲストが決められているが、特集テーマとゲストが決まった経緯について、番組パーソナリティの武田俊が説明する。
武田:自分たちがポッドキャスト番組をやっているなかで、音声および音声メディアを切り口とした特集は、いつかやりたいと思っていたことでした。ただ、企画するにあたって、音声メディアを掘り下げる回とするのか、あるいは音声を軸に違う視点で切り取る回にするのかを考えたときに、アートやインクルーシブデザインなど、クリエイティブ領域からいまの社会課題を見つめている方にお話を伺いたいなと思い、橋爪さんと篠田さんをお招きしました。
ゲストの2人については、少し補足が必要だろう。橋爪はウェブ版『美術手帖』の編集長を務めると同時に、ポッドキャスト番組『instocial by 美術手帖』でもMCを担当しており、音声を使って美術について発信。篠田が編集長を務める『THEATRE for ALL LAB』は、バリアフリー対応や多言語翻訳でアクセシビリティに特化したオンライン劇場『THEATRE for ALL』のリサーチ機関である。詳しい活動内容は配信内で語られているが、まさに「見える音、聞こえる風景」を実践している2人なのだ。
収録は緊急事態宣言の解除前だったこともありリモートで行なわれたが、利用しやすさを意味するアクセシビリティについて、そして誰も排除しないことを意味するインクルーシブについて、話を深めていけばいくほど、アートとは、鑑賞とは、創作とは、といった本質的なことを考えさせられる時間となった。演劇モデルとして自身も舞台に立つ長井短は、収録を終えてこれまで感じていたモヤモヤが解消されたようだ。
長井:たとえば駅で白い杖を持って歩いている人がいたら、助けてあげるんだよって教えられてきたじゃないですか。でも、大人になるにつれて、助けなきゃってことでもないよなというか。困っている人がいたら、相手が誰であれ「大丈夫ですか?」となるから、特別なことではないんだよなと思いながらも、聞こえない人にわかるようにしてあげようとか、見えない人にも伝わるようにしてあげようみたいな意識が、どうしても消えないなぁと気になっていたんです。
でも、今日お話を聞いて、やっぱり一緒に遊ぶなら、みんなができる遊びのほうが楽しいよね、そしてそれぞれが自分のやり方で遊んだほうが楽しいじゃんっていうシンプルなことに立ち返れたのが、ちょっと救いになったんです。やっぱり演劇をつくるときでも、伝わってほしいけど、何を受け取ってもらうかは、受け取り手の自由だから、そこのせめぎあいが特に演出や作家の人はあると思うんですけど、コントロールしようとすることが、だんだんそれって違うよねみたいになってきて。もっとそうなっていくといいなって思いました。

1993年生まれ、東京都出身。「演劇モデル」と称し、雑誌、舞台、バラエティ番組、テレビドラマ、映画など幅広く活躍する。読者と同じ目線で感情を丁寧に綴りながらもパンチが効いた文章も人気があり、様々な媒体に寄稿。近年の主な出演作品として『賭ケグルイ双』『書けないッ!?~脚本家 吉丸圭佑の筋書きのない生活~』『真夏の少年~19452020』『家売る女の逆襲』、舞台KERA×CROSS第二弾『グッドバイ』、今泉力哉と玉田企画『街の下で』、映画『あの日々の話』『耳を腐らせるほどの愛』などがある。執筆業では恋愛メディアAMにて『内緒にしといて』、yom yomにて『友達なんて100人もいらない』、幻冬舎プラスにて『キリ番踏んだら私のターン』を連載。2020年に初の著書『内緒にしといて』(晶文社)上梓。
みんなが同じ体験をできるようにっていう社会の作られ方は「けっこうヤバい」(武田)
一方の武田も、これまで持っていた危機感に対して、さらに確信を深めたようだ。
武田:まず前提として、人々の身体的特徴や認知特性について、先天的なもの、後天的なものも含め、みんなが同じ権利を持っている状態を社会が目指すことは、すごく尊いことだと思っているんです。しかしながら、みんなそれぞれ別の存在であるし、世界の甘受のしかたも違うっていうことを見過ごしてしまった状態で、みんなが同じ体験をできるようにっていう社会の作られ方がされていることは、けっこうヤバいことだとぼくは思っているんです。
じゃあ、どういう形が望ましいかという話ですけど、それはまだまっさらな状態。ならば「できるだけ選択肢を増やすことが、じつは社会の豊かさにつながるんじゃないか」っていう篠田さんのトライは、本当にその通りだなと思いました。
さらに武田は、インクルーシブやアクセシビリティについて考えることで、美術とは何かという原点に立ち返れたと続ける。
武田:多くの人がそれぞれの認知に合った見方で鑑賞するには、どうしたらいいのかっていうアプローチは、ひるがえって「鑑賞するとは何か」という原点の問いに戻ってくるというか。美術でも映画でも音楽でも、いままで自分がスタンダードだと思っていた楽しみ方って、「なんでそれがスタンダードな楽しみ方になっているんだっけ?」と立ち返って考えられる、みたいな。自分が選ばなかった楽しみ方を考慮せずに、ただ無意識に「一般的な楽しみ方」として触れていたのではないか。
そこが今回、自分が得た視点としては重要で。みんなで一緒に、あるいは、みんなでそれぞれ楽しめるようにするには、どうすればいいのかを考えることで、そもそも美術とは何か、鑑賞するとは何か、本質の議論に戻ってくる。そういうところに豊かな議論があったと思うし、ハッとさせられたポイントでした。

1986年、名古屋市生まれ。編集者、メディアリサーチャー。株式会社まちづクリエイティブ・チーフエディター。BONUS TRACK・チーフエディター。法政大学文学部兼任講師。大学在学中にインディペンデントマガジン『界遊』を創刊。編集者・ライターとして活動を始める。2011年、代表としてメディアプロダクション・KAI-YOU,LLC.を設立。『KAI-YOU.net』の立ち上げ・運営のほか、カルチャーや広告の領域を中心にプロジェクトを手がける。2014年、同社退社以降『TOweb』『ROOMIE』『lute』などカルチャー・ライフスタイル領域のWebマガジンにて編集長を歴任。2019年より、JFN『ON THE PLANET』月曜パーソナリティを担当。メディア研究とその実践を主とし、様々な企業のメディアを活用したプロジェクトにも関わる。
ここからは約2時間に及んだ収録のなかから、4月7日に公開された1週目の配信分の一部を書き起こし、編集・補足を加えてお届けする。
『美術手帖』では絵画・彫刻だけでなく「2.5次元のミュージカルとか、ボーイズラブとかも特集している」(橋爪)
長井:私、いつもの初歩的な質問から始めていいですか? まず橋爪さんにお聞きしたいんですけど、私は中学のときから美術の成績が異常に悪いので、けっこう美術に対してコンプレックスがあって(笑)。
橋爪:あー、はいはい。わかりますよ、そういうの。
長井:だから『美術手帖』は、もちろん知ってはいるんですけど、実際ちゃんと読んだりしたことはなくて。どういう媒体というか。
橋爪:どういう媒体!?
長井:何が書いてあるんですか?
橋爪:すごい。こんなざっくり質問されたの初めてかもしれない(笑)。じゃあ、改めてご説明させていただきます。
武田:お願いします!
橋爪:我々『美術手帖』は、もともと雑誌が戦後すぐに創刊して、もう70年以上の歴史がある媒体なんです。その創刊当時から「同時代の美術を紹介する」っていうのが大きなコンセプトで、いわゆる現代美術の世界で、その動向を紹介し続けてきました。つまり、同時代の美術動向を紹介する、というのが『美術手帖』です。
雑誌の歴史は長いですが、それだけではリアルタイムな情報を届けるのが難しくなってきている。そこでウェブ版も必要だろうと立ち上がったのが、現在のウェブの『美術手帖』ですね。2017年に始まって、もう丸4年経ちました。

1983年生まれ。三重県出身。立命館大学国際関係学部を卒業後、美術年鑑社『新美術新聞』の記者を経て、2016年に株式会社美術出版社に入社。2017年にウェブ版『美術手帖』を立ち上げたのち、2019年より編集長を務める。2020年12月にスタートしたポッドキャスト番組『instocial by 美術手帖』ではMCも担当。
長井:美術って聞くと、絵なのかなと思ったりするんですけど、絵に限らず?
橋爪:絵に限らずです。創刊した当初は、美術のジャンルもいまほど多様化していなくて、当然ながら絵画・彫刻が中心なわけですよね。でも、そのあとには絵画や彫刻という分野にとらわれない表現も出てくる。
たとえばインスタレーションや、演劇、メディアアートのようなものも、我々は美術のジャンルとして捉えているので、かなり多様な表現を紹介しています。そこには「これって美術なの?」というものもあって。雑誌の『美術手帖』では2.5次元のミュージカルとか、ボーイズラブとかも特集しているんですよね。
長井:そうなんですか!
橋爪:あとはマンガでいうと『ジョジョの奇妙な冒険』の荒木飛呂彦さんとか。けっこう幅広いんですよ、取り上げてきたものは。なので「美術」といいつつ、「表現」という方が近いかもしれないですね。広い意味で「表現」を取り上げていくっていうのが、『美術手帖』がいままでやってきたこと。その軸にあるのが、現代美術ということですね。
武田:現代美術を軸足にしつつ、特に近年は視覚表現を広く取り上げているというイメージですよね。
橋爪:そうですね。
長井:一気にとっつきやすくなった。
橋爪:そうなんです。やはり「美術」と一言で言っても、中身は多様なので、その多様性を紹介していくのが、一つ大きな使命なのかなと思いますね。

ウェブメディアで「アートのジャーナリズムを日本に浸透させたい」(橋爪)
武田:『美術手帖』がウェブ版を開いた2017年あたりって、新しいメディアを立ち上げていく動きが活発になっていた。そのなかでぼく自身、メディア業界の人間として「『美術手帖』がウェブをやるんだ!」っていう驚きと興味があって。すごく注目されたじゃないですか。
あのときにウェブマガジンを立ち上げていくっていう意義。もちろんタイムリーに、速く、即時的な情報を取り上げていくためっていう部分は、いまお話しいただきましたけど、他にもポイントがあったのかなと想像するんですが、どうですか?
橋爪:いちばんは当然ながら、時事性をもっと強く打ち出していきたいっていうのがありました。いま『美術手帖』の雑誌は2か月に1回の隔月刊行なんですね。それまでは月刊誌としてやってきたんですけど、雑誌のほうが2か月に1回というタイムスパンになったこともあって、よりウェブで日々の出来事を追っかけていく必要が出てきた。
雑誌は特集ベースでやっているんですね。毎号毎号、何かの特集があって、それを軸にパッケージとして届ける。そのなかにはどうしても収まりきらない細かい情報や、周辺領域の話とかも多いわけじゃないですか。特に最近は、アートにいろんな方々が関わりだして、その活動もすごく多くなってきているので、そういったものを全部すくいとっていきたい気持ちはありますね。
武田:いまこの人、絶対取り上げるべき若手なんだけど、特集テーマ的に合わないから拾えないっていうのは非常にもったいないですし。
橋爪:そういうのもありますね。
武田:そう考えるとウェブの役割は、よりジャーナルっぽい立ち位置になるんでしょうかね。
橋爪:そうですね。基本的に軸足を置いているのはジャーナリズム。アートのジャーナリズムをもうちょっと日本にも浸透させたい気持ちがあって。特にウェブメディアで、アートのジャーナリズム媒体って、日本ではほとんどなくて。
ただ、海外を見ると、ちゃんとあるんですよね。それはやっぱり、世間においても、アートがきちんと認められている証拠というか。ジャーナリズムがないと、正しい情報も、いろんな人が面白いことをやっていても伝わりにくい、伝わっていかないという状況もある。ジャーナリズムとしてちゃんと機能していくっていうのが、『美術手帖』としてはいちばんやりたいことだし、重要だなと思っています。
武田:なるほど。そのほかにも、最近はポッドキャスト番組『instocial』も始められたということで、ここについては後ほど時間をかけてゆっくり聞きたいと思うのですが、ウェブ版といい、ポッドキャストの展開といい、新しいメディアを実装するというトライを最近行なっていらっしゃるということがよくわかりました。
『instocial by 美術手帖』を聴く(Spotifyを開く)
『THEATRE for ALL』では手話通訳、字幕、音声ガイドなど「一つの作品にいろんな情報保障、バリアフリーがついた状態の映像作品を見ることができる」(篠田)
武田:一方の『THEATRE for ALL』もうかがってみたいですね、長井さん。
長井:はい。篠田さん、おまたせしてすいません。以前の収録でプリコグ(『THEATRE for ALL』を運営する株式会社プリコグ)の方が来てくださって。
篠田:代表の中村が以前お邪魔させていただいたみたいです。
長井:今回初めて聞く方のためにも、どんな活動内容なのか教えていただければなと思うんですけど。
篠田:ありがとうございます。たぶん中村が来たときは、『THEATRE for ALL』を運営しているプリコグという会社の活動の話をさせていただいたかなと思うんです。プリコグは舞台の企画制作をしている会社で、この2月5日に新規事業で始めたのが『THEATRE for ALL』というオンライン劇場の取り組みです。
特徴として「アクセシビリティに特化した劇場」と言ってるんですけど、アクセシビリティという言葉って、馴染みあります?
武田:ぼくは情報をどう伝えるかという仕事を編集者としてやっているので、わかるんですけど、この仕事についてなかったら、パッと聞いて、なんのことかわかってなかったような気もします。
篠田:ですよね。「アクセス」なので、接しやすくというか、アプローチしやすくするみたいなことなんですけど。コロナがあってオンラインの取り組みは増えていったけれども、それ以前から、たとえば聴覚や視覚に障がいがある方をはじめ、言語の壁とか、子育て中でとか、お芝居好きなんだけど、なかなか劇場に行けなかった方はたくさんいらっしゃったと思うんです。そういう方たちにも芸術作品をお届けしたいという想いから立ち上がったサービスなんです。
たとえば手話通訳とか、字幕とか、音声ガイドとか、一つの作品にいろんな情報保障、バリアフリーがついた状態の映像を見ることができる。有料のものも、無料のものもあるんですけど、そういうサービスというのがざっくりした内容です。

1990年生まれ。奈良県出身。京都大学在学中より日本の民俗芸能や古典芸能に惹かれ、特にお能の身体をリサーチして、国内外でクリエイションを行う。傍ら会社員として、広告・デザインのプロデューサー業を経験。『THEATRE for ALL』では、コミュニケーションチーム現場統括、および『THEATRE for ALL LAB』の編集長として、アクセシビリティをテーマとしたサービスの立ち上げに関わった。ボイスパフォーマーとしても活動を行なっている。
長井:誰がどうやって翻訳するかで、作品の印象がすごく変わってきて面白そう。
篠田:まさにそうで。「翻訳」と言っていただいたように、手話も一つの言語ですし、字幕や音声ガイドをどなたが作るかで、作品の伝わり方も違ったりするんです。そこを今回、公募で、「作品をバリアフリー化して配信してみたい方たち、ぜひご応募ください」と募集して、(MOTION GALLERY代表の)大高さんをはじめ審査員の皆さんに選んでいただいた作品を、いま公開しているんです。
選ばれた段階で、元々手話がついているとか、バリアフリー化された作品はほとんどなくて。作品公募の段階以降に、自分の作品はどういう方たちに届けたいか考えていただいたり、音声ガイドをつけていくってどういうことなんだろうと、障がい当事者やアーティストが混じって一緒にご相談する機会をつくったり。映像上で起こっていることを音で伝えるって、セリフを読み上げることとまた少し違うじゃないですか。ドアが閉まる音とか、車の音みたいなものが聞こえている、そのとき主人公はどんな表情をしていて、車の音がどういう効果を果たしているのか、寂しさを表すのか、何か迷いを表すのかとか。
どうやって伝えることがバリアフリーなんだろうかということを作家さんも悩まれながら、我々も手探りですけど一緒にご相談していきました。結果、作品一つひとつ、全然別々のアプローチというか、全部共通で字幕がついて、音声ガイドがついてと決まってるわけじゃなくて。それぞれ試行錯誤しながら作られた作品が、いまプラットフォームに上がって配信されています。
長井:面白い!
篠田:プリコグの大事にしていることでもあるんですけど、もともと演劇や舞台が好きだった人に届けるだけじゃなくて、いままで触れてこなかった人、たとえば地域のおばあちゃんとかもそうかもしれないですし、いろんな方たちに舞台に触れてもらうための客席づくりというか、そのためのワークショップをしたり、イベントをしたりという、教育事業のようなことにも、コロナが始まるより前から取り組んでいて。
なので今回も、配信するだけではなくて、作品を鑑賞するってどういうことだろうとか、いろんな身体を持った人が鑑賞できるようになったときに、受け取り方がどう違うんだろうみたいなことを話し合ったり、アーティストにそれをフィードバックしたりもしました。「私が作った音声ガイドは、目が見えないあなたにとって、作品を理解する助けになりましたか?」とか、「どういうふうに捉えられましたか?」みたいなことを、実際対話する場を作りながら続けていくというか。正解がないので、いまもみんなで一緒にそういったことに取り組んでいます。
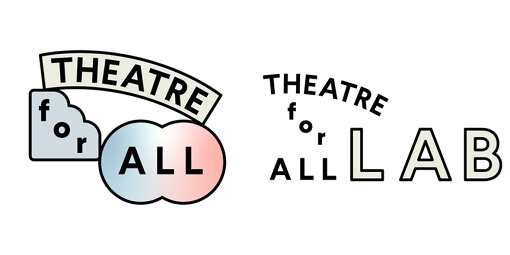
生まれつき見えない人と、途中で見えなくなった人。視覚に障がいがあるといっても、音声ガイドに求めるものは「全然違ったりする」(篠田)
武田:いま長井さんが翻訳というフレーズを使って質問してくれましたけど、まさに翻訳的な作業だと思いますし、美術作品はそもそも鑑賞者によって、いろんな解釈が生まれてしかるべきものじゃないですか。ただ、その鑑賞自体に何かしらの身体的・認知的な障がいがあるときに、その人の認知に合わせて、どういうアプローチで届けられるか。そういう試みだなと思うんですけど、その数を重ねていくことによって、人々の鑑賞に対する認知の違いとかも浮き彫りになっていく気がして、そのあたりは個人的に興味深いなと思っていたんです。
篠田:いまおっしゃってくださったみたいに「鑑賞に障がいがある」なんですよね。人に障がいがあるわけではなくて、何かを見ることに対して困難がある。それは身体の違いとか、話している言葉の違いがあることによって、何か困難があるんだけれども、そこをみんなでクリアするというか。何かしらの方策でクリアしたときに、いままで会話できなかった人と会話できるようになって、お客さんが増えるとアーティストも作品を見てくれる人が増えて、表現の幅が広がっていったり、創作のタネが見つかっていったりする。
そういう意味で「みんなの劇場」というか。まさに「THEATRE for ALL」なんです。みんなでオンゴーイングで作っていく劇場になるといいなと思いながら、完成にはまだ程遠いかもしれないですけど、始めてきたところですね。
武田:これは「鑑賞」ということを改めて考える機会にもなるかなと思ったんですけど、ここまでのお話は、美術業界にいらっしゃる橋爪さんには、どんなふうに聞こえましたか?
橋爪:すごく面白いですね。「鑑賞に障がいがある」って、確かにそうだなと思って。やっぱりコロナになってから、美術館もデジタルで作品を鑑賞してもらおうと、いろいろな取り組みをしているんだけれども、まだうまくいってないなと思うところがあって。たぶん、やり方もわからなかったりするんだと思うんです。ノウハウも全然ないし。
こんな状況になるとは、たぶんどこも思ってなくて。特に日本の美術館って、そもそもデジタル対応が遅れていたので、一気にデジタルトランスフォーメーションできないですよね。まだまだテコ入れしていかないといけない。
それに、コロナでなくとも潜在的に作品を見ることができなかった人たちはいっぱいいたと思うんですよ。「コロナで見れなくなった」じゃなくて、「コロナじゃなくても見れなかった人」は、いっぱいいたはずで。そういう人たちにどうやって作品や展覧会を届けていくのかは、いまもまだ解決できていない、でも解決しなきゃいけない課題だろうなとすごく思いますね。
武田:ニュース番組とか国会中継でも、なんでもいいんですけれども、情報を正しく届けるためのアクセシビリティへの対応って、すでにナレッジが蓄積されて、ある程度スタンダードな手法が確立されていると思うんです。だけどアート作品の鑑賞には、そもそも正解がないわけで。トライ&エラーがすごくおありなんだろうなと、お話を聞いてて感じましたし、そこにこそ可能性がありそう。
長井:たとえば、舞台で何が起きているかを音だけで説明するときって、起きてることを全部羅列するのが、起きてることを伝えてることとは限らないじゃないですか。
篠田:そうですよね。本当に難しいんですよね。
長井:説明することで、めちゃくちゃ伏線張っちゃってるみたいなことが起きそうだし、本当に難しい。けど作っていくのは、すごく楽しそうというか。
篠田:めちゃくちゃ面白いですよ。どこまで説明するのか、本当に正解がなくて。それはアーティスト側が、こう伝わってほしいっていう想いの話もありますし。たとえば視覚に障がいがある方で、生まれつき見えない方と、途中で見えなくなった方って、もともと見えない方は聴覚の世界でやってこられているので、「音声ガイドの説明がそんなにたくさんなくてもいい。説明が多いのは邪魔だ」ってなる方もいるけど、元々は見えていて、大人になってから全盲になられた方の中には、見えてたことがあるから、「見えている光景を全部説明してほしい」ってなることもある。
だから映画のガイドを作るときに「一体どこに合わせるの?」みたいな話もある。パートナー企業や当事者の方たちにモニターしていただきながら、字幕とか音声ガイドとかを作っていくんですけど、(人によって)全然違ったりするんですよね。私たちからは同じような障がいがあるように見えても、そのなかの多様性ももちろんあるから、本当に正解がないし、みなさんおっしゃることが面白い。クリエイティブな現場だなと思っています。
武田:視覚や聴覚に特別問題を抱えていないぼくですら、劇場に行って演劇を見てるときに、ステージ全体の情報を拾えてないじゃないですか。袖に出ていくときには、そっちを一瞬見ちゃったりするし、視線誘導を演出家も行なっているわけで。だから周囲のものを全部説明すると、それはそれで違うとか。そこからフィードバックして、創作はどうあるべきかみたいなところまで見えてくるような気もするんですけど、今回はこのあたりで一度切りたいなと思います。次回も引き続き、橋爪勇介さんと篠田栞さんにお話をうかがっていきたいと思います。

ポッドキャストは一見ムダな議論の細部も残せる。番組開始から1年経て感じた「対話型コンテンツの面白さ」(武田)
1週目の配信はここまで。2週目以降では『THEATRE for ALL LAB』で行なっているアクセシビリティに関するリサーチや、ポッドキャスト番組『instocial by 美術手帖』などの話をしながら、鑑賞することについてさらに深く掘り下げている。また、コロナ禍における影響も語られたほか、「人は壁に空間があると何か掛けたくなる」「自分の好みとは逆のものをレコメンドしてくれるAIがほしい」といった興味深い発言も相次いで飛び出しているので、ぜひポッドキャストで全編を聞いてほしい。
MOTION GALLERY CROSSING #047 特集『見える音、聞こえる風景』section1を聴く(Spotifyを開く)
3カ月にわたって行なってきた番組レポートは、今回で最終回となる。もちろん番組は続くので、最後に武田と長井の二人に、今後への意気込みを語ってもらった。
武田:いい文章とはなにか、っていう問いに対して「難しいことを平易な言葉で語るのがいい文章だ」、みたいな話ってあるじゃないですか。それはひとつの真ではあるけど、全部ではないと思うんです。専門用語で緻密に書くいい文章もあるし、簡単な言葉をさぞ難しいように書く技術もある。「難しいことを平易な言葉で語る」というのは、いい文章のひとつのあり方なだけであると。
これは話し言葉も一緒で、難しいことを噛み砕いてわかりやすくすることは、いい話し方の一つではあるけど、そこから取り除かれてしまったノイズというか、味わいというか、それがなくなっちゃっている可能性もあるなと思うんです。ポッドキャストだと一見ムダな議論の細部も残せるので、それも含めて体験してもらうのが対話型コンテンツの面白さなんじゃないかなって、番組を1年やってみて感じているので、それは続けていきたいと思います。
長井:私は最初に浮かぶ疑問を大切にしたい。何も知らない人がそれを聞いたときに、どう思うかっていうことを大事にしたいというか。(ゲストで来る)何かのジャンルで先頭に立っている人って、どんどん前に進もうとがんばってくれてるから、入ってきたばかりの人がぶつかる疑問とかって、なかなか思い出しづらくなっちゃうと思うんですよ。それを強制的にこっちに引きずり戻したい。
武田:もともとこの番組は九段ハウスさんで収録し、九段ハウスさんでリスナーとゲストが出会えるミートアップとか、リスナーの人たちと継続的に関わっていくための「場」を作って、みんなで番組を作っていくような状態を思い描いていたんです。それがコロナという不測の事態で描いた通りにならず、なんとか1年走ったという感じなので、これからも状況に合わせながら、いろんなツールを使って、リスナーのみなさんともっと距離を縮めて、いろんな展開をしていきたいなと思っています。
長井:もっと交流ができるようになるといいですよね。
武田:会いたいもんね、普通に。

- 番組情報
-

- 『MOTION GALLERY CROSSING』
-
編集者の武田俊と演劇モデルの長井短が「これからの文化と社会のはなし」をゲストとともに掘り下げていく、日本最大級のクラウドファンディングサイト「MOTION GALLERY」によるポッドキャスト番組。毎月テーマに沿ったゲストトークが行なわれるほか、「MOTION GALLERY」で進行中の注目プロジェクトも紹介。東京・九段下の登録有形文化財「九段ハウス」で収録され、毎週水曜に最新回が公開されている。
- プロフィール
-
- 武田俊 (たけだ しゅん)
-
1986年、名古屋市生まれ。編集者、メディアリサーチャー。株式会社まちづクリエイティブ・チーフエディター。BONUS TRACK・チーフエディター。法政大学文学部兼任講師。大学在学中にインディペンデントマガジン『界遊』を創刊。編集者・ライターとして活動を始める。2011年、代表としてメディアプロダクション・KAI-YOU,LLC.を設立。2014年、同社退社以降『TOweb』『ROOMIE』『lute』などカルチャー・ライフスタイル領域のWebマガジンにて編集長を歴任。2019年より、JFN「ON THE PLANET」月曜パーソナリティを担当。メディア研究とその実践を主とし、様々な企業のメディアを活用したプロジェクトに関わる。
- 長井短 (ながい みじか)
-
1993年生まれ、東京都出身。「演劇モデル」と称し、雑誌、舞台、バラエティ番組、テレビドラマ、映画など幅広く活躍する。読者と同じ目線で感情を丁寧に綴りながらもパンチが効いた文章も人気があり、様々な媒体に寄稿。近年の主な出演作品として『書けないッ!?~脚本家 吉丸圭佑の筋書きのない生活~』『真夏の少年~19452020』『家売る女の逆襲』、舞台KERA×CROSS第二弾『グッドバイ』、今泉力哉と玉田企画『街の下で』、映画『あの日々の話』『耳を腐らせるほどの愛』などがある。執筆業では恋愛メディアAMにて『内緒にしといて』、yom yomにて『友達なんて100人もいらない』、幻冬舎プラスにて『キリ番踏んだら私のターン』を連載。2020年に初の著書『内緒にしといて』(晶文社)上梓。
- 橋爪勇介 (はしづめ ゆうすけ)
-
1983年生まれ。三重県出身。立命館大学国際関係学部を卒業後、美術年鑑社『新美術新聞』の記者を経て、2016年に株式会社美術出版社に入社。2017年にウェブ版『美術手帖』を立ち上げたのち、2019年より編集長を務める。2020年12月にスタートしたポッドキャスト番組『instocial by 美術手帖』ではMCも担当。
- 篠田栞 (しのだ しおり)
-
1990年生まれ。奈良県出身。京都大学在学中より日本の民俗芸能や古典芸能に惹かれ、特にお能の身体をリサーチして、国内外でクリエイションを行う。傍ら会社員として、広告・デザインのプロデューサー業を経験。『THEATRE for ALL』では、コミュニケーションチーム現場統括、および『THEATRE for ALL LAB』の編集長として、アクセシビリティをテーマとしたサービスの立ち上げに関わった。ボイスパフォーマーとしても活動を行なっている。
- フィードバック 0
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-



