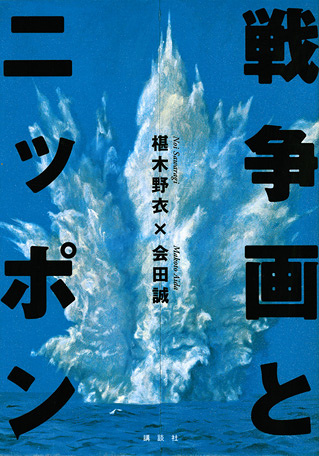政治家が「政策芸術」と言い始めてしまった
まったくいつの時代だと耳を疑ったが、自民党若手議員の勉強会『文化芸術懇話会』で提議された「政策芸術」という言葉には驚いた。この懇話会では出席議員から「マスコミを懲らしめる」「広告料収入がなくなるのが一番だから、経団連に働きかけて欲しい」といった発言が飛び交い、批判が集中した。
この会の設立趣意書に「心を打つ『政策芸術』を立案し実行する知恵と力を習得する」とある。芸術家や文化人からの意見を吸い上げつつ、自分たちの政策を「芸術」の域に引き上げ、感動を作り上げる創作やメッセージを使って、政策を理解してもらおうという意図が含まれている。これほどプロパガンダに近い言葉を政治のど真ん中が使い始めてしまったことに驚く。
会田誠と椹木野衣が「戦争画」の本質を問う
美術と政治、美術と国家の関係性を、太平洋戦争中に描かれた「戦争画」から読み解く1冊、椹木野衣・会田誠『戦争画とニッポン』(講談社)を開くと、会田が持つ美術家としての葛藤が吐露されている。「あの時代に生まれていたら、自分は戦争画を描いていただろうか?」と自問自答するものの、結局この問いに現時点で答えることなどできないのだから、どうしても「これから再びあのような時代になったら、自分は戦争画を描くだろうか?」との問いに変転していく。70年前に終わった戦争を伝える「戦争画」を前に二人で対話を重ねるなか、この主題は通底している。会田は、戦争画を量産した「当時の絵描きたちを『愚か』『悪』と裁断することは、少なくとも僕にはできません」という結論に至る。
戦争を辞さない状態に持ち込もうとするかのような法整備が議論されるなかで、「政策芸術」という取り組みが持ち出された事実は重い。会田は『戦争画RETURNS』というシリーズ作品や『なんとなくウヨク』というパフォーマンスを通して、同時代の現代美術が右翼的なものと向き合ってこなかったことを問うてきた。一方、美術批評家・椹木野衣は、自身の反戦への思いを「戦後教育の結果ではなくて、傷痍軍人を目の当たりにした視覚的なイメージの強さ」から感知し始めたとする。実体験として戦争を知らない二人が「戦争画」を語り合う本書は、戦争と芸術との距離、戦争を視覚化してきた芸術の役割を見つめ直すために、そして奇しくも「政策芸術」という言葉を投じてくる現在を問うためにも意義深い1冊となっている。
戦争画はさほどプロパガンダ的ではなかった
藤田嗣治、宮本三郎、向井潤吉、小磯良平らの「戦争画」とあらためて向き合う動機には、「芸術だけはどうして他に選択肢がなく、最初からパッケージ化されたものとして左翼なんだろうか」(会田)という疑義があった。当時、「大東亜戦争作戦記録画」を残す役割を持ち、戦争画を量産したのが「陸軍美術協会」。この協会にとって、「美術の王道は写実の油彩画で、日本画はそれに準じる立ち位置」であり、「抽象なんてのは何の役にも立たない堕落、というか国賊」でしかなかった。「戦勝国によって仕切られた戦後の平和で国際的な世界では、国籍不明の抽象絵画が共通の儀式にもなりましたから。抽象は具象に対して進歩的な絵画で、そこには民主主義も政治的イデオロギーもない。実は、『ない』ということが最大の政治であり、イデオロギーだったわけ」と椹木は話す。やがて、敗戦国である日本は「戦争画」を封印することを選んでいく。
『別冊太陽 画家と戦争 日本美術史の空白』(平凡社)の監修者である近代美術史学者・河田明久は、その序文で「戦争のなかの美術」と「美術のなかの戦争」を区分けする。その上で、戦争に直面した美術家のふるまいも、その戦争を伝える美術も、それぞれ多様であり、決して一色ではないとする。「戦時という特殊な事情はあるにせよ、画家たちのふるまいはごく普通じゃないか、と思っていただきたい」「戦中にかぎらず、戦争の前も後も、そして今も、美術家たちはあたえられた資質と立場に応じて、日々自身を取り巻く世界との交信を続けている」と記している。会田と椹木は戦争画を振り返りながら、戦争画として残されているもののなかに、人道的にアウトなものはほとんどないと言う。無論、証拠隠滅のために破棄されたり、GHQによって没収されたりした事情もあるが、戦争画はさほどプロパガンダ的ではなかったのだ。
偏った思想が滲んでいたのは、絵画よりもむしろ言葉だった。陸軍美術協会が発行した雑誌『大東亜戦争 南方画信』に掲載された、戦争画の描き手たちが集った座談会『陸軍派遣画家 南方戦線座談会』が本書に抜粋掲載されている。たとえば『神兵パレンバンに降下す』などの戦争画を描いた鶴田吾郎は「今度の戦争は日本の歴史始つて以来のことなんだし、武力戦と建設戦とが併行して行はれてゐるんだから、文化方面がウンと働く余地がある訳だな。我々は画家だから画家として御奉公することが幾らでもあるんだ」と自らの役割を直接的に宣言している。
戦後70年を見つめ直しながら、今現在の政治を疑う
二人は、「国家とモニュメント」と題された章で、いわゆる「クールジャパン」として担ぎ出される芸術に危うさを表明する。「若くしてアメリカにひとり渡り、母国からはっきりと距離を取った」草間彌生を、「国内の褒賞攻め」にし「いずれ草間彌生に文化勲章を、という道筋がつけられようとしているのではないか」(椹木)と指摘するなど、国家が政策として現代美術との距離を縮め出していることに対して慎重に言及する。
戦争と美術との位置づけを探り合う対話が続く。その探り合いを読者として体感すればするほど、「政策芸術」という言葉を平然と使ってしまう政治家たちを危うく思う。これまであまり問われてこなかった戦争画から戦後史を学び直す本書は、戦後70年を見つめ直すとともに、自分たちの動かしたい方向へ何がなんでも持ち運ぼうとする今現在の政治の働きかけを問うことにも繋がっている。
- 作品情報
-
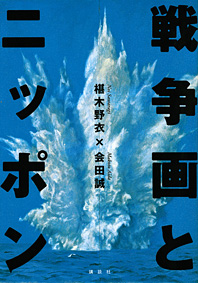
- 『戦争画とニッポン』
-
2015年6月23日(火)発売
著者:会田誠、椹木野衣
価格:2,160円(税込)
発行:講談社
- プロフィール
-
- 武田砂鉄 (たけだ さてつ)
-
1982年生まれ。ライター / 編集。2014年秋、出版社勤務を経てフリーへ。「CINRA.NET」「cakes」「Yahoo!ニュース個人」「マイナビ」「LITERA」「beatleg」「TRASH-UP!!」で連載を持ち、「週刊金曜日」「AERA」「SPA!」「beatleg」「STRANGE DAYS」などの雑誌でも執筆中。著書に『紋切型社会 言葉で固まる現代を解きほぐす』(朝日出版社)がある。
- フィードバック 0
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-