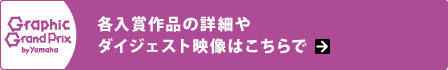「グラフィック」という言葉が、特別な輝きを持っていた時代がある。1980年にスタートした公募展『日本グラフィック展』を嚆矢とする約10年間だ。アートとデザインの境界線が崩壊したといわれるその時代に、若手として参加したアーティストは、大竹伸朗や内藤礼、さらにはタナカカツキなど、今見てみればとてもグラフィックという一言では括れない個性的な顔ぶれだ。そんな中、1982年の第3回グランプリを受賞した日比野克彦の登場は衝撃だった。荒々しく切り貼りした凸凹だらけのダンボールにアクリル絵具でペイントした彼の作品は、「平面作品に限る」という同展の応募規定を文字通り塗り替え、グラフィックの意味を覆した。
その後、様々なアートプロジェクトで、フィジカルな表現を追求してきた日比野が、今度は審査する側として「グラフィック」の意味を問い直そうとしている。ヤマハと共に、新しいコンペティション『Graphic Grand Prix by Yamaha』を始動。二次元の静止したグラフィックであれば、ジャンルを問わずあらゆる作品を受けつける同展の最大の特徴は、作品応募から受賞作発表までのすべてのプロセスをウェブ上で行うこと。しかしアナログ的でフィジカルな表現を軸に置く日比野が、デジタルをキーワードにコンペティションを行うなんて、かなり不思議な組み合わせだ。そんな違和感と疑問を抱きつつ、向かったのは羽田空港国内線ターミナル。夕方には自身のプロジェクトのため富山に発つという日比野に、インタビューする機会を得た。日比野が『Graphic Grand Prix by Yamaha』に抱く想い、そしてここから誕生する若き次世代のアーティストたちにかける期待を聞いた。
自分の職業は自分でつくるしかないと思っています。
―これから富山に向かうそうですね。
日比野:『種は船』というプロジェクトを足かけ3年やっていましてね。京都・舞鶴の人たちと一緒に自作の船をつくって、舞鶴港から新潟港まで航海するんです。日本海側の港に寄港しながら、その街の人々とワークショップをやったりする、その途中なんです。
―日比野さんは『種は船』以外にも、今年たくさんの計画を進めていますね。新潟の『水と土の芸術祭』への出品、それから浅草のホテルのために壁画も制作するとか。
日比野:そうそう。ちょうど昨日、その壁画を浅草で描いてきました。で、今日は木場の造船屋さんに行って、『水と土の芸術祭』に出品する浮き灯台…5メートルの灯台をつくって海に浮かべるんですけど、その制作状況を見てきました。どちらもいい感じで進んでますよ。

日比野克彦
―1時間後には離陸ということなので、さっそくお話を伺いたいと思いますが、今のお話でもお聞きしたとおり、日比野さんの活動は参加型のアートプロジェクトが多く、いわゆるアートマーケットに強くコミットするタイプのアーティストでもないし、かといってもちろん広告業界のクリエイティブディレクターでもないですよね。すごく立ち位置が独特の方だな、と思うのですが。
日比野:自分の職業は自分でつくるしかないと思っています。いちばんやりたいのは自分を表現することで、だからもし違うメディアで表現しやすいものがあったら、別にアートじゃなくてもいいと思ってるんですよ。ものをつくることが終着点ではなくて、人と出会うためにものをつくっている感じがします。
―『種は船』のプロジェクトもまさにそうですね。一方で、南極に行っても絵を描かれるなど、日比野さんはずっと絵を描くことにこだわってらっしゃいますね。
日比野:単純に絵が出来上がっていくのが楽しいんですよね。自分の運動が軌跡になって、絵具が定着していくのが面白い。描くというのは…相当な快感ですよ(笑)。昨日描いていた壁画は、「ザ・ゲートホテル雷門」っていう新しいホテルのための作品なんだけど、ロビーから東京スカイツリーがど〜んと見えるんです。昨日は靄(もや)が立ちこめるなかで描いていたんですけど、本当に幻想的な風景で、当然絵にも影響が表れるわけ。そういう自分の直接的な体験と結びついて、絵が出来上がっていくという面白さは日々感じていますね。
―壁画のような大きい画面と比べて、スケッチブックなどに描く場合はいかがですか?
日比野:スケッチブックも面白いですよ。どんなものだって最初はメモから始まるんですよね。宇宙ロケットをつくるエンジニアだって、アイデアが閃いた時はスケッチを描くと思うんです。例えば、さっき話した浮き灯台も1枚のスケッチから始まって、それが工場で実際にかたちになっていくのを見ると本当に感動するよね。
―浮き灯台はほとんど完成しているんですか?
日比野:もうすぐ完成。平面が立体的なものに変化していくというのは、絵の本質的なおもしろさのひとつだと思う。そういう意味ではグラフィック、二次元というのは何にでもなりうる可能性を持つものだと思いますよ。
「デジタルのコンペで日比野が審査委員長…って超アナログだろ、お前!」というのが正しい(笑)
―そんな日比野さんですが、今回、『Graphic Grand Prix by Yamaha(以下、『GGP』)』という、ウェブ上でのグラフィックコンペティションの審査委員長をされるとお伺いしました。これはどういった経緯で始まったんですか。
日比野:まず最初お話を頂いたときは「えっ?」って驚きました。ヤマハがグラフィックというのもだけど、さらにデジタルにこだわったコンペティションだって言うんですね。
―日比野さんの活動とデジタルってすごく意外な組み合わせですよね。さらに楽器やオートバイを製造しているヤマハが、プロダクトデザインじゃなくてグラフィックコンペティションというのも意外な感じがします。

日比野:音楽って振動だし、バイクも「空気を切る」って表現があるように振動でしょ。いわゆる体感こそがヤマハの真骨頂で、そこに感動があるんだってことを訴えてきた会社なわけじゃない。ヤマハに「グラフィック」というイメージを持っている人って多くないでしょう。
―では、なぜ『GGP』の審査委員長を引き受けられたんですか?
日比野:未知なものが好きだから(笑)。「ヤマハがグラフィック…、アリだな!」って思う人って、まだいないと思う。しかも「デジタルのコンペティションで日比野が審査委員長…って超アナログだろ、お前!」っていうのがリアクションとしては正しい(笑)。でも、一体どうなるんだろうというワクワクやドキドキがありますよね。
―たしかに意外な組み合わせだと思いました。
日比野:でしょ。あえて空気の振動なんかが存在しない「デジタル」にヤマハがこだわるっていうのが面白かった。同時にぼくもデジタルの可能性は日々感じている。FacebookやTwitterはもうみんな普通に使っていて、コミュニケーションに欠かせないものに進化しつつある。この間も大学で学生のプレゼンを聞いていたんだけど、みんなパワーポイントを駆使して、限られた時間のなかでうまく自分のプロジェクトを説明していくんですよね。ちょっと前だったら考えられなかった風景で、デジタルの力を感じた瞬間です。
―デジタル技術なしには成立しない社会ができあがりつつありますよね。
日比野:でも、そこに対抗したいっていう気持ちもある。だから「存在。」っていう、デジタルとはまったく相反する、超アナログなテーマを提案した。人や物がそこにいる/あるっていうフィジカルなテーマに対して、みんながどんな表現を出してくるか。『GGP』は今回が最初でもあるから、こちらが模範解答を用意しているわけじゃあない。ぼく自身も、「こんなものが見てみたい」というのを用意していない。だからこそ楽しみ。
―デジタル的な表現を日比野さんはどのようにとらえてらっしゃいますか?
日比野:ぼくの世代からすると、原画とかアナログ的なものがまずあって、その複製としてのデジタルという入り方ですよね。どうしてもぼくのなかではデジタルとアナログが分かれている。でも今の10代の子どもたちからすれば、最初からデジタルを使って作品をつくる場合も多いわけだから、ぼくと感覚が違うと思う。

―表現との出会いも変わりましたよね。TwitterやFacebookの登場によって、各人が作品を発表することができるようになり、インターネットが表現と出会う場になっています。例えば展覧会で得られる直接的な体験性と同等の位置に、インターネットの空間を置けるのではないかと思います。今回はSNSの反応も見ながら審査をされる、ということでこれまで日比野さんが感じてこなかった新しい出会いの可能性もあるんじゃないでしょうか。
日比野:どうかなあ。これから富山に行って船に乗るけれど、1時間もあれば飛行機ですぐに行ける距離ですよね。一方、Facebookとかでリアルタイムに進捗状況を確認できるけど、モニターから見ている船はやっぱり遠い存在なんです。出会いのきっかけにデジタルはなりうるけれど、その先には、もっと体感が欲しいとぼくは思う。
―ネット上でのコミュニケーションもまた「リアルな体感なんだ」という感覚も若い世代にはあると思います。その意味では、デジタルの登場で「出会い」の意味自体が多様になっているかもしれません。
日比野:グラフィックの意味も変わってきたしね。そもそもグラフィックは、日本語の「図案」「文様」に相当するものだったけれど、今はグラフィックというと、どこかの時代の空気を感じさせるようなイメージがある。アーティストという言葉だって、今はどちらかというミュージシャンを思い起こすけど、さらに遡ればシンガーソングライターって呼ばれていたじゃない。でも、身体を使って、生活とか考え方、思想も含めて俺は歌うんだ、ってことで「アーティスト」に変化してきたわけですよね。だから、グラフィックというものも、人間や空間を含めて、その人の考え方、時代性も含めて「グラフィック」と呼ばれるようになっていくと思うんです。『GGP』のテーマを「存在。」にしたのも、人間や時代すべての存在をとらえるものがグラフィックになるはずだ、っていう意味があります。
『日グラ』の流れには、大竹伸朗さんも、タナカカツキさんも、内藤礼さんもいて、混沌としていた。
―日比野さんは、1982年の『日本グラフィック展(以下『日グラ』)』でグランプリを受賞されたのをきっかけにしてキャリアを積んできました。その当時のグラフィックは今と違う意味を持っていたんですか?
日比野:当時のグラフィックは広告宣伝における原画、イラストレーションに近いよね。メディアに出る手前の平面的な作品のことをグラフィックと言っていた。でも、ぼくが『日グラ』でグランプリを獲った時は、たった5ミリ厚のダンボールに描いただけで「平面じゃない」なんて言われたんですよね。ぼくの作品は当時の感覚でいうと平面ではなかった。でもグランプリを獲ってしまった(笑)。そうすると、翌年からタガが離れちゃって、応募作にダンボールだったり、表面にいろんなものをくっつけたものが現れたわけ。
―日比野さんがきっかけになって。
日比野:10センチ飛び出していても、パネルに貼ってあるんだからグラフィックでしょう、みたいな(笑)。それがどんどん過剰になり、さすがにこれは平面じゃないよな…ってなって『日本オブジェ展』が始まった。
―さらにそれが、日本の現代アートの源流のひとつである『アーバナート展』につながっていくんですね。この流れのなかで、会田誠さん、大竹伸朗さん、内藤礼さんといった現在第一線で活躍する現代美術の作家たちが登場しています。その一方で、タナカカツキさんのようにイラストレーションの世界で活躍する人もいらっしゃいました。
日比野:豪華なメンツですよね。そして混沌としている(笑)。当時は20〜30代の作家が応募できるコンペティションは『日グラ』しかなかったから、みんな発表することに飢えていたんですよね。

―アートやデザイン、もちろんグラフィックもですが、その境界線が目まぐるしく変わっていく時代だったのだと思います。自分たちの手でジャンルを更新していくこと自体が表現であったような時代ですね。
日比野:やっぱり変わっていくものなんですよ。今回の『GGP』で一番期待しているのはまさにそこ。グラフィックの意味が変わったように、アナログに対抗する意味でのデジタルってだけじゃなくて、もうまったく違う空気感を持ったものが出てくるかもしれないと思う。
―だからこそ、『GGP』が公募の場としてデジタルを選んだのが面白いと思います。『日グラ』の流れが一旦途絶えて、その後「現代アート」というフレームのなかで引き継がれていったものもありますが、そこに収まらなかったもの、省かれていったものがたくさんあります。
日比野:日本くさ〜いものとかね。
―でも、いまやインターネットを入り口にして、さまざまな表現と出会うことができるようになりました。だからこそ、面白いアーティストが現れる可能性はすごくあるんじゃないでしょうか。
日比野:そうであって欲しい。コンペティションというのは、出品者、特にグランプリの作品がどれだけ世の中にインパクトを与えるかだから。『日グラ』の1回目に伊東淳のイラストレーションが出て来て、すごく衝撃的だったのと同じように「ええ!?」っていう作品が出てくるかどうかが勝負。だから今回のコンペティションには、とても期待していますよ。
- プロフィール
-
- 日比野克彦
-
アーティスト。1958年岐阜市生まれ。東京芸術大学先端芸術表現科教授。東京藝術大学大学院修了。大学在学中の1982年にダンボールを使った平面作品で、第3回日本グラフィック展大賞、さらに翌年には第30回ADC賞最高賞を受賞し注目を浴びる。国内外で個展・グループ展を多数開催する他、パブリックアート・舞台美術など、多岐にわたる分野で活動中。近年は各地で一般参加者とその地域の特性を生かしたワークショップを多く行っている。
- フィードバック 0
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-