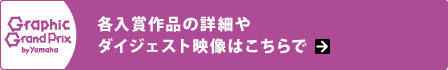今回登場するのは、美術家である梅沢和木。ゲームやアニメに親しみ、ネットカルチャーの隆盛を体感した彼の作品の特徴は、『涼宮ハルヒの憂鬱』『らき☆すた』『プリキュア』といった大人気のアニメのキャラクターを解体/再構築することだ。オタク的想像力の曼荼羅、あるいは宇宙を過剰に創造する梅沢は、ゼロ→テン年代の日本を代表するアーティストの1人であると同時に、グラフィックの変化を現在進行形で体現する表現者でもある。インタビュー場所に指定されたのは彼のアトリエ。古今東西の芸術家の画集や、人文科学の専門書、キャラクターフィギュアなどが雑多に溢れている。とりわけ目を引くのは壁一面にびっしりと貼られた紙、紙、紙…。作品の下絵、予備校時代に描いた自画像、友人作家の作品、フライヤー、人気声優の写真、そしてアニメのピンナップ。アーティストの脳内をそのまま実体化したような空間に思わず息を呑みつつ、インタビューを始めた。
梅沢和木
1985年生まれ、埼玉県出身。高校は県内の美術科に入学し、その後武蔵野美術大学映像学科を卒業。ネット上の画像を大量に収拾し、Photoshopを使ってコラージュする作品を主につくっている。黒瀬陽平、藤城嘘らと共に「カオス*ラウンジ」 のコアメンバー。公式WEBサイトの名前であり本人のニックネームでもある「梅ラボ」は、「梅沢」+「laboratory(実験室/研究所/制作室)」が由来。「漢字とカタカナを混ぜれば印象的になるかなというのと、検索に分かりやすく引っかかりやすいかなというのと、当時は写真をやろうと思っていたのでラボという言葉はちょうどいいかなと思った」とのこと。
梅ラボ
デジタルデータを「出力して終わり」っていうんじゃなくて、実際に筆を入れて自分の作品として成立させることが多い
―写真では何度か拝見していたんですが、実際に目にすると…すごい部屋ですね。
梅沢:典型的なオタク部屋って感じですよね。下の階にもう1つアトリエがあって、そこはキャンバスに向かって描くためのスペース。ここはデジタル工程のためのアトリエです。本当は、全部一緒の空間で作業できるようにしたいですけど。理想を言うとキリがないので、なんとかやってます。

―PCもかなりカスタマイズしているんじゃないですか。
梅沢:半年前くらいにメモリとかいろいろパワーアップして、作業は快適になりました。1作品つくるのに、データ容量が3ギガバイトを超えるとか普通ですから。以前、30ギガ超えの大作をつくったことがあるんですけど、容量が多すぎてPCに保存すらできなくなってしまって、結局お蔵入りになっちゃいました。あれはもったいなかったですねー。
―でも一方で、本物の筆と絵具も使っているのがちょっと意外です。梅沢さんの作品というと、ネット上にある画像を素材にしたデジタル的なコラージュが特徴です。物質のリアルな手触りを避けて、データだけの存在、情報の集積物として作品をつくっているという印象を持っていたので、制作はすべてPC上で行っていると思っていました。
梅沢:僕自身、実際に存在しているものに対する信頼感は薄いので、その印象は間違いではないですよ。人とのコミュニケーションが苦手な性格だったり、小さい頃からデジタルデバイスに慣れ親しんだ世代であったりすることも理由だと思います。でも一方で、両親が絵画教室をやっていることもあり、描くことは大好きで「絵っていいよな」っていう感覚があります。というのもあって、最近は特にデジタルデータを「出力して終わり」っていうんじゃなくて、実際に筆を入れて自分の作品として成立させることが多いです。

梅沢和木
―最近まで、京都での展示(『「隠喩としての宇宙」展』@タカ・イシイギャラリー京都、@ホテル アンテルーム京都)のために新作をつくっていたと伺ったのですが、それもかなり筆を入れたんですか?
梅沢:今回はちょっと変わったことをやっています。PC上でつくった画像をパネルにプリントアウトして、そこに本物の筆で加筆するという手法はこれまでにもやってきました。でも今回は、プリントアウトした画像と、実際に描いた部分の違いを敢えてわかりにくくしています。パネル下地の材料とプリントアウトの質感をあえてアナログっぽくし、逆に加筆するほうをデジタルっぽく寄せたというか…。

『とある人類の超風景II』2012 Kazuki Umezawa Courtesy CASHI
―トリックアートみたいな感じでしょうか? 鑑賞者を欺くような。
梅沢:そうとも言えます。キャラクターの部分はプリントアウトした画像で、抽象的なパターンは手描きだろうと見る人が多いと思うのですが、それを逆にしたりしています。また今回は飛沫のような筆跡が沢山描かれているように見えるんですけど、これらは制作の最初に紙に筆やペインティングナイフで描いた模様をスキャンして、デジタル画像としてコピー&ペーストしたものです。

『とある人類の超風景II』2012 Kazuki Umezawa Courtesy CASHI
―そこは実際に描いた部分だと思いました。
梅沢:でも、全部がそうではないんです。さらにその画像を模写するように、実際に手でキャンバスに描いたパターンもある。自分がつくったマチエール(絵具の質感)を反復して描くわけです。こうしたプロセスが画面全体を覆っています。だから鑑賞者は「これは本当に描いたもの? それともデータ?」と、混乱してしまう。見た瞬間に「これはデジタルでつくったんだな」と思われてしまうのを避けさせようという意図でもあります。

『とある人類の超風景II』2012 Kazuki Umezawa Courtesy CASHI
―それはなぜですか?
梅沢:今年3月の個展(『大地と水と無主物コア』@CASHI)は、デジタルデータそのものを見せることがテーマの一つだったんですけど、オリジナルとコピーの区別がない等価性が特徴であるはずのデジタルなのに、元になるオリジナルがどこかに存在していて、そのコピーのように作品が見えてしまう、と指摘されたんですよね。確かに、そういう見方もあるなと思いました。リアルな空間でデジタル出力そのものを作品として見せようとすると、よほど空間をつくり込まない限りうまくいかないんですよね。それはデータそのものだと感じてもらえるかもしれないし、データのコピーでしかないと受け取られるかもしれない。だから、今回の展覧会の作品ではペインティングとしての強度を高めることにも力を入れました。あともうひとつ、カタールでの村上隆さんの個展の影響もあったと思います。

『大地と水と無主物コア』@CASHI インスタレーションビュー 2012
Photo by Shintaro Yamanaka
僕のような日本人の作家が、『五百羅漢図』を無視して作品を作り続けたら後悔する
―カタール・ドーハでの『Murakami-Ego』展ですね。村上隆さんが、幅100メートルの『五百羅漢図』を展示したことで話題になりました。
梅沢:正直、村上さんとは色々あったので、個展を見に行くこと自体悩みました。こうやって僕が『五百羅漢図』を受けて自分の作品が影響されたと公言することを揶揄する人もいるくらいです。でも僕のような日本人の作家が、『五百羅漢図』を無視して作品を作り続けたら後悔するだろうなと思い、見に行きました。そして、実際に見に行って良かったと思います。
―『五百羅漢図』を実際に目の前にして、どんなことを感じられましたか?
梅沢:『五百羅漢図』は東日本大震災に対する村上さんなりの解答だったと思うのですが、衝撃的でした。何が衝撃だったかというと、「3.11」や「鎮魂」という重たいテーマを扱いながら、とにかくキラキラしていてデコラティブで、ある種の「お祭り」みたいに見えたんですよ。絢爛豪華。考えてみると、多くの歴史的な出来事って、宗教儀礼としての祭や、セレモニーとして後世に伝えられているんですよね。震災を直接体験した人たちの気持ちを、僕は本当には共有できないけれど、ある程度距離のある人たちが大きな出来事に対峙するためには何が必要なのかを考えました。ひょっとするとそれが「お祭り」的要素なのかもしれない、と。

―多くの祝日も歴史的な出来事が起きた日ですね。
梅沢:僕が2011年に大震災を受けて制作した作品は、紫とか青とか冷たい色が多かったんです。あの「現実」を受けとめ、そもそも震災を作品のテーマにすること自体どうなのか、作品なんて作っている場合なのか、など悩んだ末に捻り出したような作品です。それゆえ、現実の重みや凄惨さを反映している部分がありました。それが僕にとってのリアルでした。ところが2012年に作られた村上さんの『五百羅漢図』は、きらびやかだし、でかいし、非常にめでたい感じすらする。しかし同時に死や無限、宇宙など、様々な概念がカオスに渦巻いている。震災から1年以上経った今、どういう作品を作るべきか、カタールで作品を見ながら脳がフル回転していました。
―この頃には京都の展示作品には取りかかっていたのですか?
梅沢:出品依頼をいただいていて、5メートルの新作を作ることが既に決まっていました。村上さんの『五百羅漢図』は100メートルだから、5メートルというと20分の1の大きさなわけですよね。大きければいいという訳ではないと思うのですが、しかし自分にとって物理的に大きい作品をやらねばいかんなという気にもなっていました。1人の作家として、規模もキャリアも技術もかなわないかもしれないけど、挑戦する人がいてもいいんじゃないかと。だから、今回は明るい色をいっぱい使おうと思った。鳳凰や仏像や寿司とか、吉祥のモチーフを使って。

『とある人類の超風景II』2012 Kazuki Umezawa Courtesy CASHI
―たしかに新作のイメージは華やかですね。民俗学における「ハレ」(儀礼や祭などの非日常を指す。対義語の「ケ」は日常を意味する)を思わせます。
梅沢:深刻ぶることだけがシリアスではないと思うんです。時間が経つほどに、どうしてもリアリティーは薄れていってしまう。記憶に残していくためには何が必要だろう、ってことですね。
ムサビの映像学科に入学して感じたのは「俺、映像のセンスないなあ」でした(笑)
―最近の活動を伺ってきましたが、今度は梅沢さんのこれまでについて聞きたいと思います。出身は武蔵野美術大学ですよね。
梅沢:はい。映像学科です。僕、メディアアートやビデオアートがやりたくて入学したんですよ。
―絵画じゃないんですね。
梅沢:昔から絵は好きだったんですけど、色彩構成が苦手で。鮮やかな色を出したいのに、なぜか黄土色になってしまったり。「俺、センスないなあ」と思っていた時に、新宿美術学院で講師をやっていた志村信裕さんの映像作品を見たんです。
―志村さんというと、靴やクリップといった大量生産品が空間に降り注いでくる映像インスタレーションで知られる作家ですね。NHKの作品公募番組『デジタル・スタジアム』で2007年度のグランプリを獲得されて、最近は国際的なデザインの祭典である『ミラノ・サローネ』でも作品を発表していました。
梅沢:当時、志村さんはムサビの映像学科に在籍していて、今とはちょっと違った作品をつくっていたんですよ。朝から夜への移り変わりをアブストラクトなかたちと色だけで見せるようなインスタレーション作品でした。悠久の時間が、映像を通して表現されていて、とにかく格好いいし自分もやりたいと思った。それで僕も映像学科に進もうと。1年浪人して、なんとか合格したんですね。
―では、それが転機に?
梅沢:いや、入学して感じたのは「俺、映像のセンスないなあ」でした(笑)。映像学科のなかには写真とか、映画とか、ウェブとかいろんなコースがあるんですけど、そのなかで新しい映像表現を立ち上げようっていう気運があったんです。「イメージフェノメナン」と言って、ざっくりと言うと、水とかホコリとか日常のありふれた現象を、カメラを通すことで作品化するというものでした。僕自身、日常を切り取るっていうテーマが好きだったので頑張って取り組んだんですけど、結局、お前は何をやりたいんだ? っていうものしかできなくて…。そんな感じで悶々としていた時期に、アニメの『涼宮ハルヒの憂鬱』にハマってたんです。「イメージフェノメナン」に取り組んだ作品で、自分がやりたいものが表現できていなかったので、今度こそ自分が好きなことをやろう。どうせなら大好きなアニメやゲームに殉じた作品をやってしまおうと思った。それが本当の転機です。
日常ってなんだろう、と考えた時に自分にとってはアニメやゲームであり、ネット空間だと気づいた
―その決心が卒業制作の作品につながるわけですね。どんな作品を展示されたんですか?
梅沢:日常ってなんだろう、と考えた時に自分にとってはアニメやゲームであり、その接点がネット空間だと気づいたんです。僕にとっての日常の風景であるネット空間やパソコンの画面を現実の空間に落とし込む、というのが1つのテーマでした。現在の作品に近い、過剰に装飾的な平面作品以外にも、石膏にアニメやゲームのキャラクターを写し取るという作品もつくりました。重さの存在しないデータを石膏にコピペすることで、無理矢理重みを与えてしまおうと。

『画像の存在証明』KazukiUmezawa 2008 Courtesy CASHI
―卒業制作の段階で、実在しない存在を現実の空間に落とし込むというテーマが現れていたんですね。繰り返すようですが、リアルな物質に対する関心の希薄さを押し出すところから梅沢さんは登場したと思っていたので、石膏を使って物質の存在感を際立たせる作品からスタートしたというのは意外です。

『画像の存在証明』KazukiUmezawa 2008 Courtesy CASHI
梅沢:意外にもそうなんですよ。映像学科に在籍していたこともあって、当時は作品を展示する際の空間への意識を磨こうと必死でした。僕はそういう意識が希薄だったので、勉強になりましたね。もともとやりたかった映像インスタレーションのようなことはできなかったけど、結果的には良かったと思います。

『画像の存在証明』KazukiUmezawa 2008 Courtesy CASHI
アニメやゲームをリソースにしたコラージュ作品をつくり始めたことで、初めてグラフィックに近づけたような気がした
―今回の連載は、デジタル時代におけるグラフィックの意味を考えるという目的があるのですが、梅沢さんが考えるグラフィック表現とはなんでしょうか。あるいは、梅沢さんの作品のなかにあるグラフィック的な要素とはなんでしょうか。
梅沢:グラフィックというと、僕は多摩美術大学のグラフィックデザイン学科や、ムサビの視覚伝達デザイン学科を思い出します。どちらも美大芸大のなかでもエリート学科として知られています。僕にとってグラフィックの世界って、残酷なまでにセンスと技術を競い合う場なんですよね。さっきも言ったように、色彩構成やレイアウトに苦手意識があったので、僕にとっては憧れ半分、怖さ半分だった。でも、卒業制作でアニメやゲームをリソースにしたコラージュ作品をつくり始めたことで、初めてグラフィックに近づけたような気がしたんです。アニメの描写ってすごく魅力的だと思います。とても色鮮やかだし、見せたいものがはっきりしているし、露骨なくらい扇情的で、普通のグラフィックにはないようなエッジさがある。

『画像の存在証明』KazukiUmezawa 2008 Courtesy CASHI
―グラフィックが本来持っている視覚への訴求性にも通じますね。
梅沢:自分の好きなものであるアニメやゲームを、ネットを経由することで生まれたのが僕の作品で、グラフィックとして見ても、それはわりと良くできたものだったんですよね。不思議ですよね。単純に絵を描きたいと思っていた時は黄土色にしかならなかったものが、アニメやゲームの洗礼を受けることで成立した。

―梅沢さんにとって、アニメやゲームとの接点になったデジタルってどういうものなんでしょうか。
梅沢:うーん…。絵の話で言うと、そもそもかたちや言葉にならないものや、はっきりと伝えられない何かを描こうとするという意味で、デジタルもアナログも違いはないと思います。その意味では、描いている絵そのものには「何もない」というか、その先にある不可視なものを作家は見つめていると思うんです。僕の場合は、アナログだとそれが見えにくくなると感じます。あまりにも物質としての存在感が強すぎて、物質に対するフェティシズムに収斂していってしまう。重量感や絵具の塗りにばかり感動してしまって、その先にあるはずの、作家が崇高に捉えている重要なイメージが逃げて行ってしまうんです。

『大地と水と無主物コア』@CASHI インスタレーションビュー 2012
Photo by Shintaro Yamanaka
―つくればつくるほど、その大切なものが遠くに行ってしまう。
梅沢:そうです。デジタルはその「罠」に引っかからないための手段でもある。物理的に存在しないということは、圧倒的なマイナスでもありつつ、圧倒的なアドバンテージでもある。存在していないからこそ、透明性がある。その透明性があるからこそ、作品のイメージを正確に捉えることができると僕は信じています。ただ、未だにこれだけ紙が普及しきっている世界で、デジタルのみでの表現はどうしてもリアリティに欠けてしまう部分はある。アナログの良い部分を利用しつつ、デジタルで伝えうる作品のイメージに誘導するような狡猾さは必要だと思います。
美術家兼プロゲーマーって聞いたことないので、アリかな、と。
―梅沢さんは、今後どのような活動を展開していきたいと考えていますか?
梅沢:京都の新作はけっこう手応えがあったので、1枚の絵としての完成度を高めていく方向は続けていきたいですね。ただ、反応が良いものだけをつくればいいわけでもないので、いろいろな方向性の作品をつくっていきたい。それと、ゲームを本気で頑張りたいですね。
―ゲーム? デザイナーとして関わりたいということですか?
梅沢:そうじゃなくて、プロゲーマーというやつです。韓国とかではよく知られているんですけど、オンラインゲームとか格闘ゲームがめちゃくちゃうまい人たちが、企業の協賛を取ってゲームトーナメントに参加するんですよ。

―本物のアスリートみたいですね。
梅沢:まさにそれです! 『ビートマニア』っていうゲームをずっとやっているんですけど…。
―「音ゲー」ってやつですね。鍵盤とターンテーブルがコントローラーになっていて、タイミングよく叩くと、どんどん音がつながっていくという。高校生の時に遊んだことがあります。
梅沢:『ビートマニア』は、既に15年近い歴史があるのですが、最近はゲームの難易度も異常なまでに上がっていて、もはや常人には全く追いつけないレベルにまで進化しているんですよ。オンラインで全国ランキングに登録することもできるのですが、その『ビートマニア』のプロゲーマーになりたいんです。
―えーっと…梅沢さん、画家ですよね…。
梅沢:そうですよ(笑)。美術家兼プロゲーマーって聞いたことないので、アリかな、と。
―言っていることがよくわからないです…(笑)。
梅沢:現代美術の世界ってそんなに広いわけじゃないですけど、最近のゲームの世界もどんどん細分化していて、パイという意味ではほとんど同じくらいじゃないかと思うんです。だから「ゲームをやっているけど、こいつアーティストらしいぜ」って興味を持ってもらえたらアートとゲームの世界の架け橋になれるかな…と。
―本気なんですね。
梅沢:本気です。あと、さっきアスリートって仰ってましたけど、『ビートマニア』の世界もプロのアスリート並の身体能力が競われていると思ってます。1秒間に60フレーム分の静止画が表示されるゲームセンターのモニターで、2フレーム分だけが高得点なんですが、トッププレイヤーたちはそれを寸分違わぬタイミングで、約2分間のプレイ時間内に何千回も正確なタイミングで打鍵を繰り返している。たとえばプロのスキージャンプの世界では助走、踏切の強さ、角度、姿勢の中でも、特に踏切のタイミングが非常に重要で、100分の1秒単位のシビアさが求められるらしいんですよね。単純な比較になってしまいますが、60分の2秒を何千回も正確に叩く世界と、100分の1秒の1回を正確に狙う世界とがそこにはあるわけです。
―60分の2秒なんて意識的にカウントできるんですか?
梅沢:いえ、ほとんど直感レベルです。だから調子がいい時は、スポーツにおける「ゾーン体験」(ある行為に完全に没頭している精神状態。しばしば時間感覚が歪み、動きがゆっくり見えることもあるという)そのものですよ。まあ、偉そうなことを言っておきながらプロレベルの腕前にはまだまだ程遠いので、精進あるのみですが…。
―ゲームの世界ってバーチャルなものだと思われがちですけど、お話をお伺いしていると、バーチャルでありながらも、かつ身体性をともなった現実の話ですよね。それってデジタルデータを駆使しながら、アナログな平面を制作していく、梅沢さんの作品とも完全に一致している感じがします。デジタルとアナログって一見矛盾しているように捉えられがちですけど、そんなことはないのかもしれませんね。
梅沢:そうですね。僕は『ビートマニア』を作品制作の前に精神統一的な意味でプレイすることもあるのですが、その時の体調に応じて「あ、いま60分の3秒遅れたな」とかが分かるんです。ゲームの結果が、その日の制作に影響を与えたりすることもざらにあります。制作している時に、コンマ数ミリ単位の幅を面相筆で描く時と、PCで1ピクセル単位の画像をいじる時と、これらは完全にリンクしていると感じます。ゲームとアートのハイブリッドな融合が、これからの目標ですかね!
『Graphic Grand Prix by Yamaha』
応募期間:2012年6月29日(金)〜9月30日(日)
テーマ:「存在。」
審査委員:
日比野克彦
梅村充(ヤマハ株式会社代表取締役社長)
ヤマハ株式会社デザインセクションメンバー
柳弘之(ヤマハ発動機株式会社代表取締役社長)
ヤマハ発動機株式会社デザインセクションメンバー
Graphic Grand Prix by Yamaha (グラフィック・グランプリ by ヤマハ)
facebook - グラフィック・グランプリ by Yamaha
『「隠喩としての宇宙」展』
2012年7月20日(金)〜10月7日(日)
会場:
第1会場 京都府 タカ・イシイギャラリー京都
第2会場 京都府 ホテル アンテルーム京都
時間:第1会場 11:00〜19:00、第2会場 12:00〜19:00
休館日:
第1会場 日、月曜、祝日、8月12日(日)〜8月27日(月)
第2会場 会期中無休
隠喩としての宇宙|タカ・イシイギャラリー
GALLERY9.5:「隠喩としての宇宙」展 “The Cosmos as Metaphor” | HOTEL ANTEROOM KYOTO
『カオス*ラウンジ 「受け入れ」展』
2012年8月18(土)〜8月31日(金)
会場:東京都 ザムザ阿佐ヶ谷
時間:12:00〜22:00
休廊日:8月24日(金)、8月25日(土)、8月26日(日)
アートマガジン『GENDAI*ART vol.1』刊行記念 | CHAOS*LOUNGE official web
- フィードバック 1
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-