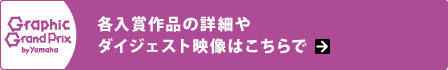「うん、肩書きは『グラフィックデザイナー』でいいですよ」。インタビュー前に趣旨を説明するにあたり、最前線で活躍するグラフィックデザイナーとして登場頂きたいことを伝えると、菊地敦己はそう言った。しかし彼の仕事には、グラフィックデザインを軸としつつ、この言葉だけではくくれない広がりがある。青森県立美術館のロゴや建物全体に配置されるシンボルマークを始めとするVI(ビジュアルアイデンティティー)計画、「mina perhonen」「Sally Scott」のブランディング、また雑誌のアートディレクションや、自身のブックレーベル「BOOK PEAK」での出版活動。そして、丸亀市猪熊弦一郎現代美術館内でのカフェ運営まで。しかし、いくつもの顔を使い分けるクリエイターというより、やりたいこととやるべきことを結びつける名手のような雰囲気も彼には漂う。「この社会には何かのためのデザインが多すぎる」というその姿勢は、いま改めてグラフィックの存在のありようを考えるヒントをくれる。
自分のイラストを入稿すると、デザイナーが上げてくるレイアウトがつまらなかった。だからMacを買ってレイアウトを組み始めたのが始まりです。
―菊地さんは、武蔵野美術大学に在学中から、既にデザインの仕事を始めていたそうですね? でも、専攻は美術学部の彫刻だったとか。

菊地敦己
菊地:もともと、自分では絵描きになると思っていたんですね。予備校ではグラフィックデザインのクラスにいたのですが、講師にイラストレーターの方もいて、公募展のカタログを見せてもらったりしました。それで面白いなと思って、自分も描き始めたんです。ただ、絵って広い場所も要らないし、いつでも描ける。だからどうせ美大に入るなら、環境がないとできない手間のかかる表現をやってみるか、というのが彫刻を選んだ理由です。あと、同時にグラフィックデザインでも受験したんですけど、結局受かったのが彫刻だったっていうのもありますけど(笑)。
―では学生時代に始めた仕事も、イラストが出発点?
菊地:そうですね。描いたものを『イラストレーション』誌の誌上コンペとか、JACA(国際芸術文化振興会)展に応募したんです。大きな賞は取れなかったけど、割とすぐ入選して、小さな仕事もやらせてもらえるようになって。自分は学校の中でやるより、こういう形で社会に出て行ったほうが早いかもな、と思った経験でした。

「Sally Scott」2013 a/w ポスター
―自立心の高い学生だったんですね。
菊地:そのあと展覧会をやったり、いったん休学したり、ちゃんと彫刻にも取り組んだり(笑)、色々あるんですけど。当時はバイトしながらの制作活動でしたが、その状態がいつまで続けられるの? という疑問もあって。お金がないせいで自分の時間が他のことに取られるのはイヤだなって思うと、やはりイラストの仕事は直接稼げるところがいいなと感じていました。
―そこからグラフィックデザインを始めたきっかけは?
菊地:イラストを渡してデザインされたものが上がってくると、どうにもつまらない。納得がいかないから、注文をつける。そうすると「じゃあどんなのがいいの?」って聞かれるんですが、そこで自分で作って見せられたら早いじゃないですか。当時、パソコンはまだ高かったけど、ちょうど一般的になってきた頃でした。思い切って借金してMacを買って、レイアウトを組み始めたのが始まりです。

「PLAY」展示風景 青森県立美術館
―その頃は、手描きのイラストをMacに取り込んでいたんですか? それとも直接Macで描きました?
菊地:両方でしたけど、Macを買ってしばらくしてからは、直接Illustratorで描くようになりました。手描きのイラストを取り込んでもいいけど、画像が重いとマシンが固まっちゃうから(笑)。
―現在の菊地さんのグラフィックデザインも、Illustratorのベジェ曲線だけで描いたような、シンプルな要素が軽妙に関わり合う印象が強いですが、当時の重たいデータに耐えられないPC環境がそのルーツ?(笑)
菊地:あぁ〜、そう……なのかなぁ?(笑)
ブルーマークは「非営利だけど面白いことをやろう。そのために、きちんとお金になる仕事もやろう」って始まりました。
―デザインと同時に、出版レーベルやカフェの運営もやってしまう今の菊地さんにつながるのかなと思うことで、学生時代のご活動についてもうひとつ伺います。当時、アーティストによる運営スペース「スタジオ食堂」のプロデューサーもしていたそうですね?
菊地:もともと美術家の中山ダイスケさんたちが始めた共同スタジオで、最初、僕は彼のアシスタントをしながら、自分の作品制作も続けていました。そのうち、ここをオルタナティブスペースとしてもっと外部に開いていこうという流れになったんですが、一方で中山さんがニューヨークに拠点を移すことになって。それでスタジオ食堂の運営は「キク、お前がやれ!」と。

『物物』書影
―大学を去ることにしたのも、その活動の本格化と関係が?
菊地:色々絡み合っていますが、まず、そのプロデューサーになった時期に、アーティストとしての自分の活動はいったん区切りをつけました。当時はもうデザインの仕事もしていて、ただし、まだそれで完全には食えていなくて。だから大学3年生のとき親に「学費のあと1年分を、大学に渡す代わりに私に投資しませんか?」的な相談をして(笑)、途中退学しました。
―20代前半にして、濃い日々ですね。
菊地:スタジオ食堂のプロデューサーは2年間。その後は、小池一子さんが江東区で運営していた「佐賀町エキジビットスペース」に携わったり、アートマネジメントのNPOの立ち上げをしたりしてアートの場づくりみたいなことに関わっていました。だから僕の20代前半の仕事は、美術とデザインの世界を並行して生きてきた感じですね。周囲の人から見るとアート界隈の人だけど、生計はデザインで立てているという。
―やりたいことの中で、経済的な支えになるものと、そう儲かりはしないけど楽しいものを上手く両立していたんですね。そのスタイルは昨年の「解散」まで、いくつもの名仕事を世に出したデザインオフィス「ブルーマーク」にもつながっているんですか?
菊地:まあ、結果的にそうですね。ブルーマークは、「Pepe California」としての音楽活動と同時にウェブディレクターもしていた斎藤寿大くんと一緒に「非営利だけど面白いことをやろう。そのために、きちんとお金になる仕事もやろう」っていうので始まりました。解散は惜しいと言って下さる方も多かったのですが、10年近く経って、良い区切りの時期だったと思っています。

最初から何案も出して分散させていくより、ひとつの「これだ!」という案を積み上げていくほうがいい。
―お話を伺っていると、グラフィックデザインはほぼ独学ですよね? その表現の自由さには、なるほどな〜と思う反面、すごく緻密な計算やルールから生まれている印象もあります。「論理と感性」みたいな話についてはどう考えていますか?
菊地:ルールや仕組みを自分で作るのは好きですね。既存の形式を使うことよりも、作ってしまったほうが面白い。アカデミックなデザインのセオリーをほとんど知らないということもありますけど。でもそんなに複雑なことをやっているわけではないですし、プロジェクトごとに実験しているという感じです。例えば青森県立美術館のロゴや館内の各種文字、サイン(すべてオリジナルフォントを使用)は、単に水平、垂直の他は45度の線を使うという、本当にシンプルなルールです。グラフィックの世界も、所謂モダンデザインのセオリーを使わないと説明を求められるので、必要なときは論理的な説明もしますけど、正直なところ僕の中では「こうなってると面白くね?」が一番の根拠なんです。

「青森県立美術館」 VI / サイン計画
―そういったアイデアをクライアントに伝える時の、菊地流プレゼンって、どんな感じですか?
菊地:僕はほとんどの場合、一案だけしか作りません。もちろん、機能的な問題とか、修正すべき点があれば、そこからどんどん改変していきますよ。でも、最初から何案も出して分散させていくより、ひとつの「これだ!」という案を作り込んでいくほうがいい。だって「一応、明朝とゴシックと両パターンご用意しました」とか、バカみたいじゃないですか(笑)。そのどちらが良いか決めるために、僕らは呼ばれてるわけで。

「青森県立美術館」 VI / サイン計画
―たしかに。でも、それでも「別の案も見たい」と言われることないですか?
菊地:ほとんどないですね。まぁ、そういうときは「ホントにいいんですね、じゃあこの案はもう捨てますからねッ?」って、資料を破らんばかりの勢いで宣言しますけど(笑)。だって、定食屋で天丼とカツ丼と両方出してもらってから、どっちを食べるか決めよう、みたいな話はあり得ないじゃないですか。
「何かのためのデザイン」が多すぎる。経済的価値さえ引き出せればいいというのがデザインの本質ではない。
―彫刻の話と結びつけて、というわけでもないのですが、菊地さんの手がけるグラフィックデザインは、平面なのに奥行きみたいなもの「三次元的という意味とはまた違う空間性」があるのかなって思います。
菊地:デザインをしていく上で「抜け」という感覚は一番大事にしますね。「何かいまひとつ抜けないな〜」っていうときは再考しますし、「抜けたな〜っ!」という瞬間は手応えがあります。おっしゃるように三次元的な立体感とも違って、例えばペタっとしたテイストでも、いい「抜け」感のあるグラフィックはある。言葉を変えると、余白が空間になるというか、二次元に空気が流れるというか。その判断基準は究極的には「気持ちいいから」って話になりますけど、単に生理的なものとも違う、情報の構造設計ができているかという側面もあります。
―今回、ヤマハが『Graphic Grand Prix by Yamaha』を開催して作品をデジタルデータで公募していますが、そのテーマが「存在」なんです。平面のグラフィックは、たとえば彫刻なんかと比べると物質性が薄いかもしれない。さらに言えばデジタルでの制作が一般化した環境で、あえてこの言葉を持ってきたのかなとも感じます。菊地さんはグラフィックデザインと「存在」という言葉の関係をどう見ていますか?
菊地:パソコン上のモニターに表示されるものだって、物質とは異なるけれど存在しているといえるんじゃないでしょうか。あとそもそもデザイナーは、大もとの形を作るのが仕事で、それが複製されて世に出ていくわけです。その大もととして生まれたものはデザインとして「存在する」わけですよね。いまなら「オリジナルデータ」ということになりますが、昔でいうなら印刷のための「版下」としての存在。それが、ネットなり印刷なり、様々な形で複製されて広がっていくわけです。
―以前に、デザインは「それ自体が存在できているどうか」が大切、との発言をなさっていましたね。
菊地:それはたぶん「何かのためのデザイン」が多すぎる、という話ですかね。もちろん何かを要求をだすクライアントがいて、それに応えるデザイナーがいてという仕事の関係はあります。でも、経済的な効果さえ引き出せればいいというのがデザインの本質的な価値ではないと思います。グラフィックの意匠自体が芸術的な価値を持っていることもあるでしょうし、新しいコミニュケーションの方法を開発して、それが社会的な価値をもつことだってあります。時代が移り変わっても残っているデザインには、そういった価値が含まれていますよね。

僕自身は、目には見えない「社会」とか、漠然とした巨大過ぎるシステムみたいなものへの不信感が結構あるんです。
―それは「社会を良くするデザイン」みたいなものとはまた違う?
菊地:うーん、それを言われたら「じゃあ良い社会ってどういう社会?」と聞いちゃうでしょうね(笑)。そりゃあ社会を良くできるなら、したいです。でも、世界はそんなに簡単にはできていない。だからデザイナーは、目の前にある対象の課題や可能性に向き合っていくことが、正直な仕事の仕方ではないかと思います。あと、僕はデザインだけが何か特別なコミュニケーションを生み出せるとは思わないです。だって、世の中すべての行いがコミュニケーションだから。デザインという職能よりも、その人間次第だと思いますけど。

『小金沢健人展 動物的』ポスター 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館
―となると、菊地さん個人が表現に向かう、一番のモチベーションは……?
菊地:そうですね……。「恨み」みたいなもの?
―う、恨みっ? この爽やかな作風の原動力が?
菊地:ちょっとアレですかね(苦笑)。いや、なんていうか、僕自身は、目には見えない「社会」とか、漠然とした巨大過ぎるシステムみたいなものへの不信感があるんです。これは誰もが多かれ少なかれ、持っている気持ちだと思うんですけど。で、個人が何かを作る原動力って、その漠然としたものへの反撃じゃないかと思うんです。倒せない相手なんだろうけれど、それでも、っていう。自分がデザインしたものが印刷やネットを介して何万部も広がっていくこの仕事も、僕にとってそういう意味合いなのかなって。それは、クライアントのいる仕事でもそうで、やっぱり作るものにはアイデンティティーが必要だと思うので。
平面は生活に馴染んだメディアだからこそ、色々挑戦しやすい。逆に「菊地が木彫りのクマをつくったらしい」とかだと、絶対うがった見方をされそうじゃないですか?(笑)
―ところで菊地さんにとって、平面メディアの魅力とは何でしょう?
菊地:気軽さというか、メディア自体に大袈裟な意味がないことですかね。あまりにも生活に馴染んだ存在だからこそ、色々挑戦しやすいというか。逆にこれが「菊地が木彫りのクマを作ったらしい」とかだと、絶対うがった見方をされそうじゃないですか?

―どうでしょう、見てみたいですけど(笑)。「気軽さ」でいうと、いまはデジタルによる制作物が、やはりデジタルデバイスによって広がっていく状況もあります。これはどう感じますか? 菊地さんは先ほどのお話の通り、そういう制作がパーソナルにも可能になった、割と早い段階での実践者なのかなとも思いますが。
菊地:デジタルで作り始めたとき一番新鮮だったのは「可変可能」ということですね。特にサイズ。絵を描いていると、どうしても選んだキャンバスの物理的サイズから逃れられない。それがコンピュータ上では制約がなくて、「6400%ってどんなの?」みたいな(笑)。でも、それが当たり前な世代もすでにいる。iPhoneやiPadなど、モニターとなるデバイスも多彩になっていく中で、この感覚はさらに変化していくのかもしれませんね。
―いまは描画作業も、主にコンピューターでなさっているんですよね?
菊地:そうですね。絵もパーツごとに描いていて。「この形、なんかいいな」というフォルムができると、すぐには使う機会がなくても保存しておきます。それが元になって別なものが生まれたりすることもあります。いま思えば、彫刻でも僕、キャスティング(型取り)で作品づくりしていましたが、あれも複製可能な方法なんですよ。複製可能なものが好きなんですかね。さらにデジタルの場合、「これ、違うかたちでも出力できるよね」といった可能性もありますし。
―『Graphic Grand Prix by Yamaha』では、1,200×1,200px以内のJPEGファイル、というフォーマットで作品を募っています。これ、手づくりの切り絵とかでも、写真に撮ってこのサイズで送ればOKらしいんです。
菊地:なるほど。そのルール、自由なようだけど難しいですね。そこから何が作れるのかっていうのは興味深い。それこそ彫刻でもいいんだろうし。もっと言えば他人の立体作品でも、その捉え方が俺のグラフィックだって言えばOKですか?(笑)

―それはたぶん……、著作権の問題をクリアしてるかどうか次第ですかね(笑)。もし菊地さんがこのルールで作品を作ってほしいとクライアントから要望されたら、どういうものを考えますか?
菊地:えっ、思いつきません(笑)。僕は普段まず取り組むべき課題や、やりたいことがあって、それを実現するのに適しているのは、紙1枚のグラフィックなのか、本なのか、映像なのか、って形でメディアを選ぶことがほとんどです。でも、メディアアートの世界に見られるように、ある特定のメディアを軸に何ができるか、という可能性の探り方もある。グラフィックデザインでもそういう考え方ができる人は尊敬しますね。それとグラフィックって、当たり前ですけど本当に幅広い領域。にも関わらず、この言葉でしか既定できない表現領域があるのも事実で、僕はそこが面白いとも感じます。
- イベント情報
-
- 『Graphic Grand Prix by Yamaha』
-
応募期間:2012年6月29日(金)〜9月30日(日)
テーマ:「存在。」
審査委員:
日比野克彦
梅村充(ヤマハ株式会社代表取締役社長)
ヤマハ株式会社デザインセクションメンバー
柳弘之(ヤマハ発動機株式会社代表取締役社長)
ヤマハ発動機株式会社デザインセクションメンバー
- 書籍情報
-

- 『物物』
-
2012年7月30日発売
著者:猪熊弦一郎、ホンマタカシ、岡尾美代子、堀江敏幸
編集:菊地敦己
監修:丸亀市猪熊弦一郎現代美術館
価格:2,940円(税込)
発行:BOOK PEAK
- プロフィール
-
- 菊地敦己
-
1974年東京生まれ。武蔵野美術大学彫刻科中退。東北芸術工科大学客員教授。1995年、在学中にネオ・スタンダードグラフィックスを立ち上げ、グラフィックデザインの仕事を始める。1997〜1998年「スタジオ食堂」プロデューサー。2000年ブルーマークを設立。アートディレクターとしてファッションブランドのブランディング・イメージ、雑誌等のエディトリアルデザイン、飲食店のプロデュースほか、多角的なデザイン活動を展開。2006年に、JAGDA新人賞とADC賞、2007年にはニューヨークTDC賞、日本サインデザイン協会賞(SDA)奨励賞受賞。2011年3月でブルーマークを解散し。4月から株式会社菊地敦己事務所を設立している。
- フィードバック 10
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-