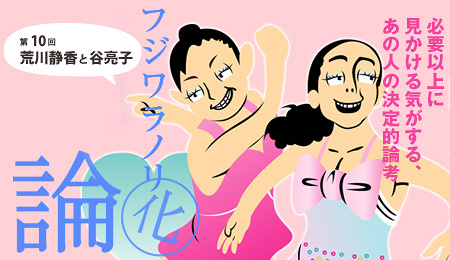其の四 荒川と谷、勝間と香山、幸せとは何か
昨年末から激化している勝間和代と香山リカの論争は、簡略化すれば、女は女として頑張るべきとする勝間と、性別がどうのじゃないし、そもそも頑張らない、しがみつかない生き方もありだとする香山による、久々に巻き起こった「女性の生き方」論争である。酒井順子の負け犬論争以来となるこの論争の醍醐味は、負け犬論争が「結婚」「子持ち」という「置かれた<状態>」の議論だったのに対し、「努力」「自立」という「臨む<態度>」に焦点が置かれている所にある。態度である以上、その程度は当人がはかる。勝間和代という目標があれば、そこを目指す。自分が今どの地点にいるかと査定するのはもちろん自分で、その評価をどうにも上げることが出来ずに追い込まれて病んでいき精神科医のもとを訪れる、そんな患者さんが(精神科医である)香山のもとに多くやってくるようになった、というのである。自分がああでなければならないと思う像がハッキリと分かっているのは、幸福なように見えて、そうならなかった時の反動は残酷な結果を招く。香山が自著「しがみつかない生き方」で「<勝間和代>を目指さない」という項目を用意し、勝間和代を目指す女性の在り方を批判、「AERA」誌上で2人が対談するなど、この論争は激化していく。対談本「勝間さん、努力で幸せになれますか」が刊行されたが、噛み合わないですよねという前提の確認作業をひたすら続けている。
この本に、一カ所、勝間和代を勝間勝代と誤記している箇所がある。思わず笑ってしまった。何故ならば、アクティブに前進する彼女を言い表すのに勝間勝代はピッタリだからだ。勝間和代が普段何をしている人か知らない。そもそも1つの職業を持っている人ではない。ともかく、頑張っている人だ。頑張って一番になろうとしている人だ。そのための努力を惜しまない人だ。合理的に時間を使い無駄を省く人だ。これまで、「日経WOMAN」誌で憧れられる女性といえば、バリバリのキャリアウーマンと決まっていた。新商品を開発しただとか、海外のプロジェクトを成功させただとか、社会とは男社会であるという前提をむしろ男性以上にクラシックに用意した上で、その社会で成功出来るんですと喧伝する姿だった。しかし、勝間和代はそうではない。とにかく凄いのではなく、何だか凄いのだ。つまり、先立つ役職などを持たずに、程度の凄さでモノを言わせるのである。
勝間和代はいつのまにか、「美」を語るようになった。香山との対談の中で、美人かどうかについて「アバブアベレージ(平均以上)であればいいです」と語っているように、ひとまず「美」において平均以上のポジションにあることに疑いを持っていない。しかし、最初はそうではなかった。メディアに出始めた頃の著書や映像を見てくれれば分かるが、むしろ野暮ったさを親しみやすさに変換していた記憶がある。昨年末に、アイドル撮影ばりの照明とPC補正に助けられたとしか思えない華麗な写真を表紙にした著書「結局、女はキレイが勝ち」を刊行した。自分の容姿がキレイだと断定はしないものの、色々な演出によって自分は女でいられていると、輝いていることを肯定していく。香山リカが、必要以上に自分は何の取り柄も無いと自分を落としこむ反動もあって、勝間和代がひとまず「美」の方面に置かれていく。その結果、自分からその「美」を動かし始めたのである。さすがに、勝間ファンにとってもこの鞍替えには驚いたようで、ネット書店のレビューなどでは冷静なジャッジが冷酷に書き込まれている。
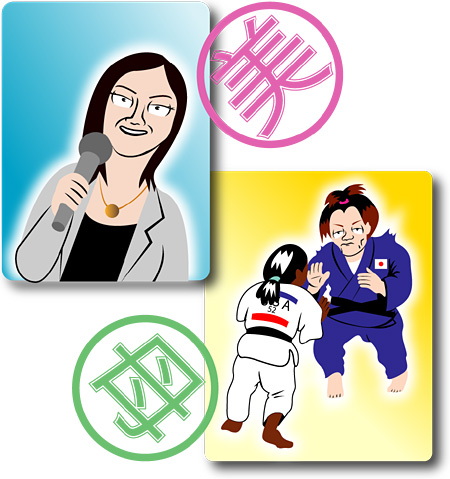
勝間和代は経済評論家、公認会計士として注目され、著書を見てみても当初は決算書、時間投資法、銀行論などについて書き記していたが、ある途端から「断る力」「まねる力」といった人生訓にスライドしていった。分かりやすいアイコンを求める世の需要は勝間和代に集中した。そこでの放任が、「結局、女はキレイが勝ち」を生む。ここまできて、ようやく読者は、勝間和代に対する違和感を体に覚えるのである。本人も酷である。自分は経済評論の部門で出てきたってのに猛スピードで目標に値する人物に設定され、専門外であっても人生訓を求められる人材へと変化を求められて、それに合わせてみた。そしたら、やりすぎだと世間は言う。なかなかどうして難しいものである。
荒川静香が金メダルを獲り現役を退いたあと、当然ながらメディアは、人生訓に近い精神的メッセージを強いた。古傷のケアをどう治してただとか、ジャンプの踏み込みのタイミングをどうやって安定化させたのかなどという話を一切求めなかった。引退によって凄い人に仕上がった彼女に求められるのは、プレッシャーに立ち向かうためにとか、スランプの脱出法だとか、精神面で汎用性を持つヒントを欲しがった。荒川はそれに答えた。まるで、みなさんもこのようにすれば、という枕詞をつけられるような言動を重ねた。そしたら「日経WOMAN」が選ぶ「ウーマン・オブ・ザ・イヤー 2007」の特別賞を獲った。もうこうなると、ジャンプの踏み込みは問われなくなった。壁にぶつかった時にどうやって乗り越えていくかというような問いに明答できるかが重要になったのだ。
勝間和代と荒川静香の流れは似ている。しかしそれはこの2人がたまたま似ていたというのではなく、テレビに頻出する女性、それも異世界のジャンルから飛び込んできた女性に対しては同じ道が敷かれているのかもしれない。専門分野をひとまず飲み込んでそれに飽き始めた頃からこちらの世界で通用する文脈でモノを語らせる。「ああこの人はこちらでも無難に出来る人だ」との評が定まってから、その成分を仕分けしてみると、そこで「美」の問題が「ひとまずクリア」と判子が押されていることを知る。前々回と今回で記したように、ここが誤認の発生源となる。以前、辻希美論でも持ち出したように、ママであることはこの誤認を避けるキーワードとなる。谷亮子が「ママでも金」というのは、議論を逸らせる、或いは彼女の場合においては議論の舵取りを自身で行なえる担保となる。子供の存在を担保とはいささか不謹慎だが、少し考えれば、ママドルというだけで持ち上げ、飽きたら次のママドルに移っていく態度の方が、より不遜であろう。
異ジャンルから飛び込んできてアイコン化した女性には、どこかの段階で、この人は美しいのかそうではないのかというジャッジが下される。それは査定会があるわけではなく、ひとまず美しいということにしておいて、その上で世の反応を見るという残酷な手段で調べられる。なぜ残酷か。本人はその「ひとまず美しいってことにしておいて」という断り書きなど目にやらないからである。美しいと言われて気を悪くする人はいない。そして、その勝手な「お試し期間」が招く誤認の果てにある責任をとるものはいない。あとは、本人が浮ついてしまうだけだ。
勝間和代というアイコンがメディアにどう消費されていくかという流れに荒川静香の消費をリンクさせていくと、「女の生き方」のロールモデルと、そのロールモデルに向かう世間と自身のブレが露になる。そのブレはこの後どうなるのか、「まとめ:アスリートは美人でなければならないのか」と題して、荒川静香論をまとめにかかりたい。
- フィードバック 0
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-