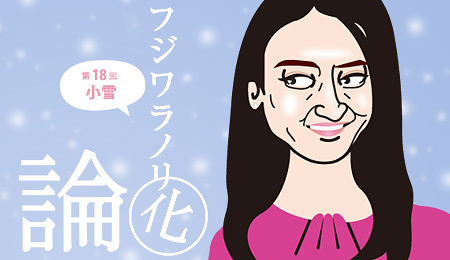其の三 小雪×庶民史
有吉弘行がマツコ・デラックスとのトーク番組で、叶姉妹の価値について異議を申し立てていた。誰が彼女らを支持しているのか、という至極真っ当な突っ込みである。常人が見れば、あの姉妹が手放し大絶賛でキレイではないことくらい分かる。グラマラスやセクシーといった言語の臨界点をリムジンで優雅に行き交っているあの姉妹、有吉の申し立てにマツコは「叶姉妹さんは『1日かけて壮大なエンターテイメントをしてる』って思ってるの。だから、あれが面白いって思える人は好きだと思う」と、珍しく煮え切らない返答に留めていた。何か特殊な事情があるのかもしれないが、実態の見えないセレブリティを放任したままなのは、おそらく、日本国民全体が彼女達の自家発電ゴージャスの創出に寛容な体つきになってしまったからだろう。叶姉妹について僕らはもう、戻れないのだ。姉妹はいつも、姉妹に向かう物語を2人で預かって練り上げる。司会が、とあるネタをふる。そうすると、まずは妹が受け取る。自分はこうだの後に、姉のことを話し、その後で姉にふる。すると、姉はそんなことないですわと、付け加えるなり反転させるなり潰すなりして、笑いをとる。最後に妹が、姉はそんなこと言ってますけど本当はと、再度、異見を加える。そのやりとりに笑いが生じるという仕組みだ。露出の極限を掛け合わせただけではなく、叶姉妹を延命させているのは、姉妹間のやり取りの巧妙さにある。
叶美香はいつも「姉は、」と繰り返す。自分の価値観を決定しているのは姉だと譲らない。この姉妹から、着物からアクセサリーから化粧まで全ての装飾物を剥ぎ落としてみるとしよう。その後に何かが残っているとするならば、それは姉妹間の結束じゃないか。聞いてもいないのに、庶民と違う、と話し出すのはこの姉妹とGACKTくらい。GACKTが、自身のキャラクターをどこまでクールに保てば良いのか悩みあぐねている一方で、叶姉妹の結束は、浴びるに耐えるゴージャスをキープし続けている。やはりそれは、「姉が」に集約されていると見る。小雪は、自分の成長あるいは価値基準が育まれた経緯について、常に「姉が」と言い、姉を礼讃する。人生の転機にはいつも姉・弥生がいた。しかし、そのやり取りからはちっとも人間味が染み出て来ない。次回の「小雪×スピリチュアル史」でも探究していくことになるが、小雪が言うように、姉が霊感少女であったから、なのかもしれない。ひたすら姉に感化されてきた小雪、自身の幼少を語ろうとも、いわゆる幼少特有の雑風景が想起出来ない。小雪は姉から「ピヨ」と呼ばれていた、理由は「危なっかしいヒヨコ」みたいだから、国語と体育は大好きだったけれど、理数系は大の苦手だったから姉に教わっていたのです……等々。自分の葛藤に糸口を見つけ出してくれるのは常に姉だった。その姿が繰り返し描かれていく。芸能人がモノを書けば、9分9厘、自らが育った環境の描写が出てくる。○○だったけど、という違和感もあれば、○○だったから、という謝辞も含まれる。しかし、小雪の周辺からは、無味無臭の学生生活しか立ち上がって来ない。小雪は、自らを「他人と自分を比較することはあまりしない。だけど、これだけは人に負けないということがあるとしたら、それは諦めないことかな(中略)体力と忍耐力が無駄にありすぎるわたしは、諦めどころが、なかなかわからない」と評していく。自己イメージを独りで培養する青春時代だったのか、と疑いたくなる。ちなみに小雪が通った神奈川県立伊勢原高等学校は、LUNA SEAのSUGIZOと真矢を輩出した県立高校である。いわゆるお嬢様学校といわれるようなスマートな学校ではなかったと予想されるが、小雪からは、その青春の断片も破片も見えて来ない。「姉が、」の連続しか、記憶から導かれて来ないのだ。
タレントはいつの時代も庶民感覚を大事にする。『アメトーーク!』でお笑い芸人が中2トークに専念し、昨日あったかのようにオモシロおかしく話を尽くすことに命を懸けるのはその庶民感覚を引っ張り出す最良の返答だと信じ込んでいるからだ。同様に、女優は「等身大」という言葉を大切にする。女優という商売がイメージ産業であることは確かだが、むしろ今はその先を行く「等身大」産業と言えまいか。ブレのない優等生的日常をイメージで象るよりも、ちょっとした色恋沙汰を混ぜ込んだほうがかえって人気が出たりする。小雪はこういった戦略的庶民感覚を投入することを忌み嫌ってきた。ある雑誌のインタビューで、「そんなに媚びないでいられるのは何故か?」と聞かれた小雪の反応は、「媚びないんじゃなくって、媚びられないのだ」。根っからもう私は、と言いたいらしい。
謎めいているのは、そんな小雪に、どういうわけか、仕事をお願いする側が「昭和の忍耐・辛酸」を背負わせることだ。『三丁目の夕日』では、借金を抱える幸薄のストリッパー役。『信さん・炭坑町のセレナーデ』では、炭鉱の町に戻ってきたシングルマザーを演じた。どちらも昭和30年代を舞台にした映画だ。『不毛地帯』では女性陶芸家を演じた。これも昭和が舞台だ。その舞台、昭和の常識において、後ろ指をさされやすい立場ばかりを演じてきた。庶民の中から数歩後ずさったところで暮らす、これが小雪の姿だった。炭鉱などもはや、昭和を象徴化する言葉になりつつある。『フラガール』の舞台、常磐ハワイアン・センターも、そもそもは常磐炭鉱が立ち行かなくなり代わりにオープンさせた娯楽施設であった。小雪の身長は170センチと大柄だ。労働厚生省「国民健康・栄養調査」にあたると、昭和30年代、成人した女性の平均身長は151.7?だというから、演じるにはだいぶデカい。かつて、『海猫』で北海道の漁村に嫁いだ女を演じた伊東美咲(171cm)は、漁師の閉鎖的な社会に吹きすさぶ寒風に耐え忍ぶ……はずだったが、どうにも画面に映る伊東のデカさばかりが気になってしまう。画面からはみ出んばかりの大きさに、求められていた悲壮感が抜けていったのだった。伊東と比べて小雪は、自分を消して役に入り込めるという俳優の基本的センスから考えた上で、優れてはいる。用意された箱に、巨体を溶かしていくことができるのだ。
2002年に放送された『情熱大陸』に出た小雪の映像を観た。番組は唐突に連想ゲームから始まる。矢継ぎ早に小雪が答えてみせる。「海→サーフィン」「イギリス→くもり」「日本→梅干し」。ひねらない。そして、ひねらないことに警戒心が無い。その後で小雪は続ける。人は誰しもペルソナを持っているでしょう、と。ペルソナとは、パーソナルの語源となるラテン語で、人格や仮面を意味する。つまり人は誰しも多面性を持っていると小雪は言うのだ。ロンドンの奥地へ一人旅に出かけた小雪は、電車に揺られながら、親が非常に厳しかったことを明かす。22歳の頃まで門限があり、門限を過ぎると5分おきに電話があった。更に小雪は続ける。自分が楽しまなきゃ人には伝わらない。今の自分を素直に生きることしか出来ないと思ってるから。どうやら番組の締めくくりかというタイミングで、付け加えるように小雪が漏らす。生きていくことはつらいよ、と。
それぞれがそれぞれの具合で意味不明のまま進んでいく30分だった。分かるだろうか、要するに小雪って、代わり映えしない一般論と、薄口のアイデンティティが、自身の体の中だけで中和しているのだ。その中和が出来るのは小雪だけ。だから、中和が出来ない・提供できない外野からみれば、共感も違和も生じない。これが「小雪への無関心」の正体だ。場合によってはその自己都合の中和が、外からはプライドに見えることがある。これが「小雪への嫌悪感」の正体だ。そして、小雪はその中和が出来なくなった時、間違いなく姉に頼る。勿論、羨望も嫉妬が中心だろうが、その隙間に滲む無関心と嫌悪感に晒されて、その姉妹の結束は肥大する。叶姉妹が何かと諸々許されるために姉妹の結束を売り込み続けるのとは違う。
小雪には「こんな意外な役柄も小雪さんならできるんじゃないか」というオファーが集中することで、いつも、そんな役(=昭和の忍耐・辛酸)ばかりを演じているという皮肉が生まれる。事実、昭和の映画に出る度に、小雪はインタビューで、昭和の舞台に演じるとはどういうことかをわざわざ尋ねられている。昭和の庶民というネタをふっかけると、先ほどまで鼻についていた、小雪の「媚びないんじゃなくって、媚びられないのだ」という発言も、少しだけ受け取り方が変わってくる。広告代理店的文脈から自身を逃れさせるためにはそう言うしかないのかもしれない。イメージと内心の乖離。そう勝手な心配を差し向ければ、小雪が少しだけかわいそうに見えてくる。その心身の補填作業のために、小雪はスピリチュアルに傾倒していったのだろうか。次回は、彼女が、姉と同様、やたらと頼るスピリチュアルとは何かへと、今回の議論を引き伸ばしていく。
- フィードバック 1
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-