コミュニケーションの「正解」に悩む人は多い。思うように話が弾まなかったり、長い沈黙が支配したり、誤解を与えたり……。「コミュ症」といわれるような言葉が広く長く共有されているのも、このような悩みや恐怖の大きさを物語っている。
けれども、コミュニケーションに成否や正解なんてあるのだろうか? そんなことを考える機会になるプロジェクトが進行中だ。今秋に展覧会が予定されている「レター / アート / プロジェクト『とどく』」は、アーティストと、さまざまな背景を持った人々が手紙などでやりとりを行ない、共同でアート作品をつくるという試み。
便利さや速さが求められる現代社会で、そして、人と人が簡単に会うことができないコロナ禍で、『とどく』はどのようなコミュニケーションの姿を見せてくれるだろうか? 『とどく』のディレクター、およびキュレーターの小川希と、「哲学対話」と呼ばれる対話型のワークショップを行なう哲学研究者の永井玲衣が、語り合う。
「会えない」を逆手にとる『とどく』。生きづらさを感じる人々と手紙で交流

左から:小川希(『とどく』キュレーター)、永井玲衣(哲学研究者)。対談はオンラインで実施した
―「レター / アート / プロジェクト『とどく』」は、手紙やビデオレターを使ったプロジェクトです。3年間の長期プロジェクトですが、小川さんがこれをやろうと思ったきっかけはなんでしょうか?
小川:企画の前提として、多様な背景を持つ人たちとアーティストがコミュニケーションをとりながら共同で作品を制作する、というのがありました。さらに、このオファーをもらったのが、2019年末のコロナウイルスが世界的に広がっていくタイミングとも重なっていて、参加者たちがリアルで会えないし、会わないということも前提条件になったんですね。
コミュニケーションの場がSNSやZoomなどのオンラインに移行していく時期でしたから、そこで交流を図ることも考えたのですが、むしろ「会えない」という不便な状況を逆手にとったほうが面白いものが生まれるのではないかと。そこで、もはや使われることがめっきり減った「手紙」というツールを使ってコミュニケーションをしていこうと思ったんです。

小川希(おがわ のぞむ)
1976年、東京生まれ。吉祥寺の芸術複合施設「Art Center Ongoing」代表。2021年3月より、文化庁新進芸術家海外研修制度によりオーストリア・ウィーンに1年間滞在中。
―参加している、大木裕之さん、齋藤春佳さん、田中義樹さんらアーティスト3名は、それぞれ、生きづらさを感じている人たち、ろうの学生たち、児童養護施設の子どもたちと手紙やビデオレターでやりとりを続けているんですよね。
小川:そうです。この3人のアーティストは絵画や映像なんかを手がける一方、言葉に関わる作品も手がけてきた人たちです。当初は意識してなかったのですが、手紙でコミュニケーションをとることで、全参加者が同じ土俵に上がるようなプロジェクトになったと思っています。社会はどうしてもマジョリティの生活に合せてつくられていますから、そこから別の環境にいったん移る、というか。
初めましての人たちと、問いを重ねじっくり考える「哲学対話」
―永井さんが行なっている「哲学対話」もコミュニケーションに関わる試みです。そこでは必ずしも明快でなめらかな対話が成立しているわけではなく、口ごもったり、沈黙の時間が長くあったりするといいます。そういうリアルな関わりは、『とどく』にも通じるように思います。
永井:あえて手紙という時間のかかるツールを使う、ある種の制約をかけるというのは、「哲学対話」と似ていると思いました。哲学対話は、司会者によってさまざまな開催形式がありますが、私が担当するときは、見知らぬ人同士が集まり、1つの問いについてみんなで考え合う時間にしています。問いは「日頃気になってることはありますか」など、身近だけど、哲学的に考えられるものを立てています。

永井玲衣(ながい れい)
1991年、東京都生まれ。専門の哲学研究と並行して、学校・企業・寺社・美術館・自治体などで「哲学対話」を幅広く行なう。
永井:対面の人と話すだけでも緊張するのに、そのうえ、調べてもすぐにはわからない哲学的な問いについて考えるのはなおさら大変だと思います。話題があちこちに行く、手間のかかる営みですが、みんなで問いを出すことにこだわっています。手紙の場合は、「書く」という意識的な行為が入るので、話し言葉よりは考えが整っているかもしれないですね。
「対話に終わりはない。言葉はずっと頭のなかに残り、反響していく」(永井)
小川:手紙の面白さでもあり、怖さでもあるのは、そもそも相手から返ってくるとも約束されず、長いあいだ待つ時間が生じることです。永井さんは著書『水中の哲学者たち』(2021年、晶文社)でも「待つ」や「聞く」の重要性が随所に書かれていましたね。
永井:コミュニケーションって、本当はものすごく幅の広い営みなんですよね。どうしてもその場のやりとりの活発さとか、発言力とか、良いコメントを返す、みたいなことに光があたりがちなんですけど、それだけじゃなくて。
手紙を受け取ったら「なんて返事しようかな」と考える時間はすごく長くて、送ったあとも「今度はなんて返ってくるだろう」と待つ時間も長い。いつコミュニケーションが始まって終わるのかもはっきりせず、とにかくその渦中にいる、みたいな。
考えてみると、哲学対話も同じで、終わりはないんですよ。物理的なタイムリミットはあっても、終わったあとも参加者たちは問いに導かれて、考え続ける。誰かの言葉がずっと頭のなかに残り、反響して、それがひょっとすると数年後に「あのとき、ああ言ってたけど」とまた再考することだってありえる。そういう対話のあり方を、手紙はより実感できる気がしますね。

小川:参加アーティストの齋藤春佳さんが、少し前に届いていた学生からの手紙を誤って他の書類に混ぜてしまい、1か月経って発見する事態がありました。学生は「なんで返事が来ないの」と戸惑ったと思います。でも、それってすごくリアルじゃないですか。思い違いだったり、勝手な解釈で成り立っていたりするほうが、人間同士の関係性では多いんですよ。
永井:「哲学対話」の面白さも、対話すればするほど伝わらなくなることです。「何でうまく伝えられないんだろう」ともどかしさを徹底的に感じることがあります(笑)。
「私たちは、わかりやすい答えや結果がすぐに出ないと不安になる」(永井)
小川:手紙ってやりとりしているうちに、自分みたいなものが溶けていく感じがあるんですよね。たとえば、一通書き終わってみると「あれ、これが自分の考えていることなのか」と疑問に思ったりすることも。そこで自分ってものへの確信が一回途切れて、相手から返事が返ってきたときに「そういえば自分はこんなこと書いていたんだな」と思い起こさせられたりする。
これって、アイデンティティを相手に委ねるということな気がしていて。相手から手紙が返ってきたときに、いまの自分と昔の自分が再会する。そこには相手の時間も混ざっていて、時間と距離があるからこそ、自分の変化を感じることがある。

永井:手紙って自分が「他者」っぽくなりますよね。自分の書いた手紙って、読み返すと「自分感」がない。それに相手のことを思い描きながら書くものですから、自己の境界が曖昧になるツールというか。
小川:いま、コミュニケーションに求められるものがあるとしたら、一瞬で相手のことを掴んで、その相手に対して的確な反応をすることだと思うんです。でも、『とどく』ではコミュニケーションの価値を違うかたちで表現したかったんですよね。
永井:なるほど。たしかに、私たちはわかりやすさを求めたり、機転をきかすことに価値を見出したりする社会で生きていると思います。たとえば「スローライフ」のような価値観ってありますよね。時間に追われず、ゆっくりと過ごすこと。でも、私たちはいまの社会の価値観に慣れてしまっていて、わかりやすい答えや結果がすぐに出ないと不安になると思うんです。

小川:スローライフを楽しみたくても、すでに楽しめない体になっていると。
永井:はい。でも、私はゆっくりと流れる時間を大切にしたいし、そこにしがみついてないとダメだと思うんです。自分がせっかちというのもあるんですけど。現代社会には、ゆっくりすることに慣れるためのレッスンが必要だと感じていて、それが「哲学対話」を始めたきっかけの一つなんです。
小川:そうなんですね。
永井:私が開く哲学対話では、参加者に自己紹介はお願いしません。どこから来ましたとか、こういう仕事をしていますとか、プロフィールに関することは聞きません。聞いても、せいぜい名前ぐらい。
人って情報が少ないときにこそ、他者の話に耳を傾ける気がしていて。その人がどんな人かという関心を超えて、その人が考えていること、前提としていること、奥行きみたいなものを気にし始める。そういう実感があるので、『とどく』の手紙のやりとりでは、もっと耳を澄まして聞きたくなる気がしました。
小川:お互いの情報が少ないからこそ、想像力を働かせる。情報をあえて隠すことは、参加者のヒエラルキーをなくし、同じ土俵にあげるという意味で、『とどく』とも共通していますね。
永井:哲学対話に参加した人からは「この時間になんの意味があるんですか?」とか言われることもあります。「そう思いますよね」と自分でも反省しちゃうんですけど(笑)。相手の話を聞く、話を遮らない、なんだかよくわからない話を粘る。これがゆっくりしたペースに慣れるうえでは重要で、トレーニングになると思っています。対話の難しさが露呈すればするほど、世界の真理に極めて接近している気がするんですよね。

ミュートやブロックが当たり前の人間関係。対話を重ねても理解は深まらない?
―世の中では、SNSは必要不可欠なものになっていて、なかには「見えない相手」とやりとりすることもあると思います。相手とコミュニケーションをしていて居心地が悪いと感じると、相手をミュートしたり、ブロックしたりして、関係を断ち切ることも容易です。こうした環境や人間関係の変化からすると、「長い時間をかけて未知の人ともゆっくり付き合う」という意識をお互いが共有しているのはすごいことだなと。
小川:時間をかけてコミュニケーションをしたのに、なにも得るものがないかもしれないと「ムダになること」を恐れている人が多い気がします。でも、人間同士の理解なんて本当はそういうものなはず。結局なにも伝わらないし、伝えられなかったなんてことのほうが普通。でも、相手とやりとりをすることでお互いの理解が深まっていくはずだという「幻想」がある気がします。
永井:私が哲学に関心を持つようになったのは、いくつかの問いがあって、そのうちの一つが「他者とともにあるとはどういうことなんだろう」というものです。単に一緒に仲良しこよしするよりも、バラバラのままに、でも「ともにいる」という様態がないだろうか、という問いです。この問いの答えは導き出せていないのですが、いまの質問を受けて、あらためて考えさせられました。

永井:じつは昨日、アーティストの寒川裕人さんとお話したんです。そこで「徒労ってものをもっとちゃんと考えたほうがいい」とおっしゃっていて、「まさに」と思いました。
―ユージーン・スタジオとして活動している方ですね。
永井:コミュニケーションをしたものの、終わりがないとか、ゴールがないとか、伝わらなかったからちょっとイライラするとか。「徒労」や「骨折り損」といってばっさり切り捨てられているものでも、いつかはきっと価値を見出すことができるのではと。今後、新しい価値が生まれることを期待しています。
「私たちは常に『受け身』。コミュニケーションに翻弄される弱い存在」(永井)
―コミュニケーションは「気まずさ」をはらんだものというか。お二人のなかで、気まずさへの向き合い方、対処法ってあったりしますか?
小川:いまウィーンに滞在しているので、気まずい会話のときは英語が話せないふりをしています(笑)。本当はわかっているけど、わからないふりで逃れるというか。これが日本だと、逃げ出したくても自分の気持ちにウソをついて、無理やり対話を埋めようとしちゃいますね。ぼくの場合は、どんなに気まずい状況でも、それを「気まずい」と認識せず、ただ身を任せるようにしてやり過ごしています。
永井:対処法はまったくわからないです(笑)。というか、コミュニケーションを「方法」と捉える人は多いかもしれませんが、方法ではないですよね。器用に話せる方法があるという考え自体が、まるで自分たちが確固たる主体を持っていて、対話から生まれる、あらゆる違和感や齟齬をクリアにできることを前提にしているじゃないですか。そんなわけない。
私たちは、つねに「受身」だと思うんです。コミュニケーションさせられているし、しゃべらされているし、問われると語り出してしまっている。コミュニケーションというものすらままならず、翻弄される、弱い存在なんだってことを哲学対話では思い知らされます。
でも、先ほどの質問をしたくなってしまう、私たちの社会について考えることはかなり重要だと思います。コミュニケーションについて考えていると、いつも「私たちを不安にさせているものは何だろう」という問いが浮びます。「沈黙が怖い」「なにか良いこと言わなきゃいけない」「ゆっくり話さないといけない」「人の話が聞けない」、これらは人間の根源的な問いであって、その正体はこれからも引き続き考えていきたいと思っています。

人から「良く思われたい」というエゴを捨てたらうまくいく
小川:ぼくは現在、日本の家族と離ればなれなんですね。娘が2人いるのですが、彼女たちとはLINEやオンライン通話で頻繁にやりとりしています。いま『とどく』をやっているので、自分も手紙を書こうと思ったりするんですよ。
でも、いざ書こうとするとなにを書いていいかわからない。「あのとき、お父さんからもらった手紙をすごく大切にしているよ」と言われたい気持ちになって、良いことを書こうとしてしまう。そう思うほど、どんどん書けなくなっていく(笑)。

―プレッシャーになっちゃうんですね。
小川:対処法としては、何てことないことを書く、良いことを書いてやろうと思わない。そうするとすらすら書けるようになって、読み返してみると、これがけっこう良い感じに仕上がっていたりする。紙や時間を埋めるために、理屈をつけたり、ストーリーを立てたりしなくても、コミュニケーションはできるんですよね。
「『とどく』は正解のない問いについて考えることを許してくれる」(永井)
―最後に『とどく』の話に戻りましょう。3年間の長期プロジェクトで、今年の10月から開催される展覧会が、終着点になるわけですが、そこに至るまでまだ時間があります。お二人はこのプロジェクトからどんなものが芽生えてほしい、育ってほしいと思っていますか?
小川:永井さんの話にもありましたが、対話が終わっても、その人たちがずっと引きずっていて、それぞれのなかにあり続けるみたいなことになればいいなあと思うんです。「これが結果です」と、パンっとそこで終わるのではなくて、それまでのプロセスやそのあとのほうが豊かであることは往々にしてありますから、展覧会でもその部分を見せていきたいですね。
『とどく』のタイトルに込めたかったものは、最終的になにか具体的なものを相手に「届ける」ってことではないんです。まして、アーティストが上の立場に立って、相手になにかを教えてあげる、みたいな偉そうなプロジェクトにはしたくありません。相手にない能力を補ってあげる、みたいなのはおこがましいこと。ヒエラルキーのない状況で、お互いの大切な要素を交換することができれば、という期待を当初から抱いていました。
いま、約2年間経過して思うのは、進行しているやりとりのなかから、アーティストたちが自分のなかになかった感情や気持ちが芽生えていると感じていたとすれば、それが「届いた」ってことなのかなと。展覧会では、来場者に「そういう体験が自分にもあるかも」と思ってもらえればいいですね。

永井:手紙には成功も失敗もないですよね。それってすごく希望だと感じています。これまでずっと言ってきたように、コミュニケーションは本来、曖昧なもので、そこには成功も失敗もない。でも、私たちはその成否を想定することにとらわれている。『とどく』は私たちの価値観を揺さぶってくれるプロジェクトだと思います。
『とどく』について考えると、いろんな問いが増えていくと思うんですよね。「結局、なにをしたら届くことになるんだろうね」「単に成功失敗じゃないよね」とか。「手紙が届いたら、それは本当に届いたってこと?」「届かなくても、思いがあれば届いたと言えるかもしれないよね」「時間が経ったら届くこともあるよね」とか。
展覧会を見る側としては、こうやって問いを考え続けることを許してくれる寛大なプロジェクトになったらいいなと思います。
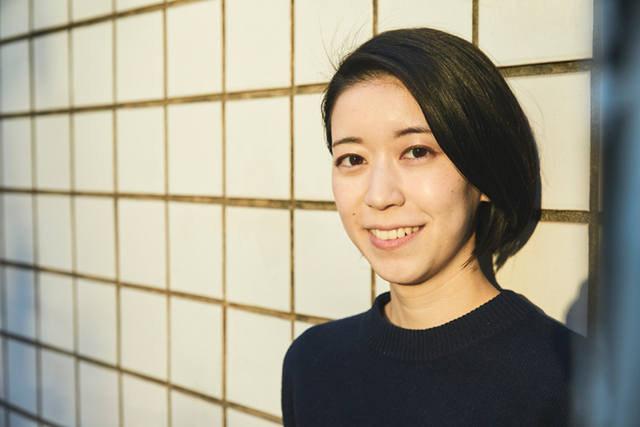
- イベント情報
-
 レター / アート / プロジェクト『とどく』
レター / アート / プロジェクト『とどく』
2020年12月~
ウェブサイトで経過報告中
参加アーティスト:
大木裕之
齋藤春佳
田中義樹レター / アート / プロジェクト『とどく』成果発表展(仮)
2022年10月8日(土)~12月18日(日)
会場:東京都渋谷公園通りギャラリー
- プロフィール
-
- 永井玲衣 (ながい れい)
-
1991年、東京都生まれ。専門の哲学研究と並行して、学校・企業・寺社・美術館・自治体などで「哲学対話」を幅広く行なう。哲学エッセイの連載も多数。セオ商事「newQ」、坂本龍一とGotchが主催する「D2021」などでも活動。詩と植物園と念入りな散歩が好き。著書に『水中の哲学者たち』(晶文社)。
- 小川希 (おがわ のぞむ)
-
1976年、東京生まれ。ディレクター、キュレーター、武蔵野美術大学非常勤講師など。吉祥寺の芸術複合施設「Art Center Ongoing」代表。2013年には国内外の作家を招き、滞在制作させるレジデンスプログラム「Ongoing AIR」を開始。2009~2020年、JR中央線高円寺駅から国分寺駅周辺を舞台に展開する地域密着型アートプロジェクト「TERATOTERA」のディレクターに就任。2021年3月より、文化庁新進芸術家海外研修制度によりオーストラリア・ウィーンに1年間滞在中。
- フィードバック 26
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-





