ポップミュージックをめぐる状況が劇的な速さで流転する昨今。ジャンルの垣根やメジャー / マイナーの境目がより曖昧なものとなるなか、CRCK/LCKSやSMTK、君島大空らを擁するレーベル「APOLLO SOUNDS」は、高度で洗練されていながらも折衷的な、実験精神に満ちたアーティストたちを輩出し続けている。
そんな同レーベルから新たに姿を現したバンドがKhamai Leon(カメレオン)だ。「エクスペリメンタルクラシック」を標榜し、メンバー全員がアカデミックな領域を出自に持ち、ラップやジャズ、クラシック、果ては現代音楽に至るまでを取り入れた、その名のとおり変幻自在な音楽性を追求している。満を辞してリリースされた1stアルバム『hymn』は、高度かつ多様な技術が披露されていながらも、同時に創作に対する深い思索、そしてたしかな情熱が落とし込まれた作品に仕上がった。
このインタビューは、そんな4人のあいだに共通する感覚やクリエイションの原点を訊いたものだ。クラシックやジャズを体系的に学んだ彼らは、なぜポップスのフィールドに打って出たのか? その背景には、1996年生まれの4人が共有する問題意識と音楽観があった。

Khamai Leon(カメレオン) / 左から:beja(Key,Gt)、Fuga Akase(Dr)、yutaozaki(Fl,MC)、Ryo Yonemitsu(Ba)
yutaozakiが率いる音楽集団。2019年4月に結成。メンバーチェンジを経て2020年5月より4人体制として活動をスタートする。動物のカメレオンのようにその瞬間その瞬間で自由に変化するスタイルのなかにメンバーそれぞれが専門的教育を受ける中で育んだ高度で一貫性を持ったサウンドアイコンを武器に、昨今のミクスチャーバンドとは一線を画す存在感を示す。2022年5月、1stアルバム『hymn』をリリース。
Khamai Leon『hymn』を聴く(Apple Musicはこちら)
King Gnu常田大希や石若駿の背中を見て、アカデミズムからポップスのフィールドへ。そこには、後輩世代だからこその葛藤も
―まずはリリースおめでとうございます。みなさんはCRCK/LCKSの小田朋美さんや石若駿さん、King Gnuの常田大希さんや井口理さんらと同様に東京藝術大学出身の2名と、昭和音楽大学出身の2名で結成されていますが、音楽を専門的に学んできたことが今の音楽性にどうつながっているのかを伺いたいです。たとえば、今挙げたようなアーティストたちからはどのような影響があったでしょうか?
yutaozaki(Fl,MC):ぼくらは全員1996年生まれで、4つ上には石若駿さんとか、現代の音楽シーンにおいて影響力のあるアーティストがすごくいっぱいいるんです。
藝大周辺のアーティストだとKing Gnuが今一番有名だと思うんですけど、石若さんを含めたその世代の、アカデミックなところから出てきて活動しているアーティストたちに憧れを抱いて今のスタイルに落ち着きました。
Khamai Leonのライブ映像
―常田さんがKing Gnuとして世に出たのが2017年ですけど、この5年での国内の音楽シーンは相当変化しましたよね。
Akase(Dr):ぼくが大学に入ってジャズを学びはじめたころ、石若さんをはじめとして若手のジャズミュージシャンの活躍が目に見えるかたちで増えはじめたように感じてました。
そのころから石若さんをずっと追っていて、いろんな音楽を知るきっかけにもなったんですけど、ジャズミュージシャンがさまざまなシーンで活躍していく流れはとても気持ちがよかったですね。
beja(Key,Gt):ジャズだけじゃなくて、音楽シーン全体として間違いなく視界は明るくなったよね。
Akase:そうそう。ただぼくらはそことは世代的には絶妙に距離があって、自分自身もその流れに入りたい気持ちはありつつも、自分たちでつくっていかなくちゃいけないんじゃないかっていう葛藤もあって。
―近いところにいるからこその葛藤があった。
beja:みんな一緒かわからないけど、あの世代の方々がああいうふうに注目を浴びたのは、ぼく個人としては「助かったな」と思ってます。
yutaozaki:多様性をつくってくれたよね。
beja:うん。「第一陣にはなれなかった」っていう気持ちももちろんありますけど。

yutaozaki:今は下の世代もたくさん出てきているんですよ。だからぼくらは板挟み状態で。「若い」って言ってもらえるんですけど、自分たちではそう思えなくて。上の世代のミュージシャンを見て「カッケーな」って思うし、悔しくて「自分は何もないな」って思っちゃう。
beja:クラシックのパーカッション出身で石若さんがあれだけいろんなシーンで活躍してるのは、ぼくらとしても引っ張ってもらっているなという感覚があります。だからこそ比べちゃうのはあるんですけど。
yutaozaki:1996年生まれってすごく中途半端だなって思う。それに大学卒業して、2020年に今の体制になってこれからやっていくぞってときにコロナで身動きが取れなくなって。
―コロナの影響も大きかったんですね。
yutaozaki:当初はもうひとり箏のメンバーがいて、ジャズと日本っぽいサウンドを押し出したインストバンドをやってたんですけど、その人が2020年の3月くらいから姿を消して(笑)。
beja:メンバーの脱退とコロナがドンピシャで被ったんですよね。ぼくたちは2年間篭って、試行錯誤をしてようやくアルバムを出せたんですけど、その苦しみの過程ってコロナ禍でいろんな人が味わってるんじゃないかなと思うんですよ。アルバムのタイトルを『hymn』にしたのも、そういう2年間を耐え抜いた自分たちへの「賛美歌(=hymn)」という意味合いがあるんです。

米津玄師のレコーディングに参加するなど、すでに活躍する4人が音楽を志した背景
―4人全員がアカデミックな出自を持つバンドは珍しいと思うんですが、みなさんがそうした道に進んだきっかけは何ですか?
yutaozaki:ぼくはフルートが好きで、東京藝大にフルート専攻で入りました。もともと吹奏楽をやっていて、「ちょっと地元で上手いやつ」みたいなところから調子に乗ったら藝大まで行けた、みたいな(笑)。
幼い頃からクラシックをずっと勉強していたわけじゃなく、ある種勢いで入ったんです。だからか、クラシックだけじゃ満たされない気持ちもあって。

yutaozaki(ユウタオザキ)
大阪府出身。東京藝術大学フルート専攻を卒業。大学在学時から自作曲の演奏や現代音楽の新曲初演を多く行なう。表現者として自己内省を繰り返すなかで生まれる哀切な感情、多くの人間に共感を持たせるリリック、西洋と和の両方の趣を感じさせる音色を持つフルートでバンドを率いる。
beja:ぼくは昔からクラシック一筋で、小さい頃からピアノを習っていて、音大以外の進路は考えたこともありませんでした。ピアノ専攻で音大に入って真面目にやってたんですけど、その一方でポップスとかも好きで。
宅録したり、高2からギターもはじめたり、いろいろぐちゃぐちゃやってきたんですけど、このメンバーと一緒にやるなかで、最近は「ぐちゃぐちゃしててもいいんだな」と思うようになりました。いろんな音楽が好きで、いろんな楽器を自然に演奏してきたんですけど、それがやっと活動につながり、楽しくなってきたところです。

beja(ベジャ)
兵庫県出身。昭和音楽大学大学院修士課程音楽芸術表現専攻ピアノを首席で修了。Khamai Leonのサウンドを担う。圧倒的な技巧と、日本の情緒溢れる演奏、作曲を基軸にノイズや多様なエフェクトを自由に駆使するギタープレイが特徴。バンド作品のミックス、アレンジを担当。
ーYonemitsuさんはいかがですか?
Yonemitsu(Ba):ぼくはもともとピアノをやりはじめたのがきっかけです。大学はコントラバス専攻だったんですけど、父親からもらったのがきっかけでベースもやっていました。
音楽科がある高校のオーケストラの授業でコントラバスに出会って。そこから専門的に極めていきたいな、と。それまではbejaみたいに音大に行こうとは思っていなかったし、エレキベースを真面目にやるようになったのも大学に入ってからですね。大学に入ってクラシックだけっていうのも自分に合わないなと感じて、他の音楽もやっていきたいなと思ったんです。

Ryo Yonemitsu(リョウ ヨネミツ)
神奈川県出身。東京藝術大学コントラバス専攻を卒業。ミュージカル『レ・ミゼラブル』や『アナと雪の女王』にて演奏するほか、米津玄師、V6などのレコーディングに参加。堅実なプレイと、エレキ楽器とは思えない有機的なサウンドが特徴。
Akase:ぼくは音楽をはじめたのは高校からなんです。「バンドかっこよくね?」って感じで高校の軽音楽部でドラムをはじめて、Yonemitsuとはそこで出会いました。
Yonemitsu:一時期、一緒にバンドやってたんですよ。
Akase:そうそう。音楽科がある高校だけど、ぼくは理数科で、音楽を志していたわけではなく、軽音楽部でドラムをはじめて、次第にジャズドラマーや技巧的なほうに興味を持ちはじめて、音大で専門的に学びたいなと。それで、ジャズコースがある音大を選んで入学しました。
ぼくは大学で4年間ジャズを学んでいて、みんなが「クラシックだけじゃ満たされない」と思ったのと同じで、ぼくもジャズだけをやりたかったわけじゃなかったんですよ。ジャズを学んで活かしたいという気持ちが強かった。

Fuga Akase(フウガ アカセ)
神奈川県出身。昭和音楽大学ドラム専攻を首席で卒業。バンドのほか、さまざまなアーティストのサポートを担う。『FUJI ROCK FESTIVAL’21』に碧海祐人のサポートで出演。歌心溢れるタッチのドラムと常に厳格なリズムでバンドのサウンドを支える。
「私の言うことに従いなさい」「オーケストラに入るには家族になることです」。音楽を専門的に学ぶなかで感じた違和感
beja:全員「疑問を抱いた人間」っていうか。ちゃんとやってきた人たちだけど、「他のこともやりたい」とか「このままでいいのか」って疑問を抱いた人間が集まって、お互いそこにシンパシーを感じたのかなって思いますね。
Khamai Leon“awake”を聴く(Apple Musicはこちら)
ークラシックやジャズを学ぶ一方で他の幅広いことに関心があって、ひとつだけじゃ満足できない方々が集まった結果こういうかたちになったと。ちなみにみなさんの抱く「疑問」というのはどんなものなんですか?
yutaozaki:ぼく個人は自分が属している業界に疑問が強くて。
beja:それはぼくも(笑)。たぶんこの4人はみんなそうだと思う。
―どういうことでしょうか?
yutaozaki:ぼくは東京藝術大学のフルート専攻だったんですけど、管楽器ってめちゃくちゃ縦社会で。先生の言うことを絶対に聞く前提で進むのがすごく窮屈だったんですよね。
「私の言うことに従いなさい」って風潮があった。そういう違和感がはじまりでしたね。大袈裟に言うと、尊敬じゃなくて崇拝する社会なんですよ。それが前提として間違っていると思った。だから自分で作品をつくらないといけないなと思ったし、そういう社会から抜け出したいなと思いましたね。

Yonemitsu:コントラバスってオーケストラでは、8本とか、何本かで同じ音を出すような楽器で。ぼくも大学の講義でコントラバスの先生に「まずオーケストラに入るためには家族になることです」って言われて、「これをずっと続けるのは無理だな……」って(笑)。自分の魂のスタイルと合わないから、ひとりだけ違うところで練習をしていました。
yutaozaki:俺とYonemitsuは学校に行くというよりは外で活動している時間が長かったよね。
クラシックやジャズを学ぶなかで感じた閉鎖性、ひとつの音楽に対する盲信的な風潮
beja:ぼくが抱いてた違和感は体制に対してというよりも、同級生や先生がクラシック音楽しか聴かないってことに対してですね。
要は、ぼくは八百万の神を信じていて、ショパンもバッハも神だし、チック・コリアもフランク・ザッパも神。でも、クラシックの世界ではクラシックがすべて。少し盲信的なんですよ。
たとえば「ドビュッシーの和声とこのポップスの和声が似ているんじゃないか」みたいな話をしても、周りにはなかなか共感してもらえませんでした。それが一番の違和感ですね。
Akase:ジャズも近いところはあって。ぼくは今でもジャズの現場をやっているし、ジャズという音楽は大好きなんですけど、「(ジョン・)コルトレーン最強」みたいな盲信的な風潮を感じることもあって。まあ実際、コルトレーンは最強なんですけど(笑)。
現場によっては、「もっとフィリー(・ジョー・ジョーンズ)とかトニー(・ウィリアムス)みたいに叩いたほうがいいよ」みたいなことを言われることもあるんですよね。たくさん聴いているしリスペクトしているけど、彼らの真似をする必要はないと思う。「スウィングしなけりゃ意味がない」という言葉があるけれど、スウィングしてなくても意味あるしなーっていう(笑)。

beja:あくまでもジャンルや要素、音は一部であって、それがすべてじゃないというか。そういう視野でやっていきたいなって思ったときに、この4人はしっくりきたんです。一方で、ぼくはショパンしか信じていない人よりもショパンを好きな自信がある。
yutaozaki:そうやんね(笑)。
beja:すべてのアートにはつながりがあるので、あらゆる要素が複合的であってほしいんですよ。別に尖ってアバンギャルドなことがやりたいわけじゃなくて、我々にとってそれが自然なんですよね。そう思って生きてきた4人なんじゃないかなと思います。
yutaozaki:それがエクスペリメンタルと掲げる所以なんだよね。今回のアルバムはそれを隠さない。
4人があえて掲げる「クラシック」。その精神とは?
ーKhamai Leonの音楽は折衷的なものだと思うんですけど、バンドのプロフィールではその音楽性が「エクスペリメンタルクラシック」と表現されています。この定義を改めて伺いたいのですが、みなさんは「クラシック」をどのように捉えているんでしょうか?
yutaozaki:クラシック音楽には、時代や文化、これまでに蓄積されてきた歴史そのものを俯瞰する姿勢が根底にあります。ぼくはそれが美しいと思ってるんですね。「その姿勢を崩さないぞ」っていう意味で「クラシック」という言葉を残しています。
「クラシックって書くと売れにくいかも」と言われたこともあったんですけど、この思想を持って現代のバンドシーンでどれだけ戦っていけるのかっていうところを「エクスペリメンタルクラシック」という言葉で表現しています。
Khamai Leon“the ray of youth”を聴く(Apple Musicはこちら)
Yonemitsu:ozakiはドビュッシーとかめっちゃ好きだよね。ぼくは楽器の弾きごたえがあるからベートーヴェンの交響曲とか「ザ・王道」が好きで、クラシックというものをもっとふわふわした定義で捉えていますね。
beja:みんな自分の魂のなかにクラシカルな部分を持ってて。それでいてジャズやロックの要素なんかも並列に見えてるほうが自然というか。
いろんなものが混ざってて自然だってことはクラシックの歴史のなかでもたくさん先例があるんですよね。メンバーみんながそういう感性を持っているから、いろんなものが混ざりつつも芸術の芯があるってことかな。
4人の音楽的つながりとなった石若駿、ポップスとして打って出る際のヒントとなったKID FRESINOの存在
ーそうした意識のもとでラップやジャズからクラシック、現代音楽、ポップスまでがクロスオーバーした独特な音楽性が形成されているわけですが、このスタイルに至るまでにどういう経緯があったのでしょうか?
yutaozaki:本当に大変でした。それぞれが好きなものが全然違ったんです。
beja:4人ともシンプルに友達として仲がよくて、そこでつなぎ止められていたけど、実際初期は音楽的なつながりは薄かったかな。

ーそれぞれが当初志向していた方向性や、当時みなさんが好きだったアーティストはどんなものだったんでしょうか?
yutaozaki:ぼくがバンドをやりたいと思った原体験はKing Gnuで、そういう感じの曲も書いていましたね。
beja:ozakiはヒップホップ好きだけど、それ以外は王道のものが好きだったよね。いわゆる「ミュージシャンズミュージシャン」みたいなものはぼくとAkaseが詳しいから、このふたりが音楽的な意味では最初に仲よくなったんですよ。
Akase:そうだったね(笑)。
beja:最初はそれぞれが曲を持ち寄って、試行錯誤して、しっくりこないっていう苦しい時期があったんです。
―ブレイクスルーのきっかけとなった曲などはあったのでしょうか?
beja:「この曲から」っていうのはなくて、「こういうものが美しいよね、かっこいいよね」っていう4人の共通認識が揃ってきた感じがして。
それは石若駿さんをはじめ、周りの音楽家の力なんじゃないかなと思います。個人的に忘れられないのが、2020年のPIT INNでのSONGBOOKのライブで。
SONGBOOKは石若駿をリーダーに、ceroのサポートやソロワークでも知られ東京藝術大学の器楽科・打楽器専攻出身の角銅真実、中村佳穂や君島大空 合奏形態のギターで知られる西田修大からなるトリオ
beja:角銅さんもクラシック出身だからというのもあって4人で観たときに「こういう道があるな」と活路を与えられた気がして、そこから全員の波長が合っていった感じがします。それが2020年の年末くらいですね。
ーある意味4人をつなぎ止めたのが石若さんだと。
yutaozaki:そうですね。で、ちょうどそれくらいの時期、2020年の10月くらいにbejaが“ubiquitous”を書いて。2021年の頭に録ったんですけど、“ubiquitous”も当初はインストの曲だったんです。
beja:インストだと令和のものじゃないというか、いま刺さるものじゃないし、自分でも聴かないなって思っちゃったんです。そうなったときの活路は、ozakiの「ヒップホップが好き」っていう部分だなと。
ー同時代性を確保するためのヒップホップだったんですね。
yutaozaki:リスナーの心をつかむには声が必要だなって、ある種戦略的に考えていたんですけど、時代に刺さるからラップをやってるというよりは、ラップが一番好きな表現で、やりたいからやってますね。
日本人で一番好きなのはKID FRESINOで、ヒップホップであり、よりアートに意識が向いているっていうところに共感するし、すごく好きだったんです。“ubiquitous”では無意識にサンプリングしちゃってる部分もあるんですけど(笑)。
Khamai Leon“ubiquitous”を聴く(Apple Musicで聴く / Spotifyで聴く)
ラップで表現された創作という営み、歴史との連続性というクラシック音楽の精神
ー“ubiquitous”には『ai qing』(2018年)以降のKID FRESINOの音楽性の影響が色濃く表れていますよね。それこそ石若駿さんとKID FRESINOは同作のリリース前後から音楽的な交流もありますけど、『ai qing』がリリースされたときはどのような印象を持ちましたか?
yutaozaki:『ai qing』はリアルタイムでは聴いてなくて。ヒップホップにめちゃくちゃハマったのは2019年くらいだったんです。
KID FRESINO『ai qing』収録曲、ドラムは石若駿
yutaozaki:最初は藝大の同期にいる、なみちえっていうやつとASOBOiSMがやってる曲にハマって。
ASOBOiSMにもKID FRESINOにも内省的なリリックがあると思うんですけど、今回のアルバムにはそういう面が自分でも出過ぎてると思うくらい出ていますね。
beja:あとはケンドリック・ラマーとか、海外のラッパーもよく聴いてるよね。
ーヒップホップのなかでもアーティスティックな人たちというか。ozakiさんのラップにはKID FRESINOたちの影響もありつつ、加えてリリックにかなり直情的な表現が多く、いずれもテーマがはっきりしていることが印象的でした。リリックのインスピレーションの元になっているのはどんなことでしょうか?
yutaozaki:初期の頃はbejaが曲をつくって、それに対して感じたものをキーワードに曲のテーマを決めて書いていたからですね。リリース前にもメンバーで集まって「この曲はこういう意図だよね」っていうのをすり合わせていたんです。
Khamai Leon“坩堝”を聴く(Apple Musicはこちら)
ー“ubiquitous”と“小径”はものをつくること自体について歌っていて、「歴史と自分の連続性」というテーマが共通していると思ったんですが、それはbejaさんの曲から感じ取ったものなんですね。
yutaozaki:もちろんそれもあるし、“ubiquitous”に関しては<偏在する意識、記憶、草木...>の部分をbejaが書いてるんですよ。まずそれが最初に提示してあって、そこから自分の主観で言葉を連ねていったのが最終的なリリック。あと、“ubiquitous”と”小径”の2曲は同じタイミングでできたんです。そういう意味でもこの2曲の思想は共通しているのかなと思います。裏表というか。
beja:クラシックって、曲から意図を読み取ることがすごく大事な音楽で。歴史との連続性についても、クラシック育ちとしてはどんなフィールドでもそれを意識しちゃうんですよね。それがozakiには伝わっていて。
普段ぼくは楽譜をつくりきっちゃうんですけど、それを彼に渡したときに書いてきた言葉が、ぼくが思っていたこととほぼ同じだったんです。「この曲に主人公がいたらこういうことを言うだろうな」って内容を彼がラップで演じてくれたので、「これはいけるな」と。それが今のスタイルに落ち着くことになった一番のきっかけですね。

和辻哲郎のテキストを引用し、創作をする心理状況そのものを表現
ー“小径”のなかには和辻哲郎のテキストが引用されていますが、これは「創作」というものを掘り下げていくなかで出会ったんですか?
yutaozaki:あれはbejaのアイデアなんです。
beja:ぼくが指定して。“小径”は旅先の道を歩いてて、綺麗な景色があったり、何か思い当たることがあって曲をつくりたくなる心理状況そのものを曲にしたくて書いたんです。
Khamai Leon“小径”を聴く(Apple Musicで聴く / Spotifyで聴く)
beja:“小径”は十二音技法を使って書いたんですけど、十二音技法もシェーンベルクっていう作曲家が行き詰まりの打開策として編み出した技法で。
それって創作の根源的な欲求だと思うんです。そういった要素を入れることで、手法的な欲求と自分がそのとき感じた欲求をリンクさせて、歴史の深みを出すような作品をつくれないかと思ったんですね。
この曲には朗読を入れたかったんですけどピンと来るものがなくて、青空文庫を漁っていたときに和辻さんの文章をたまたま見つけたんです。ぼくの作曲していた気持ちにすごく近かった。

和辻哲郎『創作の心理について』を読む(青空文庫を開く)
yutaozaki:最初に<己 創作 生まれる 問>ってリリックが出てくるんで、もうそれがテーマなんだろうなと。bejaがより「創作」ってところにフォーカスしてくれたんでしょうね。
beja:ぼくは作品で関係ないことを結びつけるのが好きで。ドラムンベースと(スティーブ・)ライヒみたいなミニマルミュージックの要素、そして十二音技法が入ってるんですけど、それらは普通に考えたらなかなか結びつかないことじゃないですか。
4人全員スタンダードに疑問を持つことからはじまってるから、ぼくのそういう癖と相性がいいんですよね(笑)。それに気づいたときに創作の打開策があった。“小径”にはそれが体現されています。そういう説明しないとわからないことをozakiが人間の感情に近い部分でリリックにしてるので、とても親和性がありますね。
友情からはじまり音楽的つながりを獲得し、バンドとしての結束はより強固に
ーリズムセクションからみても、その姿勢に共感する部分はありますか?
Akase:ぼくのドラムはなぜかいろんな人からクラシカルって言われるんですよ。あまり自覚はないんですけど、メンバーじゃない人からも言われたりして。Khamai Leonの曲中ではスウィングしたり、ジャズ的な要素を意識したりもするんですけど、それがいい意味でジャズっぽくない、クラシカルな感じでハマっていて。
yutaozaki:それは意図的にやってるのかと思ってた。
Akase:そこまで意図的ではないね。自分だけクラシックをアカデミックに学んでいないので、みんなに近づきたいなって気持ちはあるんですけどね。むしろ、ぼくがこのバンドのスパイスになればいいなと思ってやってる。
yutaozaki:Yonemitsuは音楽に対して一番フラットだなって思う。バンドではベースっていう役割を全うしてくれてて、それがこのバンドの支えになっていると思いますね。
Yonemitsu:ぼくは楽器が好きで音楽を続けてきてるんですよ。でも最近は、音楽そのものに向き合っていこうという感じに変わってきてますね。

ーお話を聞けば聞くほどいいバランスの4人だなと思います。最初からそうだったわけじゃなく、2年間の苦労の果てにそのバランスを手に入れたというか。それが結実したのが今作だと思うんですが、今後へのビジョンはもう見えていますか?
beja:2年間ひたすら内々で作業してきたものがようやく外に出て、世の中と接触したときの化学反応みたいなものが楽しみですね。
この2年で培ってきた我々の音像、サウンド感は強固にしていきつつ、さらにバンド感を強くしていきたいなと思います。今作はできることをやり切った感がすごくあるんですが、そのなかからどの要素を選びとって高めていくかが楽しみでもあります。
ー4人で培ってきたノリを保ちつつ、より開放的にしていくってことですね。
beja:この時期を経ることで関係が強固になりましたね。最初は友情が一番でしたけど、音楽的な意味でも信頼感が出てきたなって。それが新しい創作に導いてくれるのかなと思います。
yutaozaki:自分たちが本当にいいと思うものをつくりたいと思ったのが今作で。自分たち的には最高のものができて、みんなに聴いてほしいけど、これからはちゃんと上を目指したい。そういう姿勢で音楽と向き合いたいなって思いますね。

- リリース情報
-
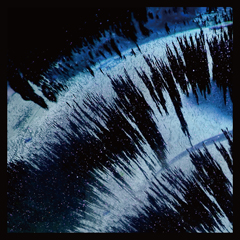 Khamai Leon
Khamai Leon
『hymn』(CD)
価格:2,750円(税込)
2022年5月11日(水)発売
APLS2204
1. introduction
2. the ray of youth
3. ubiquitous
4. 坩堝
5. たゆたい
6. 小径
7. 朝靄の街
8. improvisation #3
9. awake
10. La Mer,
11. Do you hear the hymn??
- イベント情報
-
 『Do you hear the hymn??』
『Do you hear the hymn??』
2022年6月16日(木)
会場:東京都 下北沢BASEMENT BAR
出演:Khamai Leon、LioLan
2022年7月5日(火)
会場:愛知県 名古屋CLUB UPSET
出演:Khamai Leon、LioLan
2022年7月7日(木)
会場:京都府 京都MOJO
出演:Khamai Leon、LioLan
2022年7月8日(金)
会場:大阪府 梅田Zeela
出演:Khamai Leon、LioLan
2022年8月5日(金)
会場:東京都 新宿Marz
出演:Khamai Leon、LioLan
- プロフィール
-

- Khamai Leon (カメレオン)
-
yutaozakiが率いる音楽集団。2019年4月に結成。メンバーチェンジを経て2020年5月より、yutaozaki(Fl,MC)、beja(Key,Gt)、Yonemitsu(Ba)、Akase(Dr)の4人体制として活動をスタートする。動物のカメレオンのようにその瞬間その瞬間で自由に変化するスタイルのなかにメンバーそれぞれが専門的教育を受ける中で育んだ高度で一貫性を持ったサウンドアイコンを武器に、昨今のミクスチャーバンドとは一線を画す存在感を示す。2022年5月、1stアルバム『hymn』をリリース。
- フィードバック 56
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-




