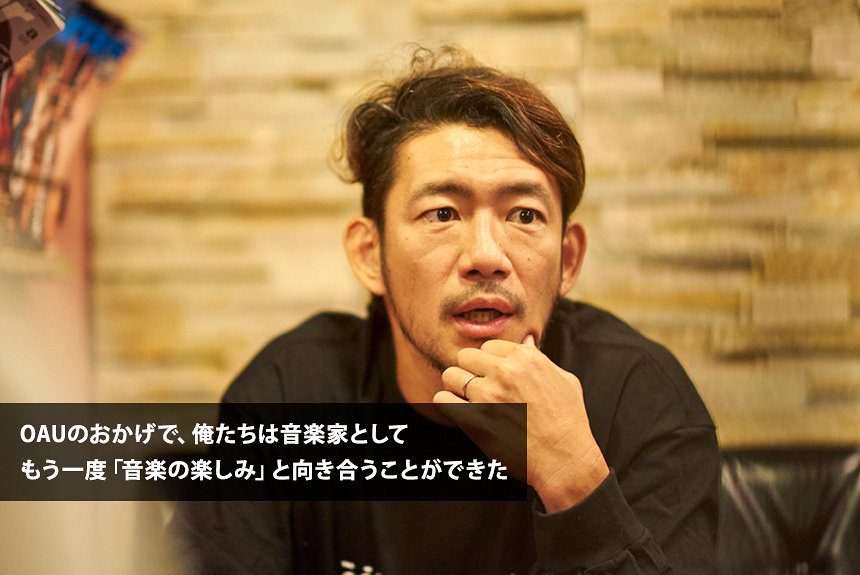ライブハウスを筆頭に、新型コロナウイルスの影響は音楽業界の至るところに依然として大きな影響を及ぼし続けている。それは無論、アーティストも同じである。とりわけ、オールスタンディングの会場で、観客がモッシュしながら熱狂する激しいライブを繰り広げてきたアーティストにとっては、自分たちの「ライブのあり方」そのものの変化を余儀なくされる事態だ。
そんななか、誰よりも「熱い」ライブで知られてきたBRAHMANが、リアルタイムCGやインタラクティブシステムを用いた新しいライブ演出を導入し始めていることをご存じだろうか。主に担当しているのは、ビジュアルアーティストの松山周平が率いるTHINK AND SENSE。膨大な情報を瞬時に解析して現実を拡張する、イマーシブな作品で知られる気鋭のテック系アーティスト集団だ。
BRAHMANの真意は、どこにあるのか。そして、松山と組んだ理由とは。ライブ音楽とテクノロジーの関係性とその未来について、BRAHMANのTOSHI-LOWと松山に話を聞いた。
テクノロジーのなかに潜む「生身」の感覚。これをライブとつなげられないか?
―ちょっと意外な組み合わせですが、そもそもどういう経緯でおふたりは一緒に仕事をされるようになったのでしょうか?
TOSHI-LOW:これまで俺たちのライブは、肉体一本で勝負してきたところがあったんだけど、コロナ禍でお客さんのなかに飛び込むようなことができなくなって。だったらちょっと視点を変えてやってみようと思って、まずステージに巨大な紗幕を引いて、そこに映像を映しながらライブをやってみたんだよね。

TOSHI-LOW(としろう)
BRAHMANのボーカリストであり、OAUのギター・ボーカル。1995年にBRAHMANを結成。全国のライブハウスを中心に活動し、幕張メッセでのセンターステージライブも開催。2018年2月には日本武道館で単独公演を行なう。コロナ禍で敢行した「Tour 2021 -Slow Dance-」はスローな楽曲を中心に構成、紗幕や映像を用いた演出が話題となった。その続編となる「Tour - slow DANCE HALL -」では初のホールツアーを行なった。
―昨年の「Tour 2021-SLOW DANCE-」は、そういうかたちでやっていましたよね。
TOSHI-LOW:そう。で、それはそれでよかったの。静かな曲を演奏して、その雰囲気に合った映像を紗幕に映す。ただ、だんだん物足りなさを感じるようになってきた。
今年に入ってフェスが復活してきて思ったんだけど、大きい会場だとステージの横に巨大なLEDビジョンがあるじゃない。そこでやっていることも、紗幕に映像を映すことも、ミュージックビデオみたいな背景が流れているだけで何か特別なテクノロジーを使っているわけでもないなって思ってきて。
それで、何か新しいやり方はないだろうかって考えて、詳しい人たちに相談しようとして……あれは、有明だっけ?
松山:そうですね。有明のパナソニックセンター東京で開催された「ETERANAL Art Space」という、海外の方の作品も含めてイマーシブな展示を体験できる機会があって。そのイベントにぼくが所属するTHINK AND SENSEで、『stillness』という禅のお寺とコラボレーションした作品を出したんです。それをTOSHI-LOWさんに見ていただいたことがきっかけになりました。

松山周平(まつやま しゅうへい)
株式会社ティーアンドエス取締役 THINK AND SENSE 部 部長 プログラマー・ヴィジュアルアーティスト。先端技術を活かした広告展示やインタラクティブなパフォーマンスを得意とする。オーディオビジュアル作品、インタラクティブなインスタレーション、など多岐に渡る活動を行っている。著書に『Visual Thinking with TouchDesigner』がある。インテルのクリエイター支援プロジェクト「インテル® Blue Carpet Club」参加クリエイター。
TOSHI-LOW:もともと「テクノロジーとアート」みたいなものにあまり乗り気ではなくて、「面白いから見てみなよ」って言われつつも、「めんどくせえな。どうせさあ……」とか思っていたんだけど(笑)。
―(笑)。
TOSHI-LOW:ただ、実際見てみたら、「あれ、思っていたのと違うな?」と。前後左右はもちろん、床と天井もスクリーンになっているような場所に作品が投影されていて、「飛び出す映画」のような衝撃があったんだよね。「あ、これ何か見たことある。子どもの頃、つくば万博で見たやつだ!」って(笑)。
ただ単にテクノロジーが「テクノロジー」としてあるのではなく、テクノロジーとアートって、もうこんなふうに融合し始めているんだって思った。

TOSHI-LOW:俺は、技術的なことは何もわからないから、単純にパソコン上でつくったものをただ見せられるんだろうなって思っていたんだけど、そうではなくて。生身のものとつくり込んだもののあいだの世界に入り込んでいるような、「あ、気持ちいいじゃん」って感覚があった。こういうもので自分たちも何かできないかなと思って、(松山)周平たちと結びつきをつくってもらった。
派手なステージ演出ではなく、BRAHMANの世界観に奥行きをつけるようなコラボレーションを
―TOSHI-LOWさんが衝撃をうけたその作品は、どういうコンセプトでつくられたものだったのでしょうか?
松山:なかなかイメージが湧かないですよね(笑)。ぼくから少し説明させていただくと、その作品は、京都にある「両足院」という禅寺を、超精密なかたちで3Dスキャンさせていただいたものがもとになっています。
両足院の副住職さんとのディスカッションを通して、それをヒントに「禅の考え方」そのものをビジュアライズした作品です。禅のフィロソフィーを言葉ではなく、直感的なイマーシブなビジュアルによって「体験」に変える。そういう作品ですね。
『Stillness』。映像の中心にいるのが両足院の副住職
―なるほど。それは、面白そうですね。
TOSHI-LOW:面白そうでしょ? その作品を体験して、「身体性と精神性」みたいなものをつなげられるような何かができるんじゃないかと思ったんだよね。それで、「あ、ちょっと話してみたい」って、引き合わせてもらった。
―松山さんは驚かれたんじゃないですか? いきなりBRAHMANのTOSHI-LOWさんに「話してみたい」と言われて。
松山:そうですね(笑)。驚きはしましたけど、ぼくももともとバンドマンで、ずっとギターを弾いていたんです。ジャンル的にはメタルだったんですけど、BRAHMANのことはもちろん知っていて。
BRAHMANって、世界観がすごく強いバンドじゃないですか。だから単純にステージを派手にするためのライブ演出ではなく、その世界観にさらに奥行きをつけるようなコラボレーションができたら面白いだろうなって、話を聞いてすぐに思いました。
同じものはつくれない。テクノロジーの力でいま起こっている「ライブ」を拡張させる
―ライブ演出の方法については、具体的にどんな打ち合わせをされていったのでしょう?
松山:最初にお会いしたときから目指したいニュアンスは見えていたところがあって。やっぱり「生感」ですよね。その瞬間にしかできないことをやる。それがまさにライブというものだから、テクノロジーの力でそれを拡張できないかっていうのは、スッと頭に入ってきました。
TOSHI-LOW:うん、そうだね。
松山:さっきTOSHI-LOWさんが言っていた、フェスとかにある大きなビジョンの話もお会いしたときにされていて。あの画面に、演者の表情をカメラで抜いたものが映し出されたりするけど、それはライブの「生感」を拡張するものではないよねって。
TOSHI-LOW:そうなんだよね。「拡張する」っていうのと「演者をアップで撮る」っていうのは、やっぱり全然違うことな気がしていて。あの大画面は、昭和のテレビがでっかくなったものと同じというか。そんな違和感をずっと感じていて、どこかで変えたいなって思っていたんだよね。

TOSHI-LOW:いままでは、俺が客のなかに飛び込んでみたり、肉体と肉体がぶつかることで何かを得ようとしたりしていたんだけど、そうじゃないとらえ方があるんじゃないかと。そんなことを考えていたらコロナになって、いままでのやり方が全部封じられてしまった。だから俺としては、自分たちのライブに関してもう一度考え直す、またとない機会でもあったんだよね。
―実際に松山さんのチームが演出したライブ映像を見せていただきました。インテル® Core™プロセッサー・ファミリー Hシリーズ搭載PCでつくられたそうで、BRAHMANのメンバーが動くとそれに連動して映像も動いていましたが、どういった演出だったのでしょうか。
松山:あれはTOSHI-LOWさんたちの動きをセンサーで感知しながら、リアルタイムで映像を生成しているんですけど、じつはモーションだけではなく、同時にバンドサウンドをもらっていて。それをリアルタイムで解析しながら、映像にエフェクトをかけているんです。そうすることで、音と映像の一体感をつくっています。ぼくがインテルのクリエイター支援プロジェクトにクリエイターとして参加しており、そのプロジェクトから最新PCを提供いただき実現できました。
TOSHI-LOW:事前につくり込んだ映像を画面に映しているのではなく、その場の動きと音に合わせてつくられているんだよね。そのとき出している音の長さも、リアルタイムで映像に反映されていて。だから現場で見ていると、実際の演奏と動き、そしてエフェクトのかかった映像がビッタシ合っている。
―なるほど。エフェクトのかかった映像が、リアルタイムで生成されているところがポイントなんですね。
松山:そうですね。「生成する」という意味で、ぼくらは「ジェネレーティブなビジュアル」と呼んでいます。ぼくとしてはライブの演出をつくっているという意識はあまりなくて、「状況」をつくるための仕組みをつくっている、というイメージで。その「状況」が、その瞬間にどうなるかは、BRAHMANのパフォーマンス次第です。同じものは2回つくれません。
新たな挑戦をし続けるクリエイターを支援するインテル®のプロジェクト「インテル® Blue Carpet Project」の一環として、11月1日にリアルタイムCG・インタラクティブシステムを用いたライブ演出についてセミナーを実施。インテル®Core™プロセッサー・ファミリー Hシリーズ搭載PCを使用し松山が手がけた、BRAHMANのライブ演出を実際に見ながら、TOSHI-LOWとのトークセッションも行なわれた
テクノロジーは手段にすぎない。大事なことはお客さんにどんな体験を提供できるか
―お話を聞いていると、松山さんがライブ演出で行なわれていることは、「映像」という言葉だけでは表現しづらいような気がます。
松山:前にTOSHI-LOWさんにも話したんですけど、プロジェクターとかLEDビジョンに投影しているものって、どんなに凝っていても「映像じゃん」ってみんな言うんです。でも、エレキギターをマーシャルのアンプにつないでガーンってかき鳴らしているものを「音じゃん」って、みんな言わないじゃないですか。スピーカーから音圧がバーンときて、エレキギターの音が出ているときとそうじゃないときの生音は全然違う。
ぼくたちがやろうとしているのは、アンプでギターの音を増幅するように映像を増幅する仕組みを使って、ライブの迫力だったり臨場感だったりっていう目に見えないものを、視覚的な情報として受け取れるようにしている。そういう考え方です。

―そのアプローチ自体が、すごくユニークですね。
松山:そうですね。そもそもテクノロジーというのは、無色透明なものだと思っていて。テクノロジーが何かとかけ合わさることではじめて色がつき、新しい体験や見たことのないものがつくれる。お客さんがその場で何を体感できるのかがいちばん大事であって、テクノロジーはあくまでも、その場の気迫や感覚をお客さんに伝えるための方法のひとつだと思っているんですよね。
―なるほど。BRAHMANが松山さんと一緒にやっている理由が、だんだんわかってきました。
TOSHI-LOW:そう。だから、テクノロジーを使ったライブ演出といっても、いわゆるデジタルマジックみたいな見た人を驚かせるようなことをやりたいわけではなくて。やっぱり俺たちは、血が通っているものをやりたいんだよね。身体性のあるものというか。
それは、音に関してはもちろんそうだし、映像に関してもそう。周平たちとは表現の手段が違うんだけど、生身のものがないと成り立たないことをどっちもやっている。その部分でちゃんと共通認識がある。
次に表現したいのは、グルーヴ感。リアルタイムで実感した「のってきた瞬間」を演出に
―これまで何度か松山さんのチームがライブ演出を手がけているとのことですが、手応えは感じていますか?
TOSHI-LOW:いろいろ試行錯誤はあったけど、回を重ねるごとにどんどんよくなってきている。まだまだ見てみたいし、一緒にやってみたいよね。
もちろん、俺たちは何百人のライブハウスでやるようなバンドであって、そもそも映像を映すシステムがない場所も多い。だから毎回っていうわけにはいかないんだけど、大きい会場でやる機会があったときに、ひとつの切り札として、周平たちのチームがいてくれるっていうのはすごく心強いし、期待もある。
―松山さんはいかがですか?
松山:前回のライブでは舞台袖にいてリアルタイムで操作をしたんですけど、あのときは、ぼくらもライブをしているような感覚を味わいました。
アリーナがうわーって盛り上がるのが見えて、「のってきた瞬間」みたいなものを感じられたんです。一緒にやれているというか、この空気をつくることに参加できている、という実感があって。あらかじめ決まりきった音楽や舞台をするのとは違う、ロックのライブならではの感じでした。空気が張り詰めるとか、全体が止まって見えるとか、そういう瞬間って本当にある。
次にやるときは、そういうグルーヴを映像でも出せないかなって思っています。
TOSHI-LOW:いいね、それ。

テクノロジーで仕組みをつくり、BRAHMANの色を乗せていく。その先に待つ体験を考える
―ライブ演出における今後のアイデアって、何か考えていますか?
TOSHI-LOW:いままでは既存の曲に合わせてつくってもらっていたので、今度はイチから生み出したもので一緒につくりたいよね。こういう曲だったら、周平たちはどういうエフェクトをかけてくるんだろうって。そういうことを考えながら、新しい曲をつくってみようかなって思っている。
―松山さんの演出を見ると、またそこからいろいろ楽曲のイメージが広がりそうで、ある意味、理想的なコラボレーションですね。
TOSHI-LOW:そう。いままでまったく関係ない世界だと思っていたものが、こうやって身近になった。自分のなかのアイデアの扉がひとつ開かれた感じ。

―松山さんのほうで考えていることはありますか?
松山:バンドの持つイメージをもっと深堀りして、それを可視化するようなビジュアルって何だろうって、次の機会に向けてリサーチを進めています。
BRAHMANのイメージって、ちょっとスピリチュアルっぽい感じがあるじゃないですか。BRAHMANというワード自体ヒンドゥー教からきているものだし。ただ、中身がそうかっていったら、全然そうではない。
TOSHI-LOW:そういうところをちゃんとわかってくれているところが、いい(笑)。BRAHMANと何かをやろうっていうと、「梵字を使いました」みたいなのばっか出てくるんだけど、別に何かの信者なわけでもないし、そもそもバンド名なんて何でもいいみたいなところから始まっているから。

松山:ぼくの理解としては、スピリチュアルに見えちゃうぐらいパワフルだっていうことなんですよね。スピリチュアルだったり、宗教だったり、あるいは地域性とか時代性とか、そういう要素が入っているわけではないのに、BRAHMANのライブではスピリチュアルな神聖さや力強さを感じてしまう。
それを可視化できるような仕組みをぼくらが用意して、そこにBRAHMANの色を乗せていったら、どういう体験になるんだろうって考えています。
バンドのかたちは変わらないし、変えるつもりもない。自分たちのまま新しい景色が見たい
―最後に、テクノロジーが加わることで音楽ライブはどのように変わっていくと思いますか?
松山:ぼくはエレキギターができる前と後みたいに思っていて。エレキギターもテクノロジーの賜物というか、当時の最先端技術だったわけですよね。それこそ、エレキギターがなかったら、いまのように大きい会場ではライブができなかったわけで。音楽のあり方そのものが、技術によって大きく変わった。テクノロジーが発展することによって音楽のあり方や表現が変わっていくことは、もうずっと昔からあると思うんです。
―たしかに。
松山:なので、ぼくらがいまリアルタイムエフェクトとか最新の技術を使うのは、新しくてすごいから使うのではなく、それによって「いま」を切り取ることができるからなんです。BRAHMANの「いま」を切り取って、テクノロジーとかけ合わせていったら、どうなるんだろうっていう。

―「いま」を切り取って、それを存分に感じるツールとしてテクノロジーがあるんですね。
TOSHI-LOW:長いことBRAHMANというバンドをやってきて、昔はいつ終わってもいいというか、刹那的に生きていた。もちろんその気持ちはいまもなくなってはいないんだけど、せっかく周平たちとやれる時代にいるんだから、素直に意見を聞いていきたい。一緒にやれる喜びをすごく感じている。
これをやっちゃいけないとか、あれをやっちゃいけないなんて、基本的にないと思うし……かといって、俺たちがバンドに打ち込みの音を入れるかっていったら、入れないと思う。自分たちがやっているもののまま、何かになりたい。ロケットに乗りたいわけではなくて、自分たちのまま空を飛びたい、みたいな。
―なるほど。すごくよくわかります。
TOSHI-LOW:バンドのかたちは変わらないし、変えるつもりもない。ライブ中にコンピューターのボタンを押して何かをするわけではなく、いままでのようにグワーッて肉体的なライブをやっているまま、そこに新しい何かが乗ることによって、新しい景色を見たい。それが、俺にとってのテクノロジーなんだよね。

- 商品情報
-
 Intel Blue Carpet Project
Intel Blue Carpet Project
松山周平氏がBRAHMANのライブ演出で使用したインテル® Core™ プロセッサー・Hシリーズ搭載PC。クリエイティブ制作に必要な圧倒的な性能と、どこにでも持ち運ぶことのできるモビリティとを兼ね備えている。
- イベント情報
-
 インテル® Blue Carpet Project
インテル® Blue Carpet Project
さまざまなプラットフォーム、さまざまな創作ジャンルで優れた作品を生み出し、新たな挑戦をし続けるクリエイターを支援するプロジェクト。
11月1日にはこのプロジェクトの一環として、TOSHI-LOW(BRAHMAN)とビジュアルアーティストの松山周平(THINK AND SENSE)による『BRAHMANライブ演出セミナー』が開催された。
- プロフィール
-
- TOSHI-LOW (としろう)
-
BRAHMANのボーカリストであり、OAUのギター・ボーカル。1995年にBRAHMANを結成。全国のライブハウスを中心に活動し、幕張メッセでのセンターステージライブも開催。2018年2月には日本武道館で単独公演を行なう。コロナ禍で敢行した「Tour 2021 -Slow Dance-」はスローな楽曲を中心に構成、紗幕や映像を用いた演出が話題となった。その続編となる「Tour - slow DANCE HALL -」では初のホールツアーを行なった。
- 松山周平 (まつやま しゅうへい)
-
株式会社ティーアンドエス取締役 THINK AND SENSE 部 部長 プログラマー・ヴィジュアルアーティスト。先端技術を活かした広告展示やインタラクティブなパフォーマンスを得意とする。オーディオビジュアル作品、インタラクティブなインスタレーション、など多岐に渡る活動を行っている。著書に『Visual Thinking with TouchDesigner』がある。インテルのクリエイター支援プロジェクト「インテル® Blue Carpet Club」参加クリエイター。
- フィードバック 13
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-