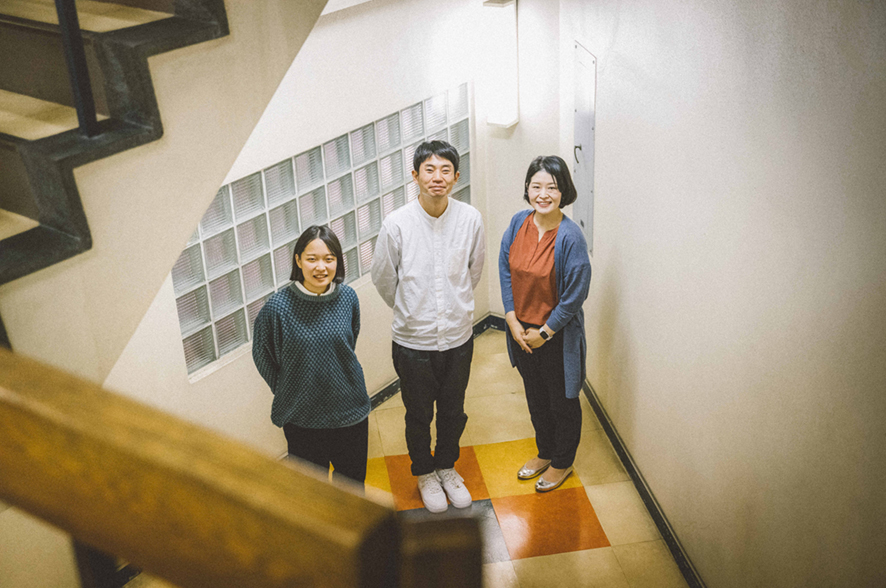演劇の醍醐味はその「ライブ性」にあるといえる。その場所、その時間だけで行なわれる生身の表現。同じ演目であっても、同じ舞台は二度と行なわれない。しかし、演劇の価値は本当にそれだけだろうか? 舞台上の役者の姿を見ることができない、声を聞くことができない、劇場に足を運ぶことができない人たちに、同じ「ライブ性」を伝えることは不可能なのだろうか?
コロナ禍で人々は、コンサートや演劇に足を運べなくなり、ライブを味わうことが困難な経験をした。代わりにたくさんの配信映像が生まれ、さまざまな言語の字幕とともに世界中を飛び交った。日本では、多言語翻訳やバリアフリー日本語字幕、音声ガイドなどに対応した映像作品配信プラットフォーム「THEATRE for ALL」が誕生。見たことのない舞台、知らなかった劇団に出合うきっかけは増えた。それは「ライブ性」がひとつの価値となる演劇へのアクセシビリティーを高める第一歩となったはずだ。「多様性」という言葉を誰もが耳にするようになったいま、あらためて「多様な人が楽しめる演劇」について考えたい。
そのために今回、2023年1月に「THEATRE for ALL」と「EPAD」との連動企画で瀬戸内国際芸術祭2022 ドキュメンタリー『7日間のままごと』を配信する劇団「ままごと」主宰の柴幸男、その柴が手がけた戯曲『反復かつ連続』を20代有志で上演し字幕作成を担当した大学院生の松橋百葉、聞こえない演劇ファンとして観劇記録や観劇のアクセシビリティーについて発信している山崎有紀子の3名に、それぞれの視点から多様な社会における演劇の可能性について語ってもらった。
「演劇とそれを映像にした作品はまったく別物」。多様な人に届けるための舞台とは
─ここ数年で、舞台芸術のアクセシビリティーやバリアフリーについて、話題にのぼることやサポートを実施する公演が増えました。柴さんはご自身の取り組みや考え方に変化はありますか?
柴幸男(以下、柴):すごく率直に言ってしまうと、アクセシビリティーやバリアフリーというものに対する自分自身の意識は、かなり低かったんです。どちらかというとぼくではなく劇団員たちが、劇場に足を運びづらいお客さまについての提案を積極的にしてくれました。たとえば公演のなかで乳幼児も入場できる回を設けたいとか、YouTubeに作品をアップロードするときにできるだけ多くの言語で字幕をつけたいというアイデアを話してくれて、ぼくはそれになんとか追いついて実現させていっています。
自分自身はつくっている演劇作品までしか頭が働かなくて、なかなかお客さまのことまで考えきれていないのが、本当に申し訳ないんですけれども、正直なところです。

柴幸男(しば ゆきお)
劇作家・演出家、「ままごと」主宰。2010年に『わが星』で『第54回岸田國士戯曲賞』を受賞。東京の劇場から北九州の船上まで、新劇から北海道の小学生との学芸会まで、場所や形態にとらわれない演劇活動を行なう
─松橋さんは、柴さんの戯曲『反復かつ連続』を20代の有志で上演して配信したときにバリアフリー字幕をつけたそうですね。そのきっかけや、実際に取り組んでみて感じたことを聞かせていただけますか。
松橋百葉(以下、松橋):もともと私は演出家ではなく、配信技術の担当として、知り合いに誘ってもらって『反復かつ連続』を上演するチームに入ったんです。コロナ禍で劇場を借りたり稽古をすることができなかったので、長期的に使える稽古場と劇場を探した結果、たまたま家を貸してくださる方がいました。その方はろう(聴覚障がいがあり、手話を第一言語とする人のこと)の小学校と幼稚部の先生をされていたことがあり、お話を聞いたり、元生徒さんにも作品を見ていただきたいなという思いもあって、バリアフリー字幕に挑戦してみようと。

松橋百葉(まつはし ももは)
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程 在学中。2020年春より配信演劇に興味を持ち、現在は演劇の配信上演における身体について研究を行なう。また、メディアアートやエンジニアとしてのバックグラウンドから、メディアやテクノロジーへの洞察をもとにオンライン演劇の脚本執筆や演出、技術開発を行なう
松橋:実際にやってみると、「これは、できるな」というのが率直な感想でした。ただそれは「配信でなら」という条件ではあります。PowerPointなどで脚本をもとに字幕データをつくって、画面に文字をかぶせていく作業自体はそんなに難しくはない。あとは演出家といかに話し合いながら作品に合ったニュアンスを模索していくか、という作業でした。
柴:字幕つきの配信を見ましたが、ぼくが劇団でやったものと似ていました。ぼく自身もコロナ禍で同じく『反復かつ連続』の配信公演をして、後にそれをアーカイブとして世に出すときに字幕をつけたんです。そのため、最初から字幕をつけることを考えている作品ではない。その点では、あらかじめ字幕を意識してつくられた松橋さんたちの『反復かつ連続』のほうが、字幕が練られていて見やすかったんじゃないでしょうか。
『反復かつ連続』配信公演のアーカイブ
柴:やっぱり字幕をつける前提だと演出も違ってきますよね。たとえばぼくらも海外公演などで字幕をつける場合は「ここはセリフが先で、字幕を意図的に遅らせよう」ということがありました。字幕も舞台上で起こること、という認識なんです。
そもそもぼくは、演劇とそれを映像にした作品はまったく別物だと考えています。舞台の演出と、字幕やカット割りなどの映像における演出は、まったく違う職能だと認識している。ぼくは演出をするので、多様な人に作品を楽しんでもらうために舞台ではどうできるかを考えていきたいです。
サポートを求める人の声、多様な人の声がつくり手に届くには
─山崎さんはアクセシビリティーやバリアフリーについての変化や影響をどう感じていますか?
山崎有紀子(以下、山崎):私の周りの状況をお伝えすると、ここ数年で公立劇場や中小規模の劇団を中心に、字幕をつける作品が増えてきています。ほかにも、手話通訳がつく舞台も少しずつ上演されるようになりました。私がよく行く劇場では東京芸術劇場や新国立劇場が演劇に字幕をつけて上演しています。あとは商業演劇ですね。たとえば宝塚歌劇団や帝国劇場で最近行なわれるようになったのが、画面から光が出ないように加工をしたタブレットで台本を読むことができるサービスです。
これらの鑑賞サポートは大きな一歩だと思いますが、サポートの質を高めるということが今後の大きな課題だと思います。

山崎有紀子(やまさき ゆきこ)
舞台『マンマ・ミーア!』との出合いをきっかけに舞台ファンに。2012年にバリアフリー字幕がついた作品を観劇、その後は鑑賞サポートを利用して小劇場から大劇場までさまざまな作品の観劇を重ねる。聴覚障がいのある宝塚歌劇ファンのグループを立ち上げ、現在約70名の参加者がいる。また、聞こえない演劇ファンとして、その観劇体験をブログやSNSで発信している
山崎:鑑賞サポートがつく舞台は少しずつ増えていますが、私が見たいと思った演劇のうち見ることができる作品は、一割あるかないかという状況です。やっぱり見たい舞台には「サポートをつけてください」と要望をして見に行くことになりますね。もちろん、サポートを要望してもそれが通るときもあれば断られてしまうときもあります。断られても何度もかけ合い、何らかの方法を検討していただいて、最終的には見に行くことができています。ただやはりこの「要望すること」そのものにも壁があります。セリフの内容がわかればもっと楽しいけれども「たぶん無理だろうな」と諦めている人もたくさんいます。
しかしまずは、本当に小さなことからでも始めていただけたら嬉しいです。たとえば劇団で台本の貸し出しを鑑賞サポートとして実施するといったような。それが舞台のチラシやサイトに書かれていると「ここは聞こえない人が見に行くことを想定してるんだな、嬉しいな」と感じます。
数年前、イギリスの劇団「ロイヤル・シェイクスピア・カンパニー」の来日公演でチラシに載っていた写真に感動しました。聞こえない役者や車椅子ユーザーの役者がほかの役者と並んで写っていたんです。「なんて多様性のある舞台なんだろう」と思いました。おそらく理想はそういうところにあるんだろうなと思いつつ、日本ではまだまだ距離があるのが現状です。費用の問題や、人手不足、著作権の問題などもあります。
それらについては、たとえば費用面では鑑賞サポートに特化した助成金が増えたり、スタッフさんの人手不足には鑑賞サポートを行なう企業が外部からサポートすることが当たり前になっていくといいですね。著作権の問題も、著作物を鑑賞サポートにスムーズに利用できるような制度づくりが必要だと思います。少しずつ少しずつ理解していただき、聞こえない人が観劇に来ることを最初から想定している劇団や劇場が増えてほしいと願っています。
松橋:バリアフリー字幕に興味を持ったときに山崎さんの観劇のブログやTwitterを拝見して衝撃的でした。「やっぱり耳が聞こえない人の体験は、私がいまここで耳を塞いだとしても違うものだ」と思ったんです。しかも、耳が聞こえないといっても人によってまったく様子が違うし、国籍によってもジェンダーによっても観劇の体験は違うんだと感じて、皆さんの言葉をすごく聞きたいと思いました。
柴:ぼくも今回の取材をきっかけにブログを拝読して、すごく面白かったし、新鮮に受け取りました。

山崎:ありがとうございます。読んでくださっていて嬉しい気持ちでいっぱいです。私がブログを書こうと思ったきっかけは、ある劇団に鑑賞サポートとして「タブレットで字幕を読ませてもらえないか」とお願いをしたときに、「周りの観客から怪しまれるのではないか、理解されにくいんじゃないか」と劇団の方から言われて。それならば聞こえない観客がどうやって舞台を見ているのかを知ってもらおうと思って書き始めました。
─やはり鑑賞サポートを利用する方の声が、つくり手にはなかなか届かないという現状はあると思います。
松橋:私たちの作品を配信したあとにアンケートをとったのですが、聞こえない方以外からも「字幕があってすごく見やすくわかりやすかった」という反応がありました。そもそも障害者手帳を持っていなくても、ご年配だったり、音声が聞き取りにくい鑑賞環境だったり、さまざまな聞こえづらい状況があるのだということに気づかされました。
柴:お客さまが実際にどう感じているのかを想像するのは非常に難しい、というのはすごく弱点ですね。いつも稽古場では、客観的な立場になってみて「見ていてどう思うか」「なにをキャッチしているか」を話し合います。ただ、どうしても自分自身の身体が変わったり衰えたり変化しない限り、自分以外のお客さまのことを想像しづらい。
社会あるいは世界には多様な人たちがいるのに、創作の現場はそれほど多様でない。それは数年前からとても気になっています。おそらく、いろんなハンディキャップがある方と一緒につくることができれば私自身の感覚をもっと広げられるし、そうしなければいけないなと考えています。
多様なはずの社会のために。大事なのは、誰とつくり、誰に見せるのか
─柴さんがおっしゃるように、ハンディキャップに限らず「いろんな方と一緒につくる」ということは、これまでさまざまな地域のなかで創作をしていることにも通じるのではないでしょうか。たとえば瀬戸内海の小豆島で長く活動されてきて、そこに暮らす人に見てもらう芝居をつくっていますが、そういったときはどんなことを意識していますか?
柴:まずきっかけのお話からすると、あるとき、ろうの方と耳が聞こえる方とが一緒にやっている人形劇の上演をろう学校で観劇させていただいたんです。最初の感想は「ぼくが普段つくっている演劇とそんなに変わらないんだ」というものでした。太鼓の音は耳が聞こえなくても空気の振動で伝わるんだとわかりましたし、手話での拍手(耳の横で両手をひらひらさせる)について「良い拍手だな」と感じたことを覚えています。きっと小さな感覚の共有が大事なんじゃないか、と思ったんです。それが「自分や作品や劇場の環境を変えるには、さまざまな人と創作をともにすることが一番の王道なんじゃないか」と思うようになったきっかけですね。

柴:去年は瀬戸内海の豊島(てしま)で『反復かつ連続』を上演しました。とくに豊島に住む人たちに見てもらいたかったので、実際に豊島に住む方にも出演していただきました。大事にしたのは、その方ができることをすること、そして、居やすい所作になるようにすべてを演出することですね。あるシーンでただ椅子に座るのか、それとも正座するのかを、ご本人と一緒に話し合いながらつくっていく。もともと一人芝居用の作品なのですが、劇団員と豊島に住む人たちによって、一人芝居ではできないようなとても良い作品になりました。
─「どこで」「誰と」「誰に向けて」「なにを」見せるのかというのは、ライブパフォーマンスの根本的なことでもありますね。しかし近年のコロナ禍ではオンライン配信が増え、「ライブであることはどういうことか」も問い直されています。松橋さんは演劇活動期間の多くがコロナ禍だったと思いますが、演劇とはなにか、誰に見せるかについてどう考えていますか?
松橋:私が演劇を始めたのは大学のサークルで、4年生のときにコロナ禍になりました。まず直面したのが、新入生歓迎会ができなくて1年生が入らずにサークルが継続できなくなる、ということ。だったらオンライン演劇をやろうと持ち掛けると、「演劇を映像で配信するのか」とサークルのなかで大議論になったんです。配信をやりたい人もいれば、絶対にお客さんの前でやりたいという人もいて、たくさん話し合いました。そんななかで私にもなにかできることはないかと考えて、専攻がメディアアートだったこともあり「演劇をなんとかして残し、上演まで持っていくことをしよう」と配信の支援もしてきました。

松橋:それから3年が経って、対面でのお話も、劇場での公演もできるようになりました。でもいまも「あのときにやっていたことを潰したくない」という思いがあります。バリアフリー字幕に挑戦したことや、演劇や配信や上演について起きたいろんなことをぜんぶ忘れてしまうのが嫌で、それらを残したい。なんとか演劇の上演というかたちにできないかと模索しているところです。
─舞台の映像配信が身近になったことで、「アーカイブすることの是非」もよく議論されました。また、遠く離れているということも劇場に集まりづらいバリアであり、コロナ禍では多くの人が離れた人への作品の届け方を模索しました。それらは柴さんが豊島での創作についてのドキュメンタリー映像をつくったことにも繋がるのではないでしょうか?
柴:コロナ禍で配信を行なったことは、より一層、誰とどこでつくるかをよく考えなければいけないと思うきっかけになりました。ただぼくは、映像の演出についてはイメージの外側だと話しましたが、アーカイブする、記録を残すことはとても大事だと考えています。だから劇団の制作から「豊島での公演をドキュメンタリーとして残そう」という提案を受けて、良い方法だなと思いました。
先ほど言ったとおり、ぼくはいま、どんな人たちとどのようにどんなやり方で演劇をつくるか、また作中や創作環境での居心地の良さや創作環境をとても重要視しています。それは劇場で観劇してもらえれば感じ取ってもらえると思っています。でも、映像でその演劇を残したとしても、見る人に伝わるかは自信がないんですよね。もし映像で残すのであれば、作品そのものよりも、自分が大事にしている「誰とどういうふうにつくっていったか」を残すべきなんじゃないか。だから作品の映像ではなくドキュメンタリーというのは、ぼくや劇団ままごとの演劇のアーカイブとしてはストレートな方法だと認識しています。
「これまでも集まりづらかった人はいた」と気づいた。コロナ禍でのアクセシビリティーの変化
─舞台芸術に関するさまざまな映像化がコロナ禍で加速し、劇場に行かずとも、知らなかった演劇や劇団にアクセスできる入り口も増えているのではないでしょうか。山崎さんは観客の立場から、昨今の舞台の映像化についてどう感じていますか?
山崎:いち演劇ファンとしては、家で舞台作品が見られることは嬉しくもありました。一方で、字幕がなければ配信があっても見ることはできません。THATRE for ALLさんのように必ず字幕や音声ガイド、ときには手話がつけられていると、本当に安心してスムーズに見ることができる。コロナ禍でそういうサイトが生まれたのは嬉しいことでした。映像配信だと、表情が見みやすくていいなとか、口の形が読みやすいなというメリットもありました。

山崎:もちろん実際に配信を見ていると、柴さんがおっしゃる「生の舞台と映像は別物」だとよくわかります。やはり同じ場に役者さんと私がいるという空気感は、生の舞台のかけがえのなさですね。ほかの観客と一緒に笑ったり泣いたり、最後は拍手を送り「素敵な作品を見ることができて良かったな」と同じ空間で感情の共有ができるのは、やはり生の舞台ならではだなと。ただ、どちらを楽しむのも鑑賞サポートがあってこそ、です。
柴:演劇の大事な要素は「生」だとよく言われますよね。でも、配信だって生だとも言える。「生」とは存在している時間が同じだということですが、じつはそれは演劇にとってそれほど強い要素ではない。おそらく、もっと大事なのはひとつの空間に集まっていることで、それが演劇の醍醐味だったんじゃないかなとコロナ禍で痛感しました。
あのとき、多くの人が同じ空間に集まれなくなった。ただきっとぼくが認知していなかっただけで、集まりづらかった人や、劇場に来ることに障壁があると感じていた人たちはずっといたはずなんです。自分自身が簡単に空間をともにできず、移動できず、集まれず、話し合えないことを体験してようやくそれがわかった。また集まれるようになっても集まりづらい人たちはまだまだいるんだということはずっと考えていかなきゃいけないと、劇団員たちと話したことをよく覚えています。
─今後としては、演劇で目指す方向にどんな可能性が考えられますか?
松橋:これまでの演劇は「いま」「ここ」でした。でもオンライン配信が出てきたときに「いま」「ここ」ではないものも「演劇」と呼ばれましたよね。たぶんこれまでの演劇とオンライン配信が出てきたあとの演劇、または映像と演劇のあいだに、いろんなパターンがあると思うんです。たとえば劇場のそばに集まって集団で配信を見る、という可能性もありうる。アーカイブをなんらかのかたちで演劇作品として成立させる形態はないだろうかと、ずっと考えています。
柴:ぼくは、基本は誰とでも演劇をつくれると考えているんですね。なので、ここ数年は広く出演者を公募して作品をつくっています。けれどもそこで国籍の広がりや、障がいのある方の応募はあまりなかった。それはきっとぼくたちの求め方や行動範囲が狭くて、その人たちまで情報が届いていないのだと思います。いままでのように待っていてもきっと出会えない。自分自身が動いていく必要があるんだろうなと、最近よく考えています。
余談ですが、いまこのインタビューで使っているUDトークアプリもとても便利ですね。

取材は音声認識アプリ「UDトーク」を利用し、プロの文字支援をつけて実施された。また、手話通訳士も同席した
柴:いまはこういう手段があるんだなと驚くことが増えました。それを知ったときに「そういう人がいるよね」じゃなくて、「自分も助けられるときがあるかも」と思えたり、自分の生活と地続きのものとしてとらえることで変化が起きたりするんだよなと、よく思っています。

- 作品情報
-
 ままごと 瀬戸内国際芸術祭2022 ドキュメンタリー
ままごと 瀬戸内国際芸術祭2022 ドキュメンタリー
『7日間のままごと』
2023年1月27日配信開始
監督:清原惟
メイン画像撮影:瀧澤日以(PHABLIC×KAZUI)
- 配信情報
-
 「THEATRE for ALL」では、2022年12月から2023年1月にかけて、演劇やダンス作品の映像をデジタルアーカイブしている「EPAD」から5つの作品の配信を開始する。 「EPAD」と「THEATRE for ALL」は、ともに新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて誕生したプロジェクト。演劇やダンスの公演、音楽のライブが次々と中止を余儀なくされ、いつ活動が再開できるかわからなかった時期に、新たな取り組みとして「EPAD」は配信・アーカイブ事業を、「THEATRE for ALL」はバリアフリーなオンライン劇場として配信サービス事業を開始した。それぞれのノウハウを生かしながら、舞台芸術界の価値ある財産を守り検証し、またこれまで舞台芸術の魅力を届けられなかった人に舞台映像を通してアプローチしている。 「EPAD」の2022年度事業は、文化庁令和3年度補正予算 文化芸術振興費補助金 統括団体によるアートキャラバン事業(コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業)である。
「THEATRE for ALL」では、2022年12月から2023年1月にかけて、演劇やダンス作品の映像をデジタルアーカイブしている「EPAD」から5つの作品の配信を開始する。 「EPAD」と「THEATRE for ALL」は、ともに新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて誕生したプロジェクト。演劇やダンスの公演、音楽のライブが次々と中止を余儀なくされ、いつ活動が再開できるかわからなかった時期に、新たな取り組みとして「EPAD」は配信・アーカイブ事業を、「THEATRE for ALL」はバリアフリーなオンライン劇場として配信サービス事業を開始した。それぞれのノウハウを生かしながら、舞台芸術界の価値ある財産を守り検証し、またこれまで舞台芸術の魅力を届けられなかった人に舞台映像を通してアプローチしている。 「EPAD」の2022年度事業は、文化庁令和3年度補正予算 文化芸術振興費補助金 統括団体によるアートキャラバン事業(コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業)である。
- プロフィール
-
- 柴幸男 (しば ゆきお)
-
劇作家・演出家、「ままごと」主宰。2010年に『わが星』で『第54回岸田國士戯曲賞』を受賞。東京の劇場から北九州の船上まで、新劇から北海道の小学生との学芸会まで、場所や形態にとらわれない演劇活動を行なう。
- 松橋百葉 (まつはし ももは)
-
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程 在学中。2020年春より配信演劇に興味を持ち、現在は演劇の配信上演における身体について研究を行なう。また、メディアアートやエンジニアとしてのバックグラウンドから、メディアやテクノロジーへの洞察をもとにオンライン演劇の脚本執筆や演出、技術開発を行なう。
- 山崎有紀子 (やまさき ゆきこ)
-
舞台『マンマ・ミーア!』との出合いをきっかけに舞台ファンに。2012年にバリアフリー字幕がついた作品を観劇、その後は鑑賞サポートを利用して小劇場から大劇場までさまざまな作品の観劇を重ねる。聴覚障がいのある宝塚歌劇ファンのグループを立ち上げ、現在約70名の参加者がいる。また、聞こえない演劇ファンとして、その観劇体験をブログやSNSで発信している。
- フィードバック 19
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-