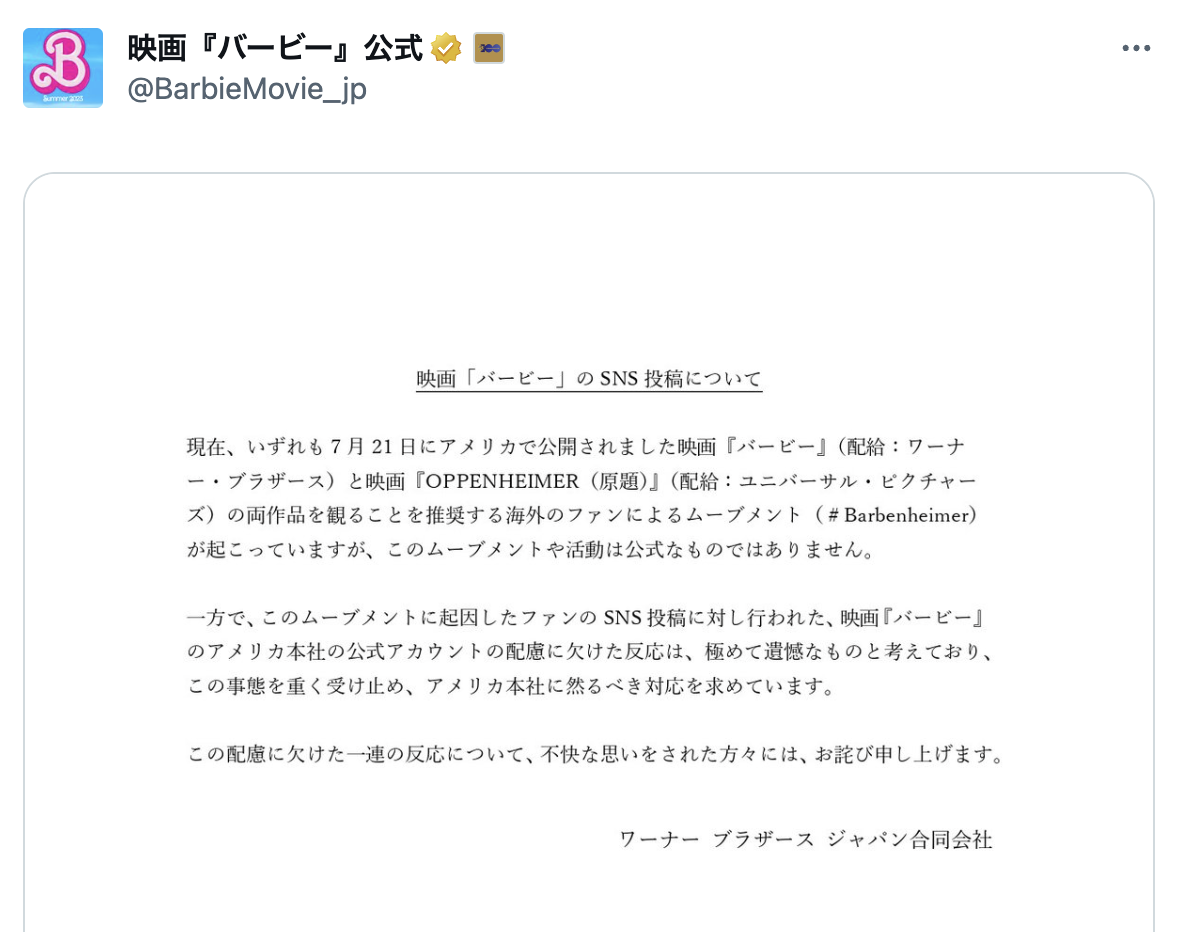「世界で一番有名なファッションドール」を実写映画化した『バービー』が、8月11日に日本公開を迎えた。プロデューサーで主演のマーゴット・ロビーと、監督のグレタ・ガーウィグがタッグを組んで完成させた唯一無二の「バービー映画」は、7月末にアメリカで公開されると、2023年公開の作品のなか中で週末オープニング記録第1位、累計の興行収入でも第2位に(8月6日時点)。単独の女性監督の作品として歴代最高の興行収入となるなど、さまざまな記録を打ち立てている。
本作は、玩具メーカーからIPビジネスへの移行を図るマテル社による、自社商品をもとにした映画作品の第1弾でもある。これまで『レディ・バード』(2017年)、『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』(2019年)といった監督作や、共同脚本・主演を務めた『フランシス・ハ』(2012年)などで、さまざまな女性の生き方と内面を描き出してきたグレタ・ガーウィグは、「バービー」という誰もが知るグローバルブランドにどのように向き合ったのだろうか? 来日した監督に話を聞いた。

グレタ・ガーウィグ
米『アカデミー賞』ノミネート経験をもつ監督であり脚本家でもある。ノア・バームバックとともに本作の脚本を書き、監督する以前に、『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』(2019)を監督。シアーシャ・ローナン、ティモシー・シャラメ、フローレンス・ピューが出演したこの作品は、米『アカデミー賞』6部門、英『アカデミー(BAFTA)賞』5部門、『全米製作者組合(PGA)賞』、『全米脚本家組合(WGA)賞』にノミネートされた。監督デビュー作『レディ・バード』(2017)は、自身の最優秀監督賞と最優秀オリジナル脚本賞を含め、米『アカデミー賞』5部門にノミネートされた。
多作の俳優でもある。ノア・バームバックと脚本を書き、出演もした『フランシス・ハ』(2012)の演技で、『ゴールデングローブ賞』にノミネートされた。2022年、バームバックが監督した最新作『ホワイト・ノイズ』に出演し、アダム・ドライバーと共演。そのほか、俳優としての出演作品には、『ダムゼル・イン・ディストレス バイオレットの青春セラピー』(2011・未)、『29歳からの恋とセックス』(2012・未)、『マギーズ・プラン 幸せのあとしまつ』(2015)、『ミストレス・アメリカ』(2015・未)、『ジャッキー/ファーストレディ 最後の使命』『20センチュリー・ウーマン』(共に2016)などがある。
※本記事には映画『バービー』本編の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承ください。
女性のエンパワメント? フェミニズムを後退させた? バービーの持つ複雑さ
『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』に続いて、多くの人の子どもの頃の思い出と結びつくモチーフに取り組んだガーウィグは、60年以上の歴史を持つ「バービー」という題材について、「まだ伝えるべき物語があるキャラクター」だと感じたのだという。「バービーの伝説を称えながら、予想外の新しい切り口で彼女の物語を掘り下げ、新鮮で活き活きとした現代に合ったバービーを描けると思った」(プロダクションノートより)と述べている。
映画『バービー』は、バービーたちが暮らす、すべてが人工的でピンク色の「バービーランド」と、人間が暮らす「リアルワールド」の2つの世界が舞台となる。バービーランドでは、大統領も医者も『ノーベル賞』受賞者もみんなバービーで、バービーたちが世界を回している。今日も明日もハッピーで、そこはバービーたちにとって「フェミニズムと権利の平等に関する問題のすべてが解決された」ユートピア(のはず)だった。
マーゴット・ロビー演じる「定番バービー」は、そんな自分たちの存在によって、現実世界の女性たちもハッピーでパワフルに暮らしていると信じていた。だが初めて人間世界を訪れた彼女の期待は裏切られる。男性たちは物を見るような視線を彼女にぶつけるし、自分の持ち主かと思われた少女には、バービーは女性をエンパワーする存在どころか、「フェミニズムを50年後退させ、女性の自信を奪ったファシスト」と言われてしまう。

『バービー』 ©2023 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.
1959年に初めて売り出されたバービーは、発売当時、アメリカで生産されていた唯一の大人の姿をした人形だったという。「You Can Be Anything(なりたいものになれる)」をモットーに、現実社会の女性が自分の銀行口座を開設することができなかった時代に自分の家を買い、人類が月面着陸する前に宇宙に行き、1992年から毎年大統領に立候補しているバービーは、たしかに女性のさまざまな可能性を体現してきた。一方で、画一的な美の基準を強化するような細身の体型や、1990年代に発売された喋るバービー人形に「数学って難しい」と喋らせるなど、その旧来的な価値観が反発や批判も引き起こしてきた。
グレタ・ガーウィグ自身は、バービーで遊ぶのが好きな子どもだったが、彼女のフェミニストの母親はバービーに拒否感を持っていたという。本作の宣伝で用いられているタグライン、「If you love Barbie, this movie is for you. If you hate Barbie, this movie is for you.」という言葉は、バービーの持つそんな複雑さを象徴している。
ガーウィグ:私たちにとって重要だったのは、マテル社とバービーの64年史を反芻することでした。私はバービーが嫌いな母のもとで育ったから、バービーに対するいろんな意見のことは母を通してよく知っていました。
でもバービーはずっと進化し、変化を続けてきているんですよね。それを反映することが、重要だと思いました。マテル社がやろうしていることは、彼らのつくる世界のバービーに、みんなが可能な限り自分自身を見出すことができる、ということ。それをとらえなければと考えていました。
『バービー』予告編
「私がつくりたいのは『この』バービー映画だった」
実際本作には、マテル社に対する批判的な視点もユーモラスに盛り込まれている。バービーがいかに女性たちを勇気づけてきたかを話す男性だけの役員会議をはじめ、CEO(ウィル・フェレル)ら社員たちの言動は終始滑稽に映る。そこにあるのは女性のエンパワメントを商品化する企業の姿だ。
ガーウィグによれば、「マテル社がこれを許すなんて」という場面は「毎日のようにあった」という。
ガーウィグ:「Drive like you stole it.」(盗んだように車を運転しろ、転じて、死ぬ気で逃げろ、のような意味)という英語の表現がありますが、まさにそんな感じでした(笑)。このようなかたちで最後までつくりあげることができたのが、いまでも信じられないですね。

当然マテル社とはさまざまな攻防があったようだが、それでもガーウィグがつくりたいのは「この」バービー映画だった。ネガティブな側面からも目を逸らすことなく、バービーの持つ複雑さを表現できなければ意味がないと考えた。
ガーウィグ:もちろんマテル社は会社として、私たちがやろうとしていることに対する不安や意見もありました。とくに長年バービーが抱えてきた複雑な部分を私たちがどう見せていくのか、という点には、いろいろ思うところもあるようでした。でも結局、私がつくりたい映画はこれだったんです。
私にはプロデューサー、出演者としてマーゴット・ロビーがいるという、アドバンテージもありました。この映画は、彼女がつくりたい映画でもあった。もしマテル社がこの映画をつくりたくないなら別にいい、私は「バービーの映画」をつくりたいんじゃなくて、「このバービーの映画」をつくりたいんだ、という気持ちでした。
なぜかというと、バービーを描く映画なのであれば、バービーのごちゃごちゃした部分を描かなくてはいけないという強い思いがあったんです。そうでないと不誠実になると考えていました。最終的には、マテル社の人たちも「居心地悪いのが居心地良い」みたいな状態になっていましたね(笑)。

乱雑に遊ばれた「変てこバービー(Weird Barbie)」に抱いていた、個人的な愛着
マーゴット・ロビー演じる、白人で金髪、細身の「定番バービー」に加えて、バービーランドには職業や体型、肌の色などの異なるバービーが多様な俳優たちによって演じられている。
ガーウィグ:みんなとても才能豊かな人たちです。キャスティングについては、すごく面白いユーモアを持っているけど、なにかを馬鹿にしないで心からの誠実さでやってくれる人たちを望んでいました。自分にとってはそれが一番大事でした。

左からそれぞれバービー役を演じたアナ・クルーズ・ケイン、シャロン・ルーニー、アレクサンドラ・シップ、マーゴット・ロビー、ハリ・ネフ、エマ・マッキー©2023 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.
「バービー」という存在に対してさまざまな思いを持っているのは、バービー役を演じた俳優たちも同様だ。
たとえば医者のバービー(Doctor Barbie)を演じたハリ・ネフは、キャスティングされた際、スケジュールの都合で出演が難しそうだったが、どうにか出演したいとグレタ・ガーウィグとマーゴット・ロビーに手紙を送ったことをSNSで明かし、その手紙の一部を公開した。
それは彼女にとってなぜこの映画に参加することが重要な意味を持つのかを綴ったもので、「バービーという名前は、すべてのアメリカの女性の前に大きく立ちはだかっている」ことや、トランスジェンダー女性として、「doll(人形)」という言葉に対して抱いていた相反する思いが述べられている。
またガーウィグの大学の同窓であるケイト・マッキノンは、子どもの頃、バービーにはあまり興味が持てず、「バービーよりも膨らませて遊ぶロブスターの人形に自分を重ねていた」(*1)と過去のインタビューで述べている。
マッキノンは本作で、バービーランドのはずれに住む「変てこバービー(Weird Barbie)」を演じているが、それは「持ち主に髪を切られ、火をつけられ、限界まで足を広げられるなど、激しく扱われたバービー」という設定だ。実際にマッキノンの幼少期、彼女の妹が怒ってバービーの髪を剃ってしまったことがあったそうだが、本作への出演オファーを聞いた際、自分が演じるならこの役だと思ったという。女の子が人形に対して持つ一筋縄ではいかない愛着や、ポジティブな感情もネガティブな感情も正直に描いた脚本に感銘を受けたそうだ(*同上)。
ガーウィグ:ケイトとは同じ大学に行っていたから、18歳の頃から知っていて、長い付き合いがあるんです。彼女が演じてくれたら最高だという確信がありました。
また、彼女が演じたバービーには、とくに個人的な思い入れもあります。私の母はバービーが好きじゃなかったから、私が遊んでいたバービーは、近所の子たちからのお下がりでした。そのバービーは髪が切られたり、裸にされたりしたものでした。そういうふうに乱雑に扱われてきたバービーが、私のバービーだったんです。だからそんなキャラクターをケイトと一緒につくることはとても素敵なことでした。

ケイト・マッキノン演じる「変てこバービー」 ©2023 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.
「ケンの視点で物語を考えたら、これは悲劇だって思いました」
バービーたちが回す世界のなかで、「バービーという素晴らしい存在をただ見つめる人としてつくられた」(ライアン・ゴズリング)のが、バービーのボーイフレンド、ケンである。
自分のアイデンティティがなく、「バービーの温かい眼差しのなかだけで生きられる」ケンは、バービーとともに訪れた人間世界の男性たちにエンパワーされ、バービーランドに家父長制の王国をつくろうとする。ガーウィグはケンについて尋ねられると、「いまだに自分がこういう映画をつくったのが信じられない」と吹き出しながらこう話した。
ガーウィグ:バービーが売り出された数年後にケンがつくられた。だからケンはいつも後付けみたいな存在に見えていました。バービーにとってケンは、彼女が持っている車よりも重要じゃなさそうだし、彼は仕事も家もなくて、とにかく悲しい存在に見えます。この物語をケンの視点で考えた途端、これは悲劇だって思いました。
だから彼の物語はすごく笑えるところもあるけど、感動するところもあるんです。バービーランドは現実世界を反転したようなところがありますよね。現実世界で女性が自分自身を誇らしく叫ぶ瞬間(”I am woman, hear me roar” moment)が必要なのと同じように、彼にもそういう瞬間が必要だと思っていました。

『バービー』 ©2023 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.
「私はずっと、同世代の女性たち、自分より若い世代の女性たち、そして上の世代の女性たちに助けられてきた」
ケンが人間世界の男社会に衝撃を受けている頃、バービーはさまざまな世代の女性たちから、それまで知らなかった人間らしい感情や感覚を教えられる。
ベンチに座る老婦、バービーの生みの親ルース・ハンドラー(リー・パールマン)、そしてマテル社の受付で働くグロリア(アメリカ・フェレーラ)とその娘サーシャ(アリアナ・グリーンブラット)。こうした世代の異なる女性の姿が描かれ、その視点が交錯するのは、『レディバード』や『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』といったガーウィグの過去作も通じる部分だ。

『バービー』 ©2023 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.
物語の終盤、自信をなくしたバービーやケンたちに洗脳されてしまったバービーたちに向けてグロリアは、現実世界の女性がいかに日常的に矛盾した期待にさらされているか、ということを語る。「痩せていなきゃいけないけど、痩せすぎてもいけないし、痩せたいと言ってもいけない」「リーダーでいなければいけないけど、意地悪になってもいけない」「私自身や他の女性たちが、人に好かれるために自分を縛りつけているのを見るのはもううんざり!」
グロリアの娘サーシャも、バービーたちとともに怒りのこもったこの言葉を聞いている。グロリアに反発していたサーシャにとっては、初めて見る母の姿だったはずだ。グロリアの言葉をバービーだけでなく、サーシャに聞かせることも重要だったか、と聞くと、「その通り」という答えが返ってきた。
ガーウィグ:私は人生でずっと、同世代の女性たち、自分より若い世代の女性たち、そして上の世代の女性たちに助けられてきたと思っています。時に自分より年上の人から学ぶこともあれば、年下の人から学ぶこともある。世代間で会話をするということはとてもパワフルなんです。
サーシャはすごく賢くて、雄弁で、洗練された議論もできて、自分の想いをちゃんと伝えることができる人物です。グロリアがあのように矛盾を語るのを聞くことによって、母親がいま感じているような、身動きがとれないような状況に彼女はならないかもしれない。彼女はそこから解放されるんじゃないかとも思います。
私はいつも世代を超えて手を差し伸べることにすごく興味があります。それに私にとって母と娘というのは興味深いテーマなんですよね。だって「お母さんとの関係はどう?」って聞かれて、「すごくシンプルだよ」って答える人は一人もいないと思う。

グレタ・ガーウィグ
最後のセリフに込められた、「普通なことをする」ことの意義
プラスチックの人形とは異なり、人間は不完全で、欠陥があり、内面も外面も変化する。年をとるし、体型も変わるし、涙も流す。いまの人間世界は決してユートピアではないが、「今日も明日も変わらずハッピー」なバービーランドもユートピアではないかもしれないことを本作は提示する。はたして「理想の世界」とはどんな姿をしているのだろうか?

『バービー』 ©2023 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.
人間世界を知ったバービーの実存の探究の旅は、意表をつくセリフで幕が降りる。この場面は、本作の撮影で最後に撮ったシーンだったため、終わりたくなくて「13回くらい撮った」のだそう。ラストがどんなセリフなのかは劇場で確認してほしいが、このエンディングにも女性の生き方についての監督なりの想いがあった。
ガーウィグ:セリフとして自分でも笑えるって思ったし、バービーが最後にすることはすごく普通なことだから、逆に響くんじゃないかなって考えたんです。彼女が大統領になったとか、CEOになったとか、なにか特別なことを達成するというのは避けたかった。「普通」であることが素敵だと思ったし、マーゴットもこのアイデア聞いて面白いと言ってくれました。
何よりマーゴットのあのセリフの言い方ですよね。すごく誇らしげに、嬉しそうに言うんです。それが笑えるところでもあるんですが、あれが勝利だとしたら最高じゃないですか? 勝利のかたちが「普通なことをすること」って。

*1:Inside the Barbie Movie: How the Massive Movie Came to Be | Time(リンクを開く)
- 作品情報
-
 『バービー』
『バービー』
2023年8月11日(金)全国ロードショー
監督・脚本:グレタ・ガーウィグ
脚本:ノア・バームバック
出演:
マーゴット・ロビー
ライアン・ゴズリング
シム・リウ
デュア・リパ
ヘレン・ミレン
配給:ワーナー・ブラザース映画
- プロフィール
-
- グレタ・ガーウィグ
-
米『アカデミー賞』ノミネート経験をもつ監督であり脚本家でもある。ノア・バームバックとともに本作の脚本を書き、監督する以前に、『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』(2019)を監督。シアーシャ・ローナン、ティモシー・シャラメ、フローレンス・ピューが出演したこの作品は、米『アカデミー賞』6部門、英『アカデミー(BAFTA)賞』5部門、『全米製作者組合(PGA)賞』、『全米脚本家組合(WGA)賞』にノミネートされた。監督デビュー作『レディ・バード』(2017)は、自身の最優秀監督賞と最優秀オリジナル脚本賞を含め、米『アカデミー賞』5部門にノミネートされた。 多作の俳優でもある。ノア・バームバックと脚本を書き、出演もした『フランシス・ハ』(2012)の演技で、『ゴールデングローブ賞』にノミネートされた。2022年、バームバックが監督した最新作『ホワイト・ノイズ』に出演し、アダム・ドライバーと共演。そのほか、俳優としての出演作品には、『ダムゼル・イン・ディストレス バイオレットの青春セラピー』(2011・未)、『29歳からの恋とセックス』(2012・未)、『マギーズ・プラン 幸せのあとしまつ』(2015)、『ミストレス・アメリカ』(2015・未)、『ジャッキー/ファーストレディ 最後の使命』『20センチュリー・ウーマン』(共に2016)などがある。
- フィードバック 81
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-