メイン画像:©2021 Dragons Films/ Lunanime
3月7日に公開された映画『Playground/校庭』は、閉じた学校という世界を、まだ小学校に入学したばかりの幼い子どもの視点で描き出す作品だ。「子ども目線」を徹底した撮影手法によって、鑑賞者は7歳のノラの視点を共有し、いじめの問題に直面していく。
今回は、本作のローラ・ワンデル監督に、映画批評家の常川拓也がインタビュー。常川は約3年前の『なら国際映画祭』にて本作を鑑賞し、胸を打たれたのだという(またその際にワンデル監督とも対面している)。ワンデル監督と同じベルギー出身の監督やその作品、また子どもや青年、学校をテーマにしたほかの作品も引用、対比させながらの対話を通して、『Playground/校庭』について紐解いていく。
あらすじ:7歳のノラが小学校に入学した。しかし人見知りしがちで、友だちがひとりもいないノラには校内に居場所がない。やがてノラは同じクラスのふたりの女の子と仲良しになるが、3つ年上の兄アベルがイジメられている現場を目の当たりにし、ショックを受けてしまう。優しい兄が大好きなノラは助けたいと願うが、なぜかアベルは「誰にも言うな」「そばに来るな」と命じてくる。その後もイジメは繰り返され、一方的にやられっぱなしのアベルの気持ちが理解できないノラは、やり場のない寂しさと苦しみを募らせていく。そして唯一の理解者だった担任の先生が学校を去り、友だちにのけ者にされて再びひとりぼっちになったノラは、ある日、校庭で衝撃的な光景を目撃するのだった……。
はじめて学校に行くときの「恐怖」。撮影手法とテーマによる没入感
2022年の『なら国際映画祭』で一緒に撮った写真をオンライン越しに見せると、ローラ・ワンデルは控えめに微笑みを返した。謙虚でシャイな人柄を垣間見せる一方で、彼女の映画には厳しい現実主義が貫かれている。
『第74回カンヌ国際映画祭』ある視点部門で国際批評家連盟賞を受賞した彼女の長編デビュー作『Playground/校庭』は、同じベルギーを代表する映画作家、ダルデンヌ兄弟(※)が切迫した社会問題を映すように、子どもたちのあいだで巻き起こるいじめの問題を極めて真剣に追う。
映画が始まると、私たちは、学校がすべてだった7歳のあの頃の世界をそのまま体験する。終始、手持ちカメラで小学校に入学したノラ(マヤ・ヴァンダービーク)に接着剤のようにべったり張り付き、彼女とともに兄アベル(ガンター・デュレ)がいじめに遭っているのを目撃するのだ。まだ靴ひもも結べず、社会を何も知らないノラは、ただ兄を救いたいと奔走する。その視野の狭い必死さと混乱を、極端に浅い被写界深度と、絶え間なく耳を突き刺す子どもたちのざわめきが表現する。私たち観客が知ることができる範囲を著しく制限させながら、観客を人物の内面に没入させる手法である。それによって、ノラの苦悩をより身近に感じさせる、親密な体験が生まれる。
ワンデルは、「コミュニティに溶け込めるかどうかは生死の問題なのだ」と主張する。本作は、はじめて学校に行くときに抱いた恐怖を思い起こさせる。たとえいくつになっても、新たに別の世界、異なる社会に入っていくときには、誰しもが猛烈な不安に押し潰されそうになる。周囲に馴染めず、適合できなければ居場所はないかもしれない――学校は、その課題を一番最初に経験する場所である。社会全体の縮図であり、将来に襲いかかる経験の先取りの場なのだ。ワンデルは、私たちが冷静な観察者でいることを許さない。『Playground/校庭』は、一瞬の休息も息抜きも与えない、能動的で直感的な映画体験である。
※兄のジャン=ピエール・ダルデンヌと、弟のリュック・ダルデンヌを指す、ベルギーの映画監督。『イゴールの約束』(1996)、『ロゼッタ』(1999)、『息子のまなざし』(2002)、『少年と自転車』(2011)など、少年少女と社会との関わりを丁寧な作劇と演出で描き出す。

©2021 Dragons Films/ Lunanime
没入感は社会問題を身近にする——ダルデンヌ兄弟や『サウルの息子』の影響
─同じくベルギー出身であるダルデンヌ兄弟の伝統に則って、『Playground/校庭』は子どもたちの問題を真摯に見つめています。2022年の『なら国際映画祭』では、彼らに『サンドラの週末』(2014)のときに実際に会って、シナリオにコメントをもらったと語っていましたね。
ワンデル:私は、ダルデンヌ兄弟から多くのことを学びました。おっしゃる通り、以前、制作した短編映画『Les corps étrangers』(2014)が『カンヌ国際映画祭』に出品されたとき、特にリュック・ダルデンヌととても近しくなり、彼に本作の脚本を読んでもらい、いくつかフィードバックをいただきました。また、編集したものも見てくれて、その際にもフィードバックをくれました。
彼らの映画から学んだのは、没入感がありながら、社会問題を身近に感じさせる手法です。そして、直面する問題に必死に抗いながらも、心の奥底では脆さを抱えた人物の描きかたも参考にしています。現在、私が完成させようとしている次回作『L'intérêt d'Adam』では、彼らに共同プロデューサーとして入っていただいています。

(c) Alice Kohl
ローラ・ワンデル
1984年ベルギー生まれ。ベルギーの視聴覚芸術院で映画製作を学ぶ。在学中に短編映像『Murs(原題)』(2007)を制作。その後、初の短編映画『O négati(原題)』(2010)を製作した後、2014年に監督した短編映画『Les corps étrangers(原題)』では『カンヌ国際映画祭』短編コンペティション部門に選出された。本作で初の長編映画デビューを飾り、『第74回カンヌ国際映画祭』ある視点部門に出品され、国際批評家連盟賞受賞。また、『第94回アカデミー賞』国際長編映画賞ショートリストにまで選出され、世界中の映画祭を席巻しデビューを飾った。最新作である『In Adam‘s Interest』(25年撮影開始予定)では、ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ製作のもと、レア・ドリュッケール、アナマリア・ヴァルトロメイをキャストに迎え、小児科病棟で働く看護師と、ある母子が直面する困難を描くドラマ作品を手がける。
─具体的に彼らからどのような助言を得たか教えていただけますか。
ワンデル:無駄なものは削ぎ落とすこと。そして、どんなことがあってもキャラクターのモチベーションを見失ってはいけない。この2つが、ダルデンヌ兄弟からいただいた、忘れがたいアドバイスでした。

©2021 Dragons Films/ Lunanime
─ノラの限定された視点を体験させるかのような主観的なアプローチを採用し、『サウルの息子』(※)のようなサバイバルスリラーとして校庭を描き出しています。学校は大人が立ち入ることのできない弱肉強食の世界であり、ノラはまるで脱出不可能であるかのように、その境界から出ることができません。学校をどのような空間として表出させようとしましたか。
ワンデル:まさに『サウルの息子』は、特に撮影の仕方において大きな影響を受けました。あの映画のようにスクリーンのなかの世界に引き込んでいく没入感を生み出したかったのです。また、映像では見えないところで暴力を感じさせる、画面外の暴力の表象方法も参考にしています。
たしかにノラは学校、校庭の世界のなかに閉じ込められているかのような存在です。でも、それは子どもたちが遭遇しうる、ある種の閉塞感を反映しています。学校や行きたい場所を選ぶことはできず、授業のプログラムも決められ、子どもたちには選択の余地がない。残念ながら、それは私たちが経験せざるを得ない暴力の一部であり、それを通り抜けないと成長できない、ひとつのプロセスかと思います。しかし、それは社会でも同じ。大人になってからもまた新しい環境に慣れて、働かなければなりません。そのような経験は、子ども時代から綿々と続くことではないかと思います。
※2015年、ハンガリーのネメシュ・ラースロー監督による映画。ユダヤ人強制収容所内でのある囚人の過酷な運命を見つめ、『第68回カンヌ国際映画祭グランプリ』、『第88回アカデミー外国語映画賞』ほか数々の賞に輝いた。
『サウルの息子』予告編
子どもの目線で子どもを語ることこそ重要だ——『CLOSE/クロース』や、セリーヌ・シアマのこと

©2021 Dragons Films/ Lunanime
─ルーカス・ドンの『CLOSE/クロース』(※)もダルデンヌ兄弟的なスタイルで、校庭で巻き起こるいじめ、特に伝統的な男らしさの規範に縛られた少年たちの苦しみを描いていました。同時期に子どもたちのいじめを描く映画がベルギーから生まれたことをどのように感じられますか。
ワンデル:本作は、『CLOSE/クロース』の約1年前にベルギーで公開されましたが、私にとって、あの映画は思春期の時代、つまりティーンエイジャーから成人への移行期について、多くを語っているように思えます。一方、私の映画では、それよりもう少し幼い子ども時代を描いています。ティーンエイジャーの視点の映画はたくさんありますが、小学校の新入生になる子どもの視点からの映画はじつはまだあまりないように思います。なので、この時期の子どもたちを見せることとともに、彼らのなかにも暴力性が存在していることを見せるのは重要だと考えたのです。
※2022年公開、無垢な少年に起こる残酷な悲劇と再生を描いた映画。ルーカス・ドンもワンデルと同じくベルギーの映画監督。
『CLOSE/クロース』予告編
─セリーヌ・シアマ(※1)も本作を称賛していますね。偶然にも『秘密の森の、その向こう』(2021)も同じく72分で子ども時代を描いていますが、以前、彼女にインタビューした際(※2)、「子どもを単に無邪気な存在ではなく、大人と同じように個人として誠実に見ることを心がけている」と語っていました。子どもの視点を描くことをどのように考えていますか。
ワンデル:まず、セリーヌ・シアマが私の映画を賞賛してくれたことを全く知らなかったので、とてもうれしいです。彼女は、私が本当に敬愛する映画作家です。彼女の子どもの描き方は本当に素晴らしい。
彼女のおっしゃる通りで、子どもは時として大人よりも明晰で鋭いため、大人と同じ地位を与えるべきだと私自身も思っています。なぜかベルギーでは、子どもと高齢者は同じような立ち位置で扱われるように感じています。子どもたちは、言ってみれば、社会のなかでまだ商業活動をしていない人たちですよね。彼らは社会に貢献も活躍もしていないために、脇に置くような存在になってしまっている。
そのために、子どもに向ける予算や彼らへの支援が足りていなかったり、子ども時代に目を向ける意識が薄かったりするのではないかと思います。でも、子どもたちこそ「未来の大人」ですから、まだ社会で活躍していないという理由で、子どもたちの問題に十分なスペースが割かれないのは間違っています。だからこそ私は、子どもたちの問題に対する意識を高め、子どもの目線で子どもについて語ることこそが重要だと考えたのです。子どもだからって子ども扱いするのではなく、大人と同じように、ひとりの人間として受け入れなければなりません。私は「子ども扱いする」という言葉自体がもう存在すべきではないと思う。人間は子どもであろうと老人であろうと、平等に扱われるべきです。
※1 フランスの脚本家、映画監督。代表作に、『水の中のつぼみ』(2008)、 『トムボーイ』(2021)、 『ぼくの名前はズッキーニ』(2018) 、『燃ゆる女の肖像』(2020)など。
※2 『燃ゆる女の肖像』セリーヌ・シアマが新作を語る。娘と母の不思議な物語、愛する人の「不在」について

©2021 Dragons Films/ Lunanime
校庭は生きるか死ぬかの場所だ——『禁じられた遊び』、そして聖書の投影
─子どもたちが鳥を埋葬しようとする場面は、『禁じられた遊び』(1952)を彷彿とさせます。劇中の授業では花の命の有限性も語られますが、子どもたちの野蛮な世界に死のイメージを導入することで、どのような効果を期待しましたか。
ワンデル:校庭は、生きるか死ぬか、サバイバルの場所なので、ある意味、死と密接に関係しています。ノラにとっては、そこでグループに溶け込めるかどうかが問題であり、もし溶け込めなかったら、それは死を意味するのです。
砂場で鳥を埋葬しようとする場面は「グループに受け入れられないかもしれない」というノラの恐怖を象徴しています。子どもたちが「校庭には死んだ子どもが埋められている」とか、さまざまな妄想を膨らませるなかで、ますますノラはこのグループから抹消されてしまう、という不安を増長させているのです。

©2021 Dragons Films/ Lunanime
─兄は聖書における人類最初の被害者と同じ名前を持っていますね(※)。人間の原初的な攻撃性、そして兄妹間の心理的葛藤を描くうえで、聖書のイメージを重ねることは意識的だったのでしょうか。
ワンデル:おっしゃる通りです。まさに聖書は、私にとって明白なリファレンスでした。なぜなら、私たちが作り出す物語、そして人間がいま起こしている問題の出発点は、すべて聖書にすでに書かれていると思っているからです。
※カイン(兄)とアベル(弟)は、旧約聖書『創世記』第4章に登場する。アダムとイブがエデンの園を追われた(失楽園)あと、二人のもとに生まれた兄弟。カインは弟アベルを殺害し、神話において「人類最初の殺人の加害者」とされている。
暴力の連鎖は「治癒」できる。ノラのようにまず耳を傾け、抱きしめるということ
─本作の英題(『Playground』)と主題は、リューベン・オストルンド(※)がスウェーデンの少年たちの間で行われるいじめを無慈悲な長回しで見据えた『プレイ』(2011)を彷彿とさせます。暴力を注意深く観察し、集団が個人の行動にどのような影響を与えるかを探ることに関心があるのでしょうか。
ワンデル:『プレイ』は私も観ましたが、暴力というものを非常によく分析した素晴らしい映画ですよね。あえて言うならば、暴力というのは一種の病気のようなものと見立てることができると思っています。なぜなら、それは伝染するものであり、治癒することができるものだから。でも、治癒しないで放っておけば、それは感染して広まっていき、どんどんとエスカレートしていくのです。そして、個人に与える影響も大きくなっていく。集団的かつ個別に取り組むことによって、治療は実現できると思います。
ふたつ目のご質問についてですが、おっしゃる通り、私たちは社会的存在だから、集団のなかで生きる必要がある。そのためには社会に同化し、個人として集団に溶け込まなければなりません。集団に受け入れられるかどうか、それがすべてなのです。ただ、最も難しいのは、集団に受け入れられながらも自分自身の個性を保つことだと思います。
※スウェーデン出身の映画監督、脚本家。『プレイ』のほか、『フレンチアルプスで起きたこと』(2014)、『ザ・スクエア 思いやりの聖域』(2017)、『逆転のトライアングル』(2022)など。CINRAでも常川がインタビューしている(映画『逆転のトライアングル』リューベン・オストルンド監督が語る「社会的立場が人間を変えてしまう」)
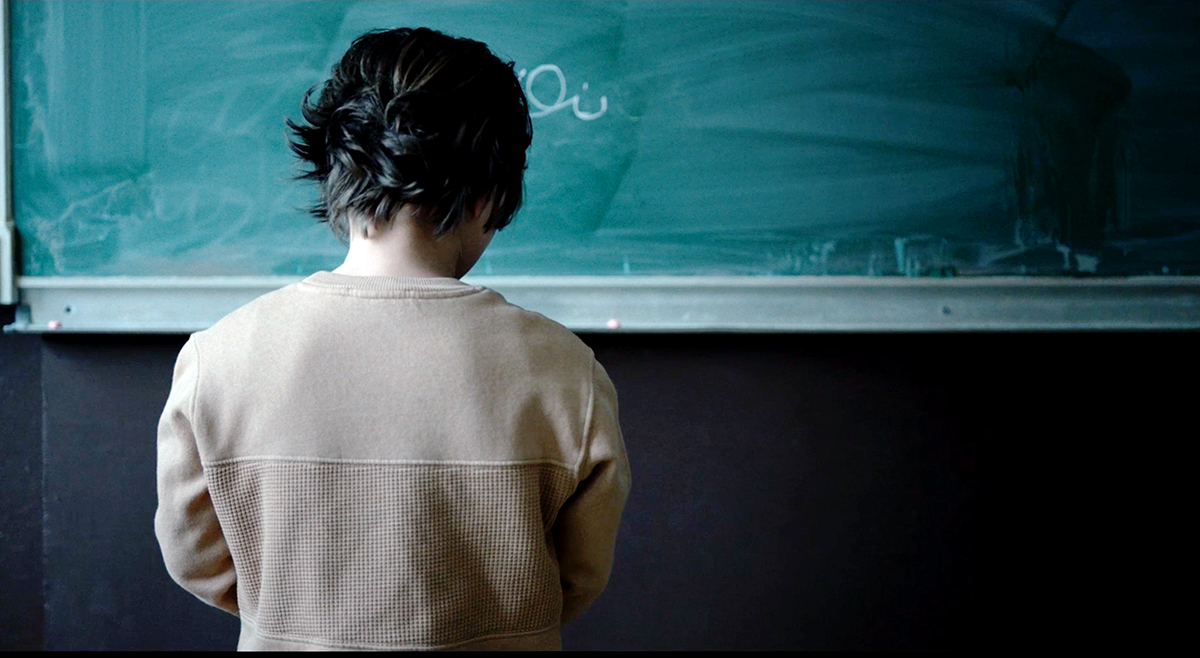
©2021 Dragons Films/ Lunanime
─劇中、子どもたちは「人種差別主義者とは、自分のことしか考えない人間」と話しますね。校庭での残酷さを冷徹に見るなかで、ノラとアベルは人間の連帯の最も本質的なかたちを表現しますが、この物語のなかで、ハグというジェスチャーをどのように表象したいと考えましたか。
ワンデル:劇中で子どもたちが「レイシストは自分のことしか考えない」と話す場面は、彼らが、親が言っているのを又聞きして歪曲していたり、間違った情報を鵜呑みにしているという描写として、挿入しました。
ノラがアベルを抱きしめる行為には、暴力の連鎖を断ち切る力があります。ナイーブかもしれませんが、私はそう信じ続けたいのです。暴力に暴力で対抗することは、暴力を増幅させるだけだと思います。だからこそ、私にとってこのジェスチャーはとても重要なのです。
アベルは自分のなかに苦しみを抱えているから、彼もいじめの加害者になってしまう。個人的には、暴力を振るったり、他人に嫌がらせをしたりする子どもたちは、心のなかに大きな傷や脆さを抱えているのだと思います。彼らが暴力を振るうのは何も理由がないわけではなく、何か問題がある。それは、子どもたちが健康ではない状態だと思います。
同時に問題なのは、私たちは目まぐるしく変化する社会に生きていて、時間がないということ。子どもの問題に耳を傾ける余裕がないような時代です。まずやるべきことは、ノラのように、ジャッジする前に耳を傾けることだと思います。ノラは、何も言わず、ただアベルを抱きしめて、彼の苦しみに耳を傾ける。その彼女のジェスチャーによって、アベルに平穏がもたらされるのです。それが暴力の連鎖を止めるための第一歩だと私は信じています。

©2021 Dragons Films/ Lunanime
- 作品情報
-
 『Playground/校庭』
『Playground/校庭』
2025年3月7日(金)新宿シネマカリテ、シネスイッチ銀座ほか全国公開
監督・脚本:ローラ・ワンデル
- プロフィール
-
- ローラ・ワンデル
-
1984年ベルギー生まれ。ベルギーの視聴覚芸術院で映画製作を学ぶ。在学中に短編映像『Murs(原題)』(2007)を制作。その後、初の短編映画『O négati(原題)』(2010)を製作した後、2014年に監督した短編映画『Les corps étrangers(原題)』では『カンヌ国際映画祭』短編コンペティション部門に選出された。本作で初の長編映画デビューを飾り、『第74回カンヌ国際映画祭』ある視点部門に出品され、国際批評家連盟賞受賞。また、『第94回アカデミー賞』国際長編映画賞ショートリストにまで選出され、世界中の映画祭を席巻しデビューを飾った。最新作である『In Adam‘s Interest』(25年撮影開始予定)では、ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ製作のもと、レア・ドリュッケール、アナマリア・ヴァルトロメイをキャストに迎え、小児科病棟で働く看護師と、ある母子が直面する困難を描くドラマ作品を手がける。
- フィードバック 5
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-








