メイン画像:©Carole Bethuel
AIが国家の社会システムを管理する未来。人間の感情は不要と見なされ、就きたい職につくためには、DNAの浄化によって「感情の消去」をしなければならない……。
突飛な世界のようで、AIの存在感が日に日に増している現代に生きる私たちにとっては、想像しやすい「悪夢のような」近未来かもしれない。4月25日に公開されたフランス映画『けものがいる』は、そんな2044年と、2014年、1910年を行き来するSF映画だ。
監督は、過去に『SAINT LAURENT サンローラン』(2014年)などを手がけたベルトラン・ボネロ。自ら劇中音楽の制作も行っているボネロ監督は、じつはかつてミュージシャンだった。クラシック音楽に造詣が深いことでも知られている。
そんなボネロ監督の作品に熱いラブコールを送るのが、ミュージシャンのジム・オルーク。長く日本に住んでいるオルークは、日本未公開のボネロ監督作品を自ら翻訳して周りに見せるほどのファンだといい、『けものがいる』についても大絶賛している。
今回は、そんなオルークとボネロ監督の対談が、オンラインで実現。本作についてのインタビューも行いつつ、2人が熱く語り合う場面もあった。本稿では、インタビューパートにて映画批評家の常川拓也が本作を深く紐解きながら、映画音楽について考える2人の対談も詳報したい。
あらすじ:AIが国家の社会システム全般を管理し、人間の感情が不要と見なされている2044年のパリ。孤独な女性ガブリエル(レア・セドゥ)は有意義な職に就きたいと望んでいるが、それを叶えるにはDNAの浄化によって〈感情の消去〉をするセッションを受けなくてはならない。人間らしい感情を失うことに恐れを感じながらも、AIの指導に従って1910年と2014年の前世へとさかのぼったガブリエルは、それぞれの時代でルイ(ジョージ・マッケイ)という青年と出会い、惹かれ合っていく……。
愛への恐怖を描いた短編小説が基。『けものがいる』でインセルを描いた理由とは

©Carole Bethuel
時間とその無常について、劇場を出た後も長く心に残る作品。2020年代に見た映画の中で、これを超える作品は思いつかない。- ジム・オルーク
『けものがいる』に公式コメントも寄せているジム・オルーク。オンライン会議室に入室してすぐ、「長い間、ずっとあなたのファンでした!」とボネロに語りかけた。「じつはボネロさんのこれまでの作品『ノクトラマ 夜行少年たち』(2016年)、『Zombi Child』(2019年)、『Coma』(2022年)などに日本語の翻訳をつけて、日本の友達にも紹介してきたんですよ」と笑顔で話すと、ボネロも「本当に? それはすごいね」と驚いていた。
—まずは、『けものがいる』について質問をさせてください。3つの時代を舞台にした本作で、1910年のパリの大洪水、2044年のAIに支配された未来とあわせて、2014年のエリオット・ロジャーの事件(※1)を取り上げていることが興味深く思いました。愛と破滅をテーマとする物語のなかで、なぜインセル(※2)だとされる彼を重大な出来事と位置づけたのでしょうか。インセルへの問題意識を持っていましたか。
ベルトラン・ボネロ(以下、ボネロ):この映画は、愛への恐怖を描いたヘンリー・ジェイムズの短編小説『密林の獣』(1903)を基にしています。1910年のシーンでは、愛を恐れているのはあきらかにガブリエルです。私は、いま現在に近いところで、その感情を現代的に捉えたいと思いました。私にとって、インセルとは愛を恐れる人々のこと。だからこそインセルを深く掘り下げたいと考え、約10年前、私の心に強く残ったエリオット・ロジャーの存在を思い出したのです。
※1 2014年5月23日、米西部カリフォルニア州サンタバーバラ近郊の学生街で、大学生6人を殺害した末に自殺したとされる容疑者(当時22歳)。同容疑者は事件の前に書いていた手記やYouTubeへの投稿で、自分を相手にしてくれない女性たちに対する恨みを晴らすと宣言していた。
※2 インターネットカルチャーのひとつで、直訳すると、望まない禁欲者、非自発的な独身者という意味(Involuntary Celibate=Incel)。日本ではいわゆる「非モテ」などの言葉が重なる。それを自覚する男性当事者たちが、匿名掲示板などでこの言葉を用いるようになり、女性嫌悪、人種差別、暴力肯定などと深く結びついてきた。

©Carole Bethuel
ベルトラン・ボネロ
1968年フランス、ニース生まれ。『ベルリン国際映画祭』パノラマ部門で上映された『何か有機的なもの』(1998年)で長編デビュー。その後『ポルノグラフ』(2001年)は、『カンヌ国際映画祭』批評家週間で上映され、国際映画批評家連盟賞受賞。『ティレジア』(2003年)は『カンヌ国際映画祭』のコンペティション部門、『戦争について』(2008年)は『カンヌ国際映画祭』監督週間に選出。『メゾン ある娼館の記憶』(2011年)で再度『カンヌ国際映画祭』のコンペティション部門に返り咲き、同作は『アカデミー賞』外国語映画賞のフランス代表作となったほか、『セザール賞』の7部門にノミネートされ、デザイン賞受賞。その後は『SAINT LAURENT サンローラン』(2014年)、パリでテロを計画する若者を描くアクション映画『ノクトラマ 夜行少年たち』(2016年)など監督。『けものがいる』は2023年の『ヴェネチア国際映画祭』のコンペティション部門で上映、映画祭の公式批評スコアで1位を獲得した。
—3つのそれぞれの時代で、人形というテーマが通底していますね。1910年には、ガブリエルの夫は人形をつくり、2044年にはAIロボットが登場し、そして2014年にはルイが女性を非人間的な人形として見ています。原作と違い主人公を女性に入れ替えたのは、インセルを出現させたこととも関係しているでしょうか。
ボネロ:たしかにルイは、ガブリエルを人形のように見ている面はあると思います。しかし同時に、彼は彼女に魅了されながら、恐怖も感じていると思う。否が応でも心を動かされ、動揺してしまう。ルイのなかにある、誰も見たことのない「何か」をガブリエルが見ているから、彼の感情を揺さぶるのでしょう。ルイの行動には、ガブリエルへの感情の高ぶりを拒絶したい気持ちが表れているのだと思います。
—前作『Coma』でも、現実の連続殺人犯のロバート・スパハルスキー(※)の映像を引用していたり、少女たちがお気に入りのシリアルキラーの会話を繰り広げたりする場面がありました。実在の連続殺人犯をフィクションに登場させることに、大きな関心を持たれているのでしょうか。
ボネロ:その通りです。映画がフィクションであればあるほど、ファンタジーであればあるほど、映画のなかに現実から生まれた要素がほしくなるんです。リアリティを持ち込むことを好む傾向にあるのだと思います。それが浸透することで、フィクションの部分をより描きやすくなる、さらに夢想できるのだと考えているのです。
※1970年代、強盗や盗難、放火などの犯罪を重ねて4度投獄された後、2005年、過去に起こした4件の殺人を告白。2006年、有罪判決を受け、懲役100年が宣告された。
あらすじ:パンデミックで隔離されたなか、寝室に閉じこもった18歳の少女は、謎めいたYouTuberのパトリシア・コーマに導かれて、いつしか夢と現実を彷徨う。新型コロナウィルスによるロックダウンの最中に撮影され、人形劇、アニメーション、Zoom映像など、様々なメディアを織り交ぜて作られた。ベルトラン・ボネロが娘に捧げた映画。
コロナ禍に制作した前作『Coma』との深いつながり。「現実」を「虚構」に引用する

© FILM : 2022 - LES FILMS DU BÉLIER - MY NEW PICTURE - 9459-5154 QUÉBEC INC. - ARTE FRANCE CINÉMA - AMI PARIS - JAMAL ZEINAL-ZADE
—オルークさんも本作を理解する上で、『Coma』とのつながりに注目しているとうかがいました。
ジム・オルーク(以下、オルーク):『Coma』も素晴らしい映画でした。当時から『けものがいる』の構想は思い描いていたのでしょうか。
ボネロ:そうなんです。当時『けものがいる』を撮影する予定だったのですが、コロナ禍を含めて、3回も延期になってしまいました。2回目はレア・セドゥのスケジュールの都合で長期間延期に。そこで12日間、資金なしで、急いで自主制作映画を撮ろうと決めて、『Coma』の脚本を書き、制作しました。制作での自由さにこだわってつくった作品でした。
オルーク:『Coma』では、『けものがいる』に向けて、いくつかのアイデアの実験のような試みを行っていますよね。
ボネロ:まさにその通りです。『けものがいる』は頭の中ですでにできあがっていたので、『Coma』を使って、異なるイメージを組み合わせるなど、さまざまなことを試してみたかったのです。

撮影:三田村 亮
ジム・オルーク
1969年シカゴ生まれ。Gastr Del SolやLoose Furなどのブロジェクトに参加。一方で、小杉武久とともにMerce Cunningham舞踏団の音楽を担当、トニー・コンラッド、アーノルド・ドレイブラット、クリスチャン・ウォルフなどの作曲家との仕事で現代音楽とポストロックの橋渡しをする。1997年、超現代的アメリカーナの系譜から『Bad Timing』、1999年、フォークやミニマル音楽などをミックスしたソロアルバム『Eureka』を発表、大きく注目される。1999年から2005年にかけてSonic Youthのメンバー、音楽監督として活動し、広範な支持を得る。2004年、Wilcoの『A Ghost Is Born』のブロデューサーとして『グラミー賞』を受賞。アメリカ音楽シーンを代表するクリエーターとして高く評価され、近年は日本に活動拠点を置く。
—『Coma』内で哲学者ジル・ドゥルーズの「人は決して他人の夢に巻き込まれるべきではない」と夢の危険性を語る言葉を参照されていましたが、今作の2014年のシーンでは、まさにルイの夢にガブリエルは巻き込まれているように見えます。
ボネロ:ジムが言うように、確かにこの2つの映画は関連しています。おそらく私が『けものがいる』を撮影するはずだったのが延期になり、その間に『Coma』を撮ったからでしょう。なので、美学的にも精神的にも、この両作にはつながりがあります。どちらの映画でも観客は誰かの頭のなかに入っていくことになる。
『Coma』の序盤で、おっしゃるようにジル・ドゥルーズの言葉を参照しましたが、まさにそれがあの映画の核でした。内側に入り込むことで、異なる世界を創造したかったのです。『けものがいる』では、同様のアイデアを別の方法で実践しました。機械を通して、頭のなかではなく、誰かの過去の人生に入り込むのです。それはある意味では意識のなかに入り込むようなものだと思います。
—『Coma』では人形がドナルド・トランプのツイートを読み上げる場面がありましたが、本作でもエリオット・ロジャーのマニフェストを、セリフに反映しています。現実の声をそのまま映画に取り入れることにどのような意図を持っていますか。
ボネロ:私は、インセルのキャラクターに愛への恐怖を語らせることにしました。そのとき、2014年のエリオット・ロジャーが投稿したビデオの数々を思い出したんです。そのなかで彼が話している言葉はそのままに、書き加えたり、変更することは何もしませんでした。
彼の言葉の簡潔さには驚かされました。恐ろしいことに、一見しただけでは彼は狂人のようには見えないんですよね。脚本にそういった現実を持ち込むことで、大胆なファンタジーやフィクションを展開できる。現実に由来することで、フィクションとの2本足で立つことが、私には必要なのだと思います。

©Carole Bethuel
—今回もトランプを戯画化したアニメーションが含まれていました。両作とも彼を風刺していますね。
ボネロ:『Coma』で小さな人形を使ったシーンはシットコム(※)ように構想したのですが、私は、その場面が悪夢になるようにしたかったんです。人形たちにトランプの言葉を使って話させることで、それができると考えました。『Coma』は少女の頭のなかに入り込み、彼女が見る悪夢について語るという物語だったので、悪夢という概念が非常に重要でした。悪夢は、私がフィクションを描くうえでよく用いる手法です。どのように悪夢が現れるかを描くことが、現代の世界の入口として、有効だと考えているためです。
※シチュエーション・コメディ(situation comedy)の略。テレビドラマの一種で、1話完結のコメディとして登場人物が様々な状況に巻き込まれる様子を描く。
ボネロとオルーク、ノンストップで映画音楽を語り合う
オルーク:私のパートナーの(石橋)英子が『悪は存在しない』の音楽を手がけていて。同じ『第80回ヴェネチア映画祭』に出品されたとき、そこでいろんな人に『けものがいる』の情報がないかということばかり聞いていたから、みんなに嫌がられていたと思う(笑)。
日本ではシネフィル(※)文化が弱まり、以前よりも海外映画を見ることが難しくなってきています。関心が薄れたのか、財政的な問題なのか、あるいはほかの理由があるのかもしれませんが、あなたがつくるような映画を日本で見る機会が本当に少なくなってきていて。だから『けものがいる』の日本公開がとてもうれしい。いまは周囲のみんなに観るべきだと言い続けています(笑)。
※映画マニア、映画ファンのこと。
—ここからは、オルークさんから音楽面をうかがっていただきたく思います。
オルーク:あなたが自分で映画のサウンドトラックを制作していることを知らない人も多いのかもしれません。映画をつくる前はミュージシャンだったのですよね。
ボネロ:小さい頃から、音楽は私の情熱でした。ピアノとオルガンが得意で、スタジオやステージなど、多くの人の前で演奏していました。でも、24、5歳くらいの頃、ある程度成功もして、少し退屈に感じるようになったんです。当時はレコードがよく売れる時代で、音楽でたくさん稼げたのですが、「40歳になったらどうしよう?」と思うようになり、映画への転向を決めました。
もともと映画マニアだったわけではないんですけどね。それではじめに自分で稼いだお金で短編映画を撮りました。あの頃、もしホームスタジオを持っていたら、まだ音楽を続けていたかもしれません。でも、音楽を諦めたわけではなく、セッションマンをやめただけなのです。
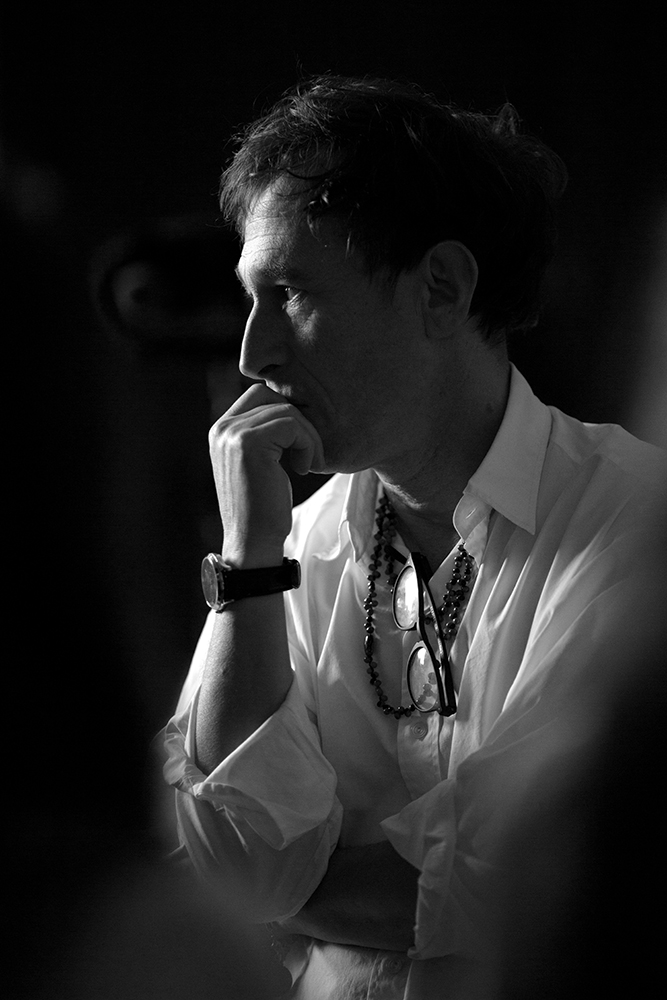
ベルトラン・ボネロ
オルーク:たしかに音楽の世界は、大きく変化しましたね。映画でも変化を感じられますか。
ボネロ:イエスであり、ノーですね。例えば、1990年代にMassive AttackやPortishead、Tricky(※1)が登場し、彼らは自分たちのスタジオで、それほどお金をかけずに新しいサウンドを生み出した。私にとってそれはまさにサウンドの革命でした。この3つのバンドとブリストルサウンド(※2)は、映画界にはまだない革命です。もちろんいまはiPhoneでも撮ることができ、だいぶ安くつくれるようになったのはたしか。誰もが違った映画をつくれるようになったけれど、クオリティはあまりよくない。映画でも革命は起きたかもしれませんが、その結果は音楽ほど明白ではないと感じています。
オルーク:『Coma』では、サウンドデザインが以前の作品よりも少しだけ前面に出てきたように思いました。さらに『けものがいる』では、音楽とサウンドデザインの境界線が……。
ボネロ:ええ、とても薄くなっています。『Coma』と『けものがいる』は精神的な映画。サウンドデザインは、そこでの精神的な体験のために作用するように考えていて、その境界線を薄くしたのです。
オルーク:両作のサウンドデザインには、本当に感銘を受けました。スクリーンで聞けるのを楽しみにしています。
※1 Massive Attack(マッシブ・アタック)、Portishead(ポーティスヘッド)はイギリス出身の音楽グループ、Tricky(トリッキー)はイギリスのミュージシャン。3者ともイギリス・ブリストルを発祥の地とするトリップホップの先駆者として知られる。
※2 イギリスのブリストルで生まれた、ヒップホップ、レゲエ、ジャズ、ソウルなど、さまざまなジャンルの要素をミックスした音楽スタイルのこと。

©Carole Bethuel
ボネロ:音は重要ですよね。私からも質問があります。映画音楽をつくるときは、監督によって違うとは思いますが、どのタイミングでレコーディングを始めるんですか?
オルーク:毎回違いますし、日本の映画とほかの国の映画によってもまったく違います。たとえば、ヴェルナー・ヘルツォーク(※)と仕事をしたときは、彼がスタジオで座っているあいだに、一緒に映像を観ながらつくってくれ、という方法でした。何もない状態よりも、映像がある状態でつくれるほうが個人的にはやりやすいですね。
ボネロ:撮影前に音楽をつくっておくのが、私は好きですね。音楽は説明的なものではなく、物語であると考えていて、脚本にも音楽がいつ始まって、いつ終わるのか、あるいはどんな音楽なのかを書き込んでいるんです。音楽は私にとってセリフのようなものなんです。
オルーク:私も『デーモンラヴァー』(2002年)のときは、オリヴィエ・アサイヤスが映画のセットで撮影するとき、実際の音楽を流したいとのことだったので、その前に音楽を制作しました。このときはうまくいきましたね。ほかの人はわかりませんが私にとって、どんな音色や楽器がその映画に合うかを探るのが、映画音楽をつくるうえでの鍵だと考えています。
ボネロ:私にとっても、映画のサウンドにどんな色彩、どんな質感、どんな楽器を使うのかということは重要ですね。
※ドイツの映画監督、脚本家、オペラ演出家。監督作品に『アギーレ/神の怒り 』(1972年)、『シュトロツェクの不思議な旅 』(1977年)、『ノスフェラトゥ』(1979年)、『フィツカラルド』(1982年)、『狂気の行方』(2009年)などがある。

©Carole Bethuel
オルーク:ボネロさんは、映画で音楽を用いるうえで、コントラストをよく使っていますね。物語上で音楽がどう作用するべきかを考えて使っているのがとても気に入っています。流れる音楽と実際に起こっていることのギャップによって、緊張感と共鳴が生まれ、それがボネロさんの映画でとてもエキサイティングなところだと感じています。
ボネロ:だからこそ、私は脚本に組み込むようにしているんですよね。あるシーンを書いていて、そこに音楽が必要だと思ったら、執筆を中断してスタジオに戻り、またコンピューターに戻る。まるでピンポンのように行き来しながら、脚本と音楽をつくっていくんです。
オルーク:面白いですね。そのような、具体的な音楽の指示がある脚本は見たことがないです。じつに興味深い。
ボネロ:私は「脚本」ではなく「映画」を書こうとしているから。私にとって音楽をつくることは、脚本を書いたり、画角を構想したりすることと近いんですよね。映画の脚本を書く段階で、音、音楽、登場人物、編集など、あらゆることを考えながら、机の上や書斎で作業しています。撮影現場ではすべてが頭のなかに入っている状態、編集室には音楽ができた状態で入るほうが好きなんです。
メロドラマに恐怖感……ジャンルミックスの面白さ。「思わず手を叩いて喜びました」(オルーク)
—『けものがいる』の話に戻りたいと思いますが、ここで描かれる2044年の都市は、不気味なほど静かで人通りがなく、まるでコロナ禍のコピーのように見えます。近未来をどのように想像して描こうと思いましたか。
ボネロ:意図的にそのように描きました。ロックダウンされたときの、何もない空っぽの通りや「浄化された」街並み、そして人々が互いに交流を持たなくなった姿に、未来と悪夢へのインスピレーションを受けたのです。
—そのような近未来像を、オルークさんはどのように感じられましたか。
オルーク:感銘を受けました。90年代に東京でよく写真を撮っていた日本人写真家がいて、最初に『けものがいる』を観たとき、彼の写真のことを思い出しました。東京の繁華街や人口密集地の巨大な雑踏が写っているのだけど、そこには人がひとりもいないというような写真でした。

© FILM : 2022 - LES FILMS DU BÉLIER - MY NEW PICTURE - 9459-5154 QUÉBEC INC. - ARTE FRANCE CINÉMA - AMI PARIS - JAMAL ZEINAL-ZADE
—『ノクトラマ』では、『ゾンビ』(1978年)へのリファレンスがあったと思います。『Coma』にはホームインベージョン的なホラーの要素が入っていましたが、本作ではそれを推し進め、スラッシャーとメロドラマを混ぜ合わせていますね。ジャンル映画、特にホラー映画のコードを用いることにどのような意図がありますか。
ボネロ:ジョージ・A・ロメロの『ゾンビ』、あるいはダリオ・アルジェントやジョン・カーペンターの映画は、10代の頃の私に大きな影響を与えました。子どもの頃、私はこれらのホラー映画をただ楽しむ目的で鑑賞していましたが、後になって、彼らは偉大な監督で、彼らがつくった偉大な映画は、非常に政治的な映画であることに気づきました。
『ノクトラマ』をつくる際、私は大好きなホラー映画のような方法で政治的な映画を作ろうと試みました。そのためおっしゃる通り、『ゾンビ』や『ジョン・カーペンターの要塞警察』(1976年)を参考にしたのです。『けものがいる』では、ジャンルをミックスすることが目標のひとつでした。メロドラマとスラッシャー、SFをミックスして、メロドラマに恐怖感を加えたかったのです。すべてをミックスしたいと考えました。
—オルークさんは、ボネロさんの映画にそういったホラーの手法が持ち込まれている点をどのように感じられますか。
オルーク:最初に『ノクトラマ』を観たとき、私もすぐに「ああ、これは『ゾンビ』だ!」と思ったことを覚えています。個人的には、ジャンルとしてのホラー自体にそれほど興味がないので答えるのが難しいのですが、ホラーが、例えばボネロさんや黒沢清さんのように、共鳴を生み出すために使われたり、ほかの要素と混ぜ合わさって新しいものを起こすために使用されるのは好きですね。
その意味では、例えば『支配階級』(1972年)なんかもホラー映画と言えると思います。私がボネロさんの映画をとても好きな理由の大きな部分は、さまざまな物事を組み合わせて通常では起こらないようなことをつくり出し、通常では得られない思考や共鳴を生み出しているところです。近年の映画では、イランの映画監督シャーラム・モクリの『Invasion』(2017年)もその好例だと思っています。『けものがいる』は、ホラーの本質に迫った、最も優れた映画のひとつだと思います。

©Carole Bethuel
—本作でガブリエルのパソコンにポップアップ広告が次々と流れ込んでくる場面では、ハーモニー・コリンの『トラッシュ・ハンパーズ』(2009年)のクリップも含まれていますよね。彼は現在の最もユニークな映画作家のひとりだと思いますが、なぜこの映画を挿入されたのでしょうか。
ボネロ:コンピューターが壊れてポップアップが次々と表示される場面で、2~3秒でクレイジーな状況がぱっと伝わる画像を探していたときに、ハーモニーの映画がまさにぴったりだと思い浮かびました。彼はクレイジーとも言えるほどに、イメージを素早く作り出す才能がありますよね。才能豊かなハーモニーの映画が大好きですが、彼の頭のなかに入りたいとは思いません(笑)。
オルーク:(笑)
—エンドクレジットをスクロールさせず、QRコードをスキャンして見るよう観客に促しているのも初めてで驚かされました。これは、スマートフォンで何でも消費してしまう社会に対するコメントとも言えるでしょうか。
ボネロ:エンドクレジットは、映画を観終わった後に観客を現実に引き戻すものですよね。通常は、映画に関わった人たちの名前が出てくるので、誰が何をしたのか想像できる。でも、QRコードは非常に短く、冷淡な印象を与えます。それがこの映画のエンディングにとてもよく合うと思いました。エンドクレジットは映画の一部であり、私にとっては、2044年の苦悩が蓄積したラストシーンとともに、考えうる最高のエンディングにできたと思います。
—ジムさんはあのエンドクレジットを見て、どのように感じられましたか。
オルーク:ボネロさんがおっしゃったように、映画のエンドクレジットは通常、映画が終わって、現実に優しく引き戻すよう誘われる感覚のものが多いと思いますが、ここで彼が行った手法には、まるで顔にいきなり平手打ちをされたような感覚を覚えました。『けものがいる』を最初に観たとき、ひとりで思わず手を叩いて喜びました(笑)。

©Carole Bethuel
—今日は対談の貴重な機会をいただき、ありがとうございました!
オルーク:音楽と『けものがいる』との関係はあまり語られることのないものだと思うから、今日はいろいろお話ができてとてもうれしかった。
ボネロ:私も音楽のお話ができてとてもうれしかった。 ありがとう!
オルーク:こちらこそ! 次の映画も楽しみにしています。
- 作品情報
-
 『けものがいる』
『けものがいる』
2025年4月25日(金)からヒューマントラストシネマ有楽町、新宿シネマカリテ、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国順次公開
第80回ヴェネチア国際映画祭 コンペティション部門正式出品
第68回バリャドリッド国際映画祭最優秀女優賞受賞
監督・脚本・音楽:ベルトラン・ボネロ
ヘンリー・ジェイムズ「密林の獣」を自由に翻案
共同プロデューサー:グザヴィエ・ドラン
- フィードバック 1
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-







