稀代の作曲家ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンは、20代後半に持病の難聴が悪化し、ほとんど耳が聞こえない状態となった。31歳のときには、のちに『ハイリゲンシュタットの遺書』と呼ばれる手紙を残して自殺を考えたとも言われている。しかし、彼は音楽への情熱を絶やすことなく、聴覚を失うという絶望を乗り越えて数々の名曲を生み出していった。
2025年1月22日に上演される一夜限りの舞台『THE GHOST』は、ベートーヴェンが残した遺書をモチーフに、深い絶望や挫折を経験した芸術家たちが「生きる」を表現するという。

その中心にいるのは、10年前にゴーストライター事件で世間を賑わせた現代作曲家・新垣隆。彼が作曲した“THE GHOST”からインスパイアされた劇作家の吉田知明が脚本・演出を手がけ、太鼓奏者の林英哲、俳優の橋爪淳、そして義足のダンサーとして知られる大前光市が舞台上でパフォーマンスを披露する。
林は、太鼓が祭を盛り上げるものとして認識されていた時代から、太鼓奏者のパイオニアとして道なき道を切り開いてきた。橋爪は俳優として活動しながら、2024年4月に大腸がんのステージ3であることを告白した。当日に向けて着々と準備が進むなか、三者三様の苦難に直面してきた新垣隆、吉田知明、林英哲、橋爪淳に、この舞台が生まれた背景や意気込みについて聞いた。
新垣隆による楽曲から生まれた舞台『THE GHOST』とは
―舞台『THE GHOST』は、新垣さんが作曲された“THE GHOST”に吉田さんが触発されたことがきっかけになって企画が立ち上がったとうかがっています。まずは、すべてのはじまりであるこの楽曲の成り立ちについて聞かせてください。
新垣隆(以下、新垣):2023年12月に演奏会があり、現代音楽の新曲もいくつか発表したんですね。そのうちのひとつが“THE GHOST”です。ベートーヴェンのピアノ三重奏曲第5番ニ長調“幽霊(ゴースト)”にインスピレーションを受けて作曲したもので、霊的なものが見えるような、ざわざわしたイメージを変奏曲というかたちで仕上げました。
と言いつつ、一般的な変奏曲とも違うんです。変奏曲は、ひとつの基となるメロディがスタイルを変えながら展開されます。しかし“THE GHOST”は、メロディ自体が曖昧で、それこそ幽霊のように姿がはっきりしない。その実体のなさがアイデアの骨子になっています。私の「ホームグラウンド」とも言える現代音楽のフィールドで、できるかぎり新しい表現に挑戦した楽曲です。

新垣隆
─ 吉田さんは“THE GHOST”のどこに惹かれたのでしょうか。
吉田知明(以下、吉田):楽曲が生まれた背景だけを聞くと、10年前に世間を賑わせたゴーストライター事件を連想する人も多いと思います。「新垣隆」「ベートーヴェン」「幽霊」という言葉が揃っていますから。私自身、事前の情報だけで「自虐的に書かれた楽曲なのでは?」と邪推していました。
新垣:もちろん、ゴーストライター事件に対する私なりのブラックユーモアも含まれていますよ(笑)。ただ、楽曲自体はおもしろおかしいものではなく、むしろ緊張感があり、音響世界に没入できるような雰囲気があると思います。
吉田:おっしゃるように、演奏会で“THE GHOST”を聴いたとき、新垣さんの穏やかな雰囲気からは想像できないくらい尖っていると言いますか、とてつもない意欲を感じたんですね。それと同時にもっと広がりを持たせることができるのではないか、という想いも沸き起こってきたんです。そこで終演後、新垣さんに「挑戦的な舞台を一緒につくりませんか」とお願いしたことが、今回の舞台『THE GHOST』につながっています。

吉田知明
―新垣さん、吉田さんのもとに林さんと橋爪さんが参画するに至った経緯もうかがえますか。
吉田:林さんは、私にとって憧れの存在で。はじめて林さんの叩く力強い太鼓の音を耳にしたときに「こんな世界があるのか」と衝撃を受け、それ以来、いつか同じ舞台に立ちたいと考えていました。今回、『THE GHOST』という舞台を構想するなかで、テーマでもある「生きる」を音で表現するには林さんの太鼓以外には考えられないと思い、出演をお願いしました。
林英哲(以下、林):お話をいただいたときは戸惑ったのが正直なところです。テーマが「生きる」という抽象的で雲をつかむようなものだったので。ただ、新垣さんとは共演したことがありますし、何かしら立体的でおもしろいものがつくれるのではないかという期待感が膨らみました。
吉田:林さんと新垣さんが音を通じてどんなコミュニケーションをとるのか、もしくは激しくぶつかり合うのか、いまからとても楽しみです。
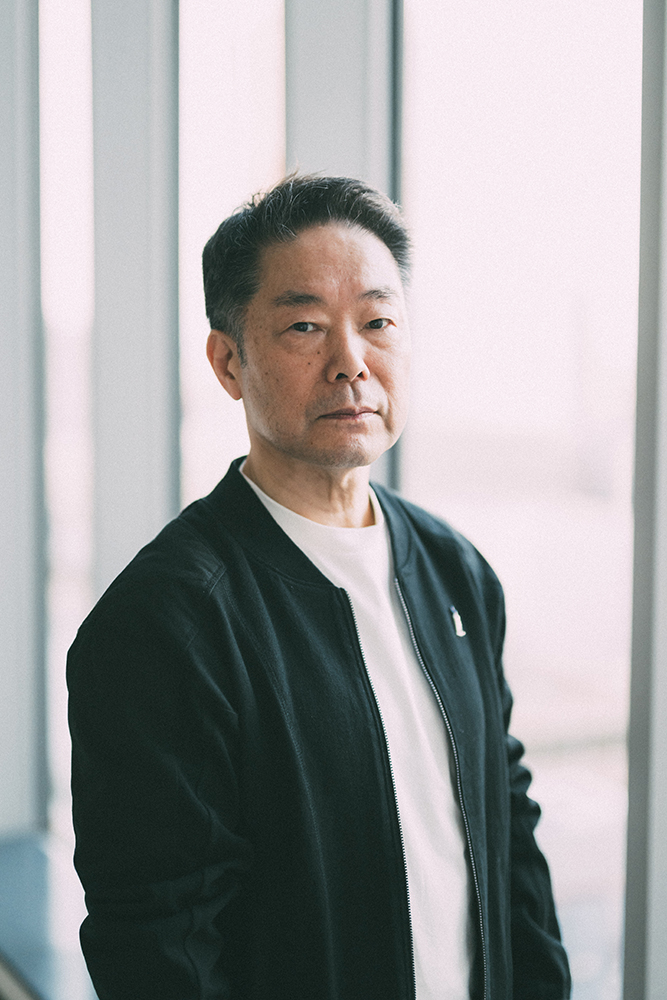
林英哲
―では、橋爪さんはどのような経緯で?
吉田:橋爪さんとは以前から舞台で共演していて、演技力はもちろん、人としての素晴らしさを知っていたので、「じつはこんな話があるのですが……」と相談しました。ただ、そのときは橋爪さんのスケジュールがはっきりせず保留になってしまったんですね。ところが、ある日の夜遅くに「あの話どうなっていますか?」と連絡をいただいて。
橋爪淳(以下、橋爪):その日は『本能寺が燃える』という戦国オペラの2日目の公演があったんですね。吉田さんは明智光秀役、私は南光坊天海役として出演したのですが、若い明智光秀と年老いた南光坊天海がすれ違うシーンで魂の触れ合いのようなものを感じたんです。
ただ、そのときは気持ちを言葉にするのを我慢したのですが、どうやら吉田さんも同じ感覚だったらしくて。舞台袖を出て、楽屋に向かう途中で、お互いに興奮しながら話をしました。そのやりとりのなかで「自分も『THE GHOST』の企画に関わるべきだ」と確信し、帰宅後、居ても立ってもいられなくなって連絡したんですよ。
吉田:橋爪さんから深夜に連絡をいただくことは滅多になかったので驚きましたが、「ぜひ出演したい」と言われたときは本当に嬉しかったです。

橋爪淳
ベートヴェンの人生を振り返りながら「生きる」の意味を問う
―この舞台では、ベートヴェンが31歳のときに弟に宛てて書いた手紙『ハイリゲンシュタットの遺書』がモチーフとして使われています。なぜこの題材を扱おうと考えたのでしょうか?
吉田:舞台の構想を練るにあたり、ベートーヴェンの人生を振り返ってみることにしたんです。私自身、音楽を生業にしていて、彼の音楽にも多大な影響を受けてきましたが、深く掘り下げる機会はなかったので。そうして生い立ちを探る過程で出会ったのが『ハイリゲンシュタットの遺書』でした。
難聴が進行し、聴覚を失ったベートーヴェンが絶望のなかに書き残したものとして知られていますが、その当時の彼の心情を想像しながら読み返してみると、ただの遺書ではなく「これからも生きていく」という宣言のように感じられたんです。
事実、ベートーヴェンは満身創痍の状態にもかかわらず、数々の名作を生み出しました。その強い生命力に驚かされるばかりか、大きな気づきがあったんです。絶望や挫折で生じた傷を完全に癒すことはできないけれど、何かしらのきっかけがあれば、それを乗り越える力が湧いてくる。それこそが「生きる」ということだ、と。

吉田:じつは昨年、私は親しい友人を亡くしていて。あまりのショックに現実を受け入れられず、なかなか前に進めない時期もあったのですが、まわりの人に支えられるなかで進むべき道を見つけることができたんですね。そうした私自身の経験と重なる部分があり、絶望の淵から立ち上がることの象徴として、『ハイリゲンシュタットの遺書』はふさわしいのではないか、と考えるに至りました。
新垣:吉田さんもおっしゃるように、ベートーヴェンは作曲家としての危機に直面しながらも、その状況を類稀な精神力で乗り越えました。彼は私にとって先生のような存在で、楽曲を通じてさまざまなことを学びましたが、なかでも創作に対する姿勢を教わった気がします。
そして、学べば学ぶほど私は彼に到底及ばないことを痛感するのですが、それでも彼のたどり着いた境地に近づきたい。だからこそ、今回の舞台は特別な想いで臨みたいんです。

そうなるはずならば――悦んで私は死に向かって行こう。――芸術の天才を十分展開するだけの機会をまだ私が持たぬうちに死が来るとすれば、たとえ私の運命があまり苛酷であるにもせよ、死は速く来過ぎるといわねばならない。今少しおそく来ることを私は望むだろう。――しかしそれでも私は満足する。死は私を果てしの無い苦悩の状態から解放してくれるではないか?――来たいときに何時いつでも来るがいい。-
―舞台化するうえで、“THE GHOST”という楽曲に新たな要素を盛り込むことも考えていますか?
新垣:そうですね。原曲をそのまま使うのではなく、あくまで素材として使っていければ。テーマである「生きる」も幽霊と同じく目に見えないものなので、それを音楽でどうやって伝えていくか。みなさんとのコラボレーションのなかで新たなかたちを生み出せたらと考えています。
林:僕は美術が好きで、太鼓をはじめる前は美術学校に通っていました。だから、美術家の人生に共感を覚えることが多いんですね。たとえば、ゴッホ。彼は生前に数多くの作品を生み出しましたが、評価が高まったのは死後のことでした。こうした背景に感情移入してしまうんです。
日本で太鼓といえば、「祭」や「伝統芸能」のイメージが強いと思います。僕が太鼓奏者として活動をはじめた1970年代は、そういう認識が特に強かった。しかし、私の太鼓は打ち方やテクニックも含めてすべて自分で生み出したものなんですよ。絵を描くような感覚で太鼓を叩くこともあり、写真家マン・レイをテーマにした『万零』や、伊藤若冲をテーマにした『若冲の翼』など、美術家をモチーフにした組曲もあります。
今回の舞台では、ベートーヴェンの人生そのものを描くわけではないにしても、絶望から立ち上がるという背景を盛り込んで一種のドラマのように仕立てるわけですよね。しかも今回は、演劇と朗読も加わる。複合的なアプローチによって、とても興味深い表現が生まれるのではないでしょうか。

―林さんから演劇と朗読の話がありましたが、橋爪さんはどのようにアプローチしようと考えていますか?
橋爪:先日、吉田さんから脚本の骨子が届いたので読んでみたのですが、なんだか心の叫びのように感じたんですね。この叫びは、人間に共通する普遍的なものだと思います。私も含め、ここにいるメンバーはそれぞれに挫折や苦悩を経験しながら再起してきた過去があるわけですが、その機会を得られずにいる人も大勢いるはず。だからこそ、舞台を観た人が少しでも勇気を持ってもらえるような表現ができればいいなと。
ただ、正直なところ、朗読には少し抵抗があるんですね。役者は台詞を覚えてこそなので。覚えた言葉をただ口に出すのではなく、感情の流れに乗せて自然と放たれることが大切なんです。でも、吉田さんの書かれた言葉を読んでみて、自分の感情が自然と乗ってくる感覚がありました。これならただの朗読ではない、新しいかたちが目指せるのではないかと感じています。

―吉田さんは現段階で舞台の完成形も見えてきているのでしょうか?
吉田:正直に申し上げますと、現段階では誰もわかっていないと思います。それは僕も含めて。おそらくですが、この作品が完成するのは、1月22日の本番。それまでは「こうでもない、ああでもない」と試行錯誤しながら組み上げていくことになるはず。
先日、林さんからジョゼフ・コーネル(※)という芸術家を教えていただいたんですね。彼は「箱のアーティスト」と呼ばれていて、小さな箱に詩的な世界を詰め込んでいるんです。もしかしたら僕のやるべきことはそれに近いんじゃないかなと。
メンバーそれぞれが持ち寄った素晴らしいアイデアを舞台という箱のなかに収めていく。最終的にどんな仕上がりになるのかは、最後までわからない。でも、その手探りの状況が、楽しくてたまらないという。一向に具体的にならないので、スタッフにはかなり迷惑をかけていると思います(笑)。
(※)ジョゼフ・コーネル(1903〜1972)……アメリカで生まれ、ニューヨークで活動した作家。

それぞれの表現が重なり合うなかで見えてくる『THE GHOST』の正体
たびたびこんな目に遭ったために私はほとんどまったく希望を喪った。みずから自分の生命を絶つまでにはほんの少しのところであった。――私を引き留めたものはただ「芸術」である。自分が使命を自覚している仕事を仕遂げないでこの世を見捨ててはならないように想われたのだ。-
―今作では、『ハイリゲンシュタットの遺書』の「自分の生命を断つまでにはほんの少しの所だった。私を引き留めたのはただ『芸術』だけであった」という象徴的な一節が引用されていますよね。この言葉のとおり、みなさんは芸術があるからこそ、絶望や挫折を乗り越えて精力的に活動されていると思います。それを踏まえて、今回の舞台にどのような気持ちで臨もうと考えていますか?
新垣:芸術が人間に与える力はたしかに存在していると感じます。ゴーストライター事件のとき、音楽家として活動していくことは世間が許さないと道を閉ざす選択肢もありました。そんな私を支えたのは、多くの方々の温かい支援です。
周囲の人がさまざまなかたちで手を差し伸べてくださったことが、どれほど大きな力になったか。そのときの励ましがなかったら再起は不可能でした。音楽があったからこそみなさんとつながれて、生きる力を得られたと思います。1月22日の舞台では、みなさんに恩返しをしたいです。

林:僕は普段、大音量で太鼓が放つ空気の振動を感じているからわかるのですが、音って人間に行動を促す力を与えてくれるんですね。身近なところだと、スマホの通知音とか、玄関のチャイムとかもそう。音があると、人は自然に反応して動くんです。それが音楽だと、人の深いところまで響くエネルギーになる。僕自身、つらいと思うことがあっても、音が励ましとなって今日まで活動を続けてくることができました。今回の舞台でも人々の生きる活力になる音を放てればと思います。

橋爪:以前、林さんの太鼓を劇場で拝聴したことがあるのですが、終わった直後の高揚感がすごかったのを覚えています。空気の振動が自分の体に伝わって、細胞が励まされるような感覚があったんです。そんな林さんの太鼓の音と、新垣さんの奏でる楽曲と、吉田さんが書く言葉がどんなふうに絡み合うのか。今からワクワクが止まりません。
そして自分のことに限って言うと、役者は演技そのものより、その人がどんな生きかたをしているかが問われる職業だと考えています。だから、この瞬間を生き切ることが大切なんです。じつは今年の春に大腸がんを患ったのですが、「それもいいんじゃない?」と前向きに捉えていて。一般的には絶望的な出来事だと思いますが、むしろ自分が成長する機会になった。それくらい、この一瞬にすべてをかけているわけです。
今回の舞台もそう。1月22日の本番がどうなるかは自分でもまったくわかりません。言葉が出なくなる瞬間があるかもしれないし、興奮しすぎて倒れてしまうかもしれない。でも、それはそれでいいと思うんですよね。あらゆることを含めてやり切りたいと思います。

―最後に、吉田さんからもひと言を。
吉田:今回の舞台は「生きるとは何か」「自分の人生とは何か」を考えることに価値があります。音楽や朗読、ダンスは形として残らず、一瞬で消えてしまうものです。それでも、瞬間ごとに重なり合う表現は、まるで絵画のようにひとつの世界を紡ぎます。そこには喜びや悲しみ、絶望や葛藤、そして存在の証明があるはずです。
新垣さんが音楽を奏で、林さんが太鼓を打ち、橋爪さんが演じ、私が鉛筆と紙で物語を描く。これらはすべて「生きる」ことだと思います。それぞれが自分なりの生きかたで、この世に少しずつ欠片を残していく。
今回の舞台は、その欠片をつなぎ合わせ、ひとつの会話を生み出す場にしたいと考えています。それを実現できたとき、『THE GHOST』の正体が見えてくるのではないでしょうか。

- INFORMATION
-
 THE GHOST | 「生きる」を表現する究極のパフォーマンス
THE GHOST | 「生きる」を表現する究極のパフォーマンス
舞台『THE GHOST』
公演日:2025年1月22日(水) 開演:19時 開場:18時
映画『THE GHOST』クラウドファンディング開催中
本舞台の全記録と出演者それぞれの真実に迫る、ライブドキュメンタリー映画
クラウドファンディング開催中キャスト:林英哲 大前光市 新垣隆 橋爪淳 吉武大地 吉田知明
作曲/音楽監督:新垣隆
脚本/演出:吉田知明
舞台監督:塩谷憲彦
照明:神山やよい
音響:福元昭太
衣装:稲垣絹代
ヘアメイク:安藤まり子
フォトグラファー:大橋愛
デザイン:阿部朝子
録音:木村雅敏
企画宣伝:山口圭介
撮影監督:勝ニ裕之
製作:堀越信二
- プロフィール
-
- 新垣隆
-
現代音楽家
1970年、東京都出身。4歳よりピアノを始める。桐朋学園大学音楽学部作曲科卒業。作曲を南聡、中川俊郎、三善晃、ピアノを森安耀子の各氏に師事。2014年、ゴーストライター騒動により、桐朋学園大学の講師を依願退職。その後様々な支援により音楽活動が継続され今日に至る。2015年「ピアノ協奏曲新生」、2016年「交響曲連祷 Litany」、2021年 「ジェニーハイ学園物語」、2023年「幽霊を主題とする」、2024年「交響的断章」を発表。コンサートのための作品、バレエ、映画、ゲームなど様々なジャンルの作曲も手がける。川谷絵音プロデュースのバンド「ジェニーハイ」にキーボードとして参加。2020年、桐朋学園大学音楽学部講師、桐朋学園大学院大学音楽研究科特任教授、大阪音楽大学短期大学部客員教授を歴任。2022年、有料配信プラットフォーム「シラス」にて『新垣隆の音楽室』を開設。日本現代音楽協会、日本演奏連盟会員。
- 林英哲
-
太鼓奏者/作曲家/「英哲風雲の会」主宰
1971年、太鼓集団に参加、各種伝統芸能を習得。太鼓曲・打法の創作に携わり、76年 小澤征爾・ボストンシンフォニーとの共演、78年 ブロードウェイ・ロングラン公演など、数多くの国内外公演で主演。1982年、ソロ活動開始。1984年、史上初の和太鼓協奏曲ソリストとして、米カーネギーホール・デビュー。以降、国内外のオーケストラと数多く共演。2000年、ドイツ・ワルトビューネでベルリン・フィルと共演。2020年、NHK大河ドラマ「麒麟が来る」のメインテーマ、劇中音楽に参加。「英哲風雲の会」を伴う舞台作品、CD、DVD多数。海外公演50数カ国。著書に「あしたの太鼓打ちへ」「太鼓日月〜独走の軌跡」。芸術選奨文部大臣賞、旭日小綬章、ほか受賞多数。東京藝術大学、洗足学園音楽大学ほか客員教授歴任。自作曲「海の豊饒」You-tube動画再生回数1600万回超。
- 橋爪淳
-
俳優/「非・演技塾」主宰
日本大学芸術学部映画学科卒業。16歳で演劇を始め、22歳で美空ひばり舞台20周年記念ミュージカル「水仙の詩」で相手役に抜擢。30歳までにテレビ、映画、舞台で主演すると決め、実現する。 2011年より高校演劇や音大などに演技指導、2014年に演技の勉強会を始める。そして2017年より新たに名前を「非・演技塾」として開塾、俳優などに演技指導している。最近は講演家としても活動しており、40年以上の演技経験で培った独自の手法で、人間力や人間の気持ちの本質を捉えた多彩なワークや実例動画を用いながらの体験型の講演は、とても新鮮な切り口で好評を博している。また、2024年2月にステージ3の大腸ガンが見つかり手術、リハビリを受けたが、4月には非・演技塾のレッスンを再開。現在も治療をしながら俳優業、演技講師、講演の活動を続けている。
- 吉田知明
-
劇作家/演出家/オペラ歌手
愛知県名古屋市出身。国立音楽大学大学院を修了後、イタリア・ミラノにて研鑽を積む。大学在学中にオペラ歌手としてデビューし、数多くの作品に出演する。2017年、オペラ「石見銀山」で脚本家、演出家としてデビュー。新国立劇場、東京文化会館で再演され、好評を博す。以後、ハイブリッドオペラ「フィガロの再婚」(2018)、戦国オペラ「本能寺が燃える」(2019/2023/2024)、幕末オペラ「新撰組外伝~歳三を愛した女~」(2020/2023)、ジャパニーズオペラ「THESPEECH」(2023/2024)、子どもオペラ「おいもさま」(2023) ほか数々のオペラ・舞台作品の脚本や演出を手掛けている。また、2021年からは、声優とオペラ歌手の朗読歌劇シリーズ「マダム・バタフライ~ある晴れた日に~」(2021)、「ラ・ボエーム〜愛あるかぎり〜」(2022)、「椿姫~不滅の恋~」(2023)の舞台脚本と演出を担当。
- フィードバック 11
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-





