未来の「ニュータウン」「郊外」はどうなっていくのか?
多摩ニュータウンで2年にわたり継続して開催されてきたCINRA主催のイベント『NEWTOWN』において、筆者も企画に関わった現代アート展が行われてきた。展覧会は、『NEWTOWN』というタイトルを正面から受け止め、ニュータウンそのものを文化的、歴史的、美術的に掘り下げ、現代の視点から提示する試みだった。

そもそも、なぜ「ニュータウン(≒郊外)」を美術展の主題として扱うのかと言えば、今「郊外」という場所が私たちの共通前提になっていると考えられるからだ。全国的に拡大した郊外空間は、少子高齢化や移民問題も含め、現代社会の局面を先鋭的に露呈させている。その意味で、美術ばかりでなく様々な文化的表現において、時代の背景をなすこの状況を完全に避けて通るのは難しい。

『NEWTOWN 2018』にて企画、開催した現代アート展『SURVIBIA!!』において示唆を得たのが、音楽ライター、磯部涼の著書『ルポ 川崎』(2017年、サイゾー)である。磯部は郊外都市である川崎を、北部(平穏だが退屈なニュータウン)と、南部(刺激的だが治安が悪い工業地帯)に区分けし、南部的なるものを「川崎サウスサイド」として描き出したのだった。

そんな中、イベント当日に開催されたのが、磯部涼と小田光雄のトークイベント『死後の〈郊外〉—混住・ニュータウン・川崎—』だ。郊外論の発端となった『〈郊外〉の誕生と死』(1997年、青弓社)を著した評論家の小田光雄と、現代の川崎をルポルタージュした磯部による世代をまたいだ対話を通して、郊外論を歴史的な縦軸でつなぎ、過去から現在、そして未来の「ニュータウン」「郊外」を占う対談としてセッティングされた、そのトークの一部始終をレポートしよう。

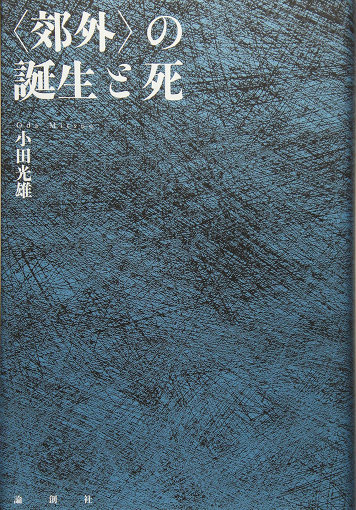
我々はどこへ行くのか? 1980年代に出来上がった新しい消費空間
繰り返し述べれば、私たちの暮らす環境は全面的に郊外化していると言って過言ではない。画家ポール・ゴーギャンの作品タイトルではないが、「我々はどこから来たのか」「我々は何者か」「我々はどこへ行くのか」が不透明な現代の社会や文化の状況にとって、この対話はその一端を解き明かすカギになるだろう。

まず、小田は郊外化以前の農村で育っているので、自身をネイティブアメリカンのような「先住民」と名指す。その農村も、1960年代の高度経済成長期を経て1970年代に入ると、グローバリゼーションの先駆けのように中央資本が押し寄せて、郊外型のロードサイドビジネスを形成するのだ。
小田:1970年代前半に消費社会化すると、産業の主流が第一次産業から第三次産業のサービス業へ移行します。これは日本の歴史始まって以来のチェンジなんですね。フランスの思想家ジャン・ボードリヤールの『消費社会の神話と構造』もその頃に書かれています。
そして1980年代になると、それまで田んぼや畑だったところにどんどん商業施設が建っていく。かつての町の商店街には必ず従業員や家族の住むバックヤードや2階、つまり「生活」があったんですが、郊外の場合には店舗しかない。つまり「商品」しかないんです。そこで新しい消費空間が出来上がった。

一方で、2017年にちょうど150万人都市になった川崎を磯部が取り上げた背景には、2015年に起きた「川崎中一殺害事件」やドヤ街である川崎区日進町での火災事件がある。今でこそラゾーナ川崎に代表されるように再開発が盛んな川崎は、かねてより公害や差別問題に対する市民運動の聖地であり、ある種日本の社会問題を象徴する場所であった。そんな川崎南部を描いた磯部も、出自はむしろ北部的な環境だったという。
磯部:僕は千葉県千葉市の幕張メッセに隣接したニュータウンに育ちました。幼少期には地平線が見えた記憶があります。その時はまだ家もポツポツとしか建っておらず、幕張メッセもなかった。そこにだんだんアスファルトが敷かれていったんですが、1990年代のバブル崩壊にさしかかって開発が途中で止まってしまったんです。
幕張で有名なツインタワー周辺も開発が止まったので、何もない中にポツンとツインタワーだけが建っている状態でした。その後で自分の住んでいる場所と全然違う環境を見に、東京に遊びに行くのが好きになる。そういう一種の「ツーリスト目線」も、僕の活動の原点にあると思います。
1951年生まれの小田と、1978年生まれの磯部。この2人の生い立ちには、戦後日本の歩んだ道程と都市の変遷とが、鮮やかに重なっている。1989年生まれで神奈川県の港北ニュータウンに育ち、郊外化が自明の前提だった筆者もそこに加えれば、郊外世代の1世から3世をまたぐことになる。

世代によって異なる「郊外」の感覚
2018年9月に起きた台風24号による静岡の停電被害を受けて、静岡在住の小田は「電気のない生活」を過ごし、郊外のもろさを改めて実感したという。同時にそれは50年ほど前に戻ったような、井戸や薪がある自給自足に近い「田舎の生活」を思い起こさせるものでもあった。そこから小田は、「なぜ郊外にこれほど消費社会が反映されてきたか」を語る。
小田:郊外において、どんな商売も「便利で安い」ことによって広がりました。それが消費社会の原則でもありますよね。それに対して近代を形作ってきたのは「デパートと鉄道文化」。デパートは階級上昇モデルの象徴でした。
しかし郊外では「便利で安い」が最優先されるので、デパートが成立しなくなり、ショッピングモール的な空間が必要になる。そして、主要な交通手段も鉄道から自動車へ移行します。つまり、アメリカ的なシステムの中に巻き込まれていって、抜けられなくなったんです。だから無意識的にそういう生活を送っていると、「自分はどこからきたのか」が分からなくなるんじゃないでしょうか。

たしかに郊外化の背景には、米軍基地に代表されるように、常に「アメリカの影」(加藤典洋『アメリカの影』1985年)があった。ショッピングモールや自動車の蔓延もまた、アメリカ型ライフスタイルによる侵食の表れの一つだ。だからこそ郊外第一世代の文学者などは、「原風景」を破壊されたという思いが強く、「郊外嫌い」が多い。しかし、この一種の疎外論に磯部が応える。
磯部:おっしゃる通り、郊外は「病理」として語られてきました。1980年に川崎北部のニュータウンで起きた象徴的な事件が、「金属バット両親殺害事件」です。また、岡崎京子の漫画『リバーズ・エッジ』(1994年)もその延長線上にあるでしょう。
生きている実感が湧かないような若者たちーーそういう語り口については、自分の世代ということもあって、ずっと複雑な受け止め方をしてきました。というのも、かつてあった故郷を喪失したのではなく、病理的な郊外が「原風景」だからです。だから地元に帰ると、計画的に設計された同じようなニュータウンの街路も、僕には獣道みたいに見える。

その感覚は筆者も共有できる。いかに病理的で無機質な計画都市であっても、そこに生まれ育てば、身体を通して有機的に把握できるからだ。たとえばニュータウンのゴミ収集場や植え込みの陰、マンションの溝やエレベーターは、子供の頃の遊び場だった。だからこそ日本中にあまねく広がっている「郊外の風景」を前提とした上で、そこでどう生き延びていくかという問いかけが重要なのではないだろうか。
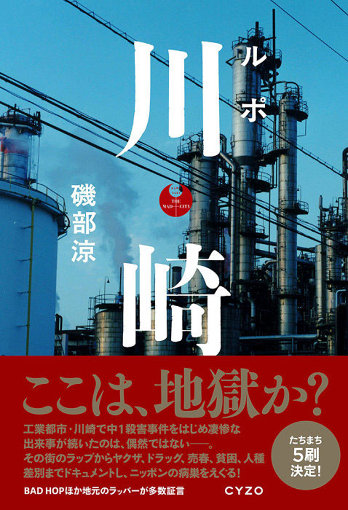
郊外のロードサイドビジネスに現れる崩壊の兆し
さらに話題は、街の「再開発」に向けられる。川崎には美味しい焼肉屋や居酒屋が多いものの、どんどん古い店がなくなり、チェーン店が増えていることを挙げて、磯部は「街のダイナミズム」を考える。
磯部:街が再開発でどんどん入れ替わっていくようなダイナミズムのあり方もあると思います。たとえば、区分としては川崎南部の中原区に位置する武蔵小杉。その武蔵小杉周辺も昔は大きな工業地帯でしたが、今や「ムサコ」なんて呼ばれて、タワーマンションが林立している。
ここ10年で人口が急増したから、日本最悪の通勤ラッシュと言われているような状態です。それはある意味で日本の近代化の象徴だった南部が、現代の象徴である北部的なものに侵蝕されていくということでもあるのかな、と。

武蔵小杉は近年、住みたい街ランキングでも上位を獲得するような新興のベッドタウンとして注目されている。むろん、再開発による「街のダイナミズム」には抗い難い。とはいえ、それは都市空間の中に奥行きがなくなるジェントリフィケーションとも捉えられる。では、このような建設ラッシュはどのような構造的問題を孕んでいるのか。小田が続ける。
小田:郊外論というのはイメージの変容と、そのせめぎ合いでもあります。タワマンで言えば、「国土計画として高く建てた方が収容効率がいい」という作る側の論理がある一方で、今の若い人は「高いところに住むのがカッコいい」と思っている。
ただ、今後の郊外の一番の懸念は「アパート、マンション問題」です。ここ20年ほどで膨大に建てられたそれらは、ほとんど土地マルチ商法みたいなもの。最悪の場合、サブプライムローンのような問題に発展する可能性があります。それによって郊外がどうなるか。

スルガ銀行のずさん融資や、レオパレスのサブリース、違法建築問題などは記憶に新しい。事実、それらは住宅街=郊外における出来事に違いないのだ。このように、ダイナミックな変化の中である種の限界を迎えつつあるように見える郊外空間では、ロードサイドビジネスにも崩壊の兆しが表れている。
磯部:今、郊外では高齢化も進み、独り暮らしの老人に食事を個人配達する形が増えてきているので、ロードサイドという形ですらコミュニティーがないんです。ただ、豊かな郊外が「病理」として語られてきたところからさらに反転して、北部的な郊外にも空き家が増えている。すると、そこに家賃が安いという理由で外国人が流入してきて実は今、街がイキイキしてもいるんです。

東日本大震災が郊外の緩慢な死を決定づけた。新しい共同体はどう生まれるか?
郊外をめぐる最前線には「多国籍化」というトピックがある。実際それは展覧会『SURVIBIA!!』においても、ブラジル人を中心に3000人以上の外国人が暮らす「保見団地」(愛知県豊田市)に3年間にわたり住み込んで撮影した名越啓介の写真作品や、山梨を拠点とする映画制作集団、空族によるブラジル移民との混住や地方都市の諸問題を活写した映画『サウダーヂ』(2011年)の上映によって可視化されていた。

小田:静岡でも日系ブラジル人を中心に、移民の方々が多く住んでいます。だから近所のリサイクルショップに行くと、トーテムポールが売られていたりする(笑)。彼らが家族連れで日本に来るのは、経済的な面もありますが、なにより治安がいいからなんですね。
磯部:『サウダーヂ』で印象的なシーンがあります。ブラジル人のお父さんとフィリピン人のお母さん、そして日本で生まれたその子供が食卓について、ポルトガル語とタガログ語(フィリピンの言語の一つ)と日本語がチャンポンになって話している。
そこで、5時のチャイムで流れる“ふるさと”のメロディに、彼らは郷愁(=サウダーヂ)を感じるんです。つまり、日本の郊外に流入してきた人たちが、そこで新たにコミュニティーを形成し、新しいノスタルジーを構成するというシーン。こういったことも、一つの時代の転換点なのだと思います。
その転換期において、小田が『郊外の果てへの旅/混住社会論』(2017年、論創社)で書いたように、これまでの郊外は緩慢な死を迎えている。その死が決定的になったのは、東日本大震災の原発事故だったのではないかと小田は見立てる。
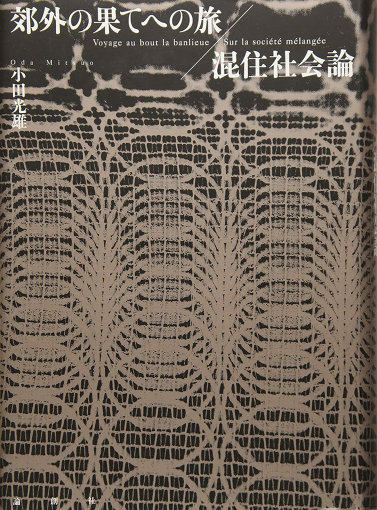
なぜなら原発こそ、都心のバックヤードとしてのロードサイドビジネスであり、アメリカとの関係も含めた、戦後日本の郊外化の構造を集約させたものだったからだ。その欠陥が白日の下にさらされた現在、今後の郊外社会はどうなっていくのだろうか。
小田:原発事故に顕著なように、まだ日本の郊外はこれまでの清算が済んでいません。消費で分断されてしまったこれからの郊外では、思考の多様性をどう確保し、いかに共同性幻想を作るかが重要になってくるでしょう。
磯部:郊外が死を迎えたのだとしたら、今まさに郊外で起きている移民や空き家の増加、あるいはひょっとしたらこれから若者が郊外に住み始めるかもしれないことを、郊外の「再生」として捉えられるのかどうか。『ルポ 川崎』の水先案内人は若きラップグループ・BAD HOPでしたが、それらも新しい共同体の立ち上げとして着目できる部分はあるかもしれません。


多層的な混住や若い世代の台頭が見られるのと同時に、様々な不良債権が山積みである現代の郊外社会。それは郊外のみならず、2020年の「東京オリンピック」をピークとして、遅かれ早かれ人口や経済がシュリンクしていく都市部も直面する課題だろう。
この対談では、高度成長期下の消費社会化から、ニュータウンの発展と衰退、現今の再開発や多国籍化、そして原発事故とその後に至るまで議論されてきた。文字通り「〈郊外〉の誕生と死」を辿る足どりの中で、「ニュータウン(≒郊外)」を再帰的に捉え直すことは、「死後の〈郊外〉」を生き抜く術を私たちに与えてくれるはずだ。
『NEWTOWN』は、まさに人口の増減によって廃校となった多摩ニュータウンの元小学校校舎(現在はデジタルハリウッド大学 八王子制作スタジオとして使用)で開催されている。その土地で地元住民と連携しながら新しい祭りや共同体を立ち上げることも、そういった課題に対する一つの実践に違いない。
「便利で安い」だけでは立ち行かなくなり、少子高齢化や長引く不況によって、この社会は下方修正を迫られている。その煽りを受けてか、都市空間や広義のアートもまた、息苦しく統御され、不自由になりつつあるように思えてならない。そんな中、それぞれの人がそれぞれの土地で、小さくとも独自の文化圏を立ち上げていくことこそが大切なのではないだろうか。

- イベント情報
-
- 『NEWTOWN 2019』
-
2019年10月19日(土)、10月20日(日)
会場:東京都 多摩センター パルテノン大通り、パルテノン多摩
東京都 多摩センター デジタルハリウッド大学 八王子制作スタジオ(旧 八王子市立三本松小学校)
-
- 美術展:『SURVIBIA!!』(サバイビア!!)
-
「郊外を、生き延びろ。」(Survive in Suburbia.)をテーマにした美術展を開催。「ノーザン・ソウル」+「サウスサイド」+「ロードサイド」からなる「郊外」を提示することを試みた
日程:2018年11月10日(土)、11月11日(日)
時間:10:30~19:00
キュレーション:中島晴矢『EXPO-SURVIBIA -千里・万博・多摩-』
秋山佑太
石井友人
キュンチョメ
中島晴矢
FABULOUZ
原田裕規『変容する周辺、近郊、団地』
[URG]
石毛健太
衛藤隆世
EVERYDAY HOLIDAY SQUAD
垂水五滴
中島晴矢
名越啓介
BIEN
yang02『PERSISTENCE_suburb』
[PERSISTENCE]
新井五差路
百頭たけし
藤林悠『川崎ミッドソウルーーアフター「ルポ 川崎」』
細倉真弓
磯部涼映画『サウダーヂ』上映
空族トークイベント『死後の〈郊外〉—混住・ニュータウン・川崎—』
11月10日(土)14:00~15:30
小田光雄
磯部涼
中島晴矢トークイベント『都市・郊外・芸術ー計画と無計画の間で』
11月11日(日)14:00~15:30
会田誠
中島晴矢『SURVIBIA!!』クロッシング・トーク
11月11日(日)17:30~19:00
出展作家多数
- プロフィール
-
- 小田光雄 (おだ みつお)
-
1951年静岡県生まれ。早稲田大学卒業。出版業に携わる。著書『〈郊外〉の誕生と死』『郊外の果てへの旅/混住社会論』(いずれも論創社)、『図書館逍遥』(編書房)、『書店の近代』(平凡社)、『出版社と書店はいかにして消えていくか』などの出版状況論三部作、インタビュー集「出版人に聞く」シリーズ、『古本探究Ⅰ~Ⅲ』『古雑誌探究』(いずれも論創社)、訳書『エマ・ゴールドマン自伝』(ぱる出版)、エミール・ゾラ「ルーゴンマッカール叢書」シリーズ(論創社)などがある。個人ブログ【出版・読書メモランダム】に「出版状況クロニクル」「古本夜話」を連載中。
- 磯部涼 (いそべ りょう)
-
ライター。主に日本の文化/風俗と社会の関わりについてのテキストを執筆。単著に『ヒーローはいつだって君をがっかりさせる』(太田出版、2004年)、『音楽が終わって、人生が始まる』(アスペクト、2011年)、『ルポ 川崎』(サイゾー、2017年)等がある。その他、共著に九龍ジョーとの『遊びつかれた朝に――10年代インディ・ミュージックをめぐる対話』(ele-king books/Pヴァイン、2014年)、大和田俊之、吉田雅史との『ラップは何を映しているのか――「日本語ラップ」から「トランプ後の世界」まで』(毎日新聞出版、2017年)、編者に『踊ってはいけない国、日本――風営法問題と過剰規制される社会』(河出書房新社、2012年)等。『文藝』(河出書房新社)2019年秋季号より連載「移民とラップ」を執筆開始。
- フィードバック 0
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-


